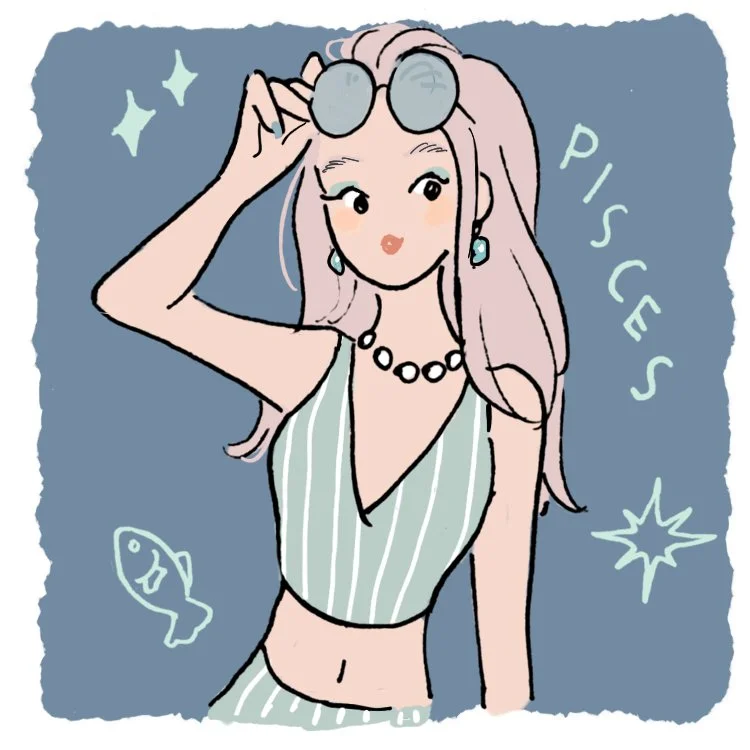【最新12星座占い】<8/8~8/21>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<8/8~8/21>の12星座全体の運勢は?
「終わりと継承」
8月23日には二十四節気の「処暑」に入り、朝夕に気候や虫の音に涼しさを感じる日も出てくるようになりますが、その直前である8月22日に水瓶座29度(数えで30度)で満月を迎えていきます。
今回の満月のテーマは「はかなさ(無常さ)の受容」。歴史上どんなに強固で安泰に思えた文明や社会も、潮が満ちれば必ず引くように、栄枯盛衰をたどってきましたが、今期は個人においても社会においてもそうした「枯れ」や「衰え」の面が顕著に実感されていきやすいタイミングなのだと言えます。これは逆に言えば、いかに自身の生活や日本社会における奇妙な混乱状況をなかったことにせずに、自覚的に受け入れていけるかがテーマになっていくということでもあります。
たとえば、日本では古来から蜉蝣(かげろう)が、成虫でいられる時間がわずか数時間から数日という短さゆえに、はかなさの象徴として歌に詠まれてきました。それは蜉蝣のきれいな透明な羽や、細長い体のいかにも弱弱しい印象も大きかったはずですが、名前の由来ともなった、日差しの強いに立ちのぼる「陽炎(かげろう)」のゆらめきを思わせるような飛び方がそれを決定づけたように思います。
蜉蝣の成虫には口も消化管も退化してありません。何も飲まず食わずで飛び回って力尽きてしまいます。なぜそんなことをするのか。それはひとえに、交尾するため。飛び回れば異性に会えるから。もちろん、交尾しても結果的に死んでしまいますが、そうすることでDNAはちゃんと受け継がれていく。つまり、遺伝子の側から見れば死ではなく、そこで継承が起きている。
さながら光が粒子であると同時に波でもあるように、蜉蝣という虫は確固とした個体であると同時に、それぞれが連綿と受け継がれていく遺伝子の中継地点でもある訳です。
つまり、保身や自己利益の最大化をはかるのではなくて、どうしたら自身がその一部であるところの大きな全体へと貢献できるか、あるいは、自分がそこに身を投じ、続いていくべき潮流は何なのか。そうした実感が、否応なく膨れあがってきやすいのが今回の満月なのだということ。
その中で、どんな自分事が終わりつつあり、その一方でどんな継承が起きつつあるのかということに、意識を向けてみるといいでしょう。
今回の満月のテーマは「はかなさ(無常さ)の受容」。歴史上どんなに強固で安泰に思えた文明や社会も、潮が満ちれば必ず引くように、栄枯盛衰をたどってきましたが、今期は個人においても社会においてもそうした「枯れ」や「衰え」の面が顕著に実感されていきやすいタイミングなのだと言えます。これは逆に言えば、いかに自身の生活や日本社会における奇妙な混乱状況をなかったことにせずに、自覚的に受け入れていけるかがテーマになっていくということでもあります。
たとえば、日本では古来から蜉蝣(かげろう)が、成虫でいられる時間がわずか数時間から数日という短さゆえに、はかなさの象徴として歌に詠まれてきました。それは蜉蝣のきれいな透明な羽や、細長い体のいかにも弱弱しい印象も大きかったはずですが、名前の由来ともなった、日差しの強いに立ちのぼる「陽炎(かげろう)」のゆらめきを思わせるような飛び方がそれを決定づけたように思います。
蜉蝣の成虫には口も消化管も退化してありません。何も飲まず食わずで飛び回って力尽きてしまいます。なぜそんなことをするのか。それはひとえに、交尾するため。飛び回れば異性に会えるから。もちろん、交尾しても結果的に死んでしまいますが、そうすることでDNAはちゃんと受け継がれていく。つまり、遺伝子の側から見れば死ではなく、そこで継承が起きている。
さながら光が粒子であると同時に波でもあるように、蜉蝣という虫は確固とした個体であると同時に、それぞれが連綿と受け継がれていく遺伝子の中継地点でもある訳です。
つまり、保身や自己利益の最大化をはかるのではなくて、どうしたら自身がその一部であるところの大きな全体へと貢献できるか、あるいは、自分がそこに身を投じ、続いていくべき潮流は何なのか。そうした実感が、否応なく膨れあがってきやすいのが今回の満月なのだということ。
その中で、どんな自分事が終わりつつあり、その一方でどんな継承が起きつつあるのかということに、意識を向けてみるといいでしょう。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「宇宙の人と成る」。

明治23年(1890)、教育勅語が発布されると東京の高等中学校では奉読式が行われ、その後に勅語に敬礼することを求められました。その時、嘱託教員だった内村鑑三が拒否したことで、不敬として糾弾され、辞職に追い込まれたのです。
しかも、有名な学者までもが国家主義の立場からキリスト教は神を第一とするから国家を軽んじるのだと批判キャンペーンを張ったため、マスコミや世間からの反応も厳しいものになっていきました。さらに追いうちをかけるように、私生活でも再婚して間もなく妻が病気で亡くなってしまい、再就職先の新潟の学校でも外国人宣教師たちと衝突してまたもや職を失い、体調も優れない日々が続きます。
そうした中で書かれたのが『基督信徒のなぐさめ』であり、そこで彼は自身の身を次々と襲った不幸の中で、人々から見捨てられたことで、かえって孤独に神と向き合い、喪失感から回復し、より一層国を愛し神を近くに感じるという境地に達し、次のように述べるのです。
「ああ余も今は世界の市民なり。生をこの土に得しにより、この土の外に国なしと思いし狭隘なる思想は、今は全く消失せて、小さきながらも世界の市民、宇宙の人と成るを得しは、余の国人に捨てられしめでたき結果の一にぞある。」
内村の立たされた立場のこともあり、国との問題はもっとも厄介なものでしたが、国を愛する形は一つではありませんでした。逆に、一定の形式に従わないのは愛国心がないからだと決めつけ、弾圧するのはそれこそ国を亡ぼす元凶だったのではないでしょうか。内村は胸に二つのJ(ジーザスとジャパン)への離れられない思いを抱いて、日本という国を「夫の家」に喩えて、さらにこう続けました。
「しからば宇宙人となりしにより余は余の国を忘れしか。ああ神よ、もしわれ日本国を忘れなば、わが右の手にその巧みを忘れしめよ。もし子たるものがその母を忘れ得るなれば余は余の国を忘れ得るなり。無理に離縁状を渡されし婦はますますその夫を慕うがごとく、捨てられし後は国を慕うはますます切なり。」
内村のこうした魂の言葉を読んでいると、日本という国であれ、属する業界や会社であれ、実際の家族であれ、それらを真に愛するためには、いったんそれらを超えたところに自分を置いていくプロセスが不可欠であるように思えてきます。
今期のおひつじ座もまた、普通なら逆境と感じる状況こそ、愛を取り戻すチャンスなのだということを念頭に置いて過ごしていくといいかも知れません。
参考:内村鑑三『基督信徒のなぐさめ』(岩波文庫)
しかも、有名な学者までもが国家主義の立場からキリスト教は神を第一とするから国家を軽んじるのだと批判キャンペーンを張ったため、マスコミや世間からの反応も厳しいものになっていきました。さらに追いうちをかけるように、私生活でも再婚して間もなく妻が病気で亡くなってしまい、再就職先の新潟の学校でも外国人宣教師たちと衝突してまたもや職を失い、体調も優れない日々が続きます。
そうした中で書かれたのが『基督信徒のなぐさめ』であり、そこで彼は自身の身を次々と襲った不幸の中で、人々から見捨てられたことで、かえって孤独に神と向き合い、喪失感から回復し、より一層国を愛し神を近くに感じるという境地に達し、次のように述べるのです。
「ああ余も今は世界の市民なり。生をこの土に得しにより、この土の外に国なしと思いし狭隘なる思想は、今は全く消失せて、小さきながらも世界の市民、宇宙の人と成るを得しは、余の国人に捨てられしめでたき結果の一にぞある。」
内村の立たされた立場のこともあり、国との問題はもっとも厄介なものでしたが、国を愛する形は一つではありませんでした。逆に、一定の形式に従わないのは愛国心がないからだと決めつけ、弾圧するのはそれこそ国を亡ぼす元凶だったのではないでしょうか。内村は胸に二つのJ(ジーザスとジャパン)への離れられない思いを抱いて、日本という国を「夫の家」に喩えて、さらにこう続けました。
「しからば宇宙人となりしにより余は余の国を忘れしか。ああ神よ、もしわれ日本国を忘れなば、わが右の手にその巧みを忘れしめよ。もし子たるものがその母を忘れ得るなれば余は余の国を忘れ得るなり。無理に離縁状を渡されし婦はますますその夫を慕うがごとく、捨てられし後は国を慕うはますます切なり。」
内村のこうした魂の言葉を読んでいると、日本という国であれ、属する業界や会社であれ、実際の家族であれ、それらを真に愛するためには、いったんそれらを超えたところに自分を置いていくプロセスが不可欠であるように思えてきます。
今期のおひつじ座もまた、普通なら逆境と感じる状況こそ、愛を取り戻すチャンスなのだということを念頭に置いて過ごしていくといいかも知れません。
参考:内村鑑三『基督信徒のなぐさめ』(岩波文庫)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは「心意気と諦めのはざまで」。

オリンピックの開会式にはその国の美学が如実に現われるものですが、個々の選手の活躍ぶりや奮闘はともかくとして、今回の東京オリンピックの開会式や開催までの経緯を振り返るにつけ、日本人の美学とは一体何だったのだろうと改めて考え込んだ人も少なくなかったのではないでしょうか。
おそらく日本の哲学者としてその問いに正面から取り組んだ人物が九鬼周造でした。彼がテーマにした「いき」というのは、江戸時代の「遊女」に託された精神性であり、おそらく“聖なるもの”としての神に仕え、神の妻とみなされていた古代の巫女の姿を重ね、そこに九鬼周造は日本人の全存在と関わる何かがあると直感し、『「いき」の構造』という本を書いたのだと思います。
とはいえ、本書で九鬼は「いきとは〇〇」であるとははっきり書かず、その代わり「塗り下駄を素足で履く」といった着こなしや、のれんや扇で風を感じるといった感覚を例に出して、そうした些細な調度や行為、仕草の中に出入りする精神や、つねに他のものとの関係性のなかでそれを語っていきました。
そうしてその最後でようやく、「運命によって「諦め」を得た「媚態」が「意気地」の自由に生きるのが「いき」である」と結論づけるのですが、一方で九鬼は文中の「生き」に長い注をつけています。
九鬼によれば、「いき」の語源の研究には「生」「息」「行」「意気」の関係を存在学的に、つまり簡単には行き着けない、入手できない、出合えない価値を見出し、解明していく必要があるのだと。ただ、そうした「いき」の関係の最も基礎にあったのは「生きる」ということそのものでした。
人は「生きる」ことで異性との関係が生まれ、そこで少なからず媚態を秘める訳ですが、それが「息遣い」と同様に単なる生理現象を超えて「意気」の次元にまで高められたとき、精神的に「生きる」ことができる。ただ、「心意気」という言葉が「相手に向かって心が行く」ことを意味するのに対し、「諦め」はどこかで自然と向かっていく心意気を止めたり、断ち切ったりすることを意味しており、九鬼は両者のはざまで、それでも人が誰かと関わったり、そうした関わりを大切にしていこうとするとするのが、「いき」すなわち「生きる」ということの美学じゃないかと言いたかったのではないでしょうか。
「「いき」の構造」が出版されたのは1930年でしたが、ヨーロッパに長らく留学していた九鬼は、おそらく日本という国が隣人であるアジア諸国への侵略戦争へと傾斜しつつあることにすでに気付いていたはずです。そう考えると、彼の著作は、日本人が何を取り戻さなければならないのかを、彼なりに必死に考え抜いた成果でもあったように思います。
今期のおうし座もまた、今この時代においてかっこいい生き方をするにはどうしたらいいか、それもかっこよすぎるとかえってダサいので、その微妙なところを行くにはどうすればいいのか、ということをあらためて九鬼にならい考え、実践してみるといいでしょう。
参考:九鬼周造『「いき」の構造』(岩波文庫)
おそらく日本の哲学者としてその問いに正面から取り組んだ人物が九鬼周造でした。彼がテーマにした「いき」というのは、江戸時代の「遊女」に託された精神性であり、おそらく“聖なるもの”としての神に仕え、神の妻とみなされていた古代の巫女の姿を重ね、そこに九鬼周造は日本人の全存在と関わる何かがあると直感し、『「いき」の構造』という本を書いたのだと思います。
とはいえ、本書で九鬼は「いきとは〇〇」であるとははっきり書かず、その代わり「塗り下駄を素足で履く」といった着こなしや、のれんや扇で風を感じるといった感覚を例に出して、そうした些細な調度や行為、仕草の中に出入りする精神や、つねに他のものとの関係性のなかでそれを語っていきました。
そうしてその最後でようやく、「運命によって「諦め」を得た「媚態」が「意気地」の自由に生きるのが「いき」である」と結論づけるのですが、一方で九鬼は文中の「生き」に長い注をつけています。
九鬼によれば、「いき」の語源の研究には「生」「息」「行」「意気」の関係を存在学的に、つまり簡単には行き着けない、入手できない、出合えない価値を見出し、解明していく必要があるのだと。ただ、そうした「いき」の関係の最も基礎にあったのは「生きる」ということそのものでした。
人は「生きる」ことで異性との関係が生まれ、そこで少なからず媚態を秘める訳ですが、それが「息遣い」と同様に単なる生理現象を超えて「意気」の次元にまで高められたとき、精神的に「生きる」ことができる。ただ、「心意気」という言葉が「相手に向かって心が行く」ことを意味するのに対し、「諦め」はどこかで自然と向かっていく心意気を止めたり、断ち切ったりすることを意味しており、九鬼は両者のはざまで、それでも人が誰かと関わったり、そうした関わりを大切にしていこうとするとするのが、「いき」すなわち「生きる」ということの美学じゃないかと言いたかったのではないでしょうか。
「「いき」の構造」が出版されたのは1930年でしたが、ヨーロッパに長らく留学していた九鬼は、おそらく日本という国が隣人であるアジア諸国への侵略戦争へと傾斜しつつあることにすでに気付いていたはずです。そう考えると、彼の著作は、日本人が何を取り戻さなければならないのかを、彼なりに必死に考え抜いた成果でもあったように思います。
今期のおうし座もまた、今この時代においてかっこいい生き方をするにはどうしたらいいか、それもかっこよすぎるとかえってダサいので、その微妙なところを行くにはどうすればいいのか、ということをあらためて九鬼にならい考え、実践してみるといいでしょう。
参考:九鬼周造『「いき」の構造』(岩波文庫)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは「生き死にを歌にのせていく」。

オリンピックを数年後に控え、冷蔵庫、掃除機、洗濯機の「三種の神器」が急速に普及しだし、日本が高度経済成長期のとば口に立った1957年。そうした時代の浮足立った歩調の一方で、深沢七郎のデビュー作である『楢山節考』という小説がベストセラーとなっていました。
それはまったく時代と逆行した内容で、「姥捨て伝説」をモチーフに、ある貧困な山村の飢餓寸前ともいえる人々の生きている姿を描いたものでした。七十歳を迎え、この冬には遠い「楢山」に捨てられる予定である主人公のおりん婆さんは、長生きを恥ずかしいと感じて、さながら嫁入りじみた妙な晴れがましさで自身の死を心待ちにしているのです。
やがておりんは息子である辰平の背板に乗って、楢山へ入ります。ほどなくして、無数の白骨が散乱し、鳥が群がっている場所に着くと、躊躇する辰平に手で早く帰るよう指示し、そこに雪が降ってくる。それに先立って、「塩屋のおとりさん運がよい 山へ行く日にゃ雪が降る」という民謡が挿入されているのですが、そこには次のような説明が付け加えられていました。
「楢山へ行く日に雪が降ればその人は運がよい人であると云い伝えられていた。塩屋にはおとりさんという人はいないのであるが、何代か前には実在した人であって、その人が山へ行く日に雪が降ったということは運がよい人であるという代表人物で、歌になって伝えられているのである。」
同時に、おりんを山に捨てに行く前日の晩のエピソードには、経験者が辰平に、大変だったら途中の谷底に落としちゃってもいいよってこっそり耳打ちする場面まで描かれているのですが、深沢の作品世界というのは、どうもある種の真摯な信仰だとか、神様がいる神話世界などとは対極の、いろんなことに理由なんかないんだっていう、虚無的な世界観が根底にあったように思います。
そして、そこに流れているある種の音楽として、作者の語りや登場人物たちの会話があって、人の生き死にがそこで歌われていく。深沢はギターのリサイタルを開いたり、日劇ミュージック・ホールの正月公演に出演したりもしていましたから、文学が先にある根っからの文学者というより、むしろ音楽が先にある人だったのかもしれません。
そういう「死んじゃったらそれまで」だし、どこかで生きる喜びを徹底的に突き放したような視点から書かれた作品を、「豊かな日本」の入口に立っていた多くの日本人がすすんで読んでいた訳ですから、当時の人たちは現代の日本人よりよっぽど人生のなんたるかを分かっていたのではないでしょうか。
今期のふたご座もまた、そうしたゴロリと野太い、乾いたユーモアをもって、自身の生き様やその後始末について思いを巡らせ、時にはそれを歌にのせて存分に歌ってみるといいでしょう(ちなみに本書の巻末には深沢が作詞・作曲した劇中歌も載っています)。
参考:深沢七郎『楢山節考』(新潮文庫)
それはまったく時代と逆行した内容で、「姥捨て伝説」をモチーフに、ある貧困な山村の飢餓寸前ともいえる人々の生きている姿を描いたものでした。七十歳を迎え、この冬には遠い「楢山」に捨てられる予定である主人公のおりん婆さんは、長生きを恥ずかしいと感じて、さながら嫁入りじみた妙な晴れがましさで自身の死を心待ちにしているのです。
やがておりんは息子である辰平の背板に乗って、楢山へ入ります。ほどなくして、無数の白骨が散乱し、鳥が群がっている場所に着くと、躊躇する辰平に手で早く帰るよう指示し、そこに雪が降ってくる。それに先立って、「塩屋のおとりさん運がよい 山へ行く日にゃ雪が降る」という民謡が挿入されているのですが、そこには次のような説明が付け加えられていました。
「楢山へ行く日に雪が降ればその人は運がよい人であると云い伝えられていた。塩屋にはおとりさんという人はいないのであるが、何代か前には実在した人であって、その人が山へ行く日に雪が降ったということは運がよい人であるという代表人物で、歌になって伝えられているのである。」
同時に、おりんを山に捨てに行く前日の晩のエピソードには、経験者が辰平に、大変だったら途中の谷底に落としちゃってもいいよってこっそり耳打ちする場面まで描かれているのですが、深沢の作品世界というのは、どうもある種の真摯な信仰だとか、神様がいる神話世界などとは対極の、いろんなことに理由なんかないんだっていう、虚無的な世界観が根底にあったように思います。
そして、そこに流れているある種の音楽として、作者の語りや登場人物たちの会話があって、人の生き死にがそこで歌われていく。深沢はギターのリサイタルを開いたり、日劇ミュージック・ホールの正月公演に出演したりもしていましたから、文学が先にある根っからの文学者というより、むしろ音楽が先にある人だったのかもしれません。
そういう「死んじゃったらそれまで」だし、どこかで生きる喜びを徹底的に突き放したような視点から書かれた作品を、「豊かな日本」の入口に立っていた多くの日本人がすすんで読んでいた訳ですから、当時の人たちは現代の日本人よりよっぽど人生のなんたるかを分かっていたのではないでしょうか。
今期のふたご座もまた、そうしたゴロリと野太い、乾いたユーモアをもって、自身の生き様やその後始末について思いを巡らせ、時にはそれを歌にのせて存分に歌ってみるといいでしょう(ちなみに本書の巻末には深沢が作詞・作曲した劇中歌も載っています)。
参考:深沢七郎『楢山節考』(新潮文庫)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは「異常という虚構の解体」。

私たちはしばしば自分が理解できないものを「気持ち悪い」とか「おかしい」などと生理的に拒絶しがちですが、特に性の領域においては、近年ほど「そうした生理自体がひとつの虚構に過ぎないのでは?」という疑義を突きつけられるようになったことは歴史上ないのではないでしょうか。
現在のところ私たちが自明視している「男性」と「女性」という区分けや両者を結合させる人間の生殖方法は、考えてみれば、自然が生んだ無数の生命が、さまざまに工夫をこらす驚くべき性の在り方の多様性のなかで至極単純で特殊な一事例に過ぎません。
例えば、民俗学者の南方熊楠は「鳥を食うて王になった話―性に関する世界各国の伝説」という興味深い論文の中で、両性具有者と去勢者を両極とした、さまざまな度合いの性の「中間者」の例だけを集め、男性と女性のどちらでもないか(性の欠如)、そのどちらでもある(性の過剰)ような、一つの性に同一化されず、また性器で結ばれる正常な性愛の領域から逸脱した例外的な個体たちの物語や生き様を徹底的に物語っていきました。
そして彼自身の実感にも基づき、性的異常者の本質に関わる部分について次のように説明しています。
「以上ざっと述べた通り、半男女と通称する内にも種々ある。身体の構造全く男とも女とも判らぬ人が稀にありて、選挙や徴兵検査の節少なからず役人を手古摺らせる。男精や月経を最上の識別標と主張する学者もあるが、ヴィルヒョウ等が逢うたごとき一身にこの両物を兼ね具えた例もあって、正真正銘の半男女たり。その他は、あるいは男分女分より少なきに随って、男性半男女、女性半男女と判つ。これは体質上の談だが、あるいは体質と伴い、あるいは体質と離れて、また精神上の半男女もある。ツールド説に、男性半男女に男を好む者多いが、女性半男女で女を好む者はそれより少ない。このんで男女どちらをも歓迎する半男女は稀有だ、と」
つまり、私たちはつねに精神的な同性愛と異性愛、身体的な同性愛と異性愛のはざまでみずからの性を形づくるのであって、その性の形態は、彼が研究したクサビラ(菌類が生殖のためにとる形態)のように、オス―メスをきっぱりと分割する直線ではなく、やわらかな曲線を描き、無限の度合いをもちながら常に変化し続けるものなのです。
熊楠はそうして強制的に「異常者」として分類され排除されてしまった種族のカテゴリーを自身の直感と実感、そして膨大な文献学上の研究に基づきながら解体し、新たな生に作り替えていきました。
同様に今期のかに座もまた、世間では「異常」とされる生き様や個体、物語をただ排除する代わりに、どうしたらそれらを新たな生に転換していけるか、といったことがテーマになっていくかも知れません。
参考:中沢新一編『南方熊楠コレクション第三巻 浄のセクソロジー』(河出文庫)
現在のところ私たちが自明視している「男性」と「女性」という区分けや両者を結合させる人間の生殖方法は、考えてみれば、自然が生んだ無数の生命が、さまざまに工夫をこらす驚くべき性の在り方の多様性のなかで至極単純で特殊な一事例に過ぎません。
例えば、民俗学者の南方熊楠は「鳥を食うて王になった話―性に関する世界各国の伝説」という興味深い論文の中で、両性具有者と去勢者を両極とした、さまざまな度合いの性の「中間者」の例だけを集め、男性と女性のどちらでもないか(性の欠如)、そのどちらでもある(性の過剰)ような、一つの性に同一化されず、また性器で結ばれる正常な性愛の領域から逸脱した例外的な個体たちの物語や生き様を徹底的に物語っていきました。
そして彼自身の実感にも基づき、性的異常者の本質に関わる部分について次のように説明しています。
「以上ざっと述べた通り、半男女と通称する内にも種々ある。身体の構造全く男とも女とも判らぬ人が稀にありて、選挙や徴兵検査の節少なからず役人を手古摺らせる。男精や月経を最上の識別標と主張する学者もあるが、ヴィルヒョウ等が逢うたごとき一身にこの両物を兼ね具えた例もあって、正真正銘の半男女たり。その他は、あるいは男分女分より少なきに随って、男性半男女、女性半男女と判つ。これは体質上の談だが、あるいは体質と伴い、あるいは体質と離れて、また精神上の半男女もある。ツールド説に、男性半男女に男を好む者多いが、女性半男女で女を好む者はそれより少ない。このんで男女どちらをも歓迎する半男女は稀有だ、と」
つまり、私たちはつねに精神的な同性愛と異性愛、身体的な同性愛と異性愛のはざまでみずからの性を形づくるのであって、その性の形態は、彼が研究したクサビラ(菌類が生殖のためにとる形態)のように、オス―メスをきっぱりと分割する直線ではなく、やわらかな曲線を描き、無限の度合いをもちながら常に変化し続けるものなのです。
熊楠はそうして強制的に「異常者」として分類され排除されてしまった種族のカテゴリーを自身の直感と実感、そして膨大な文献学上の研究に基づきながら解体し、新たな生に作り替えていきました。
同様に今期のかに座もまた、世間では「異常」とされる生き様や個体、物語をただ排除する代わりに、どうしたらそれらを新たな生に転換していけるか、といったことがテーマになっていくかも知れません。
参考:中沢新一編『南方熊楠コレクション第三巻 浄のセクソロジー』(河出文庫)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは「物深い、偉大なる人間苦」。

いまテレビやニュースは、関東平野で行われている国際的なハレの興行イベント関連のこと一色ですが、そうしたメディアの盛り上がりを見ていると、柳田國男の『遠野物語』(1910)の序文の中に書かれた有名なメッセージを思い出さずにはいられません。
「国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」
聞き書き形式で書かれた本書は、日本民俗学の父である柳田國男の業績の出発点に位置づけられ、彼が34歳の時に出版されたものですが、明治以降、急速な近代化の中で失われつつあった様々な民間伝承を伝えてくれる『物語』に触れたことで、実際に多くの人が戦慄したことでしょう。しかし、一方でその母胎をなす「無数の山神山人の伝説」を伝えてきた「さらに物深き所」に言及したり、そもそもそれを見ようとした人はほとんどいなかったように思います。
その証拠に、『遠野物語』から16年後に刊行された『山の人生』には、同じ「物深い」という言葉を用いて、次のように書かれていたのです。
「我々が空想で描いて見る世界よりも、隠れた現実の方が遥かに物深い。また我々をして考えしめる。これは今自分の説こうとする問題と直接の関係はないのだが、こんな機会でないと思い出すこともなく、また何びとも耳を貸そうとはしまいから、序文の代りに書き残して置くのである。」
ここで「隠れた現実」として先立って紹介されていたのは、例えば世間がひどく不景気だった明治中頃の美濃の山中で、炭焼きを生業にしていた五十男が、あまりの貧しさに子供二人がすすんで研いだまさかりで、思い余ってそのまま斬り殺してしまった話だったり、親子三人の心中事件でひとりだけ生き残ってしまった女の運命をめぐるものだったり。いずれも「ただ一度、この一見書類で読んで見たことがある」程度だったそうですが、柳田はそれを「あの偉大なる人間苦の記録」と呼びました。
柳田國男は近代社会が忘れ去ろうとしている「山の人生」に刻みつけられ、埋め込まれた伝承の中にこそ、日本人である限り決して忘れてはならない「物深い、偉大なる人間苦」が延々と積み重ねられてきたのだという認識を持っていたのです。
今期のしし座もまた、そもそもみずからの現実認識やそこから自然発生してくる営みは「物深い」ものでなければならないのだという思いが、より一層強くなっていくのではないでしょうか。
参考:柳田國男『遠野物語・山の人生』(岩波文庫)
「国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」
聞き書き形式で書かれた本書は、日本民俗学の父である柳田國男の業績の出発点に位置づけられ、彼が34歳の時に出版されたものですが、明治以降、急速な近代化の中で失われつつあった様々な民間伝承を伝えてくれる『物語』に触れたことで、実際に多くの人が戦慄したことでしょう。しかし、一方でその母胎をなす「無数の山神山人の伝説」を伝えてきた「さらに物深き所」に言及したり、そもそもそれを見ようとした人はほとんどいなかったように思います。
その証拠に、『遠野物語』から16年後に刊行された『山の人生』には、同じ「物深い」という言葉を用いて、次のように書かれていたのです。
「我々が空想で描いて見る世界よりも、隠れた現実の方が遥かに物深い。また我々をして考えしめる。これは今自分の説こうとする問題と直接の関係はないのだが、こんな機会でないと思い出すこともなく、また何びとも耳を貸そうとはしまいから、序文の代りに書き残して置くのである。」
ここで「隠れた現実」として先立って紹介されていたのは、例えば世間がひどく不景気だった明治中頃の美濃の山中で、炭焼きを生業にしていた五十男が、あまりの貧しさに子供二人がすすんで研いだまさかりで、思い余ってそのまま斬り殺してしまった話だったり、親子三人の心中事件でひとりだけ生き残ってしまった女の運命をめぐるものだったり。いずれも「ただ一度、この一見書類で読んで見たことがある」程度だったそうですが、柳田はそれを「あの偉大なる人間苦の記録」と呼びました。
柳田國男は近代社会が忘れ去ろうとしている「山の人生」に刻みつけられ、埋め込まれた伝承の中にこそ、日本人である限り決して忘れてはならない「物深い、偉大なる人間苦」が延々と積み重ねられてきたのだという認識を持っていたのです。
今期のしし座もまた、そもそもみずからの現実認識やそこから自然発生してくる営みは「物深い」ものでなければならないのだという思いが、より一層強くなっていくのではないでしょうか。
参考:柳田國男『遠野物語・山の人生』(岩波文庫)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは「感情システムのバランス」。

古来より都市での暮らしというのは、基本的に「興奮」と「脅威」のシステムだけが活性化しやすいものでしたが、「パンとサーカスの都」として世界史に刻まれた古代ローマなどはその典型と言えるでしょう。
しかし、私たちの感情システムというのは、けっして「興奮」と「脅威」だけでは構成されていません。例えば、サイエンス・ライターである鈴木祐の『最高の体調』では、人間の心の働きを次の3種類に分類した上で、その3つがバランスよく機能してこそ最高のパフォーマンスが出せるのだと言います。
①「興奮」:「喜び」や「快楽」といったポジティブな感情を作り、獲物や食事を探すためのモチベーションを生み出すシステム。おもにドーパミンで制御されている。
②「満足」:「安らぎ」や「安心感」といったポジティブな感情を作り、同じ種属とのコミュニケーションに役に立つシステム。オキシトシンなどで制御されている。
③「脅威」:「不安」や「警戒」といったネガティブな感情を作り、外敵や危険から身を守るためのシステム。アドレナリンやコルチゾールなどで制御されている。
この3つのうち、例えば①のような快楽ばかりを追求すれば「人生は退廃に至り」、②のような安らぎだけになれば「毎日に前進はなく」、③のような不安ばかりの暮らしになれば「日々をよどませ」てしまいますが、現代社会、とくにオリンピックとコロナ禍のコラボで湧きつつ、濃密接触の機会が著しく低下している現在の東京などの都市では、極端に「興奮」と「脅威」(①と③)のどちらかに振れやすい環境にあるのだと言えるでしょう。
従来であれば、こうした時に感じるストレスもまたショッピングやカラオケ、店舗での飲食、マッサージやサウナなどの資本主義経済のサイクル内で解消してきた訳ですが、このまま感染者数が急増していけばそれも難しくなってくるはずです。
ただ、『最高の体調』では、3つの心的機能をバランスさせる最高の方法の一つとして、「自然とのふれあい」を挙げており、これはマッサージなどの定番リラクゼーションを上回る癒し効果をもっているのだそう。
今期のおとめ座もまた、どうしたら自分の体の副交感神経を活性化できるかを追求していく上で、生活習慣のなかに少しでも自然とふれあう機会を創り出し、失われつつある感情システムのバランスを図っていきたいところです。
参考:鈴木祐『最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法』(クロスメディア・パブリッシング)
しかし、私たちの感情システムというのは、けっして「興奮」と「脅威」だけでは構成されていません。例えば、サイエンス・ライターである鈴木祐の『最高の体調』では、人間の心の働きを次の3種類に分類した上で、その3つがバランスよく機能してこそ最高のパフォーマンスが出せるのだと言います。
①「興奮」:「喜び」や「快楽」といったポジティブな感情を作り、獲物や食事を探すためのモチベーションを生み出すシステム。おもにドーパミンで制御されている。
②「満足」:「安らぎ」や「安心感」といったポジティブな感情を作り、同じ種属とのコミュニケーションに役に立つシステム。オキシトシンなどで制御されている。
③「脅威」:「不安」や「警戒」といったネガティブな感情を作り、外敵や危険から身を守るためのシステム。アドレナリンやコルチゾールなどで制御されている。
この3つのうち、例えば①のような快楽ばかりを追求すれば「人生は退廃に至り」、②のような安らぎだけになれば「毎日に前進はなく」、③のような不安ばかりの暮らしになれば「日々をよどませ」てしまいますが、現代社会、とくにオリンピックとコロナ禍のコラボで湧きつつ、濃密接触の機会が著しく低下している現在の東京などの都市では、極端に「興奮」と「脅威」(①と③)のどちらかに振れやすい環境にあるのだと言えるでしょう。
従来であれば、こうした時に感じるストレスもまたショッピングやカラオケ、店舗での飲食、マッサージやサウナなどの資本主義経済のサイクル内で解消してきた訳ですが、このまま感染者数が急増していけばそれも難しくなってくるはずです。
ただ、『最高の体調』では、3つの心的機能をバランスさせる最高の方法の一つとして、「自然とのふれあい」を挙げており、これはマッサージなどの定番リラクゼーションを上回る癒し効果をもっているのだそう。
今期のおとめ座もまた、どうしたら自分の体の副交感神経を活性化できるかを追求していく上で、生活習慣のなかに少しでも自然とふれあう機会を創り出し、失われつつある感情システムのバランスを図っていきたいところです。
参考:鈴木祐『最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法』(クロスメディア・パブリッシング)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは「ものの見方の補色関係」。
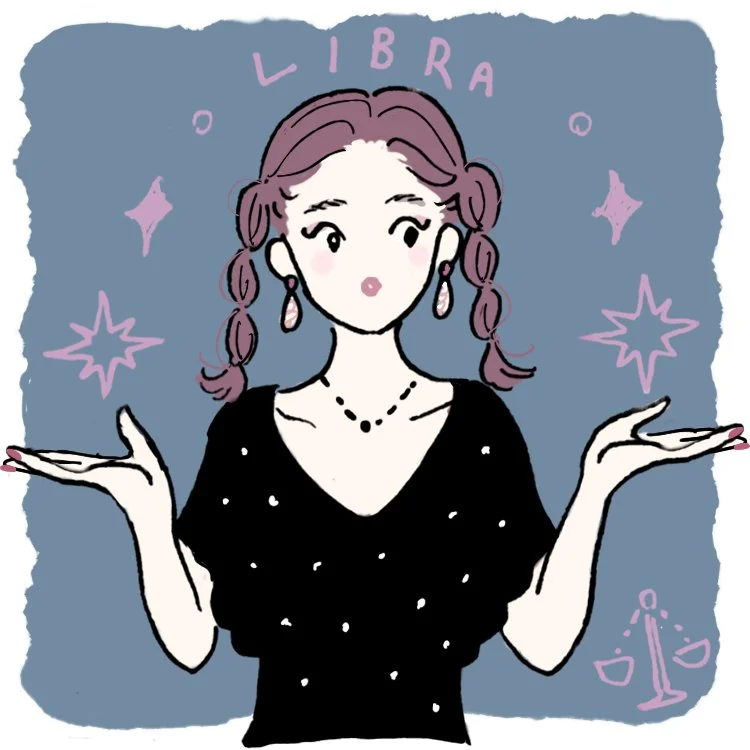
近年、従来は健常者と呼ばれてきた多数派の人間のことを「定型発達を保持している(略してNT)」と表現したり、逆に単に異常者や障害者として分類されてきたマイノリティを「非定型」であると言い直したりする風潮がにわかに顕著になってきたように感じます。
さらに一部の人たちのあいだでは今日の先進国社会の状況というのは、時代を経るにつれNTの人たちが狩猟採集生活に特化した異能者であるマイノリティを駆逐し、自分たちに都合のよい生活環境へと変えてきた結果ではないかという議論さえ起こっているのだとか。
きっかけは1996年、フランス南西部のラスコーで子どもがかくれんぼ中に偶然発見した3万年以上前のクロマニヨン人による洞窟壁画でした。そこには、人間の姿や植物や身近な小動物はほとんど描かれず、その99%が大型哺乳類で、当時の人々の狩りの対象だったシカやバイソンばかりか、脅威でしかなかったライオンやハイエナまでもが実に写実的に描かれていたことで世界中を仰天させました。
同時に、その美術描写は、文明勃興以降ではルネサンスになって初めて見られるようになったほどに高度な技法を用いたものだったため、この驚くべき事実や歴史的な不連続性にどう説明をつければよいのかという問いが大きな波紋を呼びました。
そうした中、同じ人類といえどもひとつのタイプの心の持ち方に限定されないのではないかという仮説を投げかけているのが「脳神経系の多様性(ニューロダイバーシティ)」という立場なのだそうです。
そして例えば、京大の霊長類研究所の正高信男は、仮説をさらに一歩進めて、洞窟壁画の描画スタイルと現代の自閉症者に見られる特徴との一致について、次のように指摘しています((『ニューロダイバーシティと発達障害』、2019))。
「世界の構成要素を人と自然に二分するならば、NTは自然を犠牲にして人に注意を払っている一方、自閉症児は人というものにとわれることなく自然を認識することができるということなのだ。(中略)双方のものの見方が互いに相補い合って初めて、われわれは今日あるような社会を形成することが可能であったというのが、ニューロダイバーシティの考え方であり、たとえば洞窟壁画ひとつとってみても、その特徴にこうした発想があながち見当はずれでないことの証拠を見ることができるのだと考えられるのだ。」
今期のてんびん座もまた、こうした脳神経系の多様性の立場にならって、自分のものの見方を補ってくれる補色関係にあるような相手や見方を取り入れてみるといいでしょう。
参考:正高信男『ニューロダイバーシティと発達障害』(北大路書房)
さらに一部の人たちのあいだでは今日の先進国社会の状況というのは、時代を経るにつれNTの人たちが狩猟採集生活に特化した異能者であるマイノリティを駆逐し、自分たちに都合のよい生活環境へと変えてきた結果ではないかという議論さえ起こっているのだとか。
きっかけは1996年、フランス南西部のラスコーで子どもがかくれんぼ中に偶然発見した3万年以上前のクロマニヨン人による洞窟壁画でした。そこには、人間の姿や植物や身近な小動物はほとんど描かれず、その99%が大型哺乳類で、当時の人々の狩りの対象だったシカやバイソンばかりか、脅威でしかなかったライオンやハイエナまでもが実に写実的に描かれていたことで世界中を仰天させました。
同時に、その美術描写は、文明勃興以降ではルネサンスになって初めて見られるようになったほどに高度な技法を用いたものだったため、この驚くべき事実や歴史的な不連続性にどう説明をつければよいのかという問いが大きな波紋を呼びました。
そうした中、同じ人類といえどもひとつのタイプの心の持ち方に限定されないのではないかという仮説を投げかけているのが「脳神経系の多様性(ニューロダイバーシティ)」という立場なのだそうです。
そして例えば、京大の霊長類研究所の正高信男は、仮説をさらに一歩進めて、洞窟壁画の描画スタイルと現代の自閉症者に見られる特徴との一致について、次のように指摘しています((『ニューロダイバーシティと発達障害』、2019))。
「世界の構成要素を人と自然に二分するならば、NTは自然を犠牲にして人に注意を払っている一方、自閉症児は人というものにとわれることなく自然を認識することができるということなのだ。(中略)双方のものの見方が互いに相補い合って初めて、われわれは今日あるような社会を形成することが可能であったというのが、ニューロダイバーシティの考え方であり、たとえば洞窟壁画ひとつとってみても、その特徴にこうした発想があながち見当はずれでないことの証拠を見ることができるのだと考えられるのだ。」
今期のてんびん座もまた、こうした脳神経系の多様性の立場にならって、自分のものの見方を補ってくれる補色関係にあるような相手や見方を取り入れてみるといいでしょう。
参考:正高信男『ニューロダイバーシティと発達障害』(北大路書房)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは「「夜」を受け入れる」。

いまワクチン接種の是非やその供給をめぐる情報が、日々のニュースやSNSなどで錯綜していますが、もはや多くの人はそこで一喜一憂することに疲れ果ててしまい、SNS自体をやめたりテレビやネットのニュースを以前より見なくなったという人も少なくないのではないでしょうか。
作家の五木寛之は「「見えない不安」に「心の抗体」を」を題したエッセイのなかで、コロナ禍が世界中を不気味な不安に陥れている中で、知らず知らずのうちに私たちの心が蝕まれており、私たちは今こそ精神に「心の抗体」をもつ必要があるのだと訴えています。
五木は「この感染症はおそらく、闘っても闘ってもすぐには終わらず、ダラダラと続くでしょう。心がしおれてきた時に、コロナ鬱というような「心の病」に悩まされる人も出てきてしまうでしょう」といった見通しを語った上で、自身の著作『歌いながら夜を往け』のタイトルに触れながら以下のように述べています。
「いまを「夜」として受け入れる。「朝」が訪れる見込みがあるかもわからない。だけど、口笛を吹きながら「夜を往け」。「夜」だからといって、陰々滅々とうなだれている必要はないのです。一方で、「夜明けは近い」と過度な期待を寄せることもしない。」
「私たちはいま、「夜」を受け入れ、口笛を吹きながら歩いていくしかないのでないか。朝は歩いていくなかで明ける。」
五木はここですべてを想定内に置こうとする文明の光が届かず、こちらの意図がすべからく無に帰するような絶対的な「夜」の闇に逆らわず、まずそれを「心の抗体」としてきちんと受け入れた上で、さながら目に見えない力の動きに合わせるかのように「口笛を吹き」つつ、日々精神と肉体の歩調を合わせていくことこそが、いまの英雄やリーダー不在の日本社会を生き延びるのにふさわしい態度として説いているのです。
今期のさそり座もまた、人間の外側にある、人間をはるかに超えた自然と自分が地続きであることを感じながら、少しずつその通り道を歩いていくことに慣れていきたいところです。
参考:『文藝春秋2020年10月号 コロナ時代の生と死』(文藝春秋)
作家の五木寛之は「「見えない不安」に「心の抗体」を」を題したエッセイのなかで、コロナ禍が世界中を不気味な不安に陥れている中で、知らず知らずのうちに私たちの心が蝕まれており、私たちは今こそ精神に「心の抗体」をもつ必要があるのだと訴えています。
五木は「この感染症はおそらく、闘っても闘ってもすぐには終わらず、ダラダラと続くでしょう。心がしおれてきた時に、コロナ鬱というような「心の病」に悩まされる人も出てきてしまうでしょう」といった見通しを語った上で、自身の著作『歌いながら夜を往け』のタイトルに触れながら以下のように述べています。
「いまを「夜」として受け入れる。「朝」が訪れる見込みがあるかもわからない。だけど、口笛を吹きながら「夜を往け」。「夜」だからといって、陰々滅々とうなだれている必要はないのです。一方で、「夜明けは近い」と過度な期待を寄せることもしない。」
「私たちはいま、「夜」を受け入れ、口笛を吹きながら歩いていくしかないのでないか。朝は歩いていくなかで明ける。」
五木はここですべてを想定内に置こうとする文明の光が届かず、こちらの意図がすべからく無に帰するような絶対的な「夜」の闇に逆らわず、まずそれを「心の抗体」としてきちんと受け入れた上で、さながら目に見えない力の動きに合わせるかのように「口笛を吹き」つつ、日々精神と肉体の歩調を合わせていくことこそが、いまの英雄やリーダー不在の日本社会を生き延びるのにふさわしい態度として説いているのです。
今期のさそり座もまた、人間の外側にある、人間をはるかに超えた自然と自分が地続きであることを感じながら、少しずつその通り道を歩いていくことに慣れていきたいところです。
参考:『文藝春秋2020年10月号 コロナ時代の生と死』(文藝春秋)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは「大胆な大局観より些細な日常感覚を」。

「吾々の目にとまらないほどのごく小さな原因が、吾々の認めざるを得ないような重大な結果をひきおこすことがあると、かかるとき吾々はその結果は偶然に起ったという。」
これはフランスの偉大な数学者アンリ・ポアンカレによる偶然性の定義なのですが、ワクチン接種済みの人でもコロナに感染したケースが報道され始めた現在の状況を踏まえると、ここに書かれていることはほとんど私たちの日常的なリアリティそのものと言えます。
ポアンカレはさらに「小さな原因」に「複雑な原因」を加え、自分の定義の有効性を検証するため、さまざまな事例を出していくのですが、その中にやはり日常生活から取材した例があります。
ひとりの男が所用のために通りを歩いて、とある家の前を過ぎる。その家の屋根のうえでは屋根職人が仕事をしている。ところが、この職人がうっかりして手にしていた瓦を落とす。その瓦が、そのとき下を通りかかった男の頭を直撃し、その男は死ぬ。ポアンカレはこうした偶然も、やはり「小さな偶然」ないしは「複雑な原因」に還元できるとして、次のように述べています。
「概して互に縁のない二つの世界が互に作用しあうときは、その作用の法則は必ず非常に複雑なものにかぎるのであって、また他方に於いて、その二つの世界の最初の状況がきわめてわずかに変化しさえすれば、この作用は起こらないでも済んだであろう。この男が一秒遅くとおるか、屋根師が一秒早く瓦を落とすかするためには、いずれにしてもきわめて些細な事情で充分であったであろう。」
ポアンカレの偶然論の要諦は「原因に於ける小さな差異と結果に於ける大きな差異」の対照(ないし強調)にこそあった訳ですが、これは逆に言えば、物事をみだりに単純化せず、また、ひとつひとつの些細なディティールに目をとめる日常感覚を研ぎ澄ませていくことができれば、少なくとも偶然によるショックをやわらげることはできるということでもあるのではないでしょうか。
今期のいて座もまた、いつも以上に生活の解像度をあげ、物事の複雑さへと感覚的に開かれていくことを大切にしていきたいところです。
参考:アンリ・ポアンカレ、吉田洋一訳『科学と方法』(岩波文庫)
これはフランスの偉大な数学者アンリ・ポアンカレによる偶然性の定義なのですが、ワクチン接種済みの人でもコロナに感染したケースが報道され始めた現在の状況を踏まえると、ここに書かれていることはほとんど私たちの日常的なリアリティそのものと言えます。
ポアンカレはさらに「小さな原因」に「複雑な原因」を加え、自分の定義の有効性を検証するため、さまざまな事例を出していくのですが、その中にやはり日常生活から取材した例があります。
ひとりの男が所用のために通りを歩いて、とある家の前を過ぎる。その家の屋根のうえでは屋根職人が仕事をしている。ところが、この職人がうっかりして手にしていた瓦を落とす。その瓦が、そのとき下を通りかかった男の頭を直撃し、その男は死ぬ。ポアンカレはこうした偶然も、やはり「小さな偶然」ないしは「複雑な原因」に還元できるとして、次のように述べています。
「概して互に縁のない二つの世界が互に作用しあうときは、その作用の法則は必ず非常に複雑なものにかぎるのであって、また他方に於いて、その二つの世界の最初の状況がきわめてわずかに変化しさえすれば、この作用は起こらないでも済んだであろう。この男が一秒遅くとおるか、屋根師が一秒早く瓦を落とすかするためには、いずれにしてもきわめて些細な事情で充分であったであろう。」
ポアンカレの偶然論の要諦は「原因に於ける小さな差異と結果に於ける大きな差異」の対照(ないし強調)にこそあった訳ですが、これは逆に言えば、物事をみだりに単純化せず、また、ひとつひとつの些細なディティールに目をとめる日常感覚を研ぎ澄ませていくことができれば、少なくとも偶然によるショックをやわらげることはできるということでもあるのではないでしょうか。
今期のいて座もまた、いつも以上に生活の解像度をあげ、物事の複雑さへと感覚的に開かれていくことを大切にしていきたいところです。
参考:アンリ・ポアンカレ、吉田洋一訳『科学と方法』(岩波文庫)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは「ヴァニタス」。

16世紀から17世紀にかけてヨーロッパ北部で多く描かれた静物画のジャンルに「ヴァニタス」というものがあります。宮下規久郎の『モチーフで読む美術史』によれば、「ヴァニタス」とは、はラテン語で「空虚」「むなしさ」を意味する言葉で、中世以来の「メメント・モリ(死を想え)」という主題と同じく、「この世のものはすべて虚しく朽ちていく」という教訓として、寓意的な静物画のジャンルのひとつとして盛んに描かれたのだそうです。
例えば、1651年に描かれたダーフィット・バイリーの「ヴァニタスのある自画像」。画中では、若い男が右手に絵を描くときに用いる画杖という道具を手にする一方で、左手を絵にかけています。男は画家自身なのですが、自画像を描いたとき、すでにバイリーは67歳でした。
すなわち、自画像のなかの若い男は、自身の約40年前の姿であり、さらに男が左手で支えている小さな楕円形の画面には、十年ほど前に描いた自画像がはめられています。つまり、ここには若いころの自分と、すこし前の自分の姿が描かれており、それらを描いた現在のバイリーの姿はありません。
バイリーの自画像においても、若い男が腰かけているテーブルの上には、髑髏とともに宝飾類やコイン、消えた蝋燭、花、楽器、ひっくり返った杯などが、所せましと並べられ、さらには空中に二つの大小のシャボン玉が浮かんでいます。
「透明で美しいが、すぐにはかなく消えるシャボン玉は、ヴァニタスにふさわしいモチーフとしてさかんに描かれた」
そしてその脇で、若い男は自身もやがて老いて死にゆくことを悟り、やがて自身の元にも訪れるであろう定めを予見しているのです。
同様に、今期のやぎ座もまた、もしいま自分の自画像を描くとすれば、自身の傍らにどんなモチーフや品々を置くだろうか、そして死にゆく時の自分はいったいどんな顔や風貌をしているのかと、ひと通り思案を巡らせてみるといいかも知れません。
参考:宮下規久郎『モチーフで読む美術史』(ちくま文庫)
例えば、1651年に描かれたダーフィット・バイリーの「ヴァニタスのある自画像」。画中では、若い男が右手に絵を描くときに用いる画杖という道具を手にする一方で、左手を絵にかけています。男は画家自身なのですが、自画像を描いたとき、すでにバイリーは67歳でした。
すなわち、自画像のなかの若い男は、自身の約40年前の姿であり、さらに男が左手で支えている小さな楕円形の画面には、十年ほど前に描いた自画像がはめられています。つまり、ここには若いころの自分と、すこし前の自分の姿が描かれており、それらを描いた現在のバイリーの姿はありません。
バイリーの自画像においても、若い男が腰かけているテーブルの上には、髑髏とともに宝飾類やコイン、消えた蝋燭、花、楽器、ひっくり返った杯などが、所せましと並べられ、さらには空中に二つの大小のシャボン玉が浮かんでいます。
「透明で美しいが、すぐにはかなく消えるシャボン玉は、ヴァニタスにふさわしいモチーフとしてさかんに描かれた」
そしてその脇で、若い男は自身もやがて老いて死にゆくことを悟り、やがて自身の元にも訪れるであろう定めを予見しているのです。
同様に、今期のやぎ座もまた、もしいま自分の自画像を描くとすれば、自身の傍らにどんなモチーフや品々を置くだろうか、そして死にゆく時の自分はいったいどんな顔や風貌をしているのかと、ひと通り思案を巡らせてみるといいかも知れません。
参考:宮下規久郎『モチーフで読む美術史』(ちくま文庫)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは「非時間(ときじく)の小径」。

オリンピックにしろ、医療崩壊にしろ、いまこれまで政府やマスコミ、電通などの権力サイドがつくりあげてきた「現実」の揺らぎが、もはや修復不可能なほどに揺らいでいますが、そもそも「現実」というのは、本来そこに生きている人たちの協力のもとででっちあげられ、危機のたびに揺らいできた脆弱なものでもありました。
加えて、情報チャンネルが多元化しバーチャル空間へ簡単にアクセスできるようになってきた現代社会では、現実と非現実をスムーズに行き来できる柔軟性を自然と身につけている人も増えてきたために、ますます単一の「現実」を成立させることは難しくなってきているのでしょう。
かつて思想家のハンナ・アーレントは、人はそうした精神の柔軟性を、孤独のうちで為される自己自身との対話において獲得していくのだとして、そうした自己自身との対話を「精神の生活」と呼びました。
それはたえず生成変化しているこの世の時間の流れから一寸だけ抜け出た先で初めて営むことができるものであり、さらにそうした自己内対話が営まれる領域のことを「非時間(ときじく)の小径」とも名付けました。彼女は言います。
「人間はまさしく思考するかぎりでのみ、すなわち時間による規定を受けつけない(略)かぎりでのみ、自らの具体的存在における完全なる現実として、過去と未来の間の時間の裂け目のうちで生きる。」
すなわち、過去と未来を宙づりにして静止させている今こそが、哲学する精神の生が生きている時なのであり、その静止する今は、「歴史としてのいつのことというのではなく、地上において人間が存在し始めて以来ずっとあったように見える」のだと。
「思考の活動様式は死すべき人間が住まう時間の空間のなかにこの非時間の小径を踏み固める。そして思考の歩み、つまり想起と予期の歩みは、触れるものすべてをこの非時間の小径に保存することで、歴史の時間と個人の生の時間による破壊から救うのである。」
「時間の奥底そのものの内にあるこの密やかな非時間の空間は、われわれが生まれてくる世界や文化とは異なり、示しうるのみであって過去から受け継いだり伝え残したりはできない。新しい世代それぞれが、それどころか、人間の存在は無限の過去と無限の未来に立ち現われるものであるゆえ、新たに到来する人間一人一人が、この非時間の空間を改めて発見し着実な足取りで踏みならさねばならない。」
今期のみずがめ座もまた、こうした「非時間の小径」にみずからの足で踏みならしていくべし。
参考:H・アーレント、佐藤和夫訳『精神の生活<上 第一部 思考>』(岩波オンデマンドブックス)
加えて、情報チャンネルが多元化しバーチャル空間へ簡単にアクセスできるようになってきた現代社会では、現実と非現実をスムーズに行き来できる柔軟性を自然と身につけている人も増えてきたために、ますます単一の「現実」を成立させることは難しくなってきているのでしょう。
かつて思想家のハンナ・アーレントは、人はそうした精神の柔軟性を、孤独のうちで為される自己自身との対話において獲得していくのだとして、そうした自己自身との対話を「精神の生活」と呼びました。
それはたえず生成変化しているこの世の時間の流れから一寸だけ抜け出た先で初めて営むことができるものであり、さらにそうした自己内対話が営まれる領域のことを「非時間(ときじく)の小径」とも名付けました。彼女は言います。
「人間はまさしく思考するかぎりでのみ、すなわち時間による規定を受けつけない(略)かぎりでのみ、自らの具体的存在における完全なる現実として、過去と未来の間の時間の裂け目のうちで生きる。」
すなわち、過去と未来を宙づりにして静止させている今こそが、哲学する精神の生が生きている時なのであり、その静止する今は、「歴史としてのいつのことというのではなく、地上において人間が存在し始めて以来ずっとあったように見える」のだと。
「思考の活動様式は死すべき人間が住まう時間の空間のなかにこの非時間の小径を踏み固める。そして思考の歩み、つまり想起と予期の歩みは、触れるものすべてをこの非時間の小径に保存することで、歴史の時間と個人の生の時間による破壊から救うのである。」
「時間の奥底そのものの内にあるこの密やかな非時間の空間は、われわれが生まれてくる世界や文化とは異なり、示しうるのみであって過去から受け継いだり伝え残したりはできない。新しい世代それぞれが、それどころか、人間の存在は無限の過去と無限の未来に立ち現われるものであるゆえ、新たに到来する人間一人一人が、この非時間の空間を改めて発見し着実な足取りで踏みならさねばならない。」
今期のみずがめ座もまた、こうした「非時間の小径」にみずからの足で踏みならしていくべし。
参考:H・アーレント、佐藤和夫訳『精神の生活<上 第一部 思考>』(岩波オンデマンドブックス)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは「特異点の発見」。
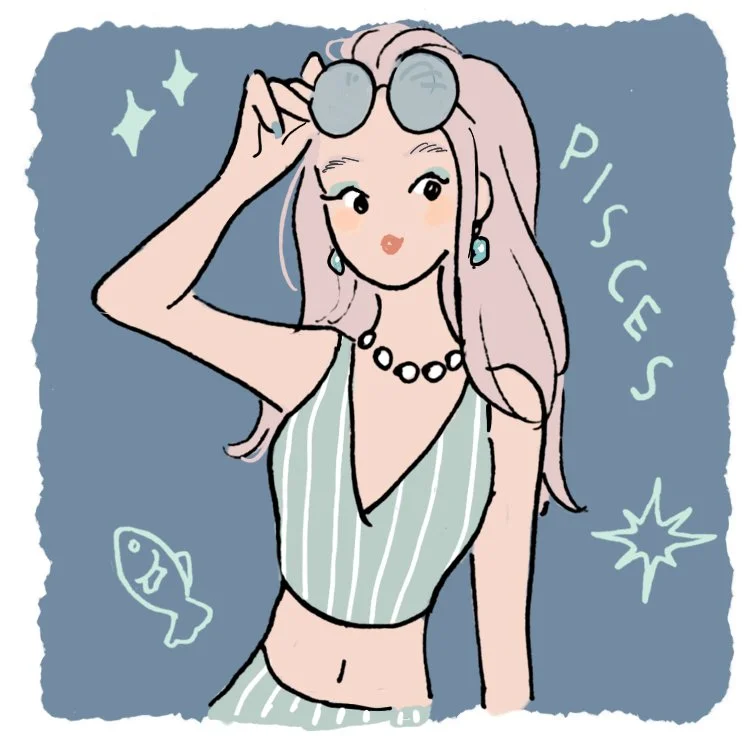
東京オリンピック開会式のパフォーマンスは、日本社会がいまや組織的にその文化的洗練を最大限に取り込んだ「儀式」を作りあげることが難しくなってしまったことを代々的に露呈させてしまった瞬間でもあったように思います。
ただこれは逆に言えば、誰かに言われた通りに何かするだけではつまらないと感じていたり、必要とあらば祝い事であれデモであれ新しい事業であれ、全部自分の手でやってみたいと思ってしまうような類の人たちにとっては、「今こそ始めよ」というスターターピストルの合図となった面もあったはずです。
時と場所を自分で選び、自分の手で狼煙を上げ、自分の責任で終わらせる。古来から文化を担ってきた人たちがそうしてきたように、より純粋かつ極私的な領域で、誰にも邪魔されず、そっと日記や儀式、作品に自分なりの世界観を吹き込んでいく訳です。
例えば、そうした広義の意味での制作のはじめにするべきことについて、『俳句の海に潜る』という対談本では日本の庭づくりにおける「空間を「立てる」」というプロセスが取り上げられています。
「小澤:私は、お花やお茶と俳句はつながるものがあると思っています。切って、立てるということです。発句を立てる。そこから出発して「立句」(連歌・連句の第一句)になる。
(中略)
中沢:庭園を造るのは空間を作る芸術のいちばんのおおもとですから、あらゆる芸術のもとは庭ではないかと僕は思っているのです。今は庭師と言うけれど、昔は「石立僧」と呼んだらしい。石を立てる禅僧、石立僧がまず空間を調べて、どこに点を打てばいいか、宇宙が始まる特異点はここだというところを発見する。そこへ細い石を立てるのが庭造りの最初で、そこから川を掘ったり、木を配置したり、空間の広がりを作る訳です」
素材であれ場所であれ、タイミングであれ相手であれ、他とは明らかに異なる、「ここしかない!」という特異点を見つけていくこと。そしてそこから、自分なりの文化や芸術をもう一度新たに始めていくこと。
それが今期のうお座に課せられたテーマと言えるのではないでしょうか。
参考:小澤實、中沢新一『俳句の海に潜る』(KADOKAWA)
ただこれは逆に言えば、誰かに言われた通りに何かするだけではつまらないと感じていたり、必要とあらば祝い事であれデモであれ新しい事業であれ、全部自分の手でやってみたいと思ってしまうような類の人たちにとっては、「今こそ始めよ」というスターターピストルの合図となった面もあったはずです。
時と場所を自分で選び、自分の手で狼煙を上げ、自分の責任で終わらせる。古来から文化を担ってきた人たちがそうしてきたように、より純粋かつ極私的な領域で、誰にも邪魔されず、そっと日記や儀式、作品に自分なりの世界観を吹き込んでいく訳です。
例えば、そうした広義の意味での制作のはじめにするべきことについて、『俳句の海に潜る』という対談本では日本の庭づくりにおける「空間を「立てる」」というプロセスが取り上げられています。
「小澤:私は、お花やお茶と俳句はつながるものがあると思っています。切って、立てるということです。発句を立てる。そこから出発して「立句」(連歌・連句の第一句)になる。
(中略)
中沢:庭園を造るのは空間を作る芸術のいちばんのおおもとですから、あらゆる芸術のもとは庭ではないかと僕は思っているのです。今は庭師と言うけれど、昔は「石立僧」と呼んだらしい。石を立てる禅僧、石立僧がまず空間を調べて、どこに点を打てばいいか、宇宙が始まる特異点はここだというところを発見する。そこへ細い石を立てるのが庭造りの最初で、そこから川を掘ったり、木を配置したり、空間の広がりを作る訳です」
素材であれ場所であれ、タイミングであれ相手であれ、他とは明らかに異なる、「ここしかない!」という特異点を見つけていくこと。そしてそこから、自分なりの文化や芸術をもう一度新たに始めていくこと。
それが今期のうお座に課せられたテーマと言えるのではないでしょうか。
参考:小澤實、中沢新一『俳句の海に潜る』(KADOKAWA)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ