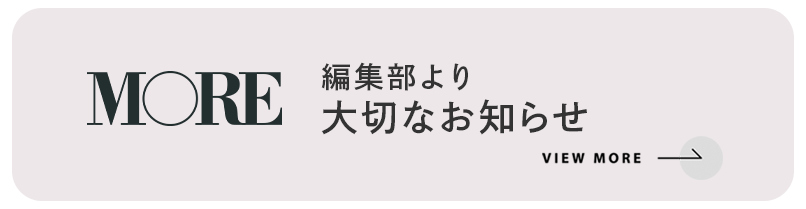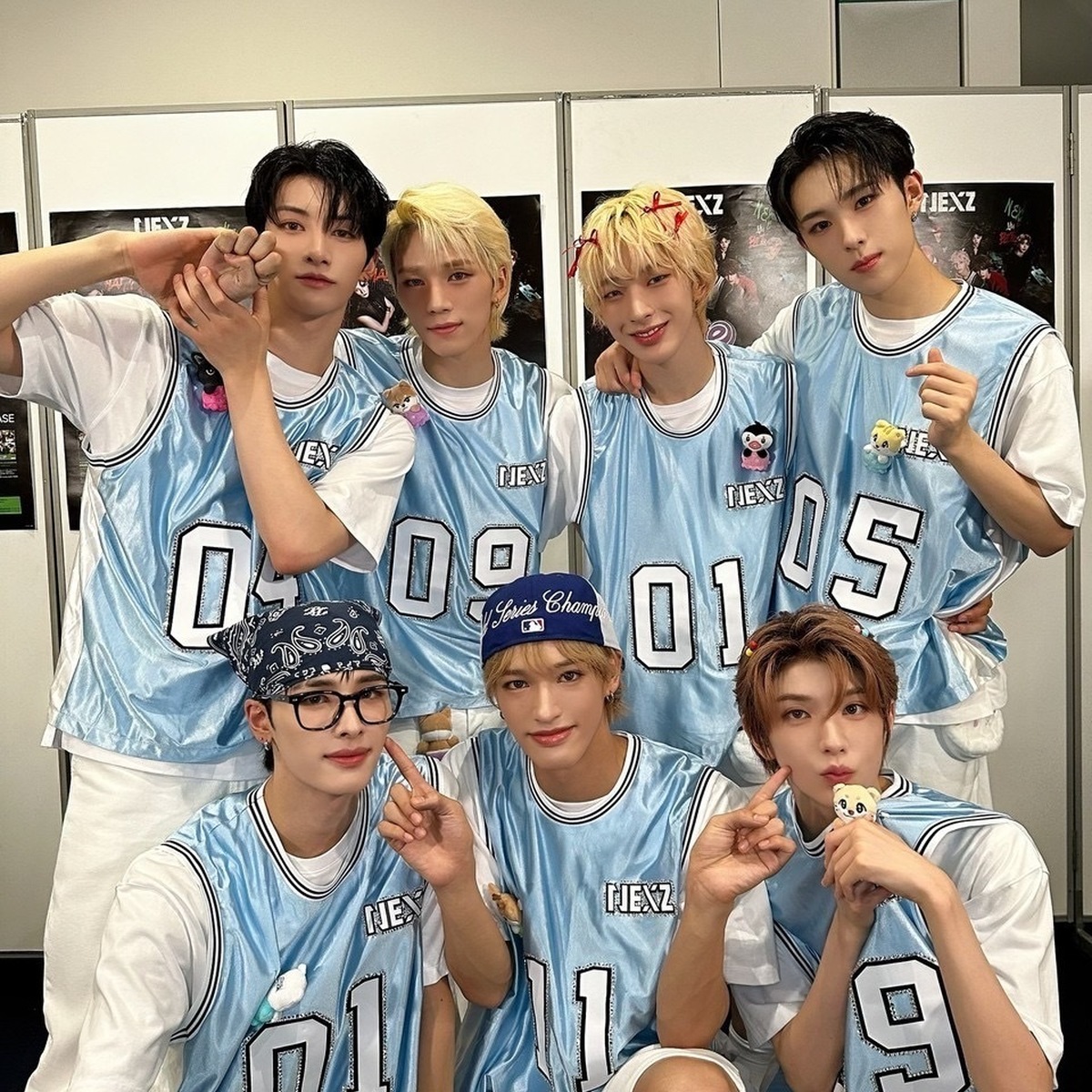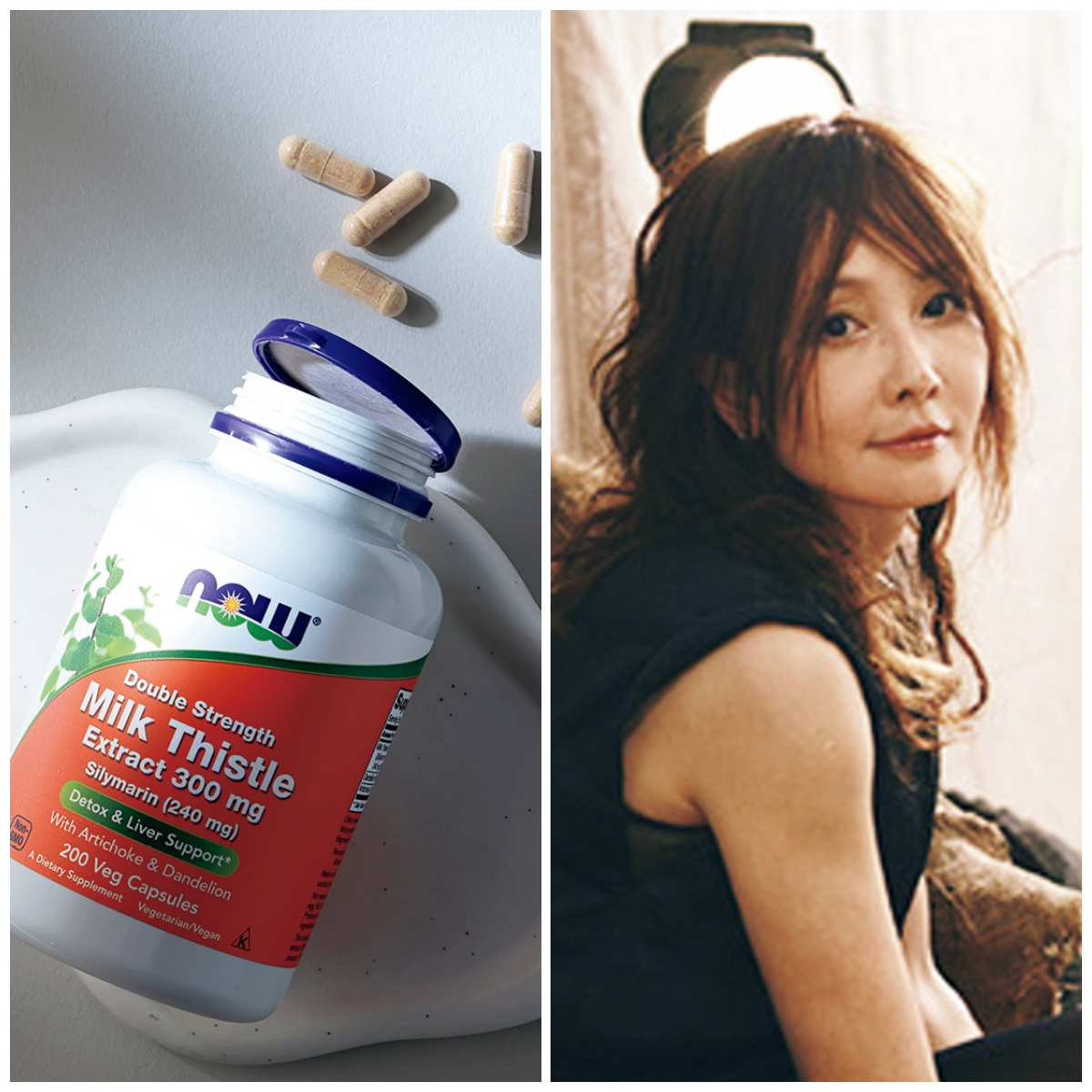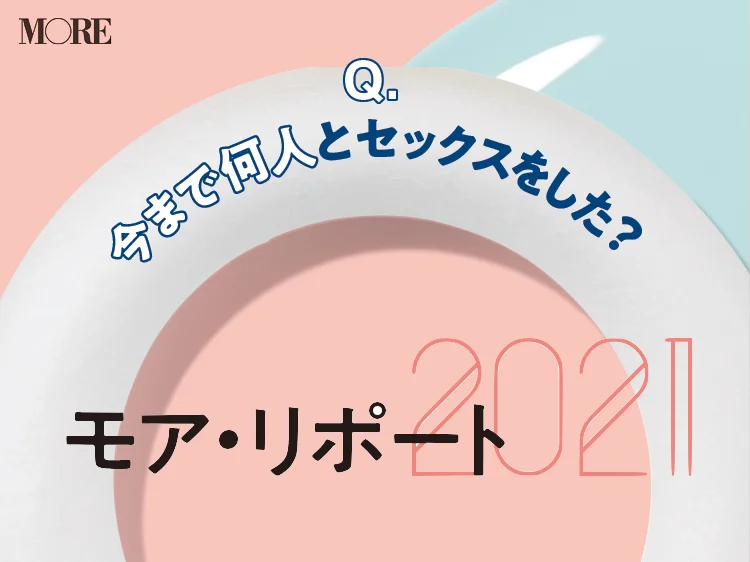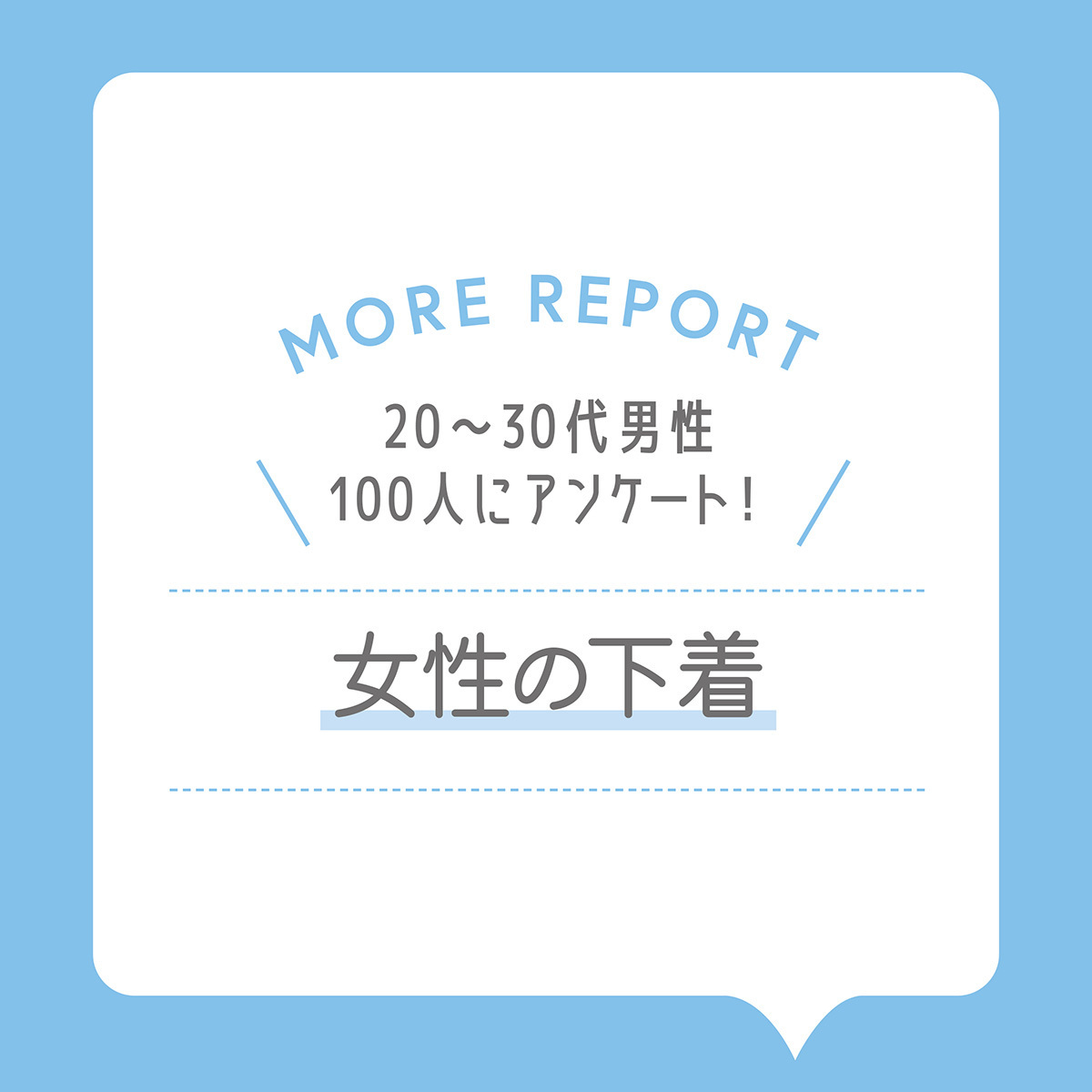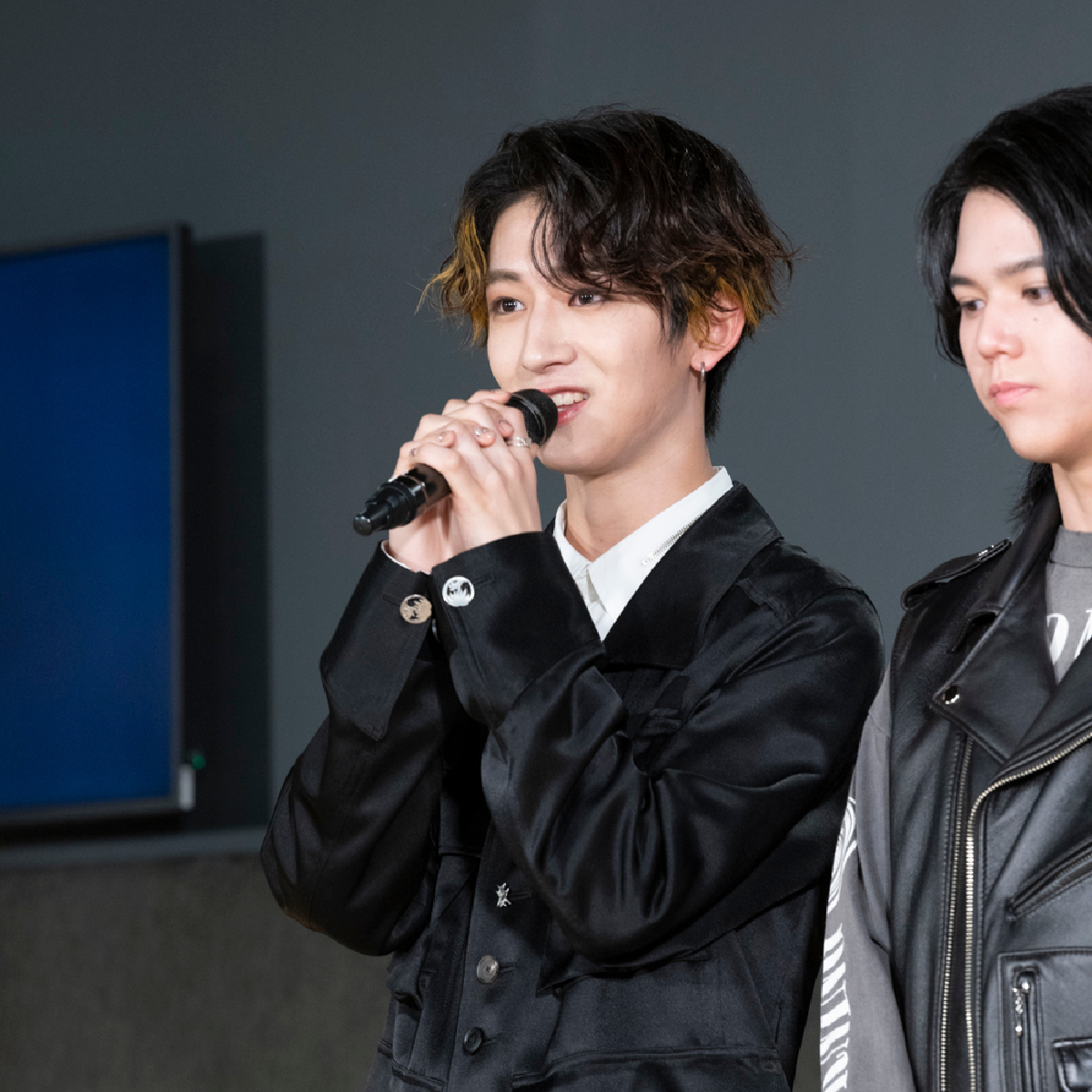【田舎暮らし】田舎のお正月の過ごし方知りたくない?
「田舎っぽいお正月」どれくらいまだ残ってるの?

「田舎っぽいお正月」どれくらいまだ残ってるの?(私の場合)
を紹介します♪
田舎らしい?!過ごし方、是非のぞき見してみてください!
毎年年末、ぎりぎりにならないうちに「大掃除」と「お正月飾り」を玄関や神棚に飾ります。
お餅つき「きね」と「うす」でやってます!

「一日飾り」といって、31日、1日だけ飾ることはよくないと祖母から教わり、29日か遅くとも30日には飾ってます。
なのでお餅つきは28日にだいたい毎年行ってます♪
小さい頃は近所中で集まって行う大きな年末行事のようでもありました。
いつのまにか、おもちの機械がでてきたり、子どもたちが地元を離れたりする中で、随分小さく親戚規模になりました。
小さい頃から大学生になるまでずっと手伝っていたのですが
今年は久々にちょっとだけお手伝い。
特技は「おもちをきれいに丸めること」だったことを思い出しました(笑)
そういえば、おもちをきれいに丸めると、「心がまんまるだからだ」とお手伝いに来てくれる近所のおばちゃんに言われたことがあります。
あの頃とはまるで心も違うけど(笑)そうしてお餅一つでも
”丁寧にやさしく関わる”って大事だよ、ってことなのかな?と今になれば思います。

お正月飾りのあれこれ

飾りには
「餅花木」と言って、木に小さなお餅をつけていくものも。
雪が降っているように見えて、風情があるので結構すき。
有名どころでいくと、
半紙の上に、かがみ餅。その上にみかん。
あとは干し柿も飾ります。
「年末についたお餅を使ってる」のが田舎!!って感じですよね。
お雑煮って何味なん?

ちなみにお雑煮に、「おさげ」と言って飾りから下げたお餅を入れてくれます。
亡くなった祖母の味を、今は祖父が引き継いでいて
懐かしい味を楽しむのがme家流かな。
関西ですが、京都のような”the白みそ”を使うわけではないんですよね。
でも周りでお雑煮の話をすると各家庭によって違い、関西のここだからこれ!この味!みたいなのも、実はいえなかったり。
それもそのはず、関西に住んでるけど関東で育った!みたいなことも当たり前にありますからね。
我が家は お味は、カツオ出汁と、醤油などを中心に。
とろっとしたおもちを入れて、仕上げは削ったゆずをぱらぱら。
シンプルだけど、やさしくてちょっとあまくて、
ゆずで冬らしさもあるのがすき。
正月本番?!何して過ごす?
話は戻りますが、1月1日は祖父の家に集合し、家族でおせちを食べ、親せき中に挨拶まわりに行き、そして毎年行っている神社やお寺へ初詣に行くのが我が家のお正月。
あんまりゆっくりはせず、バタバタと過ごすのが我が家流。
数日たったら、京都の伏見稲荷大社にも必ず毎年参拝しに行っています!
お山を一周して、「いつものとこ」と呼んでいる「三徳亭」さんで玉子丼を食べます♡
そして、「眼力社」という有名な伏見稲荷大社内の社で、おみくじを引く!

お正月がおわったらすること?!
因みに、この飾り物一式は、新年少したってから行われている「どんどやき」にもっていって焼いてもらっています。
地域によっては、「どんどんやき」と言ったりもするらしい。
「どんどやき」は、一般的に自分が書いた書道の作品や目標を、火の中に入れ、高く舞い上がるほど、目標が叶ったり、書道などが上達するという言い伝えがあります。
小さい頃はよく書いて、持って行って地区の方に焼いてもらうところをドキドキしながら見ていました♪
MORE HAPPY!!!

これが我が家の毎年の過ごし方ですが、
よく考えれば、例えば結婚したりするとまた変わるだろうし、安全で無事なご時世でないと叶わない、当たり前のようで決して当たり前でないしあわせなお正月だと、思うのです。
それに感謝して、
もうすぐ旧正月!
一つの節目ですが、みなさんにとって、
2025年が素晴らしいものとなりますように、
安全で、平和なものでありますように。
そして
みなさんの年末年始の過ごし方、すごく聞いてみたい!!
インスタで待ってます♡