-

12星座全体の運勢
「濃密なエモを嗅ぎとって堪能すればいい」
5月7日は鞍馬寺などでブッダの生涯を祝うウエサク祭が催され、蠍座で満月を迎えます。今回の蠍座の満月は「FULFILLMENT(約束の履行と実現)」がキーワード。これは言い換えれば「変容の成就」ということでもあり、古いパターンからの脱却や離脱、引きこもり期間の後に、人生のユニークでカラフルなビジョンに目覚めることがテーマとなっています。今週はできるだけ現実の豊かな匂いや味を堪能していくことで、心が昂揚する「エモッ!」を研ぎ澄ましていきたいところ。
-

牡羊座
谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』において、日の光が届かない薄暗がりにこそ日本の伝統文化の真髄があり、空間の隅々までこうこうと照らそうとする西洋文明に染まるのではなく、「陰翳」を大事にしていくのでなければならないと主張しました。
そしてこれは何も美術品や伝統芸能の世界に限った話ではなく、日頃の人間関係でも同じことが言えるのではないでしょうか。特にパートナーや家族など、近い関係性であればあるほど、相手のすべてを暴きたてようとするのではなく、薄暗いロウソクの明かりのもとに置くことで、関わりの綾も奥深く魅力的に感じられてくるもの。
「翳」という漢字には、「かざす/おおう」という意味もあるそうですが、人間関係を豊かに味わっていく上でのコツも、そういうところにあるのかも知れません。大切な人と一緒に過ごす時などは、「試しに電燈を消してみることだ」という谷崎のすすめに従ってみるといいでしょう。
出典:谷崎潤一郎『陰翳礼賛』(中公文庫)
-

牡牛座
川端康成の『雪国』の冒頭。汽車の窓から「駅長さん」と呼びかける葉子の声の印象について、作者は主人公の島村の視点から「悲しいほど美しい声」と書き、作中で何度も繰り返してみせました。
「悲しい」は感情であり、「美しい」は感覚的判断ですから、ふつうその二つは論理的には結びつかないのですが、私たちは聴覚でとらえる声のなかに、しばしば相手の輝くような黄色い喜びや青く透きとおった悲哀などの視覚的な「色」を見出し、ある種の共感覚体験をしていくことがあります。
そうした共感覚体験は、一般的に幼い子供の時期ほど経験しやすく、逆に大人になっていくほど経験しにくくなっていくとされていますが、これは心を対象から遠ざけるようになってしまうからではないでしょうか。
逆に言えば、幼児のように自分の方から心を開いて距離を寄せれば、相手の声の微妙な音色まで感じとれるもの。今週は、そんな‟出会いの場所”としての声の彩りに注目してみるといいかも知れません。
出典: 川端康成『雪国』(新潮文庫)
-

双子座
梶井基次郎は飼い猫と遊び戯れるうちに浮かんでくる空想を題材にした随筆『愛撫』の中で、「爪のない猫」について思いを巡らし、それに「空想を失ってしまった詩人」というイメージを重ねてみせました。
おそらく爪を失った猫は、高所から飛び降りることも、爪を研ぐことも、獲物めがけ飛びかかることも不可能となり、やがて絶望して死んでしまうだろう。猫の匕首(あいくち)のように鋭い爪は、「この動物の活力であり、智恵であり、精霊であり、一切である」。
従って猫の猫である所以は、爪の定期的な使用にこそあり、それを危険だからとか、喧嘩するからといった人間の自分勝手な都合で台無しにしてしまえば、詩の書けない詩人同然なのだと。
つまり、自分の中のもっとも危うい部分こそ、その適切な運用次第で最大の武器となりうる。そしてそれは他の誰かの都合を押しつけられて奪われてはならないものなのであり、今週のふたご座もまた、自分を猫に重ねてみたとき爪に該当するものが何なのかということを今一度思い浮かべてみるといいでしょう。
出典:梶井基次郎『愛撫』(ちくま日本文学028)
-

蟹座
「レモン(Lemon)」と言えば、多くの人にとって米津玄師の楽曲を思い浮かべるかも知れませんが、喚起するイメージの鮮烈さという点では今でもやはり梶井基次郎の書いた『檸檬』に勝るものはないでしょう。
「一体私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰った紡錘形の格好も。」
そう思って買った檸檬を、作者は何度も鼻に持ってきては「鼻を撲(う)つ」という言葉をきれぎれに思い浮かべます。それから、たどり着いた丸善で棚から引き出した重たい画集を何冊も積み上げた上に載せた檸檬を、「ガチャガチャした色の諧調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた」と描写するのです。
しかもその後、自分を「丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な悪漢」に重ね、大爆発したら面白いなどと妄想する始末。これほど救い難いエモイストは滅多にいませんが、今週のかに座であれば、それくらい過激な遊びの方が心地いいはず。
出典:梶井基次郎『檸檬』(ちくま日本文学028)
-

獅子座
三浦哲郎は『愛しい女』の中で、「実にかすかだが」と前置きした上で、「躰(からだ)のどこか薄暗いところに淀んでいた古い血でも波立ち騒ぐような、ざわめきが聞こえた」と書きましたが、それを読んだ時、そうか自分の身の内に流れている血も海潮と繋がっていて、月夜の晩に気持ちが疼いたり昂揚したりするのもそのためか、と思ったものでした。
あらゆる辛酸を取りこんだ母なる海の水の「味」は、地球の生み出すありとあらゆる味覚の原点が凝縮されたものであり、そうした海のなごりは生き物が海から上陸した後も血液を介して自分自身の中に生きている。
「血潮」ということばには、そんな遠い先祖の古い記憶が刻み込まれているのかも知れません。
今週のしし座もそんなふうに自分の背景にある系譜やルーツ、その根源に浸っていく中で、からだの奥底から力強い感覚がみなぎってくるのを感じていくことができるでしょう。
出典:三浦哲郎『愛しい女』(新潮文庫)
-

乙女座
蛙は一般的には「ケロケロ」や「ゲロゲロ」と鳴くことになっていますが、長塚節の『土』には「きろきろきろきろと風船玉を擦り合わせるような蛙の声」とありますし、林芙美子は『浮雲』で食用蛙の声を「ぼろんぼろん」のイメージで聴き取り、「雨滴(あまだれ)のように何時までも二人の耳についていた」と書いたり、他の箇所では「太棹(ふとざお)の三味線でも聴いているように」と三味線の音色にも喩えており、他にも書き手によって様々なヴァリエーションが存在します。
このように蛙は短歌や文芸作品のモチーフとして特にその鳴き声が愛でられてきたのですが(10世紀の古今和歌集にも「水に住む蛙も、生きとし生けるものはすべて歌を歌わない物はない」との記述あり)、17世紀の松尾芭蕉は「古池や蛙飛び込む水の音」という句を詠むことで、伝統に反した新たな詩情を蛙のなかに発見し、他とは一線を画した訳です。
今週のおとめ座もある意味でそんな芭蕉のように、何気ない日常に潜んだ身近なモチーフを通して新しい美を見出していくことがテーマとなっていきそうです。
出典:
長塚節『土』(新潮文庫)
林芙美子『浮雲』(新潮文庫)
『古今和歌集』 (角川ソフィア文庫)
松尾芭蕉『おくのほそ道』(講談社学術文庫)
-
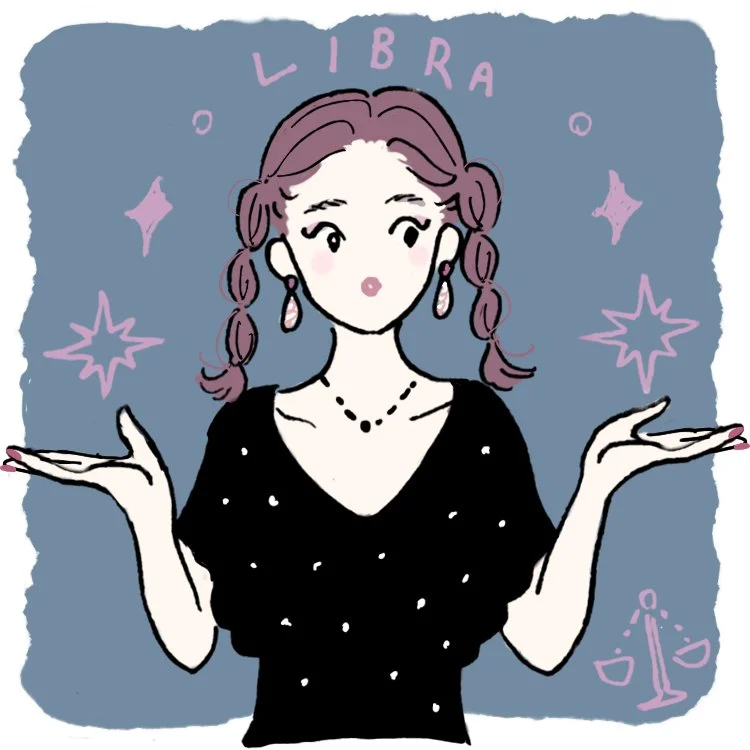
天秤座
大正時代に永井荷風が日本の花街で繰り広げられた新旧の芸妓たちによるライバルや客との恋の勝負を描いた『腕くらべ』には、「その肌の滑らかさいくら抱き〆めて見ても抱き〆めるそばからすぐ滑り抜けて行きそうな心持」といった、いささか古めかしくはありますが、現代人が読んでも思わずうっとりしてしまうような描写がこれでもかと登場します。
そこには現代人もよく使う「すべすべ」とか「するり」といった擬態語(オノマトペ)などが既に使われていて驚くのですが、一風変わった表現としては「菊千代の肌身はとろとろと飴のように男の下腹から股の間に溶け入って腰から背の方まで流れかかる心持」というものがあります。ここでも「飴(あめ)」という比喩イメージに、「とろとろ」という擬態語を添え、「(下腹から背の方まで)流れかかる」という感覚に訴えかけていくことで魔術的な相乗効果が生まれていくのが感じられるかと思います。
もちろん、これは一種の誇張表現ではあるのですが、今週のてんびん座もまたいかに自身の感覚体験を既存の狭い枠の外へとどれだけ拡張していけるかが問われていくでしょう。
出典:永井荷風『腕くらべ』(岩波文庫)
-

蠍座
自身の元に送られてきた19歳の女性ファンの日記を元に書かれた太宰治の『女生徒』には、「五月のキュウリの青味には、胸がカラッポになるような、うずくような、くすぐったいような悲しさが在る」という文章が出てきますが、悲しみという心情には、思いがけない感覚との結びつきが無数に隠れているように思います。
谷崎潤一郎の大作『細雪』にも、「それは悲しみには違いなかったが、一つの美しいものが地上から去って行くのを惜しむような、いわば個人的関係を離れた、一方に音楽的な快さを伴なう悲しみ」があった一節があり、こちらもこんな悲しみの感じ方があったのかと思わずにはいられません。
ただ、「悲しい」という情動が感覚との新たな回路を形成していく時というのは、いずれにせよ存在の核の部分が揺れ動いた時であり、満月が起きていく今週のさそり座もまた、まさにそうしたタイミングに入っているのだと言えます。
これはという新鮮な材料を見かけたら、積極的に触れて新たなエモを発掘していきたいところ。
出典:
太宰治『女生徒』(角川文庫)
谷崎潤一郎『細雪』(中公文庫)
-

射手座
太宰治の次女でもある津島佑子の連作短編のうちの一作である『鳥の夢』には、「恐怖がそのまま輝くような喜びを味わっていた」という表現が出てきます。
「喜び」とはふつう対極的な位置にある「恐怖」という感情が、恐怖であるままに喜びを味わっているという矛盾をはらんだ比喩表現ですが、おそらくそれは身震いさえ伴なうような、ゾクゾクする感覚のことであり、現代人が文明の灯りのもとで置き去りにしてきたプリミティブな本能に直結したものなのではないでしょうか。
よく人間が恐怖を感じた際の身体反応として、「全身の毛が逆立つ」とか、「血の逆流するような恐怖」などとも言いますが、生きようという本能が総動員される時というのは、ある種の強い矛盾や、逆行現象がそこに立ち現れるのかも知れません。
つまり、矛盾はエモいんです。もちろん、それは感覚の狂いでもありますから、素直で分かりやすいエモではありませんが、今週のいて座に関しては、そうした普段なら目を向けないような領域にもついつい手を伸ばしていってしまうはず。
出典:津島佑子『光の領分』(講談社文芸文庫)
-

山羊座
岸田将幸の『<孤絶-角>』には、「詩を書く人同士は怖しく離れている/ここで書いている人は互いに励まし合わなければならない/詩は慈悲深い絶望だ/極限の人間関係だ/人世に不足するのは何度でも愛され直される場所だ」という文章が出てきますが、ここで効いてくるのが詩集のタイトルにも入っている「角」でしょう。
「角」という漢字は「つの」とも「かく」とも読みますが、いずれにせよ鋭く痛覚を刺激される表現となっており、まるでそれを通じてこれまで無感覚だった神経に電気が通って、痛いほど鋭敏になる詩人の感性を象徴しているかのようです。
こうしたピリっと刺激される皮膚感覚というのは、第六感と同様、精神をある種の興奮状態に持っていくためのスイッチとなりますし、それは後戻りできない変容のプロセスの最中にある今のやぎ座の人たちにとって、まさにおあつらえ向きな‟エモ”なのではないでしょうか。
出典:岸田将幸『岸田将幸詩集』(現代詩文庫)
-

水瓶座
岡本太郎の母親で小説家であり歌人、また宗教者でもあった岡本かの子は『母子抒情』に、「初夏の晴れた空に夢のしたたりのように、あちこちに咲きほとばしるマロニエの花」と書いてみせました。
赤みがかった大ぶりの花をつけるマロニエを、湿り気たっぷりの五月の空に添えるのに、「夢のしたたり」という現実との境界線を溶かしてしまうようなモチーフを持ち出し、さらにやはり液体を連想させる「ほとばしる」という動詞を駆使して、華やかに彩っていますが、このマロニエの花はどこか奔放に生きた作者自身が重ねられているようにも感じられます。
蕾が開いて花が開くことを「咲く」と言いますが、これもどこか赤い唇を開いて「笑う」作者のイメージとやはり通い合っていく。こちらの精神が勝手に感応しているだけなのか、それともマロニエの花の精がそうさせるのか。
かつて歌人の塚本邦雄は「花は歌人を象徴する」と述べましたが、今週のみずがめ座もまた、そうした自分自身を重ねられるような花を並木道や道路脇の原っぱなどに見出してみるといいでしょう。
出典:
岡本かの子 『母子叙情 』(昭和文学全集第5巻)
塚本邦雄『百花游歴』(文藝春秋)
-
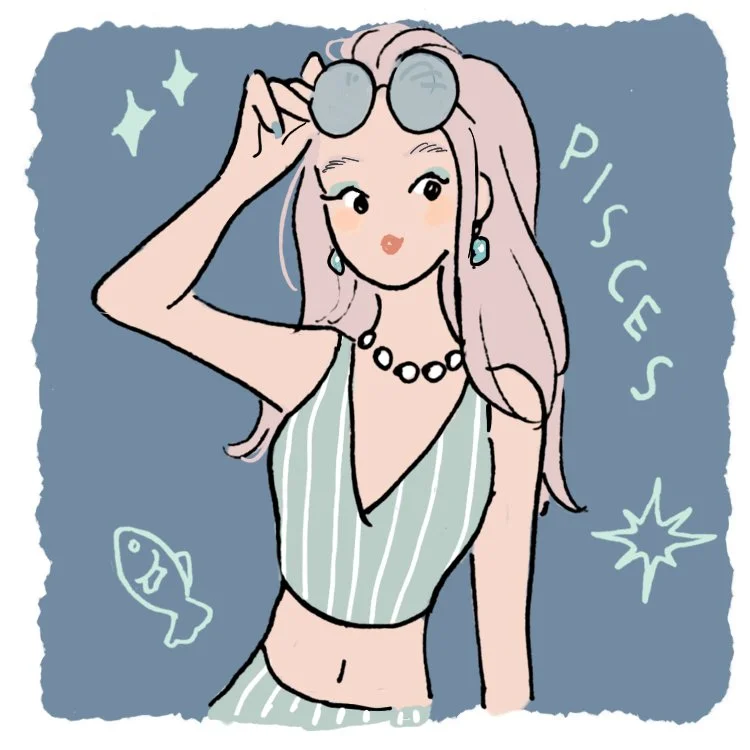
魚座
芥川龍之介の『蜘蛛の糸』で、「ひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると自分の上へ垂れて参るではございませんか」と書きましたが、ここでは心の中にあるかなきかの希望がもたらされる様子を「銀色の糸」という視覚表現に託して表されているのが分かります。
この地獄の底の犍陀多(かんだた)を地上の私たちに置き換えてみた時、おそらく「銀色の糸」と同じ効果をもたらしてくれるのが光に照らされた雨なのではないでしょうか。
石坂洋次郎の『山のかなたに』には「太い針金のように光る雨の線」という言い方が登場しますし、林芙美子は『うず潮』に「白い葱(ねぎ)をちぎって放るような雨」とも書いていますが、線状に落ちてくる雨から「糸」のようなものを連想する例は文学作品に限っても、とても多いように思います。
そうした絹糸のごとき光る雨はどこか神託のようでもあり、今週は数ある雨筋の中から、自分にとって特別光り輝いて見える「雨の線」を見つけてみるといいかも知れません。
出典:
芥川龍之介『蜘蛛の糸』(ちくま日本文学002)
石坂洋次郎『山のかなたに』(新潮文庫)
林芙美子『うず潮』(新潮文庫)
 12星座全体の運勢 「濃密なエモを嗅ぎとって堪能すればいい」 5月7日は鞍馬寺などでブッダの生涯を祝うウエサク祭が催され、蠍座で満月を迎えます。今回の蠍座の満月は「FULFILLMENT(約束の履行と実現)」がキーワード。これは言い換えれば「変容の成就」ということでもあり、古いパターンからの脱却や離脱、引きこもり期間の後に、人生のユニークでカラフルなビジョンに目覚めることがテーマとなっています。今週はできるだけ現実の豊かな匂いや味を堪能していくことで、心が昂揚する「エモッ!」を研ぎ澄ましていきたいところ。
12星座全体の運勢 「濃密なエモを嗅ぎとって堪能すればいい」 5月7日は鞍馬寺などでブッダの生涯を祝うウエサク祭が催され、蠍座で満月を迎えます。今回の蠍座の満月は「FULFILLMENT(約束の履行と実現)」がキーワード。これは言い換えれば「変容の成就」ということでもあり、古いパターンからの脱却や離脱、引きこもり期間の後に、人生のユニークでカラフルなビジョンに目覚めることがテーマとなっています。今週はできるだけ現実の豊かな匂いや味を堪能していくことで、心が昂揚する「エモッ!」を研ぎ澄ましていきたいところ。 牡羊座 谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』において、日の光が届かない薄暗がりにこそ日本の伝統文化の真髄があり、空間の隅々までこうこうと照らそうとする西洋文明に染まるのではなく、「陰翳」を大事にしていくのでなければならないと主張しました。
牡羊座 谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』において、日の光が届かない薄暗がりにこそ日本の伝統文化の真髄があり、空間の隅々までこうこうと照らそうとする西洋文明に染まるのではなく、「陰翳」を大事にしていくのでなければならないと主張しました。 牡牛座 川端康成の『雪国』の冒頭。汽車の窓から「駅長さん」と呼びかける葉子の声の印象について、作者は主人公の島村の視点から「悲しいほど美しい声」と書き、作中で何度も繰り返してみせました。
牡牛座 川端康成の『雪国』の冒頭。汽車の窓から「駅長さん」と呼びかける葉子の声の印象について、作者は主人公の島村の視点から「悲しいほど美しい声」と書き、作中で何度も繰り返してみせました。 双子座 梶井基次郎は飼い猫と遊び戯れるうちに浮かんでくる空想を題材にした随筆『愛撫』の中で、「爪のない猫」について思いを巡らし、それに「空想を失ってしまった詩人」というイメージを重ねてみせました。
双子座 梶井基次郎は飼い猫と遊び戯れるうちに浮かんでくる空想を題材にした随筆『愛撫』の中で、「爪のない猫」について思いを巡らし、それに「空想を失ってしまった詩人」というイメージを重ねてみせました。 蟹座 「レモン(Lemon)」と言えば、多くの人にとって米津玄師の楽曲を思い浮かべるかも知れませんが、喚起するイメージの鮮烈さという点では今でもやはり梶井基次郎の書いた『檸檬』に勝るものはないでしょう。
蟹座 「レモン(Lemon)」と言えば、多くの人にとって米津玄師の楽曲を思い浮かべるかも知れませんが、喚起するイメージの鮮烈さという点では今でもやはり梶井基次郎の書いた『檸檬』に勝るものはないでしょう。 獅子座 三浦哲郎は『愛しい女』の中で、「実にかすかだが」と前置きした上で、「躰(からだ)のどこか薄暗いところに淀んでいた古い血でも波立ち騒ぐような、ざわめきが聞こえた」と書きましたが、それを読んだ時、そうか自分の身の内に流れている血も海潮と繋がっていて、月夜の晩に気持ちが疼いたり昂揚したりするのもそのためか、と思ったものでした。
獅子座 三浦哲郎は『愛しい女』の中で、「実にかすかだが」と前置きした上で、「躰(からだ)のどこか薄暗いところに淀んでいた古い血でも波立ち騒ぐような、ざわめきが聞こえた」と書きましたが、それを読んだ時、そうか自分の身の内に流れている血も海潮と繋がっていて、月夜の晩に気持ちが疼いたり昂揚したりするのもそのためか、と思ったものでした。 乙女座 蛙は一般的には「ケロケロ」や「ゲロゲロ」と鳴くことになっていますが、長塚節の『土』には「きろきろきろきろと風船玉を擦り合わせるような蛙の声」とありますし、林芙美子は『浮雲』で食用蛙の声を「ぼろんぼろん」のイメージで聴き取り、「雨滴(あまだれ)のように何時までも二人の耳についていた」と書いたり、他の箇所では「太棹(ふとざお)の三味線でも聴いているように」と三味線の音色にも喩えており、他にも書き手によって様々なヴァリエーションが存在します。
乙女座 蛙は一般的には「ケロケロ」や「ゲロゲロ」と鳴くことになっていますが、長塚節の『土』には「きろきろきろきろと風船玉を擦り合わせるような蛙の声」とありますし、林芙美子は『浮雲』で食用蛙の声を「ぼろんぼろん」のイメージで聴き取り、「雨滴(あまだれ)のように何時までも二人の耳についていた」と書いたり、他の箇所では「太棹(ふとざお)の三味線でも聴いているように」と三味線の音色にも喩えており、他にも書き手によって様々なヴァリエーションが存在します。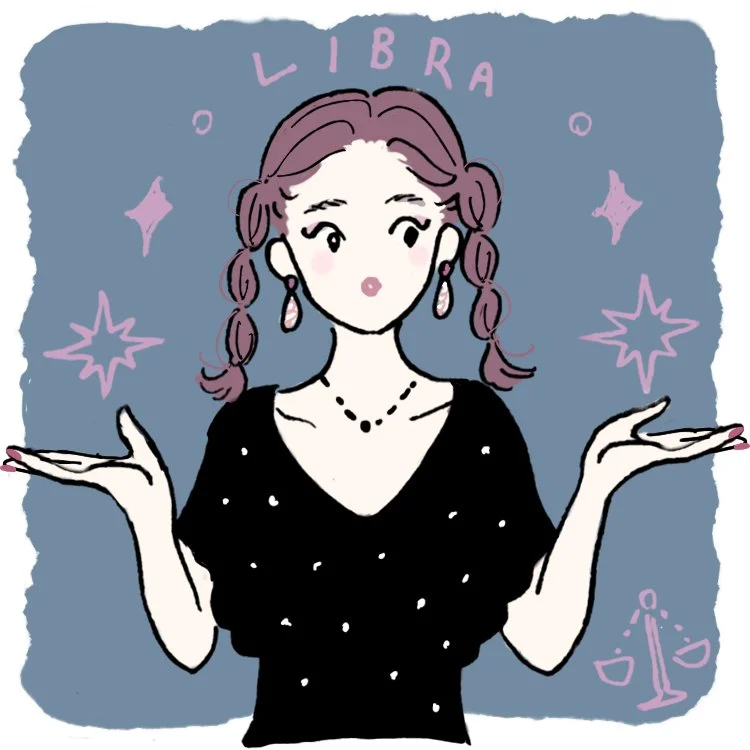 天秤座 大正時代に永井荷風が日本の花街で繰り広げられた新旧の芸妓たちによるライバルや客との恋の勝負を描いた『腕くらべ』には、「その肌の滑らかさいくら抱き〆めて見ても抱き〆めるそばからすぐ滑り抜けて行きそうな心持」といった、いささか古めかしくはありますが、現代人が読んでも思わずうっとりしてしまうような描写がこれでもかと登場します。
天秤座 大正時代に永井荷風が日本の花街で繰り広げられた新旧の芸妓たちによるライバルや客との恋の勝負を描いた『腕くらべ』には、「その肌の滑らかさいくら抱き〆めて見ても抱き〆めるそばからすぐ滑り抜けて行きそうな心持」といった、いささか古めかしくはありますが、現代人が読んでも思わずうっとりしてしまうような描写がこれでもかと登場します。 蠍座 自身の元に送られてきた19歳の女性ファンの日記を元に書かれた太宰治の『女生徒』には、「五月のキュウリの青味には、胸がカラッポになるような、うずくような、くすぐったいような悲しさが在る」という文章が出てきますが、悲しみという心情には、思いがけない感覚との結びつきが無数に隠れているように思います。
蠍座 自身の元に送られてきた19歳の女性ファンの日記を元に書かれた太宰治の『女生徒』には、「五月のキュウリの青味には、胸がカラッポになるような、うずくような、くすぐったいような悲しさが在る」という文章が出てきますが、悲しみという心情には、思いがけない感覚との結びつきが無数に隠れているように思います。 射手座 太宰治の次女でもある津島佑子の連作短編のうちの一作である『鳥の夢』には、「恐怖がそのまま輝くような喜びを味わっていた」という表現が出てきます。
射手座 太宰治の次女でもある津島佑子の連作短編のうちの一作である『鳥の夢』には、「恐怖がそのまま輝くような喜びを味わっていた」という表現が出てきます。 山羊座 岸田将幸の『<孤絶-角>』には、「詩を書く人同士は怖しく離れている/ここで書いている人は互いに励まし合わなければならない/詩は慈悲深い絶望だ/極限の人間関係だ/人世に不足するのは何度でも愛され直される場所だ」という文章が出てきますが、ここで効いてくるのが詩集のタイトルにも入っている「角」でしょう。
山羊座 岸田将幸の『<孤絶-角>』には、「詩を書く人同士は怖しく離れている/ここで書いている人は互いに励まし合わなければならない/詩は慈悲深い絶望だ/極限の人間関係だ/人世に不足するのは何度でも愛され直される場所だ」という文章が出てきますが、ここで効いてくるのが詩集のタイトルにも入っている「角」でしょう。 水瓶座 岡本太郎の母親で小説家であり歌人、また宗教者でもあった岡本かの子は『母子抒情』に、「初夏の晴れた空に夢のしたたりのように、あちこちに咲きほとばしるマロニエの花」と書いてみせました。
水瓶座 岡本太郎の母親で小説家であり歌人、また宗教者でもあった岡本かの子は『母子抒情』に、「初夏の晴れた空に夢のしたたりのように、あちこちに咲きほとばしるマロニエの花」と書いてみせました。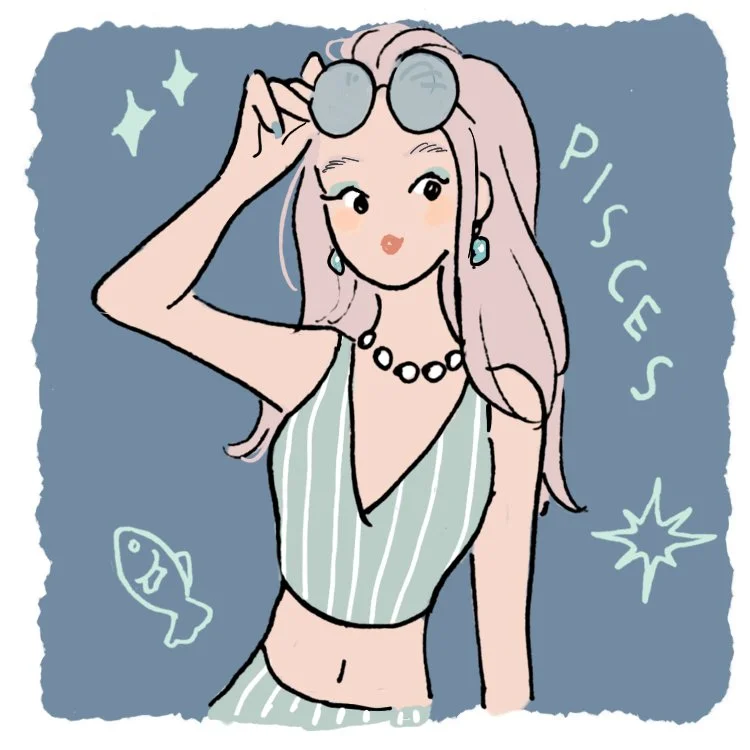 魚座 芥川龍之介の『蜘蛛の糸』で、「ひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると自分の上へ垂れて参るではございませんか」と書きましたが、ここでは心の中にあるかなきかの希望がもたらされる様子を「銀色の糸」という視覚表現に託して表されているのが分かります。
魚座 芥川龍之介の『蜘蛛の糸』で、「ひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると自分の上へ垂れて参るではございませんか」と書きましたが、ここでは心の中にあるかなきかの希望がもたらされる様子を「銀色の糸」という視覚表現に託して表されているのが分かります。












































































