-

【SUGARさんの12星座占い】<6/14~6/27>の12星座全体の運勢は?
「大きな物語に取り込まれていく」
6月21日の夏至の日の夕方16~18時にかけて、蟹座1度で部分日食(新月)が起こり、晴れていれば日本全国で欠けていく太陽が観測できます。これは日食と新月、そして一年のうち最も日が長くなる夏至が重なる特別なタイミングであり、時代の移り変わりの上でもひとつの節目となっていきそうです。そのキーワードは、「大きな物語」。これは例えば「むかしむかし、あるところに……」といった語りで始まる昔話のように、歴史ないし共同体のもつ空間的・時間的射程の中に自らを位置づけ直していくことで、個人として好き勝手に振る舞う自由を失う代わりに、手で触れられる夢のような生々しい物語の中へと取りこまれていく。今季はそんな"クラい”感覚の極致をぜひ味わっていきたいところです。
-

今週のてんびん座のキーワードは、「運命の子」。
この世に生きるものは誰であれ、自身の母親の子であると同時に"時代の子”でもありますが、その誕生の瞬間が一体いつだったのか、またいつになるのかは誰にも分かりません。
もちろん、偶然というものが存在しないとすれば話は違ってきます。例えば、サルマン・ラシュディ著の『真夜中の子供たち』という小説の主人公であり語り手でもあるサリーム・シナイは、インドがイギリスから独立を勝ち取りパキスタンと別の国家として分離独立した日の午前0時ちょうどに生まれました。
書き手によって、彼はまさに生まれた瞬間に時代の子、そして国家の子となり、彼の前半生は若い国家インドそのものの歩みと軌を一にしていった訳です。そのことについて、サリーム本人は次のように語っています。
「何しろもの静かに合掌する時計のオカルト的な力によって、私は不思議にも手錠でつながれ、私の運命は祖国の運命にしっかりと結びつけられてしまったのだ。」
ところで、この小説は書き手であるラシュディの自伝的な要素の多い作品ですが、ラシュディ自身は主人公シナイのような他人の思考を受信することができるテレパシー能力は持っておらず、代わりに想像力を駆使してこの物語を作品として書き上げていきました。
その意味で、シナイは被造物であると同時に、ラシュディの協力者ないし伴走者として、彼の人生に力を貸していった、言わばラシュディにとって"運命の子”なのだと言えます。
文章であれ写真であれ料理であれ、自分が創り出したものによって逆に形づくられ、何かに寄与したことによってその何かの一部となる。こうしたことは、今季のてんびん座においても無視できないテーマとなっていくでしょう。
自分を時代や共同体、他の誰かにとっての"運命の子”にしていくべきか、またそのためにはどんな選択をして、何を背負い、何を捨てていかねばならないのか。
今回の日食に際しては、ちょうど小説内のシナイのように、半生を振り返りながらそんなことについてゆっくり考えてみるといいかも知れません。
出典:サルマン・ラシュディ『真夜中の子供たち(上)』(岩波文庫)
-

今週のさそり座のキーワードは、「恋の夢」。
明恵(みょうえ)という華厳宗中興の祖でもある中世の僧のことは、今日では彼ほど几帳面に夢を記録した人が他にいないことで知られていますが、そもそも彼は一生不犯(一生を通して異性と交わらないこと)を貫いたとされるほど、とても信仰心の篤い人で、実際にその夢の多くも仏に関するものでした。
ただし、実際の夢の内容を見ていくと、これがなかなかに生々しいものが多いのです。例えば、彼が若い頃に見た夢には次のようなものがありました。
「同十一月六日の夜、夢に見た。(中略)建物の中に威厳ある美女がいた。衣服などはすばらしかった。しかし、世俗的な欲望の姿ではなかった。私はこの貴女と一緒にいたが、無情にもこの貴女を捨てた。この女は私に親しんで、離れたがらなかった。私は彼女を捨てて去った。まったく、世俗的な欲望の姿ではなかった。」
気持ちが惹かれていた女性を無理にでも捨てたという短い内容の中に、「世俗的な欲望の姿ではなかった」という言い訳がましい言葉が二度も登場しており、彼はその夢解きすなわち夢占いをして、「女は毘盧遮那仏(仏)なり」と結論し、夜中に起き出して道場で座禅を組んだそうです。
明恵にとって仏を愛する心は、世間の男女の愛を超えたものでありながら、どこまでも性的なものでもあり、彼が仏に近付く手立てとしたのは世俗的な欲望を使って世俗を超えようという非常に強烈なものでした。
こうした狂気すれすれまで何かを恋焦がれる力強さというは、現代社会ではもはや許容されなくなりましたが、精神的高揚や憧れの対象を改めてどこかに見出していかんとしている今季のさそり座にとっては、彼の垣間見せてくれた圧倒的な情熱は一つの指針となってくれるはずです。
出典:奥田勲・平野多恵・前川健一/編『夢記』(勉誠出版)
-

今週のいて座のキーワードは、「生む」。
歴史を振り返ると、6世紀に日本へ渡ってきた仏教は、日本土着の神を取り込んだだけではなく生や性を根本のところにおいて否定し、そこからの超越を説いてきたし、その影響は今でもじつに根深いものがあるのではないでしょうか。
では、8世紀のはじめ頃に書かれた日本最古の歴史書である『古事記』には、生と性の起源はどのように描かれていたのか、改めてひも解いてみると、次のようにあります。
「そこで、イザナキノミコトが言われるには、「私の身体には出来上がって、余分なところが一箇所ある。だから、この我が身体の余ったところを、あなたの身体の足らないところに刺し塞いで、国土を生み出そうと思う。生むことはどうだろうか」と仰ると、イザナミノミコトは、「それはよいことだ」とお答えになった」
これは今日の感覚から見ても、とても大らかな宣言ないし公的発言であり、性の合一をもって物のかたちが完成するという信仰がそこにあっただけではなく、古代人が性を隠蔽したりしなかったということがわかるのではないかと思います。
ザナギ・イザナミによる生命の誕生に向けての問答は、まさに仏教とは異なるベクトルをもった生や性への「肯定の論理」を指し示すものでしたが、これはまさに自分に足りないものを誰かの力を借りることで補い、シナジーを生み出していこうとしている今期のいて座は大切にしていきたい原動力と言えるでしょう。
参考:中村啓信/訳注『新版 古事記 現代語訳付き』(角川ソフィア文庫)
-

今週のやぎ座のキーワードは、「縁の不思議」。
粘菌類の研究で知られる自然科学者にして、民俗学の著作を無数に持ち、柳田國男から「日本人の可能性の極限」と称された南方熊楠(みなかたくまぐす)は、生涯にわたり在野の人であり、何より独学の人でしたが、彼には自分の思想上の問題を全力で遠慮なく投げかけ合える相手が一人だけいました。
それが熊楠が27歳の時にロンドンで出会った真言僧の土宜法龍(ときほうりゅう)であり、彼は明治期における最も開明的な仏教学者にして、後に高野山管長も務めた大人物でした。
彼らは科学と宗教という立場や分野の違いも超え(ついでに歳も土宜が13歳年上)、じつに死が二人を分つまでの30年間にわたって膨大な量の書簡を定期的に送り合い、そのどれもが大論文のごとき長さと密度であったそうで、その様子について、熊楠はのちにこう書いています。
「小生は件の土岐師への状を認むる(したたむる)ためには、一状に昼夜兼ねて眠りを省き二週間もかかりしことあり。何を書いたか今は覚えねど、これがために自分の学問、灼然と上達しおり候」
熊楠は人智を超えた不思議や縁の論理についてこそ、いま学問をやる人は研究せねばならないとも手紙に書いていましたが、純粋な意味でのパートナーシップや何かに自分を全力でぶつけていくことがテーマとなっている今季のやぎ座にとって、彼らの姿を追うことは何よりの励みになるのではないでしょうか。
参考:中沢新一/編『南方マンダラ』(河出文庫)
-

今週のみずがめ座のキーワードは、「誠の道」。
日本近世においていち早く近代的な考え方を先取りし、それまで神聖視されてきた儒教や仏教の典籍の聖性を剥奪していった人物に、大阪の町人階級が生んだ天才・富永仲基(とみながちゅうき)がいます。
富永は、思想はすべて時代と地域の課題に応じて形成されたものであり、前の人の説に何か新しいものを付け加えたり、それを批判することで、後の人の説が形成されていくという「加上説(かじょうせつ)」を適用し、インドと中国と日本の文化を徹底的に相対化し、比較観察していきました。
著書『翁の文』では、「仏(ぶつ)は天竺の道、儒は漢(から)の道、国ことなれば、日本の道にあらず。神(しん)は日本の道なれども、時ことなれば、今の世の道にあらず」として、どの教えも彼が生きた18世紀当時の日本には適合しないとし、従うとすれば「誠の道」だろうと述べました。
これは上記の中では儒教の実践道徳に近いですが、親あるものには親に仕え、君あるものは君に仕えるという、「あたりまえをつとめ」ることの内に道を見出していたようです。
天賦の学才に恵まれた富永が、あらゆる思想を徹底的に相対化しつくした末にたどり着いたのが、日常生活の具体性であったというのは、現代人の目から見ても非常に新鮮に映るのではないでしょうか。
自分なりの働き方や美学ないしスタイルと呼ぶべきものを見直し、また改めて確立していこうとしている今季のみずがめ座にとっては、尚更のこと興味深いはずです。
参考:永田紀久・有坂隆道/校注『日本思想体系 富永仲基・山片蟠桃』(岩波書店)
-
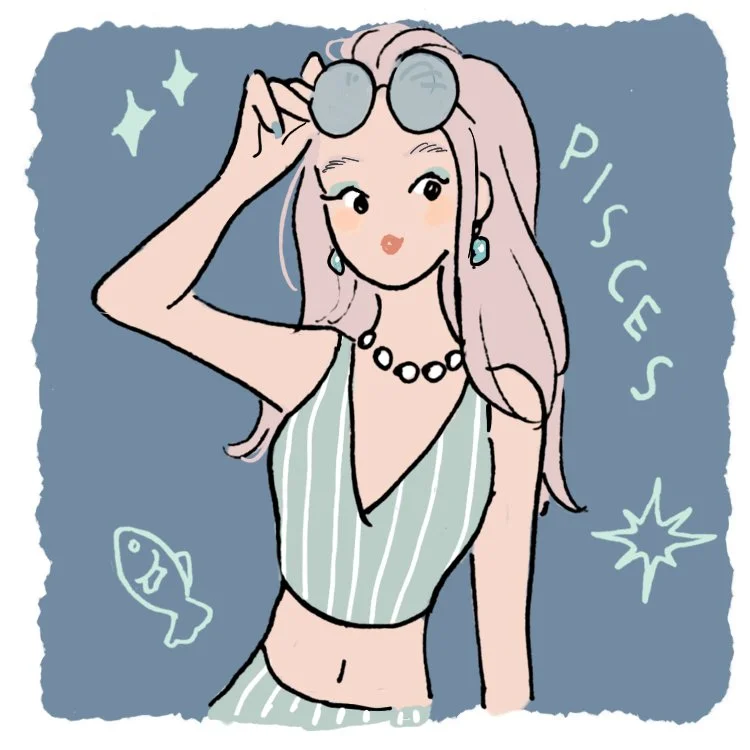
今週のうお座のキーワードは、「三密」。
今回のコロナ禍ですっかり「密」という言葉が禁忌の対象とされつつも、いかに私たちの日常生活や心身の健康というものが「密」に依存していたかも浮き彫りになったのではないでしょうか。
ただ、密と言えばわが国では古くから密教において用いられてきた言葉で、人間の理解を超えている行為のことを言い、身に印を結び、口に真言を唱え、意(こころ)に本尊を念ずることで、仏のはたらきに一致させていくことを「三密」と言いました。
中でも、顕教に対する密教の優位を説いた空海は、初期の頃の著作である『弁顕密二教論』において、次のように述べています。
「仏の本来のあり方や、その境地をみずから享受するあり方においては、みずからの真理を味わい楽しむために、自らの眷属(分身やお伴)とともに、それぞれの身体・言葉・心の三つの秘密の境地をお説きになる。」
顕教が誰にでも目に見え理解できる世界のみを扱うのに対し、密教では目に見えないものたちが躍動している不可思議な世界に足を踏み入れていきます。
そこでは、近代人のようにただ自然や物事を客観視するのではなく、天地の中ではたらき、また跳梁跋扈している神仏や精霊、悪霊や死者たちの世界にみずから参与していくべきとされており、そのための「三密」だった訳です。
もっと深く、もっと得体の知れない領域へ。趣味であれ仕事であれ、そんな風に自身のコミットを本格化させていくことがテーマとなっていく今季のうお座にとって、あたかも浅瀬の海とはまったく違う魅力と怖さを湛える深海へと誘っていくような空海の歩みは、まさに先導者のそれにふさわしいと言えるでしょう。
参考:加藤精一/訳『空海「弁顕密二教論」ビギナーズ日本の思想』(角川ソフィア文庫)
 【SUGARさんの12星座占い】<6/14~6/27>の12星座全体の運勢は? 「大きな物語に取り込まれていく」 6月21日の夏至の日の夕方16~18時にかけて、蟹座1度で部分日食(新月)が起こり、晴れていれば日本全国で欠けていく太陽が観測できます。これは日食と新月、そして一年のうち最も日が長くなる夏至が重なる特別なタイミングであり、時代の移り変わりの上でもひとつの節目となっていきそうです。そのキーワードは、「大きな物語」。これは例えば「むかしむかし、あるところに……」といった語りで始まる昔話のように、歴史ないし共同体のもつ空間的・時間的射程の中に自らを位置づけ直していくことで、個人として好き勝手に振る舞う自由を失う代わりに、手で触れられる夢のような生々しい物語の中へと取りこまれていく。今季はそんな"クラい”感覚の極致をぜひ味わっていきたいところです。
【SUGARさんの12星座占い】<6/14~6/27>の12星座全体の運勢は? 「大きな物語に取り込まれていく」 6月21日の夏至の日の夕方16~18時にかけて、蟹座1度で部分日食(新月)が起こり、晴れていれば日本全国で欠けていく太陽が観測できます。これは日食と新月、そして一年のうち最も日が長くなる夏至が重なる特別なタイミングであり、時代の移り変わりの上でもひとつの節目となっていきそうです。そのキーワードは、「大きな物語」。これは例えば「むかしむかし、あるところに……」といった語りで始まる昔話のように、歴史ないし共同体のもつ空間的・時間的射程の中に自らを位置づけ直していくことで、個人として好き勝手に振る舞う自由を失う代わりに、手で触れられる夢のような生々しい物語の中へと取りこまれていく。今季はそんな"クラい”感覚の極致をぜひ味わっていきたいところです。 今週のてんびん座のキーワードは、「運命の子」。 この世に生きるものは誰であれ、自身の母親の子であると同時に"時代の子”でもありますが、その誕生の瞬間が一体いつだったのか、またいつになるのかは誰にも分かりません。
今週のてんびん座のキーワードは、「運命の子」。 この世に生きるものは誰であれ、自身の母親の子であると同時に"時代の子”でもありますが、その誕生の瞬間が一体いつだったのか、またいつになるのかは誰にも分かりません。 今週のさそり座のキーワードは、「恋の夢」。 明恵(みょうえ)という華厳宗中興の祖でもある中世の僧のことは、今日では彼ほど几帳面に夢を記録した人が他にいないことで知られていますが、そもそも彼は一生不犯(一生を通して異性と交わらないこと)を貫いたとされるほど、とても信仰心の篤い人で、実際にその夢の多くも仏に関するものでした。
今週のさそり座のキーワードは、「恋の夢」。 明恵(みょうえ)という華厳宗中興の祖でもある中世の僧のことは、今日では彼ほど几帳面に夢を記録した人が他にいないことで知られていますが、そもそも彼は一生不犯(一生を通して異性と交わらないこと)を貫いたとされるほど、とても信仰心の篤い人で、実際にその夢の多くも仏に関するものでした。 今週のいて座のキーワードは、「生む」。 歴史を振り返ると、6世紀に日本へ渡ってきた仏教は、日本土着の神を取り込んだだけではなく生や性を根本のところにおいて否定し、そこからの超越を説いてきたし、その影響は今でもじつに根深いものがあるのではないでしょうか。
今週のいて座のキーワードは、「生む」。 歴史を振り返ると、6世紀に日本へ渡ってきた仏教は、日本土着の神を取り込んだだけではなく生や性を根本のところにおいて否定し、そこからの超越を説いてきたし、その影響は今でもじつに根深いものがあるのではないでしょうか。 今週のやぎ座のキーワードは、「縁の不思議」。 粘菌類の研究で知られる自然科学者にして、民俗学の著作を無数に持ち、柳田國男から「日本人の可能性の極限」と称された南方熊楠(みなかたくまぐす)は、生涯にわたり在野の人であり、何より独学の人でしたが、彼には自分の思想上の問題を全力で遠慮なく投げかけ合える相手が一人だけいました。
今週のやぎ座のキーワードは、「縁の不思議」。 粘菌類の研究で知られる自然科学者にして、民俗学の著作を無数に持ち、柳田國男から「日本人の可能性の極限」と称された南方熊楠(みなかたくまぐす)は、生涯にわたり在野の人であり、何より独学の人でしたが、彼には自分の思想上の問題を全力で遠慮なく投げかけ合える相手が一人だけいました。 今週のみずがめ座のキーワードは、「誠の道」。 日本近世においていち早く近代的な考え方を先取りし、それまで神聖視されてきた儒教や仏教の典籍の聖性を剥奪していった人物に、大阪の町人階級が生んだ天才・富永仲基(とみながちゅうき)がいます。
今週のみずがめ座のキーワードは、「誠の道」。 日本近世においていち早く近代的な考え方を先取りし、それまで神聖視されてきた儒教や仏教の典籍の聖性を剥奪していった人物に、大阪の町人階級が生んだ天才・富永仲基(とみながちゅうき)がいます。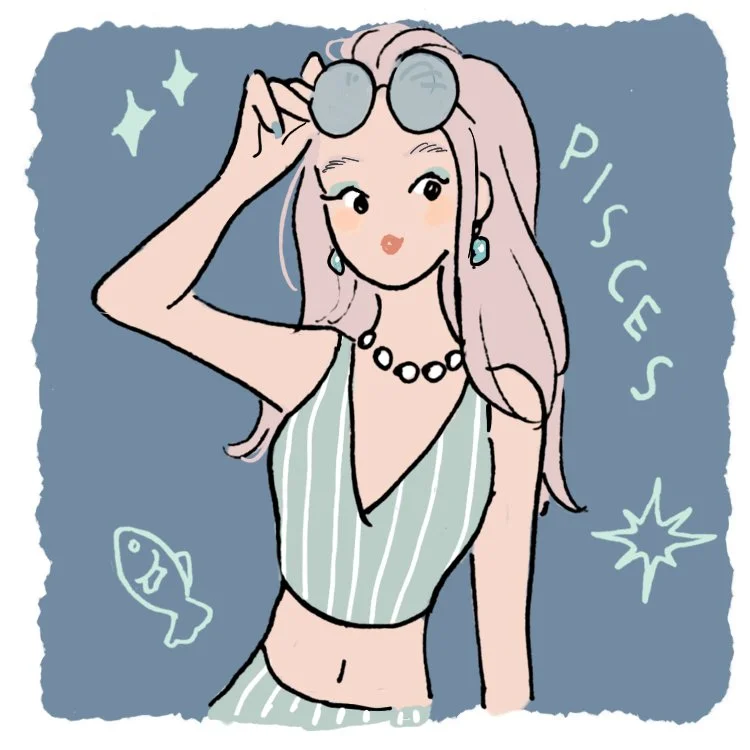 今週のうお座のキーワードは、「三密」。 今回のコロナ禍ですっかり「密」という言葉が禁忌の対象とされつつも、いかに私たちの日常生活や心身の健康というものが「密」に依存していたかも浮き彫りになったのではないでしょうか。
今週のうお座のキーワードは、「三密」。 今回のコロナ禍ですっかり「密」という言葉が禁忌の対象とされつつも、いかに私たちの日常生活や心身の健康というものが「密」に依存していたかも浮き彫りになったのではないでしょうか。










































































