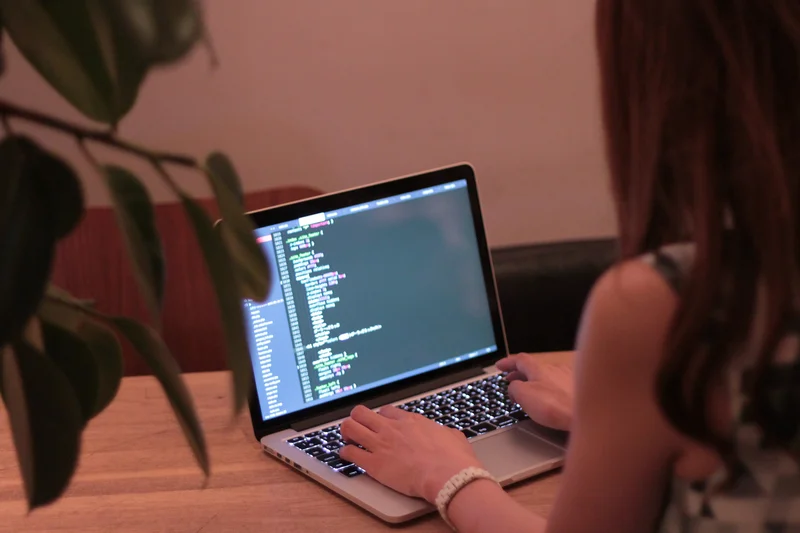-

【SUGARさんの12星座占い】<9/6~9/19>の12星座全体の運勢は?
「白紙にかえす」
「暑さ寒さも彼岸まで」の秋分直前の9月17日に、おとめ座で新月を迎えていきます。
夏のにぎわいが遠のき、秋らしくなるにつれ、次第に風が透き通っていくように感じられてくる頃合いですが、そうした時に吹く風を昔から「色なき風」と呼んできました。
中国から伝わった五行説によると、秋の色は白。日本人は、その白を、「色無き」と言い換えた訳です。本来は華やかさがないという意味でしたが、言い換えられていくうちに、しみわたるような寂寥感を言い表すようになっていったのだそうです。
そして、今回のおとめ座新月のテーマは「初心に返る」。能の大成者である世阿弥の「初心忘るべからず」という言葉と共に知られる「初心」は、普通に考えられているような“最初の志”のことではなく、自分が未熟であった頃の“最初の試練や失敗”の意ですが、これは試練に圧倒されたり、失敗の前に膝をついたりしたことのない者には、本当の成功はいつまでもやってこないのだということを指します。
そうした失敗や挫折を不当だとか、相手や世間が悪いと思い込むのではなくて、そこから人間としての完成に近づくための新たな挑戦が始まるのだと気付くこともまた「初心」なのです。人生には幾つもの初心がある。そんなことに思い至ることができた時には、きっと心のなかをとびきりの「色なき風」が吹き抜けていくはず。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「一鍬一鍬に南無阿弥陀仏」。
三河武士の出身で関ヶ原の戦いや大阪の陣にも出陣した後、中年になって突如出家して曹洞宗の禅僧となった鈴木正三が、晩年に遺した法語を弟子が集めたものが『驢鞍橋(ろあんきょう)』です。
そこには、江戸時代は儒教ばかりが称揚され仏教は堕落していたという一般的なイメージに反して、広く民衆に根を下ろして彼らを支えた生きた思想としての仏教の底力がうかがえます。
彼は同時代の一般禅僧を厳しく批判するだけでなく、何かと俗世間をのがれて静かに余生を送ることを尊いものと捉えていた中世的価値観を否定し、武士に限らず農民や被差別民まで含め、世俗の職務上の本分に即した修行の道を説きました。
例えば、「農業すなわち仏行なり」から始まる職業倫理に関する一節は、「別に用心を求むべからず(他に特別な心がけを求めてはいけない)」と畳みかけます。以下、訳文だけ引用。
「皆さん方のそれぞれの身体は仏の身体であり、心は仏の心であり、行為は仏の行為である。(中略)そうであるから、農の仕事で罪障を滅しようと大願力を起こし、一鍬一鍬に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えながら耕作するならば、必ず仏の悟りにいたるであろう。」
これは神と直接向き合うことを推奨し、魂の救済の確証を仕事に求める西洋のプロテスタントにも通じる近代的な職業倫理を既に先取りしています。既存の身分秩序を固定化したという批判もありますが、「一鍬一鍬に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」の下りのように、日々のルーティンの中にインスピレーションを見出し、そこに価値が置かれるようになったことの意味は非常に大きいでしょう。
ちなみに、タイトルは「ロバの鞍(くら)のはしくれ」のことで、愚かな男がこれを亡父の骨に見間違えたことから、誤って物事を見ていることへの戒めの意を含んだもの。
今期のおひつじ座もまた、大言壮語や出たとこ勝負はできるだけ控えて、毎日の小さな歩みに気持ちを込めて地道に積み重ねていくことを改めて意識していきたいところです。
参考:鈴木正三、鈴木大拙・校訂『驢鞍橋』(岩波文庫)
-

今期のおうし座のキーワードは、「明日の頭を創る」。
数学は論理的な学問だけれど、研究をすすめる上では「情緒」こそが大切である。そう説いたのは、歴史に残る世界的な数学者として文化勲章を受章した岡潔。そのエッセイ集『春宵十話』では、稀代の数学者の頭の中がどうなっているのかを、チラリとのぞくことができます。
例えば彼は学習のイメージについて「乾いた苔が水を吸うように学問を受け入れるのがよい頭といえる」と述べた上で、「いま、たくましさはわかっても、人の心のかなしみがわかる青年がどれだけあるだろうか」と問いかけ、「人の心を知らなければ、物事をやる場合、緻密さがなく粗雑になる。粗雑というのは対象をちっとも見ないで観念的にものをいっているだけということ」と書きつつ、話をいよいよ情緒へと移していきます。
「頭で学問をするものだという一般の観念に対して、私は本当は情緒が中心になっているといいたい」、「単に情操教育が大切だとかいったことではなく、きょうの情緒があすの頭を作るという意味で大切になる。(中略)学問はアビリティーとか小手先とかでできるものではないこともわかるだろう。」
そういう著者自身は、数学をやって何になるのかなどとは一切考えず、「数学を学ぶ喜びを食べて生きている」と豪語しています。確かに本書を読んでいると岡潔にとっての「今日の情緒」には、いつだって学ぶ喜びと自然の風土への驚きがあったのだということがよく伝わってくるはず。
そして今期のおうし座もまた、ビジネスであれ学習においてであれ「明日の頭を創る」ために、何よりもまず「今日の情緒」を豊かにすることを最優先にして日々を送る、これこそがテーマとなっていくでしょう。
その際、「対象への細かい心くばりがない」ということは、「いっさいのものが欠けることにほかならない」、つまり“心無い”といった著書の言葉もぜひ念頭に置いておきたい。
参考:岡潔「春宵十話」(光文社文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「なによりもまず穏やかさを!」。
ラジオはかつて夢のメディアでした。
フランス哲学界の巨星バシュラールは、1951年に書いた「夢想とラジオ」というエッセイの冒頭で、「ラジオというものはまったく宇宙的な問題である。地球全体が喋りまくっている」とした上で、「日常的な仕方で、人間の精神(プシュケ)とは何かを提示する役をラジオは負っているのだ」と述べつつ、「このロゴス圏、言葉の宇宙、人間の新しい現実であるこの宇宙的な話し言葉の世界における、自律的な生命を持たねばならないのである」と打ち出してみせました。
そう書かれてから70年近くが経過した今、ラジオが実際にそうした役割を果たせているかは分かりません。ただ、近年の電子書籍の台頭によってその立場が危うくなってきている本との比較もしつつ、バシュラールはラジオについて語り続けます。
「本というものは閉じられたり開かれたりして、人を孤独のうちに見出すようにも、人に孤独を課すようにも出来てはいない。反対に、ラジオは確実に人に孤独を課す。」
「孤独を課す」というのは強い表現ですが、これは本よりもラジオの方が、より自身の内側へと深く潜っていくことを促すということ。
「自分のなかに安らかさを、休息を置くことがそこでは権利でも義務でもあるような一室で、独り静かに、宵の時間に聴く必要があるだろう。ラジオには、孤独のなかで語るに必要な一切のものがある。ラジオには顔は要らない。」
恐らくバシュラールは、不幸な魂、暗鬱でありながら昂ぶった生を余儀なくされている魂たちに必要な一切のものをラジオに見出したのかも知れません。ラジオはリスナーが休息を受け入れられるような良き夜を準備してくれる。うまくいけば、めいめいが週に一度はぐっすりと眠れるように。
そうしたラジオに寄せられたかつての期待は、テレビ的なるものが完全に飽きられ、人々から距離を置かれつつある今の時代において再び高まりつつあるように思います。
何より、今期のふたご座にとっても、改めて自分ひとり孤独に過ごす夜を確保することが重要になってくるはず。雑音の海から逃れ、そっと夜そのものに深く沈んでいく中で、自分に必要なのはまず何よりも穏やかさなのだということを実感していくでしょう。
参考:ガストン・バシュラール、澁沢孝輔訳「夢見る権利」(ちくま学芸文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「内なる大衆を観察する」。
現代は大衆社会と言われますが、1930年に刊行された『大衆の反逆』において、著者であるスペインの哲学者オルテガはこの大衆を「人類史が生んだ甘やかされた子供」と呼びました。
スペイン内乱やファシズムの誕生を間近で目撃していたオルテガは、大衆社会を「完全な社会的権力の座に登った(中略)大衆というものは、その本質上、自分自身の存在を指導することもできなければ、また指導すべきでもなく、ましてや社会を支配統治するなど及びもつかない」といったアナーキーな世界として描写しましたが、そうした傾向は今日の社会においてますます顕著になってきているのではないでしょうか。
彼は人を2つのタイプに分け、「第一は、自らに多くを求め、進んで困難と義務を負わんとする人々であり、第二は(中略)自己完成への努力をしない人々、つまり風のまにまに漂う浮標のような人々」であると述べています。後者はまさに大衆の実体であり、こうした記述はいわゆるSNSでの人気取り競走やトランプ現象などのポピュリズム政治を予見していたかのようでもあります。
オルテガが大衆を「階級制度が生んだもの」とは考えず、どんな階級であれ、大衆やその運命としてのポピュリズムは近代的個人の意識のうちに少なからず潜んでいるモンスターであり、そうした大衆気質は今日では誰の中にも存在しているのだと喝破した上で、そこから脱け出すことの大切さを説いたのです。
すなわち、いま目の前に見えているもの、目先のものだけに振り回されて稚拙な結論をすぐに出そうとするのではなく、正しい判断を行うためにできるだけみずからの手と足を使って知識や情報を得る努力をすること。それはまさに、今期のかに座が改めて向き合っていくべきテーマとも言えるでしょう。
そのためにも、まず自分のなかに「自分以外の者の存在を考慮しない習慣、特に、いかなる人間をも自分に優る者とは見なさない習慣」がついていやしないか、よくよく観察してみるといいかも知れません。
参考:オルテガ・イ・ガセット、神吉敬三訳「大衆の反逆」(ちくま学芸文庫)
-

今期のしし座のキーワードは、「養生一番」。
近世における禅の復興者として知られる白隠(はくいん/1686~1769)は、それまでの古人の言動を中心とした「公案」によって修行して悟りを得るアプローチを分かりやすい言葉で体系づけただけではなく、あくまで抽象論としてではない、身体の修練を通して具体化したことにその最大の特徴がありました。
特に、まだ若かった白隠が座禅に行き詰まって心身衰弱に陥った際、京都白川の洞窟に住む白幽(はくゆう)先生という仙人を訪ねて教わり、実際に立ち直ったという内観の法を説いた『夜船閑話』は、今日もっともよく読まれている著作と言えます。
「生を養うというのは一国をまもるのと同じようであり、明君、聖主は、心をもっぱら自分以外の一般民衆の上におよぼし、暗君や凡主はつねに心を上にほしいままにし、利己的で自我中心主義で民衆の身の上をかんがえようとはしないものである」
この場合の「民衆の身の上」とは頭に対する身体のことであり、白隠は何事においても頭でっかちになりがちな傾向について「凡庸なものは、もっぱら心気を胸より上にのぼらせている」と批判しました。その上で、生を養う秘訣について次のように述べたのです。
「頭をつねに清涼ならしめ、足部を温かくしておけば、心の煩悶は去り、血液は環流し、胃腸の調子はよく、消化吸収、栄養排泄の諸作用は円滑に行われるものである。これは咽で息をしては得られず、丹田に心気を充実することによって得られるものである。」
これは一種のイメージトレーニングではありますが、白隠はこうした教えについて、「知識ではなく、実行して身体と心で(中略)体感せよ。行得せよ。かならず得る点があるであろう」と力強く断言しています。
今期のしし座もまた、理屈や知識のインプットではなく、こうした体感を伴う地道な養生を四の五の言わずに実践していくことが大切になってくるはず。まずは一日、次は三日。続けられる気力が出たなら、一週間。毎日少しの時間でも、改めてそうして身体をいたわり、自分を愛する習慣を身につけていきたいところです。
参考:直木公彦「白隠禅師 健康法と逸話」(日本教文社)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「目標を立て直す」。
シュリーマン(1822~1890)は8歳の時に本で見たトロイア戦争の挿し絵に衝撃を受け、長年伝説や夢物語とされてきたトロイアが実在したと信じるようになり、大人になったら必ず遺跡を発掘するという大志を抱いてさまざまな職業を試しながら資金を貯め、見事51歳の時に夢を実現させたことでよく知られています。
彼は非常に先見の明ある人物であった一方で、自意識過剰な俗人であり、賞賛と悪評が混在する人物でもありましたが、少なくとも目的達成のために自己投資し続けた点に関しては驚嘆すべき偉人であることは間違いありませんし、実際、彼の著書は独学による効率的な勉強法やそのヒントの宝庫と言えます。
彼はトロイア発掘という大目標の手間に、資金調達という中目標を設定し、そのために仕事の合間にさまざまな語学の勉強に明け暮れていったのですが、その徹底ぶりは凄まじいものでした。
「まず私は読みやすい筆跡を習得しようとして、ブリュッセルの有名な書家マネーに二十時間の授業をうけて、十分に目的を達した。つづいて、自分の地位をよくするために、熱心に近代語の学習をはじめた。私の年収(中略)のなかばを学習につかい、他の半分で私の生活費をまかなったのだが、どうにかやってゆけた」
本書を読んでいると、勉強するうえで一番大切なことは、目的を明確にすることであることが痛感されてきます。シュリーマンは、趣味の勉強とは一線を画した「目的達成のための勉強」ということに可能な限りこだわり、文字通り全力を尽くしていったのです。
もちろん、いきなりシュリーマンと同じレベルの努力を実行することは難しいでしょう。けれど、目標を幾つかに分け、それらを完遂するために必要なことをきちんと洗い出し、嫌でもやらざるを得ない状況にみずからを持っていく彼の方法論を真似してみることなら、そう難しくないはず。
その意味で、自身の星座で新月を迎えていく今期のおとめ座もまた、いま自分がどこに向かって、何のために、いかにして日々の努力を積み重ねていくべきかということを、改めてゼロから描き直してみるには絶好のタイミングと言えるでしょう。
参考:ハインリヒ・シュリーマン、村田数之亮訳「古代への情熱」(岩波文庫)
-
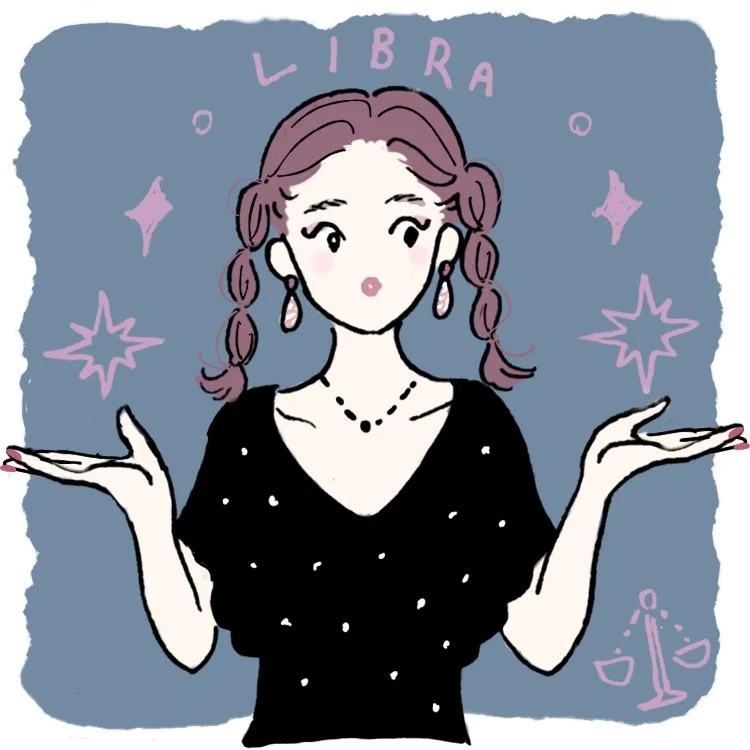
今期のてんびん座のキーワードは、「“隠れみの”を用意する」。
生活するためには何らかの職につかなければなりませんが、かと言ってあんまり無理をして職にかじりついているようでは、そうそう長くは続かないもの。
ましてや、小説であれ俳句であれ絵であれ音楽であれ、自分自身のための愉しみを別に持っている身であれば、どこかで出世や見栄には見切りをつけて、世間の目を逃れるための「隠れみの」を用意する算段をつけなければなりません。
そういうことを考える上で非常に興味深いのが、夏目漱石が40歳の時に行われた「文芸の哲学的基礎」という講演。何やらものものしいタイトルではありますが、これは彼が一切の教職を辞し、朝日新聞社に入社した直後のもので、その胸の内のホンネについて触れたじつに味わい深い一節が出てくるのです。
「私なども学校をやめて、縁側にごろごろ昼寝をしていると云って、友達がみんな笑います。――笑うのじゃない、実は羨ましいのかも知れません。――なるほど昼寝は致します。昼寝ばかりではない、朝寝も宵寝も致します。しかし寝ながらにして、えらい理想でも実現する方法を考えたら、二六時中車を飛ばして電車と競争している国家有用の才よりえらいかも知れない。私はただ寝ているのではない、えらい事を考えようと思って寝ているのである。不幸にしてまだ考えつかないだけである。」
当時の大学教授の社会的地位の高さと、ジャーナリズムの地位の低さを考えると、これは大決断だった訳ですが、当の本人にとってみれば「えらい事を考えようと思って寝ている」生活こそが最高の生き方だったのであり、「国家有用の才よりえらいかも知れない」という箇所などは、どうも本気で思っていたのではないでしょうか。
いや、自己に忠実に生きるという点では、実際に「はるかにえらい」のです。そして、今期のてんびん座の人たちもまた、多かれ少なかれ世間からの隠れ先を見つけたり、何らかの隠れみのを用意したりすることで、何をしてもよい自由で暇な時間を工面していくことが一つのテーマとなっていくはずです。
参考:「夏目漱石全集10」(ちくま文庫)
-

今期のさそり座のキーワードは、「『自省録』スタイル」。
現代人は技術の進歩と比例するかのように、ますます多忙を極めるようになってきていますが、こと多忙さという点では最盛期のローマ帝国で第十六代皇帝となって巨大組織を牽引したマルクス・アウレリウスに匹敵する者はほとんどいないでしょう。
彼は古代ギリシャの哲学者プラトンが理想とした哲人政治を、人類史上ただ一人行ったリーダーでもありましたが、彼が自分自身との対話の記録を日記形式で残した『自省録』は、ゲルマン人の反乱を制圧すべく向かった北境の遠征地でも書き継がれていきました。
「もはやさ迷い歩くな。(中略)おまえの生の目的に向かって一路急げ」
「おまえがある者の無恥に怒りを覚えるときには、直ちにおまえ自身に尋ねよ、『いったいこの宇宙の無恥な者どもが存在しないことができるか』と。ならば、できないことを求めぬことだ」
このように、彼は起きた事実を日記にそのまま記録したのではなく、自分がなすべき行動の規範を綴ったのです。そうすることで、実行すべき内容が意識の上に自然と定着していく。2000年前の超多忙な著者によって壮年時代から晩年まで実践され続けたこうした『自省録』というスタイルは、誰にでも簡単に実行できる、人生をより手応えのあるものにする優れた方法論と言えます。
彼は生来とても内向的な人で、華々しい皇帝職よりも本来は学者として静かにものを考えることを好んでいたのですが、『自省録』はそんな彼だからこそ編み出せた、自分の人生に起きる出来事を受容し、困難を乗り越えるための秘訣に他なりませんでした。
同様に、今期のさそり座もまた現実に起きた出来事をいかに受容していくかという問題に直面していきやすいはず。新月らしく、新しいノートを一冊おろして、試しに「起きたことにはすべて意味がある」という観点から、思いついたことをつらつらと書いてみるといいでしょう。
参考:マルクス・アウレリウス、鈴木照雄訳「自省録」(講談社学術文庫)
-

今期のいて座のキーワードは、「生きがいの掘り起こし」。
“高貴なるものの義務”を意味する「ノーブレス・オブリージュ」という言葉がありますが、別に貴族に生まれついた訳でなくとも、また特別社会的に高い地位にある訳ではなくとも、生きているということはそれ自体で「ノーブル」であり、何かを行う義務を伴うような大きな価値を持っているのではないか。
ハンセン病患者の実情を知り、親の反対を押し切って30歳で精神科医となった神谷美恵子の著した『生きがいについて』は、一文一文追うごとに、そうした力強い問いかけをされているように感じられてきます。
「ほんとうに生きている、という感じを持つためには、生の流れはあまりになめらかであるよりはそこに多少の抵抗感が必要であった。したがって生きるのに努力を要する時間、生きるのが苦しい時間のほうがかえって生存充実感を強めることが少なくない」
もちろん、自分ひとりだけではなかなかそうした「生存充実感」を感じられないという人は少なくありません。自己完結するのが難しく、集団性をその本質に持ついて座もまたそれに該当しやすいですが、著者はそうした人たちへの処方箋として、何かしら他者へ貢献できることを探してみるという基本の徹底を説いていきます。
世間に広く知れ渡っている訳ではなくても、自分なりに他者を喜ばせ、献身できるきっかけをつかんで、「生きがいを感じているひとは他人に対してうらみやねたみを感じにくく、寛容でありやす」く、そこには自然と「未来に向かう心の姿勢」が培われていく。
そうした姿勢こそが、本来の意味での「ノーブル」ということであり、それは生きがいを感じつつ、使命感を持って自分の身を捧げることと切っても切り離せないのです。
今期のいて座の人たちもまた、どうしたらそこに全力を注ぐことのできる自己の生存目標を掲げられるかを、自分にとって生きがいとは何かということを、改めて掘り下げ直してみるといいでしょう。
参考:神谷美恵子「生きがいについて」(みすず書房)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「美的水準を引き上げる」。
例えば、いくら華麗なドレスで着飾ったとしても、それが本来そうであるように存在していなければ、つまり、着ている本人にとってごく自然なものになっていないのならば、果たして美しいと言えるだろうか。
―否。青山二郎であれば、間髪入れずにそう答えるでしょう。
“遊び”の真の精神を知り尽くした陶器鑑賞家にして装幀家、そして美の追求者であった彼は、『眼の筍生活』というエッセイの中で次のように述べています。
「物の「在り方」は美の鑑賞なぞといううっとりした眼に、最初の印象を許すものではありません。一眼見て惚れたといいますが、文字通りそれは好き好きというもので、それとこれとは別の問題であります。好き好きという話になると、これはこれで大分面倒な趣味の事になりますが、併しもしもこの好き好きというものが、物の「在り方」と端的に一致する様になれば、先ず骨董屋より玄人といえましょう。」
著者は「うっとりした眼」の例として「お茶を習って講釈を聞くから、変てこな茶碗が茶碗に見えてくる」ことを挙げ、「思考を用立てるから美なら美が見えてくると思っている、この一般的な眼に対する不信ほど危険な習慣はありません」と注意を促し、「眼玉の純度」あるいは、「美というものは存在しない。在るものは美術品だけだ」という言い方で対象の固有性やそのあるなしをきちんと見抜くことの大切さを説きました。
現実というのは、いつだって既に思考よりも一歩進んでいるのです。そして、今期のやぎ座もまた、自身の眼の動きを信じて、余計な思考習慣をさっぱり洗い流していけるかが大いに問われていくはず。それは「引き算の美学」とでも言えましょうか。
そう考えると、涙というものも、人がもう以前の物の見え方を刷新したい時に起きる生理現象であるようにも思えてくるから不思議です。
参考:青山二郎「眼の哲学・利休伝ノート」(講談社文芸文庫)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「ふと思い出されてくるもの」。
「日本人の多数が、もとは死後の世界を近く親しく、何かその消息に通じているような気持を、抱いていた。」
敗戦直前に書き上げられ、敗戦後に出版された柳田國男の『先祖の話』の一節です。多数の人々が死に直面する太平洋戦争のさなか、日本人の死後や霊魂の観念がもともとどのようなものであったかを解明せんと書かれた本書では、日本の神は先祖神に由来するという大胆な仮説が立てられました。
著者は庶民の生活文化の中で、死後や霊魂の問題が家の継承や先祖崇拝と結びつけられてきた旨について、四つの観点に整理した上で次のように述べています。
「第一には死してもこの国の中に、霊は留まって遠くへは行かぬと思ったこと、第二には顕幽二界の交通が繁く、単に春秋の定期の祭だけでなしに、いずれか一方のみの心ざしによって、招き招かるることがさまで困難でないように思っていたこと、第三には生人の今はの時の念願が、死後には必ず達成するものと思っていたことで、これによって子孫のためにいろいろの計画を立てたのみか、更に再び三たび生まれ代わって、同じ事業を続けられるもののごとく、思った者の多かったというのが第四である。」
ただこの説は十分に客観的な根拠を持っておらず、柳田以降忘れ去られ、社会の表面からも消え去っていきましたが、約10年前の東日本大震災などを受けて、もう一度検討されるべき死生観の一伝統として再浮上してきているように思います。
同様に、今期のみずがめ座もまた、そうしていつの間にか忘れ去られていた伝統や結びつきを改めて思い出していくこと。あるいは、今の自分に必要な形で受け継いでいくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:柳田國男「先祖の話」(角川ソフィア文庫)
-
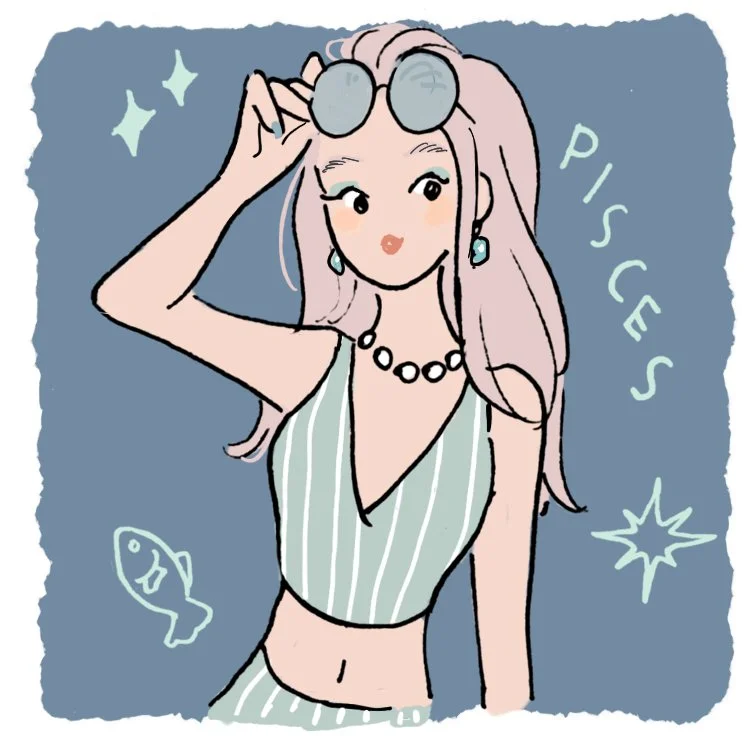
今期のうお座のキーワードは、「自分自身もメディアとして在るということ」。
「メディア」から社会の根底にある原理を読み解いたマクルーハンの『メディア論』では、西洋文明の3000年におよぶ歴史において、人類は3つの変革を経験したのだと整理します。
第一の革命は紀元前11世紀頃のアルファベットの発明であり、これによって口承で伝えられてきた物語が文字で表され、記録されるようになったのです。こうした状況は、15世紀にドイツで活版印刷機が発明されたことで、さらに大きく変わりました。それまではもっぱら「音読」メインだった読書が、「黙読」へと変わり、人間が聴覚型から視覚型へと大きく舵を切っていったのです。これが第二の革命。
そして第三の革命が20世紀のテレビの登場です。テレビによって全く受け身で情報が受け取れるようになり、またCMなどで資本主義とも深く結びついていくことで、良くも悪くも人間の思考と行動の様式を変えてしまったのです。
マクルーハンは、こうした歴史を踏まえた上で、メディアというものを「熱いメディア」と「冷たいメディア」に分け、「熱いメディアとは単一の感覚を「高精細度」で拡張するメディアのことである。「高精細度」とはデータを十分に満たされた状態のことだ」と述べ、その代表はラジオであり、音だけで囁くように人を熱く揺り動かす力を持つのだとする一方で、テレビは「冷たいメディア」の代表で、ただ受け身的に情報を垂れ流すだけであり、「ティーンエイジャーが、集団的テレビに背を向けて、私的なラジオへ向かっている。(中略)共同体の多様なグループと緊密な関わりを持とうとするのはラジオに本来的な特徴」であると分析しています。もちろん、今日のTwitterやInstagramなどのソーシャルネットワークも、熱いメディアの現代版と言っていいでしょう。
これはインターネット以前の昔に書かれた書物ではありますが、「メディアこそが世界を、人間を変えるのだ」という斬新な視座は今なお精彩を放っています。
翻って、あなたという人間自身は「熱いメディア」と「冷たいメディア」のどちらとして、周囲の人に影響を与え、かつ周囲のどんなメディアから影響を受けとっているでしょうか。
今期のうお座は、そうした他者への伝え方や向き合い方について、改めて問い直し、振り返っていくことが大きなテーマとなっていきそうです。
参考:マーシャル・マクルーハン、栗原裕・河本仲聖訳「メディア論」(みすず書房)
 【SUGARさんの12星座占い】<9/6~9/19>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<9/6~9/19>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「一鍬一鍬に南無阿弥陀仏」。 三河武士の出身で関ヶ原の戦いや大阪の陣にも出陣した後、中年になって突如出家して曹洞宗の禅僧となった鈴木正三が、晩年に遺した法語を弟子が集めたものが『驢鞍橋(ろあんきょう)』です。
今期のおひつじ座のキーワードは、「一鍬一鍬に南無阿弥陀仏」。 三河武士の出身で関ヶ原の戦いや大阪の陣にも出陣した後、中年になって突如出家して曹洞宗の禅僧となった鈴木正三が、晩年に遺した法語を弟子が集めたものが『驢鞍橋(ろあんきょう)』です。 今期のおうし座のキーワードは、「明日の頭を創る」。 数学は論理的な学問だけれど、研究をすすめる上では「情緒」こそが大切である。そう説いたのは、歴史に残る世界的な数学者として文化勲章を受章した岡潔。そのエッセイ集『春宵十話』では、稀代の数学者の頭の中がどうなっているのかを、チラリとのぞくことができます。
今期のおうし座のキーワードは、「明日の頭を創る」。 数学は論理的な学問だけれど、研究をすすめる上では「情緒」こそが大切である。そう説いたのは、歴史に残る世界的な数学者として文化勲章を受章した岡潔。そのエッセイ集『春宵十話』では、稀代の数学者の頭の中がどうなっているのかを、チラリとのぞくことができます。 今期のふたご座のキーワードは、「なによりもまず穏やかさを!」。 ラジオはかつて夢のメディアでした。
今期のふたご座のキーワードは、「なによりもまず穏やかさを!」。 ラジオはかつて夢のメディアでした。 今期のかに座のキーワードは、「内なる大衆を観察する」。 現代は大衆社会と言われますが、1930年に刊行された『大衆の反逆』において、著者であるスペインの哲学者オルテガはこの大衆を「人類史が生んだ甘やかされた子供」と呼びました。
今期のかに座のキーワードは、「内なる大衆を観察する」。 現代は大衆社会と言われますが、1930年に刊行された『大衆の反逆』において、著者であるスペインの哲学者オルテガはこの大衆を「人類史が生んだ甘やかされた子供」と呼びました。 今期のしし座のキーワードは、「養生一番」。 近世における禅の復興者として知られる白隠(はくいん/1686~1769)は、それまでの古人の言動を中心とした「公案」によって修行して悟りを得るアプローチを分かりやすい言葉で体系づけただけではなく、あくまで抽象論としてではない、身体の修練を通して具体化したことにその最大の特徴がありました。
今期のしし座のキーワードは、「養生一番」。 近世における禅の復興者として知られる白隠(はくいん/1686~1769)は、それまでの古人の言動を中心とした「公案」によって修行して悟りを得るアプローチを分かりやすい言葉で体系づけただけではなく、あくまで抽象論としてではない、身体の修練を通して具体化したことにその最大の特徴がありました。 今期のおとめ座のキーワードは、「目標を立て直す」。 シュリーマン(1822~1890)は8歳の時に本で見たトロイア戦争の挿し絵に衝撃を受け、長年伝説や夢物語とされてきたトロイアが実在したと信じるようになり、大人になったら必ず遺跡を発掘するという大志を抱いてさまざまな職業を試しながら資金を貯め、見事51歳の時に夢を実現させたことでよく知られています。
今期のおとめ座のキーワードは、「目標を立て直す」。 シュリーマン(1822~1890)は8歳の時に本で見たトロイア戦争の挿し絵に衝撃を受け、長年伝説や夢物語とされてきたトロイアが実在したと信じるようになり、大人になったら必ず遺跡を発掘するという大志を抱いてさまざまな職業を試しながら資金を貯め、見事51歳の時に夢を実現させたことでよく知られています。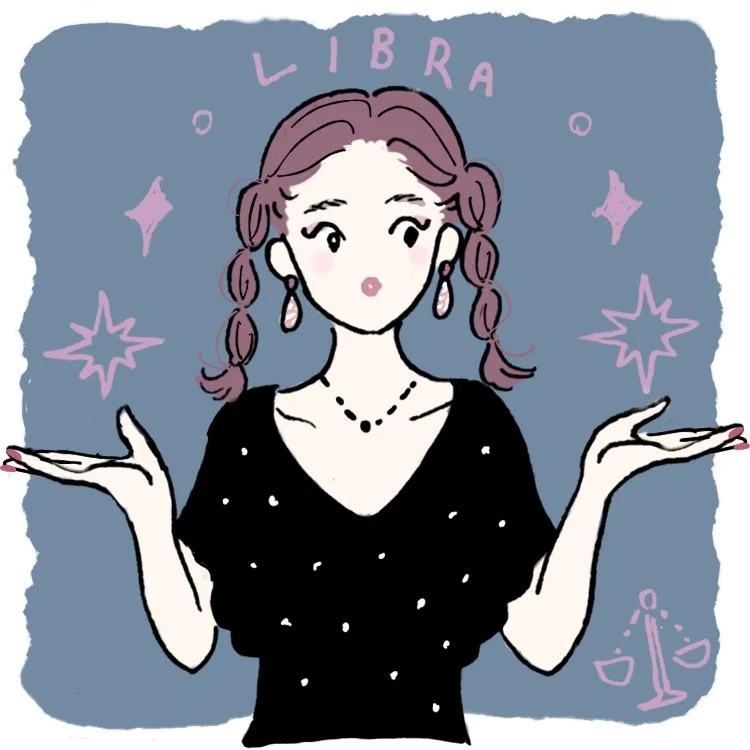 今期のてんびん座のキーワードは、「“隠れみの”を用意する」。 生活するためには何らかの職につかなければなりませんが、かと言ってあんまり無理をして職にかじりついているようでは、そうそう長くは続かないもの。
今期のてんびん座のキーワードは、「“隠れみの”を用意する」。 生活するためには何らかの職につかなければなりませんが、かと言ってあんまり無理をして職にかじりついているようでは、そうそう長くは続かないもの。 今期のさそり座のキーワードは、「『自省録』スタイル」。 現代人は技術の進歩と比例するかのように、ますます多忙を極めるようになってきていますが、こと多忙さという点では最盛期のローマ帝国で第十六代皇帝となって巨大組織を牽引したマルクス・アウレリウスに匹敵する者はほとんどいないでしょう。
今期のさそり座のキーワードは、「『自省録』スタイル」。 現代人は技術の進歩と比例するかのように、ますます多忙を極めるようになってきていますが、こと多忙さという点では最盛期のローマ帝国で第十六代皇帝となって巨大組織を牽引したマルクス・アウレリウスに匹敵する者はほとんどいないでしょう。 今期のいて座のキーワードは、「生きがいの掘り起こし」。 “高貴なるものの義務”を意味する「ノーブレス・オブリージュ」という言葉がありますが、別に貴族に生まれついた訳でなくとも、また特別社会的に高い地位にある訳ではなくとも、生きているということはそれ自体で「ノーブル」であり、何かを行う義務を伴うような大きな価値を持っているのではないか。
今期のいて座のキーワードは、「生きがいの掘り起こし」。 “高貴なるものの義務”を意味する「ノーブレス・オブリージュ」という言葉がありますが、別に貴族に生まれついた訳でなくとも、また特別社会的に高い地位にある訳ではなくとも、生きているということはそれ自体で「ノーブル」であり、何かを行う義務を伴うような大きな価値を持っているのではないか。 今期のやぎ座のキーワードは、「美的水準を引き上げる」。 例えば、いくら華麗なドレスで着飾ったとしても、それが本来そうであるように存在していなければ、つまり、着ている本人にとってごく自然なものになっていないのならば、果たして美しいと言えるだろうか。
今期のやぎ座のキーワードは、「美的水準を引き上げる」。 例えば、いくら華麗なドレスで着飾ったとしても、それが本来そうであるように存在していなければ、つまり、着ている本人にとってごく自然なものになっていないのならば、果たして美しいと言えるだろうか。 今期のみずがめ座のキーワードは、「ふと思い出されてくるもの」。 「日本人の多数が、もとは死後の世界を近く親しく、何かその消息に通じているような気持を、抱いていた。」
今期のみずがめ座のキーワードは、「ふと思い出されてくるもの」。 「日本人の多数が、もとは死後の世界を近く親しく、何かその消息に通じているような気持を、抱いていた。」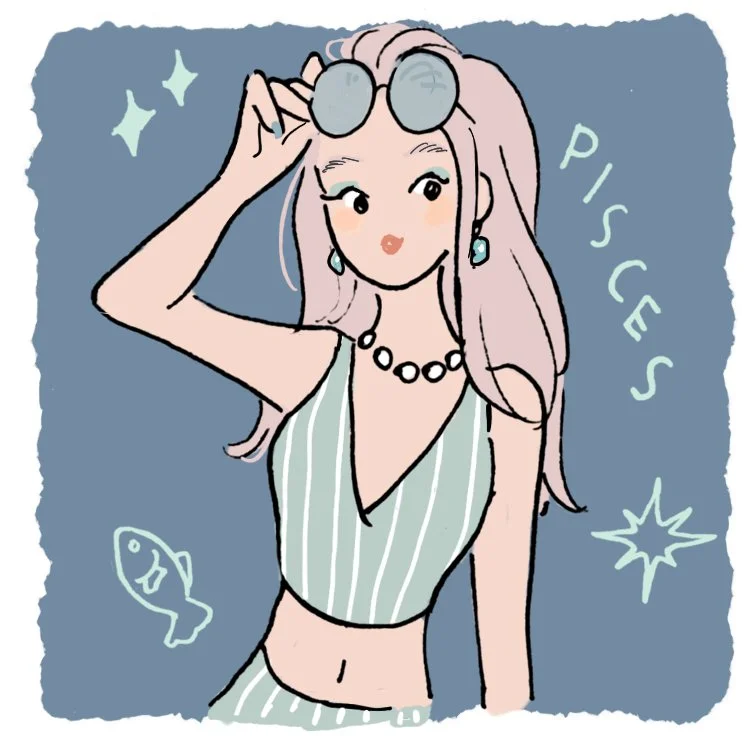 今期のうお座のキーワードは、「自分自身もメディアとして在るということ」。 「メディア」から社会の根底にある原理を読み解いたマクルーハンの『メディア論』では、西洋文明の3000年におよぶ歴史において、人類は3つの変革を経験したのだと整理します。
今期のうお座のキーワードは、「自分自身もメディアとして在るということ」。 「メディア」から社会の根底にある原理を読み解いたマクルーハンの『メディア論』では、西洋文明の3000年におよぶ歴史において、人類は3つの変革を経験したのだと整理します。