-

【SUGARさんの12星座占い】<10/18~10/31>の12星座全体の運勢は?
「何かが“やってくる”まで」
二十四節気でみると10月23日の「霜降」と11月7日の「立冬」のちょうど中間にあたる10月31日の深夜におうし座満月を迎えていきます。
霜降とは、これまでと明らかに空気が変わって、露が凍って霜になり始める頃合いで、「立冬」はいよいよ冬の到来ですが、今回の満月もまさに時代の移り変わりを体感していくような特別なタイミングとなっていきそうです。
というのも、今回の満月は牡牛座の天王星と正確に重なっているから。天王星は「既存の構造からの逸脱と変革」の星ですが、これは今年から来年へ向けて既に起きつつある大きな流れを象徴する雰囲気の根底にあるもの。そして、今回のテーマは「予測不可能なものの到来」。
将来に備え、ただ現実的なコストを算出したり、リスク回避に励んだり、身を固めていくだけでは、何かが決定的に足りない。ただし、その「何か」というのは、日常という固いアスファルトがめくれるように、これまで疑われることなく固定化されてきた文脈にずれが生じなければ、けっして到来することはありません。
その際、鍵となってくるのは、ちょっとした違和感をスルーせずに育てていくこと。月がまんまるに膨らみきっていくまでは、分かりやすい解答を求めたり、そこに安住するのではなく、「あえて」「今さら」「あらためて」というひと手間や余計なプロセスを大切にしてみるといいでしょう。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「俳句的探究」。
芭蕉以前の俳句芸能を主導する人物であった山崎宗鑑の代表句に、「風寒し破れ障子の神無月」という句があります。
神無月の破れ障子に風が寒い、意味としてはそれだけのことなのですが、「破れ障子の神無月」という言葉のうちで、神様の「神」と障子の「紙」がかけ言葉になっていて、意味としてはかけ離れている二つの言葉が音の共通性で結びついたところにユーモアが働いている訳です。
こうしたある意味でダジャレやことば遊びの延長線上にあった俳句に、決定的な転回をもたらしたのが松尾芭蕉でした。そのとき、言葉の仕組みとしての俳句の深層には、何が起こっていたのか。芭蕉にとっても、その俳人としてのキャリアの上で革命的な飛躍を遂げたとされているのが次の句です。
「古池や蛙飛び込む水のおと」。一見すると、神秘的な所は何もないどころか、それまでの俳句のような機知やユーモアもすこしも働いていません。というより、そういう言葉の働きが動き出すのを拒絶しているかのようにさえ感じられます。
芭蕉の俳句の根本にあったのは「不易流行(”永遠に変わらない不易性と絶えず移り変わっていく流行性は本質的に同じである”という理念)」ですが、この場合、「古池や」が不易で、「蛙飛び込む水のおと」が流行なのです。どういうことか。
和歌の伝統の定めるところでは、歌に詠むモチーフとしては蛙は鳴き声に限るし、取り合わせは山吹に限るのですが、芭蕉が鳴き声ではなく「水の音」を採ったのは「新しさ」であり、そこに山吹というお約束を置くのではなく「古池や」という心に浮かんだイメージをあえて置いたのです。
つまり、まず水の音が聞こえたのであり、その結果、古い池のイメージが見えたのであって、そこに宇宙と人間との直接の交流が起きているさまを描こうとしたのです。
それは、「笑い」や「妄想」の入り込む余地もなければ、意味や社会によって「生産性」に変換されることもない(「役に立つ」とか「お洒落で映える」など)、すべてがただ存在しながら、自分が存在しているという透明な力の流入の描写なのではないでしょうか。
宗教学者の中沢新一は、こうした芭蕉の試みを「人間主義の底部をぬいてしまう」革命であり、何も生産せず、蕩尽しつくすだけの芸術機械など、人類史を見渡しても稀有なのではないかと述べていました。
今期のおひつじ座もまた、「生産性」や「役に立つ」ことの呪縛からいかに自由になっていけるかが一つのテーマになっているのだと言えるかも知れません。
参考:長谷川櫂『俳句の宇宙』(中公文庫)、中沢新一『日本文学の大地』(角川学芸出版)
-

今期のおうし座のキーワードは、「性からの解放」。
ノーベル賞作家レッシングの長編小説『暮れなずむ女』の主人公で、イギリスの中産階級向けの郊外住宅に住むケイトは、よく手入れされた髪と派手になりすぎない服装をまとった「清楚な奥様」で、優しい夫と4人の子供に恵まれてそれなりに幸せに暮らしてきたが、末っ子が19歳になって家を出ることになった時、ひとつの決定的な危機を迎えていきます。
というのも、家族がケイトのことをもう更年期に入ったかのように話しているのを聞いてしまったから。45歳のケイトはまだ閉経していないし、ましてや人生が終わった訳ではないのにも関わらず、です。
ケイトはすぐさま仕事を見つけ、古い服を脱ぎ捨て、セクシーで洗練された服を買います。それはかつての奥様からかけ離れた、ケイト・フェレイラとしての「人生の旅立ちを可能にするパスポート」のようなものでした。しかし、ケイトはすぐに仕事に飽きます。というより、職場で仕事をしていても、それが母親的役割の延長線上にあったことに気付いてしまったのです。
ケイトはこの精神崩壊とでも言えるような体験をもとに、逆に悟りを開いていきます。それは、未来は昨日の続きではなく、少女だった頃に中断してしまったところから再び始まるのだ、というもの。
そして、性的魅力を気にかけたり、消費されたりするようになる以前の、未熟で、怖いもの知らずで、初々しさを失っていなかった頃の自分から、改めてバトンを引き継いでいくことでもありました。
閉経はあくまできっかけの一つに過ぎないとはいえ、それを機に自分自身を掘り下げたいという欲望に火が付く人は少なくないでしょう。
今期のおうし座もまた、年齢や社会的役割のことはいったん脇に置いて、芸術や教養や精神性を養い、自己発見の方へと目を向け直してみるといいかも知れません。
参考:ドリス・レッシング、山崎勉訳『暮れなずむ女』(水声社)
-

今期のふたご座のキーワードは、「受け取る側の感受性」。
一時期、占いをするタコがメディアで取り上げられたことがありましたが、無脊椎動物の中でもタコを含めた頭足類はかなり大きな頭脳と多くの神経細胞を持っており、彼らは簡単な足し算や引き算はおろか、パズルを解いたり、人間に対して明瞭にコミュニケーションを取ろうとさえするのだとか(少なくともそう見える)。
人間に対する好き嫌いがあって、気に入らない人間には水をかけてきたり、餌が不味ければその不満を表明しようとしてくるといった、きわめて「人間的」としか言えないような知性を感じさせるのです。
しかし、人間と違って彼らは1、2年で死んでしまう短命な生物であり、進化的背景を鑑みても、その知性やハードウェアが人間とはかなり異なったものであることは明らかであり、一見「相互理解」ができるように見えるのが一種の幻想のようにも思えてきます。
この問題に対して、実際の観察に基づいて考察を重ねて『タコの心身問題』を書いたゴドフリー=スミスは、タコとヒトが示す知性は互いによく似てはいるが、それは「他人のそら似」以上のものではなく、進化生物学的には「相同」ではなく、「相似」的類似性と呼ばれるものに相当するという。
いわば、昆虫の翅(はね)と鳥の翼の類似性のようなもので、起源が違うもの同士が図らずも似たような形や機能にたどり着いたというだけで、互いに無縁なものであると。
確かに、「知能が高い」というだけで特定の動物を特別視するのは、逆に言えば「バカは眼中にない」と言っているようなもので、それこそ言葉の通じない相手は無視しても構わない、相手をする価値もないと見なす人間の傲慢さの表れでしょう。
つまり、コミュニケーションを取れていないのは人間の方かも知れず、受け取る側の感受性が研ぎ澄まされていけば、「知性」とはまた別の基準で「相互理解」の可能性が開けてくるかもしれないという問題は残されているのではないでしょうか。
今期のふたご座もまた、そうしたコミュニケーションにおいて、ふだん自分が何を感じ取れているのか、またいないのか、といった問題が少なからず問われてくるはずですし、そこにはタコとヒト、ヒトと宇宙人など、種や進化的背景を超えたコミュニケーションが成立する可能性だって十分に開かれているように思います。
参考:ピーター・ゴドフリー=スミス、夏目大訳『タコの心身問題』(みすず書房)
-

今期のかに座のキーワードは、「ヒトの存在理由」。
1917年ロシア革命で「賦役(チェコ語でrobota)を負うもの=無給労働者」が解放された3年後の1920年に発表されたのがチェコの作家カレル・チャペックによる戯曲『ロボット』でした。
その序幕、大富豪の娘ヘレナがアメリカのロボット製造会社を見学する。人間を労苦から解放するという理想の実現のために、「感情」のような不要な機能を除去し、人間に代わる労働者として大量生産されたロボットは、金属性ではなく有機物の化学処理によってコーティングされているという説明があり、唐突に工場の運営会社の社長がヘレナに求婚するところで幕を閉じる。
しかしその10年後、人間の労働力が不要になったために全世界的に人間の不妊が広がり、ロボットの「人類絶滅」をめざす反乱が始まり、ついにロボットが「人類の時代は終わった」と宣言するに至るのです。
今後ロボット化が禁止されていく可能性が高い領域を、チャペックの戯曲からあえて推測すれば、それは「家族愛」に関与する領域なのではないでしょうか。
妊娠・出産もまた特殊なリスクが想定される営みですが、それが育児・教育にまでなだらかに広がっていく過程で総体的に成立していく家族的コミュニティの形成までロボット化の可能性を考えてみると、そこには「業務」や「機械的命令と実行の反復」によっては決して成立しえない“何か”が含まれているように思えるからです。
現代では人間は「自分にしかできない仕事や役割」を自分の社会的アイデンティティとしていますが、将来的には「人間にしかできない営みや役割」を自身の存在理由として追求するようになる時代がそう遠くない未来に訪れるのかもしれません。
今期のかに座もまた、そうした中長期的視点から今後自分が追求していくべき仕事や役割、あるいは営みについて考えてみるといいでしょう。
参考:カレル・チャペック、千野栄一訳『ロボット』(岩波文庫)
-

今期のしし座のキーワードは、「人文主義者」。
ルネサンス期に誕生した、宗教者でも法学者でもない知識人としての「人文主義者」。いまや大学の片隅や、文科系や演劇系サークルなどでひっそりと息を繋いでいますが、ブルクハルトによれば、人間がみずからを変革できる自由の力に目覚めた「近代的心性」が広まっていったのは500年ほど前の人文主義者の影響でした。
古代の知識の輸入者であり翻訳者でもある彼らの多くは、都市国家を支配する商業貴族や軍事貴族に仕えることを生業とし、統治術の指南教師として、また師弟の教育係として、あるいは外交官を兼ねた実務家として雇用されていました。
そうして人文主義の教えで育った貴族の子弟たちが、長じて都市国家の指導的地位に就くようになると、大学に修辞学や文献学の講座を作って人文主義者を高給で雇い始め、統治者のたしなみとしても積極的に評価されるようになり、いよいよ人文学は隆盛していきました。
さらに、ギリシャ・ローマに範をとった公的演説や通史の編纂ないしそれらの教授を通じて、人文主義者には世評をコントロールする絶大な力を持つようになり、やがて統治者たちに恐れられるようにまでなるのですが、そうした古代の知識やレトリックが供給過剰となり、世に新知識を提供する代わりに、内輪の勢力争いや派閥争いに明け暮れるようになります。
そして、次第に人文主義者たちは真理を追究する哲学者というより詭弁を弄する“傲慢なソフィスト”と見なされていくようになり、我欲の暗い情熱と気高い芸術性の称揚とが隣り合う、美しい悪夢のような世界が出現していくなかで、イタリア全体が外国に隷属し、諸都市も主権を失ってしまうと、人文主義者たちはあっと言う間に行き場を失ってしまったのでした。
ブルクハルトの著述は一部のエリートたちの思想や行動に偏り過ぎており、その視野があまりに狭いという批判はあるものの、運命的信仰の呪縛の下にあった古い人間社会を新しい時代へ凛と導いた者たちへの彼の揺るぎないビジョンの価値はいささかも疑う必要のないものでしょう。
今期のしし座においても、どれだけ時代の変遷や時の経過を経ても、いつまでもその輝きが失われることのない気高いビジョンをいかにして獲得していけるかどうかが問われていくことになりそうです。
参考:ヤーコプ・ブルクハルト、新井精一訳『イタリア・ルネサンスの文化』(ちくま学芸文庫)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「まだ何もかもやってみた訳じゃない」。
初出・初演から50年以上も経った今もなお、さまざまな言論人から繰り返し言及され、無数の解釈が生み出され続けている不条理時演劇の金字塔『ゴドーを待ちながら』には、ストーリーの起伏はまったくありません。
舞台はとある道端、今日を生き延びるのに必死なふたりの浮浪者ヴラジーミルとエストラゴンが、とにかくその人がくれば救われると信じているゴドーなる人物を待ち続ける二日間が描かれるのですが、それは「今日も他の日々と同じような一日であるか、むしろ他の日々とまったく同じということはない一日なのです」(M・フーコー)。
2020年の今もまた、占星術界隈では年末から本格的な「風の時代」が始まるとか、何かと「新しい時代の到来」やそれによる「変革」ついて語られていますが、よしんばそれが結果的にはある程度認められることだったとしても、それは「ゴドー」のような劇的な形ではやってこないのではないでしょうか。それでも、「平々凡々たる今日」を生き続けなければいけない私たちはどうすればいいのか。その指針となる描写が第一幕の冒頭に出てきます。
「エストラゴンが道端に坐って、靴を片方、脱ごうとしている。ハアハア言いながら、夢中になって両手で引っ張る。力尽きてやめ、肩で息をつきながら休み、そしてまた始める。同じことの繰り返し。」
ここでヴラジーミルが出てきて、次のようなやり取りをするのです。
エストラゴン「(また諦めて)どうにもならん。」
ヴラジーミル「(がに股で、ぎくしゃっくと、小刻みな足どりで近づきながら)いや、そうかもしれん。(じっと立ち止まる)そんな考えに取りつかれちゃならんと思ってわたしは、長いこと自分に言い聞かせてきたんだ。ヴラジーミル、まあ考えてみろ、まだなにもかもやってみたわけじゃない。で……また戦い始めた。」
今期のおとめ座もまた、昨日とまったく同じではないが同じような一日である今日に、まだまだできることがあるんだと、ヴラジーミルのように自分に言い聞かせていきたいところです。
参考:サミュエル・ベケット、安堂伸也・高橋康也訳『ゴドーを待ちながら』(白水Uブックス)
-
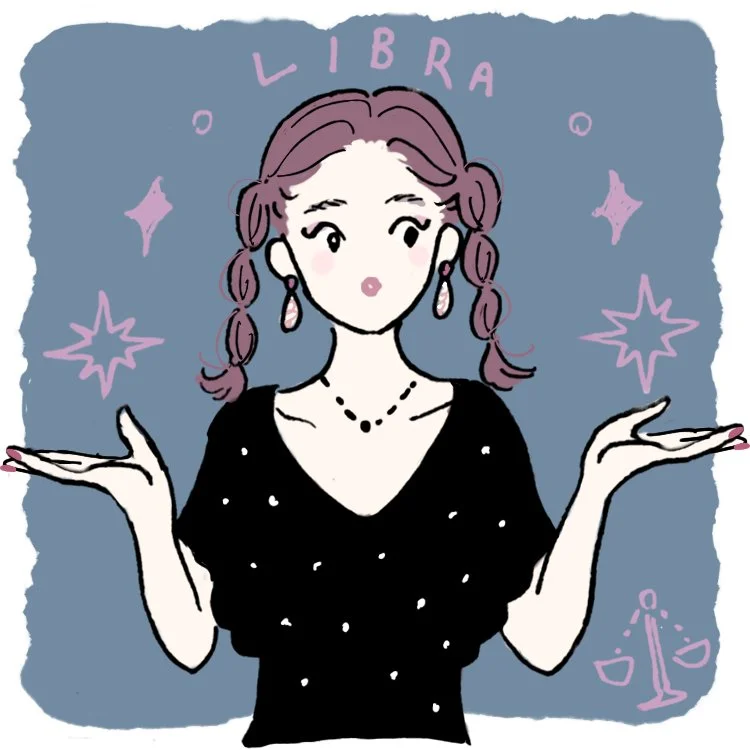
今期のてんびん座のキーワードは、「古い自分を捨てる」。
『椅子がこわい』という本は、ある日ベッドで目覚めた直後に耐えられないほどの激痛に襲われた著者・夏樹静子の腰痛放浪記です。
もちろん、すぐに病院の整形外科にかかったもののどうにもならず、鍼灸医、産婦人科、温泉療法、手かざし療法から祈祷まで、あらゆる手を打ったものの治らず、発病して2年後ほどたつと、ほとんど仕事ができなくなったばかりか、不治の病であると思うようになったそうです。
次第に絶望感めいたものが心に食い込んで、「死」に取りつかれていくのですが、それがいよいよ終盤に差し掛かったところで、著者自身でも信じられない結末を迎えていきます。
それは心療内科の平木英人医師からの「あなたの大部分を占めている夏樹静子の存在に病気の大もとの原因があると思います」という診断から始まりました。著者はすぐに「元気になれるなら夏樹を捨ててもいいくらいです」と答えましたが、平木医師は即座に「元気になれるなら、といった取引はありえない。無条件で夏樹をどうするか、結論が出たら私に話してください」と告げ、それでも煮え切らない著者に「夏樹静子を捨てなさい。葬式に出しなさい」と最終通告をしてきたのです。
バカバカしいものだと思った著者も、頑として譲らない平木医師に根負けして、ついにベストセラー作家である「夏樹静子」との決別を決意した、その直後。嘘のように激痛が消え、それから二度と腰痛は起こらなかったそうです。
言葉で書けば「心身症」の一言で終わってしまう話なのですが、物理的な痛みが自分の作り出したものに過ぎなかったという体験は、実際のところいまだに著者自身でさえ信じられないものであるはずです。
10月でてんびん座のシーズンが過ぎ去る今期のてんびん座もまた、著者のような仕方でとまではいかなくても、なんらかの仕方で古びれてすっかり硬直してしまった自分と決別することがテーマとなっていくでしょう。
参考:夏樹静子、『椅子が怖い』(文春文庫)
-

今期のさそり座のキーワードは、「“暗点”と“負性”へのまなざし」。
コロナの「以前、以後」の話が盛んにされたり、特集に組まれたりといった場面において、「以前の世界へ元通りになることへの希望」が語られることが、だんだん少なくなってきたように感じます。
そのこと自体がいいことなのか、悪いことなのかはいったん脇に置いて、以前に起きた「水俣病」という決定的な人災について、故郷の美しく豊かな海と命を奪われた人たちの思いを方言のままにつづった『苦界浄土』を書いた作家の石牟礼道子にあてて、詩人で社会活動家の谷川雁がつづった言葉をここで引用してみたいと思います。
「<水銀以前>の水俣を、あなたは聖化しました。幼女の眼で、漁師の声で、定住する勧進の足で。(中略)もはやそれはあなたの骨髄にしみとおっている性癖で、私にはしょっちゅう狐のかんざしごときものが見えて辟易しますけれども、趣味の問題はいたし方もない。それが<水俣病>の宣伝にある効果を与えたのも事実です。しかし患者を自然民と単純化し、負性のない精神を自動的にうみだす暮らしが破壊されたとする、あなたの告発の論理には<暗点>がありはしませんか。小世界であればあるほど、そこに渦巻く負性を消してしまえば錯誤が生じます。なぜなら負性の相克こそ、水俣病をめぐって沸騰したローカルな批評精神の唯一の光源ですから。」
確かに、石牟礼は化学工業メーカーによって有機水銀が垂れ流される以前の水俣を、幼い少女のまなざしや漁師などの声によって美しく描き、また狐のかんざしや妖怪など、自然と人間とが調和を保った仕方で暮らしていた頃のリアルを浮かび上がらせるのですが、それはノスタルジックな幻想であり、水銀が垂れ流される以前にもそこに住んでいる人間はたくさん問題を抱えていたのではないか。谷川は、そう言っているのです。
もちろん、手探りで現場の人々と話し合いながら作品をつくり、運動を展開していった石牟礼に明らかな非がある訳ではありません。批評的かつ怜悧な洞察の人である谷川と、具体的かつ凄まじい語り部である石牟礼とでは、単に方法が違うのでしょう。
ただ今期のさそり座にとっては、谷川のように、人々が見過ごしがちな論理の“暗点”や精神の“負性”に着目した上で、コロナ以後の人間の生き方を模索するほどの怜悧さを持つことは、大いに人生の指針になっていくはずです。
参考:『谷川雁コレクションⅡ 原点の幻視者』(日本経済評論社)
-

今期のいて座のキーワードは、「良質な食事と睡眠を」。
「ステイホーム」の大号令のもと、多くの人がその遵守と持続につとめているなか、ふとステイ(とどまる)ホーム(家庭、自分の居場所)と言ったって、自分はどこにとどまればいいのだろうか、とどまるべきホームとは何なのだろうか、という自問自答の渦巻きにはまった人もいたのではないでしょうか。
それで思い出されたのは、川端康成や三島由紀夫、池波正太郎など多くの文豪に愛され、今でも原稿執筆に使う作家が絶えず、また編集者によって缶詰にされている『山の上ホテル』です。
開業は1954年、創業者の吉田俊男は『文藝春秋』や『文學界』、『文藝』などの雑誌にみずからの手で広告コピーを綴っていたそうで、今でもロビーのメニューに遺されているそのうちの一つには「のんびりと/おうちの居間とおんなじ/こゝは/さういふ/気楽なところです」とあるそうです。
また「ごはん一食/一夜の安眠は明日の「いのち」を約束するもの/だからみんな言い知れぬ誇りを/この仕事に持っています」というものもあり、1970年に新館が建てられた際には、「健康を守るホテル」というキャッチコピーをつけたのだとか。
なるほど、食事や睡眠といったものが良質に保証されてこそ、「健康を守る」ことができるという訳ですが、こうした贅沢と質素の両方を併せ持ち、派手ではないけれど心のこもったサービスが提供されるからこそ、山の上ホテルが「ホテルであって、ホテルではないホテル」とされ、多くの人に愛された由縁なのかも知れません。
今期のいて座にとっても、自分の食事や睡眠を良質に保ってくれる場所があるのなら、それが自分の家ではなく、ホテルやバーや食堂や漫画喫茶、はたまたテントやダンボールハウスであったとしても、そここそが「ステイ」すべき「ホーム」なのだと思って、落ち着くべき日常を捉えなおしてみるといいでしょう。
参考:森裕治、『山の上ホテルの流儀―多くの作家に愛されてきた魅力とは』(河出書房新社)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「順応と縁を切れ」。
米中の対立がいよいよのっぴきならない状況へと進もうとしているなか、大統領選への注目が集まっているアメリカですが、いわゆる「アメリカ精神」を改めて理解していく上で、19世紀初めに生まれ、勃興期のアメリカを代表する思想家であったエマーソンほど重要な人物はそうはいないでしょう。
「アメリカ精神」を体現しているとされる論文『自己信頼』などを見ていくと、その率直さや物言いのストレートさに多くの日本人はいまだ面食らうはずですが、例えば彼は次のように述べます。
「いま生きていることだけが役に立ち、かつて生きたことは無用のものだ。落ち着いてしまうと、とたんに能力を失う。能力が生まれるのは、過去から新しい状態へ移る瞬間である。」
こうした生命的な働きを、おそらく、古いものを大切にする習慣が先祖の昔からDNAに染みついているようなところのある日本人にとって、過去のさまざまな価値を否定するものとしてひどく反発を覚え、ある種の怖れさえ感じるのではないでしょうか。
エマーソンは「おのれを外に求むるなかれ」を銘句にしていますが、ここでの「おのれ」とは、まさに「過去から新しい状態へ移る瞬間」の<今ここ>にある私のことであり、逆に言えば新しい状態への移行を迎えることができなければ、私は存在しないも同然なのです。
こうした精神の在り様は、ともすれば病的な強迫観念のようにもなりかねませんが、エマーソンはさらに論を展開し、「人間でありたい者は、誰でも、順応と縁を切れ」あるいは「君自身の精神の損なわれぬ本来の姿以外には神聖なものは何もない」と力強く説いていくあたりはさすがと言えます。
とはいえ、今期のやぎ座の人たちであれば、こうした止まったら死んでしまうマグロやサメのような「アメリカ精神」について、少なからず共感を覚え、場合によっては大いに糧にしていくことができるはずです。
参考:エマーソン、酒本雅之訳『エマソン論文集 上・下』(岩波文庫)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「瞬間と機縁」。
日常生活のなかで接する情報量が過剰となり、氾濫して、主体の輪郭が否応なしにあいまいになってきている現代について、すでに19世紀前半の時点で予見していた人物のひとりにキルケゴールがいます。彼は『現代の批判』という著書のなかで、
「現代は本質的に分別の時代、反省の時代、情熱のない時代であり、つかの間の感激に沸き立っても、やがて抜け目なく無感動の状態におさまってしまう時代である」
と述べていますが、まさにテレビやインターネットやYouTubeなど、一方通行的な視覚メディアに慣れ親しんでしまった現代社会を見通したような発言です。
キルケゴールはどこからこうした視点を持ち得ていたのか。彼の「時は過ぎ行く、人生はひとつの流れだ、などと人々は言う。私はそんなふうに見ることはできない。時は静止しており、私は共に静止している」といった記述からは、彼がふとした瞬間において永遠に触れられた時間こそ<満ちたる時>と見なしていたことが分かり、そうした“瞬間の意味”が忘れられていく時代の流れを感じたのでしょう。
そしてこの瞬間との関係で言及されていくのが、「機縁」であり、人と知り合う偶然の「きっかけ」です。彼が「人と人とのあいだで最高なのは、弟子は教師が自分自身を理解する機縁であり、教師は弟子が自分自身を理解する機縁である、ということだ」と述べるとき、そこには「無感動の状態におさまってしまう時代」である現代を克服していくためのヒントが示されているように思うのです。
今期のみずがめ座においても、例えば人と人との関わりである「機縁」を自他の自己発見に生かすべく、DMやLINEで簡単にメッセージが送れてしまうところを、あえて手紙を書くなどして、一瞬一瞬の価値を取り戻してみるといいかも知れません。
参考:キルケゴール、飯島宗享訳『キルケゴール著作集 11』(白水社)
-
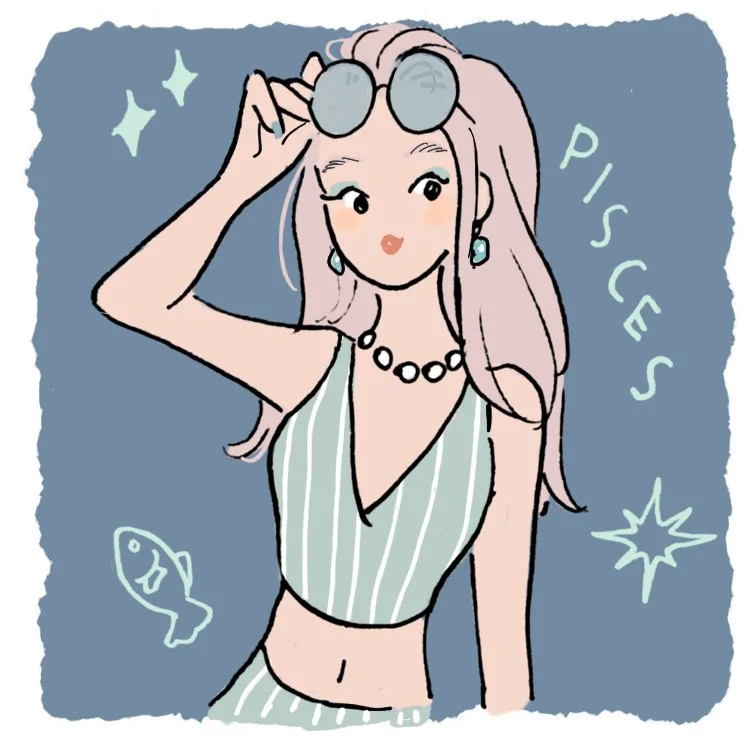
今期のうお座のキーワードは、「<笑い>のある宇宙」。
科学と宗教の対立と乖離がますます大きくなっているように感じる現代において、人々は(特に日本人は)科学を過剰に神聖視する一方で、この世界で人間が(あるいは自分が)置かれている不満足で途方に暮れる状況の「未解決性」にけりをつけてもらうことを期待して、自己啓発や占いなど、既存の宗教の代替物を求め続けているように感じます。
こうした現代の状況について、1947年に没した現代でも屈指の哲学者であるホワイトヘッドは『ホワイトヘッドの対話』という本において、<笑い>のない宗教は本当の宗教とは言えないことを力説した上で、こう述べています。
「儀式のもつ緊張は、それが不自然であるために、とても耐えがたいものになります。だから、ご存知のように、アテナイ人は悲劇のあとにいつもサチュロス(喜劇)をしたんです」
彼は<笑い>こそが生活全体のうちで生のバランスを回復する上で不可欠なものだと考えており、それを示すかのように、次のようなやりとりを披露してみませます。
ホワイトヘッドの「『自省録』を書いたマルクス・アウレリウスは書物を遺すよりローマ皇帝としての務めをよりよく果たすために時間を使うべきだった」という発言に、夫人は「それは哲学者としての縄張り意識のせいじゃない?」というツッコミを入れるのですが、それに対しホワイトヘッドは「そんなものはないよ、もし一生で何度も違った生を送れるのなら、自分は大きなデパートの社長になりたい」などと言って夫人を呆れさせるのです。
おそらく、こうしたユーモアこそ彼の構想した有機的でリズミカルな創造過程を重視するコスモロジー(宇宙論)の根底にあるものであり、そこから「生き生きしていない観念による教育は、無用であるだけではありません。なによりも有害なのです」といった社会批評も生まれてきたのではないでしょうか。
今期のうお座もまた、自身の直面している状況やおのれの人生の「未解決性」にけりをつけるにあたって、何よりもまず、どうしたら<笑い>を取り戻せるかを大切にしていきたいところです。
参考:森口兼二・橋口正夫訳『ホワイトヘッド著作集 9』(松籟社)
 【SUGARさんの12星座占い】<10/18~10/31>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<10/18~10/31>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「俳句的探究」。
今期のおひつじ座のキーワードは、「俳句的探究」。 今期のおうし座のキーワードは、「性からの解放」。
今期のおうし座のキーワードは、「性からの解放」。 今期のふたご座のキーワードは、「受け取る側の感受性」。 一時期、占いをするタコがメディアで取り上げられたことがありましたが、無脊椎動物の中でもタコを含めた頭足類はかなり大きな頭脳と多くの神経細胞を持っており、彼らは簡単な足し算や引き算はおろか、パズルを解いたり、人間に対して明瞭にコミュニケーションを取ろうとさえするのだとか(少なくともそう見える)。
今期のふたご座のキーワードは、「受け取る側の感受性」。 一時期、占いをするタコがメディアで取り上げられたことがありましたが、無脊椎動物の中でもタコを含めた頭足類はかなり大きな頭脳と多くの神経細胞を持っており、彼らは簡単な足し算や引き算はおろか、パズルを解いたり、人間に対して明瞭にコミュニケーションを取ろうとさえするのだとか(少なくともそう見える)。 今期のかに座のキーワードは、「ヒトの存在理由」。
今期のかに座のキーワードは、「ヒトの存在理由」。 今期のしし座のキーワードは、「人文主義者」。
今期のしし座のキーワードは、「人文主義者」。 今期のおとめ座のキーワードは、「まだ何もかもやってみた訳じゃない」。
今期のおとめ座のキーワードは、「まだ何もかもやってみた訳じゃない」。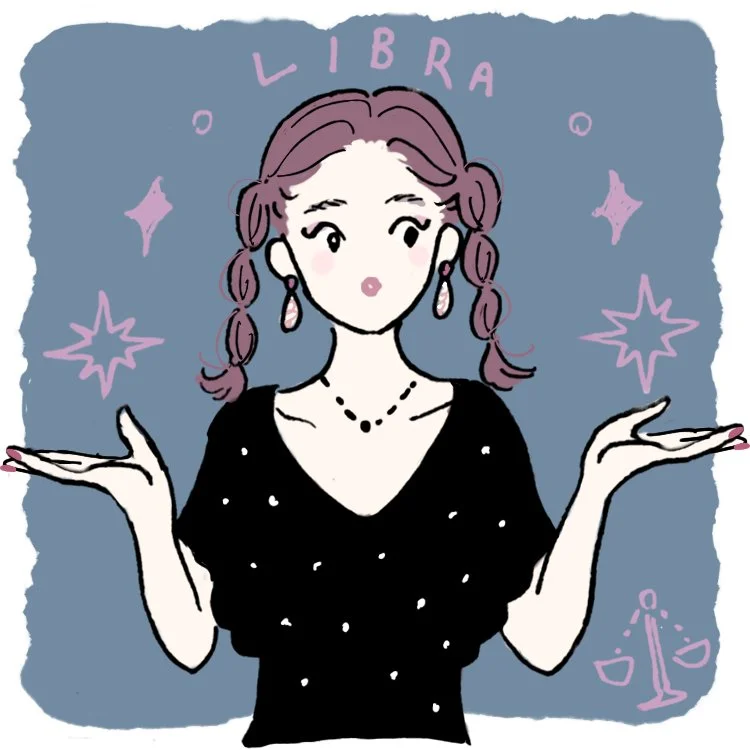 今期のてんびん座のキーワードは、「古い自分を捨てる」。
今期のてんびん座のキーワードは、「古い自分を捨てる」。 今期のさそり座のキーワードは、「“暗点”と“負性”へのまなざし」。 コロナの「以前、以後」の話が盛んにされたり、特集に組まれたりといった場面において、「以前の世界へ元通りになることへの希望」が語られることが、だんだん少なくなってきたように感じます。
今期のさそり座のキーワードは、「“暗点”と“負性”へのまなざし」。 コロナの「以前、以後」の話が盛んにされたり、特集に組まれたりといった場面において、「以前の世界へ元通りになることへの希望」が語られることが、だんだん少なくなってきたように感じます。 今期のいて座のキーワードは、「良質な食事と睡眠を」。 「ステイホーム」の大号令のもと、多くの人がその遵守と持続につとめているなか、ふとステイ(とどまる)ホーム(家庭、自分の居場所)と言ったって、自分はどこにとどまればいいのだろうか、とどまるべきホームとは何なのだろうか、という自問自答の渦巻きにはまった人もいたのではないでしょうか。
今期のいて座のキーワードは、「良質な食事と睡眠を」。 「ステイホーム」の大号令のもと、多くの人がその遵守と持続につとめているなか、ふとステイ(とどまる)ホーム(家庭、自分の居場所)と言ったって、自分はどこにとどまればいいのだろうか、とどまるべきホームとは何なのだろうか、という自問自答の渦巻きにはまった人もいたのではないでしょうか。 今期のやぎ座のキーワードは、「順応と縁を切れ」。 米中の対立がいよいよのっぴきならない状況へと進もうとしているなか、大統領選への注目が集まっているアメリカですが、いわゆる「アメリカ精神」を改めて理解していく上で、19世紀初めに生まれ、勃興期のアメリカを代表する思想家であったエマーソンほど重要な人物はそうはいないでしょう。
今期のやぎ座のキーワードは、「順応と縁を切れ」。 米中の対立がいよいよのっぴきならない状況へと進もうとしているなか、大統領選への注目が集まっているアメリカですが、いわゆる「アメリカ精神」を改めて理解していく上で、19世紀初めに生まれ、勃興期のアメリカを代表する思想家であったエマーソンほど重要な人物はそうはいないでしょう。 今期のみずがめ座のキーワードは、「瞬間と機縁」。
今期のみずがめ座のキーワードは、「瞬間と機縁」。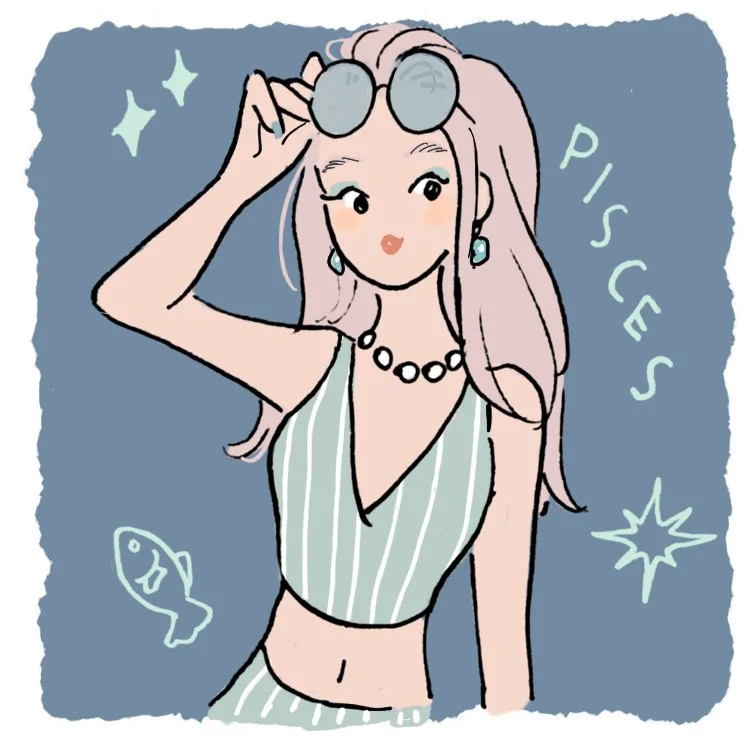 今期のうお座のキーワードは、「<笑い>のある宇宙」。
今期のうお座のキーワードは、「<笑い>のある宇宙」。










































































