-

【SUGARさんの12星座占い】<11/1~11/14>の12星座全体の運勢は?
「風通しのよい真実味」
11月7日の「立冬」を過ぎると、木枯らしが吹き始め、日に日に冬めいてくるようになります。
まだまだ晩秋の装いが色濃く残っている時期でもありますが、「雪中花(せっちゅうか)」の異名をもち、雪の中でも香り高い水仙が咲き始めるのもこの頃。そんな中、11月15日に迎えていく今回のさそり座新月のテーマは「真実を告げること」。
それは世間一般や他者のリアリティーへ順応することや黙認することを拒んで、自分本来の波長にとどまり、自分のことを正確に認識してもらうよう、相手や周囲に要求していくこと。
平安時代末期に中国より渡来した水仙は、室町時代になって一休禅師が『狂雲集』で「美人ノ陰ニ水仙花ノ香有リ」とエロティックなもののたとえに詠んだことで知られるようになりましたが、和歌にはほとんど詠まれていません。それは都からはるかに遠い辺鄙な海辺や岬などにひっそりと咲いていたから。
しかしこれからの時代、このように水仙に例えて真実を語る人たちの存在は、ますます隠しきれないものとなり、互いにゆるやかに連帯しては離れ、つながっては適切な距離をとり、といったことを繰り返していくでしょう。そして今回の新月は、多くの人にとって、そうした風通しのよい関係性へと近づいていくための大切な一歩となっていくはずです。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「怖れと不安と驚嘆と」。
今日、地球環境の保全やエコロジーへの真剣な取り組みの必要性が声高に叫ばれていますが、一方で、ゲーテ流の自然研究やその方法の重要さについてはほとんど知られていないように思います。
ゲーテの『自然科学論集』はもとより、『ファウスト』やさまざまな詩篇などに触れたことのある人なら、ゲーテによってとらえられた自然が、五感によって観察された表面的事実だけでなく、生命の本質である創造と破壊など、活動する生命の深奥にあるものを象徴的に表したものであるということは、容易に見て取れるのではないでしょうか。
例えば、そうした生命活動の本質としての「根源現象」について、『箴言と省察』の中に次のような断章があります。
「根源現象が私たちの感覚に対して裸のままで出現すると、私たちは一種の怖れを感じ、不安にさえ襲われる」
これは別の断章内にある「活動的な無知ほど恐ろしいものはない」という一句と突き合わせると、よりビビッドに現代の私たちに響いてくるように思います。
ゲーテによれば、「感覚的な人たち」が驚嘆のなかに逃げ込むのに対し、活動的な理解力の持ち主は、もっとも高貴なものをもっとも卑俗なものと結びつけて、わかったと思おうとする、と。ただいずれにしても、根源現象はわれわれ人間には直視しがたいのだとゲーテは述べている訳ですが、そういう現実を踏まえた上で、次のようにもアドバイスしています。
「人間は、不可解なものも理解できるという信念を持ち続けなければならない。さもないと、探究をしなくなるだろう」
これは今期のおひつじ座にとってもよき指針となるでしょう。その意味で、時には「本当に何もわからないで生きているのだ」と言ってみるのも悪くないはず。
参考:岩崎英二郎・関楠生訳『ゲーテ全集 13』(潮出版社)
-

今期のおうし座のキーワードは、「友愛」。
フランスの代表的なモラリスト(人間探究者)であり、不朽の名著『エセー』の著者であるモンテーニュは、実際には16世紀ルネサンス期の乱世に生きた、成り上がりの武人貴族でもあり、地方領主でした。
フランス全土で内乱内戦が続き、権力中枢が目まぐるしく移り変わっていた当時は、裏切りや寝返り、謀略、強迫、暗殺、闇討ちだまし討ちなど何でもありの世相であり、モンテーニュはそんな群雄割拠の時代を隠遁者として生き抜いた人物だったのです。
そんな疑心暗鬼になって当たり前の世界で、彼はあえて友人との関係の在り方を説き、その中で次のように述べていました。
「真の友愛においては、私は友を自分の方に引き寄せるよりも、むしろ自分を友に与える」
「単に私よりも彼自身の方が益するようにと私は願う。彼がもっぱら彼自身によくしているときこそ、彼はもっとも私によくしているのである。」
彼がここまで言えた背景にあったのは、何らかの機縁や便宜によって結ばれた互いに利害の一致する相手との交友ではなく、若くして亡くなった心の友ラ・ボエシとの、短くはあったが緊密な交友でした。
二人の結びつきの深さに関しては、当のモンテーニュでさえ「それは彼であったから」であり「私が私であったから」としか答えようがありませんでしたが、その臨終の場面で遺したラ・ボエシの「別になんら不快な感じはしない」し「それほど悪いものじゃない」といった言葉に、モンテーニュは深い感銘を受け、その意味するところをその後の人生を通じて考え続けていったのでしょう。
「自分を友に与える」とは恐らくそうした意味の上で書かれた言葉であり、モンテーニュにとってラ・ボエシの存在は、一番の理解者であったと同時に、突きつけられた一つの謎でもあったのかも知れません。そしてそれは今期のおうし座においても、程度の差こそあれ、通底してくる感覚があるはずです。
参考:モンテーニュ、原二郎訳『エセー(全六冊)』(岩波文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「詩人の作法」。
時間の使い方をめぐって、“成功する“ために自己啓発的なノウハウが語られた書籍や記事は数多いですが、フランスの哲学者ガストン・バシュラールが『詩的瞬間と形而上学的瞬間』というエッセイにおいて述べている時間の使い方は、「真実を告げるための時間の使い方」について触れている点で明らかに異彩を放っています。
いわく、「自分に固有の時間を、他人の時間に帰属させないことに慣れること。自分に固有の時間を、事物の時間に帰属させないことに慣れること」であると。
前者はなんとなく惰性的に続いてしまう社会的な枠組みや体裁の持続を破るための習慣のことであり、後者はなんとなく惰性的に続いてしまう現象的な枠組みや体裁の持続を破るための習慣のこと。
もちろん、前者だけでも難しいことであり、後者も心がけるとなるともっと難しいでしょう。ですが、バシュラールはさらに続けてこう言うのです。
「自分に固有の時間を、-これは難しいわざだが―生の時間に帰属させないことに慣れること―心臓が鼓動しているかどうか、喜びが萌しているかどうかといったことをもはや知らないこと―すなわち持続の生の枠を破ること。」
すなわち、みずからが生きている上で自明(あって当たり前)とされている一切の前提や原則を拒否することができたときに初めて、時間の平板な水平性はすべて忽然と消え失せて、そこにつながれていた存在を解放させることができるのであり、そこでは「時間はもはや流れるのではなく、噴きあげる」。
つまり、そうした垂直的時間の立ち現れにおいてこそ詩的瞬間は築かれるのであって、詩人はそこで無益な生のすべてをおろして身を軽くしていくのだと。
今期のふたご座もまた、本当に自分が生きて存在していることを遅ればせながら感じていくためにも、ときどき平らな時間への縛りつけをほどく瞬間が訪れることをみずからに促していきたいところです。
参考:ガストン・バシュラール、渋沢孝輔訳『夢見る権利』(ちくま学芸文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「小さな鐘」。
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の主人公で貧しい少年ジョバンニが敬愛する人物として、カンパネルラという名前の少年が出てきます。彼は溺れた友人を救うために死んでしまうのですが、ジョバンニは彼とともに銀河鉄道に乗って宇宙旅行をしていくのです。
ここで思い起こされるのは、ルネサンス期に生きた同じ名前の哲学僧トマーゾ・カンパネッラです。彼は学生時代にはガリレオと交友があったそうですが、何と言っても近世ユートピア思想の先駆である『太陽の都』(1623)の作者として知られています。
カンパネッラは、地球も星も宇宙もすべて感覚を有していると見なすとともに、そのなかに住む人間がいかに卑小であるかを説き、人間の慢心を戒めているのですが、例えば「自惚れに対する素晴らしき発見」という詩には次のようにあります。
「自惚れは信じやすき人間をして、万物も星もそれらがわれらより強く美しきものにも拘わらず、感覚も愛も有せざるものと信じさせ、ただわれらのためにのみ回転すと信じさせり」
「さらに、われら以外のものはすべて野蛮で無知にして、神はわれらのみを眺め給うと信じさせ、かつまた、神は僧職にあるもののみを救うと信じさせしめり。かくして、各人はただ自己のみを愛するに至れり」
宮沢賢治は熱心な日蓮宗徒でもありましたから、こうしたカンパネッラのきびしい自己批判にも少なからず感化されたのでしょう。なお、カンパネッラとはイタリア語で「小さな鐘」を意味する言葉ですが、その慎ましい響きも含めて、作者の宮沢賢治もまた、実際にカンパネッラという名の人物に敬愛の念を抱いていたのかも知れません。
今期のかに座もまた、宮沢賢治やカンパネッラのような宇宙感覚や生命感覚のなかに、何かしら響いてくるものがあるはずです。 例えば、自分を愛するということが、そのまま同時に、誰かと共に在り、響きあっていくということでもあるような。そんな在り方に開かれていきたいところです。
参考:カンパネッラ、坂本鉄男訳『太陽の都・詩篇』(現代思潮新社)
-

今期のしし座のキーワードは、「積み重ねの不思議」。
日本史上でも指折りの哲学者として世界的にも評価されている西田幾多郎は、「絶対矛盾的自己同一」などの言葉遣いの難解さのためか、国内ではその思想的可能性はいまだ十分に評価が定まっていませんが、彼が遺した書簡に目を向けてみると、思想だけでなくその人柄の奥深さにも気付かされます。
西田は50歳で長男を、55歳で妻を亡くした他、若くして亡くなった娘を何人ももつなど、家族に多くの病人を抱えて長いあいだ苦労してきた人でしたが、学生時代からの終生の友であった山本良吉へ57歳の時に書いた手紙の中で、歳月の積み重ねの不思議について次のように述べています。
「人間といふものは時の上にあるのだ。過去といふものがあつて私といふものがあるのだ。過去が現存してゐるといふ事が又その人の未来を構成してゐるのだ」
彼は続けて、それを特に妻が7,8年前に倒れた時に深く感じたと言い、「自分の過去といふものを構成してゐた重要な要素が一時なくなると共に自分の未来といふものもなくなつた様に思はれた」という切実な感想を記しています。
明治維新や文明開化の号令からの流れと軌を一にするべく、当時(あるいは今でもなお)“過去に縛られず未来に開かれて生きる”ことこそ自らの自由意志によって人生を切り開く、あるべき近代人の姿なのだと考えられていたことを思えば、西田という人が時代的潮流に惑わされることなく、ただひたすら徹底的におのれの人生や体験をもとに思索を深めていったのだということが改めてよく分かるのではないでしょうか。
今期のしし座もまた、そんな西田のようにどうしたら世間に早く広く評価されるかではなく、まず自分にとっての真実を何度も何度も掘り下げていくことを大事にしていきたいところです。
参考:『西田幾多郎全集 18』(岩波書店)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「意識的な催眠」。
アミエルといっても今でもほとんど知られていないと思いますが、19世紀を生きたスイス人の哲学者で死後に30年数年にわたって書き続けられた『内面の日記』によって世界的に有名になった人物です。
彼は少年の頃に孤児になり、生涯にわたり独身でしたが、ひたすら孤独な自己の慰めに、自身の苦悩、苦しみ、悲しみ、寂しさを、毎日毎日ノートに書き続けました。興味深いのは、その膨大な日記のある個所で、アミエルが日記への批判を行っている点です。
「日記は怠惰の枕である。すべての問題を論じないで済むし、同じことを繰り返してもよく、内的生活のあらゆる気まぐれや迂路を歩むことも、何一つ目的を立てずにいることもできる」
「一時の痛み止め、散らし薬、切り抜け策でしかない」
しかし彼はそれでも日記を書き続けるなかで、こうした自己批判をも乗り越え、日記を通じてみずからの心と行を鎮まる境地をも経験していきます。
「生きるとは日に日に治り新たになることであり、また、再び自己を見出し取り返すことである。日記は、孤独な人の打ち明け相手、慰安者、医者である」
「この毎日の独白は、祈りの一形式、精神とその原理の談話、神との対話である。これによってわれわれは、面目をすべて取り戻し、混沌から明晰へ、動揺から平静へ、散漫から自己統一へ、偶有性から恒久性へ、特殊性から調和へと立ち返るのである」
こうしたアミエルの記述を読んでいると、日記とは意識的な睡眠のようなもので、そうしたプロセスを経てはじめて私たちは宇宙的な秩序へと回帰していけるのだという気がしてきます。
今期のおとめ座もまた、そうした何でもない地味な作業を毎日毎日続けていくことの大切さに改めて思い至っていくことになるかもしれません。
参考:アミエル、河野與一訳『アミエルの日記』(岩波文庫)
-
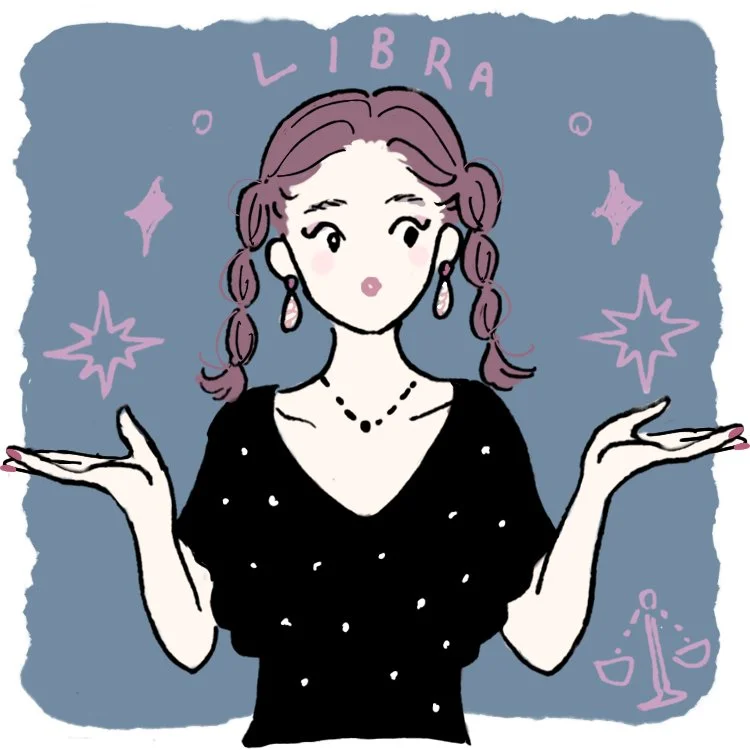
今期のてんびん座のキーワードは、「自己の半身の立て直し」。
地球環境問題は誰もが否定できない重要課題ではあるものの、日本では特にきれいごとやお題目とされやすく、具体的な自分の日常やふるさとの風景が一変する危機が間に迫らないとなかなか本気になって目を向ける人は少ないように思います。
そしてこれは世界全体や日本経済と自分の家庭のふところ事情に置き換えても、同じことが言えるのではないでしょうか。
「経済」と訳された「エコノミー」の語源はギリシャ語の「オイコノミア」で、これは「オイコス」(Oikos)と「ノモイ」(Nemu)という二つから出来ていて、「ノモイ」は法律やルール、規則、「オイコス」には主に家、家計、共同体という3つの意味があったそう。
つまり、どこにどうやって住まうか、何を出し入れしてそれを成り立たせるか、どんな人たちと関わるか、といった家庭のルールを決めてそれを運用していくことが、本来の意味での経済活動なんですね。
スペインの思想家オルテガは、『ドン・キホーテをめぐる省察』の中で、「人びとはつねに遠い彼方の何かのために戦い、通りすがりのかぐわしいスミレの花を踏みつぶして」いるのだと分析した上で、「私とは、私と私の環境である。私がもし私の環境を救わなければ、私自身は救われないことになる」と述べましたが、今まさに自身の経済や環境を踏みつけにしている人のなんと多いことか。
その意味で、今期のてんびん座は、自身の経済や環境を改めて救っていくための計画を立て直していくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:オルテガ、長南実訳『オツテガ著作集 1』(白水社)
-

今期のさそり座のキーワードは、「心身一如」。
仏教哲学者の鈴木大拙にはある有名なエピソードがあります。欧米で禅の思想を広める際、聴衆の前で両手で柏手をうち、その音が右の手の音か左の手の音かをたずねて煙に巻いたというものです。
これは大拙が日本人のこころを「霊性」という言葉で捉えたことと深く関係しており、地に足のついていない精神主義に陥らず、なかなか言語化しにくい心身一如(いちにょ)の在り様を巧みに指しているように思います。
彼は無心ということの真の意味も、宗教的なものの神髄も、そうした無意識を突き破ったところにある「云ふに云われぬ不思議」に求めていきましたが、返す刀で智(理性)の世界に収まり切らないその外側に慈悲の世界があって取り囲んでいることをすっかり忘れてしまった現代人を、『人間本来の自由と創造性をのばさう』という随筆の中で、次のように批判してみせました。
「智は悲(慈悲)によつてその力をもつのだといふことに気付かなくてはならぬ。本当の自由はここから生まれて出る」
「少し考へてみて、今日の世界に悲―大悲―があるかどうか、見てほしいものである。お互ひに猜疑の雲につつまれてゐては、明るい光明が見られぬにきまつてゐるではないか」
こうした見地から最初に述べたパフォーマンスを振り返ると、それはまるで合理的理性の作り出した「猜疑の雲」を晴らすべく相応の覚悟を抱いてとり行われた行為であったことが分かってくるはずです。
今期のさそり座もまた、もし自身を通じて少しでも世界を明るくしていきたいのならば、頭だけでそれを考えたり伝えていこうとするのではなく、悲(慈悲)を込めた行為を通して指し示していくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:『鈴木大拙全集 20』(岩波書店)
-

今期のいて座のキーワードは、「大きな表明と小さな断念」。
ニーチェは時代が現代へと移っていく20世紀の前夜に「神は死んだ」と言うことで、あらゆる価値の相対化とニヒリズムの到来を端的に示しましたが、そうした大きな真理の表明を行っていく基礎の部分には、細部にわたって人間をつぶさに観察していく眼の動きがありました。
例えば、『人間的な、あまりにも人間的な』の「もっとも必要な体操」という断章には、次のように述べられています。
「小さな自制心が欠如すると、大きな自制心の能力も潰えてしまう」のであり、「毎日少なくとも一回、なにか小さなことを断念しなければ、毎日は下手に使われ、翌日も駄目になるおそれがある」ということをよく踏まえた上で、最後に「自分自身の支配者となるよろこびを保持したければ、この体操を欠かせない」と結んでいます。
ニーチェのように大胆不敵で一面において極めて奔放な人が、これほどまでに日々の小さな自制心の行使を大切にし、小さな断念のすすめをしていることに驚く人も多いのではないでしょうか。
彼は別の断章の中で、「自分の不名誉になるような考えを最初に大胆に表明することは、自立への第一歩になる」とも述べていますが、おそらくそうして小さな断念を積み重ねていくことこそ、彼なりの自己実現法であり、大きな大胆さを呼び込むための儀式に他ならなかったのだと思います。
今期のいて座もまた、真理が悪態をついてあなたの元を離れていってしまうことのないように、まずは日常にいくらでも転がっているみずからの不名誉や自己欺瞞をよく観察し、一挙にそれをどうにかしようとするのではなく、ひとつひとつ小さく区切って断念していくことを心がけていきたいところです。
参考:ニーチェ、池尾健一・中島義生訳『ニーチェ全集 5・6』(ちくま学芸文庫)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「アクロバット的転換」。
歴史の大転換期には、後から振り返れば当然に見えても、当時の時代状況に即して考えてみると、さながらアクロバット的としか言いようのない思想潮流の切り替えがあるものです。
例えば、資本主義の精神の源流とは何であったのかを振り返っていくとき、切り替えの要点は、それまで神から与えられた使命、天職だけを意味してきたドイツ語の「ベルーフ(Beruf)」という言葉が、現世の職業労働にも当てはめられるようになったことに求められます。
首謀者はマルティン・ルター。彼が、旧約聖書をドイツ語に翻訳する際に、そういう意味を与えたのが始まりであり、それ以降、営利の追求への罪悪感は決定的に薄れていったのだと言います。
しかし、ルターはなぜそのようなことを成し得たのか。E・H・エリクソンによる『青年ルター』を読むと、その激情的でドラマチックな生涯が間近に迫って展開されてくるようですが、特にここで注目したいのは、次のような場面。
21歳の折、修道院に入ったマルティンは聖歌隊において突然発作を起こして倒れ、「それは私ではない」と叫んだという出来事が起こりました。著者はこれについて、「おまえは悪霊にとり憑かれているのだ」と言って彼の修道院入りを罵倒した父親に無意識に答えたものであり、彼の願望は「神に直接、何の困惑もなしに語る」ことだったのだ、と。
つまり、マルティンは実の父親と天の父という二人の“父親”をめぐってアイデンティティの危機に直面していたのであり、その葛藤を創造的に乗り越えた成果が、結果的に時代や国をこえて近代的な労働観念として受け継がれていったという訳です。
今期のやぎ座もまた、仕事や職業観をめぐる歴史的な転換を促す潮流と個人的な問題とが同期しつつあるように思います。その意味で、どこまで自分事として“歴史の現在”を捉えていくことができるかが、少なからず問われていくでしょう。
参考:E・H・エリクソン、西平直訳『青年ルター 1・2』(みすず書房)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「二つの天職」。
日本人に宗教はないと言われるようになって久しいですが、その問題に対して既に100年近くも前に明確に否を突きつけていた人に明治・大正のキリスト者・内村鑑三がいます。
内村は、世界のなかで孤立化を深めていく当時の日本の行く末を憂いつつ、『日本の天職』(1924)の中で「日本人は特別にいかなる民であるか。私は答えて言う、宗教の民であると。かく言いて、私は私の田に水を引き入れんとするのではない」と書いてみせたのです。
日本にはキリスト教の更新を担って世界に尽くす使命があると確信し、日本人を「宗教の民である」と断言した根拠に関して、現代の物質文明は日本にとって一時的な現象であり、その時代は今や終ろうとしており、その間際において、日本人は自分たちがイギリス人のような商売人でも、アメリカ人のような物質に憧れる民でもないことに目覚めつつあるのだと述べています。
無論、歴史を振り返れば日本はその後、内村の言葉に反する方向へと突き進んでいった訳ですが、丸一世紀が経とうとしている21世紀の日本の行く末やその「天職」について考えてみるとき、内村の言葉にはハッとさせる何かがあるように思います。
内村は日本がその使命を実現するのは「亡国とまでは至らざるも、その第一等国たるの地位をなげうちての後」になろうと述べており、この言葉にまさに日本という国の現在の姿を見る人は多いはずです。
今期のみずがめ座もまた、内村ほどではないにせよ、自分の天職(使命)ということと自分の属する共同体や国家の天職とをどこかでつなげて考えてみる中で、今自分が何をするべきか、どこへ向かっていくべきかということを見直してみるといいでしょう。
参考:松沢弘陽編『日本の名著38 内村鑑三』(中央公論新社)
-
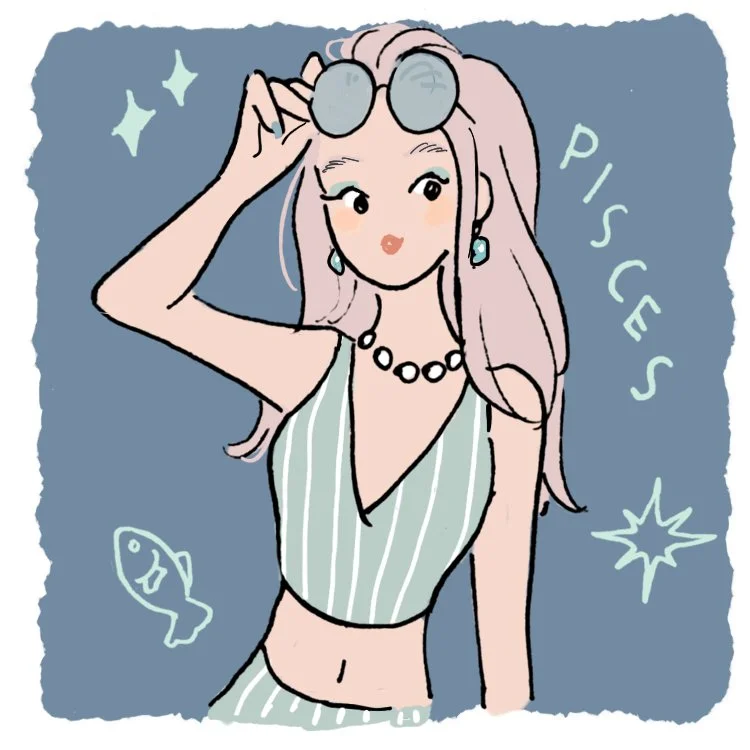
今期のうお座のキーワードは、「弱いものに従う」。
近年の欧米では、人間をキリスト教―特にプロテスタントの考えるような“強いもの”ではなく、“弱いもの”と見なして、弱者の権利を助けるイスラム教の考え方に共感を持つ人々が増えているという話を聞いたことがあります。
こうしたイスラム教の考え方への見直しは、老人の人口比率が増大している他、障害者だけでなく社会にさまざまな「弱者」が再発見されている現代日本においてもやはり大変重要なトピックでしょう。
例えば、ケアということを「支える」という視点からだけではなく、「力をもらう」という視点からも考えていく上で、イスラム教の開祖である預言者マホメットの言行録『ハディース』の一節である「力強いとは、相手を倒すことではない。それは、怒って当然というときに心を自制する力を持っているということである」という言葉は大いにヒントを与えてくれるように思います。
怒って当然。つまり、相手の理不尽な権利主張を無視して、自分の主張や要望をそのまま無理やり押し通しても構わないだろうという判断に「必然性」が感じられる時というのは、必ずその背後に「強いものに従うべき」という判断の後押しが存在します。
しかし、必然であるということは、そうしかしようがないという意味で、そこに「自由」の余地はありません。だとすれば、それを裏返して、「弱いものに従う」という判断にこそ、「自由」があると言えるのではないでしょうか。
「心を自制」して、あえて自分を空白にする。その上で相手の存在の内側へと自分を巻き込ませてみること。結果として、相手からこちらの空白へと何かが流れ込んでくる。それが「力をもらう」ケアの在り方といえます。
今期のうお座もまた、自分のペースに相手を巻き込んだり、必然性の文脈をつくろって従わせるのではなく、あえて自分を差し出し、巻き込まれてみることで、自由になっていく。そんなケアの倫理へと開かれてみるのはどうでしょうか。
参考:黒田寿郎訳『40のハディース』(イスラミックセンター・ジャパン)
 【SUGARさんの12星座占い】<11/1~11/14>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<11/1~11/14>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「怖れと不安と驚嘆と」。 今日、地球環境の保全やエコロジーへの真剣な取り組みの必要性が声高に叫ばれていますが、一方で、ゲーテ流の自然研究やその方法の重要さについてはほとんど知られていないように思います。
今期のおひつじ座のキーワードは、「怖れと不安と驚嘆と」。 今日、地球環境の保全やエコロジーへの真剣な取り組みの必要性が声高に叫ばれていますが、一方で、ゲーテ流の自然研究やその方法の重要さについてはほとんど知られていないように思います。 今期のおうし座のキーワードは、「友愛」。 フランスの代表的なモラリスト(人間探究者)であり、不朽の名著『エセー』の著者であるモンテーニュは、実際には16世紀ルネサンス期の乱世に生きた、成り上がりの武人貴族でもあり、地方領主でした。
今期のおうし座のキーワードは、「友愛」。 フランスの代表的なモラリスト(人間探究者)であり、不朽の名著『エセー』の著者であるモンテーニュは、実際には16世紀ルネサンス期の乱世に生きた、成り上がりの武人貴族でもあり、地方領主でした。 今期のふたご座のキーワードは、「詩人の作法」。 時間の使い方をめぐって、“成功する“ために自己啓発的なノウハウが語られた書籍や記事は数多いですが、フランスの哲学者ガストン・バシュラールが『詩的瞬間と形而上学的瞬間』というエッセイにおいて述べている時間の使い方は、「真実を告げるための時間の使い方」について触れている点で明らかに異彩を放っています。
今期のふたご座のキーワードは、「詩人の作法」。 時間の使い方をめぐって、“成功する“ために自己啓発的なノウハウが語られた書籍や記事は数多いですが、フランスの哲学者ガストン・バシュラールが『詩的瞬間と形而上学的瞬間』というエッセイにおいて述べている時間の使い方は、「真実を告げるための時間の使い方」について触れている点で明らかに異彩を放っています。 今期のかに座のキーワードは、「小さな鐘」。 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の主人公で貧しい少年ジョバンニが敬愛する人物として、カンパネルラという名前の少年が出てきます。彼は溺れた友人を救うために死んでしまうのですが、ジョバンニは彼とともに銀河鉄道に乗って宇宙旅行をしていくのです。
今期のかに座のキーワードは、「小さな鐘」。 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の主人公で貧しい少年ジョバンニが敬愛する人物として、カンパネルラという名前の少年が出てきます。彼は溺れた友人を救うために死んでしまうのですが、ジョバンニは彼とともに銀河鉄道に乗って宇宙旅行をしていくのです。 今期のしし座のキーワードは、「積み重ねの不思議」。 日本史上でも指折りの哲学者として世界的にも評価されている西田幾多郎は、「絶対矛盾的自己同一」などの言葉遣いの難解さのためか、国内ではその思想的可能性はいまだ十分に評価が定まっていませんが、彼が遺した書簡に目を向けてみると、思想だけでなくその人柄の奥深さにも気付かされます。
今期のしし座のキーワードは、「積み重ねの不思議」。 日本史上でも指折りの哲学者として世界的にも評価されている西田幾多郎は、「絶対矛盾的自己同一」などの言葉遣いの難解さのためか、国内ではその思想的可能性はいまだ十分に評価が定まっていませんが、彼が遺した書簡に目を向けてみると、思想だけでなくその人柄の奥深さにも気付かされます。 今期のおとめ座のキーワードは、「意識的な催眠」。 アミエルといっても今でもほとんど知られていないと思いますが、19世紀を生きたスイス人の哲学者で死後に30年数年にわたって書き続けられた『内面の日記』によって世界的に有名になった人物です。
今期のおとめ座のキーワードは、「意識的な催眠」。 アミエルといっても今でもほとんど知られていないと思いますが、19世紀を生きたスイス人の哲学者で死後に30年数年にわたって書き続けられた『内面の日記』によって世界的に有名になった人物です。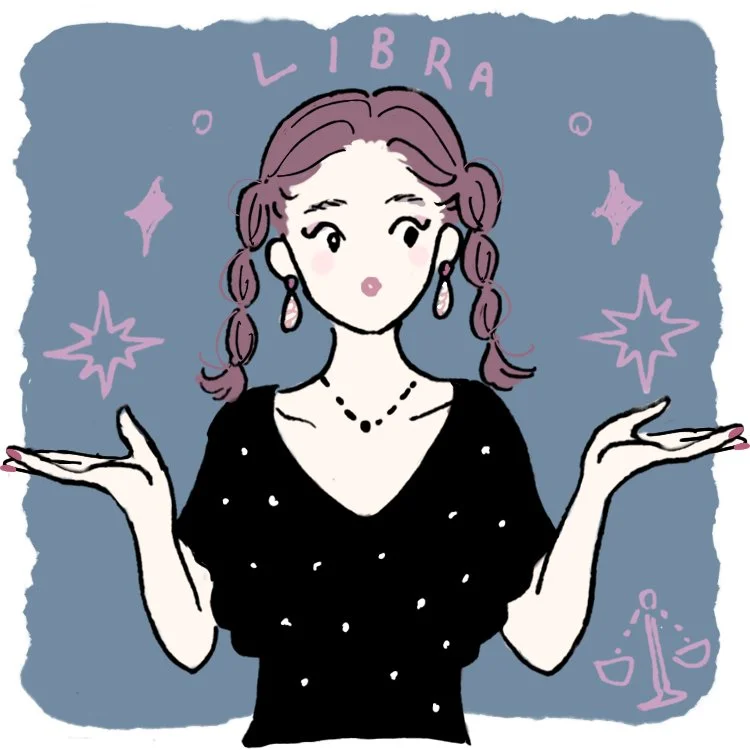 今期のてんびん座のキーワードは、「自己の半身の立て直し」。 地球環境問題は誰もが否定できない重要課題ではあるものの、日本では特にきれいごとやお題目とされやすく、具体的な自分の日常やふるさとの風景が一変する危機が間に迫らないとなかなか本気になって目を向ける人は少ないように思います。
今期のてんびん座のキーワードは、「自己の半身の立て直し」。 地球環境問題は誰もが否定できない重要課題ではあるものの、日本では特にきれいごとやお題目とされやすく、具体的な自分の日常やふるさとの風景が一変する危機が間に迫らないとなかなか本気になって目を向ける人は少ないように思います。 今期のさそり座のキーワードは、「心身一如」。 仏教哲学者の鈴木大拙にはある有名なエピソードがあります。欧米で禅の思想を広める際、聴衆の前で両手で柏手をうち、その音が右の手の音か左の手の音かをたずねて煙に巻いたというものです。
今期のさそり座のキーワードは、「心身一如」。 仏教哲学者の鈴木大拙にはある有名なエピソードがあります。欧米で禅の思想を広める際、聴衆の前で両手で柏手をうち、その音が右の手の音か左の手の音かをたずねて煙に巻いたというものです。 今期のいて座のキーワードは、「大きな表明と小さな断念」。 ニーチェは時代が現代へと移っていく20世紀の前夜に「神は死んだ」と言うことで、あらゆる価値の相対化とニヒリズムの到来を端的に示しましたが、そうした大きな真理の表明を行っていく基礎の部分には、細部にわたって人間をつぶさに観察していく眼の動きがありました。
今期のいて座のキーワードは、「大きな表明と小さな断念」。 ニーチェは時代が現代へと移っていく20世紀の前夜に「神は死んだ」と言うことで、あらゆる価値の相対化とニヒリズムの到来を端的に示しましたが、そうした大きな真理の表明を行っていく基礎の部分には、細部にわたって人間をつぶさに観察していく眼の動きがありました。 今期のやぎ座のキーワードは、「アクロバット的転換」。 歴史の大転換期には、後から振り返れば当然に見えても、当時の時代状況に即して考えてみると、さながらアクロバット的としか言いようのない思想潮流の切り替えがあるものです。
今期のやぎ座のキーワードは、「アクロバット的転換」。 歴史の大転換期には、後から振り返れば当然に見えても、当時の時代状況に即して考えてみると、さながらアクロバット的としか言いようのない思想潮流の切り替えがあるものです。 今期のみずがめ座のキーワードは、「二つの天職」。 日本人に宗教はないと言われるようになって久しいですが、その問題に対して既に100年近くも前に明確に否を突きつけていた人に明治・大正のキリスト者・内村鑑三がいます。
今期のみずがめ座のキーワードは、「二つの天職」。 日本人に宗教はないと言われるようになって久しいですが、その問題に対して既に100年近くも前に明確に否を突きつけていた人に明治・大正のキリスト者・内村鑑三がいます。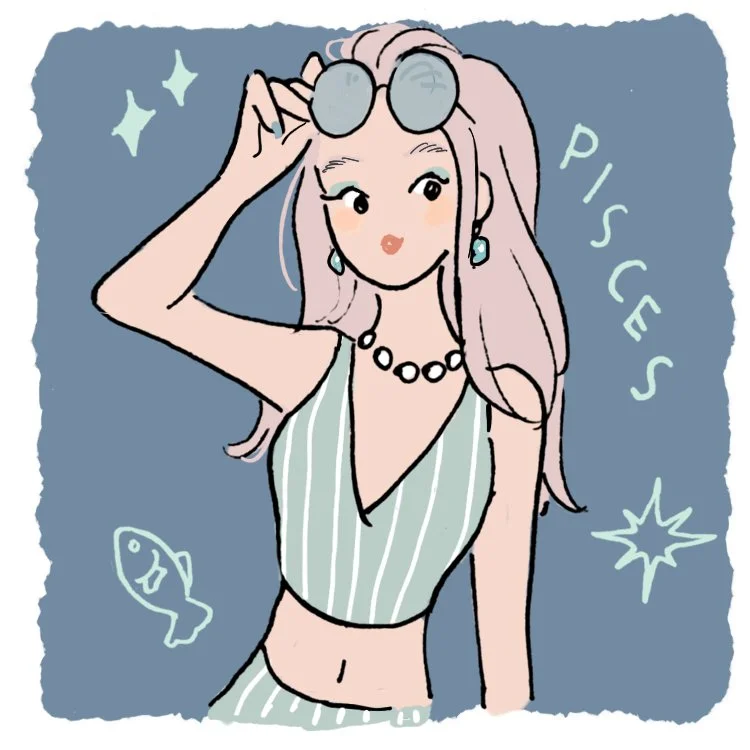 今期のうお座のキーワードは、「弱いものに従う」。 近年の欧米では、人間をキリスト教―特にプロテスタントの考えるような“強いもの”ではなく、“弱いもの”と見なして、弱者の権利を助けるイスラム教の考え方に共感を持つ人々が増えているという話を聞いたことがあります。
今期のうお座のキーワードは、「弱いものに従う」。 近年の欧米では、人間をキリスト教―特にプロテスタントの考えるような“強いもの”ではなく、“弱いもの”と見なして、弱者の権利を助けるイスラム教の考え方に共感を持つ人々が増えているという話を聞いたことがあります。










































































