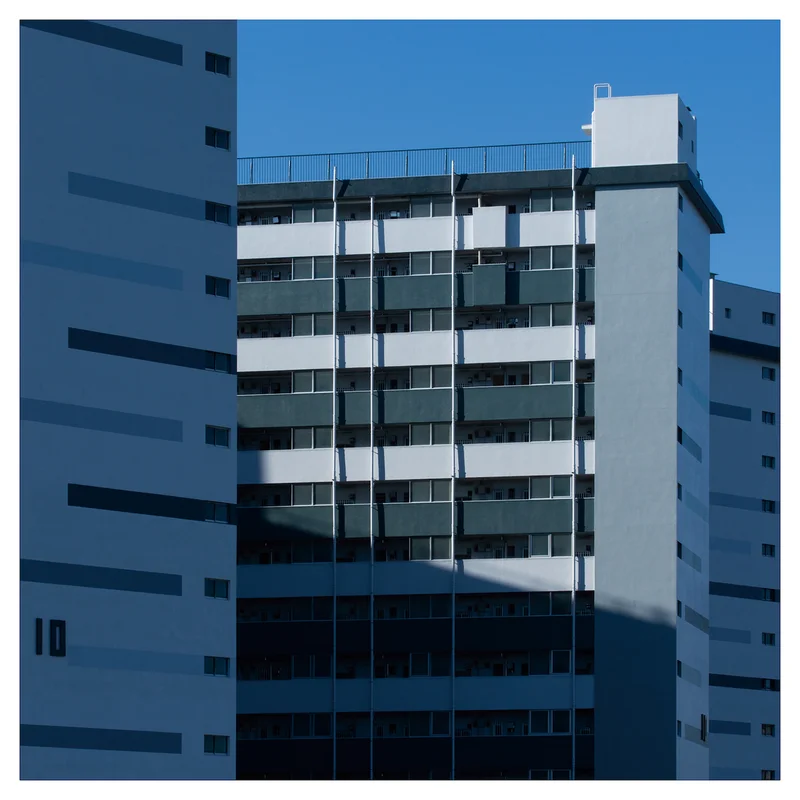【クリープハイプ・尾崎世界観さんインタビュー】モア世代女子必聴のラブソング『愛す』。「本来の言葉の意味をも超えた関係、を歌いたかった」
まさに、20代のモア世代を中心に、熱狂的な支持を受け続けているロックバンド、クリープハイプ。彼らの音楽が私たちを惹きつける理由は、“聴く”だけでなく、歌詞を“読む”ことで没入できるその先の世界を見せてくれるから。現メンバー10周年を迎えた今、3年ぶりとなるシングル「愛す(読み:ブス)」は、クリープハイプが改めて自分たちの存在を、そして世の中を見つめたうえで、これまでよりも幅広い層の人々に届くように作った曲だという。艶っぽいホーンが入ったメロウでスウィートなラブソングで、彼らにとって明らかに新機軸。その制作背景、そして、彼らが駆け抜けた“モア世代”について、フロントマンの尾崎世界観さんにインタビューを決行。モア読者のために語ってくれたスペシャルな内容をお届けします。

Profile
おざき・せかいかん●1984年生まれ、東京都出身。4人組バンド、クリープハイプのボーカルとギターを務める。2009年に現メンバーでの活動が本格的にスタートし、2012年メジャーデビュー。音楽だけでなく、半自伝的小説『祐介』、エッセイ『泣きたくなるほど嬉しい日々に』など執筆活動でも注目を集める。
「10年という節目のタイミングで原点に立ち返るのではなく、まだ僕たちの音楽が届いていないところに届けたかったんです。長くやってきたからこそ、クリープハイプのバンドサウンドのイメージも固まってきていたので、アレンジも今までやったことのない方向性に挑戦しました。
例えば、クリープハイプはギターのフレーズが特徴的なバンドなので、メンバーには『今回はバンド感が邪魔だ』ということをあえて伝えて、“クリープハイプらしさ”を極力削ることを心掛けました。僕のボーカルも癖を極力なくして、丸みを出すイメージで何度も歌い直しました。伝わるということを意識するとやっぱりメロディが大事なので、メロディを壊さないキーを意識して作りましたね」
柔らかい歌声で、“逆に”ブスと言ってしまいたくなるくらいの愛しさをキャッチーに表現している楽曲「愛す」。「愛す」と書いて「ブス」と読ませるタイトルもそうだが、愛嬌や人間臭さを含めて相手を包み込むような深い愛情が、シンプルに描かれている。
「言葉を使って仕事をしているからこそ、『言葉が邪魔だな』と思う瞬間があるんです。漠然と考えていることを言葉にしてしまった時点で、考えていたこととは違ってきてしまうというもどかしさがある。『意味としては合っているんだけど、ほんとに自分が思っている感じはこの言葉ではないんだ』と思っています。
今回、“ブス”というキーワードが浮かんだときに、その言葉が持つシビアさに迷いもあったんですけど、メロディにもハマったので入れようと決意しました。ネガティブな言葉に対して、『こういうことを言う人がいるから傷つく』とか『そんなこと言わなくてもいいのに』と、嫌悪感を抱く人もいるかもしれない。でも、“逆に”が成り立つ関係性を見つめたかったんです。長い時間一緒に過ごしたり、関係性が深まっていくと、使える言葉がだんだん増えていく。まだ出会ったばかりだと使ってはいけない言葉がいっぱいあるじゃないですか。でも、ネガティブな言葉が本来の意味とは逆の、これ以上ないほどの愛情を表現する言葉として成り立つくらいのふたりなんだということを読み取ってもらいたいんです。
ただ、より多くの人々に届けるために音や曲調やボーカルを意識的に変えたのに、歌詞は結局こうなるのが、クリープハイプというひねくれたバンドを象徴していると思います」
おざき・せかいかん●1984年生まれ、東京都出身。4人組バンド、クリープハイプのボーカルとギターを務める。2009年に現メンバーでの活動が本格的にスタートし、2012年メジャーデビュー。音楽だけでなく、半自伝的小説『祐介』、エッセイ『泣きたくなるほど嬉しい日々に』など執筆活動でも注目を集める。
「10年という節目のタイミングで原点に立ち返るのではなく、まだ僕たちの音楽が届いていないところに届けたかったんです。長くやってきたからこそ、クリープハイプのバンドサウンドのイメージも固まってきていたので、アレンジも今までやったことのない方向性に挑戦しました。
例えば、クリープハイプはギターのフレーズが特徴的なバンドなので、メンバーには『今回はバンド感が邪魔だ』ということをあえて伝えて、“クリープハイプらしさ”を極力削ることを心掛けました。僕のボーカルも癖を極力なくして、丸みを出すイメージで何度も歌い直しました。伝わるということを意識するとやっぱりメロディが大事なので、メロディを壊さないキーを意識して作りましたね」
柔らかい歌声で、“逆に”ブスと言ってしまいたくなるくらいの愛しさをキャッチーに表現している楽曲「愛す」。「愛す」と書いて「ブス」と読ませるタイトルもそうだが、愛嬌や人間臭さを含めて相手を包み込むような深い愛情が、シンプルに描かれている。
「言葉を使って仕事をしているからこそ、『言葉が邪魔だな』と思う瞬間があるんです。漠然と考えていることを言葉にしてしまった時点で、考えていたこととは違ってきてしまうというもどかしさがある。『意味としては合っているんだけど、ほんとに自分が思っている感じはこの言葉ではないんだ』と思っています。
今回、“ブス”というキーワードが浮かんだときに、その言葉が持つシビアさに迷いもあったんですけど、メロディにもハマったので入れようと決意しました。ネガティブな言葉に対して、『こういうことを言う人がいるから傷つく』とか『そんなこと言わなくてもいいのに』と、嫌悪感を抱く人もいるかもしれない。でも、“逆に”が成り立つ関係性を見つめたかったんです。長い時間一緒に過ごしたり、関係性が深まっていくと、使える言葉がだんだん増えていく。まだ出会ったばかりだと使ってはいけない言葉がいっぱいあるじゃないですか。でも、ネガティブな言葉が本来の意味とは逆の、これ以上ないほどの愛情を表現する言葉として成り立つくらいのふたりなんだということを読み取ってもらいたいんです。
ただ、より多くの人々に届けるために音や曲調やボーカルを意識的に変えたのに、歌詞は結局こうなるのが、クリープハイプというひねくれたバンドを象徴していると思います」
ここ数年のクリープハイプの音楽活動は、1年に何枚もシングルをリリースしていた時期と違い、とてもゆったりしている。そのせいか、「愛す」もそうだが、ひとつひとつの曲がきっちりと方向性を見定めて、丁寧に作られている印象がある。
「レコード会社の方も、もうリリースのペースについてあまり言わなくなりましたね(笑)。文筆業や音楽以外の活動も自然とプロモーションになっていると認識してもらえている部分があります。これまで繋がりがなかった媒体に出ていくこともプラスになりますし、そういう環境にいさせてもらえるのはすごく嬉しいです。ただ、ひたすらに楽曲を増やしていっても、ライブですぐにやらなくなる曲が増えてしまえば、それはお客さんにとっても良いことではない。そう思うようになったのは、時間をかけて本を書いたことも大きいんです。音楽も同じように、じっくり丁寧に作るべきだと思いました。そうやって作った曲は残っていくという実感も最近はあって、だから大事に作っていきたいんです」
それぞれの環境や生き方に合った多様な働き方がどんどん広がっている現在。モア世代の副業も決して珍しいことではなくなった。尾崎さんは、2016年に刊行した半自伝的小説『祐介』が各所で絶賛されて以降、毎年書籍を発表している。元々バンドのために始めた文筆業が、今や立派な「副業」になっているとも言える。
「“副業”は“福業”と書いても良いと思います(笑)。僕が小説を書き始めたのは……満足に歌えなくなってしまった時期があったからなんです。2014年くらいから、バンドの状態に変化が出てきて、お客さんも僕の少し不安定な状態を見て、『どうしたんだろう』とネットに書くので、またそれを読んで気になってしまうという悪循環もありました。
音楽活動以外のことを何かやらないと自分自身が保てない状態になっていた、そんな時に、たまたま編集者の方に誘っていただいて小説を書き始めたんです。音楽活動のストレスから逃れるように書いていたのですが、はじめは全然良い文章が書けなくて。でも、ある程度型が決まってきていた音楽活動と違って、“うまくできないこと”に救われたんです。本業ではないからこそ、肩の力を抜いて『まだまだこんなにおもしろいことがあるんだ』と思えた。新しい可能性が広がるきっかけになりました」
「レコード会社の方も、もうリリースのペースについてあまり言わなくなりましたね(笑)。文筆業や音楽以外の活動も自然とプロモーションになっていると認識してもらえている部分があります。これまで繋がりがなかった媒体に出ていくこともプラスになりますし、そういう環境にいさせてもらえるのはすごく嬉しいです。ただ、ひたすらに楽曲を増やしていっても、ライブですぐにやらなくなる曲が増えてしまえば、それはお客さんにとっても良いことではない。そう思うようになったのは、時間をかけて本を書いたことも大きいんです。音楽も同じように、じっくり丁寧に作るべきだと思いました。そうやって作った曲は残っていくという実感も最近はあって、だから大事に作っていきたいんです」
それぞれの環境や生き方に合った多様な働き方がどんどん広がっている現在。モア世代の副業も決して珍しいことではなくなった。尾崎さんは、2016年に刊行した半自伝的小説『祐介』が各所で絶賛されて以降、毎年書籍を発表している。元々バンドのために始めた文筆業が、今や立派な「副業」になっているとも言える。
「“副業”は“福業”と書いても良いと思います(笑)。僕が小説を書き始めたのは……満足に歌えなくなってしまった時期があったからなんです。2014年くらいから、バンドの状態に変化が出てきて、お客さんも僕の少し不安定な状態を見て、『どうしたんだろう』とネットに書くので、またそれを読んで気になってしまうという悪循環もありました。
音楽活動以外のことを何かやらないと自分自身が保てない状態になっていた、そんな時に、たまたま編集者の方に誘っていただいて小説を書き始めたんです。音楽活動のストレスから逃れるように書いていたのですが、はじめは全然良い文章が書けなくて。でも、ある程度型が決まってきていた音楽活動と違って、“うまくできないこと”に救われたんです。本業ではないからこそ、肩の力を抜いて『まだまだこんなにおもしろいことがあるんだ』と思えた。新しい可能性が広がるきっかけになりました」

2009年11月に現メンバーが揃ってから10周年を迎えたクリープハイプ。「バンドは小さな会社だと思っている」と尾崎さんは話す。そうなると、壁にぶつかった2014年は本格的に活動を開始してから5年目。モア読者も共感できる「社会人5年目の壁」だったとも言えるのでは?
「そうかもしれないですね。音楽活動だけに限らず、人と関わらないと成立しない仕事の場合、周りから評価されたいという承認欲求は誰しも持っているもの。特に、5年目くらいの時期は、周囲の自分への評価が『これくらいなのか』とある程度落ち着くと思います。
でも、その評価に自分自身が物足りなさを感じることもあって、『もしかして自分は落ちて行っているのかも』と思ってしまうことがあるんです。音楽だとわかりやすいんですけど、フェスなどでお客さんは新しいアーティストに飛びついていく。僕達の場合、自分たちはちゃんとやれていると思っていても、お客さんの反応が、以前ほどの熱を帯びていない感覚があった。『このズレはなんだろう?』と思っても、目の前のことに必死だったこともあって、なぜだか全然分からなくて。分からないなりに変化を加えてみたら、それはそれで『求めているものと違う』と言われました。とても悔しかったけど、今思うと、自分でもずっと好きだったアーティスト以外のアーティストに夢中になることは当たり前にあったんです。
だから、壁にぶつかった時に、必ずしも壁に向きあって乗り越える必要はないと思うんです。僕の場合、たまたま執筆のお話をいただいて、“音楽とうまくやっていくために”別の表現に挑戦しはじめた。きっかけは“音楽からの逃げ”だったかもしれないけれど、それが新しい表現を手にすることにつながりました。いかに本業をあきらめずにいられるが大事で、中途半端な状態でもいいし、立ち止まってもいい。そうしているうちに勝手に周りが変わっていって、状況が変わったりもする。特に音楽は流行りすたりがあって、自分たちは何もしていないのに勝手にまた『今っぽい』となることだってある。それはみなさんの仕事にもあてはまると思います。そうやって事態が好転して、また新たな自分の可能性が生まれるんだと思います」
バンドの、そして自身のこれまでを振り返りながら、私たちが陥りやすい不安や悩みに重ねて丁寧に言葉を紡いでくれた尾崎さん。インタビュー終了後、興味深そうにMOREを読みながら―――。
「女性誌っていいですよね。エネルギーがあって素敵だと思います。ただ、ケンカをしたとして、部屋に置いてあったMOREの角でコツンとやられたらめちゃくちゃ痛いだろうなと思いますけど(笑)」
「そうかもしれないですね。音楽活動だけに限らず、人と関わらないと成立しない仕事の場合、周りから評価されたいという承認欲求は誰しも持っているもの。特に、5年目くらいの時期は、周囲の自分への評価が『これくらいなのか』とある程度落ち着くと思います。
でも、その評価に自分自身が物足りなさを感じることもあって、『もしかして自分は落ちて行っているのかも』と思ってしまうことがあるんです。音楽だとわかりやすいんですけど、フェスなどでお客さんは新しいアーティストに飛びついていく。僕達の場合、自分たちはちゃんとやれていると思っていても、お客さんの反応が、以前ほどの熱を帯びていない感覚があった。『このズレはなんだろう?』と思っても、目の前のことに必死だったこともあって、なぜだか全然分からなくて。分からないなりに変化を加えてみたら、それはそれで『求めているものと違う』と言われました。とても悔しかったけど、今思うと、自分でもずっと好きだったアーティスト以外のアーティストに夢中になることは当たり前にあったんです。
だから、壁にぶつかった時に、必ずしも壁に向きあって乗り越える必要はないと思うんです。僕の場合、たまたま執筆のお話をいただいて、“音楽とうまくやっていくために”別の表現に挑戦しはじめた。きっかけは“音楽からの逃げ”だったかもしれないけれど、それが新しい表現を手にすることにつながりました。いかに本業をあきらめずにいられるが大事で、中途半端な状態でもいいし、立ち止まってもいい。そうしているうちに勝手に周りが変わっていって、状況が変わったりもする。特に音楽は流行りすたりがあって、自分たちは何もしていないのに勝手にまた『今っぽい』となることだってある。それはみなさんの仕事にもあてはまると思います。そうやって事態が好転して、また新たな自分の可能性が生まれるんだと思います」
バンドの、そして自身のこれまでを振り返りながら、私たちが陥りやすい不安や悩みに重ねて丁寧に言葉を紡いでくれた尾崎さん。インタビュー終了後、興味深そうにMOREを読みながら―――。
「女性誌っていいですよね。エネルギーがあって素敵だと思います。ただ、ケンカをしたとして、部屋に置いてあったMOREの角でコツンとやられたらめちゃくちゃ痛いだろうなと思いますけど(笑)」

10周年記念ツアー開催中!「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」
【スケジュール】
2020年02月07日(金)札幌ZeppSapporo
2020年02月15日(土)仙台チームスマイル仙台PIT
2020年02月16日(日)仙台チームスマイル仙台PIT
2020年02月27日(木)広島CLUB QUATTRO
2020年02月28日(金)広島CLUB QUATTRO
2020年03月01日(日)福岡ZeppFukuoka
2020年03月06日(金)名古屋ZeppNagoya
2020年03月07日(土)名古屋ZeppNagoya
2020年03月15日(日)幕張メッセ国際展示場9-11ホール
2020年03月22日(日)大阪城ホール
2020年02月07日(金)札幌ZeppSapporo
2020年02月15日(土)仙台チームスマイル仙台PIT
2020年02月16日(日)仙台チームスマイル仙台PIT
2020年02月27日(木)広島CLUB QUATTRO
2020年02月28日(金)広島CLUB QUATTRO
2020年03月01日(日)福岡ZeppFukuoka
2020年03月06日(金)名古屋ZeppNagoya
2020年03月07日(土)名古屋ZeppNagoya
2020年03月15日(日)幕張メッセ国際展示場9-11ホール
2020年03月22日(日)大阪城ホール
クリープハイプ『愛す』
取材・文/小松香里 撮影/藤澤由加