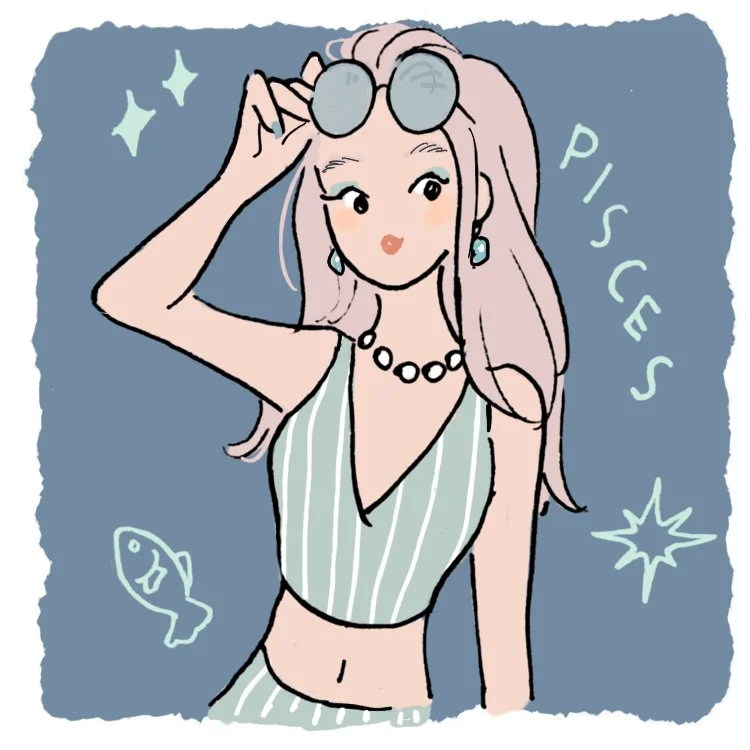【最新12星座占い】<5/16~5/29>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<5/16~5/29>の12星座全体の運勢は?
「ゲームに臨む戦略を取り戻す」
5月21日に太陽がふたご座に移り「小満」を過ぎると、万物の命もあふれんばかりに躍動し、特に植物は生気に満ちて、若葉がしたたるような青葉になりますが、そんな中、5月26日にいて座5度(数え度数で6度)で皆既月食を迎えていきます。
今回は近地点で起こる満月なので、大きいです。いわゆる「スーパームーン」なのですが、それが欠ける訳ですから、単に「エモさ」が解放されるというより、そうした「エモさ」を感じられるような心の拠りどころとなっているものが失われたり、一時的に失われかけた結果、そのありがたみが骨身に沁みるということが起きやすいタイミングなのだと言えます。
その上で、今回の皆既月食のテーマを端的に表わすとするなら、それは「ゲームプランを取り戻す」。すなわち、せっかく与えられた人生というゲームを最大限楽しんでいくために必要な目標を持ったり、誰かと共に戦っていくためのルールを設けたりすることの大切さを改めて再認識していくことです。
それは逆に言えば、もし今あなたが適切なゲームプランを持てていないばかりに、即座の結果を求めて不満を募らせていたり、ついマンネリ化して立ち往生してしまったり、また他の誰かと互いに消耗しあうような状況に陥ったりといった傾向に少しでもあるのなら、そうした現実にきちんと向き合っていかなければなりません。
ちょうどこの時期には「更衣(ころもがえ)」という季語があって、気候不順も重なって服装選びに悩む頃合いですが(制服は6月1日が衣替え)、服装だけでなくそれに連動するコンセプトやライフスタイル、生活の中で重視するポイントなどをこの機会に整理・統一してみるのもいいでしょう。
その意味で、今回の月食前後の期間は、改めて人生というゲームの遊び方のスタイルを明確にしていくことができるかどうか問われていくように思います。
今回は近地点で起こる満月なので、大きいです。いわゆる「スーパームーン」なのですが、それが欠ける訳ですから、単に「エモさ」が解放されるというより、そうした「エモさ」を感じられるような心の拠りどころとなっているものが失われたり、一時的に失われかけた結果、そのありがたみが骨身に沁みるということが起きやすいタイミングなのだと言えます。
その上で、今回の皆既月食のテーマを端的に表わすとするなら、それは「ゲームプランを取り戻す」。すなわち、せっかく与えられた人生というゲームを最大限楽しんでいくために必要な目標を持ったり、誰かと共に戦っていくためのルールを設けたりすることの大切さを改めて再認識していくことです。
それは逆に言えば、もし今あなたが適切なゲームプランを持てていないばかりに、即座の結果を求めて不満を募らせていたり、ついマンネリ化して立ち往生してしまったり、また他の誰かと互いに消耗しあうような状況に陥ったりといった傾向に少しでもあるのなら、そうした現実にきちんと向き合っていかなければなりません。
ちょうどこの時期には「更衣(ころもがえ)」という季語があって、気候不順も重なって服装選びに悩む頃合いですが(制服は6月1日が衣替え)、服装だけでなくそれに連動するコンセプトやライフスタイル、生活の中で重視するポイントなどをこの機会に整理・統一してみるのもいいでしょう。
その意味で、今回の月食前後の期間は、改めて人生というゲームの遊び方のスタイルを明確にしていくことができるかどうか問われていくように思います。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「哲学的であるということ」。

「青年の哲学(人生の問題)、大人の哲学(社会システムの問題)、老人の哲学(死の問題)はそれぞれ、文学、思想、宗教で代用できるが、子どもの哲学(存在の問題)には代用がきかない」
永井均は上記の理由から、子どもの哲学だけを「哲学」と呼び、その他にはそれぞれ代用可能な他のジャンルをあてがってみせるのですが、そうした存在の問題を扱う哲学に12星座のうちで最も直面していきやすいのは、間違いなくおひつじ座の人たちであるように思います。
というのも、列挙されたジャンルの中で最も何のためにもならないのが哲学な訳ですが、同時に、そういう目的を持ってしまったらとてもできないのも哲学だから。
そもそも、哲学というのは「何かのためになる」の「何か」とか「ためになる」ということが成立するための土台部分の疑問に引っかかってしまったり、それについて考えずにはいられない人がやらずにはいられなくて気付いてたらやってしまっているものなのですが、そこまで無目的に問題に突き当たっていけるのはおひつじ座以外にはあまり考えられないのです。
永井均は幸福な人でなければ哲学はできないと言い、なぜなら、そうでなければ幸福になるために哲学してしまうからと述べるのですが、「幸福な人がさしたる目的も持たずに哲学する」「幸福な人が何の役にも立たないことをする」というのは、考えれば考えるほどおひつじ座にうってつけのスタイルであり、ひとつの戦略と言えるのではないでしょうか。
今期のおひつじ座のあなたもまた、いたずらに他ジャンルに精を出すよりも、自分の取り組み方がどこまで哲学的であるかどうかということをまず第一に気にしてみるといいでしょう。
参考:永井均『「子ども」のための哲学』(講談社現代新書)
永井均は上記の理由から、子どもの哲学だけを「哲学」と呼び、その他にはそれぞれ代用可能な他のジャンルをあてがってみせるのですが、そうした存在の問題を扱う哲学に12星座のうちで最も直面していきやすいのは、間違いなくおひつじ座の人たちであるように思います。
というのも、列挙されたジャンルの中で最も何のためにもならないのが哲学な訳ですが、同時に、そういう目的を持ってしまったらとてもできないのも哲学だから。
そもそも、哲学というのは「何かのためになる」の「何か」とか「ためになる」ということが成立するための土台部分の疑問に引っかかってしまったり、それについて考えずにはいられない人がやらずにはいられなくて気付いてたらやってしまっているものなのですが、そこまで無目的に問題に突き当たっていけるのはおひつじ座以外にはあまり考えられないのです。
永井均は幸福な人でなければ哲学はできないと言い、なぜなら、そうでなければ幸福になるために哲学してしまうからと述べるのですが、「幸福な人がさしたる目的も持たずに哲学する」「幸福な人が何の役にも立たないことをする」というのは、考えれば考えるほどおひつじ座にうってつけのスタイルであり、ひとつの戦略と言えるのではないでしょうか。
今期のおひつじ座のあなたもまた、いたずらに他ジャンルに精を出すよりも、自分の取り組み方がどこまで哲学的であるかどうかということをまず第一に気にしてみるといいでしょう。
参考:永井均『「子ども」のための哲学』(講談社現代新書)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「時熟的であるということ」。

臨床心理学者の河合隼雄は『生と死の接点 <心理療法>コレクションⅢ』の中で、70歳のある女性が「五十年前に人を傷つけるようなことをしたため、そのことを最近になって人から責められているような気がする」という訴えで来談した事例を取りあげ、秘密ということの大切さに触れていました。
この五十年前のこととは、彼女が結婚後、近所の人たちが彼女の噂話をしていると思い込み、無記名で隣家にかなり失礼な手紙を出した、ということものでした。このときは何事もなく過ぎ、彼女はそのことについて誰にも話さず秘密にしてきたものの、事あるごとに思い出しては後悔や自責の念に駆られてきたと。
七十歳になって、そのことが急に強くなって抑うつ状態がひどくなって来談した訳ですが、治療の過程のなかで、医者のすすめもあって彼女ははじめて夫に秘密をうちあけます。すると、夫は「聞いてくれただけでなく、夫の方の苦しみなども聞く機会になった。夫婦でいながら互いにやはり一人一人苦しみを背負った人間だと思った」という展開につながり、思いがけず治療は進んでいったのだとか。
河合隼雄はこうした事例を受けて、「夫婦というものは協力し合うことはできても、理解し合うということは難しいのかも知れない」と前置きしつつ、次のようにも述べていました。
「この妻があの秘密を夫に話してしまうような人であれば、夫婦の関係はあんがい破綻していたかも知れない。秘密を一人で持ち続け、それについて考えることによって、この女性は自分を支え強く生きてきたかも知れない。秘密が語られるには、それにふさわしい時熟を必要とするのである。」
人との関わりは、それが家族や夫婦など近しいものであるほど、その間には秘密はない方がいいという考え方の人からすれば、こうした見方は対極的なものかもしれません。
それでも、今期のおうし座にとって、あまりに安易に言葉にしてしまうより、身体がそれを受け止めきって“然るべきタイミング”を訴えてくるまで秘密にしておくということも、ひとつの乗り越え方の知恵と言えるのではないでしょうか。
参考:河合隼雄『生と死の接点 <心理療法>コレクションⅢ』(講談社現代文庫)
この五十年前のこととは、彼女が結婚後、近所の人たちが彼女の噂話をしていると思い込み、無記名で隣家にかなり失礼な手紙を出した、ということものでした。このときは何事もなく過ぎ、彼女はそのことについて誰にも話さず秘密にしてきたものの、事あるごとに思い出しては後悔や自責の念に駆られてきたと。
七十歳になって、そのことが急に強くなって抑うつ状態がひどくなって来談した訳ですが、治療の過程のなかで、医者のすすめもあって彼女ははじめて夫に秘密をうちあけます。すると、夫は「聞いてくれただけでなく、夫の方の苦しみなども聞く機会になった。夫婦でいながら互いにやはり一人一人苦しみを背負った人間だと思った」という展開につながり、思いがけず治療は進んでいったのだとか。
河合隼雄はこうした事例を受けて、「夫婦というものは協力し合うことはできても、理解し合うということは難しいのかも知れない」と前置きしつつ、次のようにも述べていました。
「この妻があの秘密を夫に話してしまうような人であれば、夫婦の関係はあんがい破綻していたかも知れない。秘密を一人で持ち続け、それについて考えることによって、この女性は自分を支え強く生きてきたかも知れない。秘密が語られるには、それにふさわしい時熟を必要とするのである。」
人との関わりは、それが家族や夫婦など近しいものであるほど、その間には秘密はない方がいいという考え方の人からすれば、こうした見方は対極的なものかもしれません。
それでも、今期のおうし座にとって、あまりに安易に言葉にしてしまうより、身体がそれを受け止めきって“然るべきタイミング”を訴えてくるまで秘密にしておくということも、ひとつの乗り越え方の知恵と言えるのではないでしょうか。
参考:河合隼雄『生と死の接点 <心理療法>コレクションⅢ』(講談社現代文庫)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「語り口の工夫ということ」。

人を怒らせてしまったり非難されることになった経緯において、言動の内容そのもののためというよりも、むしろその振る舞い方や言い方こそが問題の根源となっているケースは、近年ますます増加傾向にあるように思います。
そして、その最も有名かつ今なお振り返る価値がある事例として、60年代にアメリカで出版されたユダヤ人思想家ハンナ・アーレントの『イェルサレムのアイヒマン』が挙げられます。本書はユダヤ人絶滅という重い主題を扱ったルポルタージュとしては例外的なほど、乾いた、皮肉っぽい、軽薄な(“不謹慎な”、“小生意気な”を意味する英語の「flippant」にあたる)語り口で書かれたことが要因となり、その後欧米を中心にアーレント個人に対する一大・反アーレント・キャンペーンを巻き起こし、激しい非難と一連の議論の端緒となりました。
しかし、彼女の語り口(tone)は明らかに無思慮の産物ではなく、選択されたものであり、その「ほとんど嘲弄的で悪意ある」と非難された語り口について、アーレント本人はヘブライ学の第一人者で彼女もまた年来畏敬してきた年上の知人であったゲルショム・ショーレムとの往復書簡の中で次のように述べています。
「あなたを戸惑わせているのは、(この本での)わたしの議論とわたしのアプローチが、あなたの見慣れているものとは違っているということです。別にいえば、厄介の種は、わたしが独立しているということです。このことでわたしが言おうとするのは次のことです。一つに、わたしはどんな組織にも属しておらず、つねに自分自身の名においてしか語りません。またもう一つに、わたしはレッシングが「自立的思考」と名づけたものに、多大な信を置いています。ところで、わたしの考えでは、イデオロギー、世論、信念は、これに取っては代われません。その結果としてあるものに対するあなたの異議がどうあれ、それらがまさしくわたしのものであって他の誰のものでもないということ、そのことがあなたにわからない限り、あなたはそれを理解しないでしょう。」
おそらくアーレントは、イスラエルで行われたこの裁判を、第三者として、それこそ冷静に、ルポルタージュしぬこう、そのことができれば、それはそれだけでなにごとかだ、と考えていたのではないでしょうか。つまり、先の著作において彼女は語るべき言葉を奪われた人間に残された最後の武器として、意図的に選択された「語り口」を手に取り、それで見事に戦い抜いたのだ、と。
同様に、今期のふたご座もまた、大なり小なりそうした「語り口(tone)」の工夫―例えば“重い”話題についてあくまで他人事のように語るといったような―ということについて考えてみるといいでしょう。
参考:マリー・ルイーズ・クノット、ダーヴィッド・エレディア編集、細見和之+大形綾+関口彩乃訳『アーレント=ショーレム往復書簡』(岩波書店)
そして、その最も有名かつ今なお振り返る価値がある事例として、60年代にアメリカで出版されたユダヤ人思想家ハンナ・アーレントの『イェルサレムのアイヒマン』が挙げられます。本書はユダヤ人絶滅という重い主題を扱ったルポルタージュとしては例外的なほど、乾いた、皮肉っぽい、軽薄な(“不謹慎な”、“小生意気な”を意味する英語の「flippant」にあたる)語り口で書かれたことが要因となり、その後欧米を中心にアーレント個人に対する一大・反アーレント・キャンペーンを巻き起こし、激しい非難と一連の議論の端緒となりました。
しかし、彼女の語り口(tone)は明らかに無思慮の産物ではなく、選択されたものであり、その「ほとんど嘲弄的で悪意ある」と非難された語り口について、アーレント本人はヘブライ学の第一人者で彼女もまた年来畏敬してきた年上の知人であったゲルショム・ショーレムとの往復書簡の中で次のように述べています。
「あなたを戸惑わせているのは、(この本での)わたしの議論とわたしのアプローチが、あなたの見慣れているものとは違っているということです。別にいえば、厄介の種は、わたしが独立しているということです。このことでわたしが言おうとするのは次のことです。一つに、わたしはどんな組織にも属しておらず、つねに自分自身の名においてしか語りません。またもう一つに、わたしはレッシングが「自立的思考」と名づけたものに、多大な信を置いています。ところで、わたしの考えでは、イデオロギー、世論、信念は、これに取っては代われません。その結果としてあるものに対するあなたの異議がどうあれ、それらがまさしくわたしのものであって他の誰のものでもないということ、そのことがあなたにわからない限り、あなたはそれを理解しないでしょう。」
おそらくアーレントは、イスラエルで行われたこの裁判を、第三者として、それこそ冷静に、ルポルタージュしぬこう、そのことができれば、それはそれだけでなにごとかだ、と考えていたのではないでしょうか。つまり、先の著作において彼女は語るべき言葉を奪われた人間に残された最後の武器として、意図的に選択された「語り口」を手に取り、それで見事に戦い抜いたのだ、と。
同様に、今期のふたご座もまた、大なり小なりそうした「語り口(tone)」の工夫―例えば“重い”話題についてあくまで他人事のように語るといったような―ということについて考えてみるといいでしょう。
参考:マリー・ルイーズ・クノット、ダーヴィッド・エレディア編集、細見和之+大形綾+関口彩乃訳『アーレント=ショーレム往復書簡』(岩波書店)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「「いる」ということ」。

美学者の伊藤亜紗は、リレー形式で書かれたエッセイの一つとして書かれた「体を失う日」のなかで、人類のこれまでの歴史は「体の体らしさを捨てていく過程」であり、その分かりやすい変わり目として「近代化」を挙げています。
まだ個が成立していなかった近代化以前のヨーロッパの食事シーンは盛られる皿もメニューも区別はなく、おならを我慢することもなければ唾をテーブルの上に吐くのも当たり前で、いわば「粘液的社交」に他ならず、また、自分だけのプライベートの部屋なんていうものもありえなかった訳です。
それが産業革命を通して労働が時間によって測られるようになり、一定時間内に決められた量の仕事ができる「標準的な体としての健常者」という概念を既定するようになり、近年はそれをロボットやAIが代替するビジョンが提示されるようになってきたなかで、伊藤は次のように言及しています。
「一方で、失われるものもある。私が一番恐れているのは、「いる」の喪失だ。「いる」こそ、物質としての体が私たちに与えてくれる最大の恩恵ではないだろうか。」
つまり、言語的なコミュニケーションが成り立たないような相手や状況であったとしても、非言語的な次元で取りうる最もシンプルなコミュニケーションこそが「いる」であり、と同時に、それはつねに何かを「する」よう過剰に駆り立てられている現代人が非常に苦手とするコミュニケーションでもあるのではないでしょうか。
ただし、苦手ではあっても不必要という訳ではありません。というより、ほんらい人が生き物としていきいきと生きていく上で必要不可欠であるがゆえに、それはいつの間にか外部の専門家やエリートへと委託され、産業化して私たちは単なるサービスや商品の“消費者”へと降格させられるようになったのだと言えるのではないでしょうか。
「そして「いる」とともに失われるのは「変身」の可能性である。私たちは、逆説的にも、物質的な体があることによって変身することができる。(中略)変身とは、自分と異なるものの世界の見え方をありありと実感することである。カーニバルがそうであったように、それは価値転倒の場なのだ。吉村さんの言うように、あらゆる生命体が、この世界をそれぞれの仕方で把握している。物理的な体があるからこそ、自分でないものになることができる。」
今期のかに座もまた、物理的な体を通じた「いる」というコミュニケーションや、その結果としての「変身」を自身の手のうちに取り戻し、習熟していくことを改めて大切にしていきたいところです。
参考:奥野克己・吉村萬壱・伊藤亜紗『ひび割れた日常』(亜紀書房)
まだ個が成立していなかった近代化以前のヨーロッパの食事シーンは盛られる皿もメニューも区別はなく、おならを我慢することもなければ唾をテーブルの上に吐くのも当たり前で、いわば「粘液的社交」に他ならず、また、自分だけのプライベートの部屋なんていうものもありえなかった訳です。
それが産業革命を通して労働が時間によって測られるようになり、一定時間内に決められた量の仕事ができる「標準的な体としての健常者」という概念を既定するようになり、近年はそれをロボットやAIが代替するビジョンが提示されるようになってきたなかで、伊藤は次のように言及しています。
「一方で、失われるものもある。私が一番恐れているのは、「いる」の喪失だ。「いる」こそ、物質としての体が私たちに与えてくれる最大の恩恵ではないだろうか。」
つまり、言語的なコミュニケーションが成り立たないような相手や状況であったとしても、非言語的な次元で取りうる最もシンプルなコミュニケーションこそが「いる」であり、と同時に、それはつねに何かを「する」よう過剰に駆り立てられている現代人が非常に苦手とするコミュニケーションでもあるのではないでしょうか。
ただし、苦手ではあっても不必要という訳ではありません。というより、ほんらい人が生き物としていきいきと生きていく上で必要不可欠であるがゆえに、それはいつの間にか外部の専門家やエリートへと委託され、産業化して私たちは単なるサービスや商品の“消費者”へと降格させられるようになったのだと言えるのではないでしょうか。
「そして「いる」とともに失われるのは「変身」の可能性である。私たちは、逆説的にも、物質的な体があることによって変身することができる。(中略)変身とは、自分と異なるものの世界の見え方をありありと実感することである。カーニバルがそうであったように、それは価値転倒の場なのだ。吉村さんの言うように、あらゆる生命体が、この世界をそれぞれの仕方で把握している。物理的な体があるからこそ、自分でないものになることができる。」
今期のかに座もまた、物理的な体を通じた「いる」というコミュニケーションや、その結果としての「変身」を自身の手のうちに取り戻し、習熟していくことを改めて大切にしていきたいところです。
参考:奥野克己・吉村萬壱・伊藤亜紗『ひび割れた日常』(亜紀書房)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「呼応と調和をはかるということ」。

都会とか現代というのは、人が歩くのでも情報の流れもお店の回転もいつも速くて、そこではみんな過剰に力んでいるものです。そして、それはそれで楽しいと感じる一方で、どこかで必ずその近視眼的になりがちな視線のピントを外し、身体を弛緩させたり、精神をチューニングしていく必要が出てきます。
問題なのは、占いであれソロキャンプであれ“推し”のアイドルであれ、そのチューニングの機会さえもあれこれとリコメンドされ、人はついそれらを享受してしまうため、自分で意識していかないとチューニングの手さばきを向上させていく機会がほとんど与えられないという点にあるのではないでしょうか。
「大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。たとえば星をみるとかして。」
池澤夏樹の小説『スティル・ライフ』は、染色工場でバイトしている主人公が、佐々井という男に出会って、とある不思議な仕事を頼まれるという短い物語なのですが、この佐々井がなかなか不思議な男で、こんな風に唐突に宇宙の話なんかを始めるのです。
「二つの世界の呼応と調和がうまくいっていると、毎日を過すのはずっと楽になる。心の力をよけいなことに使う必要がなくなる。
水の味がわかり、人を怒らせることが少なくなる。
星を正しく見るのはむずかしいが、上手になればそれだけの効果があがるだろう。
星ではなく、せせらぎや、セミ時雨でいいのだけれども。」
普段のテンポをすこしずらして、ピントをぼやかしたり、呼吸を楽にしたりするには、佐々井が言うように、日常社会とは異なる別のレイヤーの時間を取り入れて、「連絡をつけ」たり、「呼応と調和」をはかることが望ましい。
ただ、かつての社会であれば、この「異なる別のレイヤーの時間」は虫の音や、鳥の羽ばたきや花咲き草したたる野山と地続きだった訳ですが、現代ではお金や想像力など何らかのブースターを介在させなければ“自然”さえも繋がることができなくなってしまいました。
その意味で今期のしし座のテーマは、佐々井が話してくれたような二つの世界のあいだで「呼応と調和」をはかる力を自分で育み、鍛えていくだけの機会をどうしたら自分に与えていけるかということになるでしょう。
参考:池澤夏樹『スティル・ライフ』(中公文庫)
問題なのは、占いであれソロキャンプであれ“推し”のアイドルであれ、そのチューニングの機会さえもあれこれとリコメンドされ、人はついそれらを享受してしまうため、自分で意識していかないとチューニングの手さばきを向上させていく機会がほとんど与えられないという点にあるのではないでしょうか。
「大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。たとえば星をみるとかして。」
池澤夏樹の小説『スティル・ライフ』は、染色工場でバイトしている主人公が、佐々井という男に出会って、とある不思議な仕事を頼まれるという短い物語なのですが、この佐々井がなかなか不思議な男で、こんな風に唐突に宇宙の話なんかを始めるのです。
「二つの世界の呼応と調和がうまくいっていると、毎日を過すのはずっと楽になる。心の力をよけいなことに使う必要がなくなる。
水の味がわかり、人を怒らせることが少なくなる。
星を正しく見るのはむずかしいが、上手になればそれだけの効果があがるだろう。
星ではなく、せせらぎや、セミ時雨でいいのだけれども。」
普段のテンポをすこしずらして、ピントをぼやかしたり、呼吸を楽にしたりするには、佐々井が言うように、日常社会とは異なる別のレイヤーの時間を取り入れて、「連絡をつけ」たり、「呼応と調和」をはかることが望ましい。
ただ、かつての社会であれば、この「異なる別のレイヤーの時間」は虫の音や、鳥の羽ばたきや花咲き草したたる野山と地続きだった訳ですが、現代ではお金や想像力など何らかのブースターを介在させなければ“自然”さえも繋がることができなくなってしまいました。
その意味で今期のしし座のテーマは、佐々井が話してくれたような二つの世界のあいだで「呼応と調和」をはかる力を自分で育み、鍛えていくだけの機会をどうしたら自分に与えていけるかということになるでしょう。
参考:池澤夏樹『スティル・ライフ』(中公文庫)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「ケア的であるということ」。

日本は現在世界一の長寿大国であると同時に、世界一早い速度で少子化が進んでいる国でもありますが、多和田葉子の小説『献灯使』は、そんな日本社会の特質を縫い合わせたような作品と言えます。
東京に住む百八歳の老人作家の義郎が、身体が不自由でつねに微熱を発しているひ孫の無名(むめい)を育てるという特異な設定のこの物語では、通常は元気なはずの子どもが病気がちの横臥者で、人の助けが必要でありがちな老人が介護者という構図の反転が起きています。
そのためもあってか、義郎は無名を無意識に見下す訳でも、過剰に保護的になりすぎる訳でもなく、事あるごとに迷いつつも、絶妙なバランスでケア的であろうとしていくのですが、それを象徴しているのが義郎が無名を育てる覚悟を決めたシーンです。
無名が産まれたとき、孫はどこかへ旅行へ行ったまま行方不明で、母親も出血多量で死んでしまい、義郎は途方にくれていました。
「義郎は、ミニチュアのような赤ん坊の手を握って小さく動かし、大声で泣き笑いしたい気持ちが爆発し、口から思わず飛び出してきたのが、「二人で頑張ろう、同僚」だった。これまで使ったことのない「同僚」などという言葉がなぜこの瞬間出てきたのだろう。」
思わず「同僚」と呼びかける義郎と無名のあいだには、家父長的な父と子という序列関係はもはや存在していません。その後、無名の父親である孫の飛藻が戻ってきた際、義郎は「自分の子がかわいくないのかと」と詰問するのですが、「俺の子かどうか、どうしてわかる」というつれない返事をした孫の不道徳を責めた後、「思わず陳腐な台詞を吐いてしまった」と自分の創造性のなさに反省し、あらためて「同僚」との関係性に立ち戻っていったのです。
おそらく、ここには迷いや不安さえも創造性へと変えてしまう「ケア的である」ということの、ひとつの可能性が指し示されているのではないでしょうか。
今期のおとめ座もまた、固定的な決めつけに基づく道徳ではなく、より動的な倫理的振る舞いとしてのケアということを自身に取り入れてみるといいでしょう。
参考:多和田葉子『献灯使』(講談社文庫)
東京に住む百八歳の老人作家の義郎が、身体が不自由でつねに微熱を発しているひ孫の無名(むめい)を育てるという特異な設定のこの物語では、通常は元気なはずの子どもが病気がちの横臥者で、人の助けが必要でありがちな老人が介護者という構図の反転が起きています。
そのためもあってか、義郎は無名を無意識に見下す訳でも、過剰に保護的になりすぎる訳でもなく、事あるごとに迷いつつも、絶妙なバランスでケア的であろうとしていくのですが、それを象徴しているのが義郎が無名を育てる覚悟を決めたシーンです。
無名が産まれたとき、孫はどこかへ旅行へ行ったまま行方不明で、母親も出血多量で死んでしまい、義郎は途方にくれていました。
「義郎は、ミニチュアのような赤ん坊の手を握って小さく動かし、大声で泣き笑いしたい気持ちが爆発し、口から思わず飛び出してきたのが、「二人で頑張ろう、同僚」だった。これまで使ったことのない「同僚」などという言葉がなぜこの瞬間出てきたのだろう。」
思わず「同僚」と呼びかける義郎と無名のあいだには、家父長的な父と子という序列関係はもはや存在していません。その後、無名の父親である孫の飛藻が戻ってきた際、義郎は「自分の子がかわいくないのかと」と詰問するのですが、「俺の子かどうか、どうしてわかる」というつれない返事をした孫の不道徳を責めた後、「思わず陳腐な台詞を吐いてしまった」と自分の創造性のなさに反省し、あらためて「同僚」との関係性に立ち戻っていったのです。
おそらく、ここには迷いや不安さえも創造性へと変えてしまう「ケア的である」ということの、ひとつの可能性が指し示されているのではないでしょうか。
今期のおとめ座もまた、固定的な決めつけに基づく道徳ではなく、より動的な倫理的振る舞いとしてのケアということを自身に取り入れてみるといいでしょう。
参考:多和田葉子『献灯使』(講談社文庫)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「いきであるということ」。

よく海外のセレブが恋人の名前のタトゥーを自分の身体に入れているのを見かけることがありますが、江戸時代の日本でも大坂や京など上方の遊女たちの間では、馴染み客への“愛の証”としてその名前を刺青にする「起請彫り(きしょうぼり)」がブームとなっていたそうです。
そのあたりの呼吸について、九鬼周造は『いきの構造』の中で「「意気地」によって媚態が霊化されていることが「いき」の特色である」という言い方で表わしてみせました。
つまり、これは昔の埴輪などと同じで、本当だったら相手のために死んでしまっていたのが、だんだん象徴化されて気持ちや精神の問題に転化していく過程で現われた習俗であり、「伊達の薄着」とか「宵越しの金は持たねえ」というのと一緒で、形の上だけでもある種の強がりをしてみせることが、「いき」な態度というものの中で大きな比重を持っていたのです。
そもそも、この「いき」という言葉は、高度に洗練された日本人的な美意識を指す言葉で、それを1930年にヨーロッパ帰りの江戸っ子であった九鬼周造が改めてつかまえようと書いたのが『いきの構造』であった訳ですが、九鬼はその根本を「媚態(びたい)」に置いています。では、先に見たような「意気地」は何をしているのかというと、意気地の機能は、
「媚態の存在性を強調し、その光沢を増し、その角度を鋭くする。」
だというのです。つまり、どういう感じの「媚態」かというアクセントをつけて、それにツヤを与え、どこへ向かっているかという角度を鋭くするのだと。
すなわち、たとえ後で後悔するようなことがあったとしても、その時どきに隣にいる相手にえいやと飛び込んでみること。そうして、たまたまの偶然を自分なりの運命へと変えていくこと。そういう感性を、日常生活における規範として立ち上げていけるかどうかということを、九鬼は問うていたのです。
今期のてんびん座もまた、こうした感性の立ち上げをどれだけ人生の問題へと繋げていけるかということがテーマになっていくでしょう。
参考:九鬼周造『いきの構造』(岩波文庫)
そのあたりの呼吸について、九鬼周造は『いきの構造』の中で「「意気地」によって媚態が霊化されていることが「いき」の特色である」という言い方で表わしてみせました。
つまり、これは昔の埴輪などと同じで、本当だったら相手のために死んでしまっていたのが、だんだん象徴化されて気持ちや精神の問題に転化していく過程で現われた習俗であり、「伊達の薄着」とか「宵越しの金は持たねえ」というのと一緒で、形の上だけでもある種の強がりをしてみせることが、「いき」な態度というものの中で大きな比重を持っていたのです。
そもそも、この「いき」という言葉は、高度に洗練された日本人的な美意識を指す言葉で、それを1930年にヨーロッパ帰りの江戸っ子であった九鬼周造が改めてつかまえようと書いたのが『いきの構造』であった訳ですが、九鬼はその根本を「媚態(びたい)」に置いています。では、先に見たような「意気地」は何をしているのかというと、意気地の機能は、
「媚態の存在性を強調し、その光沢を増し、その角度を鋭くする。」
だというのです。つまり、どういう感じの「媚態」かというアクセントをつけて、それにツヤを与え、どこへ向かっているかという角度を鋭くするのだと。
すなわち、たとえ後で後悔するようなことがあったとしても、その時どきに隣にいる相手にえいやと飛び込んでみること。そうして、たまたまの偶然を自分なりの運命へと変えていくこと。そういう感性を、日常生活における規範として立ち上げていけるかどうかということを、九鬼は問うていたのです。
今期のてんびん座もまた、こうした感性の立ち上げをどれだけ人生の問題へと繋げていけるかということがテーマになっていくでしょう。
参考:九鬼周造『いきの構造』(岩波文庫)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「平等であるということ」。

断続的に政府より発令される非常事態宣言において、移動の自由や飲食の自由など、実にさまざまな自由が「不要不急」の大義名分のもと大幅に制限されるなか、そこで特定の人たちだけ選択的に制限されるような不平等が生じてしまっているのではないかという疑義が、このところかなり頻繁に呈されるようになってきたように感じます。
ただし、大抵の場合、それは「自分(たち)は我慢しているのにずるい」といった不満の表明や、単なる八つ当たりに近いものであることも珍しくなく、まだ「どのような意味での平等が社会において実現されれば理想的と言えるのか?」といった問いに対して、その答えが十分に有効な射程で議論されているとは言い難い状況にあるのではないでしょうか。
例えば、何を平等の基準とするかという問題について、1970年代以降大きな影響力をふるったロールズは「基本財(経済的な財だけでなく社会的な自由も含む)」を公平に分配することを求めましたが、1998年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センは『不平等の再検討』の中で、「自由」こそ平等に分配するべきだと述べています。これは、功利主義の立場が実際の効果効用の平等に配慮することを求めるのとも異なる第三の提起と言えるでしょう。
つまり、ロールズが私たちが自分の目標を達成するための手段として基本財に注目し、功利主義が実際に目標が達成されたかどうかに注目するのに対して、センはちょうどそれら二つの中間にあたる、基本財をつかって達成可能な目標の選択肢として何がどれだけ開かれているかに注目したわけです。そして、この選択肢の十分な開かれという指標は、必然的に性や年代、肌の色、障害などの“多様性”への配慮とも深く関係してくるはずですが、その点についてセンは次のように述べています。
「多様性にもさまざまな種類がある。もし全ての多様性に配慮しようとすれば、完全な混乱に陥ってしまうというのもおかしなことではない。実践的な必要からわれわれのとるべき道は、特定の多様性には目をつぶり、より重要な多様性に注目することだろう。このちょっとした世俗的な知恵をあざけるべきではない。事実、不平等の研究において実践的な推論と行動を志向するのであれば、計り知れないほどの多様性の多くを無視せざるを得ない。それぞれの場面で問われるべき問題は、「この文脈で重要な多様性は何か」ということである。」
このセンの指摘は、“多様性”という免罪符のもとに何でもかんでも受け入れなければならない訳ではなく、それによってもし誰かが選択肢が閉じて多大な負担を強いられ、自由の平等が毀損されるのなら、例えばヘイトスピーチを許容する表現の自由のような「特定の多様性」は後回しにされなければならないのです。
その意味で今期のさそり座もまた、その都度自分にとって重要な“多様性”をきちんと取捨選択できるよう、意識して心がけていきたいところです。
参考:アマルティア・セン、池本幸生他訳『不平等の再検討 潜在能力と自由』(岩波現代文庫)
ただし、大抵の場合、それは「自分(たち)は我慢しているのにずるい」といった不満の表明や、単なる八つ当たりに近いものであることも珍しくなく、まだ「どのような意味での平等が社会において実現されれば理想的と言えるのか?」といった問いに対して、その答えが十分に有効な射程で議論されているとは言い難い状況にあるのではないでしょうか。
例えば、何を平等の基準とするかという問題について、1970年代以降大きな影響力をふるったロールズは「基本財(経済的な財だけでなく社会的な自由も含む)」を公平に分配することを求めましたが、1998年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センは『不平等の再検討』の中で、「自由」こそ平等に分配するべきだと述べています。これは、功利主義の立場が実際の効果効用の平等に配慮することを求めるのとも異なる第三の提起と言えるでしょう。
つまり、ロールズが私たちが自分の目標を達成するための手段として基本財に注目し、功利主義が実際に目標が達成されたかどうかに注目するのに対して、センはちょうどそれら二つの中間にあたる、基本財をつかって達成可能な目標の選択肢として何がどれだけ開かれているかに注目したわけです。そして、この選択肢の十分な開かれという指標は、必然的に性や年代、肌の色、障害などの“多様性”への配慮とも深く関係してくるはずですが、その点についてセンは次のように述べています。
「多様性にもさまざまな種類がある。もし全ての多様性に配慮しようとすれば、完全な混乱に陥ってしまうというのもおかしなことではない。実践的な必要からわれわれのとるべき道は、特定の多様性には目をつぶり、より重要な多様性に注目することだろう。このちょっとした世俗的な知恵をあざけるべきではない。事実、不平等の研究において実践的な推論と行動を志向するのであれば、計り知れないほどの多様性の多くを無視せざるを得ない。それぞれの場面で問われるべき問題は、「この文脈で重要な多様性は何か」ということである。」
このセンの指摘は、“多様性”という免罪符のもとに何でもかんでも受け入れなければならない訳ではなく、それによってもし誰かが選択肢が閉じて多大な負担を強いられ、自由の平等が毀損されるのなら、例えばヘイトスピーチを許容する表現の自由のような「特定の多様性」は後回しにされなければならないのです。
その意味で今期のさそり座もまた、その都度自分にとって重要な“多様性”をきちんと取捨選択できるよう、意識して心がけていきたいところです。
参考:アマルティア・セン、池本幸生他訳『不平等の再検討 潜在能力と自由』(岩波現代文庫)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「切断しないでいるということ」。

私たちは何かしら自分たちの身に不幸に見舞われたり、つらい出来事が起きると、どこかで区切りをつけて「前向きに進んでいく」ことをよしとする傾向がありますが、哲学者の國分功一郎は『<責任>の生成―中動態と当事者研究』の中で、ハイデガーの考察を踏まえた上で、そこで無意識的に行われる「過去を自分から切り離そうとする」ことこそが、すなわち「意志」というものの本質に他ならないのだと述べています。
そして、私たちは「個人の意志」というものをどこか過剰に神聖視する一方で、思い出したくない過去や忘れたい記憶を切り離す際にアルコールや薬物など役立てたりもしている訳ですが、國分はむしろ逆に「意志という概念こそ「薬物的」なのではないか」と指摘してみせるのです。
「意志にも薬物のような効果がある。「未来志向」というのは非常にライトなかたちで世の中に浸透しているとも言えますよね。子どもたちに対しても、「未来の夢に向かって羽ばたこう」とかそういうことばかりが言われている。何か思い出したくない過去をみんなで必死に無視しようとしているようにも見えます。過去を忘れ、目を輝かせて、微笑みながら未来の夢に向かってジャンプしていく。それはハイデガー的に言えば、「考えるな、考えるな」と言っているに等しい。」
こうした議論に対し、対談相手を務める小児科医の熊谷晋一郎は長年にわたり当事者研究を共にしてきた綾屋紗月の言葉を引いて、「健常者と言われている人たちが、あまりにもうっかりしているんじゃないか」と言います。つまり、この「うっかり」ということこそが「切断」の別名に他ならず、本来なら非常に手間と時間のかかる内なる声や外部からの情報のすり合わせ過程を、あまりにもあっさりと意志にまとめ上げてしまっており、考えまいとし過ぎているのだ、と。
確かに、私たちはそうした「うっかり」が癖になっていますし、そうして判断を自動化しておいた方がラクだったり省エネ的な意味合いもあるでしょう。ただ、そうして進めている日常に違和感を覚えたり、意味ありげなつまづきに突き当たった際には、あえて過去を切断せずに、自分が感じているさまざまな情報のすり合わせに時間をかけることも大切なのではないでしょうか。
今期のいて座もまた、過剰な意志依存をいったん落ち着かせるべく、意志がもたらすある種のパターナリズムを解除して、かすかな違和感やまとまらなさに踏みとどまってみるべし。
参考:國分功一郎、熊谷晋一郎『<責任>の生成―中動態と当事者研究』(新曜社)
そして、私たちは「個人の意志」というものをどこか過剰に神聖視する一方で、思い出したくない過去や忘れたい記憶を切り離す際にアルコールや薬物など役立てたりもしている訳ですが、國分はむしろ逆に「意志という概念こそ「薬物的」なのではないか」と指摘してみせるのです。
「意志にも薬物のような効果がある。「未来志向」というのは非常にライトなかたちで世の中に浸透しているとも言えますよね。子どもたちに対しても、「未来の夢に向かって羽ばたこう」とかそういうことばかりが言われている。何か思い出したくない過去をみんなで必死に無視しようとしているようにも見えます。過去を忘れ、目を輝かせて、微笑みながら未来の夢に向かってジャンプしていく。それはハイデガー的に言えば、「考えるな、考えるな」と言っているに等しい。」
こうした議論に対し、対談相手を務める小児科医の熊谷晋一郎は長年にわたり当事者研究を共にしてきた綾屋紗月の言葉を引いて、「健常者と言われている人たちが、あまりにもうっかりしているんじゃないか」と言います。つまり、この「うっかり」ということこそが「切断」の別名に他ならず、本来なら非常に手間と時間のかかる内なる声や外部からの情報のすり合わせ過程を、あまりにもあっさりと意志にまとめ上げてしまっており、考えまいとし過ぎているのだ、と。
確かに、私たちはそうした「うっかり」が癖になっていますし、そうして判断を自動化しておいた方がラクだったり省エネ的な意味合いもあるでしょう。ただ、そうして進めている日常に違和感を覚えたり、意味ありげなつまづきに突き当たった際には、あえて過去を切断せずに、自分が感じているさまざまな情報のすり合わせに時間をかけることも大切なのではないでしょうか。
今期のいて座もまた、過剰な意志依存をいったん落ち着かせるべく、意志がもたらすある種のパターナリズムを解除して、かすかな違和感やまとまらなさに踏みとどまってみるべし。
参考:國分功一郎、熊谷晋一郎『<責任>の生成―中動態と当事者研究』(新曜社)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「敗者であるということ」。

20世紀はしばしば「戦争の世紀」とも呼ばれ、人間が行いうる限りの愚行が尽くされたかと思われましたが、21世紀に入ってからの20年を鑑みても、どうやら人間を主役とした現代文明は負の遺産を産み出し続けることになることは間違いないでしょう。
その点、かつて「人間はいまや流行遅れになりはじめた」とうそぶいてみせた思想家エミール・シオランは、生誕こそが、死にまさる真の災厄だという古代人的な発想を通奏低音に一冊の本を書き上げ、それに直訳すれば「生まれたことの不都合について」という題をつけましたが、彼が提示した人間の営為との向きあい方には、資本主義や民主主義のほころびが明らかになりつつある今こそ、ますますその重要度が増しているように思います。
シオランによれば「人間は心の奥のまた奥で、意識以前に住みついていた状態へ、なんとか復帰したいと渇望している」のであり、「歴史とは、そこまで辿りつくために、人間が借用している回り道にすぎない」訳ですが、ではそんな「回り道」を構成する一部として個々の人生において、どんなことを為し得ると言うのでしょうか。
少なくとも、シオラン自身は本を書くということに何がしかの意味を見出していたはずですが、それに関連するであろう断章をいくつか引用してみましょう。
「一冊の本の真価は、扱われる主題の大きさによるのではない(もしそうだったら、神学者たちが飛びぬけて優位に立つことになってしまう)。そうではなくて、偶発的なもの、無意味なものと取り組み、微細なものに習熟する、その流儀にかかっているのだ。重要なものは、かつてどんなささやかな才能をも求めたことがない。」
「ある個人が、天賦の才に恵まれていればいるほど、精神の次元での歩みは遅々たるものになる。才能は内面生活にとって障碍でしかない。」
「肝心なことはひとつしかない。敗者たることを学ぶ―これだけだ。」
今期のやぎ座もまた、自身のものであれ社会全体のものであれ、負の遺産を負の遺産として受け止めつつ、「敗者」だからこそ見出すことのできた偶発的なものや無意味なもの、微細なものをひとつひとつ手に取ってみるといいでしょう。
参考:エミール・シオラン、出口裕弘訳『生誕の災厄』(紀伊国屋書店)
その点、かつて「人間はいまや流行遅れになりはじめた」とうそぶいてみせた思想家エミール・シオランは、生誕こそが、死にまさる真の災厄だという古代人的な発想を通奏低音に一冊の本を書き上げ、それに直訳すれば「生まれたことの不都合について」という題をつけましたが、彼が提示した人間の営為との向きあい方には、資本主義や民主主義のほころびが明らかになりつつある今こそ、ますますその重要度が増しているように思います。
シオランによれば「人間は心の奥のまた奥で、意識以前に住みついていた状態へ、なんとか復帰したいと渇望している」のであり、「歴史とは、そこまで辿りつくために、人間が借用している回り道にすぎない」訳ですが、ではそんな「回り道」を構成する一部として個々の人生において、どんなことを為し得ると言うのでしょうか。
少なくとも、シオラン自身は本を書くということに何がしかの意味を見出していたはずですが、それに関連するであろう断章をいくつか引用してみましょう。
「一冊の本の真価は、扱われる主題の大きさによるのではない(もしそうだったら、神学者たちが飛びぬけて優位に立つことになってしまう)。そうではなくて、偶発的なもの、無意味なものと取り組み、微細なものに習熟する、その流儀にかかっているのだ。重要なものは、かつてどんなささやかな才能をも求めたことがない。」
「ある個人が、天賦の才に恵まれていればいるほど、精神の次元での歩みは遅々たるものになる。才能は内面生活にとって障碍でしかない。」
「肝心なことはひとつしかない。敗者たることを学ぶ―これだけだ。」
今期のやぎ座もまた、自身のものであれ社会全体のものであれ、負の遺産を負の遺産として受け止めつつ、「敗者」だからこそ見出すことのできた偶発的なものや無意味なもの、微細なものをひとつひとつ手に取ってみるといいでしょう。
参考:エミール・シオラン、出口裕弘訳『生誕の災厄』(紀伊国屋書店)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「手を合わせるということ」。

コロナ禍における自殺者の増加や新自由主義経済の弊害にしろ、結果的に現代という時代は「一人のいのち」というものの価値を建前では「地球より重い」などと言ってみる一方で、本音や裏ではこれほどいのちをないがしろにしている時代も他になかったのではないでしょうか。
あるいは、その取り扱いにおける不平等もまた横行しているように感じますし、それに引きずられて自分という存在を低く見てしまう人も多いのではないかと思います。
ただ、それでも普段から特別「鎮魂」とか「弔い」といったことを意識しない人であったとしても、誰かが亡くなった痕跡を直に感じると、なぜだか手を合わせたくなるのはどうしてでしょうか? こう問うと、すぐに日本は古来からアニミズム信仰の国だからという定型的返答で終わってしまうことが多い。
しかし、日本には仏教も入ってきていますし、キリスト教の影響だって想像以上に大きい訳で、そう簡単にまとめることはできないはずで、逆に言えば、これをどう捉えるかというところに、いのちを軽視してもよいという風潮を食い止めるためのよすがとなるものを見出せるはずです。
例えば、宗教学者の山折哲雄はこうした問いに対し、『救いとは何か』という著書の中で、次のように答えています。
「一つの説明の仕方として、それを挨拶の一種として捉えるということもできる。ヨーロッパにおける挨拶と言えば片手を差し出す握手ですが、あくまでそれは人間が対象となっている。もちろん、アジア仏教圏における合掌も挨拶として行われていますが、と同時にその合掌が自然や宇宙に対してもなされているのではないか。この違いは大きいと思う。」
「ならばキリスト教圏で合掌しないかというと、そんなことはありません。手を合わせている聖母マリア像もよくみる。イスラム教でも合掌はあるわけで、そうなると合掌というのはきわめて普遍的な身体行為であるということになる。何ものかに対する畏れの気持ちして、あるいは慎みや呼びかけの行為として、さらには自然からの呼び声に対する応答としてこれを解釈することができるのではないか。」
頭でどうこう考える以前に、身体的レベルで特定の人間をこえて自然や宇宙に対して返してしまう「普遍的な挨拶」であるという、この山折の視点を積極的に言い換えれば、挨拶が自然と形成されるような適切な支援がなされていけば、本来の意味でのいのちの感覚を深めていくこともまたできるのではないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、自己肯定感に対するケアを、ひとつ「挨拶」というところから見直してみるといいかも知れません。
参考:山折哲雄、森岡正博『救いとは何か』(筑摩書房)
あるいは、その取り扱いにおける不平等もまた横行しているように感じますし、それに引きずられて自分という存在を低く見てしまう人も多いのではないかと思います。
ただ、それでも普段から特別「鎮魂」とか「弔い」といったことを意識しない人であったとしても、誰かが亡くなった痕跡を直に感じると、なぜだか手を合わせたくなるのはどうしてでしょうか? こう問うと、すぐに日本は古来からアニミズム信仰の国だからという定型的返答で終わってしまうことが多い。
しかし、日本には仏教も入ってきていますし、キリスト教の影響だって想像以上に大きい訳で、そう簡単にまとめることはできないはずで、逆に言えば、これをどう捉えるかというところに、いのちを軽視してもよいという風潮を食い止めるためのよすがとなるものを見出せるはずです。
例えば、宗教学者の山折哲雄はこうした問いに対し、『救いとは何か』という著書の中で、次のように答えています。
「一つの説明の仕方として、それを挨拶の一種として捉えるということもできる。ヨーロッパにおける挨拶と言えば片手を差し出す握手ですが、あくまでそれは人間が対象となっている。もちろん、アジア仏教圏における合掌も挨拶として行われていますが、と同時にその合掌が自然や宇宙に対してもなされているのではないか。この違いは大きいと思う。」
「ならばキリスト教圏で合掌しないかというと、そんなことはありません。手を合わせている聖母マリア像もよくみる。イスラム教でも合掌はあるわけで、そうなると合掌というのはきわめて普遍的な身体行為であるということになる。何ものかに対する畏れの気持ちして、あるいは慎みや呼びかけの行為として、さらには自然からの呼び声に対する応答としてこれを解釈することができるのではないか。」
頭でどうこう考える以前に、身体的レベルで特定の人間をこえて自然や宇宙に対して返してしまう「普遍的な挨拶」であるという、この山折の視点を積極的に言い換えれば、挨拶が自然と形成されるような適切な支援がなされていけば、本来の意味でのいのちの感覚を深めていくこともまたできるのではないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、自己肯定感に対するケアを、ひとつ「挨拶」というところから見直してみるといいかも知れません。
参考:山折哲雄、森岡正博『救いとは何か』(筑摩書房)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「選ばれていくということ」。
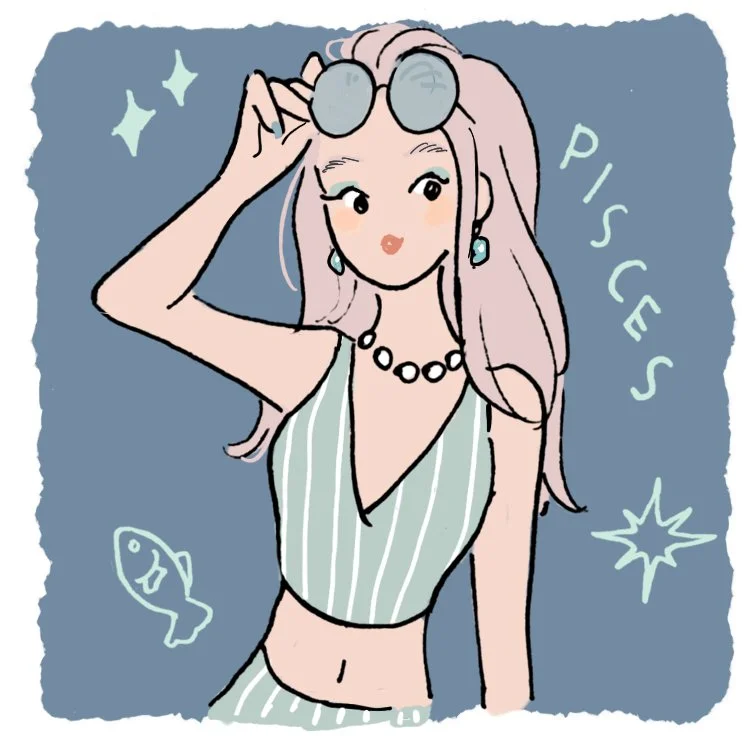
松尾芭蕉が44歳の時に書いた紀行文『笈の小文』には、短いながらも混迷のなかに光明を見出さんとする芭蕉の切々たる抒情があり、確かな響きをもって読むものの胸に迫る力があります。
その書き出しには、「百骸九竅(ひゃくがいきゅうけい)の中に物有り、かりに名付けて風羅坊(ふうらぼう)といふ。誠にうすものの風に破れやすからん事をいふにやあらん。かれ狂句を好むこと久し。終(つい)に生涯のはかりごととなす。」とありますが、この「かれ」とは芭蕉自身のことであり、「狂句」とは俳諧のことを指しています。
当時の俳諧は、まだ今のような伝統文化といったイメージはなく、まったくの新興文化ないしサブカルチャーであって、人が一生を託するに足るような地位を社会において占めていることもなく、芭蕉もはじめから俳諧師(プロの俳人)を目指していた訳ではありませんでした。侍にもなりきれず、僧侶の道もうまくいかず、最後に戻ってきた場所だったのです。そのあたりの心情を一気に詠みあげた箇所を以下に引用したいと思います。
「ある時は倦(うん)で放擲(ほうてき)せん事を思ひ、ある時は進んで人に勝たむ事を誇り、是非胸中にたたこふうて是が為に身安からず。暫(しばら)く身を立てむ事を願へども、これが為にさへられ、暫く学んで愚を暁(さとら)ん事を思へども、是が為に破られ、つひに無能無芸にして只(ただ)此の一筋に繋(つなが)る。」
すなわち、のちに「俳聖」と呼ばれるようになった芭蕉でさえ、俳諧をみずからの才知才能によって選んだのではなかったのです。それは振り切ろうとしても振り切れない一つの業のようなものであり、むしろ芭蕉は俳諧の方から選ばれたようなところがあったのではないでしょうか。
「無能無芸にして」というのは単なる謙遜などではなく、どうしようもないところで俳諧を求めずにはいられなかった芭蕉の魂の叫びであり、だからこそそれ自体が詩となっているのでしょう。
今期のうお座もまた、単に分かりやすい成功やスムーズなキャリアパスを追い求めるのではなく、どうしたら自分自身の人生を一つの詩へと昇華させていくことができるかという視点から捉えなおしてみるといいでしょう。
参考:松尾芭蕉『芭蕉紀行文集』(岩波文庫)
その書き出しには、「百骸九竅(ひゃくがいきゅうけい)の中に物有り、かりに名付けて風羅坊(ふうらぼう)といふ。誠にうすものの風に破れやすからん事をいふにやあらん。かれ狂句を好むこと久し。終(つい)に生涯のはかりごととなす。」とありますが、この「かれ」とは芭蕉自身のことであり、「狂句」とは俳諧のことを指しています。
当時の俳諧は、まだ今のような伝統文化といったイメージはなく、まったくの新興文化ないしサブカルチャーであって、人が一生を託するに足るような地位を社会において占めていることもなく、芭蕉もはじめから俳諧師(プロの俳人)を目指していた訳ではありませんでした。侍にもなりきれず、僧侶の道もうまくいかず、最後に戻ってきた場所だったのです。そのあたりの心情を一気に詠みあげた箇所を以下に引用したいと思います。
「ある時は倦(うん)で放擲(ほうてき)せん事を思ひ、ある時は進んで人に勝たむ事を誇り、是非胸中にたたこふうて是が為に身安からず。暫(しばら)く身を立てむ事を願へども、これが為にさへられ、暫く学んで愚を暁(さとら)ん事を思へども、是が為に破られ、つひに無能無芸にして只(ただ)此の一筋に繋(つなが)る。」
すなわち、のちに「俳聖」と呼ばれるようになった芭蕉でさえ、俳諧をみずからの才知才能によって選んだのではなかったのです。それは振り切ろうとしても振り切れない一つの業のようなものであり、むしろ芭蕉は俳諧の方から選ばれたようなところがあったのではないでしょうか。
「無能無芸にして」というのは単なる謙遜などではなく、どうしようもないところで俳諧を求めずにはいられなかった芭蕉の魂の叫びであり、だからこそそれ自体が詩となっているのでしょう。
今期のうお座もまた、単に分かりやすい成功やスムーズなキャリアパスを追い求めるのではなく、どうしたら自分自身の人生を一つの詩へと昇華させていくことができるかという視点から捉えなおしてみるといいでしょう。
参考:松尾芭蕉『芭蕉紀行文集』(岩波文庫)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ