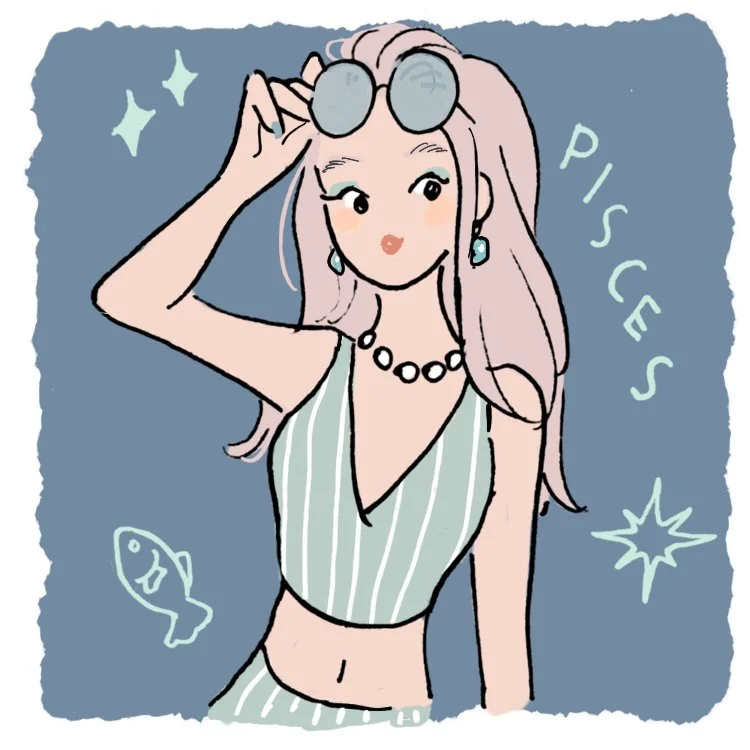【最新12星座占い】<8/22~9/4>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<8/22~9/4>の12星座全体の運勢は?
「地を這う蟻のように」
9月7日に二十四節気が「白露」に変わると、いよいよ体感的にも秋をよりはっきりと感じるようになり、夜長の季節に入って物思いにふける時間も長くなっていくはず。そして、同じ9月7日におとめ座の14度(数えで15度)で新月を迎えます。
そして今回の新月のテーマは、「プライドの置きどころ」。プライドというと、どうしてもこじらせたプライドを守るために社会や他人との関わりを切り捨てたり、過剰防衛の裏返しとしての攻撃性を他者や社会に向けたりといったネガティブなイメージを抱いてしまいますが、とはいえプライドがまったくないというのは誇りに感じているものが何もないということであり、それはみずからの未熟さを改めたり、向上に努めたり、洗練を心がけるつもりがないということに他ならないでしょう。
個人であれ集団であれ、それなりの歴史を重ねていたり、独自の文化のあるところには必ずプライドは生まれるのであって、それは決してなくしたり、馬鹿にしていいものではないはずです。はじめから守りに入って役立たずになるのはつまらないけれど、いくら実力があったとしても、何のプライドも持たず、誰とも何とも繋がらず、どこからも切り離されて生きることほどつまらないこともありません。
新月の時期というのは、種まきにもよく喩えられるのですが、それは新たにこの世界に自分を割り込ませていくということであり、多かれ少なかれ何かにトライしたみたくなるもの。
川端茅舎という俳人に、ちょうど白露の時期に詠んだ「露の玉蟻(あり)たぢたぢになりにけり」という句がありますが、できれば今期の私たちもまた、誰か何かにくじけてひるむことがあったとしても、プライドそのものを捨てることなく、地を這う蟻のように足を前に出していきたいところです。
そして今回の新月のテーマは、「プライドの置きどころ」。プライドというと、どうしてもこじらせたプライドを守るために社会や他人との関わりを切り捨てたり、過剰防衛の裏返しとしての攻撃性を他者や社会に向けたりといったネガティブなイメージを抱いてしまいますが、とはいえプライドがまったくないというのは誇りに感じているものが何もないということであり、それはみずからの未熟さを改めたり、向上に努めたり、洗練を心がけるつもりがないということに他ならないでしょう。
個人であれ集団であれ、それなりの歴史を重ねていたり、独自の文化のあるところには必ずプライドは生まれるのであって、それは決してなくしたり、馬鹿にしていいものではないはずです。はじめから守りに入って役立たずになるのはつまらないけれど、いくら実力があったとしても、何のプライドも持たず、誰とも何とも繋がらず、どこからも切り離されて生きることほどつまらないこともありません。
新月の時期というのは、種まきにもよく喩えられるのですが、それは新たにこの世界に自分を割り込ませていくということであり、多かれ少なかれ何かにトライしたみたくなるもの。
川端茅舎という俳人に、ちょうど白露の時期に詠んだ「露の玉蟻(あり)たぢたぢになりにけり」という句がありますが、できれば今期の私たちもまた、誰か何かにくじけてひるむことがあったとしても、プライドそのものを捨てることなく、地を這う蟻のように足を前に出していきたいところです。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「まともな仕事」。

今回の一連のオリンピック騒ぎで「中抜き」こそが、すっかり日本のお家産業になってしまったことがはっきりした今、何を働くというのか、仕事って何だ、金を稼ぐことなのか?というすこし青臭く感じられるような問いが、それでも多くの人の頭の中で駆け巡ったのではないでしょうか。
つまり、金のなかで経済のなかでほんとうにこころから私たちは満足できるのかと。そして70年代に西荻窪で有機八百屋「長本兄弟商会」を始めた長本光男さんも、かつてそんな問いを抱いたひとりでした。
「一九七五年秋、アメリカから帰ってきた私は、無一文であった。(中略)長かった旅の余韻のなかにいたせいもあっただろうが、まともな仕事というのは、何も会社に就職したり金儲けにはしったりすることだけではないと、徐々に気づきはじめていた。何か自然を相手にするような、私にとって、まともな仕事があるはずだ。それが具体的に何であるか、わからなかったが。」
若くてロングヘアーで、ヒッピー丸出しだった長本さんは、はじめはずいぶん警戒されて、お店を開いても近所の人たちが誰も寄りつかなかったそうですが、長本さんが金のためではなく、プライドを持ってやっていることがほどなくして伝わったのでしょう。今では50年近く続く老舗の八百屋となりました。
「私たちの八百屋は、特別な運動体として発足したのではなかった。どこの町、どこの村にも、ふつうに見られるような八百屋でありたいと願って作られたのだった。(中略)そして、自分たちの労働が重苦しい抑圧にならないようにやりたいと思った。やっていて楽しい労働であればよい、と思った。私にとって「まともな仕事」とは、そういう仕事だった。」
今期のおひつじ座もまた、自分にとって「まともな仕事」とはどんなものだろうか、といま改めて問いを巡らせてみるといいでしょう。
参考:長本光男『みんな八百屋になーれ(就職しないで生きるには 3)』(晶文社)
つまり、金のなかで経済のなかでほんとうにこころから私たちは満足できるのかと。そして70年代に西荻窪で有機八百屋「長本兄弟商会」を始めた長本光男さんも、かつてそんな問いを抱いたひとりでした。
「一九七五年秋、アメリカから帰ってきた私は、無一文であった。(中略)長かった旅の余韻のなかにいたせいもあっただろうが、まともな仕事というのは、何も会社に就職したり金儲けにはしったりすることだけではないと、徐々に気づきはじめていた。何か自然を相手にするような、私にとって、まともな仕事があるはずだ。それが具体的に何であるか、わからなかったが。」
若くてロングヘアーで、ヒッピー丸出しだった長本さんは、はじめはずいぶん警戒されて、お店を開いても近所の人たちが誰も寄りつかなかったそうですが、長本さんが金のためではなく、プライドを持ってやっていることがほどなくして伝わったのでしょう。今では50年近く続く老舗の八百屋となりました。
「私たちの八百屋は、特別な運動体として発足したのではなかった。どこの町、どこの村にも、ふつうに見られるような八百屋でありたいと願って作られたのだった。(中略)そして、自分たちの労働が重苦しい抑圧にならないようにやりたいと思った。やっていて楽しい労働であればよい、と思った。私にとって「まともな仕事」とは、そういう仕事だった。」
今期のおひつじ座もまた、自分にとって「まともな仕事」とはどんなものだろうか、といま改めて問いを巡らせてみるといいでしょう。
参考:長本光男『みんな八百屋になーれ(就職しないで生きるには 3)』(晶文社)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「ただ一人」。

日本の大正期というのは、明治期以上に西洋型の近代社会が急激に浸透していった時代でしたが、それはそれまでの日本文化にプライドを持っていた人たち、特に知的エリート層にとって、自我の崩壊を伴うような暗い歪みを受け止めていかざるを得ないという、鋭い緊張感と隣りあわせの時代だったという点で、どこか令和の今にも通じるものがあるように思います。
例えば、「咳をしても一人」など、自由律俳句で知られる尾崎放哉は、もともと東京帝国大学法学部を卒業し、保険会社の支店次長等を務めたエリートでしたが、権謀術数の渦巻く職場になじめず、深酒を繰り返すようになって辞職し、再就職先でも泥酔で問題を起こして辞め、満州で事業を起こすも病気にかかって帰国。その後は妻とも別れて全国を転々とし、最後は瀬戸内海に浮かぶ小豆島にて、41歳の若さで病没しました。
先の句を詠んだときには、すでに病身であり、苦しく生死の境をさまようような咳であったはずですが、ここでテーマになっているのは単なる孤独感ではありません。近現代の俳句研究者である青木亮人さんの解釈を引用してみましょう。
「「一人」なのはもはや自然で、主張することでもなく、そんな自分に改めて驚いてみせた感じがある。咳をしてもしなくても「一人」で居続ける自分が切なくも可笑しく、どこか抜けているような、今さら「一人」と感傷的になるのがずれているような、それでいて自分を慰めているようで、やはり誰かに構ってほしい甘えや淋しさもあり……従来の「層雲」は洗練された抒情や感傷を旨としましたが、放哉句は乾いた自己凝視で陰翳を帯びたユーモアを漂わせており、極端な短詩も異質でした。」
孤独感というのはあくまで余韻であって、掲句ではその前に「ただ一人」在ることの響きとしての咳があり、それは虚空のなかに確かに自分が存在するという強い実感があったのでしょう。つまり、「ただ一人」であるがゆえに孤独に耐えることができたのです。傲慢奇矯な性格で、トラブルも多かった放哉ですが、掲句には晩年に到達した彼のプライドの置きどころとともに、「ただ一人」であったがゆえににじみ出た他者への目立たない優しさもまた感じられるのではないでしょうか。
今期のおうし座もまた、「乾いた自己凝視」とともに、自分自身のこの世界への置きどころを改めて探ってみることで、案外そこから自分なりのユーモアが生まれてくるかも知れません。
参考:青木亮人『NHKカルチャーラジオ 文学の世界 俳句の変革者たち―正岡子規から俳句甲子園まで (NHKシリーズ)』(NHK出版)
例えば、「咳をしても一人」など、自由律俳句で知られる尾崎放哉は、もともと東京帝国大学法学部を卒業し、保険会社の支店次長等を務めたエリートでしたが、権謀術数の渦巻く職場になじめず、深酒を繰り返すようになって辞職し、再就職先でも泥酔で問題を起こして辞め、満州で事業を起こすも病気にかかって帰国。その後は妻とも別れて全国を転々とし、最後は瀬戸内海に浮かぶ小豆島にて、41歳の若さで病没しました。
先の句を詠んだときには、すでに病身であり、苦しく生死の境をさまようような咳であったはずですが、ここでテーマになっているのは単なる孤独感ではありません。近現代の俳句研究者である青木亮人さんの解釈を引用してみましょう。
「「一人」なのはもはや自然で、主張することでもなく、そんな自分に改めて驚いてみせた感じがある。咳をしてもしなくても「一人」で居続ける自分が切なくも可笑しく、どこか抜けているような、今さら「一人」と感傷的になるのがずれているような、それでいて自分を慰めているようで、やはり誰かに構ってほしい甘えや淋しさもあり……従来の「層雲」は洗練された抒情や感傷を旨としましたが、放哉句は乾いた自己凝視で陰翳を帯びたユーモアを漂わせており、極端な短詩も異質でした。」
孤独感というのはあくまで余韻であって、掲句ではその前に「ただ一人」在ることの響きとしての咳があり、それは虚空のなかに確かに自分が存在するという強い実感があったのでしょう。つまり、「ただ一人」であるがゆえに孤独に耐えることができたのです。傲慢奇矯な性格で、トラブルも多かった放哉ですが、掲句には晩年に到達した彼のプライドの置きどころとともに、「ただ一人」であったがゆえににじみ出た他者への目立たない優しさもまた感じられるのではないでしょうか。
今期のおうし座もまた、「乾いた自己凝視」とともに、自分自身のこの世界への置きどころを改めて探ってみることで、案外そこから自分なりのユーモアが生まれてくるかも知れません。
参考:青木亮人『NHKカルチャーラジオ 文学の世界 俳句の変革者たち―正岡子規から俳句甲子園まで (NHKシリーズ)』(NHK出版)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「漠然とした「場」としての<わたし>」。

わたしたちのプライドが変な仕方でこじれてしまうのはなぜか。その要因のひとつとして、<わたし>すなわち、「わたしが、いま、ここでなにかを知覚している」という出来事を、わたしたちがついつい「もの」として捉えてしまうことが考えられるのではないでしょうか。
つまり、西洋の科学が金科玉条としてきた、対象を客観的に見ることができると言うときの客観が「もの」であり、「もの」においては主観と客観がぱっきり分かれていて、そこに「人間と自然」とか、「私とあなた」、「自分事と他人事」などの構図が重なっていく訳です。
その点、あくまで例外なく、すべてを「こと」として、すなわち、すべてを客観的に固定することなく、きわめて不安定な仕方でとらえることを自身の仕事上の姿勢としていた哲学者のノース・ホワイトヘッドは<わたし>についてもまた、ほかのもろもろの現象と同じように、精神的なものや身体的なものが、時々刻々と変容し続けている、つかみどころのない曖昧な状態であると考えていました。
だって私たちは、睡眠もすれば泥酔もする。何かに集中していたかと思えば、すぐに呆然としてしまう。精神や身体といわれているものが経験していることの総体としての<わたし>は、つねに複雑にいり乱れており、ホワイトヘッドはそうしたわたしたちのありふれた事態について、身体を例に挙げ次のように述べていたりするのです。
「たとえば、われわれの身体は自分自身の個的存在を超えて位置している。けれども、その身体は、個的存在の一部なのだ。われわれは自分のことをこう思っている。つまり、人間というのは、身体で営む生活ととても親密にからみあっているから、身体と精神との複合体だ、と。だが、身体は外界の一部なのであって、外界と連続している。実際、身体は自然のなかのなにか、たとえば、川とか、山とか、雲といったものとおなじように、まさに自然の一部なのだ。また、たとえわれわれが過度に厳密になろうとしても、身体がどこからはじまり、外部の自然がどこで終わるのか、といったことを定義することはできない。」
プライドという言葉にただよう、閉鎖的でがんじがらめなムードは、こうした外界と連続した身体的背景の次元において、どこかに雲散霧消してしまう。もしかしたらふたご座というのは、精神的な変化やそれを言葉で捉えたり発したりすることを好むがゆえに、こうした身体的背景の次元の出来事にうといのかも知れません。
その意味で、今期のふたご座は、自身の身体を精神状態をもふくめた、ある漠然とした「場」として意識してみるといいでしょう。
参考:ホワイトヘッド、藤川吉見・伊藤重行訳『思考の諸様態』(松籟社)
つまり、西洋の科学が金科玉条としてきた、対象を客観的に見ることができると言うときの客観が「もの」であり、「もの」においては主観と客観がぱっきり分かれていて、そこに「人間と自然」とか、「私とあなた」、「自分事と他人事」などの構図が重なっていく訳です。
その点、あくまで例外なく、すべてを「こと」として、すなわち、すべてを客観的に固定することなく、きわめて不安定な仕方でとらえることを自身の仕事上の姿勢としていた哲学者のノース・ホワイトヘッドは<わたし>についてもまた、ほかのもろもろの現象と同じように、精神的なものや身体的なものが、時々刻々と変容し続けている、つかみどころのない曖昧な状態であると考えていました。
だって私たちは、睡眠もすれば泥酔もする。何かに集中していたかと思えば、すぐに呆然としてしまう。精神や身体といわれているものが経験していることの総体としての<わたし>は、つねに複雑にいり乱れており、ホワイトヘッドはそうしたわたしたちのありふれた事態について、身体を例に挙げ次のように述べていたりするのです。
「たとえば、われわれの身体は自分自身の個的存在を超えて位置している。けれども、その身体は、個的存在の一部なのだ。われわれは自分のことをこう思っている。つまり、人間というのは、身体で営む生活ととても親密にからみあっているから、身体と精神との複合体だ、と。だが、身体は外界の一部なのであって、外界と連続している。実際、身体は自然のなかのなにか、たとえば、川とか、山とか、雲といったものとおなじように、まさに自然の一部なのだ。また、たとえわれわれが過度に厳密になろうとしても、身体がどこからはじまり、外部の自然がどこで終わるのか、といったことを定義することはできない。」
プライドという言葉にただよう、閉鎖的でがんじがらめなムードは、こうした外界と連続した身体的背景の次元において、どこかに雲散霧消してしまう。もしかしたらふたご座というのは、精神的な変化やそれを言葉で捉えたり発したりすることを好むがゆえに、こうした身体的背景の次元の出来事にうといのかも知れません。
その意味で、今期のふたご座は、自身の身体を精神状態をもふくめた、ある漠然とした「場」として意識してみるといいでしょう。
参考:ホワイトヘッド、藤川吉見・伊藤重行訳『思考の諸様態』(松籟社)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「社会を変えるためにこそ勉強する」。

「どうせ変わりっこない」。そんな諦めを、いつからか日本人は心の深いところにくさびのように打ち込まれ、どこかで流されるように社会の移り行きを眺めてきたように思います。
しかし、ここのところのコロナ感染症への水際対策やワクチン接種の推進、オリンピックをめぐる一連の権力サイドの対応や言動の中に、とうとう行き着くところまできてしまったいう思いを抱いた人は少なくないのではないでしょうか。
その点、竹端寛の『枠組み外しの旅――「個性化」が変える福祉社会』は、文字通り社会福祉の学術書でありながらも、「思い込みという枠にとらわれた状態から脱するにはどうしたらいいのか?」という、まさに今の日本社会において誰もが無関係でいられないテーマを扱っていきます。
著者の竹端さんは、障碍者福祉政策について研究していくなかで、「仕方ない」「どうせ」といった言葉に含まれた諦めに、自分自身でも気付いていなかったりする枠組みに何度も直面し、たとえば「重度障害者は施設に収容するべき」といった固い通念がいかに打ち破られたかについて丁寧に書き進めてくれているのですが、何と言っても本書の面白さは、そこに著者自身のダイエット経験を何気なく重ねていくところにあります。
「きっかけは、ある医者から告げられた一言だった。
「あなたは“食毒”、つまり食べ過ぎ、です。」
「食べ過ぎ」という事実に、「食毒」というラベルを貼るだけで、世界が違って見えてくる。(中略)「食べ過ぎ」によって体内に消化しきれない栄養素をため込むことが「毒」である、という「食毒」概念は、自己正当化の論理を木っ端微塵に打ち砕く。」
こうして著者は「食毒」という言葉を知ったことで、食べることが無条件にプラスだと信じていた自身の「思い込み」が自分を縛っていたことに気づかされ、太っている自分を変える気になったのだと言います。そう、「社会を変える」ためには、「何が社会を縛っているのか?」を知って、確かに存在してきた思考の枠を、見えない抑圧を見えるようにすること、すなわち「勉強」から始まるのだ、と。
「社会を変えようとする前に、問題の一部は自分自身であることに気づき、まず自分を変えることからこそ、「自由」に至る回路が開かれる」
今期のかに座もまた、そうして「自由」に至る回路を開いていくべく、つねに勉強し続けてこその自分なのだというところから、今目の前にある事態にぶつかっていきたいところです。
参考:竹端寛『枠組み外しの旅――「個性化」が変える福祉社会』(青灯社)
しかし、ここのところのコロナ感染症への水際対策やワクチン接種の推進、オリンピックをめぐる一連の権力サイドの対応や言動の中に、とうとう行き着くところまできてしまったいう思いを抱いた人は少なくないのではないでしょうか。
その点、竹端寛の『枠組み外しの旅――「個性化」が変える福祉社会』は、文字通り社会福祉の学術書でありながらも、「思い込みという枠にとらわれた状態から脱するにはどうしたらいいのか?」という、まさに今の日本社会において誰もが無関係でいられないテーマを扱っていきます。
著者の竹端さんは、障碍者福祉政策について研究していくなかで、「仕方ない」「どうせ」といった言葉に含まれた諦めに、自分自身でも気付いていなかったりする枠組みに何度も直面し、たとえば「重度障害者は施設に収容するべき」といった固い通念がいかに打ち破られたかについて丁寧に書き進めてくれているのですが、何と言っても本書の面白さは、そこに著者自身のダイエット経験を何気なく重ねていくところにあります。
「きっかけは、ある医者から告げられた一言だった。
「あなたは“食毒”、つまり食べ過ぎ、です。」
「食べ過ぎ」という事実に、「食毒」というラベルを貼るだけで、世界が違って見えてくる。(中略)「食べ過ぎ」によって体内に消化しきれない栄養素をため込むことが「毒」である、という「食毒」概念は、自己正当化の論理を木っ端微塵に打ち砕く。」
こうして著者は「食毒」という言葉を知ったことで、食べることが無条件にプラスだと信じていた自身の「思い込み」が自分を縛っていたことに気づかされ、太っている自分を変える気になったのだと言います。そう、「社会を変える」ためには、「何が社会を縛っているのか?」を知って、確かに存在してきた思考の枠を、見えない抑圧を見えるようにすること、すなわち「勉強」から始まるのだ、と。
「社会を変えようとする前に、問題の一部は自分自身であることに気づき、まず自分を変えることからこそ、「自由」に至る回路が開かれる」
今期のかに座もまた、そうして「自由」に至る回路を開いていくべく、つねに勉強し続けてこその自分なのだというところから、今目の前にある事態にぶつかっていきたいところです。
参考:竹端寛『枠組み外しの旅――「個性化」が変える福祉社会』(青灯社)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「不自由さをあえて選ぶ」。

プライドという言葉はしばしば見栄と混同されがちですが、後者が外観を気にして、実際よりもよく見せようとうわべや体裁だけを取り繕うという文脈で使われるのに対して、前者は本来、いかに日ごろから自分自身や仕事に矜持や誇りを込めているか、という文脈で使われるものです。
見た目よりも中身にとことんこだわるのがプライドであって、それはそのまま、しし座の人たちが何よりも大事にしている“魂の熱源”、すなわち周囲の人たちに放射するエネルギーの源とも直結しているように思います。
そして、これと似た話を、かつて「一国の文化はその国民の日々の生活に最もよく反映される」という言い方で書いていたのが、実際に日本各地を巡った経験から日本がすばらしい手仕事の国であることへの認識を呼びかけた民藝運動の父・柳宗悦でした。
彼は「人間の真価は、その日常の暮らしの中に、最も正直に示される」と前置きした上で、日々の暮らしの中で用いられる器ものなどが、何か卑しいものとされ、軽くみられる風潮を受け、そうした実用品を「不自由な藝術」と呼びましたが、しかし一方で、そうした「不自由さ」のためにかえって現れてくる美しさがあるのだとして、次のように述べたのです。
「実は不自由とか束縛とかいうのは、人間の立場からする嘆きであって、自然の立場に帰ってみますと、まるで違う見方が成り立ちます。用途に適うということは、必然の要求に応じるということであります。材料の性質に制約せられるとは、自然の贈物に任せきるということであります。手法に服従するということは、当然な理法を守るということになります。人間からすると不自由ともいえましょうが、自然からすると一番当然な道を歩くことを意味します。それ故、かえって誤りの少ない安全な道を進むことになって来ます。ここで不自由さこそ、かえって確実さを受取る所以になるのを悟られるでしょう。」
つまり、実用的な品物に美しさが見られるのも、人間側の自由やわがままよりも、自然の理法や必然にかなっているからであり、柳はこれを人間の力を超えた「他力の美しさ」とも呼んでいました。
今期のしし座もまた、一見すると不自由に見える制約や服従のうちにすすんで入っていくことで、かえって大きな美や、大きな熱源を養っていくことを改めて心がけていきたいところです。
参考:柳宗悦『手仕事の日本』(岩波文庫)
見た目よりも中身にとことんこだわるのがプライドであって、それはそのまま、しし座の人たちが何よりも大事にしている“魂の熱源”、すなわち周囲の人たちに放射するエネルギーの源とも直結しているように思います。
そして、これと似た話を、かつて「一国の文化はその国民の日々の生活に最もよく反映される」という言い方で書いていたのが、実際に日本各地を巡った経験から日本がすばらしい手仕事の国であることへの認識を呼びかけた民藝運動の父・柳宗悦でした。
彼は「人間の真価は、その日常の暮らしの中に、最も正直に示される」と前置きした上で、日々の暮らしの中で用いられる器ものなどが、何か卑しいものとされ、軽くみられる風潮を受け、そうした実用品を「不自由な藝術」と呼びましたが、しかし一方で、そうした「不自由さ」のためにかえって現れてくる美しさがあるのだとして、次のように述べたのです。
「実は不自由とか束縛とかいうのは、人間の立場からする嘆きであって、自然の立場に帰ってみますと、まるで違う見方が成り立ちます。用途に適うということは、必然の要求に応じるということであります。材料の性質に制約せられるとは、自然の贈物に任せきるということであります。手法に服従するということは、当然な理法を守るということになります。人間からすると不自由ともいえましょうが、自然からすると一番当然な道を歩くことを意味します。それ故、かえって誤りの少ない安全な道を進むことになって来ます。ここで不自由さこそ、かえって確実さを受取る所以になるのを悟られるでしょう。」
つまり、実用的な品物に美しさが見られるのも、人間側の自由やわがままよりも、自然の理法や必然にかなっているからであり、柳はこれを人間の力を超えた「他力の美しさ」とも呼んでいました。
今期のしし座もまた、一見すると不自由に見える制約や服従のうちにすすんで入っていくことで、かえって大きな美や、大きな熱源を養っていくことを改めて心がけていきたいところです。
参考:柳宗悦『手仕事の日本』(岩波文庫)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「火を起こす」。

自分の星座で新月が起きていく時期というのは、さながらオリンピックの始まりに聖火を灯すように、たとえどんなにささやかなものであったとしても、みずからに新たな精神性を与え、新たな誓いを立てていくのに最もふさわしく、ごく自然なタイミングなのだと言えます。
しかし、電気やガスでワンタッチ式に火を使うことに慣れきってしまった現代人は、みずからの手で火を起こす術をほとんど忘れてしまったようにも思います。
例えば、そうした現代文明のもたらす決定的な危機とその先の世界の在り方を数十年来にわたって静かに訴え続けてきた屋久島在住の詩人・山尾省三は「火を焚きなさい」という詩を、次のような書き出しで始めています。
「山に夕闇がせまる/子供達よ/ほら もう夜が背中まできている/火を焚きなさい/お前達の心残りの遊びをやめて/大昔の心にかえり/火を焚きなさい」
原初、人間は火を焚くことで他の動物から一線を画しました。だから、火を焚くことができれば、それでもう人間なのです。
「少しくらい煙くたって仕方ない/がまんして しっかり火を燃やしなさい/やがて調子がでてくると/ほら お前達の今の心のようなオレンジ色の炎が/いっしんに燃え立つだろう/そうしたら じっとその火を見詰めなさい/いつのまにか――/背後から 夜がお前をすっぽりつつんでいる/夜がすっぽりとお前をつつんだ時こそ/不思議の時/火が 永遠の物語を始める時なのだ」
そう、火は物語をもたらす。それは「父さんの自慢話のよう」でもなく、「テレビで見れるもの」でもなく、あくまで「自身の裸の眼と耳と心で聴く」、自分のための「不思議な物語」なのだと。山尾は続けてこう促します。
「注意深く ていねいに/火を焚きなさい/火がいっしんに燃え立つように/けれどもあまりぼうぼう燃えないように/静かな気持ちで 火を焚きなさい」
今期のおとめ座もまた、ひとつこんな式次第で新たな火を焚き、物語を強引に始めるのでも、ただ傍観するのでもない仕方で、その過程を見詰めてみるといいでしょう。
参考:山尾省三、ゲーリー・スナイダー『聖なる地球のつどいかな』(山と渓谷社)
しかし、電気やガスでワンタッチ式に火を使うことに慣れきってしまった現代人は、みずからの手で火を起こす術をほとんど忘れてしまったようにも思います。
例えば、そうした現代文明のもたらす決定的な危機とその先の世界の在り方を数十年来にわたって静かに訴え続けてきた屋久島在住の詩人・山尾省三は「火を焚きなさい」という詩を、次のような書き出しで始めています。
「山に夕闇がせまる/子供達よ/ほら もう夜が背中まできている/火を焚きなさい/お前達の心残りの遊びをやめて/大昔の心にかえり/火を焚きなさい」
原初、人間は火を焚くことで他の動物から一線を画しました。だから、火を焚くことができれば、それでもう人間なのです。
「少しくらい煙くたって仕方ない/がまんして しっかり火を燃やしなさい/やがて調子がでてくると/ほら お前達の今の心のようなオレンジ色の炎が/いっしんに燃え立つだろう/そうしたら じっとその火を見詰めなさい/いつのまにか――/背後から 夜がお前をすっぽりつつんでいる/夜がすっぽりとお前をつつんだ時こそ/不思議の時/火が 永遠の物語を始める時なのだ」
そう、火は物語をもたらす。それは「父さんの自慢話のよう」でもなく、「テレビで見れるもの」でもなく、あくまで「自身の裸の眼と耳と心で聴く」、自分のための「不思議な物語」なのだと。山尾は続けてこう促します。
「注意深く ていねいに/火を焚きなさい/火がいっしんに燃え立つように/けれどもあまりぼうぼう燃えないように/静かな気持ちで 火を焚きなさい」
今期のおとめ座もまた、ひとつこんな式次第で新たな火を焚き、物語を強引に始めるのでも、ただ傍観するのでもない仕方で、その過程を見詰めてみるといいでしょう。
参考:山尾省三、ゲーリー・スナイダー『聖なる地球のつどいかな』(山と渓谷社)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「ラディカル・ウィル」。
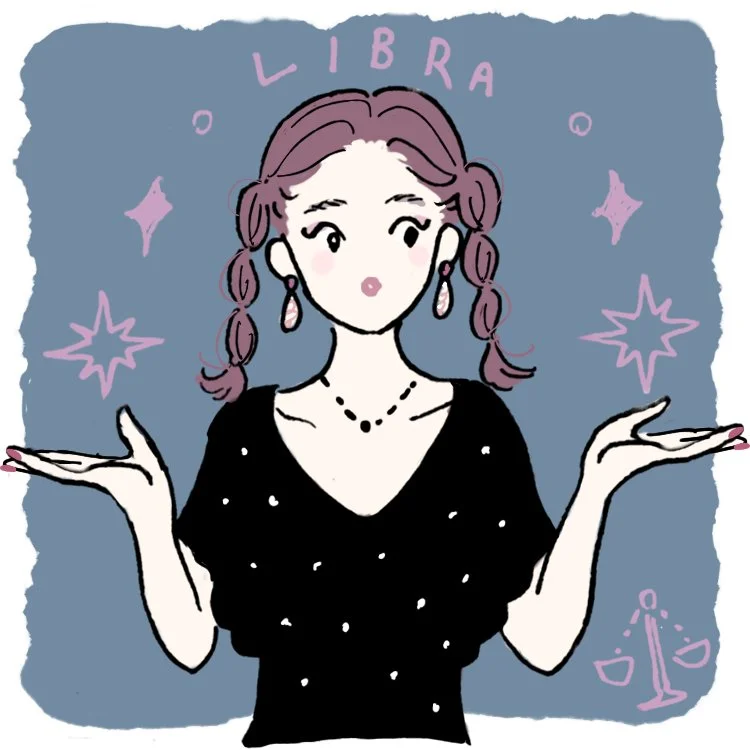
近年の「自己責任」という言葉の使われ方とともに、私たちは自分たちの一挙手一投足を知らず知らずみずから重くしてしまっているのかも知れません。つまり、何かと「強くなければいけない」という呪縛で自分を縛っていたり、言動には「必然性がなければならない」という思い込みに囲われているのではないでしょうか。
松岡正剛はかつて『フラジャイル』という著作のなかで、それと正反対の発想として「ラディカル・ウィル」という言葉を使っていました。ラディカルはラテン語の「根」や「起源」から派生した言葉で、ウィル(意志)はフランス語のヴォロンテ(意志)にも繋がってボランティアの語源にもなっていますが、それは「ふと」何かを選んでしまったり、「はっと」して言葉が漏れでたり、といった仕方での「自発」を意味しているのだと言います。
「自発とはそういうことである。なにも自己意志に頼っているのではない。そんなものに頼れば、ただ自分が重たくなるだけだ。そうではなく、「むこう」からやってくる何者かの速度に乗ってそのまま加速の流れに入り、いっとき自己の他端に降りてみて、そこから急速にどこかへ飛び出してしまうことを、自発といい、発根というのでなければならなかった。けれどもそのとき、ほんのすこしのことなのだが、悲しくなるときがある。寂しくなるときがある。弱音を吐きたくなるものなのだ。しかし、そのときこそ唯一の時熟であった。弱音とともにわれわれは、「よそ」や「ほか」という未知の音信にやっと出会っているからである。」
松岡はここで、ラディカル・ウィルを「どこかそれたところから猛烈なスピードでやってきて、われわれを貫き、またどこかへ去ろうとしているもの」、「微細な疾走者」として思い描いているのですが、それに差し当たり近いものとしてニュートリノをあげています。
「太陽と地球をすっかり鉄板などで埋めつくしたとしても、ニュートリノは毎秒一つか二つのわりあいで、われわれの体をも貫通し、地球の裏側に抜け去っていく。その途中で、何人かの体や脳をほぼ同時に貫きもする。仮に気分のシンクロニシティ(同期性)というものがあるとするなら、それはニュートリノの貫通のおかげかも知れないのである。」
今期のてんびん座もまた、逢うべき相手を決めるにしろ、喫茶店で紅茶か珈琲のどちらを頼むか決めるにしろ、ニュートリノの貫通によって脳のシナプスが発根するような、ささやかで微細な感覚から「自発」してみるといいかも知れません。
参考:松岡正剛『フラジャイル 弱さからの出発』(ちくま学芸文庫)
松岡正剛はかつて『フラジャイル』という著作のなかで、それと正反対の発想として「ラディカル・ウィル」という言葉を使っていました。ラディカルはラテン語の「根」や「起源」から派生した言葉で、ウィル(意志)はフランス語のヴォロンテ(意志)にも繋がってボランティアの語源にもなっていますが、それは「ふと」何かを選んでしまったり、「はっと」して言葉が漏れでたり、といった仕方での「自発」を意味しているのだと言います。
「自発とはそういうことである。なにも自己意志に頼っているのではない。そんなものに頼れば、ただ自分が重たくなるだけだ。そうではなく、「むこう」からやってくる何者かの速度に乗ってそのまま加速の流れに入り、いっとき自己の他端に降りてみて、そこから急速にどこかへ飛び出してしまうことを、自発といい、発根というのでなければならなかった。けれどもそのとき、ほんのすこしのことなのだが、悲しくなるときがある。寂しくなるときがある。弱音を吐きたくなるものなのだ。しかし、そのときこそ唯一の時熟であった。弱音とともにわれわれは、「よそ」や「ほか」という未知の音信にやっと出会っているからである。」
松岡はここで、ラディカル・ウィルを「どこかそれたところから猛烈なスピードでやってきて、われわれを貫き、またどこかへ去ろうとしているもの」、「微細な疾走者」として思い描いているのですが、それに差し当たり近いものとしてニュートリノをあげています。
「太陽と地球をすっかり鉄板などで埋めつくしたとしても、ニュートリノは毎秒一つか二つのわりあいで、われわれの体をも貫通し、地球の裏側に抜け去っていく。その途中で、何人かの体や脳をほぼ同時に貫きもする。仮に気分のシンクロニシティ(同期性)というものがあるとするなら、それはニュートリノの貫通のおかげかも知れないのである。」
今期のてんびん座もまた、逢うべき相手を決めるにしろ、喫茶店で紅茶か珈琲のどちらを頼むか決めるにしろ、ニュートリノの貫通によって脳のシナプスが発根するような、ささやかで微細な感覚から「自発」してみるといいかも知れません。
参考:松岡正剛『フラジャイル 弱さからの出発』(ちくま学芸文庫)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「聖なる仕事」。

外出時や人と会う際にマスクをすることが当たり前のエチケットとなり、そこにワクチン接種の有無も加わるようになってきたことで、日本社会はいま改めて「穢(けが)れ」という概念のリアリティを体感的に取り戻しているのだとも言えるかもしれません。
そしてこうした「穢れ」とセットになってきたのが差別や賤視でもあった訳ですが、民俗学者の小松和彦は『鬼がつくった国・日本』において、「忘れてはならないのは、非農業民がすべて賤民であったわけじゃない」のだと述べています。
この場合の「非農業民」とは、芸能者や職人のことですが、彼らがすべて差別されていた訳ではなくて、「主として「死」を穢れとする観念、不治の病を持った人を忌避する観念によって具現化」されたことで、室町時代に賤視される職人が増えた。彼らの多くは山の民や川の民、あるいは海の民だった訳ですが、山や海は異界すなわちあの世と地続きの死の世界と見なされていましたから、これは当然と言えば当然の話なんですね。
では、彼らはどうしたか。黙って賤視を受け入れて泣き寝入りしていたかと言うと、そうではなくて、異界も含めた根源的な支配者としての「土地の主」である天皇によって職業の保証を受けることで、つまり世俗的権力とは異なる「聖」なる存在に認可されることで、天皇と精神的な共同性を獲得し、むしろ人気と羨望の的となっていったのだそうです。
というのも、たとえば寺社の造営や橋や道路などの社会事業などは、確かな技術をもった職人や芸人たちの力を多数集結しなければ不可能であり、彼らは賤視と隣りあわせの非農業民でありつつも、「聖なる仕事」に従事する異形異類の「鬼」であり、恐れられつつもありがたい存在でもあった訳です。
社会において「穢れ」への忌避が強まれば、結局誰かがその穢れを負いつつ、見えないところで社会を支えなければなりません。今期のさそり座の人たちもまた、こうしたかつて「鬼」と呼ばれた存在にどこかで通じるところが出てくるかも知れません。
参考:小松和彦・内藤正敏『鬼がつくった国・日本』(光文社)
そしてこうした「穢れ」とセットになってきたのが差別や賤視でもあった訳ですが、民俗学者の小松和彦は『鬼がつくった国・日本』において、「忘れてはならないのは、非農業民がすべて賤民であったわけじゃない」のだと述べています。
この場合の「非農業民」とは、芸能者や職人のことですが、彼らがすべて差別されていた訳ではなくて、「主として「死」を穢れとする観念、不治の病を持った人を忌避する観念によって具現化」されたことで、室町時代に賤視される職人が増えた。彼らの多くは山の民や川の民、あるいは海の民だった訳ですが、山や海は異界すなわちあの世と地続きの死の世界と見なされていましたから、これは当然と言えば当然の話なんですね。
では、彼らはどうしたか。黙って賤視を受け入れて泣き寝入りしていたかと言うと、そうではなくて、異界も含めた根源的な支配者としての「土地の主」である天皇によって職業の保証を受けることで、つまり世俗的権力とは異なる「聖」なる存在に認可されることで、天皇と精神的な共同性を獲得し、むしろ人気と羨望の的となっていったのだそうです。
というのも、たとえば寺社の造営や橋や道路などの社会事業などは、確かな技術をもった職人や芸人たちの力を多数集結しなければ不可能であり、彼らは賤視と隣りあわせの非農業民でありつつも、「聖なる仕事」に従事する異形異類の「鬼」であり、恐れられつつもありがたい存在でもあった訳です。
社会において「穢れ」への忌避が強まれば、結局誰かがその穢れを負いつつ、見えないところで社会を支えなければなりません。今期のさそり座の人たちもまた、こうしたかつて「鬼」と呼ばれた存在にどこかで通じるところが出てくるかも知れません。
参考:小松和彦・内藤正敏『鬼がつくった国・日本』(光文社)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「怠ける自由もあっていい」。

「そんなこと、科学的には何も証明されていないことでしょう」
こうした言説において、正しさや真理がある種の強い強制力を発揮するのを目の当たりにすることが、最近とみに増えてきたように思います。しかし、真理が客観的にあると思うことで安心したくなる気持ちもわかりますが、ある命題に対する真理を成立させる根拠や原因は、いつも客観的に存在するとは限りません。
むしろこういう時勢だからこそ、命題やそれを成立させる言葉というのは、きわめて人為的に構成されたものだということも忘れてはいけないように思います。つまり、命題というのは否定を受容することができ、疑問文への変換を容易に認めることで操作に適しており、その意味で、事物のように客観的に見える答え(科学的な証明)はすぐに安心しようとする人間の心が作り出した人為的な産物に過ぎないのだとも言えるのです。
この点について、哲学者の山内志朗は『小さな倫理学入門』に収録された「人生に目的はない」というエッセイの中で、「「人生の目的とは何か」「幸福とは何か」といった問いに対して、主要な目的(dominant ends)といったものはありませんし、答えの多様性を許容し、答えがないからこそ、人生は生きるに値する」のだと前置きした上で、弱者に優しい社会を促すリベラリズム(自由主義)の立場について、次のように述べています。
「リベラリズムは、そういった目的を自由に設定できる者こそ、人格としての尊厳を有し、その尊厳を基盤として自己の価値を打ち立てられると考えます。」
「具体的に措定された目的を破壊し続けながらも、新たな目的を一人一人が勇気を持って作り続けようとすることが、自由の意味でしょう。(中略)真理は生命を凌ぐ価値を持っているわけではありません。真理への暴力的駆り立てに対しては怠けた方がよいのかもしれません。」
今期のいて座もまた、できるだけ正しさや真理の強制力からできるだけ自由なところで、勝手に決められた目的を破壊したり、怠けたり、新たな目的を作ったりしてみるといいでしょう。
参考:山内志朗『小さな倫理学入門』(慶應義塾大学三田哲学会叢書)
こうした言説において、正しさや真理がある種の強い強制力を発揮するのを目の当たりにすることが、最近とみに増えてきたように思います。しかし、真理が客観的にあると思うことで安心したくなる気持ちもわかりますが、ある命題に対する真理を成立させる根拠や原因は、いつも客観的に存在するとは限りません。
むしろこういう時勢だからこそ、命題やそれを成立させる言葉というのは、きわめて人為的に構成されたものだということも忘れてはいけないように思います。つまり、命題というのは否定を受容することができ、疑問文への変換を容易に認めることで操作に適しており、その意味で、事物のように客観的に見える答え(科学的な証明)はすぐに安心しようとする人間の心が作り出した人為的な産物に過ぎないのだとも言えるのです。
この点について、哲学者の山内志朗は『小さな倫理学入門』に収録された「人生に目的はない」というエッセイの中で、「「人生の目的とは何か」「幸福とは何か」といった問いに対して、主要な目的(dominant ends)といったものはありませんし、答えの多様性を許容し、答えがないからこそ、人生は生きるに値する」のだと前置きした上で、弱者に優しい社会を促すリベラリズム(自由主義)の立場について、次のように述べています。
「リベラリズムは、そういった目的を自由に設定できる者こそ、人格としての尊厳を有し、その尊厳を基盤として自己の価値を打ち立てられると考えます。」
「具体的に措定された目的を破壊し続けながらも、新たな目的を一人一人が勇気を持って作り続けようとすることが、自由の意味でしょう。(中略)真理は生命を凌ぐ価値を持っているわけではありません。真理への暴力的駆り立てに対しては怠けた方がよいのかもしれません。」
今期のいて座もまた、できるだけ正しさや真理の強制力からできるだけ自由なところで、勝手に決められた目的を破壊したり、怠けたり、新たな目的を作ったりしてみるといいでしょう。
参考:山内志朗『小さな倫理学入門』(慶應義塾大学三田哲学会叢書)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「働かないことの幸せ」。

現代の日本社会には、どこかで「暇そうにしてたら格好悪い」という考えが根づよくはびこっているように思います。「働かざるもの食うべからず」な勤勉さというのも、もちろん悪いものではないですが、それでもコロナ禍になってからこっち側、忙しくしようにも仕事がないという人も多いのではないでしょうか。
それで、あんまり暇にしているのもどうかということで、仕事をしているフリなんかして、バツの悪い思いをしているくらいなら、いっそのこと水木しげるのように、反対方向に思いきり舵を切ってみるのも手ではないかと。
彼の自伝やSFなんかも味わい深いのですが、インタビューで好き勝手なことを言っている時の水木さんというのは、またそれとは異質の輝きがあるようにおります。
「南方の人間は、朝起きると朝からゲームをやったりして、遊んでるんですよ。そして午前中だけ働けばいいんです。畑にちょっと歩いて行って、イモを植えときゃいいんです。(中略)彼らの考えの中には働かないことの幸せっていうのがあるんですね。ぼんやりしている。ゆったりした暮らしっていうのを彼らは幸せの基準にしている。」
「あんまり金儲けずに幸せであるという形は、いわゆる日本ではいけない言葉ということになってるけど、「土人」ということね。土の人っていうね、あれはいい言葉なんですよ。人間は土から生まれて土に帰るわけですからね。土人でいいんですよ。土人というのはいいもんだなあと思って観察しておるんですよ。」
もちろん、それなりの金を獲得しつつ、自由な時間を確保するというのが最高ではあるでしょう。けれども、今期のやぎ座は、まずは土人になったつもりで、「働かないことの幸せ」ということから始めてみるといいのかも知れません。
参考:後藤繁雄編『独特老人』(ちくま文庫)
それで、あんまり暇にしているのもどうかということで、仕事をしているフリなんかして、バツの悪い思いをしているくらいなら、いっそのこと水木しげるのように、反対方向に思いきり舵を切ってみるのも手ではないかと。
彼の自伝やSFなんかも味わい深いのですが、インタビューで好き勝手なことを言っている時の水木さんというのは、またそれとは異質の輝きがあるようにおります。
「南方の人間は、朝起きると朝からゲームをやったりして、遊んでるんですよ。そして午前中だけ働けばいいんです。畑にちょっと歩いて行って、イモを植えときゃいいんです。(中略)彼らの考えの中には働かないことの幸せっていうのがあるんですね。ぼんやりしている。ゆったりした暮らしっていうのを彼らは幸せの基準にしている。」
「あんまり金儲けずに幸せであるという形は、いわゆる日本ではいけない言葉ということになってるけど、「土人」ということね。土の人っていうね、あれはいい言葉なんですよ。人間は土から生まれて土に帰るわけですからね。土人でいいんですよ。土人というのはいいもんだなあと思って観察しておるんですよ。」
もちろん、それなりの金を獲得しつつ、自由な時間を確保するというのが最高ではあるでしょう。けれども、今期のやぎ座は、まずは土人になったつもりで、「働かないことの幸せ」ということから始めてみるといいのかも知れません。
参考:後藤繁雄編『独特老人』(ちくま文庫)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「茶気の塩梅」。

「いつになったら西洋が東洋を了解するであろう、否、了解しようと努めるであろう。われわれアジア人はわれわれに関して織り出された事実や想像の妙な話にしばしば肝を冷やすことがある。」
こう書いたのは、1906年にまず英語で『茶の本』を刊行した岡倉天心でした。彼は単なる物好きから本書を書いたのではなく、「茶」を題材に日本独自の文化論を西洋人に説くために書いたのです。そしてその冒頭には、天心みずから「茶」というものをこう位置づけています。
「茶の原理は普通の意味でいう単なる審美主義ではない。というのは、倫理、宗教と合して、天人(てんじん)に関するわれわれのいっさいの見解を表しているものであるから。それは衛生学である、清潔をきびしく説くから。それは経済学である、というのは、複雑なぜいたくというよりもむしろ単純のうちに慰安を教えるから。それは精神幾何学である、なんとなれば、宇宙に対するわれわれの比例感を定義するから。それはあらゆるこの道の信者を趣味上の貴族にして、東洋民主主義の真精神を表している。」
こう言われると、多くの人はとっつきづらく感じて、結局なんなんだというツッコミを入れたくなりそうですが、天心はそうした心理を巧みに受けつつ、そのすぐ後に、茶道の心得があることを意味する「茶気」という言葉の用例を挙げて、次のように語っています。
「茶道の影響は貴人の優雅な閨房にも、下賤の者の住み家にも行き渡ってきた。わが田夫は花を生けることを知り、わが野人も山水を愛でるに至った。俗に「あの男は茶気がない」という。もし人が、我が身の上におこるまじめながらの滑稽を知らないならば。また浮世の悲劇にとんじゃくもなく、浮かれ気分で騒ぐ半過通を「あまり茶気があり過ぎる」と言って非難する。」
まるで謎かけのようですが、つまるところ、自慢話や理論武装ばかりしていて洒脱味に欠ければ「茶気がない」、風流ということが分かっていないということなるし、あまりに遊びに徹していて我が身を滅ぼさんばかりであれば「茶気があり過ぎる」。そのへんの塩梅をいかに体感的につかむことができるかが、わが日本文化の理解度の指標なのだと。ある種の見得を切ってみせた訳ですが、こうした文章の構成そのものに、いかにも天心のプライドの重みを感じはしないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、暮らし方や習慣や文章など、ちょっとした所作やディテールにおいてこそ、茶気の塩梅を発揮していきたいところです。
参考:岡倉覚三『茶の本』(岩波文庫)
こう書いたのは、1906年にまず英語で『茶の本』を刊行した岡倉天心でした。彼は単なる物好きから本書を書いたのではなく、「茶」を題材に日本独自の文化論を西洋人に説くために書いたのです。そしてその冒頭には、天心みずから「茶」というものをこう位置づけています。
「茶の原理は普通の意味でいう単なる審美主義ではない。というのは、倫理、宗教と合して、天人(てんじん)に関するわれわれのいっさいの見解を表しているものであるから。それは衛生学である、清潔をきびしく説くから。それは経済学である、というのは、複雑なぜいたくというよりもむしろ単純のうちに慰安を教えるから。それは精神幾何学である、なんとなれば、宇宙に対するわれわれの比例感を定義するから。それはあらゆるこの道の信者を趣味上の貴族にして、東洋民主主義の真精神を表している。」
こう言われると、多くの人はとっつきづらく感じて、結局なんなんだというツッコミを入れたくなりそうですが、天心はそうした心理を巧みに受けつつ、そのすぐ後に、茶道の心得があることを意味する「茶気」という言葉の用例を挙げて、次のように語っています。
「茶道の影響は貴人の優雅な閨房にも、下賤の者の住み家にも行き渡ってきた。わが田夫は花を生けることを知り、わが野人も山水を愛でるに至った。俗に「あの男は茶気がない」という。もし人が、我が身の上におこるまじめながらの滑稽を知らないならば。また浮世の悲劇にとんじゃくもなく、浮かれ気分で騒ぐ半過通を「あまり茶気があり過ぎる」と言って非難する。」
まるで謎かけのようですが、つまるところ、自慢話や理論武装ばかりしていて洒脱味に欠ければ「茶気がない」、風流ということが分かっていないということなるし、あまりに遊びに徹していて我が身を滅ぼさんばかりであれば「茶気があり過ぎる」。そのへんの塩梅をいかに体感的につかむことができるかが、わが日本文化の理解度の指標なのだと。ある種の見得を切ってみせた訳ですが、こうした文章の構成そのものに、いかにも天心のプライドの重みを感じはしないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、暮らし方や習慣や文章など、ちょっとした所作やディテールにおいてこそ、茶気の塩梅を発揮していきたいところです。
参考:岡倉覚三『茶の本』(岩波文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「<負>の志」。
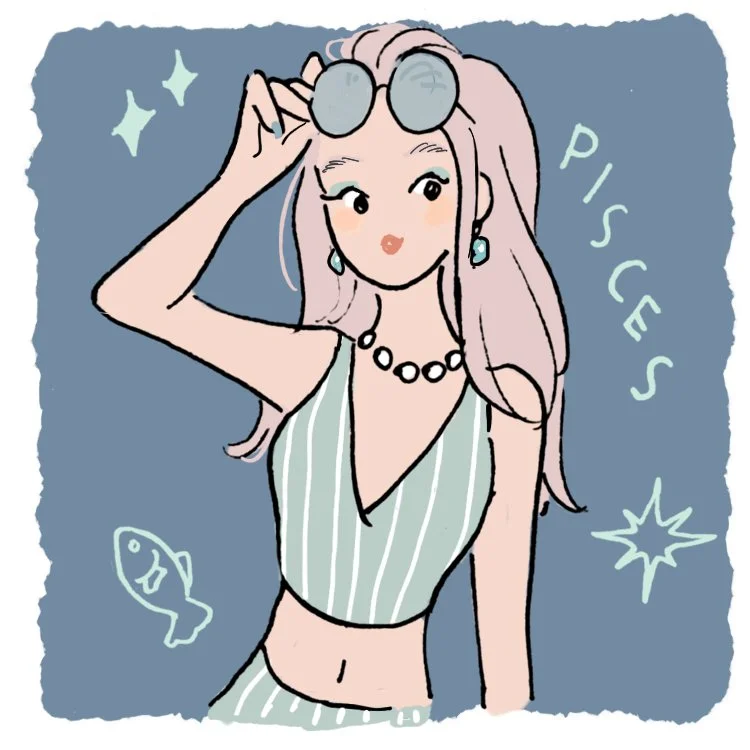
プライドや自尊心を深く自覚するのは、多くの場合、それを不本意な形で挫かれたときかもしれません。その時、それが深く自分と結びついたプライドでなければ、ただ悲しみに打ちひしがれて終わるか、そうでなければ、時間の経過が自然に傷を癒してくれるかもしれません。
しかし、もしそれが深く自分自身の魂と結びついたプライドであったなら、深い潜在力を呼び覚まし、自分自身でも知らなかったような尋常ではないバイタリティーの源となって、本人を突き動かしていくことがあるのではないでしょうか。
古来、日本ではそうした不可思議な力の発揮ぶりを「悪」と呼びましたが、その一例に能で演じられる「悪尉(あくじょう)」の面が挙げられます。この面は、強く恐ろしげな表情の老人の顔で植毛があり、多くは、老神、偉人、怨霊などに用いられてきましたが、歌人の馬場あき子の『悪尉の系譜』によれば、その特徴は「福徳円満しかも欲望に淡白な愛される老境に、あえて進もうとしなかった老いの表情」にこそあったのだと言います。
馬場は、高貴な女御に恋をした年老いた庭守りが辱められる話である世阿弥の「恋重荷」にふれて、「その恋を隔てた階級とは、まさに賤民の情念において捉えられた隔たりなのであり、禁忌としてあったその隔たりへの侮蔑が恋の裏切りとして罰せられたのではなかろうか」と書き、「多くの土着の神々の苦渋、渡来した神々の困難とは、このように悪尉の<悪>たる要素を、幾度も幾度も、にがにがしく噛みしめ噛みしめ生きる外なかったはずである」と述べた上で、その結末においてこう述べています。
「悪尉――、その人生のにがさは、回復の方途のない失地に執しつづける<負>の志である。彼はほとんど敗北と挫折の累積の中に老いている。しかし、老いは決して悪尉の悪たるゆえんを解消させはしない。ゆえに悪尉は徹底して自らの非力を信じまいとするのであり、その自恃にのみ自らの存在を賭けているのである。このような哀しいまでの超時間的なエネルギーは、すでに狂ともよびえぬ峻厳な格をそなえて、時に神に近い剛愎さをもって笞を振り上げ、忘れていた根深い感情をよびさますのである。」
今期のうお座もまた、自身の敗北と累積の中から自然に起きあがってくる<負>の志にこそ、自らの存在を賭けていくだけの思いきりを待ってみるくらいでちょうどいいのかも知れません。
参考:馬場あき子『悪尉の系譜』(『季刊パイディア12 1972年夏 特集日本的狂気の系譜』収用)
しかし、もしそれが深く自分自身の魂と結びついたプライドであったなら、深い潜在力を呼び覚まし、自分自身でも知らなかったような尋常ではないバイタリティーの源となって、本人を突き動かしていくことがあるのではないでしょうか。
古来、日本ではそうした不可思議な力の発揮ぶりを「悪」と呼びましたが、その一例に能で演じられる「悪尉(あくじょう)」の面が挙げられます。この面は、強く恐ろしげな表情の老人の顔で植毛があり、多くは、老神、偉人、怨霊などに用いられてきましたが、歌人の馬場あき子の『悪尉の系譜』によれば、その特徴は「福徳円満しかも欲望に淡白な愛される老境に、あえて進もうとしなかった老いの表情」にこそあったのだと言います。
馬場は、高貴な女御に恋をした年老いた庭守りが辱められる話である世阿弥の「恋重荷」にふれて、「その恋を隔てた階級とは、まさに賤民の情念において捉えられた隔たりなのであり、禁忌としてあったその隔たりへの侮蔑が恋の裏切りとして罰せられたのではなかろうか」と書き、「多くの土着の神々の苦渋、渡来した神々の困難とは、このように悪尉の<悪>たる要素を、幾度も幾度も、にがにがしく噛みしめ噛みしめ生きる外なかったはずである」と述べた上で、その結末においてこう述べています。
「悪尉――、その人生のにがさは、回復の方途のない失地に執しつづける<負>の志である。彼はほとんど敗北と挫折の累積の中に老いている。しかし、老いは決して悪尉の悪たるゆえんを解消させはしない。ゆえに悪尉は徹底して自らの非力を信じまいとするのであり、その自恃にのみ自らの存在を賭けているのである。このような哀しいまでの超時間的なエネルギーは、すでに狂ともよびえぬ峻厳な格をそなえて、時に神に近い剛愎さをもって笞を振り上げ、忘れていた根深い感情をよびさますのである。」
今期のうお座もまた、自身の敗北と累積の中から自然に起きあがってくる<負>の志にこそ、自らの存在を賭けていくだけの思いきりを待ってみるくらいでちょうどいいのかも知れません。
参考:馬場あき子『悪尉の系譜』(『季刊パイディア12 1972年夏 特集日本的狂気の系譜』収用)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ