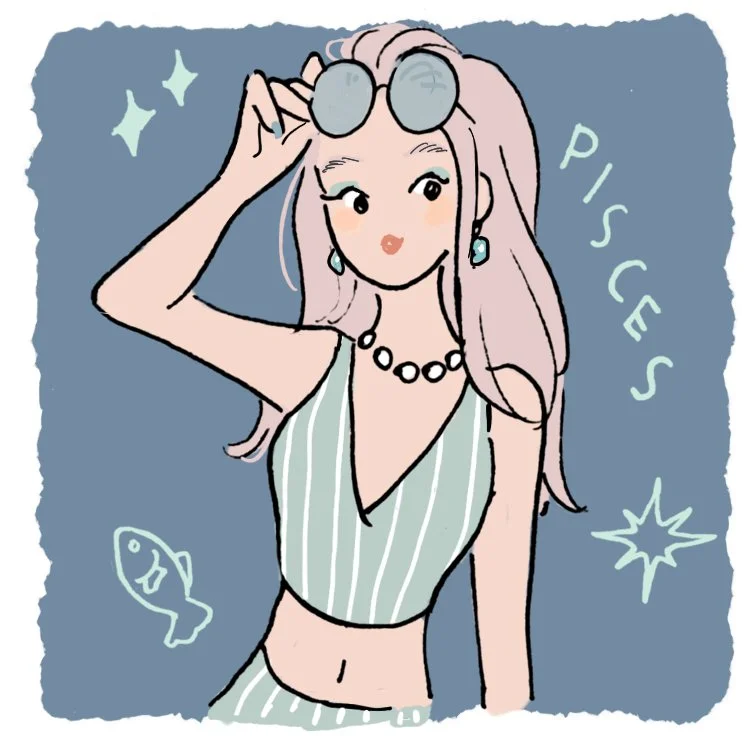【最新12星座占い】<5/29~6/11>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<5/29~6/11>の12星座全体の運勢は?
「いっそヒラリと宙返り」
夏のじめじめとした暑さと梅雨の不安定な天候との合わせ技で、服装選びに悩む衣替えの時期に入った5月30日には、ふたご座9度(数えで10度)で新月を迎えていきます。
サビアンシンボルは「アクロバット飛行」であり、これは自然のもっとも基本的な働きである"重力”に逆らう力を象徴化した度数です。
すなわち、年齢を重ねるごとに身体は老化し、体力は落ち、新しいことに挑戦する気概も失せ、心身ともに昔とった杵柄にすがりつき、なるべく現状を維持することに心血を注ごうとする傾向にあり、こうした“重力”はしばしば呪縛ともなってしまう訳ですが、今回の新月ではそうした当たり前のように人生にふりかかってくる呪縛を、いかに解き放っていけるかがテーマになっていくのだと言えます。
さながら、梅雨の不快な空気感を吹き飛ばす「青嵐(あおあらし、せいらん)」という季語が、青葉を吹きわたる清らかな空気を意味するように、「この年齢ならば」「この立場ならば」こうなって、こうして当然という流れに反するようなアクションやチャレンジを取り入れ、停滞した人生状況に風穴をあけてみるのもアリでしょう。
いずれにせよ、分かりやすいしがらみから思い切って離れ、地図にない未知の領域へと飛び込んでみることで得られる見晴らしは、あなたの人生をよりエキサイティングなものにしてくれるはず。
とりわけ、剣の上を渡るとき、氷の上を行くときは。そぞろ歩きを諦めて、いっそヒラリと宙返り。今期はそんなアクロバットを決めていけるかどうかが問われていくでしょう。
サビアンシンボルは「アクロバット飛行」であり、これは自然のもっとも基本的な働きである"重力”に逆らう力を象徴化した度数です。
すなわち、年齢を重ねるごとに身体は老化し、体力は落ち、新しいことに挑戦する気概も失せ、心身ともに昔とった杵柄にすがりつき、なるべく現状を維持することに心血を注ごうとする傾向にあり、こうした“重力”はしばしば呪縛ともなってしまう訳ですが、今回の新月ではそうした当たり前のように人生にふりかかってくる呪縛を、いかに解き放っていけるかがテーマになっていくのだと言えます。
さながら、梅雨の不快な空気感を吹き飛ばす「青嵐(あおあらし、せいらん)」という季語が、青葉を吹きわたる清らかな空気を意味するように、「この年齢ならば」「この立場ならば」こうなって、こうして当然という流れに反するようなアクションやチャレンジを取り入れ、停滞した人生状況に風穴をあけてみるのもアリでしょう。
いずれにせよ、分かりやすいしがらみから思い切って離れ、地図にない未知の領域へと飛び込んでみることで得られる見晴らしは、あなたの人生をよりエキサイティングなものにしてくれるはず。
とりわけ、剣の上を渡るとき、氷の上を行くときは。そぞろ歩きを諦めて、いっそヒラリと宙返り。今期はそんなアクロバットを決めていけるかどうかが問われていくでしょう。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「本当は友だちなんていない」。

いまの時代はSNSだ、出会い系アプリだ、ビデオ通話だとか、いかにも「友だちや知り合いなんて作ろうと思えばいくらでも作れるよ」と言わんばかりの社会になってきましたが、仮にその通りのことを言っている人がいたとしても、そのようなことの大部分はウソです。
もちろん、性格的に社交的か内向的か、といった違いはあるとしても、社交的じゃないと損をするかと言えばそんなことはなくて、ほとんどの人は知り合いはそれなりにいたとしても、本当の意味での友だちなんてほぼゼロだと思うし、仮にひとりいたとしても、人生というのは基本的には孤独との闘いなんです。
そのことに関して、糸井重里が聞き手になって思想家の吉本隆明へのインタビューをまとめた『悪人正機』のなかで、男女関係にしろ友情関係にしろ、「純粋に相手の気持ちやなんかが全てわかる」ような人間同士の関わりを<純粋ごっこ>と呼んでいて、そういうのは青春期の入りかけだったり、人生のごく一時期には成り立つこともあるけれども、以降はどうしても利害の方が先に来るし、どんどん薄まって、不可能になっていくんだと言うわけです。
でもそれじゃあ、人間は年を重ねるほどに、ますます切なくなっていくばかりじゃないか、と言いたくなると思うんですけれど、吉本はそれでいい、「その切なさみたいなもの」こそが非常に大事で、なくさない方がいい感情なんだとも言うんです。
つまり、利害をこえたようなところで関われる相手なんていうのは、生きれば生きるほどいなくなっていくものだけど、かろうじてそういう相手がひとりかふたりでも残っていたら、それは例えはた目にはどれだけ損をしていたとしても「宝物みたいなもん」であって、そういう相手をこそ、恋人でも夫でも妻でも家族でもなく、唯一「友だち」と呼べるのかも知れない、と。
その意味で、私たちはみな<純粋ごっこ>とそれ以降の切なくなっていくばかりの人生を生きている“ひとりひとり”なのであって、かろうじてそうでない場合や時期もあるだけのことなのだと言えます。
5月30日におひつじ座から数えて「コミュニケーション」を意味する3番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、普通ならゼロで当たり前の「友だち」が自分の場合、どのような関わりとして残っているのか、改めて問い直してみるといいでしょう。
参考:吉本隆明、糸井重里『悪人正機』(新潮文庫)
もちろん、性格的に社交的か内向的か、といった違いはあるとしても、社交的じゃないと損をするかと言えばそんなことはなくて、ほとんどの人は知り合いはそれなりにいたとしても、本当の意味での友だちなんてほぼゼロだと思うし、仮にひとりいたとしても、人生というのは基本的には孤独との闘いなんです。
そのことに関して、糸井重里が聞き手になって思想家の吉本隆明へのインタビューをまとめた『悪人正機』のなかで、男女関係にしろ友情関係にしろ、「純粋に相手の気持ちやなんかが全てわかる」ような人間同士の関わりを<純粋ごっこ>と呼んでいて、そういうのは青春期の入りかけだったり、人生のごく一時期には成り立つこともあるけれども、以降はどうしても利害の方が先に来るし、どんどん薄まって、不可能になっていくんだと言うわけです。
でもそれじゃあ、人間は年を重ねるほどに、ますます切なくなっていくばかりじゃないか、と言いたくなると思うんですけれど、吉本はそれでいい、「その切なさみたいなもの」こそが非常に大事で、なくさない方がいい感情なんだとも言うんです。
つまり、利害をこえたようなところで関われる相手なんていうのは、生きれば生きるほどいなくなっていくものだけど、かろうじてそういう相手がひとりかふたりでも残っていたら、それは例えはた目にはどれだけ損をしていたとしても「宝物みたいなもん」であって、そういう相手をこそ、恋人でも夫でも妻でも家族でもなく、唯一「友だち」と呼べるのかも知れない、と。
その意味で、私たちはみな<純粋ごっこ>とそれ以降の切なくなっていくばかりの人生を生きている“ひとりひとり”なのであって、かろうじてそうでない場合や時期もあるだけのことなのだと言えます。
5月30日におひつじ座から数えて「コミュニケーション」を意味する3番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、普通ならゼロで当たり前の「友だち」が自分の場合、どのような関わりとして残っているのか、改めて問い直してみるといいでしょう。
参考:吉本隆明、糸井重里『悪人正機』(新潮文庫)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「血を分かつ」。

現代という時代に働いている重力は、間違いなく人間を機械化する方向に働いているように思いますが、逆に言えば現代社会で最も失われつつあるものとは人間を生き生きとさせる生命力であり、その象徴としての「血脈」の力なのではないでしょうか。
西田知己の『血の日本思想史』によれば、もともと古くから日本では、神道の影響から血は穢(けが)れであるという不浄観が強かったのですが、江戸時代に入ってから血統が皇統と重ね合わせて解釈されるようになり、それがきっかけとなって穢れよりも生命力を感じさせる新たな「血脈」概念へと読み替えられていったのだそうです。
例えば平田篤胤(1776~1843)は「御血統」と「御正統」をともに「オホミスヂ」と読ませるなど、皇統に対して単なる「血脈」以上の格付けを試みましたが、それが結果的に幕末期の尊王攘夷運動にも取り入れられていったのだとか。
中世の日本人たちからすれば、「血」に「御」の字が冠せられる日が来るとは想像だにしなかったことでしょう。西田はこれを「イエスの「値高き御血」以来、もっとも高位に置かれた「血」認識であった」と述べ、明治維新以降に国家神道が形成されていく経緯においてさまざまな要因が連動していたにせよ、江戸時代に血筋の「血」が登場したこともその前史の一端だったことを指摘した上で次のような非常に興味深い視座を提起しています。
「明治社会は、文明開化や富国強兵といったスローガンにより、欧米社会に追いつくことを目標にしていた。最終的には、欧米社会と対峙する構図も生み出された。その当時の政治や社会の精神的支柱となった皇統の解釈に、西洋渡来の「血」の思想が潜んでいたと考えてみるのも興味深い。西洋思想の力も借りて、西洋世界に相対したようにも見えるからである。」
こうした血縁について、現代日本は民法の第七百二十五条一号において「六親等内の血族」というきわめて限定的な定義が与えられるのみですが、その思想史的な射程を鑑みるに、血脈には空間的にも時間的にも本来結びつきえないような要素を結びつけることで、個人ないし集団に生命力を与えては、力強く養っていくという大きな役割を果たしてきたことが分かるのではないでしょうか。
その意味で、5月30日におうし座から数えて「自己価値」を意味する2番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、どれだけ血を分かち合っていると感じられるような存在と繋がっていけるか、ないし、現に繋がっていることを認められるか、ということがテーマとなっていきそうです。
参考:西田知己『血の日本思想史』(ちくま新書)
西田知己の『血の日本思想史』によれば、もともと古くから日本では、神道の影響から血は穢(けが)れであるという不浄観が強かったのですが、江戸時代に入ってから血統が皇統と重ね合わせて解釈されるようになり、それがきっかけとなって穢れよりも生命力を感じさせる新たな「血脈」概念へと読み替えられていったのだそうです。
例えば平田篤胤(1776~1843)は「御血統」と「御正統」をともに「オホミスヂ」と読ませるなど、皇統に対して単なる「血脈」以上の格付けを試みましたが、それが結果的に幕末期の尊王攘夷運動にも取り入れられていったのだとか。
中世の日本人たちからすれば、「血」に「御」の字が冠せられる日が来るとは想像だにしなかったことでしょう。西田はこれを「イエスの「値高き御血」以来、もっとも高位に置かれた「血」認識であった」と述べ、明治維新以降に国家神道が形成されていく経緯においてさまざまな要因が連動していたにせよ、江戸時代に血筋の「血」が登場したこともその前史の一端だったことを指摘した上で次のような非常に興味深い視座を提起しています。
「明治社会は、文明開化や富国強兵といったスローガンにより、欧米社会に追いつくことを目標にしていた。最終的には、欧米社会と対峙する構図も生み出された。その当時の政治や社会の精神的支柱となった皇統の解釈に、西洋渡来の「血」の思想が潜んでいたと考えてみるのも興味深い。西洋思想の力も借りて、西洋世界に相対したようにも見えるからである。」
こうした血縁について、現代日本は民法の第七百二十五条一号において「六親等内の血族」というきわめて限定的な定義が与えられるのみですが、その思想史的な射程を鑑みるに、血脈には空間的にも時間的にも本来結びつきえないような要素を結びつけることで、個人ないし集団に生命力を与えては、力強く養っていくという大きな役割を果たしてきたことが分かるのではないでしょうか。
その意味で、5月30日におうし座から数えて「自己価値」を意味する2番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、どれだけ血を分かち合っていると感じられるような存在と繋がっていけるか、ないし、現に繋がっていることを認められるか、ということがテーマとなっていきそうです。
参考:西田知己『血の日本思想史』(ちくま新書)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「安っぽい人間」。

自分に酔った文章というのは総じてウザイものですが、その極北は何と言っても新聞や雑誌などの人生相談コーナーに寄せられる文章でしょう。
例えば、1971年に刊行された深沢七郎の『人間滅亡的人生案内』は十代から二十代前半の若者の悩みに深沢が答えるという悩み相談の形式をとった本なのですが、そこに寄せられている若者の悩み相談がまた、ポエム調だったり、リズミカルな口語体だったりする文章からは自意識が溢れまくっており、ことごとく何も成していない自分に焦り苛立ちつつも、考えすぎなほど自分のことを考えすぎていて、その自分に陶酔している、というウザイ文章の典型な訳ですが、それに対する深沢の痛快な回答が本書最大の魅力となっています。
例えば、「近頃何故か自分が安っぽい人間に思えて、毎日がイヤで仕方ありません」ということに悩み、「本物になるには大学に入り教養を身につけ、社会に出て、人間を知らねばだめでしょうか」と質問を投げかけてきた無職の十八歳青年に対し、「人間に本物なんかありません。みんなニセモノで」あり、本物になるためには~なんていうのは、「アキレタ考え」であるとした上で、次のように助言するのです。
「安っぽい人間ならこんな有難いことはありません。安っぽいからあなたは負担の軽いその日その日を送っていられるのです。安っぽい人間になりたくてたまらないのに、人間は錯覚で偉くなりたがるのです。心配なく現在のままでのんびりといて下さい。いちばんおすすめすることは行商などやって放浪すること、お勤めなどしないこと、食べるぶんだけ働いていればのんびりといられます。」
深沢はここで、頭を使ってやたらとモノを考えることを否定し、さびしさを埋めるために群れることを否定し、動物のように欲望に従い、植物のように何も考えず、ひたすら「安っぽい人間」になることを推奨している訳です。
ここでいう「安っぽい」とは、考えすぎの美学で暗い自意識を膨らませる代わりに、深沢自身もまた実践してきた「やりたいようにやれ。てめぇ一人で」という生き様を貫いていけるだけの“パンクさ”のことでもあるのではないでしょうか。
その意味で、5月30日に自分自身の星座であるふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そんな「安っぽい人間」のひとりとして、堂々と、孤独に、道を歩いて行きたいところです。
参考:深沢七郎『人間滅亡的人生案内』(河出文庫)
例えば、1971年に刊行された深沢七郎の『人間滅亡的人生案内』は十代から二十代前半の若者の悩みに深沢が答えるという悩み相談の形式をとった本なのですが、そこに寄せられている若者の悩み相談がまた、ポエム調だったり、リズミカルな口語体だったりする文章からは自意識が溢れまくっており、ことごとく何も成していない自分に焦り苛立ちつつも、考えすぎなほど自分のことを考えすぎていて、その自分に陶酔している、というウザイ文章の典型な訳ですが、それに対する深沢の痛快な回答が本書最大の魅力となっています。
例えば、「近頃何故か自分が安っぽい人間に思えて、毎日がイヤで仕方ありません」ということに悩み、「本物になるには大学に入り教養を身につけ、社会に出て、人間を知らねばだめでしょうか」と質問を投げかけてきた無職の十八歳青年に対し、「人間に本物なんかありません。みんなニセモノで」あり、本物になるためには~なんていうのは、「アキレタ考え」であるとした上で、次のように助言するのです。
「安っぽい人間ならこんな有難いことはありません。安っぽいからあなたは負担の軽いその日その日を送っていられるのです。安っぽい人間になりたくてたまらないのに、人間は錯覚で偉くなりたがるのです。心配なく現在のままでのんびりといて下さい。いちばんおすすめすることは行商などやって放浪すること、お勤めなどしないこと、食べるぶんだけ働いていればのんびりといられます。」
深沢はここで、頭を使ってやたらとモノを考えることを否定し、さびしさを埋めるために群れることを否定し、動物のように欲望に従い、植物のように何も考えず、ひたすら「安っぽい人間」になることを推奨している訳です。
ここでいう「安っぽい」とは、考えすぎの美学で暗い自意識を膨らませる代わりに、深沢自身もまた実践してきた「やりたいようにやれ。てめぇ一人で」という生き様を貫いていけるだけの“パンクさ”のことでもあるのではないでしょうか。
その意味で、5月30日に自分自身の星座であるふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そんな「安っぽい人間」のひとりとして、堂々と、孤独に、道を歩いて行きたいところです。
参考:深沢七郎『人間滅亡的人生案内』(河出文庫)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「街は人間の原点です」。

私たちはみな、必ずどこかの「街」に住んでおり、それはそこに住む人と、商売を営む人とによって形作られていくもの。そして、街の住みやすさというのは、往々にして街を構成する店のオリジナリティが住人に愛されることによって生み出されていくものではないでしょうか。
例えば『新宿駅最後の小さなお店ベルク』は、新宿駅の駅ビルの中で二十年以上にわたってベルクという小さなカフェを経営している経営者が書いたもので、個人店が生き残っていくための創意工夫やこだわりがふんだんに記されています。
ベルクは知る人ぞ知るカフェであり、新宿駅で異彩を放ちながら、多くのファンに長年愛されたてきた名店なのですが、驚いたことにビルの家主であるJRからは何度も立ち退きを要求されているのだそうです。
それは、ベルクに何か過失や非があったからではなく、毎年20%の店を入れ替えるという駅ビルの経営方針で、「ルミネの色に合わない」という理由だけなのだとか。
こうした大企業のやり口には思わず閉口してしまいますが、この問題はなにも駅ビルの中だけの話ではなく、経営の不安定な個人店が家主の意向から追い出され、街が大企業が経営するチェーン店だらけになっていくという社会現象として、それこそコロナ禍以降は特に、日本中で起きている問題でもあるはず。著書である井野は言います。
「街は人間の原点です。街が面白くなくなったら、人間が面白くなくなるのは当然です。」
私たちはいま、大企業の思惑に満ちた街のなかで、ただ流されるままの消費者となりさがるか、それともどこにお金を落とすかを自分の意志で決めているファンであり続けるか、大きな分岐点に差し掛かっているように思います。
その意味で、5月30日にかに座から数えて「真の自己を見出すことのできる場所」を意味する12番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、資本主義の重力に逆らって街を面白くするべく、自分の推しにきちんとお金を落としていくべし。
参考:井野朋也『新宿駅最後の小さなお店ベルク』(ちくま文庫)
例えば『新宿駅最後の小さなお店ベルク』は、新宿駅の駅ビルの中で二十年以上にわたってベルクという小さなカフェを経営している経営者が書いたもので、個人店が生き残っていくための創意工夫やこだわりがふんだんに記されています。
ベルクは知る人ぞ知るカフェであり、新宿駅で異彩を放ちながら、多くのファンに長年愛されたてきた名店なのですが、驚いたことにビルの家主であるJRからは何度も立ち退きを要求されているのだそうです。
それは、ベルクに何か過失や非があったからではなく、毎年20%の店を入れ替えるという駅ビルの経営方針で、「ルミネの色に合わない」という理由だけなのだとか。
こうした大企業のやり口には思わず閉口してしまいますが、この問題はなにも駅ビルの中だけの話ではなく、経営の不安定な個人店が家主の意向から追い出され、街が大企業が経営するチェーン店だらけになっていくという社会現象として、それこそコロナ禍以降は特に、日本中で起きている問題でもあるはず。著書である井野は言います。
「街は人間の原点です。街が面白くなくなったら、人間が面白くなくなるのは当然です。」
私たちはいま、大企業の思惑に満ちた街のなかで、ただ流されるままの消費者となりさがるか、それともどこにお金を落とすかを自分の意志で決めているファンであり続けるか、大きな分岐点に差し掛かっているように思います。
その意味で、5月30日にかに座から数えて「真の自己を見出すことのできる場所」を意味する12番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、資本主義の重力に逆らって街を面白くするべく、自分の推しにきちんとお金を落としていくべし。
参考:井野朋也『新宿駅最後の小さなお店ベルク』(ちくま文庫)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「偶然の共同体」。

一度でもネットで炎上した経験や、いわれなき非難の集中砲火を浴びたことのある人であれば分かると思うのですが、そうして「世間」や「みんな」から追放された者にとって、最も支えとなり、したがって、大事にしようと思うようになる存在は家族なのではないでしょうか。
というより、いったん社会がその攻撃的・暴力的側面を露わにすると、ほとんどの関係性は切れてしまい、逆に切ろうにも簡単には切れずに残ってしまうのが家族でもある訳ですが、一方で家族というと、現代ではむしろ旧来的な制度の象徴として「古臭いもの」、「面倒なしがらみ」として語られることの方が多いように思います。
これは逆に言えば、現代社会においては、最も身近な他者としての「家族」をいかに傷つけず、それでいてこちらも我慢しない絶妙な塩梅で関わっていけるか、ということがますます問われてきているのだとも言えるのではないでしょうか。ここで、そうした「家族」ということについて大変ラジカルな議論をしている東浩紀と高橋源一郎の対談の一部を引用してみたいと思います。
「高橋 東さんは「家族」の本質を偶有性に置いています。男女が出会うのはもちろん、子どもが生まれることも偶然にすぎない。養子やLGBTのような同性カップルも含めれば、偶然性はさらに広がる。ところが東さんは同時に、家族はそうした偶然なものでありながら、愛というエモーションで結ばれ、持続性を持っているとも語っています。(……)つまり東さんは家族を「新しい組織論」として提出しているのだと思います。ただ、その具体的なあり方がいまいち見えないのですが、どんなものを想像しているのでしょう。
東 (……)いまなら是枝裕和監督の『万引き家族』(2018)を思い浮べるとわかりやすいと思います。『万引き家族』の六人について、観客は彼らを感覚的に「家族」と呼びたくなります。けれどもこの六人を結びつける根拠は、じつは偶然いっしょにいたということ以外にない。こうした偶然の共同体に可能性があると思っています。
そこで鍵になるのは「類似性」です。『万引き家族』の六人が家族に見えるのは、ひとことで言えば彼らがどこか「たがいに似ている」からです。そのような類似性について、『観光客の哲学』では、ウィトゲンシュタインの「家族的類似性」という言葉で説明しています。この表現で重要なのは、家族が類似性にもとづいているというよりも、むしろわれわれが、類似そのものを家族の比喩でしか捉えられないということのほうです。「なにかとなにかが似ている」というのは、とてもふしぎな直感的な判断です。それはときに論理を超えることがある。そしてそういうとき、人間はそれを「家族」と捉える。ぼくはそこに注目しています。「似ている」という基準はあいまいで、いくらでも柔軟に拡張でき、ひとはどんどんそれに対応していくことができる。だからその性質を利用して共同体をつくればいい。」
その意味で、5月30日にしし座から数えて「ネットワーク」を意味する11番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、「家族」という概念をいかにアップデートしていけるかどうか問われていくことになりそうです。
参考:東浩紀ほか『新対話篇』(株式会社ゲンロン)
というより、いったん社会がその攻撃的・暴力的側面を露わにすると、ほとんどの関係性は切れてしまい、逆に切ろうにも簡単には切れずに残ってしまうのが家族でもある訳ですが、一方で家族というと、現代ではむしろ旧来的な制度の象徴として「古臭いもの」、「面倒なしがらみ」として語られることの方が多いように思います。
これは逆に言えば、現代社会においては、最も身近な他者としての「家族」をいかに傷つけず、それでいてこちらも我慢しない絶妙な塩梅で関わっていけるか、ということがますます問われてきているのだとも言えるのではないでしょうか。ここで、そうした「家族」ということについて大変ラジカルな議論をしている東浩紀と高橋源一郎の対談の一部を引用してみたいと思います。
「高橋 東さんは「家族」の本質を偶有性に置いています。男女が出会うのはもちろん、子どもが生まれることも偶然にすぎない。養子やLGBTのような同性カップルも含めれば、偶然性はさらに広がる。ところが東さんは同時に、家族はそうした偶然なものでありながら、愛というエモーションで結ばれ、持続性を持っているとも語っています。(……)つまり東さんは家族を「新しい組織論」として提出しているのだと思います。ただ、その具体的なあり方がいまいち見えないのですが、どんなものを想像しているのでしょう。
東 (……)いまなら是枝裕和監督の『万引き家族』(2018)を思い浮べるとわかりやすいと思います。『万引き家族』の六人について、観客は彼らを感覚的に「家族」と呼びたくなります。けれどもこの六人を結びつける根拠は、じつは偶然いっしょにいたということ以外にない。こうした偶然の共同体に可能性があると思っています。
そこで鍵になるのは「類似性」です。『万引き家族』の六人が家族に見えるのは、ひとことで言えば彼らがどこか「たがいに似ている」からです。そのような類似性について、『観光客の哲学』では、ウィトゲンシュタインの「家族的類似性」という言葉で説明しています。この表現で重要なのは、家族が類似性にもとづいているというよりも、むしろわれわれが、類似そのものを家族の比喩でしか捉えられないということのほうです。「なにかとなにかが似ている」というのは、とてもふしぎな直感的な判断です。それはときに論理を超えることがある。そしてそういうとき、人間はそれを「家族」と捉える。ぼくはそこに注目しています。「似ている」という基準はあいまいで、いくらでも柔軟に拡張でき、ひとはどんどんそれに対応していくことができる。だからその性質を利用して共同体をつくればいい。」
その意味で、5月30日にしし座から数えて「ネットワーク」を意味する11番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、「家族」という概念をいかにアップデートしていけるかどうか問われていくことになりそうです。
参考:東浩紀ほか『新対話篇』(株式会社ゲンロン)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「家の政治性を振り返る」。

80年代には主に職場の人間関係において使われ、取りあげられてきた「生きづらい」という言葉が、2000年代に入ってから家庭や家族という身近な人間関係においても使われ、指摘されるようになりましたが、2020年代を生きる私たちは、今や「家」や「家族」というシステムそのものを見直し、具体的に変更すべき段階に入っているのではないでしょうか。
そもそも「家」とは、幸福感などの目に見えない恩恵を受け止めるための共同体の単位すなわち「ハコ」であり、社会的現実のもっとも身近なメタファーとして機能してきた訳ですが、逆に、そうした恩恵を一切受けていない社会的状態以前の「自然状態」について、17世紀の政治哲学者ホッブスは「決定的な能力差の無い個人同士が互いに自然権を行使し合った結果としての万人の万人に対する闘争」と定義しましたが、現代の哲学者ジョルジュ・アガンベンは、「ホモ・サケル」すなわち「剝き出しの生」を現に生きている「難民」などを念頭におきつつ、次のように述べています。
「さて、ホモ・サケルの生を、あるいはまた、さまざまな点でこれに似たところのある締め出された者、平和なき者、水火の禁じられた者の生を考察してみよう。その者は、宗教的な共同体からも、あらゆる政治的な生からも排除されている。彼は、(…)その存在全体が、あらゆる権利を奪われた剥き出しの生へと還元されている。自分の生を救うには、彼は絶えず逃亡しているか、あるいは外国に避難所を見出さなければならない。だが、つねに無条件の死の脅威にさらされていることによって、彼は自分を締め出した権力と絶えず関連を持っている。彼は純粋なゾーエー(奴隷の生)である。だが、彼のゾーエーは主権的締め出しの内にゾーエーとして捉われている。彼は、主権的締め出しをつねに考慮に入れ、これを避け、欺くやり方を見出さなければならない。この意味で、流謫にある者や締め出された者であれば知っているとおり、この生ほど「政治的」な生はないのだ。」
ここで語られている「剝き出しの生」はフィクションなどではなく、太古からこうした被差別民や賤民、追放者たちは社会の中につねに存在しましたし、同性カップルを受け入れるための法改正や夫婦別姓問題などを念頭におけば、構造的な差別や、世代から世代への負の連鎖というのは、家庭や家族においても見出されるものであり、きっかけさえ得ればそれはすぐに顕在化ないし狂暴化するものであるように思います。
私たちは現にそういう世界を生きているのであり、そうしたいつ起きるとも知れない狂暴化を抑制するのは、共同体を構成する一人ひとりが、自分の中にある攻撃性や無感覚とどれだけ向き合っていけるかにかかっているのだとも言えます。
その意味で、5月30日におとめ座から数えて「政治的関わり」を意味する10番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、最も身近な他者との関わりにおいて、自分がいかに振る舞ってきたかという内省から、自身の「家」観を改めてみるといいでしょう。
参考:ジョルジョ・アガンベン、高桑和巳訳『ホモ・サケル 主権権力と剥き出しの生』(以文社)
そもそも「家」とは、幸福感などの目に見えない恩恵を受け止めるための共同体の単位すなわち「ハコ」であり、社会的現実のもっとも身近なメタファーとして機能してきた訳ですが、逆に、そうした恩恵を一切受けていない社会的状態以前の「自然状態」について、17世紀の政治哲学者ホッブスは「決定的な能力差の無い個人同士が互いに自然権を行使し合った結果としての万人の万人に対する闘争」と定義しましたが、現代の哲学者ジョルジュ・アガンベンは、「ホモ・サケル」すなわち「剝き出しの生」を現に生きている「難民」などを念頭におきつつ、次のように述べています。
「さて、ホモ・サケルの生を、あるいはまた、さまざまな点でこれに似たところのある締め出された者、平和なき者、水火の禁じられた者の生を考察してみよう。その者は、宗教的な共同体からも、あらゆる政治的な生からも排除されている。彼は、(…)その存在全体が、あらゆる権利を奪われた剥き出しの生へと還元されている。自分の生を救うには、彼は絶えず逃亡しているか、あるいは外国に避難所を見出さなければならない。だが、つねに無条件の死の脅威にさらされていることによって、彼は自分を締め出した権力と絶えず関連を持っている。彼は純粋なゾーエー(奴隷の生)である。だが、彼のゾーエーは主権的締め出しの内にゾーエーとして捉われている。彼は、主権的締め出しをつねに考慮に入れ、これを避け、欺くやり方を見出さなければならない。この意味で、流謫にある者や締め出された者であれば知っているとおり、この生ほど「政治的」な生はないのだ。」
ここで語られている「剝き出しの生」はフィクションなどではなく、太古からこうした被差別民や賤民、追放者たちは社会の中につねに存在しましたし、同性カップルを受け入れるための法改正や夫婦別姓問題などを念頭におけば、構造的な差別や、世代から世代への負の連鎖というのは、家庭や家族においても見出されるものであり、きっかけさえ得ればそれはすぐに顕在化ないし狂暴化するものであるように思います。
私たちは現にそういう世界を生きているのであり、そうしたいつ起きるとも知れない狂暴化を抑制するのは、共同体を構成する一人ひとりが、自分の中にある攻撃性や無感覚とどれだけ向き合っていけるかにかかっているのだとも言えます。
その意味で、5月30日におとめ座から数えて「政治的関わり」を意味する10番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、最も身近な他者との関わりにおいて、自分がいかに振る舞ってきたかという内省から、自身の「家」観を改めてみるといいでしょう。
参考:ジョルジョ・アガンベン、高桑和巳訳『ホモ・サケル 主権権力と剥き出しの生』(以文社)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「見知らぬ変成へと開かれる」。
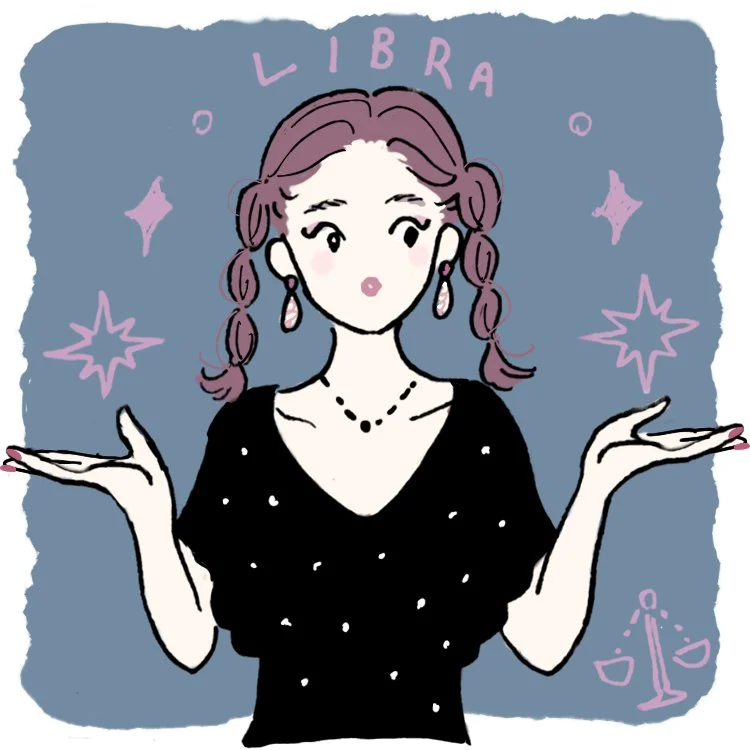
昔から女性のもつ特有の美しさは「花」に喩えられてきましたが、その一方で、「花」に喩えることは、どうしても「性を売り物にする」ようなネガティブなニュアンスもまた入り込んできてしまい、時代遅れに感じざるを得ない場合もあるように思います。
この点について、現代イタリアの哲学者コッチャは、『植物の生の哲学』の中で、花という器官が果たしている役割や機能について考察を行っていくことで、これまでの見方を覆すような大胆な議論を提示しています。
「花は<混合>の能動的な道具だ。他の個体とのあらゆる出逢い、あらゆる結合は、花によって行われる。だが花は、厳密に言って器官ではない。それは生殖を可能にするために変化した数々の器官の寄せ集めに過ぎない。そこには一時的で不安定な形成体という側面もあれば、厳密に「有機的」な領域を超越した側面もあり、両者のあいだには深い結びつきが見られる。個体や種に新たなアイデンティティーを練り上げ、作り上げ、産み出す空間として、花は個々の組織体の論理を転覆させる装置でもあるだろう。すなわち花は、個体と種が自身を変容や変化の可能性に、あるいは死の可能性に開く、究極の分水嶺なのだ。」
実際、雌雄同体の花の大半は、自家受精を避けるための自己免疫システムを持っており、それは世界によりよく自分自身を開くための、自己そのものに対する防衛でもあるのかも知れません。
すなわち、植物が花を通して行っている営みは、単に人間の性交渉のバリエーションなどではなく、むしろ自己を放棄し、自分自身にとっても見知らぬ変成へと開かれていくための<メタ有機体的地平>であり、新たな自分自身へと生まれ変わっていくための聖なる舞台でもあるのだとも言えます。
こうした視点に立つ時、性とはもはや暗い欲望が渦巻く不健全な領域などではなく、性ゆえにこそ他のあらゆる事物と触れ合い、ともに進化の過程を歩むことのできる健やかさを担う最重要領域であり、人間の脳にあたる最も重要な神経器官に他ならないのです。
ここで再びコッチャの言葉を借りれば、「性においてこそ、生物は自分自身をコズミックな混合剤とすることができ、混合は様々な存在、様々なアイデンティティーの刷新の手段となる」のであって、それはつねに「リスクであり、工夫であり、実験なの」だとも指摘しています。
その意味で、5月30日にてんびん座から数えて「アイデンティティ・クライシス」を意味する9番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そうした「コズミックな混淆剤」としての花をみずからに咲かせていくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:エマヌエーレ・コッチャ、嶋崎正樹訳『植物の生の哲学』(勁草書房)
この点について、現代イタリアの哲学者コッチャは、『植物の生の哲学』の中で、花という器官が果たしている役割や機能について考察を行っていくことで、これまでの見方を覆すような大胆な議論を提示しています。
「花は<混合>の能動的な道具だ。他の個体とのあらゆる出逢い、あらゆる結合は、花によって行われる。だが花は、厳密に言って器官ではない。それは生殖を可能にするために変化した数々の器官の寄せ集めに過ぎない。そこには一時的で不安定な形成体という側面もあれば、厳密に「有機的」な領域を超越した側面もあり、両者のあいだには深い結びつきが見られる。個体や種に新たなアイデンティティーを練り上げ、作り上げ、産み出す空間として、花は個々の組織体の論理を転覆させる装置でもあるだろう。すなわち花は、個体と種が自身を変容や変化の可能性に、あるいは死の可能性に開く、究極の分水嶺なのだ。」
実際、雌雄同体の花の大半は、自家受精を避けるための自己免疫システムを持っており、それは世界によりよく自分自身を開くための、自己そのものに対する防衛でもあるのかも知れません。
すなわち、植物が花を通して行っている営みは、単に人間の性交渉のバリエーションなどではなく、むしろ自己を放棄し、自分自身にとっても見知らぬ変成へと開かれていくための<メタ有機体的地平>であり、新たな自分自身へと生まれ変わっていくための聖なる舞台でもあるのだとも言えます。
こうした視点に立つ時、性とはもはや暗い欲望が渦巻く不健全な領域などではなく、性ゆえにこそ他のあらゆる事物と触れ合い、ともに進化の過程を歩むことのできる健やかさを担う最重要領域であり、人間の脳にあたる最も重要な神経器官に他ならないのです。
ここで再びコッチャの言葉を借りれば、「性においてこそ、生物は自分自身をコズミックな混合剤とすることができ、混合は様々な存在、様々なアイデンティティーの刷新の手段となる」のであって、それはつねに「リスクであり、工夫であり、実験なの」だとも指摘しています。
その意味で、5月30日にてんびん座から数えて「アイデンティティ・クライシス」を意味する9番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そうした「コズミックな混淆剤」としての花をみずからに咲かせていくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:エマヌエーレ・コッチャ、嶋崎正樹訳『植物の生の哲学』(勁草書房)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「先覚者として」。

近代化以降の社会の特徴として、社会の巨大化・複雑化・流動化ということが挙げられますが、そうした社会に適応しようとすればするほど、人はより大きく、より根深い欲望に憑りつかれ、まるで操られるようにそこで抱いた夢や欲動につき動かされていくのではないでしょうか。
それが結果的に幸福か不幸のどちらを人間にもたらすことが多いのかはさておき、そこでは少なくとも「夢みる自分」から「夢に生かされる自分」という主客の逆転が起きているのだと言えます。そして、こうした逆転劇はそのまま「個体が先か種が先か」という二者択一的立場から、「個体はすなわち種であり種はすなわち個体である」という生態学者・今西錦司が提唱した「種の主体性」への転換とパラレルに対応しているように思います。
今西は『生物の世界』のなかで、ダーウィンの自然淘汰の考えを全面的に否定して「種は変わるべくして変わる」と主張し、「種自身が変わっていく場合には、早く変異をとげた個体はいわば先覚者であり、要するに早熟であったというだけで、遅かれ早かれ他の個体も変異するのである」とし、さらに「形態的・機能的ないしは体制的・行動的に同じようにつくられた同種の個体は、変わらねばならないときがきたら、また同じように変わるのでなければならない」と述べ、それゆえにこそ「種の起源は種自身になければならない」と結論づけました。
こうした今西進化論は、あきらかに生命ないし「生きること」に定位した思想であり、これが対象としての生物や生命物質に定位したダーウィニズムと相容れなかったのも致し方ないことだったのでしょう。
両者はそれぞれ問題にしている「事実」の大きさが違うのであって、たとえば今西の「生物が生きるということは働くということであり、作られたものが作るものを作っていくということである」とか、「こうして生物の世界は全体としてどこまでも一つのものでありながら、それはまたつねにそれぞれの生物を中心とした世界の統合体でもあった」といった言葉からは、今西が「客観的な観察」によって生命活動を傍観者的に分析しようとしているのではなく、あくまで生命それ自身の内側から、ひとりの実践者として生命活動を考えようとしていることが伺えます。
その意味で、現代社会において欲望に憑かれ、突き動かされることで、人生の新たな扉を開けていった者たちというのは、いわば種の主体的な変異の先覚者にならんとしているのであって、それは種が消滅の危機に瀕した際に環境との境界面にのばした触手のようなものなのだとも考えられるのではないでしょうか。
5月30日にさそり座から数えて「否応なく巻き込まれること」を意味する8番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、ひとりの「先覚者」のひとりとして、ぜひとも突き抜けるところまで欲望にとりつかれていくべし。
参考:今西錦司『生物の世界 ほか』(中公クラシックス)
それが結果的に幸福か不幸のどちらを人間にもたらすことが多いのかはさておき、そこでは少なくとも「夢みる自分」から「夢に生かされる自分」という主客の逆転が起きているのだと言えます。そして、こうした逆転劇はそのまま「個体が先か種が先か」という二者択一的立場から、「個体はすなわち種であり種はすなわち個体である」という生態学者・今西錦司が提唱した「種の主体性」への転換とパラレルに対応しているように思います。
今西は『生物の世界』のなかで、ダーウィンの自然淘汰の考えを全面的に否定して「種は変わるべくして変わる」と主張し、「種自身が変わっていく場合には、早く変異をとげた個体はいわば先覚者であり、要するに早熟であったというだけで、遅かれ早かれ他の個体も変異するのである」とし、さらに「形態的・機能的ないしは体制的・行動的に同じようにつくられた同種の個体は、変わらねばならないときがきたら、また同じように変わるのでなければならない」と述べ、それゆえにこそ「種の起源は種自身になければならない」と結論づけました。
こうした今西進化論は、あきらかに生命ないし「生きること」に定位した思想であり、これが対象としての生物や生命物質に定位したダーウィニズムと相容れなかったのも致し方ないことだったのでしょう。
両者はそれぞれ問題にしている「事実」の大きさが違うのであって、たとえば今西の「生物が生きるということは働くということであり、作られたものが作るものを作っていくということである」とか、「こうして生物の世界は全体としてどこまでも一つのものでありながら、それはまたつねにそれぞれの生物を中心とした世界の統合体でもあった」といった言葉からは、今西が「客観的な観察」によって生命活動を傍観者的に分析しようとしているのではなく、あくまで生命それ自身の内側から、ひとりの実践者として生命活動を考えようとしていることが伺えます。
その意味で、現代社会において欲望に憑かれ、突き動かされることで、人生の新たな扉を開けていった者たちというのは、いわば種の主体的な変異の先覚者にならんとしているのであって、それは種が消滅の危機に瀕した際に環境との境界面にのばした触手のようなものなのだとも考えられるのではないでしょうか。
5月30日にさそり座から数えて「否応なく巻き込まれること」を意味する8番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、ひとりの「先覚者」のひとりとして、ぜひとも突き抜けるところまで欲望にとりつかれていくべし。
参考:今西錦司『生物の世界 ほか』(中公クラシックス)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「思考し続けるために」。

コロナ禍が決定的に明らかにした教訓の一つとして、国家というものはともすると国民の思考を停止させようとしてくるものなのだということが挙げられますが、こうした試みは現代社会においては、思考することすらままならぬほど多忙の中で生きていかなくてはならなくなってしまったという現実の後押しもあって、多くの場合、ごく当たり前のように実現してしまっているように思います。
しかしながら、今回のウクライナ侵攻を目の当たりにし、今後日本が戦争に巻き込まれる可能性があながち杞憂とも言えなくなってきているいま、言葉を武器に思考し続け、「みんなの意見」としてではなく、あくまで自分個人としての意見を表現することをやめてはならないのではないでしょうか。
その意味で大いに参考になるのは、最低最悪の未来を描いたSF小説の古典である『一九八四年』です。その未来世界では戦争が行われているのですが、その戦争はかつてのような分かりやすい戦争ではなく、敵は国がでっちあげた仮想の敵国で、自国に打ち込まれるロケットは、国がみずから打ち放っているのです。
いわば「でっち上げられた戦争」な訳ですが、国がなぜそのようなことをするかと言えば、国の特権階級が戦争状態を継続させることで、国民の無知と貧困、不充足な状態をつくりだし、権力による支配構造を継続させていたのです。
そこでは、やはり国民に思考をさせないために新しい言語が開発され、国民は思考を言語化することさえできず、つねに監視され、愛情や欲望を抱くことは犯罪となり、違反したものは思考警察につぎつぎと逮捕されていきます。
そうなると、もはや個人は個人ではなくなり、集団のパーツでしかなくなって、無知で隷従することしかできなくなった国民は、みずから戦争の継続を支持し、ますます自分たちを苦しみの最中に突き落としていくのです。
この小説の主人公は、物語を通じてずっと貫いてきた反権力的思考の末に、愛情を放棄し、思考を殺し、権力に飲み込まれ、すすんで無知になることで安寧を手に入れるという、最悪のバッドエンディングを迎えるのですが、これはまさに73年前から現代に向けて鳴らされた、警鐘の書と言えるでしょう。
5月30日にいて座から数えて「立場の表明」を意味する7番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そうしたネガティブアプローチを踏まえた上で、今みずからの主張を言葉にして訴えるならば、それはどんなものになるか、考えてみるべし。
参考:ジョージ・オーウェル、高橋和久訳『一九八四年』(ハヤカワepi文庫)
しかしながら、今回のウクライナ侵攻を目の当たりにし、今後日本が戦争に巻き込まれる可能性があながち杞憂とも言えなくなってきているいま、言葉を武器に思考し続け、「みんなの意見」としてではなく、あくまで自分個人としての意見を表現することをやめてはならないのではないでしょうか。
その意味で大いに参考になるのは、最低最悪の未来を描いたSF小説の古典である『一九八四年』です。その未来世界では戦争が行われているのですが、その戦争はかつてのような分かりやすい戦争ではなく、敵は国がでっちあげた仮想の敵国で、自国に打ち込まれるロケットは、国がみずから打ち放っているのです。
いわば「でっち上げられた戦争」な訳ですが、国がなぜそのようなことをするかと言えば、国の特権階級が戦争状態を継続させることで、国民の無知と貧困、不充足な状態をつくりだし、権力による支配構造を継続させていたのです。
そこでは、やはり国民に思考をさせないために新しい言語が開発され、国民は思考を言語化することさえできず、つねに監視され、愛情や欲望を抱くことは犯罪となり、違反したものは思考警察につぎつぎと逮捕されていきます。
そうなると、もはや個人は個人ではなくなり、集団のパーツでしかなくなって、無知で隷従することしかできなくなった国民は、みずから戦争の継続を支持し、ますます自分たちを苦しみの最中に突き落としていくのです。
この小説の主人公は、物語を通じてずっと貫いてきた反権力的思考の末に、愛情を放棄し、思考を殺し、権力に飲み込まれ、すすんで無知になることで安寧を手に入れるという、最悪のバッドエンディングを迎えるのですが、これはまさに73年前から現代に向けて鳴らされた、警鐘の書と言えるでしょう。
5月30日にいて座から数えて「立場の表明」を意味する7番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、そうしたネガティブアプローチを踏まえた上で、今みずからの主張を言葉にして訴えるならば、それはどんなものになるか、考えてみるべし。
参考:ジョージ・オーウェル、高橋和久訳『一九八四年』(ハヤカワepi文庫)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「うまくいく配置」。
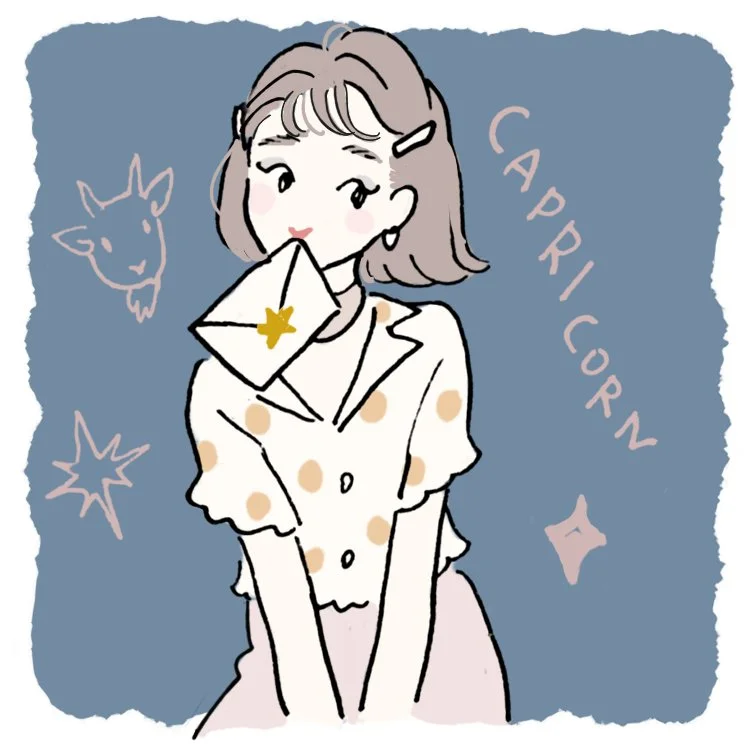
「もし私たちが、人類の精神史を古代から参照しなおすならば、実に世界を「配置」として捉える思考方法が中心的であった期間は、世界を認識する意識的な「主体」が幅を利かせている期間よりも、ずっと長いことに気付かされる。」
これはキリスト教思想研究者の柳澤田美の「馬に乗るように、ボールに触れ、音を奏でるように、人と関わる」という論文からの引用なのですが、人間は長らくたとえ内的必然性や情熱の高まりに頼る代わりに、「配置」、すなわち伝統的ないし普遍的な「型」や「脚本)」に則って世界への身の置き方を適切に態勢づけていくことで、みずからに必要な変化や成長を遂げてきたのだと言えるのではないでしょうか。
この「世界は配置(disposition)であり、人間は自らを取りまく配置によってたえず態勢づけられている(disposed)」という柳澤の世界の捉え方は、「世界を認識主体の構成物あるいは表象として捉える近代的な世界観」を相対化していくためのアプローチであり、「①身体から独立した自己意識の優位、②心の私秘性、そして③効率化優先の自然科学的な世界観」を批判しつつ、「わたし」や「あなた」や「彼ら」などの特定の人称から離れた、非人称的な「うまくいく(going well)」が成り立つとき、そこで一体何が起こっているのかを明らかにする試みなのだと説明されています。
「この関わりの「程度」は完全に数値化できるものではない。そして既存の概念もまた、なかなかこうした「うまくいく」ための関わりを十分には言い表してはくれない。「調和」「統一」といった概念は、美学的でもあり倫理的でもあるが、いずれにしてもこれらは、全体において成し遂げられた構成(composition)に向けられた概念であり、あれとこれが「うまくいっている(going well)」ことを示すには不十分である。こうした事実を前に、「うまくいく」を言語化不可能なものとして認識の外部に置くのは、あまりにも口惜しいように思われる。確かにうまくいかない事態、しかもうまくいく可能性すら見出せない事態は枚挙に暇がない。しかし、このたくさんのうまくいかない状況にも拘らず、私たちは、あるいはサッカー選手たちや演奏家たちや(砂場で一緒に遊んでいる)子どもたちは、(…)確かに「うまくやってきた」のである。あたかも、蘭と自らの使命を知らずに蘭の受粉を手伝うスズメガのように。」
このように、柳澤は「配置」というアプローチこそ、これまでの強い概念体系では捉えられなかった「幸福な倫理の可能性」に光が当てていくことができるのではないかと考えた訳ですが、自己自身の固有性を心のうちにばかり求めるのではなく、むしろ微妙な配置の仕方やその調整においてこそ求めていくという方針は、今期のやぎ座にもまさにうってつけと言えるのではないでしょうか。
5月30日にやぎ座から数えて「セルフメンテナンス」を意味する6番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、「うまくいく」ことに意識の焦点を起きつつ、身の振り方を調整していくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:柳澤田美『ディスポジション 配置としての世界』(現代企画室)
これはキリスト教思想研究者の柳澤田美の「馬に乗るように、ボールに触れ、音を奏でるように、人と関わる」という論文からの引用なのですが、人間は長らくたとえ内的必然性や情熱の高まりに頼る代わりに、「配置」、すなわち伝統的ないし普遍的な「型」や「脚本)」に則って世界への身の置き方を適切に態勢づけていくことで、みずからに必要な変化や成長を遂げてきたのだと言えるのではないでしょうか。
この「世界は配置(disposition)であり、人間は自らを取りまく配置によってたえず態勢づけられている(disposed)」という柳澤の世界の捉え方は、「世界を認識主体の構成物あるいは表象として捉える近代的な世界観」を相対化していくためのアプローチであり、「①身体から独立した自己意識の優位、②心の私秘性、そして③効率化優先の自然科学的な世界観」を批判しつつ、「わたし」や「あなた」や「彼ら」などの特定の人称から離れた、非人称的な「うまくいく(going well)」が成り立つとき、そこで一体何が起こっているのかを明らかにする試みなのだと説明されています。
「この関わりの「程度」は完全に数値化できるものではない。そして既存の概念もまた、なかなかこうした「うまくいく」ための関わりを十分には言い表してはくれない。「調和」「統一」といった概念は、美学的でもあり倫理的でもあるが、いずれにしてもこれらは、全体において成し遂げられた構成(composition)に向けられた概念であり、あれとこれが「うまくいっている(going well)」ことを示すには不十分である。こうした事実を前に、「うまくいく」を言語化不可能なものとして認識の外部に置くのは、あまりにも口惜しいように思われる。確かにうまくいかない事態、しかもうまくいく可能性すら見出せない事態は枚挙に暇がない。しかし、このたくさんのうまくいかない状況にも拘らず、私たちは、あるいはサッカー選手たちや演奏家たちや(砂場で一緒に遊んでいる)子どもたちは、(…)確かに「うまくやってきた」のである。あたかも、蘭と自らの使命を知らずに蘭の受粉を手伝うスズメガのように。」
このように、柳澤は「配置」というアプローチこそ、これまでの強い概念体系では捉えられなかった「幸福な倫理の可能性」に光が当てていくことができるのではないかと考えた訳ですが、自己自身の固有性を心のうちにばかり求めるのではなく、むしろ微妙な配置の仕方やその調整においてこそ求めていくという方針は、今期のやぎ座にもまさにうってつけと言えるのではないでしょうか。
5月30日にやぎ座から数えて「セルフメンテナンス」を意味する6番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、「うまくいく」ことに意識の焦点を起きつつ、身の振り方を調整していくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:柳澤田美『ディスポジション 配置としての世界』(現代企画室)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「<外>への意志」。

2010年代以降、私たちの想像力に求められるテーマは「いかに力を求め、それを実現するか」ということから、「いかに力の支配から抜け出せるか」といった方向へと徐々に変わってきたように思いますが、それは言い方を替えれば、これまでの共同体や歴史において強力な“お約束ごと”として機能してきた「共同幻想」の外側へと飛び出し、そこで垣間見ることのできた「現実」を言葉にしていくための足場を、他ならぬ自分たちの手で構築していくことができるかということでもあるのではないでしょうか。
この場合の「足場」とは、表現のための手段であり、ジャンルとも置き換えることができますが、個人的にはそれは戦後世界でそうであったようなサイエンスでもアカデミズムでもなく、今のところ創作や文芸のうちにより可能性を見出されるように思います。
たとえば、文筆家の木澤佐登志の「INTERNET2」という小説があります。掲載されたSFマガジンで汲まれた「異常論文特集」の監修者である樋口恭介の内容紹介には、「INTERNET2。それは過去に書かれたあらゆるテクストを自由自在に参照し、切り刻み、再構成する。そこにはここまで書かれたすべてがあり、書かれなかったすべてがある」とあるのですが、その一部をすこしだけ引用しておきましょう。
「存在の大いなる連鎖という無限の階梯を登りつめた人類は、遂にみずからを消滅させた。今や彼らはまったく別なる存在となった。性別、個人性、可死性を乗り越えた。自他の区別を乗り越え、感情を克服し、意識を克服した。ポストヒューマンの誕生。
新しい人類の視覚は、その天使的な透明さの中で、宇宙の全ての場所で生じる全ての事象を、色彩の栄光とともに幻視することができた。オルダス・ハクスリーが『知覚の扉』において、メスカリンによる祝福のもとで得た、あの<遍在精神>という聖体示現(ヒエロファニー)がようやく証明されたのであった。
(…)地球の表面上を毛細血管のように覆い尽くしたニューロンの束はやがて集合的無意識を形成するに至る。それは地球の電離層と地表とのあいだで発生するシューマン共振と同期(シンクロ)し、地球はひとつの形態形成場へと生成変化を遂げる。意識を外化させた人間たちはみずからのネットワークを繋ぐ結節点=ノードと化す。天地たちの共鳴し合う集合的無意識は宇宙の隅々にまで伝播していく。その混沌はやがてひとつの形を成していき、共感覚幻想(マトリックス)を、かつて人類が「サイバースペース」と呼んだものを到来させる。われわれはそれをINTERNET2と名付けた。」
ここに描かれたことは、荒唐無稽な絵空事というより、「これまで書かれなかったすべて」が書かれるようになった未来の予見であるように思いますが、同様に、5月30日にみずがめ座から数えて「創造」を意味する5番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、いかに「外への意志」を具現化していけるかが鋭く問われていくはず。
参考:木澤佐登志「INTERNET2」(『SFマガジン2021年6月号「異常論文特集」』所収)
この場合の「足場」とは、表現のための手段であり、ジャンルとも置き換えることができますが、個人的にはそれは戦後世界でそうであったようなサイエンスでもアカデミズムでもなく、今のところ創作や文芸のうちにより可能性を見出されるように思います。
たとえば、文筆家の木澤佐登志の「INTERNET2」という小説があります。掲載されたSFマガジンで汲まれた「異常論文特集」の監修者である樋口恭介の内容紹介には、「INTERNET2。それは過去に書かれたあらゆるテクストを自由自在に参照し、切り刻み、再構成する。そこにはここまで書かれたすべてがあり、書かれなかったすべてがある」とあるのですが、その一部をすこしだけ引用しておきましょう。
「存在の大いなる連鎖という無限の階梯を登りつめた人類は、遂にみずからを消滅させた。今や彼らはまったく別なる存在となった。性別、個人性、可死性を乗り越えた。自他の区別を乗り越え、感情を克服し、意識を克服した。ポストヒューマンの誕生。
新しい人類の視覚は、その天使的な透明さの中で、宇宙の全ての場所で生じる全ての事象を、色彩の栄光とともに幻視することができた。オルダス・ハクスリーが『知覚の扉』において、メスカリンによる祝福のもとで得た、あの<遍在精神>という聖体示現(ヒエロファニー)がようやく証明されたのであった。
(…)地球の表面上を毛細血管のように覆い尽くしたニューロンの束はやがて集合的無意識を形成するに至る。それは地球の電離層と地表とのあいだで発生するシューマン共振と同期(シンクロ)し、地球はひとつの形態形成場へと生成変化を遂げる。意識を外化させた人間たちはみずからのネットワークを繋ぐ結節点=ノードと化す。天地たちの共鳴し合う集合的無意識は宇宙の隅々にまで伝播していく。その混沌はやがてひとつの形を成していき、共感覚幻想(マトリックス)を、かつて人類が「サイバースペース」と呼んだものを到来させる。われわれはそれをINTERNET2と名付けた。」
ここに描かれたことは、荒唐無稽な絵空事というより、「これまで書かれなかったすべて」が書かれるようになった未来の予見であるように思いますが、同様に、5月30日にみずがめ座から数えて「創造」を意味する5番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、いかに「外への意志」を具現化していけるかが鋭く問われていくはず。
参考:木澤佐登志「INTERNET2」(『SFマガジン2021年6月号「異常論文特集」』所収)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「人間にしかできない営みや役割の追求」。
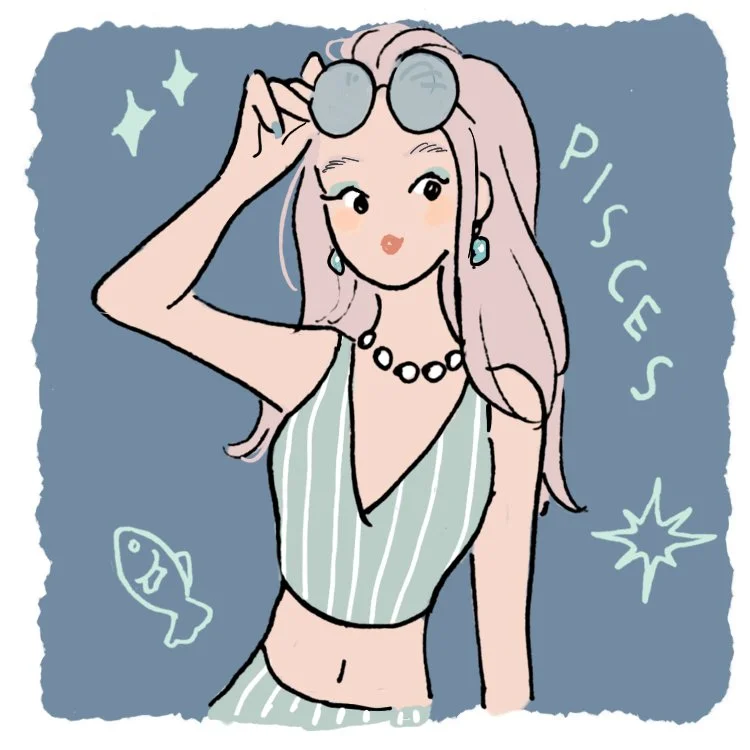
近年急激な発達を遂げてきた人工知能の研究開発の蓄積は、逆説的に人間がいかに高度で複雑なプロセスを何気なく遂行しているかという、人間の営みの再発見のプロセスでもありましたが、今後も重要な焦点となっていく命題をひとつ挙げるとすれば、それは「人間の子供の育児を行うロボットは開発可能か?」ということでしょう。
この点に関して、例えば1980年代に〈バイオエシックス、生命倫理学〉を日本に導入した倫理学者の加藤尚武は、「ロボット」という言葉を1920年に作り(チェコ語で賦役robotaを負うもの=無給労働者)、戯曲として作品化したカレル・チャペックの『ロボット』から、今後ロボット化が禁止されていく可能性が高い領域をあえて推測すれば、それは「家族愛」に関与する領域なのではないかとも述べています。
妊娠・出産もまた特殊なリスクが想定される営みですが(少なくとも子宮のロボット化は当面は技術的に不可能)、それが育児・教育にまでなだらかに広がっていく過程で総体的に成立していく家族的コミュニティの形成までロボット化の可能性を考えてみると、そこには「業務」や「機械的命令と実行の反復」によっては決して成立しえない“何か”が含まれているように思えるからです。
育児や教育というのは、そうした“何か”の内実と深く関係している人間的営みであると考えられていますし、また、世代間コミュニケーションの継続性や、世代交代の持続性を保っていく上でも必要不可欠な営みですが、さらに言えばそれはヒトという種の存在理由を問うという意味でも、証明されなければならないテーマでもあるのではないでしょうか。
現代では人間は「自分にしかできない仕事や役割」を自分の社会的アイデンティティーとしていますが、将来的には「人間にしかできない営みや役割」を自身の存在理由として追求するようになる時代がそう遠くない未来に訪れるかもしれません。
その意味で、5月30日にうお座から数えて「心の支え」を意味する4番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、育児や教育など、人間にしかできない営みや役割を追求していくことが重要なテーマとなっていきそうです。
参考:加藤尚武「ヒトはその存在を失う前に存在理由を失う」(『現代思想2020年9月臨時増刊号 総特集=コロナ時代を生きるための60冊』所収)
この点に関して、例えば1980年代に〈バイオエシックス、生命倫理学〉を日本に導入した倫理学者の加藤尚武は、「ロボット」という言葉を1920年に作り(チェコ語で賦役robotaを負うもの=無給労働者)、戯曲として作品化したカレル・チャペックの『ロボット』から、今後ロボット化が禁止されていく可能性が高い領域をあえて推測すれば、それは「家族愛」に関与する領域なのではないかとも述べています。
妊娠・出産もまた特殊なリスクが想定される営みですが(少なくとも子宮のロボット化は当面は技術的に不可能)、それが育児・教育にまでなだらかに広がっていく過程で総体的に成立していく家族的コミュニティの形成までロボット化の可能性を考えてみると、そこには「業務」や「機械的命令と実行の反復」によっては決して成立しえない“何か”が含まれているように思えるからです。
育児や教育というのは、そうした“何か”の内実と深く関係している人間的営みであると考えられていますし、また、世代間コミュニケーションの継続性や、世代交代の持続性を保っていく上でも必要不可欠な営みですが、さらに言えばそれはヒトという種の存在理由を問うという意味でも、証明されなければならないテーマでもあるのではないでしょうか。
現代では人間は「自分にしかできない仕事や役割」を自分の社会的アイデンティティーとしていますが、将来的には「人間にしかできない営みや役割」を自身の存在理由として追求するようになる時代がそう遠くない未来に訪れるかもしれません。
その意味で、5月30日にうお座から数えて「心の支え」を意味する4番目のふたご座で新月を迎えていく今期のあなたもまた、育児や教育など、人間にしかできない営みや役割を追求していくことが重要なテーマとなっていきそうです。
参考:加藤尚武「ヒトはその存在を失う前に存在理由を失う」(『現代思想2020年9月臨時増刊号 総特集=コロナ時代を生きるための60冊』所収)
<プロフィール>
慶應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
慶應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------無料占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ