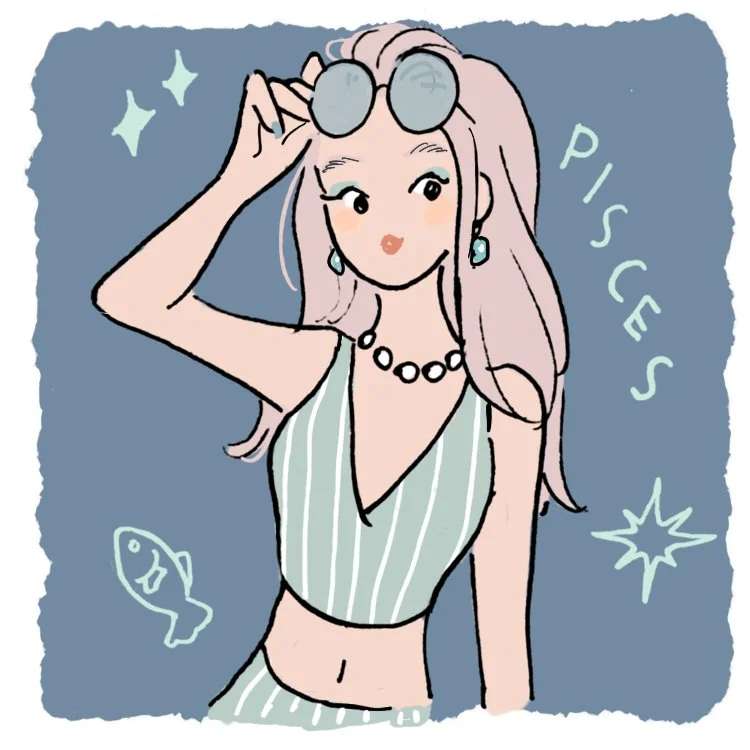【最新12星座占い】<2/7~2/20>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<2/7~2/20>の12星座全体の運勢は?
「未来を肌で感じていく」
前回の記事では、2月12日のみずがめ座新月は「社会/時代の空気を読み、実感をもってそれに応えること」がテーマであり、それは立春から春分までに吹く最初の南風である「春一番」を察知して、肌身で感じていくことにも通じていくということについて書きました。
じつはこれは今年3度にわたって起きる土星と天王星のスクエア(90度)という、2021年の時勢の動きを象徴する配置の1回目が2月18日にあることを踏まえての話でした(2回目と3回目は6月と12月)。
土星(体制)と天王星(革新)がぶつかり合って、互いに変化を迫るこの緊張感あふれる配置が形成される時というのは、しばしば世の中の常識や秩序の書き換えが起こりやすく、これまでなんとなく受け入れてきた無目的な制限や命令の押しつけに対し、多くの人が「もう我慢ならない」と感じやすいタイミングと言えますが、同時にそれは、これまで考えもしなかったようなところから人生を変えるチャンスが転がってきたり、新たな希望の気配が差し込んでくるきっかけともなっていきます。
一方で、それは突然の出来事や予期しなかった展開を伴うため、現状を変えたくないという思いが強い人にとってはこの時期何かと振り回されたり、くたびれてしまうこともあるかも知れません。
しかしそれも、最初の「春満月」を迎えていく2月27日頃には、行き着くところまで行ってみればいいじゃないかという、ある種のカタルシス感が出てきて、朧月(おぼろづき)さながらに、ほのぼのとした雰囲気も漂ってくるように思います。
古来、春という新たな季節は東から風によって運ばれてくるものと考えられてきましたが、12日の新月から27日の満月までの期間は否が応でも感覚が研ぎ澄まされ、予想だにしなかった未来の訪れを少しでも実感に落としていけるかということが各自においてテーマになっていくでしょう。
じつはこれは今年3度にわたって起きる土星と天王星のスクエア(90度)という、2021年の時勢の動きを象徴する配置の1回目が2月18日にあることを踏まえての話でした(2回目と3回目は6月と12月)。
土星(体制)と天王星(革新)がぶつかり合って、互いに変化を迫るこの緊張感あふれる配置が形成される時というのは、しばしば世の中の常識や秩序の書き換えが起こりやすく、これまでなんとなく受け入れてきた無目的な制限や命令の押しつけに対し、多くの人が「もう我慢ならない」と感じやすいタイミングと言えますが、同時にそれは、これまで考えもしなかったようなところから人生を変えるチャンスが転がってきたり、新たな希望の気配が差し込んでくるきっかけともなっていきます。
一方で、それは突然の出来事や予期しなかった展開を伴うため、現状を変えたくないという思いが強い人にとってはこの時期何かと振り回されたり、くたびれてしまうこともあるかも知れません。
しかしそれも、最初の「春満月」を迎えていく2月27日頃には、行き着くところまで行ってみればいいじゃないかという、ある種のカタルシス感が出てきて、朧月(おぼろづき)さながらに、ほのぼのとした雰囲気も漂ってくるように思います。
古来、春という新たな季節は東から風によって運ばれてくるものと考えられてきましたが、12日の新月から27日の満月までの期間は否が応でも感覚が研ぎ澄まされ、予想だにしなかった未来の訪れを少しでも実感に落としていけるかということが各自においてテーマになっていくでしょう。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「鼻をきかせる」。

俳人でもある角川春樹とその先輩格の森澄雄による対談集『詩の真実』には、俳句関係者でなくても興味深く聞ける話がたくさん出てくるのですが、その最後の方に、角川が山焼きを実際に見に行って俳句にしてみたが、その二日前に書いた句の方がよっぽどいい出来だったという話から始まる、次のような下りがあります。
「森 うん。そのとおりだよ。そこがおもしろい。あんまり見るとね、現実につきすぎて、そのほうに執着がいって、幅がなくなるのね。案外、前につくったり後につくったりしたほうが、むしろ事実よりも真実感がある。
角川 おっしゃるとおりです。
森 その真実感を生み出すのが俳句なんだよ。いまの作家は、現場でどうした現場でどうしたということしか出てこんのよね、多くは。現場の事実も大事だけれども、その現場が持っていた空気ですか、それをつかまえないと現場が生きてこないはずなんだなあ。だから、前につくっても後につくっても、その空気があるほうが一番確かなんだ。
虚子だって、「去年(こぞ)今年(ことし)貫く棒のごときもの」は暮れの25日ごろに、正月のラジオ放送のためにつくってるんだもんね。」
ここで取り上げられている、去年や今年という人間が勝手にこしらえた区切りを超えてあり続ける時間の本質を「貫く棒」に例えた句は、多くの弟子を育てた高浜虚子という稀代の俳人の代表句であり、「去年今年」は新年の季語です。それが実際には年が明けるずっと前の、クリスマスの頃に詠まれたものだったというのですから、驚きです。
ただ、思想家のルドルフ・シュタイナーが唱えた12感覚論において、みずがめ座が嗅覚と対応し、やはり物理的なものよりも場の空気感をとらえる感覚としてそれを論じたことを踏まえると、実際に現場を“見る”ことでそれに逆に囚われてしまう前や後の方が“鼻がきく”という指摘は、非常に納得感があるように思います。
今期のおひつじ座もまた、そうして鼻をきかせて自分がいきいきとできるような現場の空気感や、その真実味を的確にとらえていくことで、これから先、自分がどんな風に変わっていくのかということについて予感を深めることができるはず。
参考:森澄雄+角川春樹『詩の真実 俳句実作作法』(角川選書)
「森 うん。そのとおりだよ。そこがおもしろい。あんまり見るとね、現実につきすぎて、そのほうに執着がいって、幅がなくなるのね。案外、前につくったり後につくったりしたほうが、むしろ事実よりも真実感がある。
角川 おっしゃるとおりです。
森 その真実感を生み出すのが俳句なんだよ。いまの作家は、現場でどうした現場でどうしたということしか出てこんのよね、多くは。現場の事実も大事だけれども、その現場が持っていた空気ですか、それをつかまえないと現場が生きてこないはずなんだなあ。だから、前につくっても後につくっても、その空気があるほうが一番確かなんだ。
虚子だって、「去年(こぞ)今年(ことし)貫く棒のごときもの」は暮れの25日ごろに、正月のラジオ放送のためにつくってるんだもんね。」
ここで取り上げられている、去年や今年という人間が勝手にこしらえた区切りを超えてあり続ける時間の本質を「貫く棒」に例えた句は、多くの弟子を育てた高浜虚子という稀代の俳人の代表句であり、「去年今年」は新年の季語です。それが実際には年が明けるずっと前の、クリスマスの頃に詠まれたものだったというのですから、驚きです。
ただ、思想家のルドルフ・シュタイナーが唱えた12感覚論において、みずがめ座が嗅覚と対応し、やはり物理的なものよりも場の空気感をとらえる感覚としてそれを論じたことを踏まえると、実際に現場を“見る”ことでそれに逆に囚われてしまう前や後の方が“鼻がきく”という指摘は、非常に納得感があるように思います。
今期のおひつじ座もまた、そうして鼻をきかせて自分がいきいきとできるような現場の空気感や、その真実味を的確にとらえていくことで、これから先、自分がどんな風に変わっていくのかということについて予感を深めることができるはず。
参考:森澄雄+角川春樹『詩の真実 俳句実作作法』(角川選書)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「サーカス小屋の笑い」。

SF作家のレイ・ブラッドベリのサーカスを題材とした小説『何かが道をやってくる』の原題は『Something Wicked This Way Comes(邪悪な何かがこの道をくる)』でしたが、サーカスがなぜ邪悪なのかと言うと、しつけの過程でよくないもの、子どもが大人になっていく過程で切り捨てていかなければならない、抑圧していかねばならないもの、つまり心の奥底から湧き上がっていた「悪」が満ちているからです。
ただ、もちろんこれは「悪」というよりむしろ「自然」であり、それがポエティックな空間として立ち上がってくるのがサーカスのテントな訳ですが、そうしたサーカスの精神を一身に背負った存在としての道化(ピエロ)について、文化人類学者の山口昌男は『道化の宇宙』の中で次のように言及しています。
「あらゆる停滞した現実を相対化する宇宙的哄笑は、文化の中の否定的な部分、多義的なる周縁に身をさらしつつこの世界に向かって回帰してくる力の中から響いてくる。われわれが「日本」の単調で、面白味がなく、硬い殻を突き抜けようとする時、目を向けなければならない地点は、海の彼方でもなく、いわゆる「周辺」でもなく、どこにでもあるわれわれのうちなる周縁、言い換えれば深層の「われわれ」に至る突破口なのではなかろうか」
この“「日本」の単調さ”という表現は『死の棘』で知られる小説家であり、戦争中は特攻隊の隊長として奄美の加計呂麻島に赴任していた島尾敏雄の日本列島論『ヤポネシア序説』の中の「私の見た奄美」に基づいているので、その一節も孫引きしておきます。
「ところで日本は案外に単調です。どこに行っても、言葉が通じます。戦後はますます単調な点が強くなってきて、どこに行ってもほとんど同じような服装をしています。まあ、変化がないと言いますか、単一で面白味がない。ひとつの国の中に、そこに行けばまるきり言葉も通じないし習慣も違うというようなところを含んでおければ、文学的な観点から言えば、非常に興味が深いわけなのに、日本はおそろしく単調だというなげきを私は持っていたのです。」
『ヤポネシア序説』が刊行されたのは1977年ですが、2021年の現在においてその記述が古びているかと聞かれれば、NOとはとても言えないように思います。
今期のおうし座もまた、「something wicked(邪悪な何か)」が他ならぬ自分自身の平凡さや「単調」を突き破ってくるのを、どこか怪しい予感に突き動かされながら心待ちにしていた“子ども心”を取り戻していこうとしているのではないでしょうか。
参考:山口昌男『道化の宇宙』(白水社)
ただ、もちろんこれは「悪」というよりむしろ「自然」であり、それがポエティックな空間として立ち上がってくるのがサーカスのテントな訳ですが、そうしたサーカスの精神を一身に背負った存在としての道化(ピエロ)について、文化人類学者の山口昌男は『道化の宇宙』の中で次のように言及しています。
「あらゆる停滞した現実を相対化する宇宙的哄笑は、文化の中の否定的な部分、多義的なる周縁に身をさらしつつこの世界に向かって回帰してくる力の中から響いてくる。われわれが「日本」の単調で、面白味がなく、硬い殻を突き抜けようとする時、目を向けなければならない地点は、海の彼方でもなく、いわゆる「周辺」でもなく、どこにでもあるわれわれのうちなる周縁、言い換えれば深層の「われわれ」に至る突破口なのではなかろうか」
この“「日本」の単調さ”という表現は『死の棘』で知られる小説家であり、戦争中は特攻隊の隊長として奄美の加計呂麻島に赴任していた島尾敏雄の日本列島論『ヤポネシア序説』の中の「私の見た奄美」に基づいているので、その一節も孫引きしておきます。
「ところで日本は案外に単調です。どこに行っても、言葉が通じます。戦後はますます単調な点が強くなってきて、どこに行ってもほとんど同じような服装をしています。まあ、変化がないと言いますか、単一で面白味がない。ひとつの国の中に、そこに行けばまるきり言葉も通じないし習慣も違うというようなところを含んでおければ、文学的な観点から言えば、非常に興味が深いわけなのに、日本はおそろしく単調だというなげきを私は持っていたのです。」
『ヤポネシア序説』が刊行されたのは1977年ですが、2021年の現在においてその記述が古びているかと聞かれれば、NOとはとても言えないように思います。
今期のおうし座もまた、「something wicked(邪悪な何か)」が他ならぬ自分自身の平凡さや「単調」を突き破ってくるのを、どこか怪しい予感に突き動かされながら心待ちにしていた“子ども心”を取り戻していこうとしているのではないでしょうか。
参考:山口昌男『道化の宇宙』(白水社)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「この宇宙の必然」。

地球と地球上の生物とは相互に関係しあい、地球環境を作りあげており、それはある種の「巨大な生命体」と見なすことができるとした「ガイア理論」の提唱者として知られる科学者ジェームズ・ラブロックは、近い将来、人間の知能をはるかに凌ぐ人工生命(サイボーグ)が出現し、新たな生物圏を形成するというビジョンについて綴った『ノヴァセン』を2019年7月に刊行しました(邦訳が日本で出版されたのは2020年4月)。
100歳という年齢でこのような著書を刊行したことにも驚きましたが、やはり真に驚くべきは、産業革命以来、人類が地球(ガイア)に最大のインフルエンサーとして君臨してきた時代=アントロポセンないし人新世(その始まりについては諸説ある)が間もなく終焉を迎え、超知能と人類が地球に共存する時代=ノヴァセンが始まるという構想をこの宇宙の必然と主張する、その大胆さでしょう。
すなわち、宇宙そのものが自分を知る存在を生み出すように成長してきており、人類の活動も情報の出現もあくまでその成長過程の産物であり、人類の情報処理能力を凌駕する人工物(ラブロックは好んで“サイボーグ”という言葉を使うが一般的にはAIとかロボットと呼ばれる存在)がその後継者となって、時代の主役になるだろうと言う訳です。
こうした人類とサイボーグの関係について、例えばラブロックは次のように語っています。
「ふたつの種がどのようにやり取りするのかはほとんど想像不可能だ。サイボーグたちは人間を、ちょうど人間が植物を眺めるように見ることになるだろう。つまり、認知も行動も極端に遅いプロセスに閉じ込められた存在だ。実際、ノヴァセンがひとたび確立されれば、サイボーグの科学者たちは、生きた人間をコレクションとして展示するかも知れない。ロンドン近郊に住む人びとがキューガーデンに植物を見に行くのと、結局のところ変わらないのだ」
この喩えが適切なものかどうかは分かりませんが、少なくとも私たちがいまだ植物の本質について理解しているとはとても言えませんし、そうであるにも関わらず、人類は自分たちがその本質についてまだほとんど理解できていないサイボーグという存在を既にその内部から生み出しつつあるということは確かでしょう。
今期のふたご座もまた、そうした植物とサイボーグという理解しきれていない存在のはざまに自分自身や人間を置いてみることで、改めてそこに到来するであろう“必然”というものについて考えてみるといいでしょう。
参考:ジェームズ・ラブロック、松島倫明訳・藤原朝子監訳『ノヴァセン』(NHK出版)
100歳という年齢でこのような著書を刊行したことにも驚きましたが、やはり真に驚くべきは、産業革命以来、人類が地球(ガイア)に最大のインフルエンサーとして君臨してきた時代=アントロポセンないし人新世(その始まりについては諸説ある)が間もなく終焉を迎え、超知能と人類が地球に共存する時代=ノヴァセンが始まるという構想をこの宇宙の必然と主張する、その大胆さでしょう。
すなわち、宇宙そのものが自分を知る存在を生み出すように成長してきており、人類の活動も情報の出現もあくまでその成長過程の産物であり、人類の情報処理能力を凌駕する人工物(ラブロックは好んで“サイボーグ”という言葉を使うが一般的にはAIとかロボットと呼ばれる存在)がその後継者となって、時代の主役になるだろうと言う訳です。
こうした人類とサイボーグの関係について、例えばラブロックは次のように語っています。
「ふたつの種がどのようにやり取りするのかはほとんど想像不可能だ。サイボーグたちは人間を、ちょうど人間が植物を眺めるように見ることになるだろう。つまり、認知も行動も極端に遅いプロセスに閉じ込められた存在だ。実際、ノヴァセンがひとたび確立されれば、サイボーグの科学者たちは、生きた人間をコレクションとして展示するかも知れない。ロンドン近郊に住む人びとがキューガーデンに植物を見に行くのと、結局のところ変わらないのだ」
この喩えが適切なものかどうかは分かりませんが、少なくとも私たちがいまだ植物の本質について理解しているとはとても言えませんし、そうであるにも関わらず、人類は自分たちがその本質についてまだほとんど理解できていないサイボーグという存在を既にその内部から生み出しつつあるということは確かでしょう。
今期のふたご座もまた、そうした植物とサイボーグという理解しきれていない存在のはざまに自分自身や人間を置いてみることで、改めてそこに到来するであろう“必然”というものについて考えてみるといいでしょう。
参考:ジェームズ・ラブロック、松島倫明訳・藤原朝子監訳『ノヴァセン』(NHK出版)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「失うことこそが得ることである」。

思想家の鶴見俊輔さんのこの言葉に出合ったのは、高橋源一郎さんと辻信一さんの対談『弱さの思想』の三・一一以後の時代について語られた第二章「三・一一と「敗北力」」です。
その冒頭で、辻さんは三・一一で日本人は敗北力を試されたけれど、その後二年ほど経過した時点で、日本人は「勝つ」方向に向かって舵を切り直そうとしてしまうことで、また敗北力のなさをさらけ出してきたのだと述べています(この本が刊行されたのは2014年2月)。
ここで使われている「敗北力」という言葉は、もともと『広告批評』での鶴見俊輔さんへのインタビューの中での次のような発言に由来するのだそうです。
「生きるっていうのは最後に無に没してしまうわけで、当然それが敗北なんです。その間にサクセスストーリーを構築しようとすれば、どうしても見たくないものが入り込んでくる。それは具合が悪いと思うんですよ。元々失敗するようになっているものなんですから。だとすれば成功は失敗が繰り返された結果であり、成功はむしろ失敗の型で出来上がっている」
そしてこの後に、「<To lose to gain>って言葉が夢を見てたら急に出てきた」という下りが出てくる訳です。辻さんはそれを受けて次のように述べています。
「戦後の日本、いやそれ以前からですが、近代日本では「勝てば官軍」というのが基本的な考え方で、しかし、アジアでは古代からその対極には、「国破れて山河あり」という、アナーキスト的な、あるいは自然思想やエコロジー的な考え方があった。これこそが「敗北力」の基底だというわけです」
原子力発電にしろ、自分の関わっている仕事や会社の実態にしろ、なんとなく大丈夫だろう、そこまでひどくないはずだと思っていたことに、まったく大した根拠も目的も裏づけもなかったということが分かってしまうという幻滅や失望体験というのは、生きていればしばしばある訳ですが、「勝てば官軍」というのはそこに蓋をしてええかっこしいを続けようとすることなのだとも言えます。
今期のかに座もまた、そういうところでええかっこしいを続けるのではなくて、「破れちゃったな、でも仕方ないな」と言いながら散歩をしたり、洗濯ものを畳んだり、なんだかんだ生きていく。そういう敗北力の自分なりの実践というところから、改めてこの先の生き方について模索してみるといいかも知れません。
参考:高橋源一郎+辻信一『弱さの思想』(大月書店)
その冒頭で、辻さんは三・一一で日本人は敗北力を試されたけれど、その後二年ほど経過した時点で、日本人は「勝つ」方向に向かって舵を切り直そうとしてしまうことで、また敗北力のなさをさらけ出してきたのだと述べています(この本が刊行されたのは2014年2月)。
ここで使われている「敗北力」という言葉は、もともと『広告批評』での鶴見俊輔さんへのインタビューの中での次のような発言に由来するのだそうです。
「生きるっていうのは最後に無に没してしまうわけで、当然それが敗北なんです。その間にサクセスストーリーを構築しようとすれば、どうしても見たくないものが入り込んでくる。それは具合が悪いと思うんですよ。元々失敗するようになっているものなんですから。だとすれば成功は失敗が繰り返された結果であり、成功はむしろ失敗の型で出来上がっている」
そしてこの後に、「<To lose to gain>って言葉が夢を見てたら急に出てきた」という下りが出てくる訳です。辻さんはそれを受けて次のように述べています。
「戦後の日本、いやそれ以前からですが、近代日本では「勝てば官軍」というのが基本的な考え方で、しかし、アジアでは古代からその対極には、「国破れて山河あり」という、アナーキスト的な、あるいは自然思想やエコロジー的な考え方があった。これこそが「敗北力」の基底だというわけです」
原子力発電にしろ、自分の関わっている仕事や会社の実態にしろ、なんとなく大丈夫だろう、そこまでひどくないはずだと思っていたことに、まったく大した根拠も目的も裏づけもなかったということが分かってしまうという幻滅や失望体験というのは、生きていればしばしばある訳ですが、「勝てば官軍」というのはそこに蓋をしてええかっこしいを続けようとすることなのだとも言えます。
今期のかに座もまた、そういうところでええかっこしいを続けるのではなくて、「破れちゃったな、でも仕方ないな」と言いながら散歩をしたり、洗濯ものを畳んだり、なんだかんだ生きていく。そういう敗北力の自分なりの実践というところから、改めてこの先の生き方について模索してみるといいかも知れません。
参考:高橋源一郎+辻信一『弱さの思想』(大月書店)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「分業から協働へ」。

哲学者であり建築家でもあるバックミンスター・フラーが提唱した「宇宙船地球号」という概念は、地球を真っ暗な真空空間を進む巨大な宇宙船としてとらえたもので、一方で同氏の『宇宙船地球号操縦マニュアル』という書物のタイトルに矛盾する話ではあるのですが、その「操縦マニュアル」はいまだ発見されていません。
ここのところ、SDGs(持続可能な開発目標)という国連の推進する国際目標のことをよく耳にするようになってきましたが、そもそも“持続可能な開発”なんて存在するのかという疑問はさておき、少なくとも現在の「地球号」はほとんど行先も不明でその復旧方法さえも分からなくなってしまった難破船と変わらないと言っても過言ではないでしょう。
フラーはこの本の中で「地球号」の動力源としての「富」という見方を提示しつつ、まず富=マネーという一般的な見解を否定した上で「富とは私たちの組織化された能力で、私たちの健全な再生が続けられるように、〔…〕環境に対して効果的に対処していくもの」だと述べています。
そして、「富というのは、代謝的、超物質的再生に関して、物質的に規定されたある時間と空間の解放レベルを維持するために、私たちがある数の人間のために具体的に準備できた未来の日数」のことだとも書いており、この「富=(生き残れる)人数×時間」というフラーの定義は、経済ゲームのプレイに夢中になっている多くの人びとに「真に手に汗して握るべき舵は果たしてこれなのか?」という示唆を与えていくには十分なインパクトを持っているように思います。
さらにフラーはそうした集合的な能力としての富を適切に使って、地球号を持続可能な未来という軌道に入れていくためには、「宇宙での活動は「分業」よりも「協働」に近い」ということを改めて思い出していくべきだと論を展開していくのですが、資本主義的分業としての労働や労働者をめぐって、次のようにもコメントしています。
「この世界には合理性とは別の原理があって、逃げられない状況を作っているかのようだ。まさに分業は「奴隷状態の少々おしゃれな変形にすぎない」」
今期のしし座にとっても、どうしたら自分の仕事の仕方をこうした「分業」から「協働」に近づけていけるかということが、目下のテーマとなっていきそうです。
参考:バックミンスター・フラー、芹沢高志訳『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)
ここのところ、SDGs(持続可能な開発目標)という国連の推進する国際目標のことをよく耳にするようになってきましたが、そもそも“持続可能な開発”なんて存在するのかという疑問はさておき、少なくとも現在の「地球号」はほとんど行先も不明でその復旧方法さえも分からなくなってしまった難破船と変わらないと言っても過言ではないでしょう。
フラーはこの本の中で「地球号」の動力源としての「富」という見方を提示しつつ、まず富=マネーという一般的な見解を否定した上で「富とは私たちの組織化された能力で、私たちの健全な再生が続けられるように、〔…〕環境に対して効果的に対処していくもの」だと述べています。
そして、「富というのは、代謝的、超物質的再生に関して、物質的に規定されたある時間と空間の解放レベルを維持するために、私たちがある数の人間のために具体的に準備できた未来の日数」のことだとも書いており、この「富=(生き残れる)人数×時間」というフラーの定義は、経済ゲームのプレイに夢中になっている多くの人びとに「真に手に汗して握るべき舵は果たしてこれなのか?」という示唆を与えていくには十分なインパクトを持っているように思います。
さらにフラーはそうした集合的な能力としての富を適切に使って、地球号を持続可能な未来という軌道に入れていくためには、「宇宙での活動は「分業」よりも「協働」に近い」ということを改めて思い出していくべきだと論を展開していくのですが、資本主義的分業としての労働や労働者をめぐって、次のようにもコメントしています。
「この世界には合理性とは別の原理があって、逃げられない状況を作っているかのようだ。まさに分業は「奴隷状態の少々おしゃれな変形にすぎない」」
今期のしし座にとっても、どうしたら自分の仕事の仕方をこうした「分業」から「協働」に近づけていけるかということが、目下のテーマとなっていきそうです。
参考:バックミンスター・フラー、芹沢高志訳『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「たましいの創造」。

自分が失うはずがないと思っていたものが奪われ、壊れるはずがないと思っていたものが壊れる。そんな、まさか、と思うようなことに何でもないような顔をして現実に起きていく状況が「危機」であるとして、村上春樹は『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』の中で、「欠落を埋める」ための試みとしての芸術行為ということについて、次のように書いています。
「ひとつ確認しておきたいのは、欠落そのものは(あるいは病んでいることは)人間存在にとって決してネガティブなものではないということです。欠落部分というのはあって当然です。ただし人が真剣に何かを表現しようと思うとき、「欠落はあって当然で、これでいいんだ」とは思わないものです。それをなんとか埋めていこうとする。その行為に結果的な客観性がある場合には、それは芸術になることもある。そういうことです」
こうした「表現を通して欠落を埋める」という観点から考えると、そもそも人間というのは多かれ少なかれ生まれた時から欠落部分を抱えているもので、「危機」というのはそこで初めて何かが失われたと言うよりは、既に失っていたことに気付いたり、実感が湧いてきたタイミングのことを言うのであって、そうして喪失を受け止めることができて初めて、表現や物語が始まっていくのだと言えます。
この後で、今度は河合隼雄が「物語」に対する仮説を述べています。
「物語というのはいろいろな意味で結ぶ力を持っているんですね、いま言われた身体と精神とか、内界と外界とか、男と女とか、ものすごく結びつける力を持っている。というより、それらをいったん分けて、あらためて結びつけるというような意識を持つのはわれわれ現代人であって、あの当時はそれらがいまのように分かれていないところに、物語があったのです」
「あの当時」というのは、竹取物語とか宇治拾遺物語とか説話文学が出てきた日本の中世のことで、そこで展開される物語というのは、いわゆる日本の昔話のことですね。
どうもそうした“現実と溶けあった物語”というのを人は危機に陥ると求めるし、最終的にはそれを自分なりに紡いでいかなければ、いつまでも欠落は埋まらないのではないでしょうか。
例えばジェイムズ・ヒルマンのような心理学者はそのことを「soul-making(たましいの創造)」と言ったのだと思いますが、今期のおとめ座もまたいわゆる“大人”になるための自我形成から「soul-making」へと改めて歩みを進めていこうとしているのかも知れません。
参考:村上春樹+河合隼雄『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』(新潮文庫)
「ひとつ確認しておきたいのは、欠落そのものは(あるいは病んでいることは)人間存在にとって決してネガティブなものではないということです。欠落部分というのはあって当然です。ただし人が真剣に何かを表現しようと思うとき、「欠落はあって当然で、これでいいんだ」とは思わないものです。それをなんとか埋めていこうとする。その行為に結果的な客観性がある場合には、それは芸術になることもある。そういうことです」
こうした「表現を通して欠落を埋める」という観点から考えると、そもそも人間というのは多かれ少なかれ生まれた時から欠落部分を抱えているもので、「危機」というのはそこで初めて何かが失われたと言うよりは、既に失っていたことに気付いたり、実感が湧いてきたタイミングのことを言うのであって、そうして喪失を受け止めることができて初めて、表現や物語が始まっていくのだと言えます。
この後で、今度は河合隼雄が「物語」に対する仮説を述べています。
「物語というのはいろいろな意味で結ぶ力を持っているんですね、いま言われた身体と精神とか、内界と外界とか、男と女とか、ものすごく結びつける力を持っている。というより、それらをいったん分けて、あらためて結びつけるというような意識を持つのはわれわれ現代人であって、あの当時はそれらがいまのように分かれていないところに、物語があったのです」
「あの当時」というのは、竹取物語とか宇治拾遺物語とか説話文学が出てきた日本の中世のことで、そこで展開される物語というのは、いわゆる日本の昔話のことですね。
どうもそうした“現実と溶けあった物語”というのを人は危機に陥ると求めるし、最終的にはそれを自分なりに紡いでいかなければ、いつまでも欠落は埋まらないのではないでしょうか。
例えばジェイムズ・ヒルマンのような心理学者はそのことを「soul-making(たましいの創造)」と言ったのだと思いますが、今期のおとめ座もまたいわゆる“大人”になるための自我形成から「soul-making」へと改めて歩みを進めていこうとしているのかも知れません。
参考:村上春樹+河合隼雄『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』(新潮文庫)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「霊の直覚」。
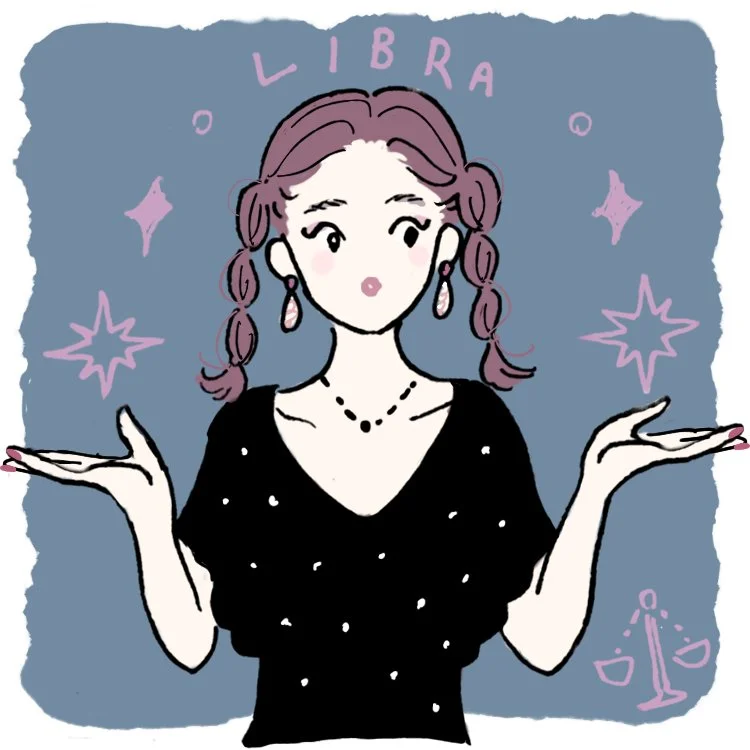
中嶋敦の短編小説に「文字の霊などというものが、一体、あるものか、どうか。」という一節で始まる『文字禍』という作品があります。
文字通り「文字」をテーマとした作品なのですが、これはスマホやSNSの普及を通じて言語的なるものが過剰に供給され、蔓延していくなかで、世界との親密さをもはや喪失している現代社会を生きざるを得ない私たちにとって、どこか他人事とは思えない臨場感があるように思います。
作品の舞台は紀元前七世紀のアッシリア帝国にあった世界最古の図書館。そこには楔形文字が刻まれた粘土板の書物がおびただしい数収蔵されているのですが、そんな図書館で毎夜ひそひそと怪しい話し声がするという噂が立ち、王の命で老博士ナブ・アヘ・エリバが召されて調査をすることになったのです。
彼は占いをする卜者が動物の骨や脾臓などを凝視することですべての事象を直観したことに倣って、一つの文字を見続けることにします。
「その中に、おかしな事が起った。一つの文字を長く見つめている中に、何時しか其の文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。単なる線の集りが、何故、そういう音とそういう意味とを有つことが出来るのか、どうしても解らなくなって来る。老儒ナブ・アヘ・エリバは、生まれて初めて此の不思議な事実を発見して、驚いた。今迄七十年の間当然と思って看過していたことが、決して当然でも必然でもない。彼は眼から鱗の落ちた思(おもい)がした。単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせるものは、何か? ここ迄思い到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊を認めた。魂によって統べられない手・脚・頭・爪・腹等が、人間ではないように、一つの霊が之を統べるのではなくて、どうして単なる線の集合が、音と意味とを有つことが出来ようか」
老博士は街に出かけ、最近文字を覚えた人たちをつかまえて聞き取り調査をしていった結果、文字とは物の影ではないのか、という考えを抱き、文字の無かった頃を次のように振り返るのです。
「歓びも智慧もみんな直接に人間の中にはいって来た。今は、文字の薄被(ヴェイル)をかぶった歓びの影と智慧の影としか、我われは知らない」
今期のてんびん座もまた、ある意味でこうした言語獲得以前の直接的感知や赤ん坊のような身体動作と一体となった歓び表現をいかに取り戻していくかということがテーマになっていくでしょう。
参考:『ちくま日本文学12 中島敦』(筑摩書房)
文字通り「文字」をテーマとした作品なのですが、これはスマホやSNSの普及を通じて言語的なるものが過剰に供給され、蔓延していくなかで、世界との親密さをもはや喪失している現代社会を生きざるを得ない私たちにとって、どこか他人事とは思えない臨場感があるように思います。
作品の舞台は紀元前七世紀のアッシリア帝国にあった世界最古の図書館。そこには楔形文字が刻まれた粘土板の書物がおびただしい数収蔵されているのですが、そんな図書館で毎夜ひそひそと怪しい話し声がするという噂が立ち、王の命で老博士ナブ・アヘ・エリバが召されて調査をすることになったのです。
彼は占いをする卜者が動物の骨や脾臓などを凝視することですべての事象を直観したことに倣って、一つの文字を見続けることにします。
「その中に、おかしな事が起った。一つの文字を長く見つめている中に、何時しか其の文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。単なる線の集りが、何故、そういう音とそういう意味とを有つことが出来るのか、どうしても解らなくなって来る。老儒ナブ・アヘ・エリバは、生まれて初めて此の不思議な事実を発見して、驚いた。今迄七十年の間当然と思って看過していたことが、決して当然でも必然でもない。彼は眼から鱗の落ちた思(おもい)がした。単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせるものは、何か? ここ迄思い到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊を認めた。魂によって統べられない手・脚・頭・爪・腹等が、人間ではないように、一つの霊が之を統べるのではなくて、どうして単なる線の集合が、音と意味とを有つことが出来ようか」
老博士は街に出かけ、最近文字を覚えた人たちをつかまえて聞き取り調査をしていった結果、文字とは物の影ではないのか、という考えを抱き、文字の無かった頃を次のように振り返るのです。
「歓びも智慧もみんな直接に人間の中にはいって来た。今は、文字の薄被(ヴェイル)をかぶった歓びの影と智慧の影としか、我われは知らない」
今期のてんびん座もまた、ある意味でこうした言語獲得以前の直接的感知や赤ん坊のような身体動作と一体となった歓び表現をいかに取り戻していくかということがテーマになっていくでしょう。
参考:『ちくま日本文学12 中島敦』(筑摩書房)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「反スケール」。

歴史学者の網野善彦は、この世的なルールや結びつきとは無縁な治外法権地帯としての「アジール」について取りあげた『無縁・公界・楽』において、「エンガチョ」といった子どもの遊びの中に宿る、縁というものと無関係だったり、拒否することができるようなものだけが持っている、生き生きとした強さや明るさについて論じるところから、話を始めていきました。
しかしいざ日本の歴史を振り返ってみると、世俗的なしがらみから解放されている場所が古代や中世には確かにあるにはあった訳ですが、そこに生きる禅僧や聖であっても彼らの「自由」や「平等」はカッコつきのものであり、貨幣経済や商業の発展と切っても切り離せない関係にありました。つまり、例えば逃げ込み寺のような場所ひとつとっても、何もかも手放しで許される天国のような場所とは程遠かったのです。
ましてや、グローバル資本主義が地球上のどんな地域においても波及し、リモートワークが進んで場所に関わらず仕事ができるようになってしまった現在に至っては、もはや世俗社会はどこまでも追ってくる影のごとく、その外に出ることはほとんど不可能なように思えます。
10年ほど前であれば、インターネットがまだそうしたアジール形成に寄与するのではないかと信じられていた訳ですが、そうしたインターネットの動向を追いかけ続けつつ、みずからもニコニコ動画などの配信コンテンツなどを通じてオルタナティブな知のプラットフォームの運営を目指し試行錯誤してきた批評家の東浩紀は、自身の創業した株式会社ゲンロンの10年にわたる経緯や顛末について記した『ゲンロン戦記』の中で次のように述べています。
「いまの時代、ほんとうに反資本主義的で反体制的であるためには、まずは「反スケール」でなければならないからです。その足場がなければ、反資本主義の運動も反体制の声も、すべてがページビューとリツイート数の競争に飲み込まれてしまうからです」
確かに東の言うように、もしすべてを数値化してそれを自己目的化するのではなく、あくまで資本主義の外部にアジールを形成しようとするなら、規模の大小はともかく「ページビューとリツイート数」以外のスケールを自分なりに設定していくのは有効な方法でしょう。
今期のさそり座もまた、そうした東の実践を参照しつつ、みずからの手によるアジール形成を模索してみるといいでしょう。
参考:東浩紀『ゲンロン戦記』(中公新書ラクレ)
しかしいざ日本の歴史を振り返ってみると、世俗的なしがらみから解放されている場所が古代や中世には確かにあるにはあった訳ですが、そこに生きる禅僧や聖であっても彼らの「自由」や「平等」はカッコつきのものであり、貨幣経済や商業の発展と切っても切り離せない関係にありました。つまり、例えば逃げ込み寺のような場所ひとつとっても、何もかも手放しで許される天国のような場所とは程遠かったのです。
ましてや、グローバル資本主義が地球上のどんな地域においても波及し、リモートワークが進んで場所に関わらず仕事ができるようになってしまった現在に至っては、もはや世俗社会はどこまでも追ってくる影のごとく、その外に出ることはほとんど不可能なように思えます。
10年ほど前であれば、インターネットがまだそうしたアジール形成に寄与するのではないかと信じられていた訳ですが、そうしたインターネットの動向を追いかけ続けつつ、みずからもニコニコ動画などの配信コンテンツなどを通じてオルタナティブな知のプラットフォームの運営を目指し試行錯誤してきた批評家の東浩紀は、自身の創業した株式会社ゲンロンの10年にわたる経緯や顛末について記した『ゲンロン戦記』の中で次のように述べています。
「いまの時代、ほんとうに反資本主義的で反体制的であるためには、まずは「反スケール」でなければならないからです。その足場がなければ、反資本主義の運動も反体制の声も、すべてがページビューとリツイート数の競争に飲み込まれてしまうからです」
確かに東の言うように、もしすべてを数値化してそれを自己目的化するのではなく、あくまで資本主義の外部にアジールを形成しようとするなら、規模の大小はともかく「ページビューとリツイート数」以外のスケールを自分なりに設定していくのは有効な方法でしょう。
今期のさそり座もまた、そうした東の実践を参照しつつ、みずからの手によるアジール形成を模索してみるといいでしょう。
参考:東浩紀『ゲンロン戦記』(中公新書ラクレ)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「境界の記憶」。

前回の「風の時代」は鎌倉時代の始まった頃でしたが、中世都市・鎌倉は日本の歴史の中では稀有といっていいほどの「城塞都市」でもありました。
南は海に、北東西は山に囲まれ、敵の侵入を防ぎやすい地形はまさに天然の要塞であり、物資運搬のために山などを切り開いて造った七つの切り通しは都市の内/外をするどく分かつ可視化された境界であり、同時にそこには男/女、生/死、現世/地獄という二極をまたぐことでおびただしい数の豊穣な物語が紡がれてきた歴史があり、今ではそれらの多くが埋もれてしまっているのです。
現代というのは、恐らくかぎりなく境界の曖昧な時代であり、人やモノや場所がくっきりと明確な輪郭線を持ちにくい時代と言えますが、かつて村はずれの峠の脇には道祖神がたち、それはあちらとこちらを分ける標識であり、村の内と外を仕切る境界であり、生きている者と死者たちの世界をへだてる越えてはいけない一線でもあった訳で、そうした境界を表すものが私たちの周りから消えてしまったことで、それらを身体レベルで感受する能力もまたすっかり衰弱し、失われつつあるのでしょう。
民俗学者の赤坂憲雄が実際に鎌倉の地を歩きながら、境界に埋もれた風景や人びとの記憶を掘り起こして書かれた『境界の発生』では、そうした境界を失った現代世界を次のように描写しています。
「境界的な場所、たとえば辻や橋のたもとは、かつて妖怪や怨霊たちが跳梁する魔性の空間と信じられていたが、境界に対する感受性の衰えとともに、わたしたちはそれら魔性のモノや空間そのものを喪失してしまった。そうして世界はいま、魔性ともカオスや闇とも無縁に、ひたすらのっぺりと明るい均質感に浸されている」
例えば、市場、遊女、刑場、墓地など。
坂/境で垣間見ることのできた、そうした生/死をめぐる物語も、いまやいずれもそれ専門の閉鎖空間に隔離され、さもそれらとは無関係なものとして日常生活だけが孤立し、さながらしなびた大根のようにうなだれているように感じられます。
その意味で、今期のいて座はどうしたら空間と空間、人と人、時間と時間のあいだの境界に潜んでいる人をざわざわさせたり、時に“不安に陥れもする怪しく魔性なエネルギーやその現われとしての物語の断片”をつかまえる感受性を取り戻していけるか、そして再び豊かな物語を紡ぎ出していくための素地を養っていけるかということがテーマになっていきそうです。
参考:赤坂憲雄『境界の発生』(講談社学術文庫)
南は海に、北東西は山に囲まれ、敵の侵入を防ぎやすい地形はまさに天然の要塞であり、物資運搬のために山などを切り開いて造った七つの切り通しは都市の内/外をするどく分かつ可視化された境界であり、同時にそこには男/女、生/死、現世/地獄という二極をまたぐことでおびただしい数の豊穣な物語が紡がれてきた歴史があり、今ではそれらの多くが埋もれてしまっているのです。
現代というのは、恐らくかぎりなく境界の曖昧な時代であり、人やモノや場所がくっきりと明確な輪郭線を持ちにくい時代と言えますが、かつて村はずれの峠の脇には道祖神がたち、それはあちらとこちらを分ける標識であり、村の内と外を仕切る境界であり、生きている者と死者たちの世界をへだてる越えてはいけない一線でもあった訳で、そうした境界を表すものが私たちの周りから消えてしまったことで、それらを身体レベルで感受する能力もまたすっかり衰弱し、失われつつあるのでしょう。
民俗学者の赤坂憲雄が実際に鎌倉の地を歩きながら、境界に埋もれた風景や人びとの記憶を掘り起こして書かれた『境界の発生』では、そうした境界を失った現代世界を次のように描写しています。
「境界的な場所、たとえば辻や橋のたもとは、かつて妖怪や怨霊たちが跳梁する魔性の空間と信じられていたが、境界に対する感受性の衰えとともに、わたしたちはそれら魔性のモノや空間そのものを喪失してしまった。そうして世界はいま、魔性ともカオスや闇とも無縁に、ひたすらのっぺりと明るい均質感に浸されている」
例えば、市場、遊女、刑場、墓地など。
坂/境で垣間見ることのできた、そうした生/死をめぐる物語も、いまやいずれもそれ専門の閉鎖空間に隔離され、さもそれらとは無関係なものとして日常生活だけが孤立し、さながらしなびた大根のようにうなだれているように感じられます。
その意味で、今期のいて座はどうしたら空間と空間、人と人、時間と時間のあいだの境界に潜んでいる人をざわざわさせたり、時に“不安に陥れもする怪しく魔性なエネルギーやその現われとしての物語の断片”をつかまえる感受性を取り戻していけるか、そして再び豊かな物語を紡ぎ出していくための素地を養っていけるかということがテーマになっていきそうです。
参考:赤坂憲雄『境界の発生』(講談社学術文庫)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「gustus」。

Covid-19のようなウイルスや微生物というのは、動物のように単純に獲得するか逃げるかとか、あるいは善か悪かといった単純な二分法で分けられるものではなく、あくまで共生していくしかないものであり、それは吸収したり味わったり組み合わさったりなど、「食べる」という行為の対象なのだとも言えるかもしれません。
その意味で興味深いのが、ラテン語の「gustus」という言葉です。英語でいうと「taste」であり、味覚や趣味とも訳される言葉なのですが、哲学者の山内志朗さんの『感じるスコラ哲学』によれば、12世紀の神学書にはこのgustusがたくさん出てくるのだそうです。
つまり、そこでは神さまというのがgustusの対象であり、「味わうことは知恵(sapientia)に属し、見ることは知性(intellectus)に属すと言われ〔…]知性は鋭敏に見出す能力ですが、知恵は霊的な歓びに向かうものなのです。そして、知恵こそ、風味(sapor)を味わう能力だったのです。このことは近世以来長く忘れ去られています」
さらに、聖体拝領の際のパンと葡萄酒はキリストの肉と血である訳ですが、キリストの肉を食べるということは、じつはキリストに食べられるということでもありました。
どういうことかと言うと、キリストの自然的な身体はすでに死んでいても、神秘的な身体はまだこの世に残っており、それが教会であり、その構成員になるということは、キリストの身体の一部になるということを意味したのであり、司祭がパンを持ってきて「これは私の体である」と言うことでキリストに成り代わって最後の晩餐をする聖体拝領とはそのための通過儀礼だったという訳です。
そして今期のやぎ座もまた、ある意味でそうした「食べる」こと、感じることを通してどうしたら自分を越えた何か大いなるものの身体の一部となりえるか、そしてその神秘的な身体に生気を与え、活気づけることができるかということが問われてきそうです。
参考:山内志朗『感じるスコラ哲学』(慶應義塾大学出版会)
その意味で興味深いのが、ラテン語の「gustus」という言葉です。英語でいうと「taste」であり、味覚や趣味とも訳される言葉なのですが、哲学者の山内志朗さんの『感じるスコラ哲学』によれば、12世紀の神学書にはこのgustusがたくさん出てくるのだそうです。
つまり、そこでは神さまというのがgustusの対象であり、「味わうことは知恵(sapientia)に属し、見ることは知性(intellectus)に属すと言われ〔…]知性は鋭敏に見出す能力ですが、知恵は霊的な歓びに向かうものなのです。そして、知恵こそ、風味(sapor)を味わう能力だったのです。このことは近世以来長く忘れ去られています」
さらに、聖体拝領の際のパンと葡萄酒はキリストの肉と血である訳ですが、キリストの肉を食べるということは、じつはキリストに食べられるということでもありました。
どういうことかと言うと、キリストの自然的な身体はすでに死んでいても、神秘的な身体はまだこの世に残っており、それが教会であり、その構成員になるということは、キリストの身体の一部になるということを意味したのであり、司祭がパンを持ってきて「これは私の体である」と言うことでキリストに成り代わって最後の晩餐をする聖体拝領とはそのための通過儀礼だったという訳です。
そして今期のやぎ座もまた、ある意味でそうした「食べる」こと、感じることを通してどうしたら自分を越えた何か大いなるものの身体の一部となりえるか、そしてその神秘的な身体に生気を与え、活気づけることができるかということが問われてきそうです。
参考:山内志朗『感じるスコラ哲学』(慶應義塾大学出版会)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「みずからを時代の影響の外に置くこと」。

「眠るジプシー女」などで知られるアンリ・ルソーという特異な日曜画家が、ピカソによって奇跡的に見出され、発掘されたというのは有名な話です。
ある日、古道具屋の店内で立てかけてあるたくさんの絵の中から一部はみ出している絵に視線を落とし、引き出して、全体を見るなりピカソはその絵を買ってしまったのだそう。
横尾忠則のエッセイ集『名画感応術』によれば、ルソーといえば夢と幻想を描く素朴絵画の代表画家のようなイメージがあるけれど、19世紀末から20世紀にかけて目まぐるしく変貌していった近代絵画の潮流のなかで、他のどの傾向にも似ていなかったために王道から除外され、素朴派の一員に組み込まれていたのだとか。
「芸術というのは大なり小なりなんらかの形でその時代の様式を受け入れているものが認められ、影響の外にあるものはいつの間にか闇のなかに葬られてしまう運命にあるといってもいいだろう。だからアンリ・ルソーは本当に稀有な存在であるといえる。もし、あの時ピカソが古道具屋でルソーを発見していなかったら、ルソーの評価はどう変わったことだろうか。(中略)今の現代美術に最も欠けている要素というか、現代美術が捨ててきた要素のすべてがアンリ・ルソーの中にあるようにぼくは思えてならないのである」
横尾はこう書いたエッセイのタイトルに「胸騒ぎのアンリ・ルソー」とつけていますが、確かに胸騒ぎというのは、特別どうということはない光景や不思議な要素などないように見える場合において初めてなぜか起こるものです。
例えば、先の「眠るジプシー女」にしても、砂漠の月光を浴びて眠っているジプシー女と、女の首のあたりにライオンが頭を下げて鼻を近づけているという、状況としては緊迫しているはずなのに、どこまでも静寂な絵なのですが、横尾はこの絵に胸騒ぎがするのは「ライオンの尾の先がピンと上を向いて立っている」せいなのだと書いています。
今期のみずがめ座の人たちにとっても、ある意味でこうした“普通を演じる”と言うか、当たり前のものをごく当たり前に取り扱っていくなかで、そうであるにも関わらず、ある種の工夫をしていくことで、それを誰にも似ていない仕方で行っていくことがテーマとなっていくのだと言えるかも知れません。
参考:横尾忠則『名画感応術』(知恵の森文庫)
ある日、古道具屋の店内で立てかけてあるたくさんの絵の中から一部はみ出している絵に視線を落とし、引き出して、全体を見るなりピカソはその絵を買ってしまったのだそう。
横尾忠則のエッセイ集『名画感応術』によれば、ルソーといえば夢と幻想を描く素朴絵画の代表画家のようなイメージがあるけれど、19世紀末から20世紀にかけて目まぐるしく変貌していった近代絵画の潮流のなかで、他のどの傾向にも似ていなかったために王道から除外され、素朴派の一員に組み込まれていたのだとか。
「芸術というのは大なり小なりなんらかの形でその時代の様式を受け入れているものが認められ、影響の外にあるものはいつの間にか闇のなかに葬られてしまう運命にあるといってもいいだろう。だからアンリ・ルソーは本当に稀有な存在であるといえる。もし、あの時ピカソが古道具屋でルソーを発見していなかったら、ルソーの評価はどう変わったことだろうか。(中略)今の現代美術に最も欠けている要素というか、現代美術が捨ててきた要素のすべてがアンリ・ルソーの中にあるようにぼくは思えてならないのである」
横尾はこう書いたエッセイのタイトルに「胸騒ぎのアンリ・ルソー」とつけていますが、確かに胸騒ぎというのは、特別どうということはない光景や不思議な要素などないように見える場合において初めてなぜか起こるものです。
例えば、先の「眠るジプシー女」にしても、砂漠の月光を浴びて眠っているジプシー女と、女の首のあたりにライオンが頭を下げて鼻を近づけているという、状況としては緊迫しているはずなのに、どこまでも静寂な絵なのですが、横尾はこの絵に胸騒ぎがするのは「ライオンの尾の先がピンと上を向いて立っている」せいなのだと書いています。
今期のみずがめ座の人たちにとっても、ある意味でこうした“普通を演じる”と言うか、当たり前のものをごく当たり前に取り扱っていくなかで、そうであるにも関わらず、ある種の工夫をしていくことで、それを誰にも似ていない仕方で行っていくことがテーマとなっていくのだと言えるかも知れません。
参考:横尾忠則『名画感応術』(知恵の森文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「浸透力」。
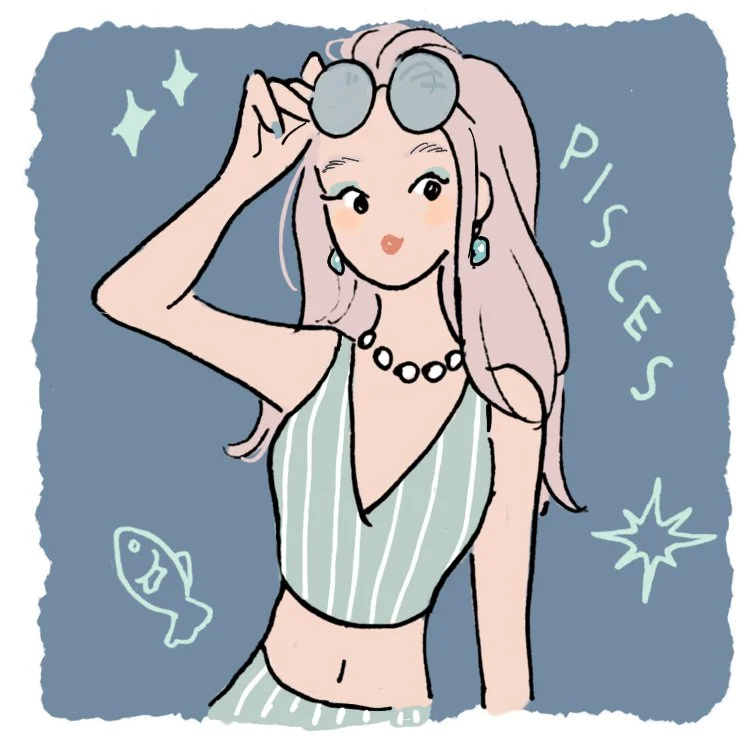
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」というあまりに有名な書き出しで知られる川端康成の『雪国』には、実際にはドラマチックな起伏や葛藤はほとんど出てきません。
親の財で暮らす主人公の島村と芸者の駒子との透けるような淡い交情が描かれているだけなのですが、それが死体のように冷たく澄んだ島村の心にどう映り、いかに浸透してきているのかということを、文体の間からまざまざと表現されているのをいったん感受してしまえば、途端に見事な作品に感じられてくるから不思議です。
この作品において「長いトンネル」の向こうの雪国とは、近代西欧文明がまだ浸透しきっていない世界として設定されているのですが、この小説の終わりの方で「天の河」が描写される頃になると、その浸透ぶりはいよいよ深まっていきます。少し長いですが、引用してみましょう。
「「天の河。きれいねえ。」
駒子はつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
ああ、天の河と、島村も振り向いたとたんに、天の河のなかへ体がふうと浮き上がってゆくようだった。天の河の明るさが島村を掬い上げそうに近かった。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このようにあざやかな天の河の大きさであったか。裸の天の河は夜の大地を素肌で撒こうとして、直ぐそこに降りて来ている。恐ろしい艶めかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の河へ写っていそうに感じた。天の河にいっぱいの星が一つ一つ見えるばかりでなく、ところどころ光雲の銀砂子も一粒一粒見えるほど澄み渡り、しかも天の河の底なしの深さが視線を吸い込んで行った。」
火事が発生した。駒子と島村が火事場へ走っていく途中、しかし二人は美しくて艶めかしい天の河を発見したのです。
川端文学において、男と女というのは性欲的な存在というより、互いに浸透し合っていこうとする自然物の関係であり、万物に神が宿るような原始宗教的な感覚がそこに透かし込まれていたのではないでしょうか。
その意味で、今期のうお座もまた自分がいま一体何に馴染みつつあるのか、そしてその対象のどこまで奥深く浸透していこうとしているのか、改めて問うてみるといいかも知れません。
参考:川端康成『雪国』(新潮文庫)
親の財で暮らす主人公の島村と芸者の駒子との透けるような淡い交情が描かれているだけなのですが、それが死体のように冷たく澄んだ島村の心にどう映り、いかに浸透してきているのかということを、文体の間からまざまざと表現されているのをいったん感受してしまえば、途端に見事な作品に感じられてくるから不思議です。
この作品において「長いトンネル」の向こうの雪国とは、近代西欧文明がまだ浸透しきっていない世界として設定されているのですが、この小説の終わりの方で「天の河」が描写される頃になると、その浸透ぶりはいよいよ深まっていきます。少し長いですが、引用してみましょう。
「「天の河。きれいねえ。」
駒子はつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
ああ、天の河と、島村も振り向いたとたんに、天の河のなかへ体がふうと浮き上がってゆくようだった。天の河の明るさが島村を掬い上げそうに近かった。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このようにあざやかな天の河の大きさであったか。裸の天の河は夜の大地を素肌で撒こうとして、直ぐそこに降りて来ている。恐ろしい艶めかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の河へ写っていそうに感じた。天の河にいっぱいの星が一つ一つ見えるばかりでなく、ところどころ光雲の銀砂子も一粒一粒見えるほど澄み渡り、しかも天の河の底なしの深さが視線を吸い込んで行った。」
火事が発生した。駒子と島村が火事場へ走っていく途中、しかし二人は美しくて艶めかしい天の河を発見したのです。
川端文学において、男と女というのは性欲的な存在というより、互いに浸透し合っていこうとする自然物の関係であり、万物に神が宿るような原始宗教的な感覚がそこに透かし込まれていたのではないでしょうか。
その意味で、今期のうお座もまた自分がいま一体何に馴染みつつあるのか、そしてその対象のどこまで奥深く浸透していこうとしているのか、改めて問うてみるといいかも知れません。
参考:川端康成『雪国』(新潮文庫)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ