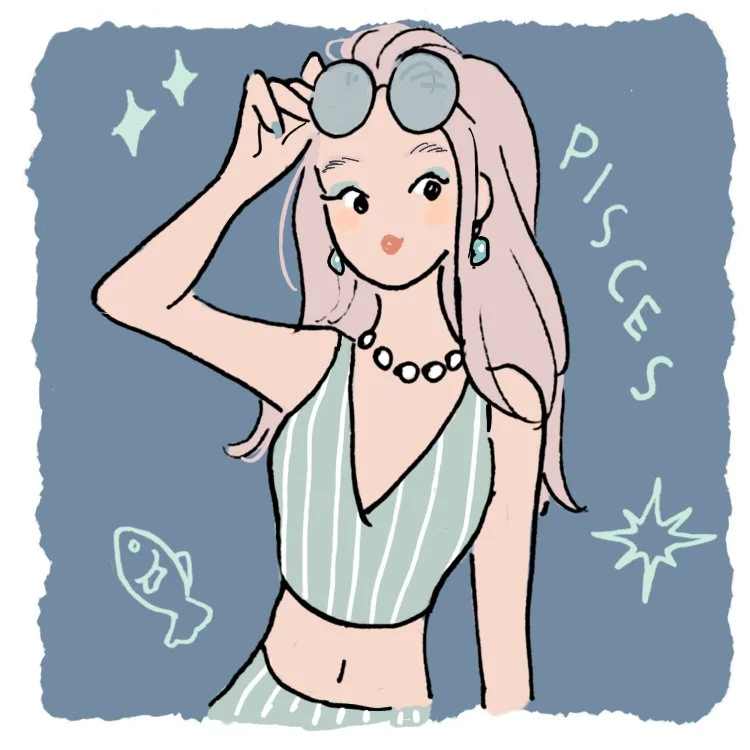【最新12星座占い】<7/25~8/7>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<7/25~8/7>の12星座全体の運勢は?
「死に寄り添う生」
8月7日の「立秋」はまさに真夏の盛りですが、日本の伝統的な季節感では夏がピークに達するときに秋がスタートし、人びとは小さな秋の兆しを探し始めてきたのです。そして、そんな立秋直後の8月8日にしし座の新月を迎えていきます。
今回の新月は土星(体制、課題)と天王星(転覆、改革)と二等辺三角形を形成するため、今年一年を通じて進行していく既存の権威やこれまで機能してきた体制側の自己防衛や無意識の視野狭窄を破壊して再構築プロセスにかなり直結していくものとなるでしょう。
その上であえてそれを端的にテーマ化するなら、「死に寄り添う生の在り方を探る」といったものになるように思います。例えばこれは、これまでのように社会を強固で一枚岩的な現実に統合せんとしてきた近代的な考え方においては、死は完全な敵であり、それに対して断固として立ち向かうか、徹底的に視界から排除されるべきものだった訳ですが、超高齢化が進展するポスト成長時代のこれからは、老いのプロセスの中で、徐々に死を受け入れ、和解し同化していく中で、生と死のゆるやかなグラデーションを取り戻していくことが求められていく、ということともリンクしてくるはず。
ちょうど芭蕉の句に「閑(しづか)さや岩にしみ入る蝉の声」という句がありますが、短い一生ながら懸命に鳴いている蝉とその声はまさに「いのち」の象徴であり、一方で、奥深い山の池のほとりで苔むして黒々としている「岩」とは「死」の象徴とも言えるのではないでしょうか。
そして、蝉の声が岩に「しみ入る」というのは、まさに意識の静寂のさなかで「生と死」が融合し、その連続性を取り戻していく宇宙的とも言える世界観を表現したもの、とも解釈できます。今期の私たちもまた、そんな句のように、死を敵と考えたり、排除するのではなく、どうしたら和解していけるか、また、個人的なものであれ社会的なものであれ、死とは何かをいかに問い直していけるかが問われていくように思います。
今回の新月は土星(体制、課題)と天王星(転覆、改革)と二等辺三角形を形成するため、今年一年を通じて進行していく既存の権威やこれまで機能してきた体制側の自己防衛や無意識の視野狭窄を破壊して再構築プロセスにかなり直結していくものとなるでしょう。
その上であえてそれを端的にテーマ化するなら、「死に寄り添う生の在り方を探る」といったものになるように思います。例えばこれは、これまでのように社会を強固で一枚岩的な現実に統合せんとしてきた近代的な考え方においては、死は完全な敵であり、それに対して断固として立ち向かうか、徹底的に視界から排除されるべきものだった訳ですが、超高齢化が進展するポスト成長時代のこれからは、老いのプロセスの中で、徐々に死を受け入れ、和解し同化していく中で、生と死のゆるやかなグラデーションを取り戻していくことが求められていく、ということともリンクしてくるはず。
ちょうど芭蕉の句に「閑(しづか)さや岩にしみ入る蝉の声」という句がありますが、短い一生ながら懸命に鳴いている蝉とその声はまさに「いのち」の象徴であり、一方で、奥深い山の池のほとりで苔むして黒々としている「岩」とは「死」の象徴とも言えるのではないでしょうか。
そして、蝉の声が岩に「しみ入る」というのは、まさに意識の静寂のさなかで「生と死」が融合し、その連続性を取り戻していく宇宙的とも言える世界観を表現したもの、とも解釈できます。今期の私たちもまた、そんな句のように、死を敵と考えたり、排除するのではなく、どうしたら和解していけるか、また、個人的なものであれ社会的なものであれ、死とは何かをいかに問い直していけるかが問われていくように思います。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「業を見極める旅」。

日常生活の継続が困難になるほどの悩みや苦しみに捕らわれてしまったとき、人は振り切ろうとしてもどうしても振り切れないものが何であるのか、そんな自身の業(ごう)を見極めるため、旅に出てきたのかも知れません。
その意味では、まさに生涯を数多の旅に生きた江戸時代の俳聖・松尾芭蕉の遺稿から旅の記をとりあげ、死後に刊行された『笈の小文』は、その冒頭から混迷の中に光明を見出していくためのドラマが満ちており、読む者に切々と訴えかけてくる独特の迫力があります。
「百骸九竅(ひゃくがいきゅうきょう)の中に物あり。かりに名付て風羅坊(ふうらぼう)といふ。誠にうすものゝかぜに破れやすからん事をいふにやあらむ。かれ狂句を好むこと久し。終に生涯のはかりごとゝなす。」
はじめに出てくる「百骸九竅」とは多くの骨と穴のあいた肉体のことで、「風羅坊」は芭蕉の別号で傷つきやすい心の意、また「かれ」は芭蕉自身のこと、「狂句」とは俳句のことを指しています。すなわち、身の内に一つの抑えがたいものがあって、それがやがて生涯にわたり取り組むこととなったと述べているのですが、この後が凄いのです。
「ある時は倦んで放擲(ほうてき)せん事をおもひ、ある時はすゝむで人にかたん事をほこり、是非胸中にたゝかふて、是が為に身安からず。しばらく身を立む事をねがへども、これが為にさへられ、しばらく学んで愚をさとらん事をおもへども、是が為に破られ、つゐに無能無芸にして只此一筋に繋る。」
芭蕉ははじめから俳諧師を目指していた訳ではなく、「しばらく身を立む事をねがへども」とあるように、侍として出世することを願い、また、仏道に精神の充足を求めたが結局は俳諧が妨げになり、どちらにもなりきれなかったのです。しかも当時の俳諧は、まだ新興のマイナージャンルに過ぎず、少なくとも気骨ある青年が生涯の仕事として志すようなものではありませんでした。けれど、芭蕉はこの旅を通してそんな俳諧を捨てきれないことをやっと自覚し、俳諧に選ばれたのだという結論に達したのです。
ただそれも「無能無芸にして」とあるように、決して過大な自我肥大によるものというより、俳諧という何だかよく分からないものに憑りつかれ、しかも頼みは自分の手だけであるといううめき声とともに、やっとの思いでしぼり出したものでした。
今期のおひつじ座も、芭蕉ほどいのちがけの旅をすることは難しくとも、それくらいギリギリのところで「徒手空拳の戦い」を展開していきたいところです。
参考:中村俊定・校注『芭蕉紀行文集』(岩波文庫)
その意味では、まさに生涯を数多の旅に生きた江戸時代の俳聖・松尾芭蕉の遺稿から旅の記をとりあげ、死後に刊行された『笈の小文』は、その冒頭から混迷の中に光明を見出していくためのドラマが満ちており、読む者に切々と訴えかけてくる独特の迫力があります。
「百骸九竅(ひゃくがいきゅうきょう)の中に物あり。かりに名付て風羅坊(ふうらぼう)といふ。誠にうすものゝかぜに破れやすからん事をいふにやあらむ。かれ狂句を好むこと久し。終に生涯のはかりごとゝなす。」
はじめに出てくる「百骸九竅」とは多くの骨と穴のあいた肉体のことで、「風羅坊」は芭蕉の別号で傷つきやすい心の意、また「かれ」は芭蕉自身のこと、「狂句」とは俳句のことを指しています。すなわち、身の内に一つの抑えがたいものがあって、それがやがて生涯にわたり取り組むこととなったと述べているのですが、この後が凄いのです。
「ある時は倦んで放擲(ほうてき)せん事をおもひ、ある時はすゝむで人にかたん事をほこり、是非胸中にたゝかふて、是が為に身安からず。しばらく身を立む事をねがへども、これが為にさへられ、しばらく学んで愚をさとらん事をおもへども、是が為に破られ、つゐに無能無芸にして只此一筋に繋る。」
芭蕉ははじめから俳諧師を目指していた訳ではなく、「しばらく身を立む事をねがへども」とあるように、侍として出世することを願い、また、仏道に精神の充足を求めたが結局は俳諧が妨げになり、どちらにもなりきれなかったのです。しかも当時の俳諧は、まだ新興のマイナージャンルに過ぎず、少なくとも気骨ある青年が生涯の仕事として志すようなものではありませんでした。けれど、芭蕉はこの旅を通してそんな俳諧を捨てきれないことをやっと自覚し、俳諧に選ばれたのだという結論に達したのです。
ただそれも「無能無芸にして」とあるように、決して過大な自我肥大によるものというより、俳諧という何だかよく分からないものに憑りつかれ、しかも頼みは自分の手だけであるといううめき声とともに、やっとの思いでしぼり出したものでした。
今期のおひつじ座も、芭蕉ほどいのちがけの旅をすることは難しくとも、それくらいギリギリのところで「徒手空拳の戦い」を展開していきたいところです。
参考:中村俊定・校注『芭蕉紀行文集』(岩波文庫)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「悪への加担」。

高度経済成長期などに象徴されるように、国家という枠組みの中で現実が一枚岩的なものへと統合されてきた日本社会では、いつからか社会のあらゆる場所から「死」が排除され、その隠蔽が巧妙化してきましたが、今回のコロナ禍ではそうした社会のベクトルがもはや立ち行かなくなって機能不全に陥っていることを徹底的に露呈させてきました。
そしてそれは挙国一致を謳いながら、繰り出す判断のことごとくがコロナウイルスという自然がもたらすリスクを見誤り続けている日本政府や経済界のリーダーたちの現状を見るにつけ、ある種のピークを迎えつつあるように感じます。
では、ヒューマン(社会)とノンヒューマン(自然)とが激しく接触をしていくようなタイミングで、私たちは自然といかに向かい合っていけばいいのでしょうか。
例えば、それにはどこまでも社会に適応した“いい人”をやめること、より積極的にはある種の“悪い人”になるというものがあります。宗教学者の中沢新一は俳人の小澤實との対談集『俳句の海に潜る』の中で、そのことを次のような言い方で表しています。
「もともと、「悪」には死という意味もあります。要するに人間の外にあるものに触れていますからね。でも悪はパワーが強い。死に接近しているのが悪、自然です。和歌の世界の、作られた世界って、その悪にはあえて接近しないのでは。でも、俳句はむしろ悪に接近した芸術ではないか。今や悪という言葉をもっと豊かにしていかないといけないと思います。「自然」と書いて、「あく(悪)」と読んでも「かみ(神)」と読んでも昔はよかったんですよ。」
そして、自然と向き合いそれを俳句という文芸に昇華していく俳人には、松尾芭蕉や飯田蛇笏など、どこか非人間的なところが感じられる一群の人たちがいるのだというやり取りが為されるのですが、中沢によれば、「悪」というのは、本来むき出しの自然、ぜんぜん人間の力ではどうにもならない恐るべきパワーの世界に接近して、そこに踏み込んでいく行為のことを言うのだそうです。
中沢「悪は同時に「美」ですから。悪はさっき言ったみたいにデス(死)、ネイチャー(自然)をビューティ(美)に昇華していく行為です。(中略)小澤さんの目指しているのもそうなのでしょう。」
小澤「ええ。それができたらと思います。」
中沢「美を目指すとはいえ、目の前で接触しているものって収まりつかないものばっかりでしょう。」
同様に、今期のおうし座もまた、そうした意味での「悪人」や「悪女」、「悪太郎」になっていくことがテーマになっているのではないでしょうか。今こそ、自分のなかのタガを外していく時です。
参考:中沢新一、小澤實『俳句の海に潜る』(角川書店)
そしてそれは挙国一致を謳いながら、繰り出す判断のことごとくがコロナウイルスという自然がもたらすリスクを見誤り続けている日本政府や経済界のリーダーたちの現状を見るにつけ、ある種のピークを迎えつつあるように感じます。
では、ヒューマン(社会)とノンヒューマン(自然)とが激しく接触をしていくようなタイミングで、私たちは自然といかに向かい合っていけばいいのでしょうか。
例えば、それにはどこまでも社会に適応した“いい人”をやめること、より積極的にはある種の“悪い人”になるというものがあります。宗教学者の中沢新一は俳人の小澤實との対談集『俳句の海に潜る』の中で、そのことを次のような言い方で表しています。
「もともと、「悪」には死という意味もあります。要するに人間の外にあるものに触れていますからね。でも悪はパワーが強い。死に接近しているのが悪、自然です。和歌の世界の、作られた世界って、その悪にはあえて接近しないのでは。でも、俳句はむしろ悪に接近した芸術ではないか。今や悪という言葉をもっと豊かにしていかないといけないと思います。「自然」と書いて、「あく(悪)」と読んでも「かみ(神)」と読んでも昔はよかったんですよ。」
そして、自然と向き合いそれを俳句という文芸に昇華していく俳人には、松尾芭蕉や飯田蛇笏など、どこか非人間的なところが感じられる一群の人たちがいるのだというやり取りが為されるのですが、中沢によれば、「悪」というのは、本来むき出しの自然、ぜんぜん人間の力ではどうにもならない恐るべきパワーの世界に接近して、そこに踏み込んでいく行為のことを言うのだそうです。
中沢「悪は同時に「美」ですから。悪はさっき言ったみたいにデス(死)、ネイチャー(自然)をビューティ(美)に昇華していく行為です。(中略)小澤さんの目指しているのもそうなのでしょう。」
小澤「ええ。それができたらと思います。」
中沢「美を目指すとはいえ、目の前で接触しているものって収まりつかないものばっかりでしょう。」
同様に、今期のおうし座もまた、そうした意味での「悪人」や「悪女」、「悪太郎」になっていくことがテーマになっているのではないでしょうか。今こそ、自分のなかのタガを外していく時です。
参考:中沢新一、小澤實『俳句の海に潜る』(角川書店)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「地理的な位置づけの見直し」。

東アジアの果てに弧状に連なる日本列島は大陸から断絶した、大小の島の集合体、すなわち群島(アーキペラゴ)であり、そこへ大海を渡って、島を渡り継いで流れ着いたはるかな先祖たちの記憶は、水底に蓄えられた泥が浮き沈みを繰り返すように、私たちの内部における死者が浮上したまさに瞬間ごとに、連綿と歴史に受けとられてきたはず。
したがって、今その歴史的な変節を迎えつつあるこの極東の島宇宙では、どこか懐かしくも恐ろしい海鳴りにも似た、薄暗く、宿命的な先祖の声や叫びがこだましているのではないでしょうか。
文化人類学者の今福龍太は2008年に刊行した『群島―世界論』において、そうした群島を徘徊する死の影について、次のように描写しています。
「群島は死者の絆である。群島を繋ぎ、群島の想像力を喚起するのは生者ではなくてむしろ死者のほうである。現世において死者を追悼し、死者に祈り、死者を祀ろうとするいかなる行為も、純粋に生者の領土での行為、生者の精神運動にほかならない。死者が語り出す畏怖に満ちた声を封鎖し、死者の現前を未然に防ごうとする生者の意識の規制こそが、死者の追悼と顕彰と呼ばれる行為の内実なのである。だがそうした生者による抑圧の網目をかいくぐって、死者はいまという時間にたえざる顕現を繰り返している。」
群島(アーキペラゴ)では陸地という陸地に必ず海の声やその気配が漂うものですが、海の声というのは決してひとつの声ということはなく、溺れた人たちの声だったり、数多くの死者や亡霊のうめき声が入り混じった多声音楽(ポリフョニー)であり、したがって群島とはその本質から多言語的な反響世界、あらゆる言葉が響きあう混沌世界なのだと言えます。
「生者のただ中で、死者は語り出す。とすれば、まさにこれら死者の語り出しの瞬間を繊細にとらえ、そこに固有の時と場を与え、国家や民族の空間に封鎖された死者の位置や意味を、海と河を繋ぐようなヴィジョンのもとに世界大に結びあわせる新しい群島の想像力を、私たちはいま必要としている」
「群島は死者の声の浮上を待ちつづける、意識のフロンティアである。大陸の論理の派生として島を眼差すのではなく、島影の背後から、ハリケーンの押し流す泥の深みから、死者の顕現を感じつつ、彼方の陸地に対峙してゆくこと……。そのような新たな流儀によって、近代世界をすみずみまで構築した大陸の原理が、そのおおもとにたちかえりながら、裏返されてゆくであろう。」
今まさにこの極東において、大陸の原理の賜物たる一大行事がその限界を露呈しつつある中、今期のふたご座もまた、群島的な流儀にしたがって裏返っていこうとしているのかも知れません。
参考:今福龍太『群島―世界論』(岩波書店)
したがって、今その歴史的な変節を迎えつつあるこの極東の島宇宙では、どこか懐かしくも恐ろしい海鳴りにも似た、薄暗く、宿命的な先祖の声や叫びがこだましているのではないでしょうか。
文化人類学者の今福龍太は2008年に刊行した『群島―世界論』において、そうした群島を徘徊する死の影について、次のように描写しています。
「群島は死者の絆である。群島を繋ぎ、群島の想像力を喚起するのは生者ではなくてむしろ死者のほうである。現世において死者を追悼し、死者に祈り、死者を祀ろうとするいかなる行為も、純粋に生者の領土での行為、生者の精神運動にほかならない。死者が語り出す畏怖に満ちた声を封鎖し、死者の現前を未然に防ごうとする生者の意識の規制こそが、死者の追悼と顕彰と呼ばれる行為の内実なのである。だがそうした生者による抑圧の網目をかいくぐって、死者はいまという時間にたえざる顕現を繰り返している。」
群島(アーキペラゴ)では陸地という陸地に必ず海の声やその気配が漂うものですが、海の声というのは決してひとつの声ということはなく、溺れた人たちの声だったり、数多くの死者や亡霊のうめき声が入り混じった多声音楽(ポリフョニー)であり、したがって群島とはその本質から多言語的な反響世界、あらゆる言葉が響きあう混沌世界なのだと言えます。
「生者のただ中で、死者は語り出す。とすれば、まさにこれら死者の語り出しの瞬間を繊細にとらえ、そこに固有の時と場を与え、国家や民族の空間に封鎖された死者の位置や意味を、海と河を繋ぐようなヴィジョンのもとに世界大に結びあわせる新しい群島の想像力を、私たちはいま必要としている」
「群島は死者の声の浮上を待ちつづける、意識のフロンティアである。大陸の論理の派生として島を眼差すのではなく、島影の背後から、ハリケーンの押し流す泥の深みから、死者の顕現を感じつつ、彼方の陸地に対峙してゆくこと……。そのような新たな流儀によって、近代世界をすみずみまで構築した大陸の原理が、そのおおもとにたちかえりながら、裏返されてゆくであろう。」
今まさにこの極東において、大陸の原理の賜物たる一大行事がその限界を露呈しつつある中、今期のふたご座もまた、群島的な流儀にしたがって裏返っていこうとしているのかも知れません。
参考:今福龍太『群島―世界論』(岩波書店)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「自己という行為」。

ワクチンの接種が日本でもようやく進みはじめたいま、改めて読んでおきたい一冊に免疫学者・多田富雄の『免疫の意味論』があります。
免疫系は非自己と見なされたものを自己から排除するシステムですが、それが決して厳密には機能しておらず、自己と非自己の線引きは私たちが思っている以上に曖昧なものであり、本書は人間の中に住みついたウイルスや細菌のすべてをひっくるめたものが自己であること、しかし自己は固定した存在ではなく「自己という行為」そのものがその本質なのだということを明らかにしてくれました。
興味深いのは、免疫系の働きにおいては、「「自己」の全体性からはみ出した細胞を積極的に「自殺」させるという営みが行われている」のだということ。そうして死を古代ギリシャにおいては秋の落葉現象を指していた「アポトーシス」という、死ぬために組みこまれたプログラムが作動した結果だと捉えていくとき、そこでは死は従来考えられてきたような受動的かつ偶然的なものではなく、積極的かつ必然的なもの、少なくとも高度に調整された生命現象なのだという発想の転換が促されてくるはずです。
「死を実行するためには、まず死を決定する遺伝子が働き、死を執り行うタンパク質の新たな合成が行われなければならない。細胞は、自らの設計図であるDNAを切断して死んでゆく。それによって逆に、脳神経系や免疫系などの高度の生命システム、私が超システムと呼ぶものが保証されていたのであった。」
多田は科学的知見に基づきつつ、「生命はもともと死すべきものとして生まれてきた」のだということをひとつひとつ確認していくことで、古く硬直したものになりつつある従来の生命観そのものを書き換えようとしたのでしょう。
「私がこの本で試みようとしているのは、個体の生命現象を眺めながら、より高次の生命活動としての文明、都市や言語、経済活動をも「超システム」として考えてみることである。文明というものが、人間という個体によって成立する生命活動だとすれば、個体の死もまた、より高次の超システムの成立のために、もともとプログラムされているのかも知れない。「超システム」の中での死の位置づけは、さまざまな文化現象の成立と崩壊を考える鍵となると思われる。」
ひとつの文明ないし文化の産物が崩壊を迎えつつある今、かに座のあなたもまた、自身の生き様をそうした大いなる「超システム」の枠組みの中で捉え直し、いったいどうすることが「「自己」という行為」なのかを考え、実行していく必要に迫られているのだと言えるのではないでしょうか。
参考:多田富雄『免疫の意味論』(新潮社)
免疫系は非自己と見なされたものを自己から排除するシステムですが、それが決して厳密には機能しておらず、自己と非自己の線引きは私たちが思っている以上に曖昧なものであり、本書は人間の中に住みついたウイルスや細菌のすべてをひっくるめたものが自己であること、しかし自己は固定した存在ではなく「自己という行為」そのものがその本質なのだということを明らかにしてくれました。
興味深いのは、免疫系の働きにおいては、「「自己」の全体性からはみ出した細胞を積極的に「自殺」させるという営みが行われている」のだということ。そうして死を古代ギリシャにおいては秋の落葉現象を指していた「アポトーシス」という、死ぬために組みこまれたプログラムが作動した結果だと捉えていくとき、そこでは死は従来考えられてきたような受動的かつ偶然的なものではなく、積極的かつ必然的なもの、少なくとも高度に調整された生命現象なのだという発想の転換が促されてくるはずです。
「死を実行するためには、まず死を決定する遺伝子が働き、死を執り行うタンパク質の新たな合成が行われなければならない。細胞は、自らの設計図であるDNAを切断して死んでゆく。それによって逆に、脳神経系や免疫系などの高度の生命システム、私が超システムと呼ぶものが保証されていたのであった。」
多田は科学的知見に基づきつつ、「生命はもともと死すべきものとして生まれてきた」のだということをひとつひとつ確認していくことで、古く硬直したものになりつつある従来の生命観そのものを書き換えようとしたのでしょう。
「私がこの本で試みようとしているのは、個体の生命現象を眺めながら、より高次の生命活動としての文明、都市や言語、経済活動をも「超システム」として考えてみることである。文明というものが、人間という個体によって成立する生命活動だとすれば、個体の死もまた、より高次の超システムの成立のために、もともとプログラムされているのかも知れない。「超システム」の中での死の位置づけは、さまざまな文化現象の成立と崩壊を考える鍵となると思われる。」
ひとつの文明ないし文化の産物が崩壊を迎えつつある今、かに座のあなたもまた、自身の生き様をそうした大いなる「超システム」の枠組みの中で捉え直し、いったいどうすることが「「自己」という行為」なのかを考え、実行していく必要に迫られているのだと言えるのではないでしょうか。
参考:多田富雄『免疫の意味論』(新潮社)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「無、あるいは操作の取り消しの感覚」。

今の日本社会は、この世の物事はある種の決定論的なシステムのなかで秩序づけられているとするニュートン的な思考のままどこまでも突き進み続けているようなところがありますが、そもそもノーベル賞の受賞にもつながったような過去50年間の日本の理論物理学の目覚ましい業績の背景には、そうしたニュートン的な思考とは対極的な思考があったように思います。
気鋭の哲学者マルクス・ガブリエルと中国哲学を専門とする中島隆博による2020年に行われた対談を書籍にした『全体主義の克服』では、たとえば量子力学やひも理論の根底にあるような東洋的な発想について、中島が次のように喩えています。
「「穴」や「窓」や「器」といった外に開かれたものが出てくる底がある。つまり、物の背景自体は物ではない。このことに気付くと、物と思われるものも物ではない、つまり「無」であることがわかる。」
そして、これがニュートンやカントのように、現実=実在というものを何らかの自然法則に支配されたたくさんの点のようにして確かに存在するものの集合だと考えると、「無」というものが物のもっている安定性を得てしまう訳ですが、これは誤解なのだということを、3世紀の中国の哲学者である王弼(おうひつ)を引いてさらにこう言及してみせるのです。
「たとえば『老子』第六章に「谷神(こくしん)は死なず。これを玄牝(げんぴん)」という一節があります。それに対して王弼は「谷神は、谷の中央にあり無谷である。それは影も形もなく、逆らうことも相違することもなく、低い位置にあって動かず、静かさを守って衰えない」と注釈をつけています。(中略)ここで王弼が考えているのは、特定の谷に物が存在すると考えてはいけないということです。あえて言うならば、これは根底的で現代的な哲学です。」
ここで言う「無」とは、物と無とを分ける二元論ではなくて、物以前に働くものであり、中島はそれを王弼にならって「一種の取り消された働き」とか「何らかの操作の取り消し」と呼んでいますが、それこそまさに今の日本政府に必要な発想でしょう。
つまり、無の中にきちんと根を下ろしているから、物事の終わらせ方が感覚的に分からなくなってしまったのではないか、と。
そして同様に、今期のしし座もまた、やはりどうしたら近代合理主義やそれを基礎づけているニュートン・カント的パラダイムを超えたところにある発想を取り入れられるかが、ひとつの鍵になってくるのではないでしょうか。
参考:マルクス・ガブリエル、中島隆博『全体主義の克服』(集英社新書)
気鋭の哲学者マルクス・ガブリエルと中国哲学を専門とする中島隆博による2020年に行われた対談を書籍にした『全体主義の克服』では、たとえば量子力学やひも理論の根底にあるような東洋的な発想について、中島が次のように喩えています。
「「穴」や「窓」や「器」といった外に開かれたものが出てくる底がある。つまり、物の背景自体は物ではない。このことに気付くと、物と思われるものも物ではない、つまり「無」であることがわかる。」
そして、これがニュートンやカントのように、現実=実在というものを何らかの自然法則に支配されたたくさんの点のようにして確かに存在するものの集合だと考えると、「無」というものが物のもっている安定性を得てしまう訳ですが、これは誤解なのだということを、3世紀の中国の哲学者である王弼(おうひつ)を引いてさらにこう言及してみせるのです。
「たとえば『老子』第六章に「谷神(こくしん)は死なず。これを玄牝(げんぴん)」という一節があります。それに対して王弼は「谷神は、谷の中央にあり無谷である。それは影も形もなく、逆らうことも相違することもなく、低い位置にあって動かず、静かさを守って衰えない」と注釈をつけています。(中略)ここで王弼が考えているのは、特定の谷に物が存在すると考えてはいけないということです。あえて言うならば、これは根底的で現代的な哲学です。」
ここで言う「無」とは、物と無とを分ける二元論ではなくて、物以前に働くものであり、中島はそれを王弼にならって「一種の取り消された働き」とか「何らかの操作の取り消し」と呼んでいますが、それこそまさに今の日本政府に必要な発想でしょう。
つまり、無の中にきちんと根を下ろしているから、物事の終わらせ方が感覚的に分からなくなってしまったのではないか、と。
そして同様に、今期のしし座もまた、やはりどうしたら近代合理主義やそれを基礎づけているニュートン・カント的パラダイムを超えたところにある発想を取り入れられるかが、ひとつの鍵になってくるのではないでしょうか。
参考:マルクス・ガブリエル、中島隆博『全体主義の克服』(集英社新書)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「愛し得ないがゆえに、日輪と共に始めよ」。

心理学やカウンセリング、またそれらを汲んだ占いがいかにクライアントや世間に自己実現を促そうとも、人間はしょせん「断片的な存在」であることから免れえず、それゆえに、私たちができることは自身を含め、周囲の人間に対して「実に嫉妬深い、恨みがましい、妄執の鬼と化するに終る」ことだけなのだ。と、そう説いたのは、近代文明が人間生活にもたらす悪影響を一貫して主題として扱ってきたD・H・ロレンスであり、彼の最晩年の畢生の論考である『黙示録論』(1929)でした。
とは言え、現代人はいくら「断片的」であるとそしられようとも、もはや個人主義を手放そうとはしないでしょう。その一方で、いつの時代も人間は他者や何らかの共同体との結びつきを求め、その成果として近代文明を築くにいたった訳ですが、ロレンスはそうした近代社会的な精神の在り様を厳しく批判しています。
「キリスト教と私たちの理想とする文明とは、長く続く逃避の一形態だった。こうした宗教と文明が際限なき虚偽と貧困を、物質の欠乏ではなくそれよりずっと危険な生命力の欠乏、すなわち今日わたしたちが経験している貧困を生んできた。生命を欠くよりパンを欠くほうがましだ。長く逃避を続け、そうして得られた唯一の成果が機械とは!」
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。その点については、ロレンスの『黙示録論』を翻訳し、自分に思想と呼べるものがあるとするならそれは本書によって形成されたとさえ述べた福田恆在(ふくだつねあり)は、「ロレンスの黙示録論について」というエッセイの中で、次のように述べています。
「ぼくたちは―純粋なる個人というものがありえぬ以上、たんなる断片にすぎぬ集団的自我というものは―直接たがいにたがいを愛しえない。なぜなら愛はそのまえに自律性を前提とする。が、断片に自律性はない。ぼくたちは愛するためにはなんらかの方法によって自律性を獲得せねばならぬ。近代は個人それ自体のうちにそれを求め、そして失敗した。自律性はうちに求めるべきではない。個人の外部に―宇宙の有機性そのもののうちに求められなければならぬ。」
今まさに日本社会全体が有機的な統合をなさずちりぢりの断片であることを露呈しているなか、今期のおとめ座もまた、ロレンスが訴えたように、個人主義とともに人間の勝手を捨てて、コスモスの一部としてあるべく「まず日輪と共に始めよ」という言葉に従ってみるといいでしょう。
参考:D・H・ロレンス、福田恆在訳『黙示録論 現代人は愛しうるか』(ちくま学芸文庫)
とは言え、現代人はいくら「断片的」であるとそしられようとも、もはや個人主義を手放そうとはしないでしょう。その一方で、いつの時代も人間は他者や何らかの共同体との結びつきを求め、その成果として近代文明を築くにいたった訳ですが、ロレンスはそうした近代社会的な精神の在り様を厳しく批判しています。
「キリスト教と私たちの理想とする文明とは、長く続く逃避の一形態だった。こうした宗教と文明が際限なき虚偽と貧困を、物質の欠乏ではなくそれよりずっと危険な生命力の欠乏、すなわち今日わたしたちが経験している貧困を生んできた。生命を欠くよりパンを欠くほうがましだ。長く逃避を続け、そうして得られた唯一の成果が機械とは!」
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。その点については、ロレンスの『黙示録論』を翻訳し、自分に思想と呼べるものがあるとするならそれは本書によって形成されたとさえ述べた福田恆在(ふくだつねあり)は、「ロレンスの黙示録論について」というエッセイの中で、次のように述べています。
「ぼくたちは―純粋なる個人というものがありえぬ以上、たんなる断片にすぎぬ集団的自我というものは―直接たがいにたがいを愛しえない。なぜなら愛はそのまえに自律性を前提とする。が、断片に自律性はない。ぼくたちは愛するためにはなんらかの方法によって自律性を獲得せねばならぬ。近代は個人それ自体のうちにそれを求め、そして失敗した。自律性はうちに求めるべきではない。個人の外部に―宇宙の有機性そのもののうちに求められなければならぬ。」
今まさに日本社会全体が有機的な統合をなさずちりぢりの断片であることを露呈しているなか、今期のおとめ座もまた、ロレンスが訴えたように、個人主義とともに人間の勝手を捨てて、コスモスの一部としてあるべく「まず日輪と共に始めよ」という言葉に従ってみるといいでしょう。
参考:D・H・ロレンス、福田恆在訳『黙示録論 現代人は愛しうるか』(ちくま学芸文庫)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「くらがえすること」。
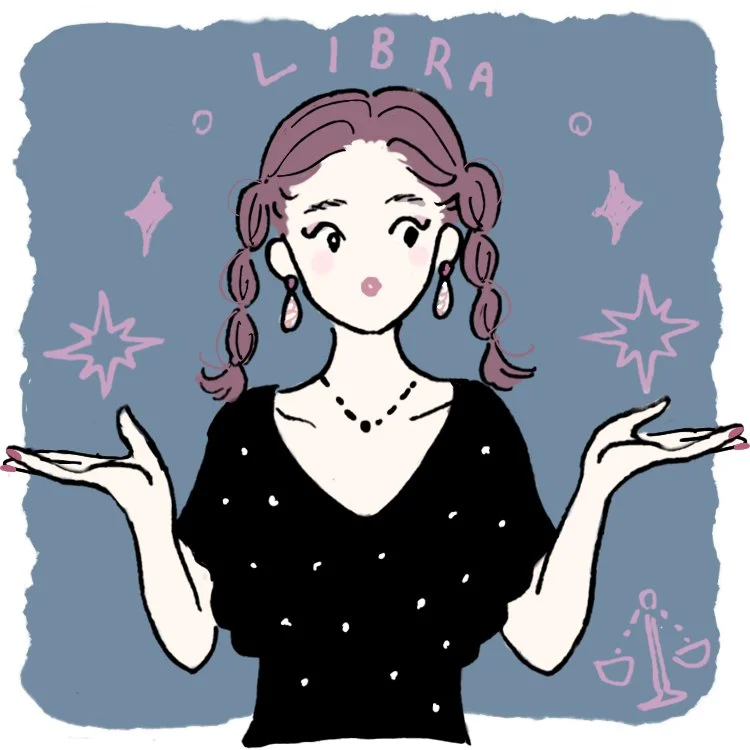
今回の新型コロナウイルスによる死者も、経済活動の停滞による生活困窮者も、言ってみればグローバル資本主義と、感染症被害が拡大するはるか以前から実施されてきた経済的ジェノサイドのごとき政策の犠牲者に他ならない訳ですが、この国の権力サイドの人びとは、いまだに民衆を騙しおおせる自信を少しも失っていないように見えます。
こうした状況の中で思い出される人物に深沢七郎がいます。東京オリンピックより前の1950年代終わりに発表された『楢山節考』以来、深沢の文学作品は日本の大衆文化の規格や制度的な枠に呑み込まれることなく、「日本国」というリアリティを平然と越えていった数少ない日本語文学の一つでしたが、そうなりえた要因のひとつは、恐らく深沢が“お上”を信じるという体質をまったく持ち合わせていなかったからではないでしょうか。
深沢は商人の家に生まれたこともあって、中学を卒業するとデッチ奉公に出されたそうですが、いとこの影響もあって、何回も奉公先をくらがえしたのだそうです。その上で、彼のエッセイ「生態を変える記」では次のように述べられています。
「デッチ奉公をした者にはよく判ることだが、その国に住んでいることは「こうしてはいけない、ゼニの稼ぎは出せ、きめられたとおりにことをしろ」と主人に言われるのと同じだと思っている。ゼニを出せということは税金のことで、これも稼ぎのうわ前をはねられることなのである。言うことをきけというのはデモで反対したことも従わなければならないことで、こうしてはいけないというのは官僚や政治家の都合のいいようにきめられることである。
つまり、旦那が奉公人に勝手な我儘を言っているのと同じである。それだから、その国に住んでいることはその国に奉公しているデッチと同じだ、と私は思っているのである。
奉公人はその家が厭になれば奉公先をかえる。つまり、くらがえするのである。
ほんとに簡単なこの法則をなぜみんな実行しようとしないのだろうか。」
もし深沢が生きていたら、今回の東京オリンピックについて何と言及したでしょうか。おそらく、何でもないような顔をして、さっとどこか田舎へ引っ越して畑仕事でも始めたかもしれない。そして、私たちに向かってこう言うのです。
「バカだな、おなじところにばかりいるなんて」
今期のてんびん座もまた、お上の滑稽な妄想や我儘に付き合う代わりに、ひょいと自分なりの「くらがえ」にいそしんでみるといいかも知れません。
参考:『深沢七郎コレクション 転』(ちくま文庫)
こうした状況の中で思い出される人物に深沢七郎がいます。東京オリンピックより前の1950年代終わりに発表された『楢山節考』以来、深沢の文学作品は日本の大衆文化の規格や制度的な枠に呑み込まれることなく、「日本国」というリアリティを平然と越えていった数少ない日本語文学の一つでしたが、そうなりえた要因のひとつは、恐らく深沢が“お上”を信じるという体質をまったく持ち合わせていなかったからではないでしょうか。
深沢は商人の家に生まれたこともあって、中学を卒業するとデッチ奉公に出されたそうですが、いとこの影響もあって、何回も奉公先をくらがえしたのだそうです。その上で、彼のエッセイ「生態を変える記」では次のように述べられています。
「デッチ奉公をした者にはよく判ることだが、その国に住んでいることは「こうしてはいけない、ゼニの稼ぎは出せ、きめられたとおりにことをしろ」と主人に言われるのと同じだと思っている。ゼニを出せということは税金のことで、これも稼ぎのうわ前をはねられることなのである。言うことをきけというのはデモで反対したことも従わなければならないことで、こうしてはいけないというのは官僚や政治家の都合のいいようにきめられることである。
つまり、旦那が奉公人に勝手な我儘を言っているのと同じである。それだから、その国に住んでいることはその国に奉公しているデッチと同じだ、と私は思っているのである。
奉公人はその家が厭になれば奉公先をかえる。つまり、くらがえするのである。
ほんとに簡単なこの法則をなぜみんな実行しようとしないのだろうか。」
もし深沢が生きていたら、今回の東京オリンピックについて何と言及したでしょうか。おそらく、何でもないような顔をして、さっとどこか田舎へ引っ越して畑仕事でも始めたかもしれない。そして、私たちに向かってこう言うのです。
「バカだな、おなじところにばかりいるなんて」
今期のてんびん座もまた、お上の滑稽な妄想や我儘に付き合う代わりに、ひょいと自分なりの「くらがえ」にいそしんでみるといいかも知れません。
参考:『深沢七郎コレクション 転』(ちくま文庫)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「「生」を生き抜くこと」。

茶番だとわかっていてもそれに付き合わなければならない、あるいは、「もうどうしようもないのだ」という既視感のある無能感を、いま多くの人が改めて感じているはずですが、ここで思い出されるのが、漫画家の山岸涼子の『朱雀門』という作品です。
中学生の女の子である千夏と、その叔母でフリーデザインの仕事をしている三十代前半の独身女性の春秋子(すずこ)さんという二人を軸に展開されるこのお話は、春秋子さんが千夏の部屋で彼女がたまたま読んでいた芥川龍之介の『六の宮の姫君』を見つけるところでグッと核心に入ります。
『六の宮の姫君』についても、簡単に説明しておくと、ある平安時代の姫君が、親に死なれ頼れる人もおらず、途方に暮れている。世話をしてくれた男も、任を授かって京から遠く離れた地へ行くために去ってしまう。姫君はおいおい泣くばかりの日々で、結局、姫君は屋敷も失い、朱雀門の下で成仏することなく息を引き取る。その後、ほどなくして門のほとりでは、女の悲壮な泣き声が聞こえるようになる。法師は言う、あの泣き声は「極楽も地獄も知らぬふがいない女の魂でござる」と。
千夏は「これじゃあんまり姫君がかわいそうじゃない!?」とこの結末に疑問を持ちますが、叔母はむしろそこが芥川のすごいところなのだと告げ、「生」を生きない者は、「死」をも死ねない…と彼は言いたいのよ」と返すのです。
時代的に仕方なかったところはあるかも知れませんが、確かに春秋子さんの言う通り、六の宮の姫君はただの一度も生活苦を改善しようとも、男を追いかけたり愛そうともせず、すなわち自分の運命を自分でどうこうしようと努力しませんでした。ただ襲ってくる運命を甘んじて受けるだけだったのです。
「この何も知らない、見ない、ただ待つだけ、耐えるだけなんて、そういった人間は自分の「生」を満足に生きていないのと同じよ。たとえこの時代のお姫さまだとてね」
「生とはね、生きて生き抜いてはじめて「死」という形で完成するんですって」
「つまりは生きるという実感がなければ、死ぬという実感がなくてあたりまえなのよ。六の宮の姫君は自分が死んだという実感もまたわからないまま死んだんだと思うわ。結局死をうけいれられなかったのよね」
春秋子の指摘を踏まえて読むと、この六の宮の姫君はどこか今の大多数の日本国民の姿と重なりはしないでしょうか。すくなくとも今期のさそり座は、ただ座して運命を甘受するのでなく、どうしたらみずからの「生」を生きて生き抜くことができるのか、考えていきたいところです。
参考:山岸涼子『二日月』(潮出版社)
中学生の女の子である千夏と、その叔母でフリーデザインの仕事をしている三十代前半の独身女性の春秋子(すずこ)さんという二人を軸に展開されるこのお話は、春秋子さんが千夏の部屋で彼女がたまたま読んでいた芥川龍之介の『六の宮の姫君』を見つけるところでグッと核心に入ります。
『六の宮の姫君』についても、簡単に説明しておくと、ある平安時代の姫君が、親に死なれ頼れる人もおらず、途方に暮れている。世話をしてくれた男も、任を授かって京から遠く離れた地へ行くために去ってしまう。姫君はおいおい泣くばかりの日々で、結局、姫君は屋敷も失い、朱雀門の下で成仏することなく息を引き取る。その後、ほどなくして門のほとりでは、女の悲壮な泣き声が聞こえるようになる。法師は言う、あの泣き声は「極楽も地獄も知らぬふがいない女の魂でござる」と。
千夏は「これじゃあんまり姫君がかわいそうじゃない!?」とこの結末に疑問を持ちますが、叔母はむしろそこが芥川のすごいところなのだと告げ、「生」を生きない者は、「死」をも死ねない…と彼は言いたいのよ」と返すのです。
時代的に仕方なかったところはあるかも知れませんが、確かに春秋子さんの言う通り、六の宮の姫君はただの一度も生活苦を改善しようとも、男を追いかけたり愛そうともせず、すなわち自分の運命を自分でどうこうしようと努力しませんでした。ただ襲ってくる運命を甘んじて受けるだけだったのです。
「この何も知らない、見ない、ただ待つだけ、耐えるだけなんて、そういった人間は自分の「生」を満足に生きていないのと同じよ。たとえこの時代のお姫さまだとてね」
「生とはね、生きて生き抜いてはじめて「死」という形で完成するんですって」
「つまりは生きるという実感がなければ、死ぬという実感がなくてあたりまえなのよ。六の宮の姫君は自分が死んだという実感もまたわからないまま死んだんだと思うわ。結局死をうけいれられなかったのよね」
春秋子の指摘を踏まえて読むと、この六の宮の姫君はどこか今の大多数の日本国民の姿と重なりはしないでしょうか。すくなくとも今期のさそり座は、ただ座して運命を甘受するのでなく、どうしたらみずからの「生」を生きて生き抜くことができるのか、考えていきたいところです。
参考:山岸涼子『二日月』(潮出版社)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「実存協同の鎖」。

自然なものであれ人の手で招いたものであれ大きな災禍は多数の非業の死者をうみ、生き残った者も深い負い目に苦しむことになります。日本はそれを第二次世界大戦の際に経験しましたが、哲学の立場からそれを正面から扱ったのは、ただひとり田辺元だけだったのではないでしょうか。
彼は最晩年にあたる1950年代に最後の力をふりしぼってエッセイ「メメント・モリ」を発表しましたが、そこには次のような一節があります。
「自己は死んでも、互に愛によって結ばれた実存は、他において回施のためにはたらくそのはたらきにより、自己の生死を超ゆる実存協同において復活し、永遠に参ずることが、外ならぬその回施を受けた実存によって信証せられるのである。死復活というのは死者その人に直接起る客観的事件ではなく、愛に依って結ばれその死者によってはたらかれることを、自己において信証するところの生者に対して、間接的に自覚せられる交互媒介事態たるのである。(中略)個々の実存は死にながら復活して、永遠の絶対無即愛に摂取せられると同時に、その媒介となって自らそれに参加協同する。」
ここで田辺は死者との「実存協同」ということを説いていますが、これは禅籍の『碧巌録』に出る師弟の話に基づいています。
修行僧の漸源(ぜんげん)は、生死の問題に迷い、師の道吾(どうご)に問うたが、「生ともいわじ、死ともいわじ」という答えを得て、理解できませんでした。しかし師の没後、兄弟子の石霜(せきそう)の指導で悟り、その時、漸源は師がみずからのうちに生きてはたらいていることを自覚し、懺悔感謝したのだ、といいます。
しかしこのことは、禅の修行者に限らず、ぼくたちの日常においてごく普通に起こっていることなのではないでしょうか。田辺の場合は妻をうしない、死んだ妻が自分のうちに生きていると実感したことが大きかったようですが、それだけでなく、ビキニ環礁でのアメリカの核実験によって第五福竜丸が被爆し、核の脅威による死という事態に人類が直面したことを受けてもいたのでしょう。
大乗仏教の菩薩は、道吾のように、死後もなお生者のこころに復活して、弟子の漸源にそうしたように、衆生済度(しゅじょうさいど)の愛に生き続ける、すなわち、みずから菩薩として次に来る人を導くとされますが、「実存協同」の鎖というのは、そうしてはじめて「自己の生死を超」えていくことができるのかも知れません。
今期のいて座もまた、みずからがどんな「実存協同」の鎖のなかにいるのかという視点から、改めてそのまなざしを開いていきたいところです。
参考:藤田正勝編『田辺元哲学選Ⅳ 死の哲学』(岩波文庫)
彼は最晩年にあたる1950年代に最後の力をふりしぼってエッセイ「メメント・モリ」を発表しましたが、そこには次のような一節があります。
「自己は死んでも、互に愛によって結ばれた実存は、他において回施のためにはたらくそのはたらきにより、自己の生死を超ゆる実存協同において復活し、永遠に参ずることが、外ならぬその回施を受けた実存によって信証せられるのである。死復活というのは死者その人に直接起る客観的事件ではなく、愛に依って結ばれその死者によってはたらかれることを、自己において信証するところの生者に対して、間接的に自覚せられる交互媒介事態たるのである。(中略)個々の実存は死にながら復活して、永遠の絶対無即愛に摂取せられると同時に、その媒介となって自らそれに参加協同する。」
ここで田辺は死者との「実存協同」ということを説いていますが、これは禅籍の『碧巌録』に出る師弟の話に基づいています。
修行僧の漸源(ぜんげん)は、生死の問題に迷い、師の道吾(どうご)に問うたが、「生ともいわじ、死ともいわじ」という答えを得て、理解できませんでした。しかし師の没後、兄弟子の石霜(せきそう)の指導で悟り、その時、漸源は師がみずからのうちに生きてはたらいていることを自覚し、懺悔感謝したのだ、といいます。
しかしこのことは、禅の修行者に限らず、ぼくたちの日常においてごく普通に起こっていることなのではないでしょうか。田辺の場合は妻をうしない、死んだ妻が自分のうちに生きていると実感したことが大きかったようですが、それだけでなく、ビキニ環礁でのアメリカの核実験によって第五福竜丸が被爆し、核の脅威による死という事態に人類が直面したことを受けてもいたのでしょう。
大乗仏教の菩薩は、道吾のように、死後もなお生者のこころに復活して、弟子の漸源にそうしたように、衆生済度(しゅじょうさいど)の愛に生き続ける、すなわち、みずから菩薩として次に来る人を導くとされますが、「実存協同」の鎖というのは、そうしてはじめて「自己の生死を超」えていくことができるのかも知れません。
今期のいて座もまた、みずからがどんな「実存協同」の鎖のなかにいるのかという視点から、改めてそのまなざしを開いていきたいところです。
参考:藤田正勝編『田辺元哲学選Ⅳ 死の哲学』(岩波文庫)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「弱さゆえにこそ」。

日本人の平均寿命も80年を超えた現代では、「限られた時間の中でどれくらい強く生を燃焼させるか」という問いの立て方はもはや時代遅れなのかもしれません。
とは言え、現在のコロナ禍において自分たちの生き死にに大きく関わるようなことさえも、自分たちで決定することができないという状況にあって、やはりそのような問いを地で生きた者、すなわち、いい意味で「わがまま」に生きた者の言葉には、独特の凄味と説得力が感じられるのではないでしょうか。
例えば、日本を代表する文豪である夏目漱石は、50年でその生涯を終えました。彼はある時、まだ大学卒業前の弟子とも言えない弟子にあてて、自らの弱さをいかに扱うか、という問題について次のように手紙にしたためています。
「他人を決しておのれ以上遥かに卓越したものではない。また決しておのれ以下に遥かに劣ったものではない。特別の理由がない人には僕はこの心で対している。」
「君、弱い事をいってはいけない。僕も弱い男だが弱いなりに死ぬまでやるのである。やりたくなったってやらなければならん。君もその通りである。」
「死ぬのもよい。しかし死ぬより美しい女の同情でも得て死ぬ気がなくなる方がよかろう」
前年に『吾輩は猫である』を書き始めて作家として出発した漱石は、当時39歳。先の文言は、『猫』への大町桂月の悪口などにはめげないで書き続けるという宣言の後の一節でしたが、これぞまさに、おのれの弱さに悩みながらも、文句や愚痴を言ってへたれるのではなく、自分がしたいと思ったことを存分にやり切った漱石ならではの助言と言えます。
結果的に、漱石はこの年『坊つちゃん』や『草枕』を書きあげているのですが、この手紙には既に後の代表作『こころ』にも通じていくような師弟関係の熱さがこもっているように感じられますし、人びとがじっくり手紙を書くことをしなくなって失われたものがいかに大きいかも気付かせてくれるように思います。
今期のやぎ座もまた、いつの間にか自分が失っていたものがあるとしたら、それは何だろうかということを一つ考えてみるといいかも知れません。
参考:三好行雄編『漱石書簡集』(岩波文庫)
とは言え、現在のコロナ禍において自分たちの生き死にに大きく関わるようなことさえも、自分たちで決定することができないという状況にあって、やはりそのような問いを地で生きた者、すなわち、いい意味で「わがまま」に生きた者の言葉には、独特の凄味と説得力が感じられるのではないでしょうか。
例えば、日本を代表する文豪である夏目漱石は、50年でその生涯を終えました。彼はある時、まだ大学卒業前の弟子とも言えない弟子にあてて、自らの弱さをいかに扱うか、という問題について次のように手紙にしたためています。
「他人を決しておのれ以上遥かに卓越したものではない。また決しておのれ以下に遥かに劣ったものではない。特別の理由がない人には僕はこの心で対している。」
「君、弱い事をいってはいけない。僕も弱い男だが弱いなりに死ぬまでやるのである。やりたくなったってやらなければならん。君もその通りである。」
「死ぬのもよい。しかし死ぬより美しい女の同情でも得て死ぬ気がなくなる方がよかろう」
前年に『吾輩は猫である』を書き始めて作家として出発した漱石は、当時39歳。先の文言は、『猫』への大町桂月の悪口などにはめげないで書き続けるという宣言の後の一節でしたが、これぞまさに、おのれの弱さに悩みながらも、文句や愚痴を言ってへたれるのではなく、自分がしたいと思ったことを存分にやり切った漱石ならではの助言と言えます。
結果的に、漱石はこの年『坊つちゃん』や『草枕』を書きあげているのですが、この手紙には既に後の代表作『こころ』にも通じていくような師弟関係の熱さがこもっているように感じられますし、人びとがじっくり手紙を書くことをしなくなって失われたものがいかに大きいかも気付かせてくれるように思います。
今期のやぎ座もまた、いつの間にか自分が失っていたものがあるとしたら、それは何だろうかということを一つ考えてみるといいかも知れません。
参考:三好行雄編『漱石書簡集』(岩波文庫)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「阿呆ばかりのこの大舞台」。

シェイクスピアの『リア王』(1606年推定初演)は、王室内の骨肉の争いがたちまち国家の規模をこえて、宇宙的な広がりを感じさせるダイナミックな展開へと進んでいく比類なき芝居ですが、その話の副筋であるグロスターとその子エドガーのたどる残酷な運命は、劇全体をじつに味わい深いものにしてくれているのと同時に、そうした逆境においてこそ、平穏な生活中では到底見えなかったものが見えてくるという意味で、現在の日本人の置かれた状況にも通底しているように思います。
グロスター伯爵は、庶子エドマンドの奸計により、その兄にあたる嫡出のエドガーを反逆者と思い込み、追手を差し向けるのですが、グロスターは両目をくりぬかれて荒い荒野を彷徨することになります。
そしてエドガーは頭のおかしい物乞いのトムに身をやつし、父にもそれと気付かれずにドーヴァー海峡に向かう父の手を引いていく。盲目のグロスターは、すぐ目の前に息子がいるのに気付かず、つぶやくのです。
「わしには道などないのだ。だから目はいらぬ。目が見えたときにはよくつまづいたものだ」
「よくあることだが、ものがあれば油断する、なくなればかえってそれが強みになる。ああ、エドガー、お前は騙された愚かな父の怒りの生贄になった!生き永らえていつかお前の体に触れることができたら、そのとき、俺は言うだろう、父は目をふたたび取り戻した」
そしてこの後、グロスターがドーヴァーの崖から身を投げようとしたのを、エドガー(トム)が一計を案じて救い、二人が狂乱のリア王と出会って、王の口からことばを聞いたとき、一連の場面は普遍的なものとなったように思います。いわく、
「ひとはみな、泣きながらことの世にやってきたのだ、そうであろう、誰でも初めてこの世の大気に触れるとき、必ず泣きわめく」
「生まれ落ちるや、誰も大声をあげて泣き叫ぶ、阿呆ばかりのこの大きな舞台に突き出されたのが悲しくなる」
今期のみずがめ座もまた、狂気のなかで理性をよみがえらせた『リア王』の面々のごとく、改めて”心の眼”を取り戻していきたいところです。
参考:松岡和子訳『チェイクスピア全集 5』(ちくま文庫)
グロスター伯爵は、庶子エドマンドの奸計により、その兄にあたる嫡出のエドガーを反逆者と思い込み、追手を差し向けるのですが、グロスターは両目をくりぬかれて荒い荒野を彷徨することになります。
そしてエドガーは頭のおかしい物乞いのトムに身をやつし、父にもそれと気付かれずにドーヴァー海峡に向かう父の手を引いていく。盲目のグロスターは、すぐ目の前に息子がいるのに気付かず、つぶやくのです。
「わしには道などないのだ。だから目はいらぬ。目が見えたときにはよくつまづいたものだ」
「よくあることだが、ものがあれば油断する、なくなればかえってそれが強みになる。ああ、エドガー、お前は騙された愚かな父の怒りの生贄になった!生き永らえていつかお前の体に触れることができたら、そのとき、俺は言うだろう、父は目をふたたび取り戻した」
そしてこの後、グロスターがドーヴァーの崖から身を投げようとしたのを、エドガー(トム)が一計を案じて救い、二人が狂乱のリア王と出会って、王の口からことばを聞いたとき、一連の場面は普遍的なものとなったように思います。いわく、
「ひとはみな、泣きながらことの世にやってきたのだ、そうであろう、誰でも初めてこの世の大気に触れるとき、必ず泣きわめく」
「生まれ落ちるや、誰も大声をあげて泣き叫ぶ、阿呆ばかりのこの大きな舞台に突き出されたのが悲しくなる」
今期のみずがめ座もまた、狂気のなかで理性をよみがえらせた『リア王』の面々のごとく、改めて”心の眼”を取り戻していきたいところです。
参考:松岡和子訳『チェイクスピア全集 5』(ちくま文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「国々の命運はその食事によって左右される」。
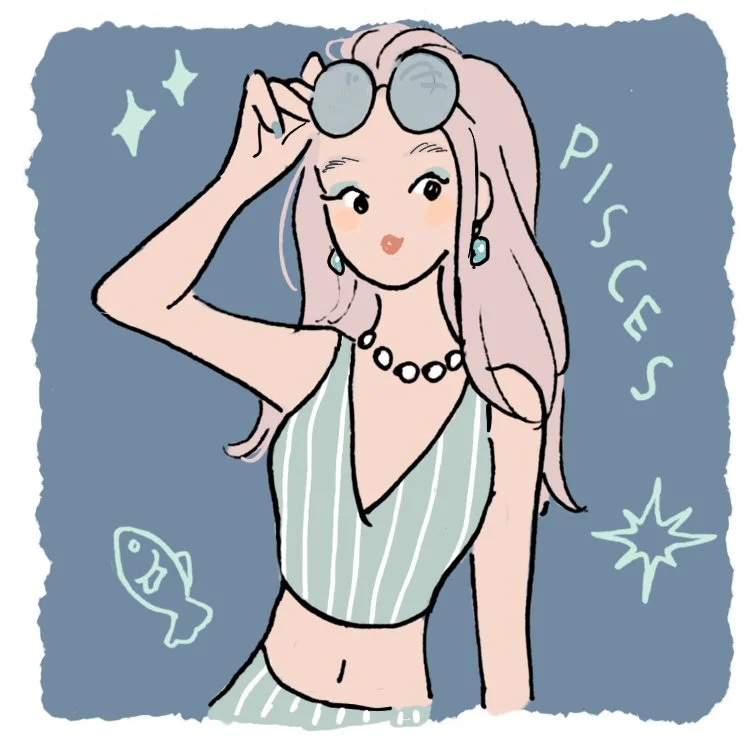
「死に寄り添う生」ということで、私たち日本人が忘れてはいけないことの一つが、日本神話においては生者のいのちを養ってくれる食べ物の起源は「女神の死」にあることでしょう。
『古事記』によれば、高天原を追放されたスサノオは、空腹を覚えてオホゲツヒメ(大気都比売神、イザナギとイザナミの間に生まれた女神)に食物を求め、オホゲツヒメはおもむろに様々な食物をスサノオに与えました。それを不審に思ったスサノオが食事の用意をするオホゲツヒメの様子を覗いてみると、オホゲツヒメは鼻や口、尻から食材を取り出し、それを調理していた。スサノオは、そんな汚い物を食べさせていたのかと怒り、オホゲツヒメを斬り殺してしまった。すると、オホゲツヒメの頭から蚕が生まれ、目から稲が生まれ、耳から粟が生まれ、鼻から小豆が生まれ、陰部から麦が生まれ、尻から大豆が生まれた。これをカミムスヒ(神産巣日御祖神)が回収したのだといいます。
こうした「死、殺害、最初の生殖」という神話的なテーマは、世界各地に見られる食物起源神話の型式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするハイヌウェレ型神話では繰り返し語られるモチーフですが、吉田敦彦の『日本神話の源流』によれば、日本の場合、このオホゲツヒメによって「粟」が広がったのだと言います。
つまり、スサノオによって殺されたオホゲツヒメの死体各部が種となり、その後、カミムスヒによって天上に回収され、その穀類の種が再び地上で用いられるようになった種が、その後のオオクニヌシの国造りに用いられる穀物として選ばれるようになっていったのだそうですが、ここで注目すべきはその国造りにおいて、オオクニヌシに力を貸した神スクナビコナが、カミムスヒの子でありやはり穀物神であったということ。
フランスの法律家にして美食批評家のブリア=サヴァランはかつて「国々の命運はその食事によって左右される。」(『美味礼賛』)という言葉を残しましたが、非常事態宣言を繰り返す中で飲食店や飲食業界を悪者扱いにして実質的な経済的虐殺をおこなっている現在の日本は、まさにこうした自分たちのアイデンティティを基礎づけてきた神話そのものを忘れてしまったのかもしれません。
今期のうお座もまた、いま自分が享受している豊かさが一体どんな犠牲の上でもたらされたものなのか、改めてその源流を想起していくことで、今後何を大切にしていくべきかを判断していきたいところです。
参考:吉田敦彦『日本神話の源流』(講談社学術文庫)
『古事記』によれば、高天原を追放されたスサノオは、空腹を覚えてオホゲツヒメ(大気都比売神、イザナギとイザナミの間に生まれた女神)に食物を求め、オホゲツヒメはおもむろに様々な食物をスサノオに与えました。それを不審に思ったスサノオが食事の用意をするオホゲツヒメの様子を覗いてみると、オホゲツヒメは鼻や口、尻から食材を取り出し、それを調理していた。スサノオは、そんな汚い物を食べさせていたのかと怒り、オホゲツヒメを斬り殺してしまった。すると、オホゲツヒメの頭から蚕が生まれ、目から稲が生まれ、耳から粟が生まれ、鼻から小豆が生まれ、陰部から麦が生まれ、尻から大豆が生まれた。これをカミムスヒ(神産巣日御祖神)が回収したのだといいます。
こうした「死、殺害、最初の生殖」という神話的なテーマは、世界各地に見られる食物起源神話の型式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするハイヌウェレ型神話では繰り返し語られるモチーフですが、吉田敦彦の『日本神話の源流』によれば、日本の場合、このオホゲツヒメによって「粟」が広がったのだと言います。
つまり、スサノオによって殺されたオホゲツヒメの死体各部が種となり、その後、カミムスヒによって天上に回収され、その穀類の種が再び地上で用いられるようになった種が、その後のオオクニヌシの国造りに用いられる穀物として選ばれるようになっていったのだそうですが、ここで注目すべきはその国造りにおいて、オオクニヌシに力を貸した神スクナビコナが、カミムスヒの子でありやはり穀物神であったということ。
フランスの法律家にして美食批評家のブリア=サヴァランはかつて「国々の命運はその食事によって左右される。」(『美味礼賛』)という言葉を残しましたが、非常事態宣言を繰り返す中で飲食店や飲食業界を悪者扱いにして実質的な経済的虐殺をおこなっている現在の日本は、まさにこうした自分たちのアイデンティティを基礎づけてきた神話そのものを忘れてしまったのかもしれません。
今期のうお座もまた、いま自分が享受している豊かさが一体どんな犠牲の上でもたらされたものなのか、改めてその源流を想起していくことで、今後何を大切にしていくべきかを判断していきたいところです。
参考:吉田敦彦『日本神話の源流』(講談社学術文庫)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ