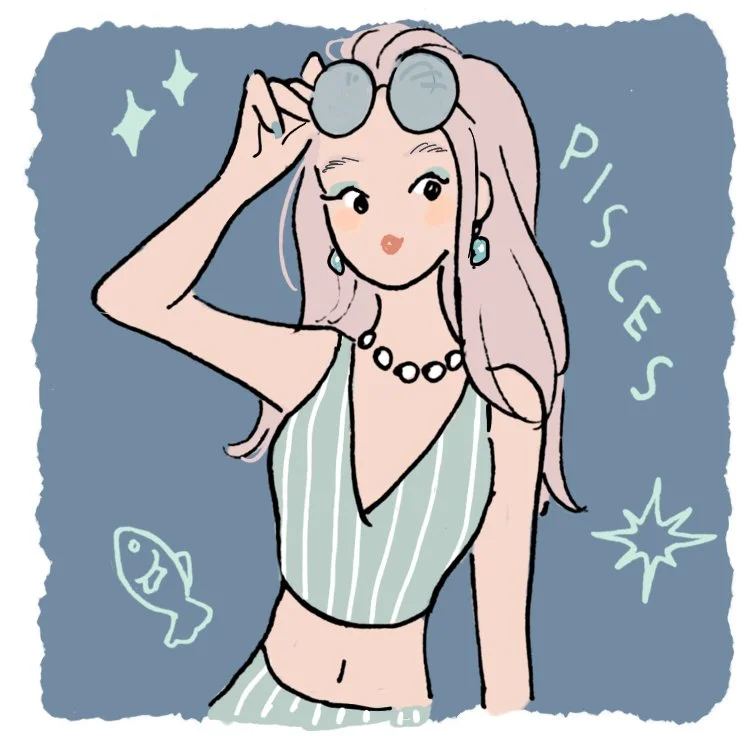【最新12星座占い】<10/31~11/13>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<10/31~11/13>の12星座全体の運勢は?
「一石を投じる」
暦の上で冬に入る「立冬」直前の11月5日、いよいよ紅葉も深まって、冬支度を急いでいくなか、さそり座の12度(数えで13度)で新月を形成していきます。
「危機と変革」を司る天王星へと思いっきり飛び込んでいく形で迎える今回の新月のテーマは、「リスクを引き受ける力」。
それはすなわち、普通に日常生活を送っている分にはまず見つからないような可能性を徹底的に追求し、そのために必要な材料をかき集め、まだ誰も試みていないことに手を出してみる勇気であったり、たとえそれがその界隈のタブーを破る行為であったり、厄介な相手に睨まれることになったとしても、ある種の「賭け」に出ていく姿勢に他なりません。
私たちの心の深層に潜んでいる集合的な変革衝動というのは、社会や現実の屋台骨を担う恒常性(ホメオスタシス)を維持したいという欲求にかならず切断・阻止・妨害される運命にある訳ですが、その意味で今期はこうした葛藤や対立に伴う緊張をヒリヒリと感じつつも、ひょんなことから「不満を大きく」したり、「自分を黙らせておけなくなって」、「もっとよりよくなるはず」という誘惑がどうにもできないほどに強烈なものなっていきやすいのだと言えるでしょう。
ギリシャ神話では、トロイア戦争に参加した女神エリスが「戦いの兆し」を持って軍船の上に立って雄叫びを上げると、兵士たちは闘争心と不屈の気力が湧き、戦いを好むようになったとされていますが、今期の私たちもまた、そうしたこれまでの膠着状態を破るための「一石を投じる」行動や企てが促されていくはずです。
「危機と変革」を司る天王星へと思いっきり飛び込んでいく形で迎える今回の新月のテーマは、「リスクを引き受ける力」。
それはすなわち、普通に日常生活を送っている分にはまず見つからないような可能性を徹底的に追求し、そのために必要な材料をかき集め、まだ誰も試みていないことに手を出してみる勇気であったり、たとえそれがその界隈のタブーを破る行為であったり、厄介な相手に睨まれることになったとしても、ある種の「賭け」に出ていく姿勢に他なりません。
私たちの心の深層に潜んでいる集合的な変革衝動というのは、社会や現実の屋台骨を担う恒常性(ホメオスタシス)を維持したいという欲求にかならず切断・阻止・妨害される運命にある訳ですが、その意味で今期はこうした葛藤や対立に伴う緊張をヒリヒリと感じつつも、ひょんなことから「不満を大きく」したり、「自分を黙らせておけなくなって」、「もっとよりよくなるはず」という誘惑がどうにもできないほどに強烈なものなっていきやすいのだと言えるでしょう。
ギリシャ神話では、トロイア戦争に参加した女神エリスが「戦いの兆し」を持って軍船の上に立って雄叫びを上げると、兵士たちは闘争心と不屈の気力が湧き、戦いを好むようになったとされていますが、今期の私たちもまた、そうしたこれまでの膠着状態を破るための「一石を投じる」行動や企てが促されていくはずです。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「アポトーシスを促す」。

私たちがふだん当たり前に見聞きする言葉の中に「自然死」という言葉がありますが、生物学的には“受動的”な死というものは存在しないのだそうです。つまり、死がきちんと実行されるためには、まず死を決定する遺伝子が働き、死を執り行うタンパク質の新たな合成が行われなければならないのだとか。
なんだか面倒な話ではありますが、要はわたしたち人間が有機体である限り、そうした面倒な手続きを踏まなければ、勝手に死ぬことさえできないという訳です。こうした個体を構成する細胞に予め埋め込まれていた死のプログラムを稼働させていくための、高度に調整された積極的な自殺現象のことを「アポトーシス」とも呼ぶそうですが、免疫学者の多田富雄は、「自己」というものが成立するためにはアポトーシスの働きが不可欠であり、「個体の「生」を保証していたのは細胞の「死」のプログラムだった」と述べた上で、次のように書いています。
「細胞は、みずからの設計図であるDNAを切断して死んでゆく。それによって逆に、脳神経系や免疫系などの高度な生命システム、私が超システムと呼ぶものが保証されていたのであった。」
ここで「超システム」とされているものこそが免疫であり、免疫はみずから規定した「自己」以外の異物を攻撃することで「自己の全体性」を守っていくのです。
「しかし、ここではっきりしたことは、個体の行動様式、いわば精神的「自己」を支配している脳が、もうひとつの「自己」を規定する免疫系によって、いともやすやすと「非自己」として排除されてしまうことである。つまり、身体的に「自己」を規定しているのは免疫系であって、脳ではないのである。脳は免疫系を拒絶できないが、免疫系は脳を異物として拒絶したのである。」
つまり「自己」らしさを感じていくためには、たえずなんとなくこれは自分らしくないなと身体全体(を司る免疫系)で感じ、判断することで、自身の一部を殺していかなければならない訳ですが、これは今期のおひつじ座にとっても、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という意味で通底していくテーマと言えるのではないでしょうか。
参考:多田富雄、『免疫の意味論』(新潮社)
なんだか面倒な話ではありますが、要はわたしたち人間が有機体である限り、そうした面倒な手続きを踏まなければ、勝手に死ぬことさえできないという訳です。こうした個体を構成する細胞に予め埋め込まれていた死のプログラムを稼働させていくための、高度に調整された積極的な自殺現象のことを「アポトーシス」とも呼ぶそうですが、免疫学者の多田富雄は、「自己」というものが成立するためにはアポトーシスの働きが不可欠であり、「個体の「生」を保証していたのは細胞の「死」のプログラムだった」と述べた上で、次のように書いています。
「細胞は、みずからの設計図であるDNAを切断して死んでゆく。それによって逆に、脳神経系や免疫系などの高度な生命システム、私が超システムと呼ぶものが保証されていたのであった。」
ここで「超システム」とされているものこそが免疫であり、免疫はみずから規定した「自己」以外の異物を攻撃することで「自己の全体性」を守っていくのです。
「しかし、ここではっきりしたことは、個体の行動様式、いわば精神的「自己」を支配している脳が、もうひとつの「自己」を規定する免疫系によって、いともやすやすと「非自己」として排除されてしまうことである。つまり、身体的に「自己」を規定しているのは免疫系であって、脳ではないのである。脳は免疫系を拒絶できないが、免疫系は脳を異物として拒絶したのである。」
つまり「自己」らしさを感じていくためには、たえずなんとなくこれは自分らしくないなと身体全体(を司る免疫系)で感じ、判断することで、自身の一部を殺していかなければならない訳ですが、これは今期のおひつじ座にとっても、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という意味で通底していくテーマと言えるのではないでしょうか。
参考:多田富雄、『免疫の意味論』(新潮社)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「たましいの嗅覚」。

社会に流れる空気がきな臭くなればなるほど、論理的な思考や常識的判断を一気に飛び越えて危険を察知していく“たましいの嗅覚”というものが問われていきます。
日本の哲学者である山内志朗は、『感じるスコラ哲学』の中で、精神医学者のテレンバッハの『味と雰囲気』を引用しつつ、「諦めは苦く、許すことが甘く、苦労が酸っぱいとされ」、「いやでたまらないことはにおいと結びついて」おり、「ラテン語では、くさい(odor)と嫌悪(odium)は同じ語根から出ていると考えられ」るのだと述べた上で、次のような重要な指摘を行っています。
すなわち、「嗅覚は、近距離の場面では回避すべき危険を示すのが主たる機能であり、その次に有益な食料の存在を示す機能があったと考えられます。だからこそ、「おいしい」という味覚と連合する感覚については、近接効果が大きいと思われ」、逆に「臭覚に障害が生じると、要素主義的にしか味覚が働か」ず、対象やそれがもたらす経験の微妙でさまざまなグラデーションを適切な距離感で識別できなくなるのだ、と。
この適切な距離感というのは、「テリトリー(縄張り)」という言葉の指し示す実際的な拡がりのことであり、それをより実存的な色彩で表現すれば「雰囲気」という言葉になります。
集団生活や社会生活を余儀なくされる人間は、自身にとって適切なテリトリーを必ずしも維持できず、しかもテリトリー内部を精密に調べられるほどの嗅覚の鋭さを失ってしまっていますが、だからこそ私たちは意図的に「近距離にある事物の有害・有益を判定」するセンサー機能を正常に働かせるべく、日頃からどうしても許せないものの雰囲気や匂いに敏感になっていかなければならないのです。
その上ではじめて、「母親的なものを経験する中核である(テレンスバッハ)」とされるあなたが真に求めるべき“いい雰囲気”を嗅ぎ当てていくことができるのではないでしょうか。今期のおうし座は、ひとつ鼻が感じるにおいにとことん従って、ときにはこのにおいだけは無理と、その一切を拒絶してみるべし。
参考:山内志朗『感じるスコラ哲学』(慶應義塾大学出版)
日本の哲学者である山内志朗は、『感じるスコラ哲学』の中で、精神医学者のテレンバッハの『味と雰囲気』を引用しつつ、「諦めは苦く、許すことが甘く、苦労が酸っぱいとされ」、「いやでたまらないことはにおいと結びついて」おり、「ラテン語では、くさい(odor)と嫌悪(odium)は同じ語根から出ていると考えられ」るのだと述べた上で、次のような重要な指摘を行っています。
すなわち、「嗅覚は、近距離の場面では回避すべき危険を示すのが主たる機能であり、その次に有益な食料の存在を示す機能があったと考えられます。だからこそ、「おいしい」という味覚と連合する感覚については、近接効果が大きいと思われ」、逆に「臭覚に障害が生じると、要素主義的にしか味覚が働か」ず、対象やそれがもたらす経験の微妙でさまざまなグラデーションを適切な距離感で識別できなくなるのだ、と。
この適切な距離感というのは、「テリトリー(縄張り)」という言葉の指し示す実際的な拡がりのことであり、それをより実存的な色彩で表現すれば「雰囲気」という言葉になります。
集団生活や社会生活を余儀なくされる人間は、自身にとって適切なテリトリーを必ずしも維持できず、しかもテリトリー内部を精密に調べられるほどの嗅覚の鋭さを失ってしまっていますが、だからこそ私たちは意図的に「近距離にある事物の有害・有益を判定」するセンサー機能を正常に働かせるべく、日頃からどうしても許せないものの雰囲気や匂いに敏感になっていかなければならないのです。
その上ではじめて、「母親的なものを経験する中核である(テレンスバッハ)」とされるあなたが真に求めるべき“いい雰囲気”を嗅ぎ当てていくことができるのではないでしょうか。今期のおうし座は、ひとつ鼻が感じるにおいにとことん従って、ときにはこのにおいだけは無理と、その一切を拒絶してみるべし。
参考:山内志朗『感じるスコラ哲学』(慶應義塾大学出版)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「ラスコーリニコフ的生活」

ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公で、頭は回るが仕事がないラスコーリニコフは、亀が甲羅の中に入り込むように穴ぐらのような部屋に引きこもって、散らかった室内でろくに片付けもせず、ひたすらごろごろ寝そべってして過ごしています。
こうした不潔な生活スタイルや、むやみやたらに他人にムカついている態度などは、村上春樹の小説に登場するどこか“のっぺり”とした主人公にはありえないことですが、教育学者の斎藤孝は、『ドストエフトキーの人間力』においてこうした「精神の内圧」の高さや、「過剰さ」こそがドストエフスキーの小説に出てくる人物の特徴であり、爆発的な祝祭性を生み出す原動力となっていくのだと述べています。
ラスコーリニコフはただ引きこもっているだけでなく、不意に街をうろつきます。普通はそうした散歩で鬱屈した気分も少しは緩和されるはずなのですが、斎藤はその点についても次のように描写しています。
「とくに行き場所があるわけではない。どこかへ行こうと思って出たとしてもすぐにそれがどこかを忘れてしまう。「<ところでおれはどこへ行こうとしているのか?>」と不意に考え込んだりする。歩きながら独り言を声に出して言ったりして、道行く人をびっくりさせる。独り言を言いながらせかせかと歩き回る人は、不気味なエネルギーを発している。ただ元気がないのならば大した危険はないのだが、自分の内部にこもっているのに、独り言を言いながらうろつきまわる行動的なタイプは危険な香りを発散している。」
そうしてラスコーリニコフは実際に、金貸しの老婆殺しというとんでもない一件を引きおこす訳ですが、それは彼のこころが冷え切っていたからでも、心神喪失状態にあったためでもなく、不意に彼を孤独の感情が襲い、ドストエフスキー自身による説明によれば「彼の内部には何かしら彼のまったく知らない、新しい、思いがけぬ、これまで一度もなかったものが生まれかけていた」のであり、「彼はそれを理解したわけではなかったが、はっきりと感じていた。感覚のすべての力ではっきりとつかみとっていた」というのです。
こうしたからだの奥底にまで届いてしまう「感覚」に、理屈とかではなく、いかに直接的に触れていくことができるか、ということが今期のふたご座にとっても重要なテーマとなっていくでしょう。
参考:斎藤孝、『ドストエフトキーの人間力』(新潮文庫)
こうした不潔な生活スタイルや、むやみやたらに他人にムカついている態度などは、村上春樹の小説に登場するどこか“のっぺり”とした主人公にはありえないことですが、教育学者の斎藤孝は、『ドストエフトキーの人間力』においてこうした「精神の内圧」の高さや、「過剰さ」こそがドストエフスキーの小説に出てくる人物の特徴であり、爆発的な祝祭性を生み出す原動力となっていくのだと述べています。
ラスコーリニコフはただ引きこもっているだけでなく、不意に街をうろつきます。普通はそうした散歩で鬱屈した気分も少しは緩和されるはずなのですが、斎藤はその点についても次のように描写しています。
「とくに行き場所があるわけではない。どこかへ行こうと思って出たとしてもすぐにそれがどこかを忘れてしまう。「<ところでおれはどこへ行こうとしているのか?>」と不意に考え込んだりする。歩きながら独り言を声に出して言ったりして、道行く人をびっくりさせる。独り言を言いながらせかせかと歩き回る人は、不気味なエネルギーを発している。ただ元気がないのならば大した危険はないのだが、自分の内部にこもっているのに、独り言を言いながらうろつきまわる行動的なタイプは危険な香りを発散している。」
そうしてラスコーリニコフは実際に、金貸しの老婆殺しというとんでもない一件を引きおこす訳ですが、それは彼のこころが冷え切っていたからでも、心神喪失状態にあったためでもなく、不意に彼を孤独の感情が襲い、ドストエフスキー自身による説明によれば「彼の内部には何かしら彼のまったく知らない、新しい、思いがけぬ、これまで一度もなかったものが生まれかけていた」のであり、「彼はそれを理解したわけではなかったが、はっきりと感じていた。感覚のすべての力ではっきりとつかみとっていた」というのです。
こうしたからだの奥底にまで届いてしまう「感覚」に、理屈とかではなく、いかに直接的に触れていくことができるか、ということが今期のふたご座にとっても重要なテーマとなっていくでしょう。
参考:斎藤孝、『ドストエフトキーの人間力』(新潮文庫)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「幻想の不可能性」。

平安時代の貴族の結婚は、女たちはほとんど不動産のように生活空間と一体化して動かず、外から訪れてくる男たちの動きによってのみ発生しており、宗教学者の中沢新一はそれは決して世界に幸福と豊穣の感覚をもたらさなかった一方で、「女性の文学」を生み出したのだと述べていました。
こうした移動する男性の放浪的な愛を待ち受けつつ、女たちが狭い生活空間で子供とのきわめて濃密な一体感を狭い空間で余儀なくさせられていく、という当時の結婚形式は、どこか現代の日本社会の一部でも積極的に推奨されている旧来的で女性差別的な考え方の源流のひとつにもなっているように感じられてしまいますが、そうした結婚において、女性は権力を操作するためのものであるか、「色好み」の対象でした。
そして中沢は後者について解説するなかで、いかに男性が結婚に幻想を見ていた一方で、女流日記のさきがけとされた『蜻蛉日記』の作者のようなすぐれた知性の女性たちは、むしろ幻想の不可能性を発見していたのだと指摘しつつ、次のように書いています。
「この「色好み」には、『源氏物語』などにみごとに表現されているように、母親に対するコンプレックスが、はっきり投影されている。はやい話が、貴族男性たちは、女性を愛するときに、かつて幼い頃に、自分の母親に充当されたリビドーを、そのまま若い女性たちの上に投影しながら、彼らの色事をおこなっているように、強く感じられるのである。彼らはどうも、一つの個性をそなえた女性を愛しているというよりも、大人になるためにあきらめざるをえなかった、濃密な母子の関係の中で発生したリビドーを、つぎつぎと異なる女性に投影しては、そのたびに失望を味わい、また別の女性に移っていくという、プロセスをくりかえしていたように、思えるのである。」
今期のかに座もまた、男たちの幻想につきあうことで育まれた、かつての女性たちの結婚生活における不幸と、それに反比例した豊かな日本語を下敷きにしつつ、あらためて自分が求めているリアルがどこにあるのかを模索していきたいところです。
参考:中沢新一「日本文学の大地」(角川学芸出版)
こうした移動する男性の放浪的な愛を待ち受けつつ、女たちが狭い生活空間で子供とのきわめて濃密な一体感を狭い空間で余儀なくさせられていく、という当時の結婚形式は、どこか現代の日本社会の一部でも積極的に推奨されている旧来的で女性差別的な考え方の源流のひとつにもなっているように感じられてしまいますが、そうした結婚において、女性は権力を操作するためのものであるか、「色好み」の対象でした。
そして中沢は後者について解説するなかで、いかに男性が結婚に幻想を見ていた一方で、女流日記のさきがけとされた『蜻蛉日記』の作者のようなすぐれた知性の女性たちは、むしろ幻想の不可能性を発見していたのだと指摘しつつ、次のように書いています。
「この「色好み」には、『源氏物語』などにみごとに表現されているように、母親に対するコンプレックスが、はっきり投影されている。はやい話が、貴族男性たちは、女性を愛するときに、かつて幼い頃に、自分の母親に充当されたリビドーを、そのまま若い女性たちの上に投影しながら、彼らの色事をおこなっているように、強く感じられるのである。彼らはどうも、一つの個性をそなえた女性を愛しているというよりも、大人になるためにあきらめざるをえなかった、濃密な母子の関係の中で発生したリビドーを、つぎつぎと異なる女性に投影しては、そのたびに失望を味わい、また別の女性に移っていくという、プロセスをくりかえしていたように、思えるのである。」
今期のかに座もまた、男たちの幻想につきあうことで育まれた、かつての女性たちの結婚生活における不幸と、それに反比例した豊かな日本語を下敷きにしつつ、あらためて自分が求めているリアルがどこにあるのかを模索していきたいところです。
参考:中沢新一「日本文学の大地」(角川学芸出版)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「帰るべき場所」。

1983年に刊行された立花隆の『宇宙からの帰還』は、アメリカのアポロ計画に携わった宇宙飛行士たちを取材した内容でしたが、宇宙からの帰還後の飛行士たちの歩んだ道は実にさまざまでした。キリスト教の伝道師になった者もいれば、実業家になった者や政治家に転身した者などがいる一方で、長く心を病んだ者もいました。いずれにせよ、宇宙体験は彼らの帰還後の人生や価値観に多大な影響を与えた訳ですが、たとえば帰還後にキリスト教の伝道師となったジョン・アーウィンは次のように語りました。
「地球を離れて、はじめて丸ごとの地球を一つの球体として見たとき、それはバスケットボールくらいの大きさだった。それが離れるに従って、野球のボールくらいになり、ゴルフボールくらいになり、ついに月からはマーブルの大きさになってしまった。はじめはその美しさ、生命感に目を奪われていたが、やがて、その弱々しさ、もろさを感じるようになる。感動する。宇宙の暗黒の中の小さな青い宝石。それが地球だ。」
そして、時を経て2016年に宇宙空間に4か月間の長期滞在ミッションを果たした新世代の宇宙飛行士・大西卓哉は、そんなアーウィンの言葉を受けて、自身の宇宙体験について、次のように語っています。
「アポロ時代よりももっと遠く、地球が他の星と同じような点になるようになることを想像してみてほしいんです。地球が“マーブル”ですらない遠く、夜空の星と見分けがつかないような点でしかなくなっていく。そのとき、僕が宇宙でずっと感じていた安心感は消えてしまうでしょう。自分が生まれ育った、人類の全てのただ一個の故郷である星。そこから遠く離れた人間は、親から切り離された子供みたいなものです。手の届きそうなところにあったその星が、『帰れる場所』ではなくなったそのとき、人間の精神が受ける影響は計り知れないものがある、と僕は宇宙で思いました。もちろん実際に自分がどう感じるか、その孤独感に耐えられるかどうかは、とても興味深いことではありますけどね」
『宇宙からの帰還』で立花は地球低軌道、船外活動、月軌道や月に降り立った飛行士など、さまざまな種類や深さの宇宙体験を描き、「この地球以外、我々にはどこにも住む所がないんだ」という3度の宇宙飛行を経験したウォーリー・シラーの言葉を印象的に伝えていましたが、今期のしし座もまた、そうした「帰るべき場所」をめぐる実感をいかに深めていけるかどうかが問われていくことになるかも知れません。
参考:立花隆『宇宙からの帰還』(中公文庫)
稲泉連『宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全12人の証言』(文藝春秋)
「地球を離れて、はじめて丸ごとの地球を一つの球体として見たとき、それはバスケットボールくらいの大きさだった。それが離れるに従って、野球のボールくらいになり、ゴルフボールくらいになり、ついに月からはマーブルの大きさになってしまった。はじめはその美しさ、生命感に目を奪われていたが、やがて、その弱々しさ、もろさを感じるようになる。感動する。宇宙の暗黒の中の小さな青い宝石。それが地球だ。」
そして、時を経て2016年に宇宙空間に4か月間の長期滞在ミッションを果たした新世代の宇宙飛行士・大西卓哉は、そんなアーウィンの言葉を受けて、自身の宇宙体験について、次のように語っています。
「アポロ時代よりももっと遠く、地球が他の星と同じような点になるようになることを想像してみてほしいんです。地球が“マーブル”ですらない遠く、夜空の星と見分けがつかないような点でしかなくなっていく。そのとき、僕が宇宙でずっと感じていた安心感は消えてしまうでしょう。自分が生まれ育った、人類の全てのただ一個の故郷である星。そこから遠く離れた人間は、親から切り離された子供みたいなものです。手の届きそうなところにあったその星が、『帰れる場所』ではなくなったそのとき、人間の精神が受ける影響は計り知れないものがある、と僕は宇宙で思いました。もちろん実際に自分がどう感じるか、その孤独感に耐えられるかどうかは、とても興味深いことではありますけどね」
『宇宙からの帰還』で立花は地球低軌道、船外活動、月軌道や月に降り立った飛行士など、さまざまな種類や深さの宇宙体験を描き、「この地球以外、我々にはどこにも住む所がないんだ」という3度の宇宙飛行を経験したウォーリー・シラーの言葉を印象的に伝えていましたが、今期のしし座もまた、そうした「帰るべき場所」をめぐる実感をいかに深めていけるかどうかが問われていくことになるかも知れません。
参考:立花隆『宇宙からの帰還』(中公文庫)
稲泉連『宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全12人の証言』(文藝春秋)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「才能のある子」。

幼児虐待とその社会への影響に関する研究で知られる心理学者のアリス・ミラーは、愛情があるかのように偽装されているにも関わらず、実際には愛情が欠如しており、子どもが無条件には決して受け入れられておらず、何らかの「よいこと」をしたときにだけ、「生存キップ」が渡されるような家庭に「才能のある子」が出現する、という事実を明らかにしました。
こうした「才能のある子」は、世間的には平均以上の成功をおさめていても、つねに不安にさらされていたり、虚しさに苦しめられていることが多いのですが、その点について学際的な研究で知られる安富渉は、東大や京大をはじめとしたエリート大学出身者たちというのは、その大抵が「重症の「才能のある子」である」と喝破しつつ、特に「官僚的」と呼ばれるような人たちを取りあげて次のように指摘しています。
すなわち、一見すると確実性の探求のように見える彼らの仕事ぶりや話し方というのは、端的に言って「「叱られない」ためのものであって、手続き的厳密性・整合性・隠蔽性に傾斜して」おり、「おそらくは「神」からもとやかく言われないため」の、不安の裏返しに過ぎない、と。
そうして安富は、ミラーの「才能のある子」という概念との出会いを通して、「「自分に対する裏切り」を引き起こすコミュニケーション過程の全体を「魂の植民地化」と捉え、そこから離脱する方向を探し求めるようになった」のだそうですが、これは今期のおとめ座の人たちにもどこか通底する話と言えるかも知れません。
参考:安富渉『合理的な神秘主義』(青灯社)
こうした「才能のある子」は、世間的には平均以上の成功をおさめていても、つねに不安にさらされていたり、虚しさに苦しめられていることが多いのですが、その点について学際的な研究で知られる安富渉は、東大や京大をはじめとしたエリート大学出身者たちというのは、その大抵が「重症の「才能のある子」である」と喝破しつつ、特に「官僚的」と呼ばれるような人たちを取りあげて次のように指摘しています。
すなわち、一見すると確実性の探求のように見える彼らの仕事ぶりや話し方というのは、端的に言って「「叱られない」ためのものであって、手続き的厳密性・整合性・隠蔽性に傾斜して」おり、「おそらくは「神」からもとやかく言われないため」の、不安の裏返しに過ぎない、と。
そうして安富は、ミラーの「才能のある子」という概念との出会いを通して、「「自分に対する裏切り」を引き起こすコミュニケーション過程の全体を「魂の植民地化」と捉え、そこから離脱する方向を探し求めるようになった」のだそうですが、これは今期のおとめ座の人たちにもどこか通底する話と言えるかも知れません。
参考:安富渉『合理的な神秘主義』(青灯社)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「意味の外へ」。
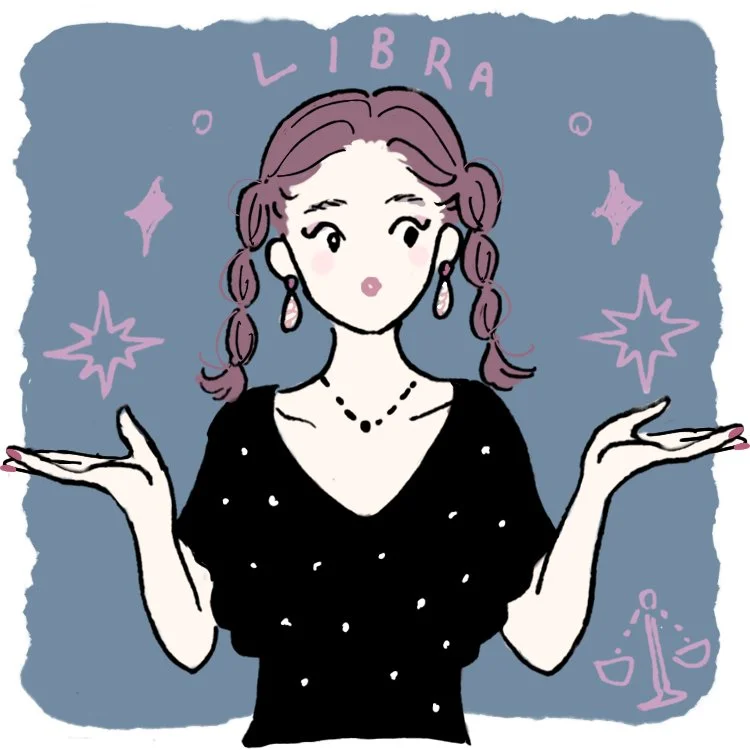
哲学者の鷲田清一は、『「聴く」ことの力』のなかで、患者の話をただ聞くだけで、解釈を行わない治療法を例にあげつつ、ケアというのは「なんのために?」という問いが失効するところでなされるものだ、と主張しています。
「他人へのケアといういとなみは、まさにこのように意味の外でおこなわれるものであるはずだ。ある効果を求めてなされるのではなく、「なんのために?」という問いが失効するところで、ケアはなされる。こういうひとだから、あるいはこういう目的や必要があって、といった条件つきで世話をしてもらうのではなくて、条件なしに、あなたがいるからという、ただそれだけの理由で享ける世話、それがケアなのではないだろうか。」
特定の「目的」も「必要」も関係ないところで、すなわち、あらかじめ自分で立てた計画や心に秘めた算段に固執せず、相手が入り込めるような何もない余白をもって、ただ相手を「享ける」こと。
鷲田はそれこそがケアなのではないかと言う訳ですが、こうしたことがわざわざ論じられなければならないということは、いかに社会に「押しつけの利他」が跋扈しており、私たちがそれにうんざりしているか、それに無意識に応えてしまってきたことで疲弊しているかを表しているのではないでしょうか。
親であれ恋人であれ子供であれ、何の条件もなしに、ほかの誰かと「ともにいる」ことが難しくなっている現代社会において、いかに他者を意味の外へ、自由な余白へと連れ出していけるか、そこにとどまれるか。今期のてんびん座は、ひとつそんなことを念頭においてみるといいかもしれません。
参考:鷲田清一『「聴く」ことの力―臨床哲学試論』(阪急コミュニケーションズ)
「他人へのケアといういとなみは、まさにこのように意味の外でおこなわれるものであるはずだ。ある効果を求めてなされるのではなく、「なんのために?」という問いが失効するところで、ケアはなされる。こういうひとだから、あるいはこういう目的や必要があって、といった条件つきで世話をしてもらうのではなくて、条件なしに、あなたがいるからという、ただそれだけの理由で享ける世話、それがケアなのではないだろうか。」
特定の「目的」も「必要」も関係ないところで、すなわち、あらかじめ自分で立てた計画や心に秘めた算段に固執せず、相手が入り込めるような何もない余白をもって、ただ相手を「享ける」こと。
鷲田はそれこそがケアなのではないかと言う訳ですが、こうしたことがわざわざ論じられなければならないということは、いかに社会に「押しつけの利他」が跋扈しており、私たちがそれにうんざりしているか、それに無意識に応えてしまってきたことで疲弊しているかを表しているのではないでしょうか。
親であれ恋人であれ子供であれ、何の条件もなしに、ほかの誰かと「ともにいる」ことが難しくなっている現代社会において、いかに他者を意味の外へ、自由な余白へと連れ出していけるか、そこにとどまれるか。今期のてんびん座は、ひとつそんなことを念頭においてみるといいかもしれません。
参考:鷲田清一『「聴く」ことの力―臨床哲学試論』(阪急コミュニケーションズ)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「無のほうへ開いておく」。

日本という国は万葉集の昔から現代まで、一貫して決められた形式の歌を、しかも身分の上下に関係なく作り続けてきたという、非常に大きな文化資産を有している訳ですが、ただそこにも時代の経過によって不可逆的な変化というのは起きていて、たとえば俳人の小澤實は、宗教学者の中沢新一との対談のなかで、それを近代に入ってから「俳句が独立し過ぎている」という言い方で表しています。
「中沢 優れた近世の俳句では底のところで無のほうへ開いていて、まるで幽霊みたいに足が消え去るような作りをしている。明治以降はそういう行き方が難しくなってきて、ヨーロッパ音楽みたいに底の開部を埋めてしまうんじゃないかな。そうすると一個一個の俳句が粒となって自立、独立してしまう。
小澤 現代の俳句は独立し過ぎているのかもしれません。
中沢 それは俳句の中だけで起こっていることではなくて、実は人間の生きている世界の構造が変わってしまったのだと思います。今作っている俳句と芭蕉が作っていた俳句はおのずから構造が違う、ということになります。だから、小澤さんが「芭蕉に帰る」と言っている時は、世界の構造を変えていかなきゃいけないという意思が同時にあるんでしょうね。」
これは「俳句」というところを「人間」に置き換えても通用する話ではないでしょうか。ただ「自立、独立」と言えば聞こえはいいですが、それは使うことばやそれを発する心身の「硬直」であり「死に体」に他ならず、人間としての「振れ幅」や「しなやかさ」が失われつつあることの何よりの表れという風にも受け取ることができるように思います。
今期のさそり座は、少なくとも詩であれ音楽であれ、何かが心の琴線に触れた時に軽く踊れるくらいには、自身をゆらいだ状態にしていくこと、すなわち、自身の存在の根底を「無のほうへ開いて」いくことで、いざとなれば何者にも変貌できるくらいの余地を与えていくことがテーマとなっていきそうです。
参考:中沢新一、小澤實『俳句の海に潜る』(角川書店)
「中沢 優れた近世の俳句では底のところで無のほうへ開いていて、まるで幽霊みたいに足が消え去るような作りをしている。明治以降はそういう行き方が難しくなってきて、ヨーロッパ音楽みたいに底の開部を埋めてしまうんじゃないかな。そうすると一個一個の俳句が粒となって自立、独立してしまう。
小澤 現代の俳句は独立し過ぎているのかもしれません。
中沢 それは俳句の中だけで起こっていることではなくて、実は人間の生きている世界の構造が変わってしまったのだと思います。今作っている俳句と芭蕉が作っていた俳句はおのずから構造が違う、ということになります。だから、小澤さんが「芭蕉に帰る」と言っている時は、世界の構造を変えていかなきゃいけないという意思が同時にあるんでしょうね。」
これは「俳句」というところを「人間」に置き換えても通用する話ではないでしょうか。ただ「自立、独立」と言えば聞こえはいいですが、それは使うことばやそれを発する心身の「硬直」であり「死に体」に他ならず、人間としての「振れ幅」や「しなやかさ」が失われつつあることの何よりの表れという風にも受け取ることができるように思います。
今期のさそり座は、少なくとも詩であれ音楽であれ、何かが心の琴線に触れた時に軽く踊れるくらいには、自身をゆらいだ状態にしていくこと、すなわち、自身の存在の根底を「無のほうへ開いて」いくことで、いざとなれば何者にも変貌できるくらいの余地を与えていくことがテーマとなっていきそうです。
参考:中沢新一、小澤實『俳句の海に潜る』(角川書店)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「遁世(とんせい)術」。

理由や動機が不明な状態で行方をくらませ、本人がどこへ行ったのかを知る手がかりも残されていない状態を「蒸発」と呼んだりしますが、SNSやネット社会の発達によって国内外のあらゆる情報が簡単に手に入るようになった現代では、もはやそれも死語になりつつあります。
しかし、ワイドショーのコメンテーターのように、何か事件や物珍しいことが起こると、何かもっともらしい理由や背景を語らずにはいられないというのは、それ自体が不自然であるように思いますし、果たして「蒸発」という行動パターンそのものが無くなるかと言えば、それは疑わしいのではないでしょうか。
例えば民俗学者の柳田國男は、数千年来の庶民の暮らしやその口伝を研究した『山の人生』のなかで、「生活の全く単調であった前代の田舎には、存外に跡の少しも残らぬ遁世(とんせい)が多かった」のだと述べた上で、現代の私たちにとっては珍しいことでも、昔は「なんの頼むところもない弱い人間」や「いかにしても以前の群とともにおられる者」にとっては「死ぬか今ひとつは山に入るという方法しかなかった」のであり、蒸発ということも起きてはならないことと言うより、「普通の生存の一様式」であったのだと指摘しています。
「人にはなおこれという理由がなくてふらふらと山に入って行く癖のようなものがあった。少なくとも今日の学問と推理だけでは説明することのできぬ人間の消滅、ことにはこの世の執着の多そうな若い人たちが、突如として山野に紛れ込んでしまって、何をしているかも知れなくなることがあった。自分がこの小さな書物で説いてみたいと思うのは主としてこうした方面の出来事である。」
現代人には、むしろこうした「山に入る」機会や選択肢が必要なのではないかと思うことがありますが、特に今期のいて座の人たちにとって、出世して自己承認欲求を満たすことばかりではなく、一時的にであれ俗世との関わりを断つ遁世やその術ということを、何らかの形で身につけていくことも視野に入れてみるといいでしょう。
参考:柳田國男『山の人生』(岩波文庫)
しかし、ワイドショーのコメンテーターのように、何か事件や物珍しいことが起こると、何かもっともらしい理由や背景を語らずにはいられないというのは、それ自体が不自然であるように思いますし、果たして「蒸発」という行動パターンそのものが無くなるかと言えば、それは疑わしいのではないでしょうか。
例えば民俗学者の柳田國男は、数千年来の庶民の暮らしやその口伝を研究した『山の人生』のなかで、「生活の全く単調であった前代の田舎には、存外に跡の少しも残らぬ遁世(とんせい)が多かった」のだと述べた上で、現代の私たちにとっては珍しいことでも、昔は「なんの頼むところもない弱い人間」や「いかにしても以前の群とともにおられる者」にとっては「死ぬか今ひとつは山に入るという方法しかなかった」のであり、蒸発ということも起きてはならないことと言うより、「普通の生存の一様式」であったのだと指摘しています。
「人にはなおこれという理由がなくてふらふらと山に入って行く癖のようなものがあった。少なくとも今日の学問と推理だけでは説明することのできぬ人間の消滅、ことにはこの世の執着の多そうな若い人たちが、突如として山野に紛れ込んでしまって、何をしているかも知れなくなることがあった。自分がこの小さな書物で説いてみたいと思うのは主としてこうした方面の出来事である。」
現代人には、むしろこうした「山に入る」機会や選択肢が必要なのではないかと思うことがありますが、特に今期のいて座の人たちにとって、出世して自己承認欲求を満たすことばかりではなく、一時的にであれ俗世との関わりを断つ遁世やその術ということを、何らかの形で身につけていくことも視野に入れてみるといいでしょう。
参考:柳田國男『山の人生』(岩波文庫)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「遍歴の騎士」。

「自分の神話を生きることは、たんに一つの神話を生きるこということではない」と主張したのは元型心理学者のジェイムズ・ヒルマンでしたが、このヒルマンの主張は、「多様性」という言葉が一人歩きしたまま、実質的には新自由主義社会が規定するような「勝ち組」になることが人生を規定する唯一の基準となりつつある現代社会にとって、ますます重要な問いかけとなってきているように思います。
ヒルマンは一神教であるキリスト教神学や、合理的な真理を追求する科学であれば、意味の単一性を獲得しようと試みるけれど、神話はわれわれの生に内在する「意味の複数性」を提供するのだとして次のように述べています。
「私は多くの人物なのだから、私はさまざまな神話の諸々の断片を上演しているのだ。すべての神話が互いに重なりあっているので、いかなる単一の断片も「これが私の神話だ」という陳述によって他から引き離すことができない。神話的なものとはパースペクティブであって、プログラムではないことを忘れてはいけない。神話を実践に使用しようとすることは、われわれを依然として英雄的自我のパターンにとどめ、その行為をいかに正しく行うかを学ぼうとすることに等しい。」
黙って実行すれば全てが自動的にうまくいく「プログラム」から離れ、一つの神話から別の神話への繋がりをたえず想像し、問いかけていくといった「パースペクティブ」を手に取っていくとき、結果的に、私たちの歩む道はまっすぐではなくなります。
すなわち、その道行きはたくさんの無駄にまみれ、まとまりもなくなり、いかにも英雄的だったりヒロイン的には振る舞えず、ある種の滑稽さを宿していくわけですが、ヒルマンはそれを「洞察を拾い集める遍歴の騎士」と呼びました。
心身の不調を抱えてでも満員電車にのって会社に出社しようとしてしまう日本人は、果たして「遍歴の騎士」になれるのか、いやそうなることを自分自身や身近な相手に許すことができるのか。今期のやぎ座は、そうした「意味の単一性」を切断し、いかに「複数性」を割り込ませていけるかが問われていくでしょう。
参考:ジェイムズ・ヒルマン、入江良平訳『魂の心理学』(青土社)
ヒルマンは一神教であるキリスト教神学や、合理的な真理を追求する科学であれば、意味の単一性を獲得しようと試みるけれど、神話はわれわれの生に内在する「意味の複数性」を提供するのだとして次のように述べています。
「私は多くの人物なのだから、私はさまざまな神話の諸々の断片を上演しているのだ。すべての神話が互いに重なりあっているので、いかなる単一の断片も「これが私の神話だ」という陳述によって他から引き離すことができない。神話的なものとはパースペクティブであって、プログラムではないことを忘れてはいけない。神話を実践に使用しようとすることは、われわれを依然として英雄的自我のパターンにとどめ、その行為をいかに正しく行うかを学ぼうとすることに等しい。」
黙って実行すれば全てが自動的にうまくいく「プログラム」から離れ、一つの神話から別の神話への繋がりをたえず想像し、問いかけていくといった「パースペクティブ」を手に取っていくとき、結果的に、私たちの歩む道はまっすぐではなくなります。
すなわち、その道行きはたくさんの無駄にまみれ、まとまりもなくなり、いかにも英雄的だったりヒロイン的には振る舞えず、ある種の滑稽さを宿していくわけですが、ヒルマンはそれを「洞察を拾い集める遍歴の騎士」と呼びました。
心身の不調を抱えてでも満員電車にのって会社に出社しようとしてしまう日本人は、果たして「遍歴の騎士」になれるのか、いやそうなることを自分自身や身近な相手に許すことができるのか。今期のやぎ座は、そうした「意味の単一性」を切断し、いかに「複数性」を割り込ませていけるかが問われていくでしょう。
参考:ジェイムズ・ヒルマン、入江良平訳『魂の心理学』(青土社)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「脱・身体調教」。

やってみようとすればすぐにわかると思いますが、心臓の鼓動であれ、全身の血の循環であれ、ほんらい名前もなく、立場もなく、資格もない自分のリアルな身体の生起現場に居合わせることは、非常に難しいことです。
というのも、ぼくたちの意識や思考は、すぐに外界へと旅立ってしまい、<今ここ>を見失ってしまうから。そして、それだけでなく、「身体の調教」という社会文脈もここに重なってきます。
哲学者の古東哲明は、M・フーコーの「社会の軍事的な夢」として概念化した、身体調教を通して人間主体の奥深くにインダストリアル(勤勉な、しかし機械的)な精神をうえつけ、自動的かつ自発的に社会秩序ができあがるようにしようとする近代社会特有の生き方を、本来は「野性体(遊体)」でしかない身体を、容易に操作可能な「<従順体>への改造」と呼びました。そして、そうした改造がすすめば、「かつてのような暴力的外圧(大権力)によって、各主体を抑圧する手間がはぶける」と。
例えば、近代社会が作り出した諸施設(学校、兵舎、工場、病棟、刑務所、学寮)というのは、みなそんな身体改造(サイボーグ化)のための調教装置であり、そこで私たちはさまざまな「身体図式」をインプットさせられていく訳ですが、一方で私たちは半ば本能的に踊りや体操であったり、瞑想や座禅などの宗教的な身体行など、社会や会社のもとめる生産性とは無縁な活動を通して、すっかり規格化され、抑圧された身体の「野性体(遊体)」としての本質をいま一度活性化したり、身体を従順体へと改造するプログラムコードを無効化しようともがいているのではないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、すっかりやせ細って魅力を失ってしまった近代社会的なリアリティを切り崩すべく、どうしたら「身体の調教」という拘束具を脱ぎ捨てられるのかということに、改めて取り組んでみるといいかも知れません。
参考:古東哲明『現代思想としてのギリシャ哲学』(ちくま学芸文庫)
というのも、ぼくたちの意識や思考は、すぐに外界へと旅立ってしまい、<今ここ>を見失ってしまうから。そして、それだけでなく、「身体の調教」という社会文脈もここに重なってきます。
哲学者の古東哲明は、M・フーコーの「社会の軍事的な夢」として概念化した、身体調教を通して人間主体の奥深くにインダストリアル(勤勉な、しかし機械的)な精神をうえつけ、自動的かつ自発的に社会秩序ができあがるようにしようとする近代社会特有の生き方を、本来は「野性体(遊体)」でしかない身体を、容易に操作可能な「<従順体>への改造」と呼びました。そして、そうした改造がすすめば、「かつてのような暴力的外圧(大権力)によって、各主体を抑圧する手間がはぶける」と。
例えば、近代社会が作り出した諸施設(学校、兵舎、工場、病棟、刑務所、学寮)というのは、みなそんな身体改造(サイボーグ化)のための調教装置であり、そこで私たちはさまざまな「身体図式」をインプットさせられていく訳ですが、一方で私たちは半ば本能的に踊りや体操であったり、瞑想や座禅などの宗教的な身体行など、社会や会社のもとめる生産性とは無縁な活動を通して、すっかり規格化され、抑圧された身体の「野性体(遊体)」としての本質をいま一度活性化したり、身体を従順体へと改造するプログラムコードを無効化しようともがいているのではないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、すっかりやせ細って魅力を失ってしまった近代社会的なリアリティを切り崩すべく、どうしたら「身体の調教」という拘束具を脱ぎ捨てられるのかということに、改めて取り組んでみるといいかも知れません。
参考:古東哲明『現代思想としてのギリシャ哲学』(ちくま学芸文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「禅機」。
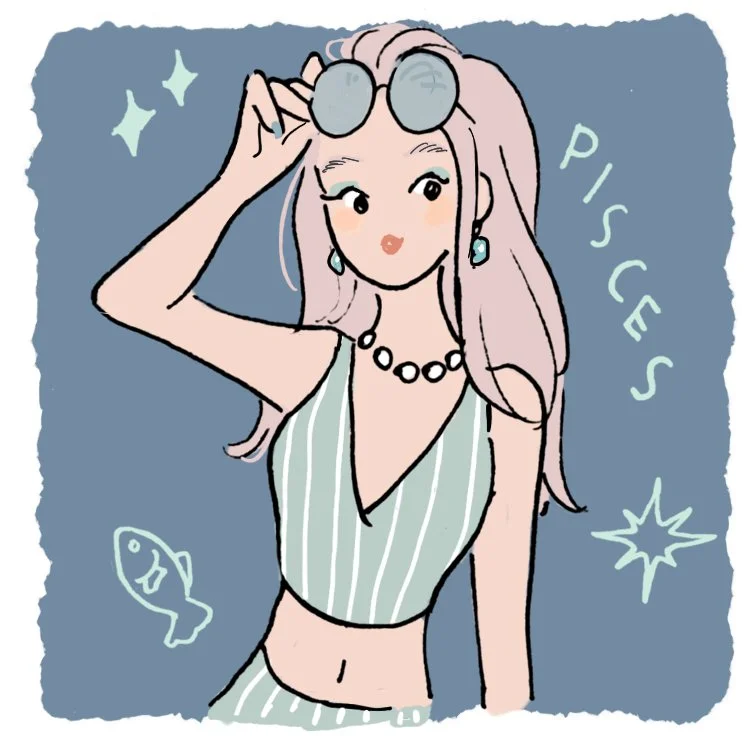
瞬間的・直観的に修行者に与えられるある種の気付きや、それが起こるプロセスのことを、禅宗では「禅機」と呼びますが、それは何も特別なことではなく、眠くなったときにスッと眠りに入って、そこで日中に削られたなにかが回復する、というある種のバランス感覚であり、私たち日本人はそうしたはたらきを例えば「わび・さび」という言葉でも表現してきたんではないでしょうか。
編集者の赤田祐一は、『spectator』の「わび・さび」特集号で、「“わび・さび”は「見つける」ものというより「見つかってしまう」ものであり、知識や理屈ではなく、むしろそこからはずれてしまうということのようだ」と書きながら、頻繁に旅行に出かけては岩や森にシャッターを切りまくっていた漫画家の水木しげるの言葉を引用しています。
「わたしは賢いんです。見るところがなくても、自然の中にいるとね、岩や樹が勝手に妖怪の造形を造ってくれるんです」
つまり、どうやら水木写真と「わび・さび」はとても似ているということらしいのですが、いくつかの旅行に同行していた作家の荒俣宏は次のようにも書いています。
「日本では心霊写真と称して、曖昧な陰翳を霊の姿と解釈することが流行している。基本はあれと同じ、偶然に生まれたロールシャッハテストみたいなものだが、水木大先生は霊の顔などというあたり前なイメージを見つけ出すのではない。もっと、根源的で力強い自然の精(エロス)のようなものを写真に撮られるのだ」
ここにさらに、実験音楽家のジョン・ケージが80年代に雑誌『遊』に残した言葉を引用しておきたいと思います。
「ポットの音―できれば鉄瓶の方がのぞましいけれど―が湧いた瞬間だっていい。寿司の肴の色が変わるか変わらないかの分かれ目だっていい。広重の雨がポツンと降ってきた矢先だっていい。そこに禅機があり、音楽がある。日本人はそんな禅機を禅以外にもたくさんもっている。俳句もそのひとつだ。」
今期のうお座もまた、写真や詩であれ、散歩やただぼーっとすることであれ、そうした禅機と戯れたり、誘われたりする時間を大切にしてみるといいかもしれません。
参考:エディトリアル・デパートメント『スペクテイター〈43号〉 わび・さび』(幻冬舎)
編集者の赤田祐一は、『spectator』の「わび・さび」特集号で、「“わび・さび”は「見つける」ものというより「見つかってしまう」ものであり、知識や理屈ではなく、むしろそこからはずれてしまうということのようだ」と書きながら、頻繁に旅行に出かけては岩や森にシャッターを切りまくっていた漫画家の水木しげるの言葉を引用しています。
「わたしは賢いんです。見るところがなくても、自然の中にいるとね、岩や樹が勝手に妖怪の造形を造ってくれるんです」
つまり、どうやら水木写真と「わび・さび」はとても似ているということらしいのですが、いくつかの旅行に同行していた作家の荒俣宏は次のようにも書いています。
「日本では心霊写真と称して、曖昧な陰翳を霊の姿と解釈することが流行している。基本はあれと同じ、偶然に生まれたロールシャッハテストみたいなものだが、水木大先生は霊の顔などというあたり前なイメージを見つけ出すのではない。もっと、根源的で力強い自然の精(エロス)のようなものを写真に撮られるのだ」
ここにさらに、実験音楽家のジョン・ケージが80年代に雑誌『遊』に残した言葉を引用しておきたいと思います。
「ポットの音―できれば鉄瓶の方がのぞましいけれど―が湧いた瞬間だっていい。寿司の肴の色が変わるか変わらないかの分かれ目だっていい。広重の雨がポツンと降ってきた矢先だっていい。そこに禅機があり、音楽がある。日本人はそんな禅機を禅以外にもたくさんもっている。俳句もそのひとつだ。」
今期のうお座もまた、写真や詩であれ、散歩やただぼーっとすることであれ、そうした禅機と戯れたり、誘われたりする時間を大切にしてみるといいかもしれません。
参考:エディトリアル・デパートメント『スペクテイター〈43号〉 わび・さび』(幻冬舎)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ