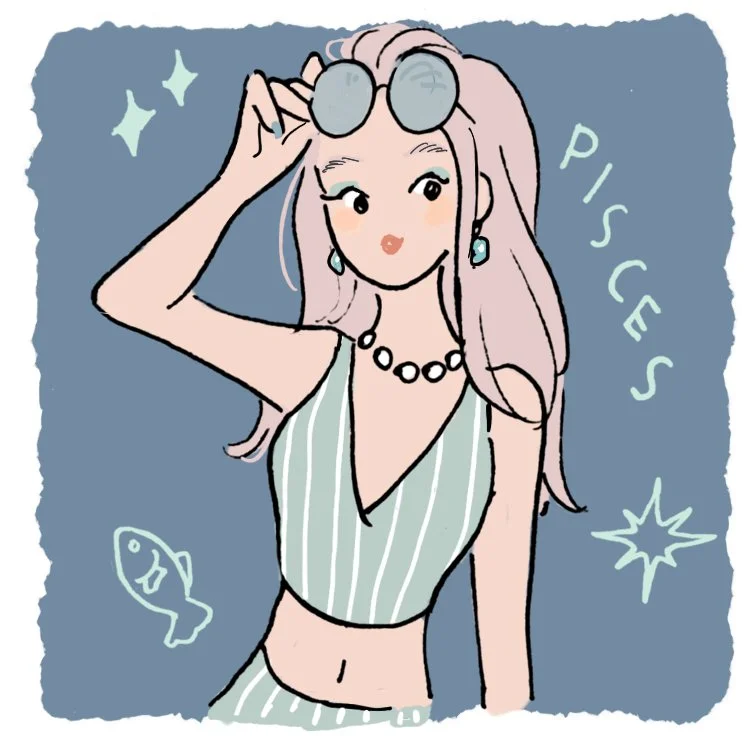【最新12星座占い】<1/9~1/22>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<1/9~1/22>の12星座全体の運勢は?
「苦みは早春の味わい」
一年のうちで最も寒さが厳しくなる「大寒」の直前にあたる1月18日には、2022年最初の満月をかに座27度(数えで28度)で迎えていきます。
ちなみに大寒の始まりは七十二候で言うと「欵冬華(ふきのはなさく)」にあたります。「欵」には叩くという意味があるのですが、蕗(ふき)は冬に氷をたたき割るようにして地中から地表へ出てくることから、冬を叩き割ると書いて「欵冬(かんとう)」という異名がついたのだとか。
同様に、変容の星である冥王星を巻き込んだ今回の満月のテーマは「とことん深い受容」。これまでのあなたの価値観や常識をバリバリと叩き壊し、心地よい日常へと闖入し、あなたを異世界へと連れ去ってしまうような“ストレンジャー(よそ者、流れもの、うさんくさいもの)”をいかにふところ深くに受け入れていくことができるか、そしてそれによってあなた自身の変容も感じとっていけるかどうかが問われていくでしょう。さながら、かつて70年代以降ネイティブアメリカンの文化に深く影響を受けていった現代アメリカの若者たちのように。
うまくいけば、これまでのあなたならとても受け入れられなかったり、価値観や世界観を共存させることができなかったような異質な考えや経験の芽が、まるで蕗の薹のような何とも言えない苦味を伴ってあなたの心中に流れ込んでくるはず。
それはやがてやってくる自然界の壮大な生まれ変わりの祭典である春の芽吹きを一足早く告げ知らせる、早春の味とも言えるかもしれません。
ちなみに大寒の始まりは七十二候で言うと「欵冬華(ふきのはなさく)」にあたります。「欵」には叩くという意味があるのですが、蕗(ふき)は冬に氷をたたき割るようにして地中から地表へ出てくることから、冬を叩き割ると書いて「欵冬(かんとう)」という異名がついたのだとか。
同様に、変容の星である冥王星を巻き込んだ今回の満月のテーマは「とことん深い受容」。これまでのあなたの価値観や常識をバリバリと叩き壊し、心地よい日常へと闖入し、あなたを異世界へと連れ去ってしまうような“ストレンジャー(よそ者、流れもの、うさんくさいもの)”をいかにふところ深くに受け入れていくことができるか、そしてそれによってあなた自身の変容も感じとっていけるかどうかが問われていくでしょう。さながら、かつて70年代以降ネイティブアメリカンの文化に深く影響を受けていった現代アメリカの若者たちのように。
うまくいけば、これまでのあなたならとても受け入れられなかったり、価値観や世界観を共存させることができなかったような異質な考えや経験の芽が、まるで蕗の薹のような何とも言えない苦味を伴ってあなたの心中に流れ込んでくるはず。
それはやがてやってくる自然界の壮大な生まれ変わりの祭典である春の芽吹きを一足早く告げ知らせる、早春の味とも言えるかもしれません。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「醜を含めた上での美」。

目の前の難敵に向かっていく決意を強く固めるため「あえて退路を絶つ」シーンが、よく映画やドラマ、漫画などで描かれることがありますが、今の日本社会や日本人を見ていると「あえて」という決意や自覚を持たないまま、半ば無意識のうちにみずから自滅の道に突き進んでいるのでは、と思わざるを得ないところが多々あるように思います。
おひつじ座は12星座の中でもっとも“見切り発車”をしでかす星座ですが、今期のおひつじ座は、いま現在の歩みが自滅に向かっているのか、そうでないのかを判断していく上で、受け入れなくてはならないことは何か?ということが特に問われていきやすいでしょう。
例えば、文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンは、最晩年に若い世代へのメッセージとして書いた『精神と自然』の娘と父親との対話という形式で構成されたメタローグ「それで?」の中で、<父親>が生命体の運命について語った次のような一節があります。
「どんな種だって進化の袋小路に入り込んでしまうことがある。(…)奇跡とは、物質主義者の考える物質主義的脱出法にほかならない。」
ここでベイトソンが言及している「奇跡」とは、かつて一世を風靡したインドの聖者サイババが、何もないところからビブーティと呼ばれる聖なる灰を出現させるパフォーマンスなどをイメージすると分かりやすいでしょう。
宗教は魔術から発生したという考え方がありますが、じつは魔術とは宗教の堕落したものであり、ベイトソンは魔術の延長線上にある降霊術や幽体離脱などはみな「物質主義的」なもので、そういうもので救われようとするのは安易で誤った試みに他ならないと指摘した上で<父親>にこう結論づけさせます。
「野卑な物質主義を逃れる道は奇跡ではなく美である―もちろん、醜を含めた上での美だけれどね。」
その美の例として、ベイトソンはバッハの交響曲やミケランジェロの彫刻のようなものだけでなく、サボテンやウミヘビ、ネコなど、学校では教えてくれない生きた美しさを挙げるのです。
すなわち、一発逆転的な奇跡ではなく、自分もまたそうした意味での美的な存在でありえているかというツッコミこそ、何よりもおひつじ座が日々の生活の中で、少しずつ受け入れていかなくてはならないものなのだと言えるかも知れません。
参考:グレゴリー・ベイトソン、佐藤良明訳『精神と自然』(思索社)
おひつじ座は12星座の中でもっとも“見切り発車”をしでかす星座ですが、今期のおひつじ座は、いま現在の歩みが自滅に向かっているのか、そうでないのかを判断していく上で、受け入れなくてはならないことは何か?ということが特に問われていきやすいでしょう。
例えば、文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンは、最晩年に若い世代へのメッセージとして書いた『精神と自然』の娘と父親との対話という形式で構成されたメタローグ「それで?」の中で、<父親>が生命体の運命について語った次のような一節があります。
「どんな種だって進化の袋小路に入り込んでしまうことがある。(…)奇跡とは、物質主義者の考える物質主義的脱出法にほかならない。」
ここでベイトソンが言及している「奇跡」とは、かつて一世を風靡したインドの聖者サイババが、何もないところからビブーティと呼ばれる聖なる灰を出現させるパフォーマンスなどをイメージすると分かりやすいでしょう。
宗教は魔術から発生したという考え方がありますが、じつは魔術とは宗教の堕落したものであり、ベイトソンは魔術の延長線上にある降霊術や幽体離脱などはみな「物質主義的」なもので、そういうもので救われようとするのは安易で誤った試みに他ならないと指摘した上で<父親>にこう結論づけさせます。
「野卑な物質主義を逃れる道は奇跡ではなく美である―もちろん、醜を含めた上での美だけれどね。」
その美の例として、ベイトソンはバッハの交響曲やミケランジェロの彫刻のようなものだけでなく、サボテンやウミヘビ、ネコなど、学校では教えてくれない生きた美しさを挙げるのです。
すなわち、一発逆転的な奇跡ではなく、自分もまたそうした意味での美的な存在でありえているかというツッコミこそ、何よりもおひつじ座が日々の生活の中で、少しずつ受け入れていかなくてはならないものなのだと言えるかも知れません。
参考:グレゴリー・ベイトソン、佐藤良明訳『精神と自然』(思索社)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「因果づくの物の怪」。

地道に生きるのが一番だ、という生活観は長らく日本社会に根付いてきましたが、ここ数年で子どもの将来なりたい職業ランキング上位に毎年YouTuberが食い込んでくるようになってきたのを見ていると、どうもそうした従来のスタンダードだった生活観は確実に変化を求められ、地道には生きられないとまでは言わずとも、みな何かしらの情報発信や自己表現をするのが当たり前になりつつあるように感じます。
特に、2018年ないし2019年頃から価値観の転倒を意味する天王星が滞在し続けているおうし座の人たちは、少なからずこれまではする必要性さえ感じていなかったSNSやメディアでの情報発信や自己表現がグッと身近になってきたり、何だかんだとチャレンジせざるを得ない状況に巻き込まれてきた人が少なくないのではないでしょうか。
ただ、こうした広義の意味での自己表現という文脈でふと思い出されるのが、作家の車谷長吉の「因果づく」というエッセイです。その中で、車谷は「小説を書くという振る舞いは、魔物に「ふれる」というより、魔物に「さわる」という行為に近く、時にみずからが分泌する人間毒に感電して、何とも得体の知れないメランコリア(憂鬱)に囚われてしまうことがある」のだと告白します。
そして、かつて行った目黒の権之助坂のおさわりバーの話などを持ち出しつつ、「「さわらないではいられない」因果づくの物の怪に追われて「さわる」のであって、魔物に「さわった」途端、こちらの生血が吸い取られる。が、当り「さわり」のない話だけを書いていたのでは、文学にならない」のだとうそぶくのです。
「いずれにしても、この「さわりたい」「さわらないではいられない」というみずからの中の魔物は、人にあっては不可避の出来事である。本当は「さわりたくない」「さわらない方がいい」、けれども「さわりたい」「さわらざるを得ない」「さわらないではいられない」「さわることなしには生きて行けない」、そういうことがある。そういう因果づくの物の怪が、人という生物の中には息をしている。まことに厄介な、にがい厄である。文学がどうのを抜きにしても、人の生はそういう厄を負うているのではないだろうか。「厄」とは木の節の目のことであり、この目は木の中にシコリとなっていて、鋸の歯など飛ばしてしまうのである。」
今期のおうし座もまた、そんなふうに自身の中に棲みついては息をしている「因果づくの物の怪」にさわらずにはいられない自分のさがについて受け入れてみるといいでしょう。
参考:車谷長吉『業柱抱き』(新潮文庫)
特に、2018年ないし2019年頃から価値観の転倒を意味する天王星が滞在し続けているおうし座の人たちは、少なからずこれまではする必要性さえ感じていなかったSNSやメディアでの情報発信や自己表現がグッと身近になってきたり、何だかんだとチャレンジせざるを得ない状況に巻き込まれてきた人が少なくないのではないでしょうか。
ただ、こうした広義の意味での自己表現という文脈でふと思い出されるのが、作家の車谷長吉の「因果づく」というエッセイです。その中で、車谷は「小説を書くという振る舞いは、魔物に「ふれる」というより、魔物に「さわる」という行為に近く、時にみずからが分泌する人間毒に感電して、何とも得体の知れないメランコリア(憂鬱)に囚われてしまうことがある」のだと告白します。
そして、かつて行った目黒の権之助坂のおさわりバーの話などを持ち出しつつ、「「さわらないではいられない」因果づくの物の怪に追われて「さわる」のであって、魔物に「さわった」途端、こちらの生血が吸い取られる。が、当り「さわり」のない話だけを書いていたのでは、文学にならない」のだとうそぶくのです。
「いずれにしても、この「さわりたい」「さわらないではいられない」というみずからの中の魔物は、人にあっては不可避の出来事である。本当は「さわりたくない」「さわらない方がいい」、けれども「さわりたい」「さわらざるを得ない」「さわらないではいられない」「さわることなしには生きて行けない」、そういうことがある。そういう因果づくの物の怪が、人という生物の中には息をしている。まことに厄介な、にがい厄である。文学がどうのを抜きにしても、人の生はそういう厄を負うているのではないだろうか。「厄」とは木の節の目のことであり、この目は木の中にシコリとなっていて、鋸の歯など飛ばしてしまうのである。」
今期のおうし座もまた、そんなふうに自身の中に棲みついては息をしている「因果づくの物の怪」にさわらずにはいられない自分のさがについて受け入れてみるといいでしょう。
参考:車谷長吉『業柱抱き』(新潮文庫)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「「もれ」を促す」。

「近年、日本人の貧しさを突きつけられる機会が何かと増えた」
ラオスで現地人にたかろうとする日本人バックパッカーの話や、新幹線の自由席で隣の席に荷物を置き、途中の駅で人が乗ってきても一車両のほぼ全員がそのままにしている光景を直接見たという話を、先日或るご年配の方から聞いていたとき、ふとそんな言葉が漏れてきました。
私たちは、「貧しさ」の問題にちゃんと向き合えているのでしょうか。日本で貧困ということが取り沙汰されるとき、それは国や自治体が対応すべき課題であり、社会問題であるという意識がどこか根強いように思いますが、それはもはや普通の人々の暮らしの外側で起きている訳ではないということに、気付き始めている人も少なくないはず。
ここでいう「貧困」とは、ただ年収や生活レベルなど経済的な問題に限らず、子どもへの虐待にせよ、高齢者の孤立にしろ、すぐ横にいる問題を抱えた他者の困難を知りえない、関心を持てないという状況そのものが、日々の暮らしから政治や経済を遠ざけている構造を生んでいることを指しているのですが、例えば、文化人類学者の松村圭一郎は『くらしのアナキズム』の中で、自身のフィールドワーク経験から次のように述べています。
「目を見てあいさつを交わすような、人が人として対面する状況では、他人の問題がたんなる他人事ではすませられなくなる。そこでいやおうなく生じる感情が、人を何らかの行為へと導く。嫌悪感やうしろめたさを含め、つねに感情的な交わりの回路が維持されていることが、ともに困難に対処するきっかけになりうる。」
「歴史家の藤原辰史が『縁食論』の中で、安藤昌益の「もれる」という概念に注目している。(…)他人の問題がつねにもれでている。だから、それぞれが手にした富を独り占めすることも難しくなり、必要な人へともれだしていく。富が独占されず、他人の困難が共有されるためには、問題が個人や家庭だけに押し付けられ、閉じ込められてはいけない。」
「日本でよく耳にする「他人に迷惑をかけてはいけない」という言葉。エチオピアの人びとのふるまいを見ていると、その言葉が、いかに「もれ」を否定し、抑圧してきたのかがわかる。人間は他人に迷惑も、喜びも、悲しみも怒りも、いろんなものを与え、受け取って生きている。それをまず肯定することが「もれる」社会への一歩だ。」
今期のふたご座もまた、貧しさときちんと向き合うためにも、日常の些細なコミュニケーションの中で、みずからにそうした「もれ」を促してみるといいかも知れません。
参考:松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)
ラオスで現地人にたかろうとする日本人バックパッカーの話や、新幹線の自由席で隣の席に荷物を置き、途中の駅で人が乗ってきても一車両のほぼ全員がそのままにしている光景を直接見たという話を、先日或るご年配の方から聞いていたとき、ふとそんな言葉が漏れてきました。
私たちは、「貧しさ」の問題にちゃんと向き合えているのでしょうか。日本で貧困ということが取り沙汰されるとき、それは国や自治体が対応すべき課題であり、社会問題であるという意識がどこか根強いように思いますが、それはもはや普通の人々の暮らしの外側で起きている訳ではないということに、気付き始めている人も少なくないはず。
ここでいう「貧困」とは、ただ年収や生活レベルなど経済的な問題に限らず、子どもへの虐待にせよ、高齢者の孤立にしろ、すぐ横にいる問題を抱えた他者の困難を知りえない、関心を持てないという状況そのものが、日々の暮らしから政治や経済を遠ざけている構造を生んでいることを指しているのですが、例えば、文化人類学者の松村圭一郎は『くらしのアナキズム』の中で、自身のフィールドワーク経験から次のように述べています。
「目を見てあいさつを交わすような、人が人として対面する状況では、他人の問題がたんなる他人事ではすませられなくなる。そこでいやおうなく生じる感情が、人を何らかの行為へと導く。嫌悪感やうしろめたさを含め、つねに感情的な交わりの回路が維持されていることが、ともに困難に対処するきっかけになりうる。」
「歴史家の藤原辰史が『縁食論』の中で、安藤昌益の「もれる」という概念に注目している。(…)他人の問題がつねにもれでている。だから、それぞれが手にした富を独り占めすることも難しくなり、必要な人へともれだしていく。富が独占されず、他人の困難が共有されるためには、問題が個人や家庭だけに押し付けられ、閉じ込められてはいけない。」
「日本でよく耳にする「他人に迷惑をかけてはいけない」という言葉。エチオピアの人びとのふるまいを見ていると、その言葉が、いかに「もれ」を否定し、抑圧してきたのかがわかる。人間は他人に迷惑も、喜びも、悲しみも怒りも、いろんなものを与え、受け取って生きている。それをまず肯定することが「もれる」社会への一歩だ。」
今期のふたご座もまた、貧しさときちんと向き合うためにも、日常の些細なコミュニケーションの中で、みずからにそうした「もれ」を促してみるといいかも知れません。
参考:松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「笑いとおっぱい」。

昨秋にコロナ禍での外出や飲食の制限が解除され始めて以来、それまで行き場を失って滞っていたエネルギーをどこに向けてどう解放すればいいのか、戸惑ったり分からなくなってしまっていた人も少なくないのではないでしょうか。
特に、今回の満月を自身の星座で迎えていくかに座の人たちは、以前のように飲み歩いたり、派手に遊んで発散したりという方向には振り切れないし、そこに注いでいたエネルギーをこれまでとはまったく異なる仕方で使っていきたいと感じている人も多いはず。
ここで思い出されるのが、宗教学者の中沢新一は2009年に開催された日本ユング心理学会のシンポジウムでの基調講演「ユングと曼荼羅」で紹介されていた、ユングの「3に1を加え、4で表現しよう」という考え方です。
中沢によれば、キリスト教では神の本質をあらわした三位一体に象徴されるように、「3」が正統的な数である一方で、ユングはむしろ3を否定し、「大地を加えなさい」という言い方をして、「4」の強調を曼荼羅の思想へと展開していったことが大切であり、そのことがフロイトの「痕跡しか残さない無意識」とユングの「完備してコンパクトである無意識」との大きな違いを作り出したのだそうです。
とはいえ、それは小難しい抽象的な話ではなく、「現実世界というのはとにかく触れるものだ」ということであり、「3に1を加える」とか「4で表現する」というのは、例えば「母親の乳房にどうやって触れるか」ということなのだとした上で、こう述べています。
「母親のおっぱいに唇が触れたときに、湧き上がっていた欲動がそこでさーっと広がって、まさにキルコル(曼荼羅)なのです。広がっていくときに、その広がりの感覚が、今度は人間の横隔膜の運動につながっていって、顔の表情の筋肉変化をつくり出して、笑うという現象となる。どうも人間的であるということの一番のベースに、その平面の触れ合いの重要性というのがあるのではないかと思うのです。」
今期のかに座もまた、笑いであれおっぱいであれ、こうしたやわらかな、それでいて力強い「触れ合い」ということが、いかに大切であるかということを、改めて実感していきやすいのではないでしょうか。
参考:日本ユング心理学会編『ユング心理学研究第2巻 ユングと曼荼羅』(創元社)
特に、今回の満月を自身の星座で迎えていくかに座の人たちは、以前のように飲み歩いたり、派手に遊んで発散したりという方向には振り切れないし、そこに注いでいたエネルギーをこれまでとはまったく異なる仕方で使っていきたいと感じている人も多いはず。
ここで思い出されるのが、宗教学者の中沢新一は2009年に開催された日本ユング心理学会のシンポジウムでの基調講演「ユングと曼荼羅」で紹介されていた、ユングの「3に1を加え、4で表現しよう」という考え方です。
中沢によれば、キリスト教では神の本質をあらわした三位一体に象徴されるように、「3」が正統的な数である一方で、ユングはむしろ3を否定し、「大地を加えなさい」という言い方をして、「4」の強調を曼荼羅の思想へと展開していったことが大切であり、そのことがフロイトの「痕跡しか残さない無意識」とユングの「完備してコンパクトである無意識」との大きな違いを作り出したのだそうです。
とはいえ、それは小難しい抽象的な話ではなく、「現実世界というのはとにかく触れるものだ」ということであり、「3に1を加える」とか「4で表現する」というのは、例えば「母親の乳房にどうやって触れるか」ということなのだとした上で、こう述べています。
「母親のおっぱいに唇が触れたときに、湧き上がっていた欲動がそこでさーっと広がって、まさにキルコル(曼荼羅)なのです。広がっていくときに、その広がりの感覚が、今度は人間の横隔膜の運動につながっていって、顔の表情の筋肉変化をつくり出して、笑うという現象となる。どうも人間的であるということの一番のベースに、その平面の触れ合いの重要性というのがあるのではないかと思うのです。」
今期のかに座もまた、笑いであれおっぱいであれ、こうしたやわらかな、それでいて力強い「触れ合い」ということが、いかに大切であるかということを、改めて実感していきやすいのではないでしょうか。
参考:日本ユング心理学会編『ユング心理学研究第2巻 ユングと曼荼羅』(創元社)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「取るに足らない歓び」。

日本社会が政治においても経済においても、そして文化においてもここまで行き詰まってしまったことは戦後なかったのではないかと思うほど、今の日本は混迷の極みにあるように感じますが、昨年のしし座の人たちの星回りはどこかでそうした社会の混迷を一身に受けようとしていたところがあったのではないでしょうか。
そんなしし座にとって、2022年最初の満月である1月18日前後のタイミングは、そうした身に受けた混迷と自身の悩みや苦しみがまじりあった精神の行き詰まり状態が、一面を覆う暗雲から一条の光が差し込むように、ほんのわずかでも不意に開けていきやすいタイミングと言えます。
そんな折に思い出されるのが、古今東西のあらゆる哲学者のうちでも、その陰鬱さで突出した人物を二、三挙げろと言われれば、必ずその一角に入るであろうショーペンハウアーの『幸福について』の次のような一節。
「華やかさというものはたいてい、劇場の書き割りのように単なる見せかけであって、本質が欠けている。たとえば、旗や花輪で飾られた船、祝砲、銅鑼や喇叭、歓声や喝采などは、歓びを表す看板であり、暗示であり、象形文字だ。ところが、歓びそのものは多くの場合そこにはない。ご本人だけが祝宴に来ることを辞退した格好だ。歓びが本当に姿を見せるときは、しばしば招かれたわけでもなく、前触れなしに、ひとりで気取らずに静かにやってくる。たいていはありきたりの状況の、取るに足らないごく些細なことで、輝きも晴れがましさもない機会に現われるのだ。」(ショーペンハウアー、『幸福について』、新潮文庫)
彼の哲学においては素朴な陽気さはほとんど居場所がありませんでしたが、とはいえその人生においては、予測できなかった小さな幸福の瞬間が確かにあり、こんな小さな奇跡があることを、ときに彼も目を見開きながら噛みしめていたのかも知れません。
何かと派手好みで、ひときわ存在感を放って衆目を集めることに執心しがちなしし座ですが、今期においては、ショーペンハウアーが述べたようなごく些細で、取るに足らない形で訪れる「歓び」をこそ、大切に迎え入れていきたいところです。
参考:アルトュル・ショーペンハウアー、橋本文夫訳『幸福について』(新潮文庫)
そんなしし座にとって、2022年最初の満月である1月18日前後のタイミングは、そうした身に受けた混迷と自身の悩みや苦しみがまじりあった精神の行き詰まり状態が、一面を覆う暗雲から一条の光が差し込むように、ほんのわずかでも不意に開けていきやすいタイミングと言えます。
そんな折に思い出されるのが、古今東西のあらゆる哲学者のうちでも、その陰鬱さで突出した人物を二、三挙げろと言われれば、必ずその一角に入るであろうショーペンハウアーの『幸福について』の次のような一節。
「華やかさというものはたいてい、劇場の書き割りのように単なる見せかけであって、本質が欠けている。たとえば、旗や花輪で飾られた船、祝砲、銅鑼や喇叭、歓声や喝采などは、歓びを表す看板であり、暗示であり、象形文字だ。ところが、歓びそのものは多くの場合そこにはない。ご本人だけが祝宴に来ることを辞退した格好だ。歓びが本当に姿を見せるときは、しばしば招かれたわけでもなく、前触れなしに、ひとりで気取らずに静かにやってくる。たいていはありきたりの状況の、取るに足らないごく些細なことで、輝きも晴れがましさもない機会に現われるのだ。」(ショーペンハウアー、『幸福について』、新潮文庫)
彼の哲学においては素朴な陽気さはほとんど居場所がありませんでしたが、とはいえその人生においては、予測できなかった小さな幸福の瞬間が確かにあり、こんな小さな奇跡があることを、ときに彼も目を見開きながら噛みしめていたのかも知れません。
何かと派手好みで、ひときわ存在感を放って衆目を集めることに執心しがちなしし座ですが、今期においては、ショーペンハウアーが述べたようなごく些細で、取るに足らない形で訪れる「歓び」をこそ、大切に迎え入れていきたいところです。
参考:アルトュル・ショーペンハウアー、橋本文夫訳『幸福について』(新潮文庫)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「喉元に死者がいる」。

岸田首相の年頭の記者会見で、感染者が急増している新型コロナの変異株「オミクロン株」への対応をめぐり、陽性者全員を一律に入院させる現行の措置を見直し、重症度に応じて自宅療養で対応できるようにとの方針を示しましたが、会見内容を見ていてどこか3.11直後に「がんばろう」や「がんばれ」といった言葉が乱発されていたテレビ放送のことを思い出していました。
狂ったように「がんばれ」と言い続けるのは、言葉をかける側が想像力を失い、また言葉を失っているからで、同様に、現在の政府や官邸周辺もまた未曽有の感染症に対してどう対応していいか分からないだけでなく、そこで生じる二人称の死というものをどう受け止めていいのか分からないがゆえに、ああいう指示の出し方や語り口になってしまうのではないか。そして、それは実は私たち国民の側も同じなのではないでしょうか。
では、どうすればいいのか。例えば、近代日本思想を専門とする中島岳志は、『現代の超克』の中で、ヒンディー語の与格構文という構文に言及しつつ次のように述べています。
「ヒンディー語では、「私は、ヒンディー語を話すことができる」は、「私にヒンディー語がやってきてとどまっている」という言い方をするのです。「私」という主体が言語というものを能力によってマスターし、それによって私が主体的に言語を話しているのではないのです。「私」という器に言葉がやってきて私にとどまっている、という言い方をヒンディー語ではします。/では、言葉はどこからやってくるのか。それは、過去からであり、死者からです。過去や死者からやってきて、私にとどまり、そして私の中を風のように通過してこの口を伝って言葉が出てくる。そうとしか思えない、ということがヒンディー語の中に与格構文として組み込まれています。ヒンディー語を勉強し、そのことを知ったときに、さすがインドだなと思いました。」
中島は、何かを話しているときに慄くときの感覚について「喉元に死者がいる」という言い方もしているのですが、慄くとともに「少しほっとする」のだとも言います。それは、自分がひとり単独の存在ではなく、死者や過去と言葉を通じてつながり、ともに生きていることを感じられたからでしょう。
今期のおとめ座もまた、ふとしたときの言葉のあり方を通じて、そうした「喉元に死者がいる」という感覚や、死者とともに生き、彼らが紡いだ言葉を宿す器になるということがいかに可能なのか、見つめ直してみるべし。
参考:中島岳志、若松英輔『近代の超克』(ミシマ社)
狂ったように「がんばれ」と言い続けるのは、言葉をかける側が想像力を失い、また言葉を失っているからで、同様に、現在の政府や官邸周辺もまた未曽有の感染症に対してどう対応していいか分からないだけでなく、そこで生じる二人称の死というものをどう受け止めていいのか分からないがゆえに、ああいう指示の出し方や語り口になってしまうのではないか。そして、それは実は私たち国民の側も同じなのではないでしょうか。
では、どうすればいいのか。例えば、近代日本思想を専門とする中島岳志は、『現代の超克』の中で、ヒンディー語の与格構文という構文に言及しつつ次のように述べています。
「ヒンディー語では、「私は、ヒンディー語を話すことができる」は、「私にヒンディー語がやってきてとどまっている」という言い方をするのです。「私」という主体が言語というものを能力によってマスターし、それによって私が主体的に言語を話しているのではないのです。「私」という器に言葉がやってきて私にとどまっている、という言い方をヒンディー語ではします。/では、言葉はどこからやってくるのか。それは、過去からであり、死者からです。過去や死者からやってきて、私にとどまり、そして私の中を風のように通過してこの口を伝って言葉が出てくる。そうとしか思えない、ということがヒンディー語の中に与格構文として組み込まれています。ヒンディー語を勉強し、そのことを知ったときに、さすがインドだなと思いました。」
中島は、何かを話しているときに慄くときの感覚について「喉元に死者がいる」という言い方もしているのですが、慄くとともに「少しほっとする」のだとも言います。それは、自分がひとり単独の存在ではなく、死者や過去と言葉を通じてつながり、ともに生きていることを感じられたからでしょう。
今期のおとめ座もまた、ふとしたときの言葉のあり方を通じて、そうした「喉元に死者がいる」という感覚や、死者とともに生き、彼らが紡いだ言葉を宿す器になるということがいかに可能なのか、見つめ直してみるべし。
参考:中島岳志、若松英輔『近代の超克』(ミシマ社)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「偽善より悪」。
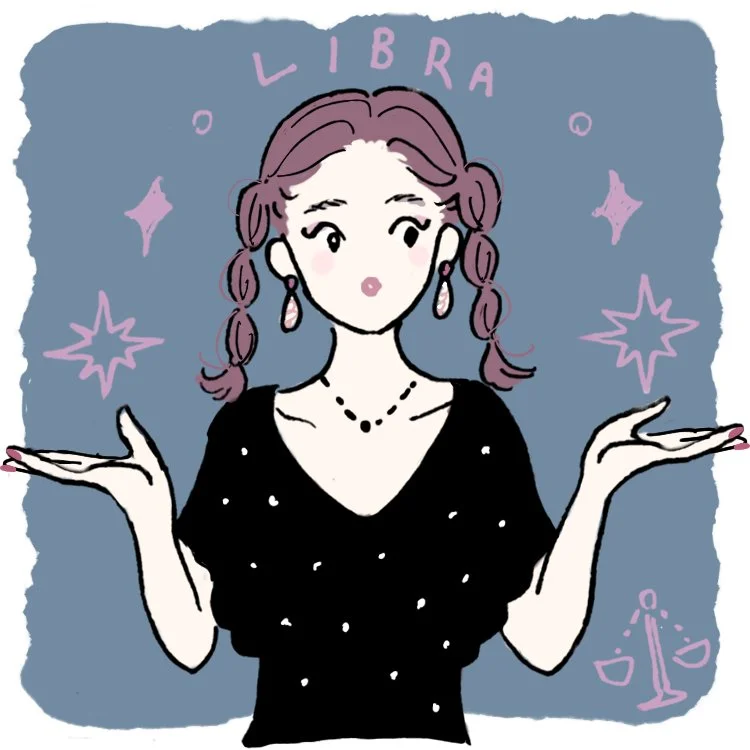
昨年2021年後半は通常の感覚では動機を理解することが難しい凶悪事件が頻発しました。それらは明らかにこれまでとは“質的”に異なっており、単純な厳罰化や表面的な「悪」の捉え方では今後ますます追いつかなくなっていく分岐点にすでに突き当たってしまっているのではないでしょうか。
その意味で、今ほど悪の避けがたさや、悪の複雑性、ないし善悪の不分明さをきちんと考慮に入れた「悪」の思想を先人からくみ上げていく必要のある時機はそうない訳ですが、その参照先として、例えば、大正と昭和の二度にわたって国家弾圧をうけた大本教の教祖であった出口王仁三郎(おにざぶろう)などはピッタリのように思えます。
王仁三郎は、教祖・出口ナオの娘婿であり、ナオの峻厳な善悪二元論を引き継ぎながらも、悪の概念に独自の奥行きと広がりをもたらすことで、教義を再構築させていったのですが、その初期の著作である『裏の神諭』を見ると、王仁三郎が本来の善悪とは表面的な次元では見抜きにくい次元にこそあり、欺きや自己欺瞞によって隠されがちなものとして考えていたことが分かります。
「世の中には化け物が沢山をるので、表面(うわつら)はおとなしい虫も殺さんような顔してをる者が、かえって極悪人で人を殺したり盗人をしたり、いたづらをする世の中である。表面は鬼のような顔して、憎まれ口を言ふ者の心はかえって水晶で、案外正しい人は見かけによらん者と言ふ譬へのままである。それに気が付かずに、今の人民は追従して面前で優しい顔して甘い事を言ふて、媚びへつらふ悪魔は十人好きがする。」
「この世の中のことは何ほど偉そうに言ふても、真の神様より真実(まこと)は判りはせぬ、皆どんぐりの背比べ、お猿の尻笑ひである。神様の御前に出たなれば、誰も彼も罪汚ればかりで、恥ずかしいて人の心がどうじやの、行ひがこうじやのと、人の身の上の事を批判する資格は無いのである。おのれの尻から拭いて、足下を掃除して、おのれに一点の曇りが無いと言ふようになりてから、他人の事を言ふてやらんと聞く人が無いぞ、あつたら口に風を引かさぬが良かろう、この世の偽善者の化け物改心なさい。」
王仁三郎が偽善に対してここまで激しく批判の矛先を向けたのは、おそらくみずからもまた避けられない罪の堆積のしたで苦しんできた経験から、みずからが陥る/陥ったかも知れない悪に対する無自覚が特に許しがたく感じられたからでしょう。
今期のてんびん座もまた、どうしたって「悪」ということと無関係ではいられない自身の身の上を受け入れていくべし。
参考:島薗進編著『思想の身体 悪の巻』(春秋社)
その意味で、今ほど悪の避けがたさや、悪の複雑性、ないし善悪の不分明さをきちんと考慮に入れた「悪」の思想を先人からくみ上げていく必要のある時機はそうない訳ですが、その参照先として、例えば、大正と昭和の二度にわたって国家弾圧をうけた大本教の教祖であった出口王仁三郎(おにざぶろう)などはピッタリのように思えます。
王仁三郎は、教祖・出口ナオの娘婿であり、ナオの峻厳な善悪二元論を引き継ぎながらも、悪の概念に独自の奥行きと広がりをもたらすことで、教義を再構築させていったのですが、その初期の著作である『裏の神諭』を見ると、王仁三郎が本来の善悪とは表面的な次元では見抜きにくい次元にこそあり、欺きや自己欺瞞によって隠されがちなものとして考えていたことが分かります。
「世の中には化け物が沢山をるので、表面(うわつら)はおとなしい虫も殺さんような顔してをる者が、かえって極悪人で人を殺したり盗人をしたり、いたづらをする世の中である。表面は鬼のような顔して、憎まれ口を言ふ者の心はかえって水晶で、案外正しい人は見かけによらん者と言ふ譬へのままである。それに気が付かずに、今の人民は追従して面前で優しい顔して甘い事を言ふて、媚びへつらふ悪魔は十人好きがする。」
「この世の中のことは何ほど偉そうに言ふても、真の神様より真実(まこと)は判りはせぬ、皆どんぐりの背比べ、お猿の尻笑ひである。神様の御前に出たなれば、誰も彼も罪汚ればかりで、恥ずかしいて人の心がどうじやの、行ひがこうじやのと、人の身の上の事を批判する資格は無いのである。おのれの尻から拭いて、足下を掃除して、おのれに一点の曇りが無いと言ふようになりてから、他人の事を言ふてやらんと聞く人が無いぞ、あつたら口に風を引かさぬが良かろう、この世の偽善者の化け物改心なさい。」
王仁三郎が偽善に対してここまで激しく批判の矛先を向けたのは、おそらくみずからもまた避けられない罪の堆積のしたで苦しんできた経験から、みずからが陥る/陥ったかも知れない悪に対する無自覚が特に許しがたく感じられたからでしょう。
今期のてんびん座もまた、どうしたって「悪」ということと無関係ではいられない自身の身の上を受け入れていくべし。
参考:島薗進編著『思想の身体 悪の巻』(春秋社)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「くつを脱げ」。

「運がいい」とは、その人がそのタイミングで立つべき場所にきちんと立っている、ということでもありますが、逆に言えば、私たちは人生を通じてしばしば立つべき場所を見誤るがゆえに運を逃し、場合によっては、どこに立つべきか分からないまま一生を終えることだってそう珍しくないでしょう。
特に、いったん罪を犯してしまったり、貧困に陥ったり、「普通の暮らし」から逸脱してしまった人に、日本社会はなかなか居場所を与えてくれませんし、その傾向は昨今ますます強まっているように感じますが、だからこそ「立つべき場所」ということについて、ここで今一度考えてみたいと思います。
例えば、ユダヤ教・聖書研究者の前島誠は、『不在の神は<風>の中に』の中で、エジプトで殺人を犯した若き日のモーセが遠く離れた地に身を隠し、所帯を持って羊飼いをしていた際、あるときシナイ山の麓で神に呼び止められ、「ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである」と言われたという聖書の一節を引いて、次のように述べています。
「神は燃える「しば」の中にいた。そこに「近づくな」と言う。モーセは足をとめた。神のいる所から距離を置いた。そしてサンダルを脱いだ。そのとき神は言う、「お前の立っているその場所が聖である」と。このくだり、ふしぎな一節だ。/ふつうなら、神の立つ所(燃えるしば)が聖なる場所と考えるだろう。だがそうではなかった。モーセ自身がたつ場所こそ聖であると神は言う。どういうことか。/いかにもいそうな所に、神はいないということだ。いわゆる聖なる匂いのする所、神殿や教会、神社などに神はいない。まさに不在の神である。しかし、人が自らの使命を自覚してしっかり立つとき、神はその場所に触れてくる。モーセがサンダルを脱いだのは、そこが文字通り聖なる場所、すなわち神の臨在する場所だったからだ。」
古代において、サンダルは名誉と誇りのしるしであり、言うならばエゴの象徴でしたから、「くつを脱げ」という神の命令は「まず自分の過去を捨てよ」ということであり、かつての身分やいい暮らしが忘れられないモーセに中途半端にしがみついている体裁や立場から脱却して、それとは裏腹の現実を受容せよ、という意味があったのかも知れません。
今期のさそり座もまた、みずからの立つべき場所に立つためにも、そうした意味での「くつを脱ぐ」ということを試みてみるといいでしょう。
参考:前島誠『不在の神は<風>の中に』(春秋社)
特に、いったん罪を犯してしまったり、貧困に陥ったり、「普通の暮らし」から逸脱してしまった人に、日本社会はなかなか居場所を与えてくれませんし、その傾向は昨今ますます強まっているように感じますが、だからこそ「立つべき場所」ということについて、ここで今一度考えてみたいと思います。
例えば、ユダヤ教・聖書研究者の前島誠は、『不在の神は<風>の中に』の中で、エジプトで殺人を犯した若き日のモーセが遠く離れた地に身を隠し、所帯を持って羊飼いをしていた際、あるときシナイ山の麓で神に呼び止められ、「ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである」と言われたという聖書の一節を引いて、次のように述べています。
「神は燃える「しば」の中にいた。そこに「近づくな」と言う。モーセは足をとめた。神のいる所から距離を置いた。そしてサンダルを脱いだ。そのとき神は言う、「お前の立っているその場所が聖である」と。このくだり、ふしぎな一節だ。/ふつうなら、神の立つ所(燃えるしば)が聖なる場所と考えるだろう。だがそうではなかった。モーセ自身がたつ場所こそ聖であると神は言う。どういうことか。/いかにもいそうな所に、神はいないということだ。いわゆる聖なる匂いのする所、神殿や教会、神社などに神はいない。まさに不在の神である。しかし、人が自らの使命を自覚してしっかり立つとき、神はその場所に触れてくる。モーセがサンダルを脱いだのは、そこが文字通り聖なる場所、すなわち神の臨在する場所だったからだ。」
古代において、サンダルは名誉と誇りのしるしであり、言うならばエゴの象徴でしたから、「くつを脱げ」という神の命令は「まず自分の過去を捨てよ」ということであり、かつての身分やいい暮らしが忘れられないモーセに中途半端にしがみついている体裁や立場から脱却して、それとは裏腹の現実を受容せよ、という意味があったのかも知れません。
今期のさそり座もまた、みずからの立つべき場所に立つためにも、そうした意味での「くつを脱ぐ」ということを試みてみるといいでしょう。
参考:前島誠『不在の神は<風>の中に』(春秋社)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「悪のリアリティ」。

いまの時代はアカデミズムを始めとして、人びとがますます近代実証主義の枠から外れたことを扱うのが苦手になってしまっていて、そうすると人間の体験知のごく一部が守備範囲になりますから、良くも悪くも超越的なものに遭遇したり、目に見えない世界に接することに無自覚になってしまったように思います。
そうした現代社会が陥っている傾向について、作家の佐藤優と美学者の高橋巌は二人の対談本である『なぜ私たちは生きているのか』のなかで、「悪のリアリティに鈍感になっている」という言い方で指摘していました。それは個人の内面だけでなく、宇宙全体のなかにも悪の要素というのは働いていて、それが出会いや縁など人間関係にも作用しているということなのですが、これは具体的な文脈でないとなかなか伝わらないでしょう。以下に二人のやりとりを少し引用してみましょう。
「佐藤 ちょっとした会話から悪が生まれ、それによって人間が変わってしまう。言葉というのは怖いものなのです。聖書にも、何を食べたら罪になるかを心配している弟子に、イエスが食べ物は心配ない、口から出るものが問題だと伝える場面があります。悪は言葉から出てくるけれど、人間は言葉なくして生きていくことができない。でも善も、言葉から生まれてくるわけです。キリスト教的には「なぜあなたは生きているのか」という問いには「神の言葉によって生きている」という答えになる。最終的には言葉の問題です。
高橋 悪を通して善を実現することは、私にとっての大問題なのです。(…)「悪を通して」を「限界状況を通して」とも言えるのではないでしょうか。いずれにしても、最終的には言葉の問題だということはよくわかります。この言葉の問題は召命でもあるのですね。
佐藤 そうです。突然やってくる召命に対して応えるか拒否するか、言葉で対応するしかありませんから。ただ言葉を重視するというのは、西側の考え方ではあるのです。言語ではないやり方では瞑想というのがありますが、自意識が肥大化している状態であるのに悟りを得たと勘違いしてしまう危険性があります。これでは、言語化しても私的言語になってしまう。ヴィトゲンシュタインが言ったように、私的言語では成立しません。二人以上の人がいて、一定の共同主観性のあるなかでしか言語は成立しえないですから。
高橋 言葉は共同主観性のなかでしか成立しない、つまり共同体がなければ成立しないということを大切にしたいと思います。ヨハネ福音書の冒頭に、「言(ことば)のうちに命があった」とありますね。命のなかには善だけでなく悪が入っている。だから言葉によって神が現われたり、悪魔が現われたりもする。」
つまり、困難で命がけの状況になればなるほど、自分ひとりでいるのではなく、他者と共にいるということが重要になり、他者との関係性の中にこそ悪があり、逆に言えば神様がいるのだということ。これは今期のいて座にとっても大切な留意点となっていくはずです。
参考:佐藤優、高橋巌『なぜ私たちは生きているのか』(平凡社新書)
そうした現代社会が陥っている傾向について、作家の佐藤優と美学者の高橋巌は二人の対談本である『なぜ私たちは生きているのか』のなかで、「悪のリアリティに鈍感になっている」という言い方で指摘していました。それは個人の内面だけでなく、宇宙全体のなかにも悪の要素というのは働いていて、それが出会いや縁など人間関係にも作用しているということなのですが、これは具体的な文脈でないとなかなか伝わらないでしょう。以下に二人のやりとりを少し引用してみましょう。
「佐藤 ちょっとした会話から悪が生まれ、それによって人間が変わってしまう。言葉というのは怖いものなのです。聖書にも、何を食べたら罪になるかを心配している弟子に、イエスが食べ物は心配ない、口から出るものが問題だと伝える場面があります。悪は言葉から出てくるけれど、人間は言葉なくして生きていくことができない。でも善も、言葉から生まれてくるわけです。キリスト教的には「なぜあなたは生きているのか」という問いには「神の言葉によって生きている」という答えになる。最終的には言葉の問題です。
高橋 悪を通して善を実現することは、私にとっての大問題なのです。(…)「悪を通して」を「限界状況を通して」とも言えるのではないでしょうか。いずれにしても、最終的には言葉の問題だということはよくわかります。この言葉の問題は召命でもあるのですね。
佐藤 そうです。突然やってくる召命に対して応えるか拒否するか、言葉で対応するしかありませんから。ただ言葉を重視するというのは、西側の考え方ではあるのです。言語ではないやり方では瞑想というのがありますが、自意識が肥大化している状態であるのに悟りを得たと勘違いしてしまう危険性があります。これでは、言語化しても私的言語になってしまう。ヴィトゲンシュタインが言ったように、私的言語では成立しません。二人以上の人がいて、一定の共同主観性のあるなかでしか言語は成立しえないですから。
高橋 言葉は共同主観性のなかでしか成立しない、つまり共同体がなければ成立しないということを大切にしたいと思います。ヨハネ福音書の冒頭に、「言(ことば)のうちに命があった」とありますね。命のなかには善だけでなく悪が入っている。だから言葉によって神が現われたり、悪魔が現われたりもする。」
つまり、困難で命がけの状況になればなるほど、自分ひとりでいるのではなく、他者と共にいるということが重要になり、他者との関係性の中にこそ悪があり、逆に言えば神様がいるのだということ。これは今期のいて座にとっても大切な留意点となっていくはずです。
参考:佐藤優、高橋巌『なぜ私たちは生きているのか』(平凡社新書)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「猥褻」。

いまや社会で生きていく上で資本主義の影響を否定する人間はほとんどいないでしょう。というより、私たちは資本主義こそが唯一の存続可能な政治・経済的制度であるということを疑いもしないどころか、その代わりになるような代替物を想像することさえ不可能になってしまっているように思います。
そう考えると、資本主義というのは、いつまでたっても解けない呪いのようでもありますが、少なくともその起源となった時代を思い返していくことは可能であるはずです。日本の場合、それは戦後の高度経済成長期がひとつの大きな転換期になった訳ですが、例えば三島由紀夫は高度経済成長期に一歩踏み出し始めた1954年からの二年間を舞台にした小説『鏡子の家』を書いており、この作品について「時代を描こうと思った」と述べています。
主人公である資産家の令嬢・鏡子は夫と別居し、8歳の娘と実家の財産を切り崩しながら自由気ままに暮らすまだ三十女ですが、彼女の家には年下の四人の若者が日々集まり、いずれもそれぞれの仕方で時代の「壁」のようなものに直面していると感じて、どこかに虚無感を抱えています。
4人はその後まさに栄枯盛衰を地でいく波乱万丈な人生を歩んでいくのですが、ここではその詳細は省くとして、最後にすっかり財産を使い尽くし、夫が帰ってくることになったところで、「人生という邪教」を生きる覚悟をあらためて固めた鏡子の選択を象徴するようなセリフをひとつ引用しておきたいと思います。
「神聖なものほど猥褻だ。だから恋愛より結婚のほうがずっと猥褻だ。」
猥褻というのは、みだらな想いで心がかき乱れ、汚れて穢れていることを表す言葉ですが、この一文は何よりも、昭和二十年代の戦後の焼け跡や廃墟の光景を、暴力的なまでの圧力で葬り去り、自身の内面や記憶までも否応なく塗り替えて行こうとしていた日本人に向けられた、三島なりの痛烈な批判だったのではないでしょうか。
今期のやぎ座は、そんなかつての日本人の心の動きとそれに向けられた三島の批判の両方に、いまの自分自身の状況を重ねてみるといいかも知れません。
参考:三島由紀夫『鏡子の家』(新潮文庫)
そう考えると、資本主義というのは、いつまでたっても解けない呪いのようでもありますが、少なくともその起源となった時代を思い返していくことは可能であるはずです。日本の場合、それは戦後の高度経済成長期がひとつの大きな転換期になった訳ですが、例えば三島由紀夫は高度経済成長期に一歩踏み出し始めた1954年からの二年間を舞台にした小説『鏡子の家』を書いており、この作品について「時代を描こうと思った」と述べています。
主人公である資産家の令嬢・鏡子は夫と別居し、8歳の娘と実家の財産を切り崩しながら自由気ままに暮らすまだ三十女ですが、彼女の家には年下の四人の若者が日々集まり、いずれもそれぞれの仕方で時代の「壁」のようなものに直面していると感じて、どこかに虚無感を抱えています。
4人はその後まさに栄枯盛衰を地でいく波乱万丈な人生を歩んでいくのですが、ここではその詳細は省くとして、最後にすっかり財産を使い尽くし、夫が帰ってくることになったところで、「人生という邪教」を生きる覚悟をあらためて固めた鏡子の選択を象徴するようなセリフをひとつ引用しておきたいと思います。
「神聖なものほど猥褻だ。だから恋愛より結婚のほうがずっと猥褻だ。」
猥褻というのは、みだらな想いで心がかき乱れ、汚れて穢れていることを表す言葉ですが、この一文は何よりも、昭和二十年代の戦後の焼け跡や廃墟の光景を、暴力的なまでの圧力で葬り去り、自身の内面や記憶までも否応なく塗り替えて行こうとしていた日本人に向けられた、三島なりの痛烈な批判だったのではないでしょうか。
今期のやぎ座は、そんなかつての日本人の心の動きとそれに向けられた三島の批判の両方に、いまの自分自身の状況を重ねてみるといいかも知れません。
参考:三島由紀夫『鏡子の家』(新潮文庫)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「女児のよう」。

ここのところ、介護や育児などの現場への見直しと並行して、従来の男性優位社会で推し進められてきた、正しいか正しくないかを知的な論理によって構築する「正義の倫理」に対し、他者との触れ合いの中で生まれる感情を重視する「ケアの倫理」に何かと注目が集まり、また称揚されつつある動きがあります。
ただ、そうした動きはもともとアメリカのフェミニストであるキャロル・ギリガンら海外の理論家から出てきた議論だったため、日本においても現状では海外の議論やその背景となる文学や社会情勢の流れを踏襲したものがほとんどであるように思います。
一方で、他者への繊細な「心づかい」を大切にする日本の伝統的な考え方は、もともと自律的な個人の立場に立つ「正義の倫理」よりも、他者との関係性の中で動く「ケアの倫理」の方に親和性が高いのではないでしょうか。
例えば、日本におけるケアの倫理の原形をかたどった人物のひとりに江戸後期の国学者である本居宣長がいます。宣長は、当時は諸説あって定かではなかった源氏物語の作者・紫式部のことや、物語の概要について「もののあはれ」の観点から論じたものなのですが、その中で光源氏ら物語の男たちが「何事にも心弱く未練にして、男らしくきつとしたる事はなく、ただ物はかなくしどけなく愚か」であって「其の心ばへ女童のごとく」ではないかという問いに対し、みずから次のように答えています。
「おおよそ人の本当の心というものは、女児のように未練で愚かなものである。男らしく確固として賢明なのは、本当の心ではない。それはうわべを繕い飾ったものである。本当の心の底を探ってみれば、どれほど賢い人もみな女児と変わらない。それを恥じて隠すか隠さないかの違いだけである。」
男らしさとされているものは、うわべを飾っているだけで「本当の心(実の情)」ではなく、女性性こそが人間の本質であるという私的は、現代においてフェミニズムの中から出てきた「ケアの倫理」とまさに一致するところであり、驚くべき先見性と言えます。
今期のみずがめ座もまた、人間の本質たる女性性(女児のさが)を大切に、うわべを飾るための男性性(それもとても重要な要素である)とのバランスをいかにとっていけるか、ということを改めて自身の指針にしていくといいでしょう。
参考:本居宣長、子安宣邦校注『紫文要領』(岩波文庫)
ただ、そうした動きはもともとアメリカのフェミニストであるキャロル・ギリガンら海外の理論家から出てきた議論だったため、日本においても現状では海外の議論やその背景となる文学や社会情勢の流れを踏襲したものがほとんどであるように思います。
一方で、他者への繊細な「心づかい」を大切にする日本の伝統的な考え方は、もともと自律的な個人の立場に立つ「正義の倫理」よりも、他者との関係性の中で動く「ケアの倫理」の方に親和性が高いのではないでしょうか。
例えば、日本におけるケアの倫理の原形をかたどった人物のひとりに江戸後期の国学者である本居宣長がいます。宣長は、当時は諸説あって定かではなかった源氏物語の作者・紫式部のことや、物語の概要について「もののあはれ」の観点から論じたものなのですが、その中で光源氏ら物語の男たちが「何事にも心弱く未練にして、男らしくきつとしたる事はなく、ただ物はかなくしどけなく愚か」であって「其の心ばへ女童のごとく」ではないかという問いに対し、みずから次のように答えています。
「おおよそ人の本当の心というものは、女児のように未練で愚かなものである。男らしく確固として賢明なのは、本当の心ではない。それはうわべを繕い飾ったものである。本当の心の底を探ってみれば、どれほど賢い人もみな女児と変わらない。それを恥じて隠すか隠さないかの違いだけである。」
男らしさとされているものは、うわべを飾っているだけで「本当の心(実の情)」ではなく、女性性こそが人間の本質であるという私的は、現代においてフェミニズムの中から出てきた「ケアの倫理」とまさに一致するところであり、驚くべき先見性と言えます。
今期のみずがめ座もまた、人間の本質たる女性性(女児のさが)を大切に、うわべを飾るための男性性(それもとても重要な要素である)とのバランスをいかにとっていけるか、ということを改めて自身の指針にしていくといいでしょう。
参考:本居宣長、子安宣邦校注『紫文要領』(岩波文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「<私>への救済と<私>からの救済」。
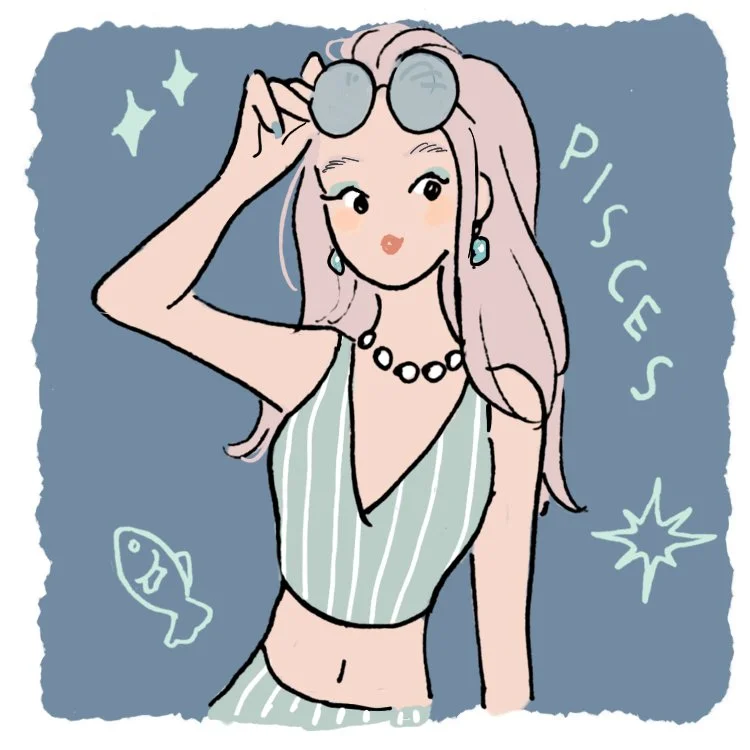
占いという職業柄、普段から何かと「自分らしい人生を送りたい」「私にしかできないことを仕事にしたい」「私に与えられた使命を教えてください」といった生の声に接する機会が多いように思います。
どれもわたし、わたし、わたし、という叫びにも似た声に感じるのですが、こうした「私を生きるとは、私を仕上げて完成させる、ないし実現させることである」という考え方はたぶんにキリスト教(プロテスタント)的なものであり、哲学者の山内志朗は『小さな倫理学入門』において、そうした考えをどこまでも自己・個体の根底にあるものに帰着し、そうすることで救われようとする「<私>への救済」と呼んでいます。
山内はこうした「<私>への救済」と対比する形で、自己の滅却や輪廻からの脱出を願ったり、「「ピンピンコロリ」を願」って「寺社に参詣する」老人のような仏教に典型的な<私>から遠ざかるベクトルにおいて展開される思想を「<私>からの救済」と呼び、この二つをきちんと分けて考えることの重要性を指摘しています。
日本社会というのは、伝統的に後者の「<私>への救済」ということを社会の根底に据えてきたところがありますが、それはともすると「<私>というのは、世界から切除されるべき腫瘍に似ている」という極端な考えと結びつきがちであり、それは冒頭のような声を
真っ向から否定する無言の圧力となり、多くの人が感じている“生きづらさ”にも繋がっているのではないでしょうか。その点について、山内は次のようにも書いています。
「絶えざる苦しみにありながら、生を続ける者もあれば、一時の苦しみから生を絶つ者もいます。/人生とは何なのでしょうか。苦の多寡、喜びの有無は、そこでは肝要ではありません。比較などは成り立たず、死しか心にないでしょう。<私>とは治療されるべき病であると考える者に、「生命・個人の尊厳」や「生命の喜び」や「存在の意味」を説く者は愚かであるように思います。岬の先端に立って、ためらう人間を後ろから突き飛ばす行為に似ていないのでしょうか。/哲学もまた、<私>への救済と、<私>からの救済という二つのベクトルを合わせ含んでいると思います。」
そう、この二つのベクトルは二者択一を迫られるべきものではなく、事あるごとに「合わせ含」むことによって、少しずつ<私>を救っていくものであるはず。
今期のうお座もまた、そのどちらか一方に偏るのではなく、いかに自分に欠けがちなもう一方の思想を受け入れていけるかということに、改めて思いを寄せていきたいところです。
参考:山内志朗『小さな倫理学入門』(慶応義塾大学出版)
どれもわたし、わたし、わたし、という叫びにも似た声に感じるのですが、こうした「私を生きるとは、私を仕上げて完成させる、ないし実現させることである」という考え方はたぶんにキリスト教(プロテスタント)的なものであり、哲学者の山内志朗は『小さな倫理学入門』において、そうした考えをどこまでも自己・個体の根底にあるものに帰着し、そうすることで救われようとする「<私>への救済」と呼んでいます。
山内はこうした「<私>への救済」と対比する形で、自己の滅却や輪廻からの脱出を願ったり、「「ピンピンコロリ」を願」って「寺社に参詣する」老人のような仏教に典型的な<私>から遠ざかるベクトルにおいて展開される思想を「<私>からの救済」と呼び、この二つをきちんと分けて考えることの重要性を指摘しています。
日本社会というのは、伝統的に後者の「<私>への救済」ということを社会の根底に据えてきたところがありますが、それはともすると「<私>というのは、世界から切除されるべき腫瘍に似ている」という極端な考えと結びつきがちであり、それは冒頭のような声を
真っ向から否定する無言の圧力となり、多くの人が感じている“生きづらさ”にも繋がっているのではないでしょうか。その点について、山内は次のようにも書いています。
「絶えざる苦しみにありながら、生を続ける者もあれば、一時の苦しみから生を絶つ者もいます。/人生とは何なのでしょうか。苦の多寡、喜びの有無は、そこでは肝要ではありません。比較などは成り立たず、死しか心にないでしょう。<私>とは治療されるべき病であると考える者に、「生命・個人の尊厳」や「生命の喜び」や「存在の意味」を説く者は愚かであるように思います。岬の先端に立って、ためらう人間を後ろから突き飛ばす行為に似ていないのでしょうか。/哲学もまた、<私>への救済と、<私>からの救済という二つのベクトルを合わせ含んでいると思います。」
そう、この二つのベクトルは二者択一を迫られるべきものではなく、事あるごとに「合わせ含」むことによって、少しずつ<私>を救っていくものであるはず。
今期のうお座もまた、そのどちらか一方に偏るのではなく、いかに自分に欠けがちなもう一方の思想を受け入れていけるかということに、改めて思いを寄せていきたいところです。
参考:山内志朗『小さな倫理学入門』(慶応義塾大学出版)
--------無料占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ