-

【SUGARさんの12星座占い】<9/19~10/3>の12星座全体の運勢は?
「月を呑む」
10月1日は「仲秋の名月」です。旧暦8月15日の夜に見えるまあるい月のことを、昔から「月見る月はこの月の月」といって心待ちにされてきました。
厳密には正確に満月となるのは10月2日の早朝ですが、十五夜の翌日は「十六夜(いざよい)」、前日の月は「待宵(まつよい)」としていずれも大切にされ、その際、月に照らされていつもより際立って見える風景や、月を見ることでやはり美しく照り映える心の在り様のことを「月映え(つきばえ)」と言いました。
そして、そんな今回の満月のテーマは「有機的な全体性」。すなわち、できるかぎりエゴイズムに毒されず、偏った見方に陥らないような仕方で、内なる世界と外なる現実をひとつのビジョンの中に結びつけ、物事をクリアに見通していくこと。
ちなみに江戸時代の吉原では、寿命が延びるとして酒を注いだ杯に十五夜の月を映して飲んでいたのだとか。どうしても手がふるえてしまいますから、水面にまるい月を映すことは難しかったはずですが、綺麗なビジョンを見ようとすることの困難もそれとどこか相通じているように思います。ただ、透き通った光を飲み干すと、昔の人は何か説明のできない不思議な力が宿ったように感じたのかも知れません。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「エウ・フェーミアー」。
古代ギリシャ語には「エウ・フェーミアー」という言葉があり、「よき前兆を告げること」「吉兆の告知」というほどの意味で使われる一方で、「畏れ慎んで黙ること」「沈黙」の意味を持っていました。
例えば、アイスキュロスの悲劇オレステイア三部作の最終部「恵みの女神たち」の大団円では、復讐の女神たちがその憤怒をアテーナー女神にようやくなだめられ、今後アテネの都市にとって恵みの女神になることを約束し、市内の祭祀の中心地である地下の洞窟に移り住みます。それをアテネの市民たちが老若男女問わず、歌い舞いながら送るのですが、その祝祭の行進の場面で、先導の者たちが女神たちに次のように出発を促すのです。
「―さて、お越しを、荒ぶる女神がた、夜より産まれた産まずの御子たち、賑わい競う楽の音に送られて、どうかお立ちを。喜んでお伴をつとめましょう。
静粛にされよ、国びとら。
―地の下の聖なる奥処にあって、礼拝と供物を手厚く享けられることになりましょう。
静粛にされよ、街びとあまねく。」
ここで「静粛にされよ」と訳された箇所が、先の動詞「エウ・フェーミアー」の命令形であり、<畏れ慎んで沈黙せよ>とも、<神聖な沈黙を守れ>とも訳せるのですが、さらにこの言葉には<吉兆に応えて歓呼する>という意味も持ち、恐らくこれら3つの意味は挙げた意味の順番に変わっていくのでしょう。
つまり、ここでは<沈黙>という所作こそが神託=ビジョンを招きもたらすことに等しく、吉と出るか凶と出るかの分岐の上で普通なら声をあげてしまいがちなところを、じっと耐えてできる限り平静を保とうとすることこそが、<傲慢(ヒュブリス)>を抑える唯一の方法だったのかも知れません。
同様に、今期のおひつじ座もまた肝心な場面でこそ沈黙を守れるかどうかが問われていくことになるでしょう。
参考:アイスキュロス、高津春繁訳『ギリシア悲劇〈1〉アイスキュロス 』(ちくま文庫)
-

今期のおうし座のキーワードは、「偶然をめぐる感情」。
「私が生れたよりももつと遠いところへ。そこではまだ可能が可能なままであつたところへ」
これは哲学者の九鬼周造が、別の自分でもありえたのかもしれないという人生の根底でうごめく感情について表したもの。それは幾つになっても、いや年齢を重ねれば重ねるほど、不意に頭をもたげてくるものなのではないでしょうか。
例えば、重い病気にかかったり、不幸な事故の渦中にたたき落とされたりした時も、人は同じ感情に浸され、病や事故に遭わない人生もありえたはずなのに、なぜよりによってこんな目に遇わなければいけなかったのかと、問いを発していく。
<わたし>を襲った偶然への問い。それは答えようのない問いではありますが、それを問うことで、人は偶然の折り重なりとしての<わたし>という感覚を深め、さらにそこでもうひとつ、別の偶然が折り重なることに気付くのです。
それは、たがいに見知らぬ人同士の偶然の出会いが、家族との必然の関係に劣らず、ときに人生を大きく左右してしまうことがあるということ。そしてそうした決定的な意味を持った偶然的出来事を人は「運命」と呼ぶ訳ですが、それもやはり偶然に襲われることで初めて<わたし>に訪れるのです。
ここで冒頭の一文に続く文章を、もう少し前から引用しておきたい。
「今日ではすべてが過去に沈んでしまつた。そして私は秋になつてしめやかな日に庭の木犀の匂を書斎の窓に嗅ぐのを好むようになつた。私はただひとりでしみじみと嗅ぐ。そうすると私は遠い遠いところへ運ばれてしまう。」
今期のおうし座もまた、どこまでがただの偶然で、どこからが運命だったのか、しみじみと九鬼の言い表した感情に浸ってみるといいでしょう。
参考:九鬼周造『九鬼周造随筆集』(岩波文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「幸福論」。
20世紀を過ぎて、アリストテレスから近代のモラリストたち、そして功利主義まで伝統的に書き継がれてきた幸福論はぱたりと書かれなくなり、代わりに不幸論や苦悩論が盛んに書かれるようになりました。
ナチスに協力した一般人の心理的傾向を研究した、ドイツ出身のユダヤ人思想家アドルノなどは「アウシュビッツのあとで詩を書くことは野蛮である」とまで書いた訳ですが、確かに、おいしいものを食べるのであれ、愛する人と心ゆくまで肌を重ねるのであれ、陶酔の後には必ず倦怠が訪れ、幸福とは束の間しか続かないかりそめのものであり、むしろ不幸なときに養われる一つの幻想、実体のないイメージに過ぎないのだとも言えます。
ただ、一方で日本の歌人・劇作家の寺山修司(1935~1983)は「幸福の相場を下落させているのは、幸福自身ではなく、むしろ幸福という言葉を軽蔑している私たち自身にほかならない」と言い、さらに「幸福が終わったところからしか『幸福論』がはじまらないのだとしたら、それは何と不毛なものであることだろう」と続けたのです。
イメージであっても、一瞬であったとしても、それでもいいではないか。幸福について考える時ほど、自分を時のなかを漂い、流れゆく存在であることを痛いほど思い知らされることはない。だからこそ、一瞬しか訪れることのない幸福のイメージを、私たちは自分の手で豊かに膨らませていかなければならないのではないか。寺山の言葉は、そんな風に語りかけているように思います。
「幸福について語るとき位、ことばは鳥のように自分の小宇宙をもって、羽ばたいてほしかった。せめて、汽車の汽笛ぐらいのはげましと、なつかしさをこめて。」
今期のふたご座もまた、みずからに訪れた幸福や、これから掴み取りたい幸福について、縦横に語りあい、またひとりそのイメージをしんしんと、たおやかに広げていきたいところです。
参考:寺山修司『幸福論』(角川文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「おのれをほどく」。
もはや「自己実現」という言葉は、就活を控えた大学生から定年を迎えた後のお年寄りまで、あらゆる年代で当たり前のように使われるようになってきました。
自分をさらに自分らしく。自分と社会やこの世界との結びつきをしっかりとした、ゆるぎないものにしていきたいという志向性は、確かに人生をある目的に向かって、意味のあるものにしていきたいと願う人にとっては最優先されるべきものと言えるかも知れません。
しかし一方で、自分というものから解き放たれたい、特定の目的や役割とかたく結びついてしまった自分を解除してしまいたい思うこともあるのではないでしょうか。
例えばパリに生まれた詩人ボードレールは、匿名の人間として群衆のなかをひとり、ぶらぶら歩きする愉しみを「群衆に沐浴(ゆあみ)する」と表現しました。
そうした群衆のなかにあって、自分という囲いを外し、通りかかる未知のものにみずからをそっくり与えてしまう快楽を、次のように述べてみせたのです。
「群衆とたやすく結婚する者は、金庫のように閉ざされたエゴイストや、軟体動物のように殻に閉じこもった怠け者などには永久に与えられることのないような、熱烈な享楽を知るのである。彼は、めぐり合せが提示してくれる職業のすべて、歓びのすべて、悲惨のすべてを、自らのものとして受け入れる」
確かに、あまり意味のあることばかりしていると、移ろいやすいもの、傷つきやすいもの、滅びやすいものが眼に入らなくなるという意味で、それしかできないというのは無能力の証なのかも知れません。
今期のかに座もまた、自分を閉じるのではなく開くことがテーマとなっているのだと言えます。そのためにも、たまには街を無目的にぶらぶら歩いて、その道すがら、未知のものの感触に自分を委ねてみるのもそう悪いことではないでしょう。
参考:ボードレール、阿部良雄訳『ボードレール全詩集〈2〉』(ちくま文庫)
-

今期のしし座のキーワードは、「魂を確かめる」。
コロナ禍によって、街での他者との、あるいは異物との密な接触の機会が回避されるようになったと言われていますが、こうした傾向はじつは随分前から既に社会全般で見られるようになっています。
例えばスーパーなどで売られている商品は透明なラップや包装にますます包まれ、また、携帯電話やインターネット、動画サイトなど、他者とのコミュニケーションや情報の取得も間接的なものの割合がずっと大きくなっており、いつの間にか「被膜ごし」にしか出来事や他者に触れられなくなってしまった私たちは、傷つくことをひどく恐れるようになっただけでなく、直接<触れる>ことの価値や豊かさをすっかり見失ってしまったように思います。
フランスの哲学者ミシェル・セールは、皮膚という表層の効果として<内部>ということを捉えました。つまり、皮膚と皮膚が接触するところに<魂>が生まれるのであり、唇をかみしめ、額に手を当て、手と手を合わせ、括約筋を締めることでそれは初めて可能になるのだと。さらにセールによれば、他人の皮膚との接触は「魂のパスゲーム」を意味し、皮膚を通して<魂>をさらすゲームの中でこそ、人は自分の存在そのものに触れていくことができるのだと。セールは次のように語りかけます。
「もし君が身を救いたいと思うならば、君の皮膚を危険にさらしなさい」
もちろん、皮膚を危険にさらせば、必ずどこかで傷を負うことになるでしょう。けれど、そうして負った傷の分だけ、確かに<わたし>は存在していると言えるのではないでしょうか。
同様に、今期のしし座もまた、ゆっくりと真綿で絞めつけるように<わたし>を消していこうとする被膜を思いきって引き裂き、誰か何かに直接触れてみること。あるいは、何かのきっかけで疼きだした傷のなかで、みずからが生きて在ることを確かに感じとっていくことになるはず。
参考:ミシェル・セール、米山親能訳『五感―混合体の哲学』(法政大学出版)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「新しさの根源」。
今ときめいているどんなものも、いずれ必ず輝きを失っていく。その意味では、この世のすべては現れては消えゆく泡沫のようなものであり、本当に決定的と言えるものは存在しない。そんな感覚が日常化しているのが今の社会なのだと言えるのではないでしょうか。
ドイツの批評家・思想家のベンヤミンは1939年に書いた「セントラルパーク」という断章集のなかで、既に唯一の例外をのぞいて、現代社会には本当に新しいものは何も残されていないのだと書いていました。
「いまの人間にとって、根本的に新しいものはひとつしかない。それはつねに同じ新しいもの、つまり死である。」
そう、<新しさ>というのは取り換えや買い替えのきくものを通して、ほんの一瞬だけ経験することのできるものであり、それは過去との縁を断ち切り、自分をちゃらにするという意味で、死の疑似体験とも言えるのかも知れません。
死というのは、人間の意志と理解を超えた向こうからやってくる出来事です。ですから、人間にとって死は絶対的に不可解なものであり、恐れと同時にどこか気になって仕方のないものでもあります。
そうだとすると、死の疑似体験としての<新しさ>とは、すなわちこの不可解を思い出すことであり、自身の根源的な無知に立ち戻るということでもあるはずです。
今期のおとめ座もまた、服を買い替えるとか、メイクやプロフィール画像を変えるといったありきたりの仕方で自分を新しくするのではなく、<新しさ>を突き詰めた先で人が必ず行き着くであろう大いなる謎の前で立ち尽くし、そこで自分の存在が根底から一新されていくのを感じていきたいところです。
参考:ヴァルター・ベンヤミン、浅井 健二郎・久保 哲司訳『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』(ちくま文庫)
-

今期のてんびん座のキーワードは、「誰かへの贈り物」。
占いをしていると、「自分探し」や「自己実現」に本気で取り組みたいのだと言う人の話を見聞きすることがあります。
ただ、自分はどんな風に歩いているんだろうと考え始めると途端に足がもつれて、それまでのように自然に歩けなくなってしまうように、“本当の自分”などというものは本気で探しだすほどにますます見えなくなっていくもの。であり、場合によっては、普段なら蓋をしている自分のみっともないところや情けない点をこれでもかと突きつけられて、なんとも惨めな気分になるものです。
一方で、それと対極的なところに自分の在り処を指し示してくれるのが、キルケゴールの次のような言葉です。
「何に対してじぶんがじぶんであるかという、その関係の相手方が、つねにじぶんを測る尺度となる」
そうか、自分はどんなに情けない人間であろうとも、自分が気にかけ、心のうちに住まわせている人が立派であるなら、それでいいんだ、と。この言葉に励まされる人も多いのではないでしょうか。
べつにじぶんは「偉い人」である必要はなく、それどころか一匹の動物であっても構わない。じぶんというのはきっと、他人に贈られるものなのです。例えば、傷ついた他人の顔を鏡にして初めて傷つけた自分の顔やその表情に気付くように。
そして今期のてんびん座もまた、自分が誰に対しての贈り物なのかを改めて痛感していくことになるはず。できることなら、命令や打算ではなく、憧れによって自分を捧げていきたいところです。
参考:キルケゴール、訳『死に至る病』(岩波文庫)
-

今期のさそり座のキーワードは、「やるべき仕事」。
「それをはじめた者がまた最もよくそれを仕上げうる者であるような仕事が世にあるとすれば、それこそ私のやっている仕事なのである」
これは「われ思う、ゆえにわれ在り」の言葉で知られる17世紀フランスの哲学者デカルトが『方法序説』に書いた一節。「石の上にも三年」という言葉がもはや時代遅れになりつつある現代からすれば、羨ましさを通り越して圧倒されるような凄味があります。
デカルトがここで取り掛かっている仕事というのは“学問の改造”でしたが、同時に彼の野心でもありました。それは、この文章を学者仲間だけで通用するラテン語ではなく、普通の一般民衆が普段使っているフランス語で書くという試みをした点にもよく表れています。
その後フランス文学が「明晰かつ判明」を指標とするようになったのは、デカルトの影響が大きいとも言われているのですから、彼の試みは成功したのだと言えるでしょう。
もちろん、自分以外の人には不可能な仕事というのはそうそうあるものではありません。むしろ、別に自分じゃなくたっていいんじゃないかという思いが、職場で一度もよぎったことのない人などいないはずですし、そうした虚しさ、寂しさというのは、思いのほか現代人の気分に深く染み込んでいるように思います。
とはいえ、デカルトだって学校を卒業してすぐにそうした「仕事」に取り掛かれた訳ではなく、20年以上にわたる遍歴や隠棲生活を経て、四十代になってやっと『方法序説』を敢行したのです。
今期のさそり座もまた、そうしたデカルトの姿を追いように、他ならぬ自分がはじめ、またそれを自分の手で仕上げられるような仕事とは何かということを、改めて浮き彫りにしていきたいところです。
参考:デカルト、谷川多佳子訳『方法序説』(岩波文庫)
-

今期のいて座のキーワードは、「言葉のもどかしさ」。
「本当に思っていることを、うまく書けない文章のほうがときには文章としては上である」
これは詩人の荒川洋治の『本を読む前に』からの一節ですが、この「書きえぬ」感覚というのは、顔文字やスタンプやそれに近い決まり文句でのやりとりの機会が増えていくほどに失われていくものでもあります。
現代社会は、そもそも言葉が多すぎるのです。黙っていられない人、言葉の不在を恐れる人、思ってもいないことを平気で上手に書いてしまう人。そうした人たちは言葉が途絶えることに不安を感じ、間が持たないことに焦れ、言葉をきちんと感じる前に継ぎ足していくことで、かえって虚しさを増大させてしまうのです。
何を見ても、何を感じても、「カワイイ」「ウザイ」「スキ」「キモチワルイ」などの特定の便利な言葉ですぐに処理してしまっていたり、「絆」や「自己責任」など言葉がたどり着こうとしている先がとうに擦り切れてしまっている場合なども、言葉はただの決まり文句となって、私たちのあいだから滑り落ちていきます。
ふっと言葉が浮かんで書きかける。その言葉をじっと眺めたり、何度か繰り返しているうちに、言葉が宙に浮きだして、それ以上書けなくなる。言葉がいつだって舌足らずで、もどかしさがつきものですが、何でもないような時に、またふっとその続きが思い浮かんできたりもする。とにかく、意識して書こうとすると、途端にダメになってしまうものなのです。
そして、今期のいて座もまた、まさにそうした何かを語ること、自分の言葉にしていくことの不思議さに感じ入っていくことがテーマなのだと言えます。間違っても上手に書こうとか、業界の目を気にしようなどという考えは、いったん脇に置いていきましょう。
参考:荒川洋治『本を読む前に』(新書館)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「青春の解放」。
「ぼくは20歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとは誰にも言わせまい」
これは二十世紀フランス文学のなかでも最もよく引用されるであろう、ポール・ニザンの青春小説『アデン・アラビア』の冒頭の一節です。
ここでは「二十歳」とは青春を表すひとつの記号なのでしょう。子供から大人へと向かう過程で、決定的な通過儀礼や生涯忘れることのない痛くて切ない経験をさせられる過渡期のことを、人は青春と呼んで特別視してきた訳ですが、近年では少し事情が違ってきているように思います。
まだ「大人」ではないが「子ども」でもない、そんな「青年」特有の背伸びをすることなく、したがって大きく失敗することもない。現実や将来が「なんか見えてしまっている」という、冷めた認識が諦めとも倦怠感ともつかないまま、熱や高ぶりを抱くこともなく淡々とそこを通過していくように映るのです。
一日もはやく「大人」になりたいと思う時代はとうに過ぎ去ってしまった訳ですが、その代わり、一定の社会人経験を経た後や定年後に大学や大学院に入り直したり、ずっと憧れていた夢や希望を叶えようする人というのも増えてきているのではないでしょうか。
「あの頃はよかった」という過去への虚飾や、「大人」でない者へ美しいイメージを押しつけることで現在のみじめさを埋め合わせようという欺瞞(ぎまん)は、今後はますます成り立たなくなっていくはず。
今期のやぎ座もまた、みずからの「青春」は他ならぬ今や今後にこそあるのだという感覚を改めて深めていくことがテーマなのだと言えます。夢を巧妙に隠しておくことは、もはや大人の節度などでないのです。
参考:ポール・ニザン、篠田浩一郎訳『アデン・アラビア』(晶文社)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「割り切れぬところ」。
仕事というのは「仕事」とカッコつきで書いてちょうどいいくらいの、中途半端なものであることがほとんどで、自分以外の誰かに振り回されるなかで、それでも仕方なくこなしていくもの。ふと、そんな風に思うことはないでしょうか。
例えば看護師であれ、デザイナーであれ、そこでは他人の事情ばかりが優先されて、その後始末に奔走したり、先取りしたりすることが多く、何か割り切れないものを抱えながらも、それでも淡々と片付けていかなければなりません。
しなやかに、卒なく、と言えば聞こえはいいけれど、実際のところは、いいかげんで、中途半端な自分を持て余している。そして、そうした時期が長く続くと、人は否応もなく疲れてくる。
アドルノの本に引用されていた、ボルハルトという詩人の次のような詩の一節はそんな疲労を癒してくれるように思います。
「ただザワザワとざわめいているだけでいいんだよ。はっきりとした音をお前から聴きたいなんて思っていないのさ。耳を澄ましたりすれば、きっとお前も痛いだろうから」
人は疲れのなかでこそ、どうにもならない真理や人生の在り様を知るのかも知れません。
今期のみずがめ座もまた、自分の奥深くにためこんでいる割り切れない思いや感情を、そっと解き放っていくことで、くたくたになった自分をまずは認めてあげるといいでしょう。
参考:アドルノ、渡辺祐邦訳『三つのヘーゲル研究』(河出書房新社)
-
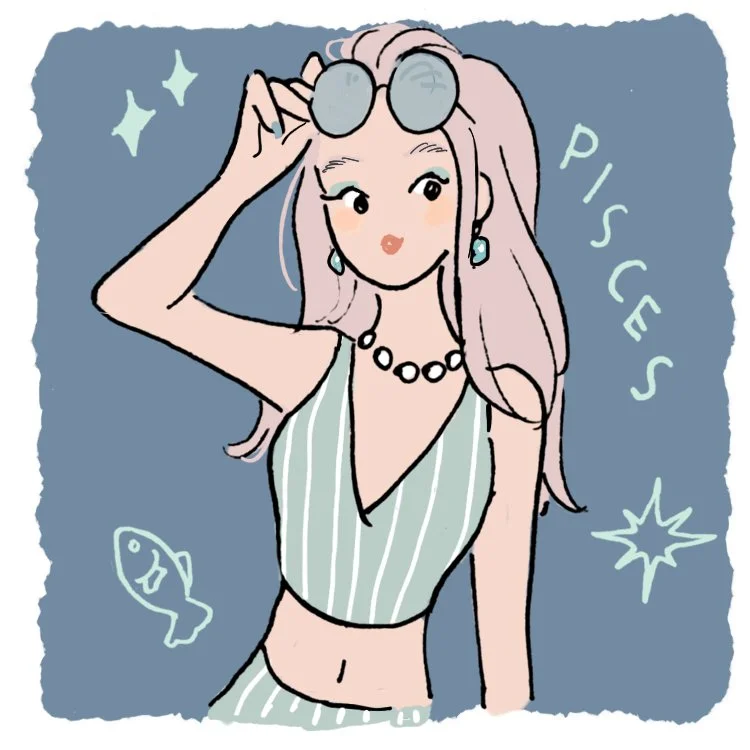
今期のうお座のキーワードは、「魂の健康」。
脳の働きや精神というものほどいいかげんで、事実をねじ曲げて手前勝手なことばかり主張する代物はないように思いますが、その点、身体には精神よりもはるかに常識が備わっています。
危険を察知したときはきちんと信号を送ってくれるし、限界がきたら拒絶反応を示し、心の深い傷は身体にその爪痕を残し、身体が凍りついたり変な汗をかいたりなど、たびたび疼くことでまだその傷が癒えてないことを教えてくれるのです。
19世紀に生まれ、米国の心理学の祖となったウィリアム・ジェイムズは、こうした身体の知恵によってむしろ精神がどれだけ救われているのかを最初にはっきりと示した人物の一人であり、「ひとは悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」と言って、その逆ではないのだということを強調しました。
せっかく美しい事物を知覚しても、然るべき身体の裏打ちがなければ、「生気なく、色合いなく、感情の熱を欠く」のであり、感情を身体や感覚の微細な変化の映しと捉えたのです。
つまり、私たちは嬉しいことが起きるから幸せで、快活であれるのではなく、快活な姿勢をとっているからこそ、自然と嬉しさを感じやすくなり、結果として嬉しい気持ちが湧いてくるのであり、精神と肉体は別ものであり、肉体を疎かにしたり軽蔑したりすることは、最も恥ずべき行いとさえ言えるのだということ。
ジェイムズは「魂の健康」について語る中で、悲嘆に暮れているときは、胸を張って大きく空気を吸って、大股で歩いてみることを勧めています。そうすることで、感情の均衡をとるとした訳です。
今期のうお座もまた、自分なりの身体への敬意の払い方や、付き合い方というものを改めて見直し、他でもないみずからの身体に精神を委ねていくといいでしょう。
参考:ウィリアム・ジェイムズ、今田寛訳『心理学<上>』(岩波文庫)
 【SUGARさんの12星座占い】<9/19~10/3>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<9/19~10/3>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「エウ・フェーミアー」。 古代ギリシャ語には「エウ・フェーミアー」という言葉があり、「よき前兆を告げること」「吉兆の告知」というほどの意味で使われる一方で、「畏れ慎んで黙ること」「沈黙」の意味を持っていました。
今期のおひつじ座のキーワードは、「エウ・フェーミアー」。 古代ギリシャ語には「エウ・フェーミアー」という言葉があり、「よき前兆を告げること」「吉兆の告知」というほどの意味で使われる一方で、「畏れ慎んで黙ること」「沈黙」の意味を持っていました。 今期のおうし座のキーワードは、「偶然をめぐる感情」。 「私が生れたよりももつと遠いところへ。そこではまだ可能が可能なままであつたところへ」
今期のおうし座のキーワードは、「偶然をめぐる感情」。 「私が生れたよりももつと遠いところへ。そこではまだ可能が可能なままであつたところへ」 今期のふたご座のキーワードは、「幸福論」。 20世紀を過ぎて、アリストテレスから近代のモラリストたち、そして功利主義まで伝統的に書き継がれてきた幸福論はぱたりと書かれなくなり、代わりに不幸論や苦悩論が盛んに書かれるようになりました。
今期のふたご座のキーワードは、「幸福論」。 20世紀を過ぎて、アリストテレスから近代のモラリストたち、そして功利主義まで伝統的に書き継がれてきた幸福論はぱたりと書かれなくなり、代わりに不幸論や苦悩論が盛んに書かれるようになりました。 今期のかに座のキーワードは、「おのれをほどく」。 もはや「自己実現」という言葉は、就活を控えた大学生から定年を迎えた後のお年寄りまで、あらゆる年代で当たり前のように使われるようになってきました。
今期のかに座のキーワードは、「おのれをほどく」。 もはや「自己実現」という言葉は、就活を控えた大学生から定年を迎えた後のお年寄りまで、あらゆる年代で当たり前のように使われるようになってきました。 今期のしし座のキーワードは、「魂を確かめる」。 コロナ禍によって、街での他者との、あるいは異物との密な接触の機会が回避されるようになったと言われていますが、こうした傾向はじつは随分前から既に社会全般で見られるようになっています。
今期のしし座のキーワードは、「魂を確かめる」。 コロナ禍によって、街での他者との、あるいは異物との密な接触の機会が回避されるようになったと言われていますが、こうした傾向はじつは随分前から既に社会全般で見られるようになっています。 今期のおとめ座のキーワードは、「新しさの根源」。 今ときめいているどんなものも、いずれ必ず輝きを失っていく。その意味では、この世のすべては現れては消えゆく泡沫のようなものであり、本当に決定的と言えるものは存在しない。そんな感覚が日常化しているのが今の社会なのだと言えるのではないでしょうか。
今期のおとめ座のキーワードは、「新しさの根源」。 今ときめいているどんなものも、いずれ必ず輝きを失っていく。その意味では、この世のすべては現れては消えゆく泡沫のようなものであり、本当に決定的と言えるものは存在しない。そんな感覚が日常化しているのが今の社会なのだと言えるのではないでしょうか。 今期のてんびん座のキーワードは、「誰かへの贈り物」。 占いをしていると、「自分探し」や「自己実現」に本気で取り組みたいのだと言う人の話を見聞きすることがあります。
今期のてんびん座のキーワードは、「誰かへの贈り物」。 占いをしていると、「自分探し」や「自己実現」に本気で取り組みたいのだと言う人の話を見聞きすることがあります。 今期のさそり座のキーワードは、「やるべき仕事」。 「それをはじめた者がまた最もよくそれを仕上げうる者であるような仕事が世にあるとすれば、それこそ私のやっている仕事なのである」
今期のさそり座のキーワードは、「やるべき仕事」。 「それをはじめた者がまた最もよくそれを仕上げうる者であるような仕事が世にあるとすれば、それこそ私のやっている仕事なのである」 今期のいて座のキーワードは、「言葉のもどかしさ」。 「本当に思っていることを、うまく書けない文章のほうがときには文章としては上である」
今期のいて座のキーワードは、「言葉のもどかしさ」。 「本当に思っていることを、うまく書けない文章のほうがときには文章としては上である」 今期のやぎ座のキーワードは、「青春の解放」。 「ぼくは20歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとは誰にも言わせまい」
今期のやぎ座のキーワードは、「青春の解放」。 「ぼくは20歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとは誰にも言わせまい」 今期のみずがめ座のキーワードは、「割り切れぬところ」。 仕事というのは「仕事」とカッコつきで書いてちょうどいいくらいの、中途半端なものであることがほとんどで、自分以外の誰かに振り回されるなかで、それでも仕方なくこなしていくもの。ふと、そんな風に思うことはないでしょうか。
今期のみずがめ座のキーワードは、「割り切れぬところ」。 仕事というのは「仕事」とカッコつきで書いてちょうどいいくらいの、中途半端なものであることがほとんどで、自分以外の誰かに振り回されるなかで、それでも仕方なくこなしていくもの。ふと、そんな風に思うことはないでしょうか。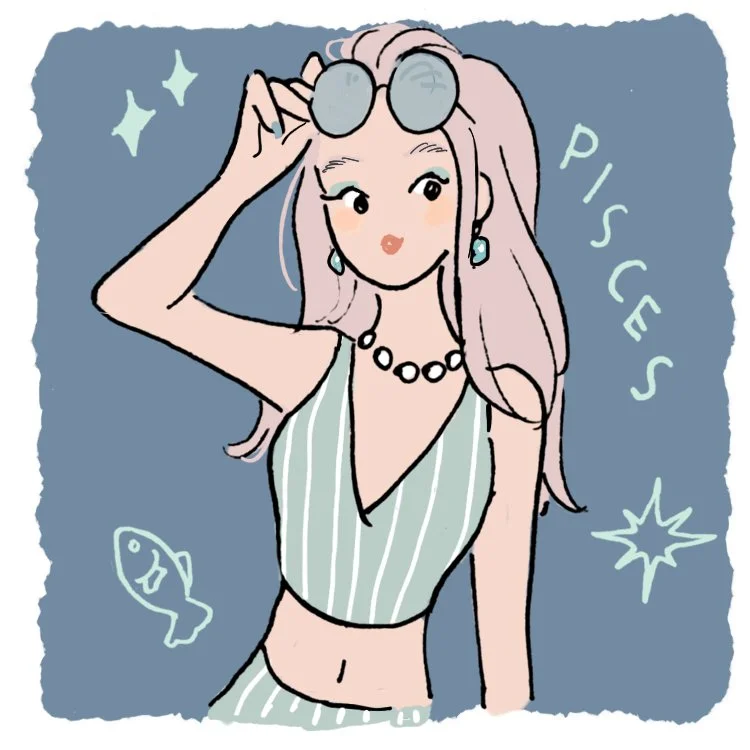 今期のうお座のキーワードは、「魂の健康」。 脳の働きや精神というものほどいいかげんで、事実をねじ曲げて手前勝手なことばかり主張する代物はないように思いますが、その点、身体には精神よりもはるかに常識が備わっています。
今期のうお座のキーワードは、「魂の健康」。 脳の働きや精神というものほどいいかげんで、事実をねじ曲げて手前勝手なことばかり主張する代物はないように思いますが、その点、身体には精神よりもはるかに常識が備わっています。










































































