-

【SUGARさんの12星座占い】<10/4~10/17>の12星座全体の運勢は?
「新たな習慣、新たな取り組み」
10月8日を過ぎると二十四節気では「寒露」に入り、晩秋を迎えます。「晩秋」というと、どこか寂しさをそそりますが、旧暦の時代には10月のことをさまざまな言い方で表してきました。
例えば、稲を収穫することから「小田刈月(おだかりづき)」、また菊も咲き始めるので「菊月」、木の葉が染まり出し、梨や柿や金柑など、さまざまな果実も実りのときを迎えていくので「色取月(いろとりづき)」など。
まさに心豊かに過ごせる時期と言えますが、そんな中、10月17日にはてんびん座で新月を迎えていきます。今期のテーマは「蝶の第三の羽」。
蝶は古来より「霊的な復活のプロセスの結末」を表すシンボルであり、二枚の羽の代わりに三枚の羽を持っているなら、霊的生活の観点において特別な発達があったことを示していますし、また「3」という数字は「充足」の象徴でもあります。
すなわち、合理的知性では説明がつかない新たな可能性を秘めた習慣や試み、突然変異的な取り組みを生活の中に取り込んでいく機運が高まっていきやすいタイミングなのだと言えるでしょう。
充実した秋の夜長を過ごすべく、これまでは手が伸びなかったような新しい何かに打ち込んでいくのにもうってつけかも知れません。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「顔という現象」。
雑誌の表紙や朝のニュース番組、お気に入りのYoutuber、駅構内や電車内のポスターなど、都市は顔で充ちている一方で、ひと昔前に比べると“顔という現象”はひどくうすっぺらいものになってきたように思えます。
この顔ということについて独特の角度から考察を加えたのが、ユダヤ人哲学者エマニュエル・レヴィナスでした。
レヴィナスによれば、私たちの顔はおよそ正直そのものだが無防備であり、人によっては「慎み深い露出」を行っていたりもするが、本質的には<貧しい>ものであると言う。人がことさら気取った表情をしたり、平静を装ったりするのも、実はこの貧しさを隠すためなのだ、と。
ここでレヴィナスが<貧しい>という言葉で言おうとしているのは、「ヴァルネラビリティ(傷つきやすさ)」とも言い換えることができるでしょう。だからこそ、他人の顔との関わり=顔という現象との向き合い方には、必然的に倫理的なものが求められてくるのです。
「顔とは殺すことのできないものであり、少なくとも「汝殺すなかれ」と語りかけるところに、顔の意味がある」
そう、顔とは、本来見られることへの呼びかけとしてそこに在るものであり、そうであればこそ、そこに迫りくるような力が宿ってくる。
けれど、テレビや動画配信などによる一方的な顔との関わりを通じ、相手の顔をじろじろ見たり、何のひけ目もなく観察することにあまりに慣れ過ぎれば、まなざしまなざされる他人からのまなざしの中で立ち上がってくる顔という現象はますます貧しくなり、いずれは顔に何も感じなくなりかねないのではないでしょうか。
今期のおひつじ座もまた、顔という自分の在り様を正直に露呈する鏡のようなものを通して他人に語り、また相手の顔に応答することを通して対話するということを、改めて意識していきたいところです。
そうして、自分や相手の顔がしばらくすると「いい顔」になっていたり、逆に「よくない顔」になっていたりといった、微妙な変化に気付いて、それを積み重ねていくことが、顔という現象を少なからず豊かなものにしてくれるはず。
参考:レヴィナス、西山雄二訳『倫理と無限』(ちくま学芸文庫)
-

今期のおうし座のキーワードは、「体に運ばれる必要」。
パリを拠点にした英語の文芸誌『パリ・レビュー』のインタビューにおいて、村上春樹は長編小説を書いているとき、午前4時には起床し、5~6時間ぶっ通しで仕事をし、午後はランニングをするか水泳をするかして(両方ともすることもある)、雑用を片付け、本を読んで音楽をきき、夜9時には寝るという。
しかも「この日課を毎日、変えることなく繰り返す」のだと言う。いわく、「繰り返すこと自体が重要になってくるんです。一種の催眠状態というか、自分に催眠術をかけて、より深い精神状態にもっていく」。
というのも、長編小説を書き上げるには精神的な鍛練や気の持ちようだけではどうにもならず、「体力が、芸術的感性と同じくらい必要」となるからだと強調しています。
ここでは村上は「体力」と簡単に言っていますが、それはおそらくペンを握る指先や腕の力だけでなく、深い呼吸に入っていくための肺や横隔膜、地面を踏みしめる脚力、背中が固まることのない柔軟性など、体のすみずみに至るまで、自らの創作活動が“運ばれる”ことが大切なのだということでしょう。
もちろん、村上も最初からこうした習慣を実行していた訳ではなく、プロの作家になってから数年間は、東京で小さなジャズクラブを経営しながら、座ってばかりの生活をしていて、一日に60本ものタバコを吸い、急激に体重が増えていき、そこで生活習慣を根本的に変えることを余儀なくされたのだとか。
「読者は僕がどんなライフスタイルを選ぼうが気にしない。僕の新しい作品が前の作品よりよくなっているかぎりは。だったらそれが、作家としての僕の義務であり、もっとも優先すべき課題だろう」
今期のおうし座もまた、自身の生活習慣をもっとも優先すべき課題や関係性に応じて、よりふさわしいものに作り変えていくことが大きな課題となっていくはず。
まずは、自分の人生で欠かすことのできない課題や関係は何なのかということを、改めて明確にするべく自分自身に問いかけてみるといいでしょう。
参考:青山南訳『パリ・レヴュー・インタヴュー(2)』(岩波書店)
-

今期のふたご座のキーワードは、「心眼を得る」。
谷崎潤一郎の『春琴抄』にも盲目になってかえって心眼が得られるという話が出てきますが、世界で最もよく知られている同型の話としては、何と言ってもシェイクスピアの『リア王』の一連の場面を挙げない訳にはいかないでしょう。
弟にあたる庶子のエドマンドのわるだくみにより、反逆者に仕立てられ追放されたグロスター伯爵の息子エドガーは、頭のおかしい乞食のトムに身をやつすうちに、両眼をくりぬかれた父にも実の息子だと気付かれずに、ドーヴァー海峡へ向かう父の手を引いていくことになります。
盲目のグロスターが、すぐ目の前にエドガーがいるのに気付かずに「わしには道などないのだ。だから目はいらぬ。目が見えたときにはよくつまづいたものだ」とつぶやき、さらに続けてこう言うのです。
「よくあることだが、ものがあれば油断する、なくなればかえってそれが強みになる。ああ、エドガー、お前は騙された愚かな父の怒りのいけにえになった! 生き永らえていつかお前の体に触れることができたなら、そのとき、おれは言うだろう、父はめをふたたび取り戻した」と。
こうして残酷な逆境に置かれるようになって初めて、平穏な生活の最中ではとうてい見えなかったことが見えるようになり、グロスターにしろエドガーにしろ、それを見る観客の心をも奥底から突き動かしていく訳です。
シェイクスピアは『ソネット集』においても、「目をしっかりつむっているときに私はいちばんよく見える」とうたっており、お気に入りのモチーフだったことが伺われますが、これは今期のふたご座にとっても大事な指針となっていくはず。
すなわち、特に大事な判断や物事の真価をはかる際には、これまでと同じように今後も当たり前にあると思ってしまっているものはないか、いったん「目をつむって」みるよう試してみるといいでしょう。
参考:シェイクスピア、松岡和子訳『シェイクスピア全集<5>』(ちくま文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「一生弟子」。
このところ、占星術界隈では「風の時代」という言葉がやたらと使われるようになってきました(約20年ごとに起こる木星と土星の邂逅が、今年12月を期に約200年ぶりに「土」の星座から「風」の星座に移っていくことを指す)。
そこでは古い呪縛からの解放や個人的自由の拡大など、何かとそのよい側面ばかりが語られているように感じますが、その実際のところはどうなのでしょうか。日本では前回の風の時代の到来はちょうど鎌倉時代にあたります。
この時代、確かに日本仏教は絢爛と花開き、法然や親鸞、一遍、道元、日蓮などの高僧たちが活躍し、それぞれが独自に教えを発展させていきましたが、彼らに並ぶ高僧のなかに明恵という、長年にわたって克明に自己の夢の内容を書き綴った『夢記(ゆめのき)』を遺した人物がいました。
彼は隠遁生活に入った24歳の時、僧侶としての剃髪着衣以上に仏道修行へとおのれを集中させるため右耳を切り落とすのですが、その直後に夢のなかで“文殊菩薩”を見ます。
この菩薩は「三人寄れば文殊の知恵」の文殊のことで、仏教において仏陀に代わるほどの知恵の体現者であるばかりでなく、その知恵は<空>に立脚していました。すなわち、一切のこだわりや固定化を排したもので、いたずらな知識のため込みではなく、誰からでも虚心にものを学ぼうとするゼロ状態の精神のことですが、後に明恵はこの夢の体験を踏まえて次のような言葉を遺しました。
「我は師をば儲けたし、弟子はほしからず(師匠は欲しいが弟子はいらない)。尋常は、いささかの事あれば師には成りたがれども、人に随ひて一生弟子とは成りたがらぬにや。」
こうして彼は「一生稽古」、「一生弟子」の志を貫いていくことで、華厳宗という宗派(組織)に属しながらも、宗教の党派性から自由でいられる自身の在り様をようやく確立していったのです。
今期のかに座もまた、やたらと先生になろうとするのではなく、とことん弟子になればいいと考え実践していった明恵のように、余計な心配事を減らすための自身の在り様について模索していきたいところです。
参考:久保田淳・山口明穂校註『明恵上人集』(岩波文庫)
-

今期のしし座のキーワードは、「我を忘れる瞬間」。
鎌倉時代に踊り念仏を広めた一遍上人は「捨てることを捨てよ」と説きましたが、ほぼ同時期のドイツに生きた大神学者で「ドイツ神秘主義の源泉」と言われるマイスター・エックハルトもまた<内なる貧しさ>という言い方でそれに相通じる教えを説いていました。
いわく、積極的な意味での<貧しさ>には二種類あり、一つは<外なる貧しさ>、つまり物を所有することなく文字通り貧しく生きようとする生き方。
そして<外なる貧しさ>よりもっと本質的なものが<内なる貧しさ>で、これは所有の真っ只中にあって、しかもその所有関係の囚われから自由であるような人間の在り方のことを言うのだ、と。
エックハルトによれば、どんなに懺悔や祈りや徳の修練を行って「聖者」と呼ばれるようになったところで、まだ本人のなかに神に愛されようという意志がまだ残っているかぎり、<外なる貧しさ>にとどまるのであり、それは「内から見れば愚かなロバでしかない」のだとまで言うのです。
すなわち、いくら物質的な所有物を捨てても、おのれの意志を捨てなければ無にはなりきれない、つまり神と一つにはれないのだということですが、これは仏教における「仏道をならふといふは、自己をならふということなり。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり」という教えとやはり不思議に一致してくることに気が付きます。
今期のしし座もまた、そうした不意の一致のなかで、自意識を忘れ、意志を捨てられる瞬間を一秒でも長く感じられるようにしていくことで、人間としてのより自由な在り方を深めていくことができるかどうかが問われていくでしょう。
参考:田島照久編訳『エックハルト説教集』(岩波文庫)、頼住光子「正法眼蔵入門 」(角川ソフィア文庫)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「身体と私」。
『マトリックス』に影響を与え、ハリウッド映画やアニメにもなって改めて知られるようになってきた士郎正宗の『攻殻機動隊』(漫画原作は1995年に刊行)の世界では、人間はサイボーグ化され、身体は自由に付け替えのきく「義体」と呼ばれるものとなっていますが、それでも、その世界は主人公・草薙素子(くさなぎもとこ)の視点に中心化された世界であり、ストーリーのなかで義体が破壊された際にもそれは変わりません。
ただ、そのこと自体に草薙は疑問を抱き、次のようなセリフをつぶやくのです。
「私は時々『自分はもう死んじゃってて、今の私は義体と電脳で構成された模擬人格なんじゃないか』って思う事もあるわ」
しかし、もしそうだとしたなら、もう死んじゃっている「自分」とは、誰のことになるのか。また、そういう「自分」と「今の私」とはどういう関係にあるのか。
あるいは、仮に「模擬人格」なのだとしたら、オリジナルの自分の記憶や嗜好や性格などはどこまで再現されているのだろうか。そして、そうしたすべての疑念を勘案し、受け入れたとしても、「今の私」が現にここにこうしているということは疑いようがないけれど、それはどうしてなのか。
これらはすべて、すぐに答えを用意することができないどころか、答えられるかどうかさえ見当がつかない難問ですが、今後ヒトゲノム(遺伝情報のひとつ)の解析もますます進み、医学領域だけでなくより日常的な場面で用いられる生体科学の研究や技術開発が発展していくだろう2020年代には、こうした問いや疑問はますますリアリティーを増していくことは間違いないでしょう。
この作品では、「ゴースト」「魂」「生命体」などと表現される存在者が世界の中に客観的に存在し、それが何らかの器に宿るといわば自我が生じるかのように考えられていますが、それは90年代初期という時代を考慮してもやや素朴に感じられます。
今期のおとめ座もまた、私が他ならぬこの私でいられるための成立条件や、そもそも私であるということは何であることなのか、といった謎の感覚を改めて呼び覚ましてみるといいかも知れません。
参考:士郎正宗『攻殻機動隊(1)』(講談社)
-
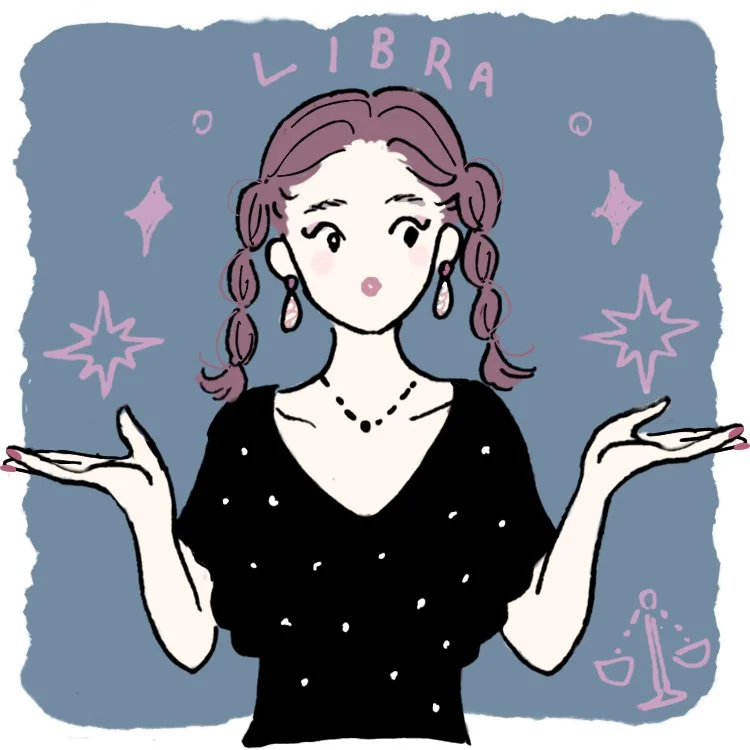
今期のてんびん座のキーワードは、「思い出のクォリティー」。
人工知能との比較で、人間のもつ想起的な記憶(思い出)の重要性が再評価されてきている今、数世紀の時代をこえてぜひ思い出していきたい人物のひとりにレオナルド・ダ・ヴィンチがいます。
15~6世紀のイタリアに生きたダ・ヴィンチは、一流の画家・芸術家であったばかりでなく、科学者・技術者でもありました。ルネサンス期の多くの万能人の中でも、その才能に対して「神のごとき」(ヴァザーリ)という形容詞がつけられているのはミケランジェロと彼だけであることから、まさに「万能の天才」の名に値すると言えるでしょう。
ダ・ヴィンチは膨大な手記を遺しており、そこからはスケッチや絵画からだけではうかがい知れない彼の思想や主張が肉声をともない聞こえてくるかのようです。例えば、記憶にかかわる断章は次のような一文から始まります。
「人々が時の流れのあまりにすみやかなことに罪を着せて、時の流れ去るのを嘆くのは見当違いだ。」
というのも、人々は時間というものが「十分な余裕をもって推移する」ことに気付いていないとし、さらに次のように述べています。
「だが、自然がわれわれに贈ってくれる上等な記憶は、過ぎ去った遠い昔のあらゆることを目前にあるかのように思わせる」と。
彼はまた「絵画は科学(知)なり」というモットーでも知られていますが、「魂の窓と呼ばれる眼は、それにより共通感覚がもっとも豊かかつ壮大に、限りない自然の作品を考察しうる第一義的な道だから」とも言っていて、彼がきちんと眼で観察することを「上等な思い出」の想起の上で何よりも大切にしていたことが分かります。
今期のてんびん座もまた、内容を十分練らないままに自己主張をしたり、早々に評価されようとして躍起になる前に、改めて微細な観察の手間や工夫を凝らしていくことで、五感を貫く根源的な「共通感覚」を活性化させ、「思い出」の質を高めていく習慣をつけていきたいところです。
参考:レオナルド・ダ・ヴィンチ、杉浦明平訳『レオナルド・ダ・ヴィンチ 上・下』(岩波文庫)
-

今期のさそり座のキーワードは、「内なる狂気」。
「狂気」はきわめて現代的な問題のひとつと言えます。というのも、狂気がどう規定されるかは、その本質上、時代や社会との関係に極めて密接に結びついており、古代社会から現代の資本主義社会にいたるまで、人間社会ではさまざまな表情の「狂人」がつくり出されてきたからです。
フランスの思想家M・フーコーは『狂気の歴史』において、中世およびルネッサンス期には狂気に対して寛容だったヨーロッパ社会が、17世紀前半になるとほとんど全ヨーロッパ的な規模で狂人の監禁を実施し始め、しかもそれが国家権力と治安維持を背景にしたものだったことに言及しました。
その後、18世紀末に科学と博愛主義によってそれらの人々は解放されたと一般的には思われていますが、フーコーはそこで解放されたのは、あくまで制約と掟に服従ないし合致しない「周辺的存在」の一部に過ぎず、精神医学の対象とされ精神病棟に閉じ込められている狭義の“狂人”以外にも、いまも現に社会は「周辺的存在」を排除し続けているのだと言います。彼によれば、排除の基準、排除された者たちは以下の4つに分類されます。
a 経済に寄与しない者(働かない人、その能力のない人)
b 通常の社会関係を結ぶことができない者(放蕩者、色情狂、浪費家)
c 普通の言葉を信用しない者、異常な言辞を弄する者(冒涜者、文学者、哲学者)
d 宗教的祝祭から排除される者(障害者、高齢者)
ここでフーコーがあえて使った「狂人」という言葉は、現代の日本でも厳然と使われている「非正規従業員」や「シャドーワーカー」などの言葉と近しいとも言えるでしょう。
すなわち、狂気の人と理性の人とは普通に思われる以上に境目がないばかりか、「自分は狂ってなどいない」という確信の持ち主であっても「内なる狂気」をまったく、ないし一時的にでも含んでいない人などありえないでしょう。さらに現代社会は上記以外の新しい排除の条件をつくりだしていないとも限らないのです。
同様に、今期のさそり座のテーマもまた、そうした「目に見えぬ営み」としての狂気体験(すなわち時に放蕩に出たり、意味もなく浪費したり、働く気が失せたり、文学や芸術にはまったり)を自分や身の周りに浮き上がらせていくことで、今まで見えていなかった世の現実やみずからの人生における真実に少なからず感知していくことにあるのだと言えるでしょう。
参考:M・フーコー、田村俶訳『狂気の歴史』(新潮社)
-

今期のいて座のキーワードは、「詩人の務め」。
小林秀雄が『ランボオ論』の書き出しで、「向うからやつて来た見知らぬ男が、いきなり僕を叩きのめしたのである」とその衝撃を表現してみせたことはあまりにも有名ですが、彼以外にもアルチュール・ランボーは日本の多くの若者や文学者たちに強烈なインパクトを与えてきました。
なぜそれだけランボーが特別であったかは、おそらく、彼が作品だけでなく生き様としても「詩」を生み切ったからでしょう。
20歳で詩を放棄するまでのわずか三年間に、それまでの詩の伝統を変えるような詩集を立て続けに発表した後、詩を捨てて漂泊の旅へ出て、アラビアやアフリカにまで足を延ばし、最後は砂漠の武器商人として生を終えたその鮮烈な軌跡に、人々は詩の神髄を見たのでしょう。
では、その神髄とは何か。少なくとも、ランボー自身は詩の使命や力についてどのように考えていたのでしょうか。知人であるポール・ドメニー宛の書簡(見者の手紙)のなかでこう書いています。
「詩人になろうと望む人間の探究すべきことの第一は、自己自身を認識すること、それも全面的に認識することです。自分の魂を探索し、綿密に検査し、誘惑し、学ぶことです。自分の魂を知ったら、すぐにそれを養い育てなければなりません。」
一見すると特別難しくない、つまり自分でもやれそうだと感じる内容ですが、実際にはそうではない理由として、ここでランボーは「自分の魂」というものを「まったく未知なもの」にまで高めなければならないと主張し、さらに次のように続けるのです。
「詩人は、その時代に、万人の魂のうちで目覚めつつある未知なものの量を、明らかにすることになるでしょう」
実際彼はその人生のなかで、さまざまな形の愛や苦悩、狂気をふくむものとして「自分の魂を探索し、綿密に検査し、誘惑し、学」び、実際それを「養い育て」ていったのでしょうし、そのためには、向こうからやってきた見知らぬ相手とぶつかるように、定期的にみずからの人生を刷新していく必要があったのかも知れません。
今期のいて座もまた、自分自身やその人生を、まったく触れたことも経験したことのない場所へとあえて置いてみることで、ある種の詩人の務めを果たしていくことができるかも知れません。
参考:宇佐美斉訳『ランボー全詩集』(ちくま文庫)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「未熟の惑星」。
映画化もされた小説『存在の耐えられない軽さ』(1984)で有名になったチェコ出身のミラン・クンデラには、あまり知られていませんが『七十三語』(1986)という味わい深い私家版の用語集があり、中でも「未熟」の項に書き添えられた次のような一文は非常に印象的です。
「老人は自分の老齢に無知な子供であり、この意味で人間の世界は未熟の惑星なのである。」
冒頭の小説に作者が最初に付けようとした題名も「未熟の惑星」であったそうですが、しかしなぜ未熟なのか。
それは、私たちは一度しか生まれないために、前の生活から得た経験を新しい生活に活かすことができず、若さの何かを知らずに少年期を去り、結婚をよく知らずに結婚し、自分が何に向かって歩んでいるかを知らずに老境に入って行く。つまり、いくつになっても現在の自分を知らないのだ、と。
地球はそういう人間の住む惑星だという訳です。なお惑星は、つねに変わらない恒星に対して、宇宙をたえず彷徨う星であり、クンデラはそうした人類の不安定で未熟な在り様を二重に強調するために、「未熟の惑星」という言葉を考えついたのでしょう。
けれど、(小説を読めばわかるのですが)それは必ずしも悲観的な意味で使われている訳ではありません。永遠に未熟であるとは、いたずらに過去にこだわって「あの頃はよかった」「あの頃に戻れれば」と執着するべきではないということでもあるからです。
そして、今期のやぎ座もまた、うすうす感じつつあった現在の自分の未熟さを直視していくことで、また一つ過去から解き放たれていくことができるはず。
参考:ミラン・クンデラ、金井裕・浅野敏夫訳『小説の精神』(法政大学出版)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「平常心の試み」。
最近、TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSサービスは今や怒りや嫉妬、傲慢など負の感情の温床と化しているという話を目にしました。
確かに、歴史を振り返っても、おそろしいことに人間というのは善き人であらんと「誠」を貫くことによって、嘘を重ねることもできれば、人に手をかけることだってできてしまうという落とし穴があり、誠意の名において、前提や方向性を顧みない一方的な他者への働きかけが許されてきた側面があるように思います。
こうした主観的な「誠」に対して、12世紀南宋に生まれ中国の元や明の時代や日本の江戸時代に教学となった朱子学では、「敬」という徳目を重視するのだと言います。
この「敬」とは、普通の意味での尊敬のことではなく、心の覚醒状態を保って内面活動が恣意的になるのを防ぐべく、自己を客観化しようという朱子学の基調意識のことであり、平易な言い方をすれば、「畏敬の念」のことであり、その結果いたる「こだわりのない平常心」を指すのだとも考えられます。
朱子が弟子の問いに答えた言葉を集めた『朱子文集』いわく、「心がいつも敬の状態にあるならば、肢体はおのずと引きしまり、なにも意識しないでも、肢体はひとりでにのびのび」するようになり、その意味で「敬」とは「心の全体があまねく流動して、行き届かないものはなにもない」状態なのです。
SNSが営利企業の運営する“サービス”である限り、人間の欲動を刺激することが本質にある訳ですが、そうして刺激され高揚した心理は明らかにこうした「敬」と対極にある状態と言えるのではないでしょうか。
今期のみずがめ座もまた、こうした「敬」の精神をあらためて見直していくことで、誰かの手によって意図的に引き起こされた刺激や高揚から脱却し、少なからず自己を客観化していくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:荒木見悟訳『世界の名著19 朱子/王陽明』(中央公論新社)
-
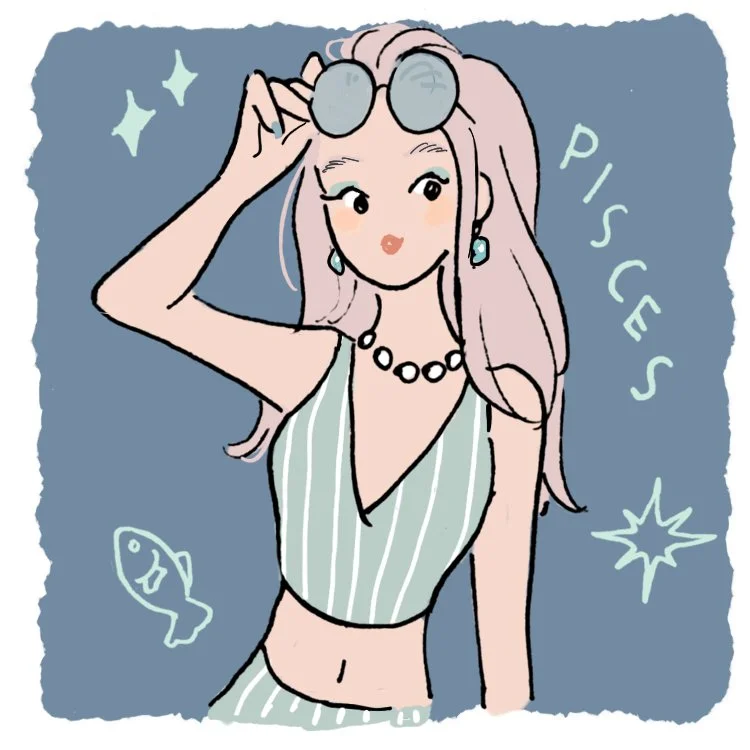
今期のうお座のキーワードは、「一日の円」。
資本主義で回る現代社会というのは、つくづく他人の欲望に踊らされ続ける人生が量産される社会であり、人々はうらやましがったり、愚痴をこぼしたり、不満や怒りを訴えたりしながら、労働や人間関係などを通して、気安く他人に時間を与えてばかりいるという実感が、最近人々の間でにわかに深まってきたように感じます。
そして、ふとそうした自身のうちにも潜んでいる危うさに気付いた時、足を止めて立ち返りたくなる一冊に古代ローマに書かれた『道徳書簡集』が挙げられます。
ストア派の哲学者セネカが晩年に著したとされるこの書簡集には、人間の一生をどのように考えるべきか、どう生きるかという主題がそこかしこに顔を出すのですが、そこには「すぐれた人は自分の時間が少しでも他人に奪われることを許さない」といった時間の重要性を示唆する文言が頻出するのです。
忙しすぎる生活からは真に自分自身を生きているという実感は得られないし、私たちの持っている時間は決して短くない一方で、使い方次第でその実感は大きく変わってくるのだとセネカは言います。
そこで語られるさまざまな言葉の中で特に印象深く、また今のうお座にふさわしいと思われるのが次の一文です。
「われわれの全生涯がいくつもの部分から成り立っており、小さな円を真ん中にして次々に大きな円に囲まれています」
少年時代を包む円もあれば、老年期を包む円もある。ただ、その中心にはいつだって一日の円があるのです。
今期のうお座もまた、その日その日を精いっぱい生きて、たとえ今日が最後の一日だったとしても後悔しないでいられるかどうかを、一日のどこかで念じてみるといいかも知れません。
参考:セネカ、茂手木元蔵訳『セネカ 道徳書簡集』(東海大学出版会)
 【SUGARさんの12星座占い】<10/4~10/17>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<10/4~10/17>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「顔という現象」。 雑誌の表紙や朝のニュース番組、お気に入りのYoutuber、駅構内や電車内のポスターなど、都市は顔で充ちている一方で、ひと昔前に比べると“顔という現象”はひどくうすっぺらいものになってきたように思えます。
今期のおひつじ座のキーワードは、「顔という現象」。 雑誌の表紙や朝のニュース番組、お気に入りのYoutuber、駅構内や電車内のポスターなど、都市は顔で充ちている一方で、ひと昔前に比べると“顔という現象”はひどくうすっぺらいものになってきたように思えます。 今期のおうし座のキーワードは、「体に運ばれる必要」。 パリを拠点にした英語の文芸誌『パリ・レビュー』のインタビューにおいて、村上春樹は長編小説を書いているとき、午前4時には起床し、5~6時間ぶっ通しで仕事をし、午後はランニングをするか水泳をするかして(両方ともすることもある)、雑用を片付け、本を読んで音楽をきき、夜9時には寝るという。
今期のおうし座のキーワードは、「体に運ばれる必要」。 パリを拠点にした英語の文芸誌『パリ・レビュー』のインタビューにおいて、村上春樹は長編小説を書いているとき、午前4時には起床し、5~6時間ぶっ通しで仕事をし、午後はランニングをするか水泳をするかして(両方ともすることもある)、雑用を片付け、本を読んで音楽をきき、夜9時には寝るという。 今期のふたご座のキーワードは、「心眼を得る」。 谷崎潤一郎の『春琴抄』にも盲目になってかえって心眼が得られるという話が出てきますが、世界で最もよく知られている同型の話としては、何と言ってもシェイクスピアの『リア王』の一連の場面を挙げない訳にはいかないでしょう。
今期のふたご座のキーワードは、「心眼を得る」。 谷崎潤一郎の『春琴抄』にも盲目になってかえって心眼が得られるという話が出てきますが、世界で最もよく知られている同型の話としては、何と言ってもシェイクスピアの『リア王』の一連の場面を挙げない訳にはいかないでしょう。 今期のかに座のキーワードは、「一生弟子」。 このところ、占星術界隈では「風の時代」という言葉がやたらと使われるようになってきました(約20年ごとに起こる木星と土星の邂逅が、今年12月を期に約200年ぶりに「土」の星座から「風」の星座に移っていくことを指す)。
今期のかに座のキーワードは、「一生弟子」。 このところ、占星術界隈では「風の時代」という言葉がやたらと使われるようになってきました(約20年ごとに起こる木星と土星の邂逅が、今年12月を期に約200年ぶりに「土」の星座から「風」の星座に移っていくことを指す)。 今期のしし座のキーワードは、「我を忘れる瞬間」。 鎌倉時代に踊り念仏を広めた一遍上人は「捨てることを捨てよ」と説きましたが、ほぼ同時期のドイツに生きた大神学者で「ドイツ神秘主義の源泉」と言われるマイスター・エックハルトもまた<内なる貧しさ>という言い方でそれに相通じる教えを説いていました。
今期のしし座のキーワードは、「我を忘れる瞬間」。 鎌倉時代に踊り念仏を広めた一遍上人は「捨てることを捨てよ」と説きましたが、ほぼ同時期のドイツに生きた大神学者で「ドイツ神秘主義の源泉」と言われるマイスター・エックハルトもまた<内なる貧しさ>という言い方でそれに相通じる教えを説いていました。 今期のおとめ座のキーワードは、「身体と私」。 『マトリックス』に影響を与え、ハリウッド映画やアニメにもなって改めて知られるようになってきた士郎正宗の『攻殻機動隊』(漫画原作は1995年に刊行)の世界では、人間はサイボーグ化され、身体は自由に付け替えのきく「義体」と呼ばれるものとなっていますが、それでも、その世界は主人公・草薙素子(くさなぎもとこ)の視点に中心化された世界であり、ストーリーのなかで義体が破壊された際にもそれは変わりません。
今期のおとめ座のキーワードは、「身体と私」。 『マトリックス』に影響を与え、ハリウッド映画やアニメにもなって改めて知られるようになってきた士郎正宗の『攻殻機動隊』(漫画原作は1995年に刊行)の世界では、人間はサイボーグ化され、身体は自由に付け替えのきく「義体」と呼ばれるものとなっていますが、それでも、その世界は主人公・草薙素子(くさなぎもとこ)の視点に中心化された世界であり、ストーリーのなかで義体が破壊された際にもそれは変わりません。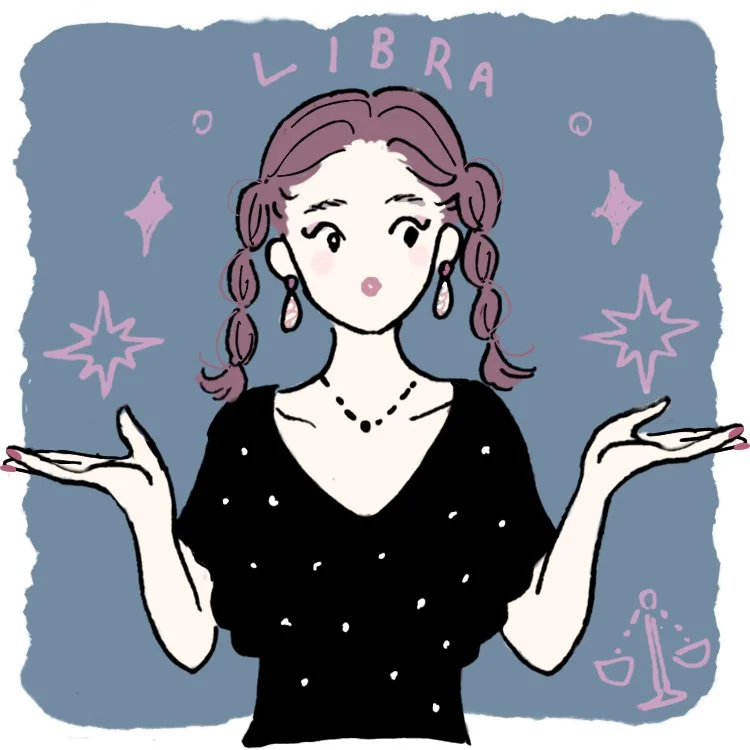 今期のてんびん座のキーワードは、「思い出のクォリティー」。 人工知能との比較で、人間のもつ想起的な記憶(思い出)の重要性が再評価されてきている今、数世紀の時代をこえてぜひ思い出していきたい人物のひとりにレオナルド・ダ・ヴィンチがいます。
今期のてんびん座のキーワードは、「思い出のクォリティー」。 人工知能との比較で、人間のもつ想起的な記憶(思い出)の重要性が再評価されてきている今、数世紀の時代をこえてぜひ思い出していきたい人物のひとりにレオナルド・ダ・ヴィンチがいます。 今期のさそり座のキーワードは、「内なる狂気」。 「狂気」はきわめて現代的な問題のひとつと言えます。というのも、狂気がどう規定されるかは、その本質上、時代や社会との関係に極めて密接に結びついており、古代社会から現代の資本主義社会にいたるまで、人間社会ではさまざまな表情の「狂人」がつくり出されてきたからです。
今期のさそり座のキーワードは、「内なる狂気」。 「狂気」はきわめて現代的な問題のひとつと言えます。というのも、狂気がどう規定されるかは、その本質上、時代や社会との関係に極めて密接に結びついており、古代社会から現代の資本主義社会にいたるまで、人間社会ではさまざまな表情の「狂人」がつくり出されてきたからです。 今期のいて座のキーワードは、「詩人の務め」。 小林秀雄が『ランボオ論』の書き出しで、「向うからやつて来た見知らぬ男が、いきなり僕を叩きのめしたのである」とその衝撃を表現してみせたことはあまりにも有名ですが、彼以外にもアルチュール・ランボーは日本の多くの若者や文学者たちに強烈なインパクトを与えてきました。
今期のいて座のキーワードは、「詩人の務め」。 小林秀雄が『ランボオ論』の書き出しで、「向うからやつて来た見知らぬ男が、いきなり僕を叩きのめしたのである」とその衝撃を表現してみせたことはあまりにも有名ですが、彼以外にもアルチュール・ランボーは日本の多くの若者や文学者たちに強烈なインパクトを与えてきました。 今期のやぎ座のキーワードは、「未熟の惑星」。 映画化もされた小説『存在の耐えられない軽さ』(1984)で有名になったチェコ出身のミラン・クンデラには、あまり知られていませんが『七十三語』(1986)という味わい深い私家版の用語集があり、中でも「未熟」の項に書き添えられた次のような一文は非常に印象的です。
今期のやぎ座のキーワードは、「未熟の惑星」。 映画化もされた小説『存在の耐えられない軽さ』(1984)で有名になったチェコ出身のミラン・クンデラには、あまり知られていませんが『七十三語』(1986)という味わい深い私家版の用語集があり、中でも「未熟」の項に書き添えられた次のような一文は非常に印象的です。 今期のみずがめ座のキーワードは、「平常心の試み」。 最近、TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSサービスは今や怒りや嫉妬、傲慢など負の感情の温床と化しているという話を目にしました。
今期のみずがめ座のキーワードは、「平常心の試み」。 最近、TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSサービスは今や怒りや嫉妬、傲慢など負の感情の温床と化しているという話を目にしました。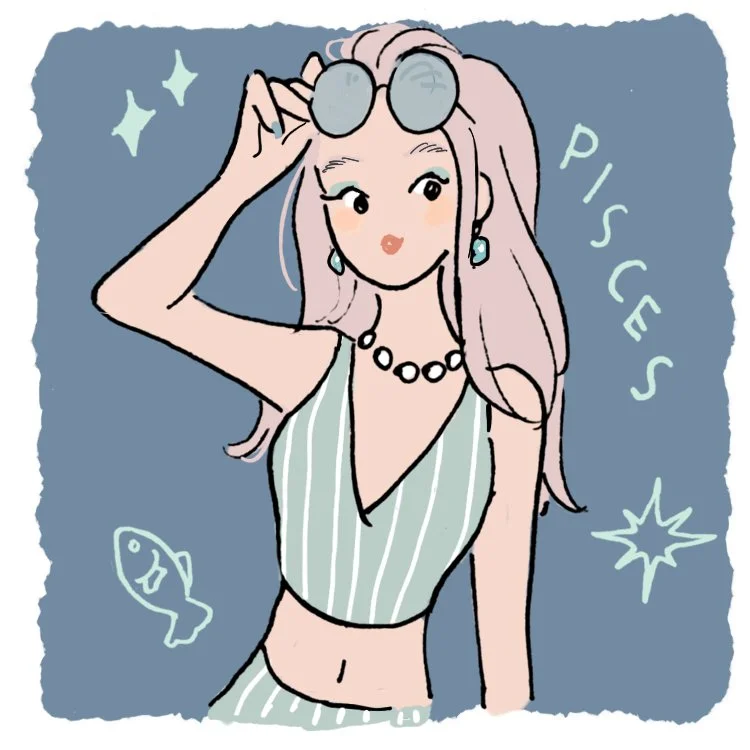 今期のうお座のキーワードは、「一日の円」。 資本主義で回る現代社会というのは、つくづく他人の欲望に踊らされ続ける人生が量産される社会であり、人々はうらやましがったり、愚痴をこぼしたり、不満や怒りを訴えたりしながら、労働や人間関係などを通して、気安く他人に時間を与えてばかりいるという実感が、最近人々の間でにわかに深まってきたように感じます。
今期のうお座のキーワードは、「一日の円」。 資本主義で回る現代社会というのは、つくづく他人の欲望に踊らされ続ける人生が量産される社会であり、人々はうらやましがったり、愚痴をこぼしたり、不満や怒りを訴えたりしながら、労働や人間関係などを通して、気安く他人に時間を与えてばかりいるという実感が、最近人々の間でにわかに深まってきたように感じます。










































































