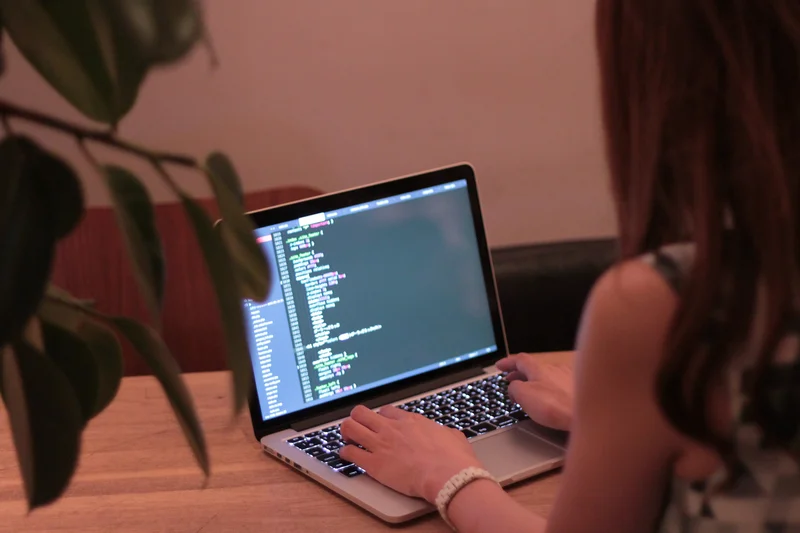-

【SUGARさんの12星座占い】<3/21~4/3>の12星座全体の運勢は?
「花時へ立ち返る」
いよいよ3月20日に「春分」を迎え天文学的にも春となり、その後はじめての満月が3月29日にてんびん座8度(数え度数で9度)で形成されていきます。
今回のテーマは「触発されること」。たとえば、過去の偉大な芸術や文学作品の洗練された様式に触れることは、瞑想と同じような効果があるのではないでしょうか。いずれにせよ、混沌とした社会の中で新しい価値をさがそうとして迷っている時には、まずもって原点に立ち返ることが重要です。
ちょうど、この時期の季語に「花時」という言葉があります。古くから、花と言えば桜。ですから、普通は「花時」といえば、桜の花が美しく咲いているあいだのことを言うのですが、とはいえ、私たちは桜が咲く前からいつ咲くかと心待ちにしたり、散り始めてからの方がより風情を感じたりと、それぞれにとっての「花時」を持っていたように思います。
松尾芭蕉の「さまざまな事思ひ出す桜かな」という俳句のように、その時々に刻まれた思い出は、桜を見るたびに何度も蘇ってくるもの。もしかしたら、ひとりひとりの心の中に、「花時」という特別な時間軸があるのかも知れません。
その意味で、今期は自分のこころをもっとも触発してくれるような「花時」に立ち返っていけるか、そこでしみじみとしていけるかということが、大切になってくるはずです。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「死者のまなざしに触れる」。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春分を過ぎるとようやく気温も安定してきますが、春分をはさんだ7日間をさす「彼岸」はそうした体感温度の切り替え時であるだけでなく、昔から極楽浄土に最も近づける期間とされ、先祖や故人の霊と向き合ってきたものでした。
「草葉の陰」などとも言うように、キリスト教圏などとは違って日本人にとって、あの世はかぎりなくこの世に近く、死者は<すぐそこ>にいるものと考えられてきました。
たとえば、民俗学的な資料のあとづけのもと、そうした「日本人の他界観」をはじめて明確に言語化した柳田國男の『先祖の話』によれば、そこには4つの特徴があるのだそうです。
「1. ひとは、死んだあとでも、この国のなかに、霊としてとどまる。この国から超絶した彼方に往くとは、思っていない。
2. あの世とこの世という幽顕二界のあいだの交通が、頻繁におこる。定期的な祭りばかりではなく、死者からも生者のがわからも、招き招かれるという生死往還、彼此往来が、そんなに困難なことではなかった。
3. 生前の念願は死後にも達成される。だから死者は、子孫のためいろんな計画を立てて、子孫を助けている。
4. 死者はふたたび、みたびこの世に再生すると思っていた者もおおかった。」
こうした近傍他界観によれば、なにか特別な別世界などというものはなくて、もし他界にひらくまなざしがあるとすれば、それはこの世を見ている(ただし別角度から)ということになります。
そうだとするなら、私たち生者のまなざしの中に死者のまなざしが重なる瞬間というのは、そう珍しいことではなく、日常的に起きていることになりますし、これから迎えていくお彼岸の時期というのは、新たに生者のまなざしに死者が住みつくタイミングでもあるのかも知れません。
今期のおひつじ座は、そんな風に死者の存在や彼らなりのまなざしに改めて触れていくことがテーマとなっていきそうです。
参考:柳田國男『先祖の話』(角川ソフィア文庫)
-

今期のおうし座のキーワードは、「裂け目と浮雲」
さいきん「風の時代になれば~」と夢みたいなことばかり書き連ねてあるのをよく見聞きしますが、前回の風の時代にあたる鎌倉時代前期に書かれた『方丈記』には、大飢饉や自然災害に加え悪疫流行によってまさに地獄と化したこの世で苦しみあえぐ人びとの様子が克明に描かれていました。
その中には、あの有名な「さりがたき妻・をとこ持ちたるものは、その思いまさりて深きもの、必ず先立ちて死ぬ。その故は、わが身は次にして、人をいたはしく思ふあいだに、稀稀得たる食ひ物をも、かれに譲るによりてなり」という一節も出てくるのですが、1945年3月の東京大空襲のただなかにあった作家・堀田善衛はこうした方丈記の記述の中に、自身の戦中体験を再発見していったのでした。
そして飢えや地震などの描写の他にもう一つ、堀田の心に響いたのは「戦禍の先にある筈のもの」である「新たなる日本についての期待の感及びそのようなものは多分にありえないのではないかとい絶望の感」がそこに見出されたためとも述べています。
さらに鴨長明の「古京はすでに荒れて、新都はいまだ成らず。ありとしある人は皆浮雲の思ひをなせり。」という一文を引いて、堀田は次のように続けています。
「断裂、亀裂、裂け目そのもの、裂け目それ自体、地震のくだりのことばを使うなら、「土裂けて」の、その裂け目自体の上に、というか、裂け目のなかに、というか、とにかくそれ自体のところに在らせしめられたものの思いが、すなわち「浮雲の思ひ」なのであった。新都、すなわち新たなる日本についてのイメージ、あるいはその期待に具体性を付与できる人ならば、決して「浮雲の思ひ」などをなす筈はないのだ。」
ここでいう「断絶」や「裂け目」という言葉は、これまで当たり前のように持続してきたものが、ある日を境に突然、必然でも自然でもなくなってしまった新たなる事態に襲われた人の感じをよく言い表しているのではないでしょうか。
今期のおうし座もまた、そうした「断絶」や「裂け目」のなかで、みずから「浮雲」となって、堀田が方丈記から受け取ったような歴史感覚や歴史というものの実在感、歴史というものがあるからこそ自分が持たなければならない不安に触発されていくことになるかも知れません。
参考:堀田善衛『方丈記私記』(ちくま文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「伝統的な生命リズムとしての五七調」。
今の政治システムや社会のあり方に対して、日本の若者たちはよくも黙っていられるものだ――。
ここ数年、いやより厳密にはSEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)が2016年8月に解散したからしばらく時間がたち、記憶が風化し始めてから、またそんな嘆きにも似た感想をよく耳にするようになった気がしますが、果たしてそうだろうかと考えたとき、改めて思い出されてくるのが1960年代から70年代初頭にかけて学生が主体となって行われた全共闘運動です。
世間の回顧的批評によれば、それは「戦後民主主義批判」をというスローガンを掲げ、文化大革命に影響を受けて展開された若者たちの異議申し立てということになりますが、哲学者の山折哲雄は次のように述べていました。
「だがほんとうのところをいえば、われわれの日常生活を律してきた古典的リズムへの藩校、伝統的な生活感覚への反逆を意味していたのである。」
「全共闘運動というのは、五七調とか七五調とかいうリズムを破壊するための運動だったのかもしれない。「短歌的抒情」を全面的に否定するための無意識の叫びであったのだろう。」
「「政府の……」とか「日本国家は……」とか「大学教官たちの……」とかのかれらの演説調の言葉が、その字数のいかんを問わず、すべて五五調にのせられて発音されていたからである。」
山折によれば、1987年に「与謝野晶子以来の大型新人歌人」としてデビューした俵万智の『サラダ記念日』が記録的大ヒットしたのも、「あの灰色の五五調の退屈さ」に飽き飽きしていたところに「われわれの意識下に眠らされていた五七調というリズムをあらためて気づかせ」「和歌の伝統的な生命リズムがそれを触媒にして快く刺激された」からではないかと述べています。
ただ、1987年という年は日本の貿易黒字が過去最高を記録した「バブル元年」でもあり、息を吹き返した「伝統的な生命リズム」は軽やかな広告コピーと歩調を合わせていきましたが、その点、2021年現在の日本経済はまさにそれとは対照的な様相を呈しているように思えます。
今期のふたご座もまた、古くて新しい言葉のリズムであり、日本の伝統的な生命リズムである「五七調」に立ち返りつつ、今という時代だからこそそこに乗せていくことのできる感受性のありようを模索してみるといいでしょう。
参考:山折哲雄『歌の精神史』(中公文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「無縁と横断」。
経済生活ということを人生の中心に据えている現代の日本人は、何をするにしてもどこかで貨幣に縛られてしまっているところがありますが、こうした「目に見えない」精神の在り様が目に見える「お金」に縛られてしまうという関係性の在り方について、どのように理解したらいいのでしょうか。
その点で参考になるのが、歴史学者の網野善彦の『無縁・公界・楽』です。ここで網野は「無縁」すなわち「縁切り」ということをテーマにしています。
「縁」という仏教用語が下敷きになっていることからも分かるように、「無縁」とは年貢や地縁などさまざまな形でひとを縛りつける支配関係や決まりごとに対する民衆の生活そのものの底から湧きおこってくる自由・平等・平和の理想への本源的な願いを表現した言葉であり、網野によればそうした無縁の原点は他ならぬ「家」にあるのだと言います。
家と言えば、資本主義社会では「私的所有の原点」とされていますが、中世日本では逆に「垣の内は氏神の守る聖域」であり「権力の介入を排除できる「不入」の場」とされ、外ではどんな仕事をして、誰と付き合っていようと、いったん家に帰れば社会と関わるすべての縁が切れて、世俗から無縁なところで生きていける平和領域だったのです。
つまり、そこでは無縁とは「目に見えない世界」のことで、かつての日本人はこの「無縁」を“てこの原理”にして横のつながりをも作っていきました。例えば、網野は時宗の一遍上人を取りあげ、そこでは乞食であろうが遊女であろうが侍であろうが、いったん一遍上人のグループに入ると、「~アミ」という名前を名乗ってフラットな関係の仲間になったのだと述べています。
確かに、『一遍聖絵』などを見ると、ハンセン病にかかっている病人や遊女や乞食などが集まって、楽しそうに一緒に暮らしており、日本にもかつてはそういう伝統があったことが分かります。
今期のかに座もまた、どうしたら自分の生活にそうした「無縁の原理」を持ち込めるのか、それによって様々なしがらみを横断していけるか、ということを考えてみるといいでしょう。
参考:網野善彦『無縁・公界・楽』(平凡社ライブラリー)
-

今期のしし座のキーワードは、「TAZ」。
コロナ禍におけるリモートワークやオンラインツールの普及は、企業と個人との関係性を確実に変えただけでなく、平成の時代に抱かれていたようなインターネットの持つツールとしての可能性に、令和に変わって改めて光を当てられるきっかけとなっていったように思います。
ここで思い出されるのが、90年代に覇権主義的なグローバリズムへの抵抗として書かれ、世に出たハキム・ベイの『T.A.Z.―一時的自律ゾーン、存在論的アナーキー、詩的テロリズム』です。
本のタイトルである「T.A.Z.」すなわち「一時的自律ゾーン」とは、「古い社会の殻の内部での新しい社会の核心を築く」ための一形態であり、たえず新しい世界状況に適合させるために「リライト」されねばならないものとして構想されました。
例えば、2001年のアメリカにおける同時多発テロ事件は反グローバリズムの動きが強まる大きなきっかけとなりましたが、2003年に書かれた第二版のまえがきには、次のような一節があります。
「「TAZ」は、地理的な嗅覚、触覚、味覚を備えた肉体的空間に存在せねばならない(サイズからすると、いわば、大都市に対するダブルベッドの大きさ)――さもなければ、「TAZ」は、もはやひとつの青写真か夢想でしかない。ユートピア的な夢は、(中略)生きられた生、現実的存在、冒険そして愛の代わりにはならないものである。仮にあなたが、メディアというものを生活の中枢とするならば、あなたは、媒介された/メディア化された生を送ることになる―しかし「TAZ」は、メディアを介さない直接的なものであることを、さもなくば無であることを望むのである。」
2021年現在、フリーランスという言葉が人工に膾炙し、大企業が積極的に副業を認めるようになってきつつある世の中の流れにおいて、「自律」ということはますます「あった方がまし」なものとして、相対的にその必要性が増してきていることは確かでしょう。
「TAZは、空間よりも、時間への流動的な関連の中に存在する。それは、真に一時的なものであるが、恐らくはまた、休日、バカンス、夏休みのキャンプといった繰り返す自律のように、周期的に訪れるものでもあるだろう。それは、首尾よく成功したコミーン、あるいは放浪者の小領域のように、「恒久的」自律ゾーンである「PAZ(パーマネントなTAZ)」となれるかも知れない。」
その意味で今期のしし座もまた、自分なりの「TAZ(一時的自律ゾーン)」をいかに日常に組み込み、生存に関する一つの実験を試みていけるかが問われていくのではないでしょうか。
参考:ハキム・ベイ、箕輪裕訳『T.A.Z.―一時的自律ゾーン、存在論的アナーキー、詩的テロリズム〔第2版]』(インパクト出版会)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「つれづれ」。
3月は別れの季節であり、あちこちの職場や学校で多くの人が別れを迎え、そこでは「さよなら」と同じ数だけ「ありがとうございました」という言葉もまた交わされていきます。
言葉の来歴からすれば、もともとは「有り難い」つまり、めったにないがゆえに尊く喜ばしいという思いが、やがて、その稀有なことをあらしめた何事か、あるいは何ものかに対する感謝となってきたということだと思いますが、ただ日本においてそれは、何によってかは分からない「ありがたき不思議」という文脈において積極的に使われてきたのではないでしょうか。
つまり、仏教的には「ご慈悲」や「ご縁」という言い方で、より一般的には「おかげさま」とも言われてきたところの何ものかにおいて表象されてきたのではないか、と。
倫理学者の竹内整一は『やまと言葉で哲学する』の中で、そうした生きて在ることの「ありがたき不思議」に通底するものを、例えば吉田兼好『徒然草』の死生観に見出しています。
「兼好は、死とは、いつか来るというものではなく、「かねて後に迫れり(すでに前もって背後に迫っているものだ)」(一五五段)と言う。それゆえ、「思ひかけぬは死期なり。今日までのがれ来にけるは、ありがたき不思議なり」(一三七段)と説くのである。」
「兼好は、だからこそ、その日その時を楽しんで過ごせ、と言うのである。「つれづれ」とは、無目的ということであるが、たんなる暇つぶしの意味ではない。その日、その時を何か今あること以外の目的のためだけに費やして生きることの否定であり、今ここでしたいと思う事をするという「今・ここ」の積極的な肯定のすすめなのである。」
「兼好にとっては、この眼前の日常現実は、それ自体、本来ありえなかった「ありがたさ」の折り重なりとして感受されていたのである。」
「感謝」について考える際にも、こうした「本来ありえなかった」という前提に立つことは不可欠な観点ですが、改めて兼好がその上での「「今・ここ」の積極的な肯定」を「モチベーション」などのいかにも他人事然とした白々しい言い方ではなく、あえて力みの抜けた「つれづれ」という言葉で表わしたことは、日本文化の到達点の一つと言っても過言ではないでしょう。
今期のおとめ座もまた、今ここに在ることができる不思議に感じ入りつつ、「つれづれなるままに」筆を取るなり、誰かへのプレゼントを選ぶなり、手料理を振る舞うなりしてみるといいかも知れません。
参考:竹内整一『やまと言葉で哲学する』(春秋社)
-
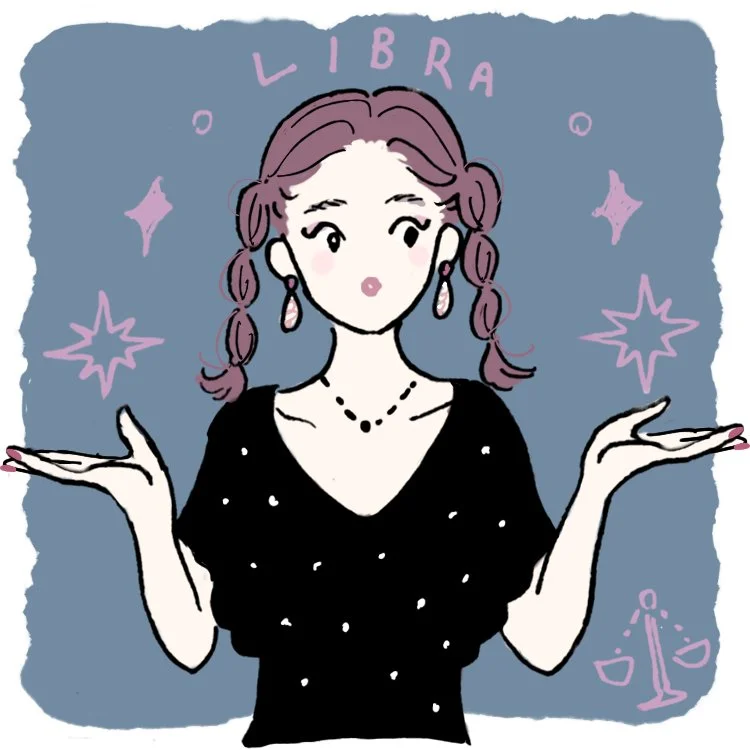
今期のてんびん座のキーワードは、「仮住まいの花」。
春がやってきて、道の脇の小さな草花やきらきらと反射する川の流れを眺めながら、ぷらぷらと歩いているうちに、思わず気が緩んで、この人生は、この現実は、このわたしは、夢ではないか。と、頬をつねってみてもまだ信じられないような感覚に襲われる人は少なくないんじゃないかと思います。
いつからか、そんな風に「仮定された有機交流電燈」のような気分になった時には、漢詩を読むようになっていったのですが、最近は、もっぱら俳人の小津夜景さんの『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』という数々の漢詩をみずからの手で訳し、そこに瑞々しいエッセイを添えた本を開くことにしています。
例えば、北宋の女詩人である謝希孟の「芍薬」という詩について書かれた「仮住まいの花」。
「かりそめの花の香りよ
つかのまの夢の一生(ひとよ)よ
だからこそ笑って贈る
この歌に想いをのせて」
「ほんとうのわたし、という物語など気にもとめず、かりそめの生、うたかたの世、うつしよの言といった虚構を堂々と生きる女性ならではの気品がある。この手の気品を綺麗に写しとるには、歌謡の香りをふんだんに薫きしめた訳がふさわしい。たとえば、」
「つゆのまの花のかんばせ
いのちあるもののはかなさ
たはむれにさしあげませう
つかのまのよろこびのため」(小池純代・訳)
「じぶんもこんなふうに、シュレーディンガーの猫的に、存在論的幽霊的に、底なしに奥行きのないリヴァーシブルな死生をうふふと味わいつつ、蛍のように明滅してゆきたい」
ああ、もう。どうしたらこんな風に言葉を紡げるのだろう、と感嘆してしてしまいますが、今期のてんびん座もまた、こうした「こよなき言葉、いとしい意味」を、さらさらと我が身を通して流していく時間を大切にしていけるといいのですが。
参考:小津夜景『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版)
-

今期のさそり座のキーワードは、「縞柄」。
桜の花の咲きぶりや散り具合、そしてそうした光景を描いた浮世絵などの近代以前の奥行きのない世界を見ていると、案外、高度な精神の現れというのは、モノや文様のパターンなど、目に見える具体的な形で表わされているのではないかと、改めてハッとさせられるのですが、江戸文化研究家の田中優子も『江戸百夢 近世図像学の楽しみ』の中で、着物の縞(しま)柄つまりストライプ模様について触れて同様のことを述べています。
「九鬼周造は『「いき」の構造』の中で、「模様としての縞」が『いき』と見做されるのは決して偶然ではない」と書いた。なぜなら、「いき」の表現は「媚態」のもっている二元性を表わしていなければならず、「永遠に動きつつ永遠に交わらざる平行線」としての縞は、その二元性のもっとも純粋な表現だからだ、と。」
「いったいこの媚態の二元性とは何か。九鬼によれば「一元的の自己が自己に対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度」のことである。ひらたく言えば、惚れた相手と同一化したいと思っているあいだの緊張した状態のことだ。だから、完全に同一化してしまえば関係は「いき」でなくなる。しかし個人と個人が完全に同一化するなどあり得ないことだから、幸福な幻想さえもたなければ、惚れ合っていてもおおいに「いき」であり得る。縞とはつまりそういうことの現れだと思うと、着物の文様もばかにできない。」
「この場合「いき」であり得る縞は横縞でなく縦縞でなければいけない。縦縞は「軽巧精息の味が一層多く出ているため」だ。」
ところで、この縞というのはもともとセイラス島、ベンガラ島、サントメ島、チャンパ島などの東南アジアの「島」のことだったのだそうです。つまり、やがて「いき」の象徴となる縦縞はアジアの古い記憶を宿した文様であり、それを取り入れていった日本とアジアの関わりにこそ、高度な「いき」の精神の原点なのではないでしょうか。
今期のさそり座もまた、縞柄の着物や小物をさりげなく身につけ、文字通り「いき」の精神を我が身に宿してみるといいかも知れません。
参考:田中優子『江戸百夢 近世図像学の楽しみ』(朝日新聞社)
-

今期のいて座のキーワードは、「横断的な戦術」。
IT技術やAIの導入によって余暇が増えるどころか、現代人がますます忙しくなってきているように感じるのは、単純に物理的な時間が足りなくなっているからではなく、おそらく労働と余暇のあいだの境界線があいまいになってしまったからではないでしょうか。
もはや余暇は「いい仕事をするため」には必要不可欠なイケてる社会人の条件であり、とはいえ余暇が多過ぎればそれはそれで「単なるヒマ人」として忌避される。そうした状況では労働と余暇はたがいに同質化しつつあり、縛りあいながらもそこにコミットしている人間の生を均質化して、真の意味での遊びをそこから追い出してしまう。
では、どうすればいいのか。フランスの哲学者ミシェル・ド・セルトーは『日常的実践のポエティーク』の中で、押しつけられた秩序に従いつつも、「職場の隠れ作業」のように「なんとかやっていく」手法をとりあげ、こうした「横断的な戦術」は使う人の特質を活かしながら、そこに「遊び(ゲーム)を作り出していくとして、次のように述べています。
「たとえば(家でも言語でも)、故郷のカビリアに独特の「住みかた」、話しかたがあり、パリやルベーに住むマグレブ人は、低家賃住宅の構造やフランス語の構造が押しつけてくるシステムのなかにこれをしのびこませるのである。かれは、二重にかさねあわせたその組み合わせによって、場所や言語を強制してくる秩序をいろいろなふうに使用するひとつのゲーム空間を作り出す。」
「否応なくそこで生きてゆかねばならず、しかも一定の掟を押しつけてくる場から出てゆくのではなく、その場に複数性をしつらえ、創造性をしつらえるのだ。二つのもののあいだで生きる術を駆使して、そこから思いがけない効用をひきだすのである。」
セルトーはこうした「もののやりかた」について、「(軍事的な意味での)「作戦」の意、特有の型式と創意をそなえつつ、蟻にも似た消費作業をひそかに編成してゆくさまざまな作戦の意をこめ」て、「使用法(usages)」と名付けています。
今期のいて座もまた、労働を増やすのでもなく、単に余暇を取得するのでもない、第三のやり方としての与えられた状況で「なんとかやっていく」ための「使用法」の実践ということがテーマとなっていくのではないでしょうか。
参考:ミシェル・ド・セルトー、山田登世子『日常的実践のポエティーク』(ちくま学芸文庫)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「古代の哲学者たちのように」。
「風の時代」という言葉がひとり歩きして、どうも占星術における風=思考機能という定義からだいぶかけ離れた社会展望がそこかしこで語られているような状況が生まれていますが、いずれにせよ現時点で確実に言えることは、これからの「風の時代」ますます「自分なりに考えてみる」ことの重要性や緊急性は増していくだろうということ。
そうした「自分なりに考えてみる」の最も古典的な元型は「哲学者」という人種でしょう。とはいえ、最初の哲学とされるタレスや、占星術におけるエレメントの考え方のルーツともなっているエンペドクレスなど、ソクラテス以前の“古代ギリシャの哲学者たち”は、現代における「哲学者」という言葉のイメージとはかけ離れた、ひとりひとりが一宗を興すほどの宗教家であり、実践家でもありました。
彼らは「神」というチート概念を用いずにこの世界の成り立ちを説明するモデルを、自分なりに編み出していった人びとでもあった訳ですが、そんな“古代の哲学者たち”と現代のそれとの違いについて、ルーマニア出身の思想家シオランは、『思想の黄昏』の中で次のように極めて辛辣な筆致で述べています。
「古代の哲学者たちと現代の哲学者たちとを分かつもの――きわめて明瞭な相違であり、そして後者にとってはきわめて都合の悪い相違であるが――は、後者が仕事机で、書斎で哲学したのに対して、前者が庭園で、市場で、あるいはどこかは知らぬ海岸を歩きながら哲学したことに由来する。」
「そして現代の哲学者たちよりも怠惰な古代の哲学者たちは、長いあいだ横になっていたものだ。というのも、彼らは霊感が水平にやってくることを知っていたからである。そんなわけで、彼らは思想の来るのを待っていたのである。現代の哲学者たちは読書によって思想を強制し、挑発する。そういう彼らの姿からは、瞑想の無責任性なるものの歓びをいまだかつて知ったこともなく、そのさまざまの観念を企業家はだしの努力をもって組織したのだ、という印象を抱かせられる。」
こうしたシオランの言にひと言加えさせてもらうならば、古代の哲学者たちと現代の哲学者たちとを分かつものに「闇の深さ」の体験も挙げられるのではないでしょうか。書斎や読書で哲学が可能なのは、電気が発明され普及していったためであり、それが精神に与える影響もまた想像以上に大きかったのではないかと思います。
今期のやぎ座もまた、いっそ自分が古代の哲学者たちになったつもりで、「霊感が水平にやってくること」、「思想の来るのを待」つことに徹してみるといいでしょう。
参考:エミール・シオラン、金井裕訳『思想の黄昏』(紀伊国屋書店)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「動物のまなざし」。
夜道をひとり、なんとなく心許なく感じながら歩いているとき、目の前に突然何かが飛び出してくる。幽霊か?いや獣だ(こんな現れ方は獣にしかできない)。暗闇に光る二つの目。思わず目が合う……。ただ、それはよく見たら猫だった。なーんだ。ただしばらくしてから、その一瞬の邂逅が最近の他のどんな出来事よりも鮮明な印象を自分の中に残していたことに気が付く―。
そんな経験をしたことはないだろうか。猫のところは、犬でもタヌキでもオコジョでもいい。ここで大事なのは、もしかしたら人間が支配する世界も、獣が支配する世界もないのではないかという考えです。
つまり、「あるのはただ、移り変わり、かりそめの支配、機会、逃走、そして出会いだけ」かも知れないということ。
そう述べたのは、フランスの思想家ジャン=クリストフ・バイイであり、彼は『思考する動物たち』という著書の中で、例えばラスコーの壁画に描かれたような、人間と動物との聖なる絆のネットワークにおいて「具現化されていたぞくぞくするような絆は、半透明になり、ほとんど消えつつある。だが、私たちが少しでも注意を払って、彼らが存在し、動いているのを見さえすれば、どの動物もみな記憶の保有者であることが分かるだろう。記憶とは、動物にも私たちにもあずかり知れぬものだが、そこには動物という種と私たち人間との軋轢が刻み込まれている」と書いています。
ここでバイイが語ろうとしているのは、人間から動物へ、動物から人間への侵犯についてではなく、そのわずかな接触からなる接近であり、そうした接近において起きてくる人間中心主義の解体についてです。
そこで明らかになるのは、「私たちの生きている世界が他の生物たちから見られているということ」。バイイはさらに続けてこう結んでいます。
「可視の世界は生き物たちの間で共有されている。そして、そこから政治が生まれるかもしれない―手遅れでなければ。」
今期のみずがめ座もまた、そうした太古からそこにいた先行性をもった存在としての動物に、自分なりの接近を通して開かれていくことになるかも知れません。
参考:ジャン=クリストフ・バイイ、石田和男・山口俊洋訳『思考する動物たち』(出版館ブック・クラブ)
-
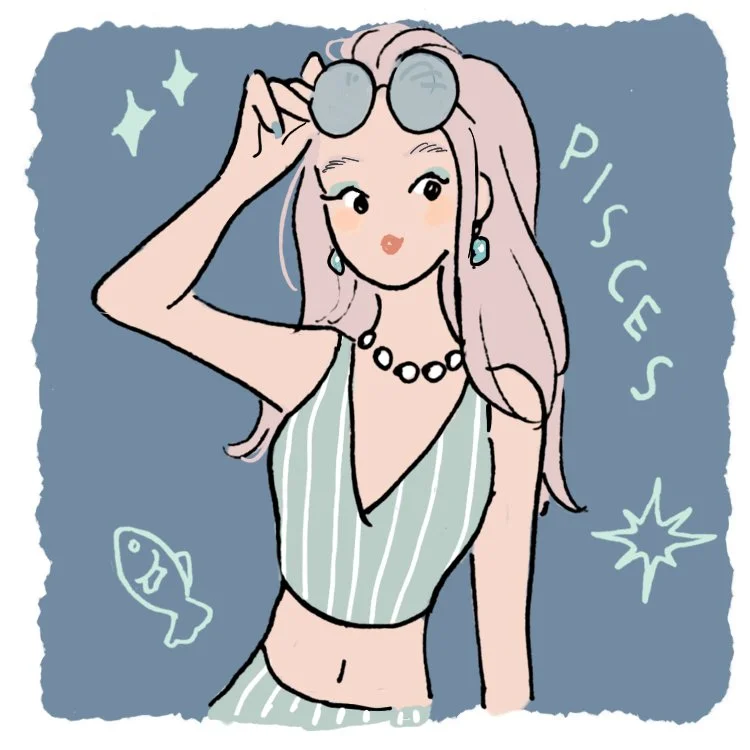
今期のうお座のキーワードは、「無限の悲しみへのたしかな自覚」。
文明以前ということをすっかり見失ってしまった現代人は、事の当然の帰結としてこの世界においてひどく傷つきやすい存在となってしまい、311を経た今もなお強情に文明への“引きこもり”を決め込んでいるようなところがありますが、そうした人間の悲しさを小説の世界で描いてみせたのがポール・ボウルズの『シェルタリング・スカイ』でした。
話は第二次世界大戦後のニューヨークから始まり、倦怠期の夫婦であるポートとキットが、親友のタナーを伴ってアフリカ旅行へおもむくところから始まります。
この旅行は一応は夫婦関係の修復が目的なのですが、一行が北アフリカのアルジェからサハラの奥へと向かううちに、夫婦はやはりうまくいかなくなり、キットはタナーに身を許し、ポートはチフスに罹って苦しんだのちあっけなく死んでしまいます。
それを機にタナーは別行動を取り、ひとり残されたキットは途中さまざまなことを経験したのち、半ば錯乱状態となって旅の始まりの街であるアルジェへと戻ってきてたところで話は終わる。なんとも突き放されたような、切ないような、言葉にできない読後感が残るのですが、ここで改めて小説の冒頭で、男が眠りから覚めてから抱くある思いを振り返ると、これこそがこの小説の核心だったのかという不思議な納得感が広がるのです。
「どこかしらある場所に彼はいた。どこでもない場所から、広大な地域を通って戻ってきたのである。意識の革新には、無限の悲しみへのたしかな自覚があった。しかしその悲しみは心強かった。というのは、ただそれだけが馴染みのあるものだったからだ。」
これは生誕によって時間の中に入ったことをきっかけに始まった存在論的分離の追体験であり、自分が世界における異邦人なのだという自覚の再生産に他なりません。ただ、現代人がそうして自己を欠如のあらわれとして把握する機会さえ失いつつあることを思えば、やはり立ち返るべき原点なのだと言えるのではないでしょうか。
今期のうお座もまた、この小説の登場人物のように文明がその帰結として持たざるを得ず、何より自身がすでに抱えてしまっている“悲しさ”ということに想いを馳せてみるといいかも知れません。
参考:ポール・ボウルズ、大久保康雄訳『シェルタリング・スカイ』(新潮文庫)
 【SUGARさんの12星座占い】<3/21~4/3>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<3/21~4/3>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「死者のまなざしに触れる」。 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春分を過ぎるとようやく気温も安定してきますが、春分をはさんだ7日間をさす「彼岸」はそうした体感温度の切り替え時であるだけでなく、昔から極楽浄土に最も近づける期間とされ、先祖や故人の霊と向き合ってきたものでした。
今期のおひつじ座のキーワードは、「死者のまなざしに触れる」。 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春分を過ぎるとようやく気温も安定してきますが、春分をはさんだ7日間をさす「彼岸」はそうした体感温度の切り替え時であるだけでなく、昔から極楽浄土に最も近づける期間とされ、先祖や故人の霊と向き合ってきたものでした。 今期のおうし座のキーワードは、「裂け目と浮雲」 さいきん「風の時代になれば~」と夢みたいなことばかり書き連ねてあるのをよく見聞きしますが、前回の風の時代にあたる鎌倉時代前期に書かれた『方丈記』には、大飢饉や自然災害に加え悪疫流行によってまさに地獄と化したこの世で苦しみあえぐ人びとの様子が克明に描かれていました。
今期のおうし座のキーワードは、「裂け目と浮雲」 さいきん「風の時代になれば~」と夢みたいなことばかり書き連ねてあるのをよく見聞きしますが、前回の風の時代にあたる鎌倉時代前期に書かれた『方丈記』には、大飢饉や自然災害に加え悪疫流行によってまさに地獄と化したこの世で苦しみあえぐ人びとの様子が克明に描かれていました。 今期のふたご座のキーワードは、「伝統的な生命リズムとしての五七調」。 今の政治システムや社会のあり方に対して、日本の若者たちはよくも黙っていられるものだ――。
今期のふたご座のキーワードは、「伝統的な生命リズムとしての五七調」。 今の政治システムや社会のあり方に対して、日本の若者たちはよくも黙っていられるものだ――。 今期のかに座のキーワードは、「無縁と横断」。 経済生活ということを人生の中心に据えている現代の日本人は、何をするにしてもどこかで貨幣に縛られてしまっているところがありますが、こうした「目に見えない」精神の在り様が目に見える「お金」に縛られてしまうという関係性の在り方について、どのように理解したらいいのでしょうか。
今期のかに座のキーワードは、「無縁と横断」。 経済生活ということを人生の中心に据えている現代の日本人は、何をするにしてもどこかで貨幣に縛られてしまっているところがありますが、こうした「目に見えない」精神の在り様が目に見える「お金」に縛られてしまうという関係性の在り方について、どのように理解したらいいのでしょうか。 今期のしし座のキーワードは、「TAZ」。 コロナ禍におけるリモートワークやオンラインツールの普及は、企業と個人との関係性を確実に変えただけでなく、平成の時代に抱かれていたようなインターネットの持つツールとしての可能性に、令和に変わって改めて光を当てられるきっかけとなっていったように思います。
今期のしし座のキーワードは、「TAZ」。 コロナ禍におけるリモートワークやオンラインツールの普及は、企業と個人との関係性を確実に変えただけでなく、平成の時代に抱かれていたようなインターネットの持つツールとしての可能性に、令和に変わって改めて光を当てられるきっかけとなっていったように思います。 今期のおとめ座のキーワードは、「つれづれ」。 3月は別れの季節であり、あちこちの職場や学校で多くの人が別れを迎え、そこでは「さよなら」と同じ数だけ「ありがとうございました」という言葉もまた交わされていきます。
今期のおとめ座のキーワードは、「つれづれ」。 3月は別れの季節であり、あちこちの職場や学校で多くの人が別れを迎え、そこでは「さよなら」と同じ数だけ「ありがとうございました」という言葉もまた交わされていきます。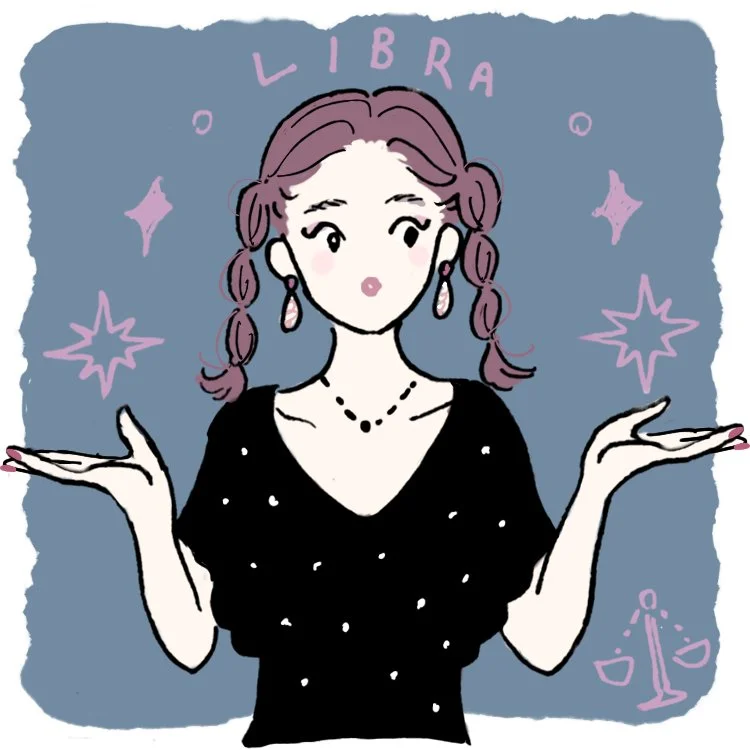 今期のてんびん座のキーワードは、「仮住まいの花」。 春がやってきて、道の脇の小さな草花やきらきらと反射する川の流れを眺めながら、ぷらぷらと歩いているうちに、思わず気が緩んで、この人生は、この現実は、このわたしは、夢ではないか。と、頬をつねってみてもまだ信じられないような感覚に襲われる人は少なくないんじゃないかと思います。
今期のてんびん座のキーワードは、「仮住まいの花」。 春がやってきて、道の脇の小さな草花やきらきらと反射する川の流れを眺めながら、ぷらぷらと歩いているうちに、思わず気が緩んで、この人生は、この現実は、このわたしは、夢ではないか。と、頬をつねってみてもまだ信じられないような感覚に襲われる人は少なくないんじゃないかと思います。 今期のさそり座のキーワードは、「縞柄」。 桜の花の咲きぶりや散り具合、そしてそうした光景を描いた浮世絵などの近代以前の奥行きのない世界を見ていると、案外、高度な精神の現れというのは、モノや文様のパターンなど、目に見える具体的な形で表わされているのではないかと、改めてハッとさせられるのですが、江戸文化研究家の田中優子も『江戸百夢 近世図像学の楽しみ』の中で、着物の縞(しま)柄つまりストライプ模様について触れて同様のことを述べています。
今期のさそり座のキーワードは、「縞柄」。 桜の花の咲きぶりや散り具合、そしてそうした光景を描いた浮世絵などの近代以前の奥行きのない世界を見ていると、案外、高度な精神の現れというのは、モノや文様のパターンなど、目に見える具体的な形で表わされているのではないかと、改めてハッとさせられるのですが、江戸文化研究家の田中優子も『江戸百夢 近世図像学の楽しみ』の中で、着物の縞(しま)柄つまりストライプ模様について触れて同様のことを述べています。 今期のいて座のキーワードは、「横断的な戦術」。 IT技術やAIの導入によって余暇が増えるどころか、現代人がますます忙しくなってきているように感じるのは、単純に物理的な時間が足りなくなっているからではなく、おそらく労働と余暇のあいだの境界線があいまいになってしまったからではないでしょうか。
今期のいて座のキーワードは、「横断的な戦術」。 IT技術やAIの導入によって余暇が増えるどころか、現代人がますます忙しくなってきているように感じるのは、単純に物理的な時間が足りなくなっているからではなく、おそらく労働と余暇のあいだの境界線があいまいになってしまったからではないでしょうか。 今期のやぎ座のキーワードは、「古代の哲学者たちのように」。 「風の時代」という言葉がひとり歩きして、どうも占星術における風=思考機能という定義からだいぶかけ離れた社会展望がそこかしこで語られているような状況が生まれていますが、いずれにせよ現時点で確実に言えることは、これからの「風の時代」ますます「自分なりに考えてみる」ことの重要性や緊急性は増していくだろうということ。
今期のやぎ座のキーワードは、「古代の哲学者たちのように」。 「風の時代」という言葉がひとり歩きして、どうも占星術における風=思考機能という定義からだいぶかけ離れた社会展望がそこかしこで語られているような状況が生まれていますが、いずれにせよ現時点で確実に言えることは、これからの「風の時代」ますます「自分なりに考えてみる」ことの重要性や緊急性は増していくだろうということ。 今期のみずがめ座のキーワードは、「動物のまなざし」。 夜道をひとり、なんとなく心許なく感じながら歩いているとき、目の前に突然何かが飛び出してくる。幽霊か?いや獣だ(こんな現れ方は獣にしかできない)。暗闇に光る二つの目。思わず目が合う……。ただ、それはよく見たら猫だった。なーんだ。ただしばらくしてから、その一瞬の邂逅が最近の他のどんな出来事よりも鮮明な印象を自分の中に残していたことに気が付く―。
今期のみずがめ座のキーワードは、「動物のまなざし」。 夜道をひとり、なんとなく心許なく感じながら歩いているとき、目の前に突然何かが飛び出してくる。幽霊か?いや獣だ(こんな現れ方は獣にしかできない)。暗闇に光る二つの目。思わず目が合う……。ただ、それはよく見たら猫だった。なーんだ。ただしばらくしてから、その一瞬の邂逅が最近の他のどんな出来事よりも鮮明な印象を自分の中に残していたことに気が付く―。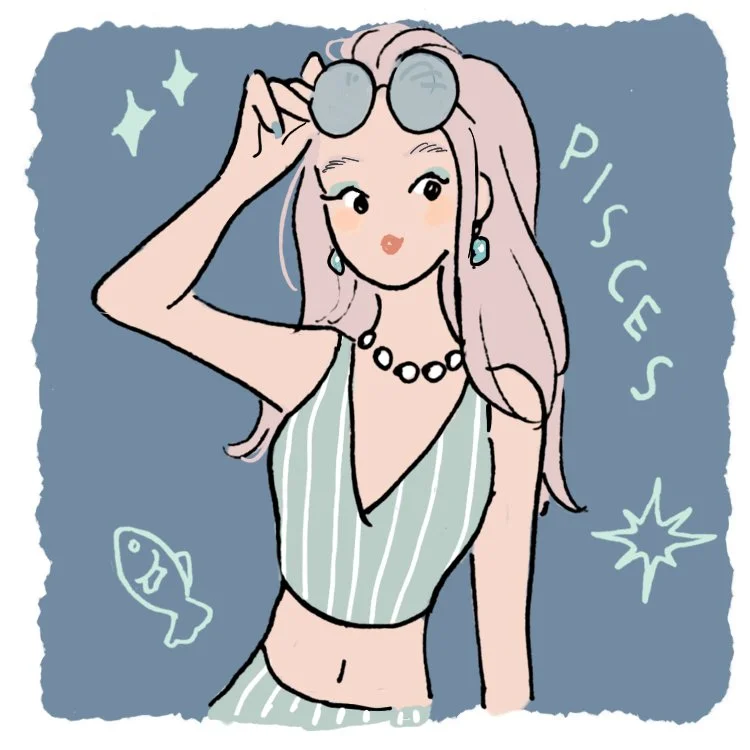 今期のうお座のキーワードは、「無限の悲しみへのたしかな自覚」。 文明以前ということをすっかり見失ってしまった現代人は、事の当然の帰結としてこの世界においてひどく傷つきやすい存在となってしまい、311を経た今もなお強情に文明への“引きこもり”を決め込んでいるようなところがありますが、そうした人間の悲しさを小説の世界で描いてみせたのがポール・ボウルズの『シェルタリング・スカイ』でした。
今期のうお座のキーワードは、「無限の悲しみへのたしかな自覚」。 文明以前ということをすっかり見失ってしまった現代人は、事の当然の帰結としてこの世界においてひどく傷つきやすい存在となってしまい、311を経た今もなお強情に文明への“引きこもり”を決め込んでいるようなところがありますが、そうした人間の悲しさを小説の世界で描いてみせたのがポール・ボウルズの『シェルタリング・スカイ』でした。