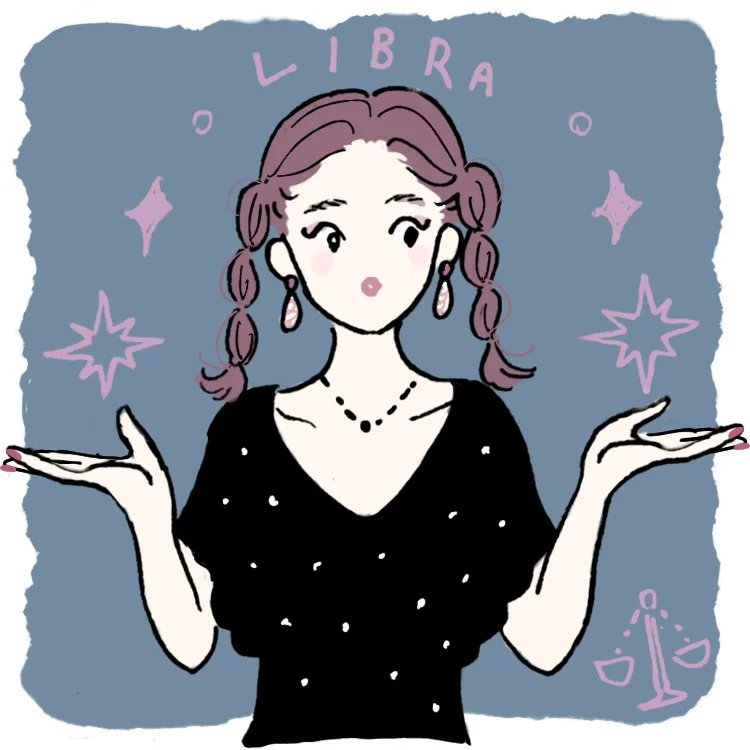【蠍座】哲学派占い師SUGARさんの12星座占い<7/25~8/7> 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモいー
12星座全体の運勢
「死に寄り添う生」
8月7日の「立秋」はまさに真夏の盛りですが、日本の伝統的な季節感では夏がピークに達するときに秋がスタートし、人びとは小さな秋の兆しを探し始めてきたのです。そして、そんな立秋直後の8月8日にしし座の新月を迎えていきます。
今回の新月は土星(体制、課題)と天王星(転覆、改革)と二等辺三角形を形成するため、今年一年を通じて進行していく既存の権威やこれまで機能してきた体制側の自己防衛や無意識の視野狭窄を破壊して再構築プロセスにかなり直結していくものとなるでしょう。
その上であえてそれを端的にテーマ化するなら、「死に寄り添う生の在り方を探る」といったものになるように思います。例えばこれは、これまでのように社会を強固で一枚岩的な現実に統合せんとしてきた近代的な考え方においては、死は完全な敵であり、それに対して断固として立ち向かうか、徹底的に視界から排除されるべきものだった訳ですが、超高齢化が進展するポスト成長時代のこれからは、老いのプロセスの中で、徐々に死を受け入れ、和解し同化していく中で、生と死のゆるやかなグラデーションを取り戻していくことが求められていく、ということともリンクしてくるはず。
ちょうど芭蕉の句に「閑(しづか)さや岩にしみ入る蝉の声」という句がありますが、短い一生ながら懸命に鳴いている蝉とその声はまさに「いのち」の象徴であり、一方で、奥深い山の池のほとりで苔むして黒々としている「岩」とは「死」の象徴とも言えるのではないでしょうか。
そして、蝉の声が岩に「しみ入る」というのは、まさに意識の静寂のさなかで「生と死」が融合し、その連続性を取り戻していく宇宙的とも言える世界観を表現したもの、とも解釈できます。今期の私たちもまた、そんな句のように、死を敵と考えたり、排除するのではなく、どうしたら和解していけるか、また、個人的なものであれ社会的なものであれ、死とは何かをいかに問い直していけるかが問われていくように思います。
今回の新月は土星(体制、課題)と天王星(転覆、改革)と二等辺三角形を形成するため、今年一年を通じて進行していく既存の権威やこれまで機能してきた体制側の自己防衛や無意識の視野狭窄を破壊して再構築プロセスにかなり直結していくものとなるでしょう。
その上であえてそれを端的にテーマ化するなら、「死に寄り添う生の在り方を探る」といったものになるように思います。例えばこれは、これまでのように社会を強固で一枚岩的な現実に統合せんとしてきた近代的な考え方においては、死は完全な敵であり、それに対して断固として立ち向かうか、徹底的に視界から排除されるべきものだった訳ですが、超高齢化が進展するポスト成長時代のこれからは、老いのプロセスの中で、徐々に死を受け入れ、和解し同化していく中で、生と死のゆるやかなグラデーションを取り戻していくことが求められていく、ということともリンクしてくるはず。
ちょうど芭蕉の句に「閑(しづか)さや岩にしみ入る蝉の声」という句がありますが、短い一生ながら懸命に鳴いている蝉とその声はまさに「いのち」の象徴であり、一方で、奥深い山の池のほとりで苔むして黒々としている「岩」とは「死」の象徴とも言えるのではないでしょうか。
そして、蝉の声が岩に「しみ入る」というのは、まさに意識の静寂のさなかで「生と死」が融合し、その連続性を取り戻していく宇宙的とも言える世界観を表現したもの、とも解釈できます。今期の私たちもまた、そんな句のように、死を敵と考えたり、排除するのではなく、どうしたら和解していけるか、また、個人的なものであれ社会的なものであれ、死とは何かをいかに問い直していけるかが問われていくように思います。
蠍座(さそり座)
今期のさそり座のキーワードは、「「生」を生き抜くこと」。

茶番だとわかっていてもそれに付き合わなければならない、あるいは、「もうどうしようもないのだ」という既視感のある無能感を、いま多くの人が改めて感じているはずですが、ここで思い出されるのが、漫画家の山岸涼子の『朱雀門』という作品です。
中学生の女の子である千夏と、その叔母でフリーデザインの仕事をしている三十代前半の独身女性の春秋子(すずこ)さんという二人を軸に展開されるこのお話は、春秋子さんが千夏の部屋で彼女がたまたま読んでいた芥川龍之介の『六の宮の姫君』を見つけるところでグッと核心に入ります。
『六の宮の姫君』についても、簡単に説明しておくと、ある平安時代の姫君が、親に死なれ頼れる人もおらず、途方に暮れている。世話をしてくれた男も、任を授かって京から遠く離れた地へ行くために去ってしまう。姫君はおいおい泣くばかりの日々で、結局、姫君は屋敷も失い、朱雀門の下で成仏することなく息を引き取る。その後、ほどなくして門のほとりでは、女の悲壮な泣き声が聞こえるようになる。法師は言う、あの泣き声は「極楽も地獄も知らぬふがいない女の魂でござる」と。
千夏は「これじゃあんまり姫君がかわいそうじゃない!?」とこの結末に疑問を持ちますが、叔母はむしろそこが芥川のすごいところなのだと告げ、「生」を生きない者は、「死」をも死ねない…と彼は言いたいのよ」と返すのです。
時代的に仕方なかったところはあるかも知れませんが、確かに春秋子さんの言う通り、六の宮の姫君はただの一度も生活苦を改善しようとも、男を追いかけたり愛そうともせず、すなわち自分の運命を自分でどうこうしようと努力しませんでした。ただ襲ってくる運命を甘んじて受けるだけだったのです。
「この何も知らない、見ない、ただ待つだけ、耐えるだけなんて、そういった人間は自分の「生」を満足に生きていないのと同じよ。たとえこの時代のお姫さまだとてね」
「生とはね、生きて生き抜いてはじめて「死」という形で完成するんですって」
「つまりは生きるという実感がなければ、死ぬという実感がなくてあたりまえなのよ。六の宮の姫君は自分が死んだという実感もまたわからないまま死んだんだと思うわ。結局死をうけいれられなかったのよね」
春秋子の指摘を踏まえて読むと、この六の宮の姫君はどこか今の大多数の日本国民の姿と重なりはしないでしょうか。すくなくとも今期のさそり座は、ただ座して運命を甘受するのでなく、どうしたらみずからの「生」を生きて生き抜くことができるのか、考えていきたいところです。
参考:山岸涼子『二日月』(潮出版社)
中学生の女の子である千夏と、その叔母でフリーデザインの仕事をしている三十代前半の独身女性の春秋子(すずこ)さんという二人を軸に展開されるこのお話は、春秋子さんが千夏の部屋で彼女がたまたま読んでいた芥川龍之介の『六の宮の姫君』を見つけるところでグッと核心に入ります。
『六の宮の姫君』についても、簡単に説明しておくと、ある平安時代の姫君が、親に死なれ頼れる人もおらず、途方に暮れている。世話をしてくれた男も、任を授かって京から遠く離れた地へ行くために去ってしまう。姫君はおいおい泣くばかりの日々で、結局、姫君は屋敷も失い、朱雀門の下で成仏することなく息を引き取る。その後、ほどなくして門のほとりでは、女の悲壮な泣き声が聞こえるようになる。法師は言う、あの泣き声は「極楽も地獄も知らぬふがいない女の魂でござる」と。
千夏は「これじゃあんまり姫君がかわいそうじゃない!?」とこの結末に疑問を持ちますが、叔母はむしろそこが芥川のすごいところなのだと告げ、「生」を生きない者は、「死」をも死ねない…と彼は言いたいのよ」と返すのです。
時代的に仕方なかったところはあるかも知れませんが、確かに春秋子さんの言う通り、六の宮の姫君はただの一度も生活苦を改善しようとも、男を追いかけたり愛そうともせず、すなわち自分の運命を自分でどうこうしようと努力しませんでした。ただ襲ってくる運命を甘んじて受けるだけだったのです。
「この何も知らない、見ない、ただ待つだけ、耐えるだけなんて、そういった人間は自分の「生」を満足に生きていないのと同じよ。たとえこの時代のお姫さまだとてね」
「生とはね、生きて生き抜いてはじめて「死」という形で完成するんですって」
「つまりは生きるという実感がなければ、死ぬという実感がなくてあたりまえなのよ。六の宮の姫君は自分が死んだという実感もまたわからないまま死んだんだと思うわ。結局死をうけいれられなかったのよね」
春秋子の指摘を踏まえて読むと、この六の宮の姫君はどこか今の大多数の日本国民の姿と重なりはしないでしょうか。すくなくとも今期のさそり座は、ただ座して運命を甘受するのでなく、どうしたらみずからの「生」を生きて生き抜くことができるのか、考えていきたいところです。
参考:山岸涼子『二日月』(潮出版社)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
文/SUGAR イラスト/チヤキ