-

<7/26~8/8>の12星座全体の運勢は?
「引いた視点で俯瞰する」
暦の上で秋となる「立秋」の直前、まさに夏真っ盛りの8月4日に水瓶座で満月を迎えていきます。この時期にはお盆をひっくり返したような激しい雨(覆盆の雨)が降るとされてきましたが、今回の満月は変革と普及をつかさどる「天王星」と激しい角度をとっており、まさに意識の覚醒を促されるタイミングとなりそうです。
テーマはずばり、「現時点での自分のレベルの把握」。2020年の年末にはいよいよ約200年単位の占星術上の時代の移り変わりがあり、モノの豊かさの「土」の時代から、情報や繋がりの多様性が価値基準となる「風」の時代へなどと言われていますが、今回の満月はそうした時代の変化にどこまで同調できているか、またできていないのかということが浮き彫りになるはず。
そこにはかなりの個人差が生じるものと思われますが、とくに痛みや違和感、プレッシャーの感じ方などは、これまでの生き様やその蓄積、ふだん触れている情報や立ち位置、周囲の人間関係、属するコミュニティなどによってまったく異なってくるでしょう。
ともに地球に生き、一見同じ位置にあるように見える人間同士でも、進化における種類と段階の違いは厳然と存在するのだということを、今期はよくよく念頭に置いていくべし。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「恐れなき発言」。
現代フェミニズム思想を代表する思想家ジュディス・バトラーは「恐れなき発言と抵抗」と題されたセミナーにおいて、「恐れなき発言とは何か、あるいはそれはどのように機能するのか、と問うことで、私たちは、今日の抵抗の構造あるいは意味について重要な何かを見出すことができるかも知れません」と問いかけました。
まずこの「恐れなき発言」とは、「率直に話すこと」「真実を述べること」と翻訳されてきたギリシャ語の「パレーシア」という言葉が前提に置かれています。そして、ここでは語り手は、(主に権力者にとって)都合の悪い真実を語るため、つねに反撃や孤立、拘留、死などのリスクに曝されており、それゆえ「恐れなき発言」の遂行にはヒロイズム的な徳(勇気など)が必要とされてきました。
しかし、バトラーは政治的勇気にとって恐れなき語りが不可欠だとは考えて“いない”と告白します。というのも、私たちはしばしば恐れを乗り越えていないかもしれないが、「それでも語り、恐れつつ大胆」であったりしますし、また「語る際に、時に私たちは単に自分自身の声では語っておらず、他者たちと共に語っている」からでしょう。
そして、今のおひつじ座においてもまた、自分が何に対して、いかに、また誰と協力しあって「恐れなき発言」を発しているのか、といった「抵抗の形式」は大きな焦点となっていくでしょう。
特に「恐れなき発言」をするにあたり、どうしたら自己責任や個人主義を回避し、いかに連帯し、それを蓄積していけるか、という点については、自分自身が反撃や孤立、拘留、死などのリスクに潰されてしまわないためにも、しっかりと自問していきたいところです。
出典:ジュディス・バトラー、佐藤嘉幸訳「恐れなき発言と抵抗」(『現代思想2019年3月臨時増刊号』)
-

今期のおうし座のキーワードは、「無意識に触れること」。
罪悪感というのは、たとえそれがほんの些細なものであったとしても、抱え続けていくうちに次第に攻撃性や支配欲、怒りといったさらにネガティブな感情へと変化していって、心の根本的なところを蝕んでいくものですが、そうした罪の意識について徹底的に深く探究した作品としてはドストエフスキーの『罪と罰』を取りあげない訳にはいかないでしょう。
主人公のラスコーリニコフは元大学生の無職で、ボロアパートの屋根裏部屋でギリギリの困窮生活をしているのですが、自尊心が高く知性も教養もあるにも関わらず、強欲な金貸しの老婆を殺してその金を奪うという恐ろしいたくらみに憑りつかれ、実際に殺してしまいます。ところが、その現場を彼女の腹違いの妹に偶然見られてしまい、勢いで彼女まで殺してしまうのです。
強欲な金貸しを打倒するだけならまだしも、これはさすがに法的にも道徳的にも完全にアウトであると感じたラスコーリニコフは、思い悩み過ぎて支離滅裂なことを口走りながら町を徘徊するようになりますが、たまたま出会った娼婦のソーニャの友情と愛に支えられ、やがてみずからの犯行を自白するに至ります。
彼は罪を隠し通すこともできたかも知れませんが、一方でソーニャは罪を告白することなしには人生を取り戻すことはできないと分かっていました。
ここではラスコーリニコフは近代都市と個人主義のはざまにある孤独や虚無の象徴であり、一方の見捨てられた人間ではあるが素朴であたたかなソーニャは大地そのものと言えます。
そして小説の題名でもある「罪と罰」を、ラスコーリニコフひとりでは決して引き受けることはできませんでしたが、ソーニャの象徴する大地のように、意識を底支えする「無意識」に触れ、それに任せて行動していった結果、彼ははじめて罪悪感を祓い清め、生まれ変わることができたのです。
今のおうし座の人たちもまた、少なからず彼と同じプロセスを必要としているのではないでしょうか。つまり、どこかで見ないふりをしたり、なかったことにしていた、心の奥底に引っかかっているかすかな罪悪感やその兄弟分である羞恥心と向き合っていかざるを得なくなったり、その中でどうしたら自分で自分を許すことができるかが大切なテーマとなっていくでしょう。
出典:ドストエフスキー、工藤精一郎訳『罪と罰』(新潮文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「仲間と希望」。
小柄で頭の切れるジョージと知的障害を持つ怪力の大男レニー。二人は農場を渡り歩く季節労働者であり、新しい農場に着いてひと稼ぎすると、町へ出てそれを使い果たしてしまう。そんな生活を繰り返していました。
家族もなく、家もなく、人生でこれ以上何かを期待することもできない。二人は自分たちを「この世でいちばんさびしい人間」だと思っているのですが、一方で、ジョージはレニーに「おれたちはふつうの宿無しとはちがう」と言い聞かせ続けます。
レニーはふわふわのものをなでるのが好きで、自分の怪力を自覚していないがゆえに、行く先々で問題を起こしてきたのですが、そんな中ジョージは、いつかは小さな家と土地を買って自給自足し、ウサギをたくさん飼ってレニーになでさせてやるんだ、という夢を持っていました。
ただしこの『ハツカネズミと人間』という小説では、物語は貧しさに引きずられ、どんどん暗い方へ転がり落ちていき、ジョージがこの夢を自分でも信じられなくなったとき、すべてが雲散霧消してしまいます。なぜなら、ジョージはレニーと共有していた希望があったからこそ、どんな状況であれ前に進むことができたから。夢の話は、レニーを慰めるためであると同時に、自分自身を励ますためでもあったのです。
そして、今のふたご座の人であれば、誰の心の中にもレニーがいて、“ウサギをたくさん飼う話”をしてもらう必要があるのだということがよく分かるのではないでしょうか。
あるいは、誰しもが時にジョージとなって、仲間にウサギの話をして元気づけてやることで自分もまた歩みを止めずにいられるのだと。
「人間には仲間が必要だ―そばにいる仲間が」
今期のふたご座は、いま自分がどちらの側に立っているのか、あるいは、どんな希望に生かされているのかを、改めて確認していくことになるかもしれません。
出典:ジョン・スタインベック、高村博正訳『スタインベック全集4 はつかねずみと人間<小説・戯曲>』(大阪教育図書)
-

今期のかに座のキーワードは、「哀しみのまなざし」。
南アフリカ出身の作家クッツェーの小説『恥辱』は、52歳の芯から腐ったような男を主人公としたタイトルの通りどうしようもないお話です。
大学の准教授だけれどやる気はゼロで、無教養な人間や田舎者をひたすら軽蔑にしている一方で、性欲をコントロールできずに教え子に手を出すものの反省はゼロ。そのため、その一件で大学を追われた後も転落の一途をたどっていくという非常に重たいストーリーなのですが、どうしたことか読み出すと止まらないのです。
おそらくそれは重くて禍々しい展開を、ひたすら俯瞰的な文体で描いているからでしょう。例えば、主人公が教え子と会話している次のくだり。
「ふたりの関係を心配しているのか?」
「そうかも」彼女は言う。
「なら心配いらない。気をつけるよ。行きすぎないようにしよう」
行きすぎる。この手の話で、〝行く〟だの〝行きすぎる〟だの、なんのことだ? 彼女の行きすぎと、こちらの行きすぎは、果たしておなじなのか?
小説としてはまだ序盤の段階にも関わらず、まるで語り手はすでに主人公を見放しているかのように本音を漏らしています。こうした箇所がその後も随所に出てくるのです。ただ、それは単に主人公を見下しているというよりは、哀しみのまなざしであり、単純な善悪や白黒はっきりじゃないグレーな人間を見つめるそれなのだということも分かってきます。
そして、まさに今のかに座に求められているのも、自身のことをこうしたまなざしをもって見つめていくだけの距離感でしょう。
今期のかに座もまた、「自分を甘やかした考えや行動」や「楽な選択」に走るのではなく、自分を通して人間という事象の裏の裏までを見通すだけの奥行きをあなたの人生に持ち込んでいきたいところ。
出典:J・M・クッツェー、鴻巣友季子訳『恥辱』(ハヤカワepi文庫)
-

今期のしし座のキーワードは、「我は我として」。
激動の昭和に数多くの歴史小説を書いた作家・中山義秀の遺作となったのは『芭蕉庵桃青』という、風狂の俳人・松尾芭蕉を描いた歴史小説でした。
その冒頭にて、賑やかな日本橋界隈に住み俳句の宗匠(マスター)となっていた芭蕉が、当時は辺鄙な場所であった深川の粗末な小屋に移り住み、それまでの俳句とはちがった独自の作風を確立し始めた頃に詠まれた「枯枝に烏のとまりたるや秋の暮」という句について、次のように指摘しています。
「芭蕉としては三十七歳を期に、一切を放下して世捨人の境涯に入り、あらたに自分の句境をきりひらこうとする、意気込みだったことと思われる。/彼はその頃からして、体内になにやらうごめく力を感じていた。小我をはなれ眼前の現象を離脱して、永遠の時のうちに不断の生命をみいだそうとする、かつて自覚したことのない活力である。/その活力が「烏(カラス)のとまりたるや」という、字あまりの中十句に、余情となってうち籠められている。」
こう書いた中山もまた、早咲きの同級生を横目に、中学校の教師生活や校長とのトラブル、妻の闘病と死、貧困といった生活上の困難を経て、37,8歳頃にようやく自身の文学の道を確立したのでした。
中山にとっての文学の道とは、時代や状況に流されることのない、独立自尊の気風であり、芭蕉を描いた筆致にも、自然と自身のたどってきた道への思いが重ねられていたように思います。
中山というひとりの作家にとって、芭蕉はヒーローでもなければ天才でもありませんでした。「おのれの才能はともあれ、孤独に耐えられることだけが、自分の取柄だということ」の覚悟と信念をもって一生を歩んでいった“もうひとりの自分”だったのではないでしょうか。
そして、こうした過大評価するのでも、過小評価に陥るのでもなく、ありのままに自分自身を捉えていくためのまなざしこそ、今のしし座に必要なものでもあるはずです。
誰に媚びるでもなく、時代に流されるのでもない。どんなに素朴でささやかなものであれ、そんな自身の歩むべき道を見出していきたいところです。
出典:中山義秀『芭蕉庵桃青』(講談社文芸文庫)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「火遊び」。
バリ島でかつて重要な社会的行事であった「闘鶏」について、アメリカの人類学者ギアーツが分析した論文のタイトルには「ディープ・プレイ」という言葉が使われました。
これはもともとイギリスの思想家ベンサムが18世紀末に著した『道徳および立法の諸原理序説』のなかで「功利主義者としてみた場合、賭け金があまりに高くてそれに関わるのは非合理であるような遊び」を指すために用いた言葉なのですが、ギアーツはそこに人々が“深く”巻き込まれてしまう象徴的なゲームとして積極的な意味合いを見出したのです。
ギアーツによれば、あからさまな衝突を嫌い「おとぼけの達人」であるバリ人にとって、闘鶏とは遠回しに互いの面目を傷つけあうゲームであり、そこではみずからの存在の根拠が賭けられた上で、地位の急激な転倒にともなう感情の複雑で激しい動揺を味わうものの、
勝負によって尊敬されたり侮辱されたりするのはその場だけの話で、現実の地位が実際に取引されることはなかったそうです。
言ってみれば、激しい攻撃で鶏たちが血を流す闘鶏は「彼ら自身による彼らの物語」であり、その意味で参加者によって解釈される「深い演劇」でもあったのです。
そして、まさにこうしたどこかで「深い演劇」を演じていく感覚や、それによって引き起こされる感情の複雑さを通じた「一種の感情教育」こそ、今期のおとめ座のテーマとなっていくはず。
これは例えば、恋人とのデートや応援しているサッカーチームの試合観戦など、日常生活にセレモニーを設置し、そこに織り込まれている解釈のうちに、自分を深く挿入していくことで、単なる事実の寄せ集め以上の“物語”を編んでいくということでもあります。
あくまで想像上の次元で行われる「火遊び」に、自分がどれだけはまってきたのか、また、それによってどれだけ自身の物語は豊かになってきたのか。この機会に今一度振り返ってみるといいでしょう。
出典:C・ギアーツ「ディープ・プレイ―バリの闘鶏に関する覚え書き」(吉田禎吾、中牧弘允、 柳川啓一、板橋作美訳『文化の解釈学Ⅱ』所収)
-
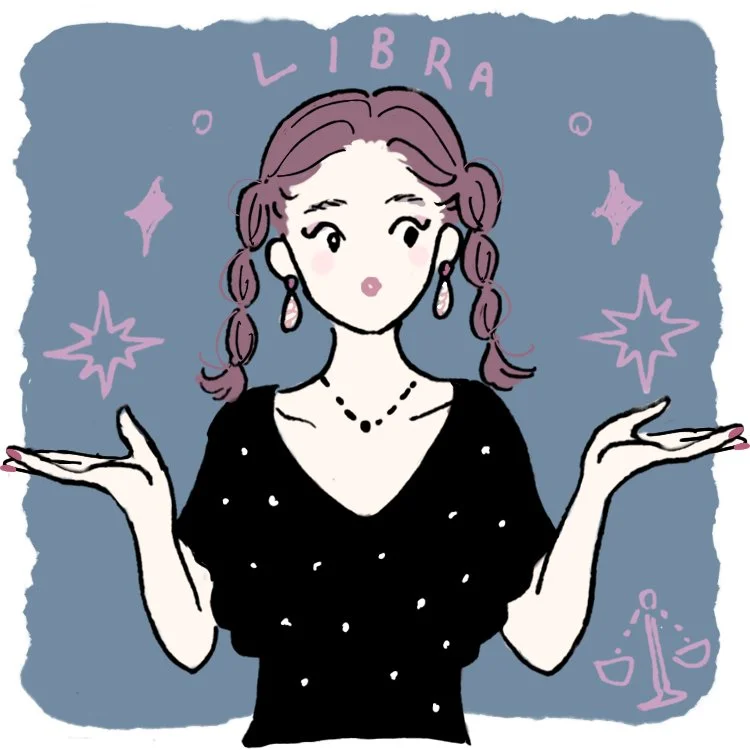
今期のてんびん座のキーワードは、「夜が育む想像力」。
人間対自然という対決構図において、本来人間に勝ち目などほとんどないのだということを最も強く思い出させてくれるのは“夜の闇”ですが、同時に、人間の孤独な魂を崇高なところまで引き上げてくれるのも、やはり“夜”に他ならないのではないでしょうか。
まだ夜間の飛行が命がけだった時代、郵便事業に命をかけた者たちを描いたサン=テグジュペリの『夜間飛行』を読んでいると、そんな思いに駆られます。
主人公は「嫌われ者の上司に睨まれることで初めて現場の規律は保たれる」という信念のもと、部下に1つのミスも許さない厳しい支配人であらんとするリヴィエール。彼は内心の葛藤や孤独に苦しみつつも、それを紛らわすために繰り出した散歩からの帰り道、ふと見上げた夜空の星に何かを感じ取ります。彼の独白を引用してみましょう。
「今夜は、二台も自分の飛行機が飛んでいるのだから、僕はあの空の全体に責任があるのだ、あの星は、この群衆の中に僕をたずねる信号だ、星が僕を見つけたのだ。だから僕はこんなに場違いな気持ちで、孤独のような気持ちがしたりする」
人間にとって夜とは、ある意味で死に近づいていくことであり、夜の底に埋もれた宝物を見つけていくことで、改めて生を更新していく時間でもあるのでしょう。そして、そんな夜という時間だけが育むことのできる想像力こそ、今のてんびん座の人たちに問われているものでもあるはず。
リヴィエールのように夜空に輝く星々のなかに自分を見つめてくれる星を探すもよし。あるいは、自分がこれまでくぐり抜けてきた幾多の夜のことを思い返すもよし。今期のてんびん座は、そんな風にあらためて夜の底からいま生きていることを感じ直していきたいところです。
出典:サン=テグジュペリ、堀口大學訳『夜間飛行』(新潮文庫)
-

今期のさそり座のキーワードは、「自分のちっぽけさを笑う」。
カフカの『変身』と言えば、布地の販売員をしていたごく普通の青年グレゴールがある朝起きると毒虫に変わっていたところから始まる話としてあまりにも有名。
どうして虫になってしまったのか、虫は何かの象徴なのかといったことは全然説明されず、主人公が虫であること以外はすべてがリアルに進行する。同居する家族の状況もあいまって、読者はパラレルワールドへ連れ出されたような奇妙な不安を感じさせられます。
ただし、一般的な暗く切迫したイメージに反し、じつはこの小説の本当に大事なポイントは「とにかく笑える」というところにあるように思います。
例えば、グレゴールは自分が虫になってしまったことにはさほど驚かない一方で、目覚まし時計を見て出勤時間を寝過ごしたことにはもの凄く驚くのですが、そんな場面をカフカはこんな風に書いています。
「それから時計に目をやった。戸棚の上でチクタク音を立てている。「ウッヒャー!」と彼はたまげた」
あるいは、だんだん虫として漫然と過ごすことに退屈してくると、部屋中をはい回るようになるのですが、それもこんな調子。
「グレゴールは這いまわりはじめた。いたるところを這いつづけた。四方の陰も、家具調度も、天井も這いまわった。やがて部屋全体がグルグル回りはじめたとき、絶望して大きなテーブルの真ん中に落下した」
実際、カフカ本人はこの作品を友人らの前で朗読する際、絶えず笑いを漏らし、時には吹き出しながら読んでいたのだそう。
と同時に、虫以前と虫以後の時間の流れ方が全然違っていて、仕事や時間に追い立てられていた主人公が、虫になった途端に時間の流れがどんどんゆっくりになっていることにも気づかされます。
ここには、引きこもりのメタファーであるとか、合理主義的な機械文明におしつぶされる人間の悲劇が記されているといった、月並でありきたりな読み解きを許さない不条理ギャグの絶妙な味わいが感じられないでしょうか。
そして、今期のさそり座もまたどれだけ自分という時間の流れを客体視しつつ、人間のちっぽけさを笑う目をどれだけ持てるかが問われていくことになりそうです。
出典:フランツ・カフカ、池内紀訳『変身』(白水uブックス)
-

今期のいて座のキーワードは、「乗客ではなく」。
人間は限られた時間しか生きられません。そのこと自体は誰もが知っていることですが、実際には貴重な時間を自分にとって特別な意味を持つことに使おうという気概は、歳を追うごとにどんどん弱くなっていくように思います。中年を過ぎて老年になってしまえばもう人生の方向性や価値はほとんど決まってしまうのだと考える人も多いのではないでしょうか。さながら、自分は人生のパイロットではなく、乗客のようだと。
しかし、映画化もされたスウェーデンの作家ヨナス・ヨナソンの小説『窓から逃げた100歳老人』の主人公であるアランという老人は、そうではありませんでした。
彼はつねにいい加減に、確信より好奇心にしたがって生きてきたのですが、どういう訳か20世紀の重大事件の多くで重要な役割を果たしてきました。それで、老人ホームで行われる彼の100歳の誕生日パーティーには、市長や新聞記者などたくさんの来賓が訪れる予定だったのですが、前日になってふと彼はこんな風に思います。
老人ホームが自分の終の棲家ではない。“どこか別の場所”で死のう。そう決めたのだ、と。幸いにも、彼はホームを脱走してすぐに大金の詰まったスーツケースを手に入れ、彼があまり品行方正な人間ではなかったことも相まって、驚くべき展開をしていきます。
それでも彼は、そうした最中で1905年に誕生してからの人生をおもしろおかしく振り返りながら現在の冒険を進行させていき、101歳になった頃にはずっと若い女性(85歳)とともにバリで新たな人生を踏み出すにいたるのです。
この小説のメッセージははっきりしています。もし人生の操縦席に座るチャンスがあると感じたときは、迷わずパイロットになりきること。
そして、今期のいて座もまた、乗客席から人生を眺めるのではなく、操縦席から人生の景色を臨んでいけるかが少なからず試されていくはず。
アランほど老齢ではなくても、迷った時は自分の“終の棲家”はどこにしたいか、ということを考えてみるといいかも知れません。
出典:ヨナス・ヨナソン、柳瀬尚紀訳『窓から逃げた100歳老人』(西村書店)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「混乱や矛盾を含みつつ」。
もし実際に理想郷があなたの手や足の届くところにあったとして、そこに行けば自分の理想が叶えられるとして、あなたは他のすべてを捨ててでもそこに行こうと思うだろうか?
おそらく、その答えの多くはNOだろう。とりあえずこの現実で手に入れたものとか、出会った人たちとか、そういうものがあって、なんだかんだそういうものが大事だから。
けれど、この世界には先の問いかけにYESと答えて、さっと向こう側に飛び込んでいってしまう人がいるのだということも、忘れてはならないように思います。
村上春樹がオウム真理教の元ないし現役の信者たちに行ったインタビューをまとめた『約束された場所で』は、そういうことをまざまざと思い出させてくれる本であると同時に、村上が自分の創り出す物語世界において何を大事にしようとしているかが垣間見えてくる作品でもあります。例えば、村上の次のような発言。
「現実というのは、もともとが混乱や矛盾を含んで成立しているものであるのだし、混乱や矛盾を排除してしまえば、それはもはや現実ではないのです。」
「そして一見整合的に見える言葉や論理に従って、うまく現実の一部を排除できたと思っても、その排除された現実は、必ずどこかで待ち伏せしてあなたに復讐するでしょう」
オウムの元信者たちはまさに「整合的に見える言葉や論理」で現実を固めた、ツッコミや他者を必要としない人たちであり、彼らの道行きは壮大ではあっても、どこか氷の上のようなツルツルとした表面を滑っているように感じられてしまう。
ただ、そういう現実性を欠いた言葉はある意味、現実よりずっと美しく、力を持ってしまうのだということも、村上はちゃんとわかっている。
それでも、いびつででこぼこしていてどこまでも割り切れない現実を引き受けていくためにも、あえて「いちいち夾雑物を重石のようにひきずって行動しなくてはならない」言葉や論理をつかって、土を蹴り立てて歩みを進めていこうと村上は強く心に決めているように感じられます。そしてこれはそのまま、今のやぎ座の人たちに求められている態度でもあるのではないでしょうか。
こちら側の現実のなかでズレを抱え、周囲からツッコミをもらいつつ、たとえ不格好でも、大地をしっかり踏みしめていくこと。今期のやぎ座はその覚悟のほどを、改めて固めていきたいところです。
出典:村上春樹『約束された場所で』(文春文庫)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「時代錯誤の効用」。
ビル・ゲイツが何度も読み直したという『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』は、アメリカが経済破綻寸前で一党独裁による軍事化が進んだ世界線であり、誰もが信用度や性的魅力を数値化され、手元の端末で簡単にプロフィールを検索されるなど、過度にメディアが発達した近未来を描いたディストピア小説。
主人公は時代に逆行して紙の本を愛するロシアからきたユダヤ系移民で39歳の“時代錯誤おじさん”ことレニーと、彼が一目惚れした24歳の韓国人女学生ユーニス。
この小説世界は文学が衰退したポスト文学社会であり、個人のクレジットカードの履歴やSNS上の人気ランキングからおススメ買い物情報や友人のホットなゴシップなどが絶えずデジタルデバイスを通じて提供され続ける一方で、自分の感情を知るにも<エモート・パッド>という感情測定器を胸にあてなければ分からなくなっているという有り様。さらに内乱状態になってインターネットが落ちてしまい、繋がらなくなったスマホを握りしめた若者が次々と自殺してしまうなど、随所に無惨な戯画的描写が登場してきます。
自分と家族の幸せを願ってあがくユーニスは、未来への不安が高まるにつれ、自分でも驚くことに“魅力最低ランク”のはずのレニーにいつも安らぎを感じていくのですが、そんなユーニスに限らず、この本を読んだ人は改めて“印刷・製本された更新されることのないメディア製品”に手を伸ばしたり、紙の日記をつけたくなってくることは間違いないでしょう。
とくに、今のみずがめ座の人たちであれば、人生の優先順位を他者からの評価という基準で選ぶのではなく、たとえ“パーソナリティ格付け”がグンと下がろうと、自分もトルストイの著作を手にするレニーのように振る舞いたくなってくるはず。
過剰にテクノロジーが進歩していけば、どこかで人間がそれに追いつかなくなって機能不全に陥る危険をはらむものですが、今期のみずがめ座の人たちは加速する時代の流れといったん距離をおいたところで、他ならぬ自分のための幸福ということについて考えていきたいところです。
出典:ゲイリー・シュタインガード、近藤隆文訳『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』(NHK出版)
-
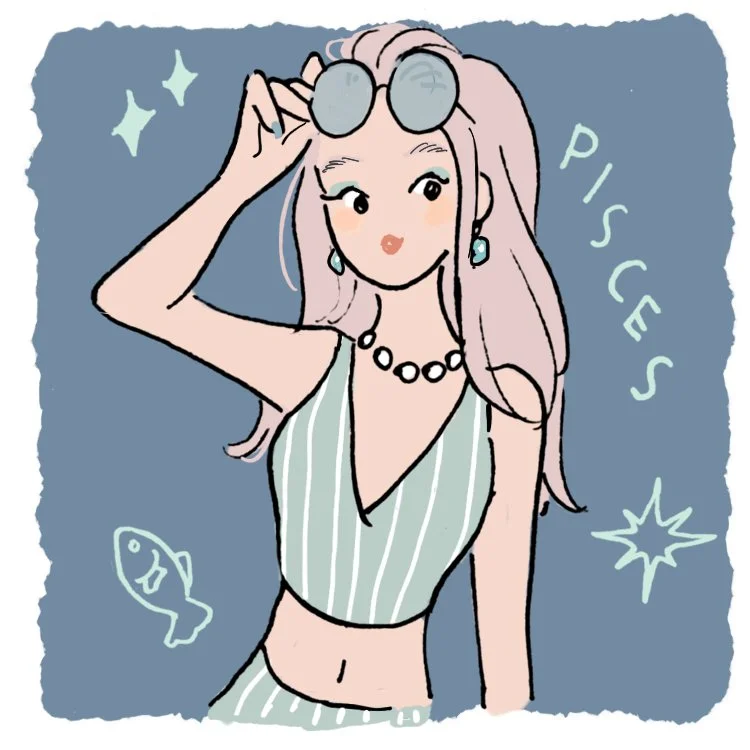
今期のうお座のキーワードは、「満たされること」。
地方から上京してきた著者が東京という都市について綴った随筆集『東京で生きる』では、快楽と幻想と記号の世界としての「東京」で生きることの怖さと魅力とがあますことなくすくいとられており、時にハッとするような繊細な文章で読者の胸をついてきます。
「私は何かを信じたいし、信じることをやめたくなんかない。けれど、東京では私が唯一信じられる自分の欲望が、よくわからなくなる。欲しいと思って手に入れたものが、あっという間になんの魅力もない布切れやがらくたに変貌していく。越境すればものの価値など一瞬で変わる。そんなものを見つけるために途方もない時間を使い、果てしなくお金を払う。見つけて買うまでの瞬間だけは「これは運命だ」と思うことができる。
私は、何のサイコロを転がしているのだろうか?」
朝の満員電車に乗っていたり、深夜にタクシーで帰宅したりすると、ときどき「まぁ、なんだかんだ大丈夫でしょ」と鈍感を決めこんでいたはずの自分が揺らいでしまう瞬間がある。
実際に東京に住んでいようと、そうでなかろうと、きっとそんな人であれば「幻想を見る以上に楽しいことが、この世にどれだけあるのだろうか」「ほんとうに満たされることを、もしかしたら自分は知らないのかもしれない」「知らないからこんなに求めてしまうのかもしれない」といった著者の内的独白の切実さが痛いほどに分かるのではないでしょうか。
ここに書かれた「東京」とは、巨大で複雑な欲望喚起システムがうなりをあげて駆動する猥雑な場所であり、加速し続けている資本主義のメタファーとも捉えられます。
そして、他人の欲望に侵食され、自分というものが溶けてなくなってしまうことについて、本当にそれでいいの?と問いかけることこそ、今のうお座のするべきことなのかも知れません。
著者のようにそこにあえて乗っかり、それができる場所への愛着を深めて食らいついていくのか、それともどこかで線を引いて静かに自分が回復していく過程を待つのか。4日の満月前後は少しでもひとりの時間を確保して、ゆっくり自分と語りあってみるといいでしょう。
出典:雨宮まみ『東京を生きる』(大和書房)
 <7/26~8/8>の12星座全体の運勢は? 「引いた視点で俯瞰する」 暦の上で秋となる「立秋」の直前、まさに夏真っ盛りの8月4日に水瓶座で満月を迎えていきます。この時期にはお盆をひっくり返したような激しい雨(覆盆の雨)が降るとされてきましたが、今回の満月は変革と普及をつかさどる「天王星」と激しい角度をとっており、まさに意識の覚醒を促されるタイミングとなりそうです。 テーマはずばり、「現時点での自分のレベルの把握」。2020年の年末にはいよいよ約200年単位の占星術上の時代の移り変わりがあり、モノの豊かさの「土」の時代から、情報や繋がりの多様性が価値基準となる「風」の時代へなどと言われていますが、今回の満月はそうした時代の変化にどこまで同調できているか、またできていないのかということが浮き彫りになるはず。 そこにはかなりの個人差が生じるものと思われますが、とくに痛みや違和感、プレッシャーの感じ方などは、これまでの生き様やその蓄積、ふだん触れている情報や立ち位置、周囲の人間関係、属するコミュニティなどによってまったく異なってくるでしょう。 ともに地球に生き、一見同じ位置にあるように見える人間同士でも、進化における種類と段階の違いは厳然と存在するのだということを、今期はよくよく念頭に置いていくべし。
<7/26~8/8>の12星座全体の運勢は? 「引いた視点で俯瞰する」 暦の上で秋となる「立秋」の直前、まさに夏真っ盛りの8月4日に水瓶座で満月を迎えていきます。この時期にはお盆をひっくり返したような激しい雨(覆盆の雨)が降るとされてきましたが、今回の満月は変革と普及をつかさどる「天王星」と激しい角度をとっており、まさに意識の覚醒を促されるタイミングとなりそうです。 テーマはずばり、「現時点での自分のレベルの把握」。2020年の年末にはいよいよ約200年単位の占星術上の時代の移り変わりがあり、モノの豊かさの「土」の時代から、情報や繋がりの多様性が価値基準となる「風」の時代へなどと言われていますが、今回の満月はそうした時代の変化にどこまで同調できているか、またできていないのかということが浮き彫りになるはず。 そこにはかなりの個人差が生じるものと思われますが、とくに痛みや違和感、プレッシャーの感じ方などは、これまでの生き様やその蓄積、ふだん触れている情報や立ち位置、周囲の人間関係、属するコミュニティなどによってまったく異なってくるでしょう。 ともに地球に生き、一見同じ位置にあるように見える人間同士でも、進化における種類と段階の違いは厳然と存在するのだということを、今期はよくよく念頭に置いていくべし。 今期のおひつじ座のキーワードは、「恐れなき発言」。 現代フェミニズム思想を代表する思想家ジュディス・バトラーは「恐れなき発言と抵抗」と題されたセミナーにおいて、「恐れなき発言とは何か、あるいはそれはどのように機能するのか、と問うことで、私たちは、今日の抵抗の構造あるいは意味について重要な何かを見出すことができるかも知れません」と問いかけました。
今期のおひつじ座のキーワードは、「恐れなき発言」。 現代フェミニズム思想を代表する思想家ジュディス・バトラーは「恐れなき発言と抵抗」と題されたセミナーにおいて、「恐れなき発言とは何か、あるいはそれはどのように機能するのか、と問うことで、私たちは、今日の抵抗の構造あるいは意味について重要な何かを見出すことができるかも知れません」と問いかけました。 今期のおうし座のキーワードは、「無意識に触れること」。 罪悪感というのは、たとえそれがほんの些細なものであったとしても、抱え続けていくうちに次第に攻撃性や支配欲、怒りといったさらにネガティブな感情へと変化していって、心の根本的なところを蝕んでいくものですが、そうした罪の意識について徹底的に深く探究した作品としてはドストエフスキーの『罪と罰』を取りあげない訳にはいかないでしょう。
今期のおうし座のキーワードは、「無意識に触れること」。 罪悪感というのは、たとえそれがほんの些細なものであったとしても、抱え続けていくうちに次第に攻撃性や支配欲、怒りといったさらにネガティブな感情へと変化していって、心の根本的なところを蝕んでいくものですが、そうした罪の意識について徹底的に深く探究した作品としてはドストエフスキーの『罪と罰』を取りあげない訳にはいかないでしょう。 今期のふたご座のキーワードは、「仲間と希望」。 小柄で頭の切れるジョージと知的障害を持つ怪力の大男レニー。二人は農場を渡り歩く季節労働者であり、新しい農場に着いてひと稼ぎすると、町へ出てそれを使い果たしてしまう。そんな生活を繰り返していました。
今期のふたご座のキーワードは、「仲間と希望」。 小柄で頭の切れるジョージと知的障害を持つ怪力の大男レニー。二人は農場を渡り歩く季節労働者であり、新しい農場に着いてひと稼ぎすると、町へ出てそれを使い果たしてしまう。そんな生活を繰り返していました。 今期のかに座のキーワードは、「哀しみのまなざし」。 南アフリカ出身の作家クッツェーの小説『恥辱』は、52歳の芯から腐ったような男を主人公としたタイトルの通りどうしようもないお話です。
今期のかに座のキーワードは、「哀しみのまなざし」。 南アフリカ出身の作家クッツェーの小説『恥辱』は、52歳の芯から腐ったような男を主人公としたタイトルの通りどうしようもないお話です。 今期のしし座のキーワードは、「我は我として」。 激動の昭和に数多くの歴史小説を書いた作家・中山義秀の遺作となったのは『芭蕉庵桃青』という、風狂の俳人・松尾芭蕉を描いた歴史小説でした。
今期のしし座のキーワードは、「我は我として」。 激動の昭和に数多くの歴史小説を書いた作家・中山義秀の遺作となったのは『芭蕉庵桃青』という、風狂の俳人・松尾芭蕉を描いた歴史小説でした。 今期のおとめ座のキーワードは、「火遊び」。 バリ島でかつて重要な社会的行事であった「闘鶏」について、アメリカの人類学者ギアーツが分析した論文のタイトルには「ディープ・プレイ」という言葉が使われました。
今期のおとめ座のキーワードは、「火遊び」。 バリ島でかつて重要な社会的行事であった「闘鶏」について、アメリカの人類学者ギアーツが分析した論文のタイトルには「ディープ・プレイ」という言葉が使われました。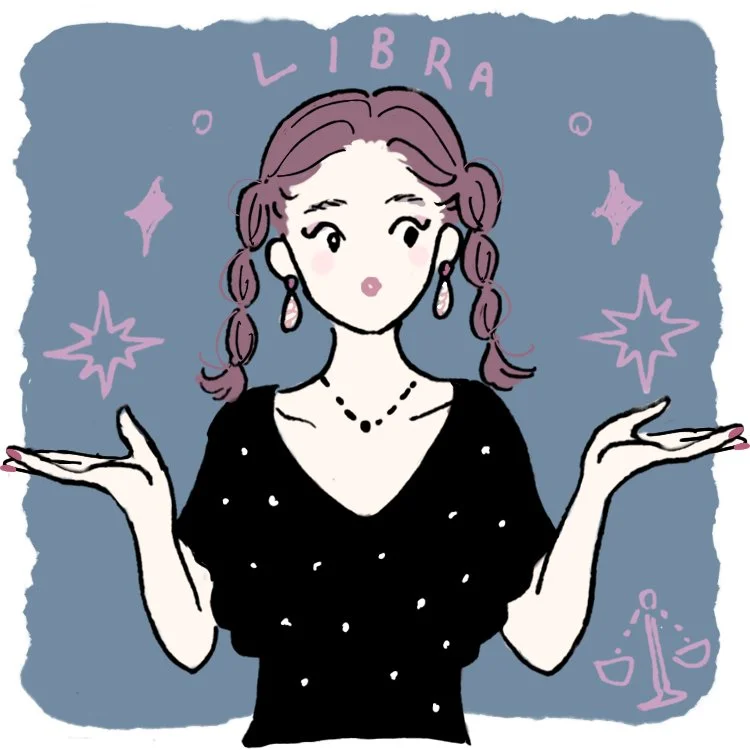 今期のてんびん座のキーワードは、「夜が育む想像力」。 人間対自然という対決構図において、本来人間に勝ち目などほとんどないのだということを最も強く思い出させてくれるのは“夜の闇”ですが、同時に、人間の孤独な魂を崇高なところまで引き上げてくれるのも、やはり“夜”に他ならないのではないでしょうか。
今期のてんびん座のキーワードは、「夜が育む想像力」。 人間対自然という対決構図において、本来人間に勝ち目などほとんどないのだということを最も強く思い出させてくれるのは“夜の闇”ですが、同時に、人間の孤独な魂を崇高なところまで引き上げてくれるのも、やはり“夜”に他ならないのではないでしょうか。 今期のさそり座のキーワードは、「自分のちっぽけさを笑う」。 カフカの『変身』と言えば、布地の販売員をしていたごく普通の青年グレゴールがある朝起きると毒虫に変わっていたところから始まる話としてあまりにも有名。
今期のさそり座のキーワードは、「自分のちっぽけさを笑う」。 カフカの『変身』と言えば、布地の販売員をしていたごく普通の青年グレゴールがある朝起きると毒虫に変わっていたところから始まる話としてあまりにも有名。 今期のいて座のキーワードは、「乗客ではなく」。 人間は限られた時間しか生きられません。そのこと自体は誰もが知っていることですが、実際には貴重な時間を自分にとって特別な意味を持つことに使おうという気概は、歳を追うごとにどんどん弱くなっていくように思います。中年を過ぎて老年になってしまえばもう人生の方向性や価値はほとんど決まってしまうのだと考える人も多いのではないでしょうか。さながら、自分は人生のパイロットではなく、乗客のようだと。
今期のいて座のキーワードは、「乗客ではなく」。 人間は限られた時間しか生きられません。そのこと自体は誰もが知っていることですが、実際には貴重な時間を自分にとって特別な意味を持つことに使おうという気概は、歳を追うごとにどんどん弱くなっていくように思います。中年を過ぎて老年になってしまえばもう人生の方向性や価値はほとんど決まってしまうのだと考える人も多いのではないでしょうか。さながら、自分は人生のパイロットではなく、乗客のようだと。 今期のやぎ座のキーワードは、「混乱や矛盾を含みつつ」。 もし実際に理想郷があなたの手や足の届くところにあったとして、そこに行けば自分の理想が叶えられるとして、あなたは他のすべてを捨ててでもそこに行こうと思うだろうか?
今期のやぎ座のキーワードは、「混乱や矛盾を含みつつ」。 もし実際に理想郷があなたの手や足の届くところにあったとして、そこに行けば自分の理想が叶えられるとして、あなたは他のすべてを捨ててでもそこに行こうと思うだろうか? 今期のみずがめ座のキーワードは、「時代錯誤の効用」。 ビル・ゲイツが何度も読み直したという『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』は、アメリカが経済破綻寸前で一党独裁による軍事化が進んだ世界線であり、誰もが信用度や性的魅力を数値化され、手元の端末で簡単にプロフィールを検索されるなど、過度にメディアが発達した近未来を描いたディストピア小説。
今期のみずがめ座のキーワードは、「時代錯誤の効用」。 ビル・ゲイツが何度も読み直したという『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』は、アメリカが経済破綻寸前で一党独裁による軍事化が進んだ世界線であり、誰もが信用度や性的魅力を数値化され、手元の端末で簡単にプロフィールを検索されるなど、過度にメディアが発達した近未来を描いたディストピア小説。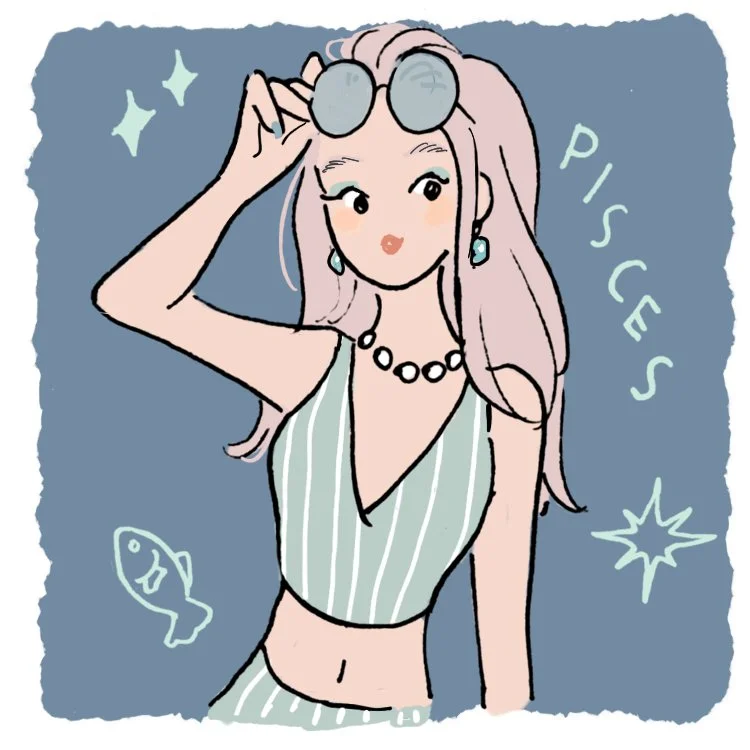 今期のうお座のキーワードは、「満たされること」。 地方から上京してきた著者が東京という都市について綴った随筆集『東京で生きる』では、快楽と幻想と記号の世界としての「東京」で生きることの怖さと魅力とがあますことなくすくいとられており、時にハッとするような繊細な文章で読者の胸をついてきます。
今期のうお座のキーワードは、「満たされること」。 地方から上京してきた著者が東京という都市について綴った随筆集『東京で生きる』では、快楽と幻想と記号の世界としての「東京」で生きることの怖さと魅力とがあますことなくすくいとられており、時にハッとするような繊細な文章で読者の胸をついてきます。











































































