-

【SUGARさんの12星座占い】<11/15~11/28>の12星座全体の運勢は?
「雪が花に変わるとき」
11月22日の「小雪」を過ぎれば、もう雪の季節。「一片飛び来れば一片の寒」と言うように舞いくる寒さに本格的に備え始めるこの頃には、こたつを導入したり暖房を入れ始める人も増えてくるはず。
そして11月30日には、静かに深まってゆく冬の夜に双子座の満月を迎えていきます。今回のテーマは「緊張の中にあるゆるみ」。精神を鋭敏に研ぎ澄ましていくなかで訪れる一瞬の静けさ、そして平穏。それは瞑想の境地が深まったときの感覚にも似ています。初めは雑念ばかりが浮かんで、かえって心が騒がしく感じたり、眠くなってしまったりしていたのが、自然と頭が消えて胴体だけになったように感じてきて、意識は活動しているのに、何かを「志向する」ことなしにいられる「非思考」状態に入っていく。
禅ではこれを「自分自身の『私』を忘れる」とか「非思量」などと言うそうですが、それはどこか「風花」というこの時期の季語を思わせます。風花とは風に運ばれてちらちらと舞う雪のかけらのことですが、あっけないほどのはかなさで消えていく雪片に、ひとつの花を見出していくのです。それはすべてのものに命があると考えていた日本人が、厳しい冬の訪れにも愛おしむような気持ちを向けていたことの何よりの証しでしょう。
今回の満月でも、集中力を高めて厳しい現実や人生の課題(雪片)と向かい合っていくことで、そのなかに隠された恵みや喜び(花)を見出していくことができるかどうかが問われていくはず。
-

今期のおひつじ座のキーワードは、「不条理に抗う」。
カミュの『ペスト』は、新型コロナウイルス感染症が世に広まってから、おそらく最も読み返されている文学作品の一つですが、じつは多くの人が感染症に脅かされた経験や事実から書かれたものではなく、第二次大戦中にナチスに支配された傀儡政権下のフランスで、閉ざされた生活環境のなか、結核の再発に怯えつつ過ごす中で構想された作品でした。
つまり、見捨てられるように死んでいく人が多数出てしまう感染症は、この作品ではあくまで隠喩として用いられ、主人公としてそれに淡々と立ち向かう現場の医師リウーは、絶望的な状況での抵抗の生き方を指し示しているのだと言えます。
それは例えば、不条理と感じられる事態に対して「悔い改める」ことを要求するパヌルー神父との間に交わされた次のような会話にも凝縮して表現されています。
リウー「まったくあの子だけは、少なくとも罪のない者でした。あなたもそれはご存知のはずです!」
パヌルー「どうして私にあんな怒ったような言い方をなさったのです。私だってあの光景は見るに忍びなかったのですよ」
リウー「ほんとに、そうでした。悪く思わないでください。…この街では僕はもう憤りの気持ちしか感じられなくなるときがよくあるんです」
パヌルー「それはわかります。まったく憤りたくなるようなことです。しかし、それはつまり、それがわれわれの尺度を超えたことだからです。恐らくわれわれは自分たちの理解できないことを愛さねばならないのです」
リウー「そんなことはありません。僕は愛というものをもっと違ったふうに考えています。そうして、子供たちが責め苛まれるように作られたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯んじません」
パヌルー「(寂しげに)ほんとにリウーさん。私には今やっとわかりました。恩寵と言われているのはどういうことか」
リウー「それは僕にはないものです、確かに。しかし僕はそんなことをあなたと議論したいとは思いません。われわれは一緒に働いているんです、冒涜や祈祷を越えてわれわれを結びつける何ものかのために。それだけが重要な点です」
主人公は神を信じてはいませんが、神に代わる何かについて語り、何よりそれを日々の生活に即した労働の中に見出そうとしているのです。人間を責めるのではなく、穏やかに受け入れるようになるために。
今期のおひつじ座もまた、犠牲者が次々と生み出されていく構造が厳然と存在している現代世界において、どうしたら自分の生活をこの主人公の振る舞いに近づけていけるか、改めて考えてみるといいでしょう。
参考:アルベール・カミュ、宮崎嶺雄訳『ペスト』(新潮文庫)
-

今期のおうし座のキーワードは、「癖を愛でる」。
16~17世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンは、大法官として当時イギリスの政治事情にも深く関わっていた人物でもあり、そうした経験をふんだんに交えて書かれた『エッセー』の著者としても知られています。
その中でも「運命」をめぐる一連の記述は、今期のおうし座にとっても重要な指針となっていくはず。
ベーコンは、人間の運命は外的な諸条件にも左右されるが「目を凝らして注意深く観察すれば、運命を見分けることができよう。運命は盲目だが、見分けられぬものではないから」とまずことわった上で、次のように述べるのです。
「運命の歩みは、空の銀河に似ている。銀河は多くの小さな星の集まり、あるいは塊りである。小さな星は散在していてよく見えないが、一緒になって光っている。同様に、多くの小さな、見えにくい徳性が集まって人々を仕合わせにするのである」
面白いのは、それに付け加えて「イタリア人はそれらのうち、人のほとんど気付かない二、三の点に注目し、見どころのある人間について、ちょっと愚直なところがあることを他の条件とともに挙げている」とベーコンが言っている部分。
「愚か」と評したくなるほどに実直で一本気であることは、確かに「小さな、見えにくい徳性」の例としては適切ですし、案外、ほどよく表裏がなくて誰からも好感をもたれる性格よりも、よほど人の運命を左右する要因になるのかも知れません。
そうした、場合によってはアクに感じられるような、普段ほとんど意識していないような小さな癖を見つめるように心がければ、確かにベーコンの言う通り、あまりひどく運命に翻弄されることからは免れられるはず。
自分にはどんな些細な癖や、「小さな、見えにくい徳性」があるのか―。今回の満月はそんなことを意識してみるといいでしょう。
参考:渡辺義雄訳『ベーコン随想集』(岩波文庫)
-

今期のふたご座のキーワードは、「スナフキン」。
言われてみれば当然のことですが、人生は仕事がすべてではない。今すぐ仕事場の外へ出て、あたりをぐるりと見回したら、あくせく働いたりする生き方とは対極にある人物―『ムーミン』シリーズの影のヒーローであるスナフキン―のことを思い出してみてください。
スナフキンは謎めいた旅人で、詩人で、音楽家でもあり、毎年春になると帽子をかぶりハーモニカをもってムーミン谷に姿を現します。ムーミンたちはいつもスナフキンのことを待ちわびていて、スナフキンが来てはじめて本当に春が来たように感じるほど。
ただし、だからといって彼をあてにしてはいけない。スナフキンは「都合がついたら来るよ」と言う一方で、「もしかしたらぜんぜん来ないかもしれない。まったくちがう方向へ行ってしまうかもしれないからね」とも言っているから。
風変わりな自由人スナフキンは、何より身軽に旅をすることを大切にしています。トランクはいつもほとんど空っぽ。興味がわいたものを徹底的に知り尽くしたら、後に置いていって、持ち歩いたりしない。
そして、気が向いた場所にテントを張って、どこまでも続く道を家とする。
もちろん、すべてをスナフキンのようにするのは難しいでしょう。けれど、ふたご座の人が世界をすばらしく輝かしい場所と感じていくためには、机にかじりついていたり、人間関係や財産をあまりにガチガチに固定したり、詰め込み過ぎてしまうのはご法度なのだということも痛感しているはず。
今期のふたご座は、そんな本来の自分らしさを取り戻す意味でも、スナフキンのように帽子に羽根をつけて軽やかに道をいくイメージを大切にしていきたいところ。
参考:トーベ・ヤンソン、山室静訳『たのしいムーミン一家』(講談社文庫)
-

今期のかに座のキーワードは、「後悔しないために」。
画家のポール・ゴーギャンと言えば、19世紀末のパリで新しい画壇の指導者的存在と見なされていたにも関わらず、ヨーロッパを逃れてオセアニアのタヒチ島に飛び出し、現地で牧歌的生活を送ったイメージが浮かびます。
しかし、実際にはオセアニアでは度重なる妻との別離や、健康状態の悪化、隣人とのいさかい、名誉棄損での有罪判決など、波瀾に満ちた生活を送り、晩年は孤独な日々を過ごし、急死した後もその報は母国に届かず、遺言もなかったため、家財はほとんど売り払われてしまったのだとか。
彼が自分の死期が近いことを悟ってから書いた回顧録風のエッセー集には、実に味わい深い文章が数多く収められているのですが、中でも「人生とは」という野暮ったい表題が付けられた章には、率直にその生きざまのエッセンスが込められているように思います。
冒頭には「人生とは、人がそれを意志的に実践するのでなければ、少なくともその人の意志の程度にしか、意味を持たないものだ、と私は考えている。美徳、善・悪などはことばである。もし人々が、それを挽き砕いて建物をたてるのでなければ、(中略)意味を持たない」とあり、続いてあっちこっち矛盾する述懐をこねくりまわした後に「私はときには善良であった―私はそのことで得意になりはしない。私はしばしば不良であった―私はそれを後悔しない」と爽やかに結んでみせるのです。
それはヨーロッパ文明の人工的・因習的な何もかもから脱出せんとしたゴーギャンがたどりついた、自然で未知に取り囲まれたありのままの生の姿だったのではないでしょうか。
今期のかに座もまた、いったんは破綻し、当たり前のようにあった現実が壊れてしまったその跡地でこそ、ゴーギャンが掴み取ったような自然体な生が立ち現れてくるのだということを実感していけるはず。絵に描いたような「ことば」ではなく、それを噛み砕いた自分なりの実感を大切にしていきたいところです。
参考:ゴーギャン、前川堅市訳『ゴーガン 私記』(美術出版社)
-

今期のしし座のキーワードは、「生活を詩にすること」。
「労働者に必要なのは、パンでもバターでもなく、美であり、詩である」。
ユダヤ人女性思想家シモーヌ・ヴェイユ(1909~1943)の言葉です。彼女は、労働の意味だけでなく、芸術の本質についても、この宇宙を統御している二つの力「重力と恩寵(おんちょう)」という独自の用語によって、同名の断章集の中で何度も繰り返し考察していました。
彼女の言う「重力」とは、物体の重力にも似た”こころの惰性的で功利的な働き”のことであり、それに対して「恩寵」とは、”こころの単なる自然な働きを超えたもの”を指し、「光」とも言い換えられています。
例えば、彼女は「グレゴリオ聖歌のひとつの旋律は、ひとりの殉教者の死と同じだけの証言」をしており、それは「重力のすることを、もう一度愛によってやり直す」という"二重の下降運動”こそ、「あらゆる芸術の鍵」なのだと述べた上で、次のように言い切るのです。
「情熱的な音楽ファンが、背徳的な人間だということも大いにありうることである。だが、グレゴリオ聖歌を渇くように求めている人がそうだなんてことは、とても信じられない」、と。
彼女は、労働者たちには「その生活が詩になること」こそ必要なのであり、「ただ宗教だけが、この詩の源泉となることができる」こと、また「宗教ではなく、革命こそが民衆のアヘンである」と強調していました。
彼女の生きたのは二十世紀前半でしたが、彼女の「労働者から詩が奪われていることこそ、あらゆる形での道徳的退廃の理由なのだ」といった指摘は現代人においても、ますます重要になってきているように思います。
今期のしし座もまた、自身の生活がどれだけ重力に支配されているか、また、恩寵を迎え入れるだけの渇望や真空状態にどれだけ敏感になれているか、改めて振り返ってみるといいでしょう。
参考:シモーヌ・ヴェイユ、田辺保訳『重力と恩寵』(ちくま学芸文庫)
-

今期のおとめ座のキーワードは、「Bライフ」。
都心に一戸建てを買う。その代わり、三十年ローンを組んで数千万の借金をして、家と会社に自身を縛りつける。そういう生き方がもう当たり前には成り立たなくなってきた昨今、郊外や田舎への移住だけでなく、「家は借金をしてでもいつかは買うもの」という常識自体が揺らぎ始めているように思います。
高村友也の『自作の小屋で暮らそう』は、路上生活を経て合法的な小屋暮らしを志向した著者が、実際に10万円で山梨の雑木林に掘っ立て小屋を建て、ベーシックに暮らす(Bライフ)までの試行錯誤をまとめた本であり、断捨離やスローライフなどに興味を抱いている多くの人にとってバイブルのような一冊と言えるのではないでしょうか。
本書には、実際の小屋を建てる上での工夫や工程だけでなく、家計簿や生活サイクルなどの“裏側”情報が満載なのですが、中でもひときわ目をひくのが、章と章のあいだに差し込まれている著者の生活を垣間見た隣人や来訪者などにかけられた印象的な言葉の数々。
それは例えば、家を建てたばかりの頃に、宅配便のおじさんがかけてきた、「ここでがんばってるんですか?」という一言で、「がんばって」の箇所には強調点が打たれています。
この言い方には、確かにひっかかる何かがあります。それは「小屋暮らし」というものが、普通の暮らしをひとつひとつ手放していくことで、生活の「最低限」を頑張って下げていった先にあるものという世間の一般的なイメージを浮き彫りにするだけでなく、大きな犠牲を払うだけの理由やうしろめたさを思わず探ってしまう人間心理を炙りだすからでしょう。
けれど、著者のスタンスはどうもそういうものとは違っているのです。「好きなだけ寝転がっていられる」自由な状態をできる限り続けたいと思って小屋を建てた訳で、「基本が野宿」というか、普通の生活を手放していくというより、何もないところから足していく感じで「最低限」を模索している。
その意味では、今期のおとめ座もまた、自分なりの「ベーシックライフ」というものを、普通から減らしていく形ではなく、これだけは譲れないor譲りたくない生活の根幹から足していくやり方で模索してみるといいかも知れません。
参考:高村友也『自作の小屋で暮らそう』(ちくま文庫)
-
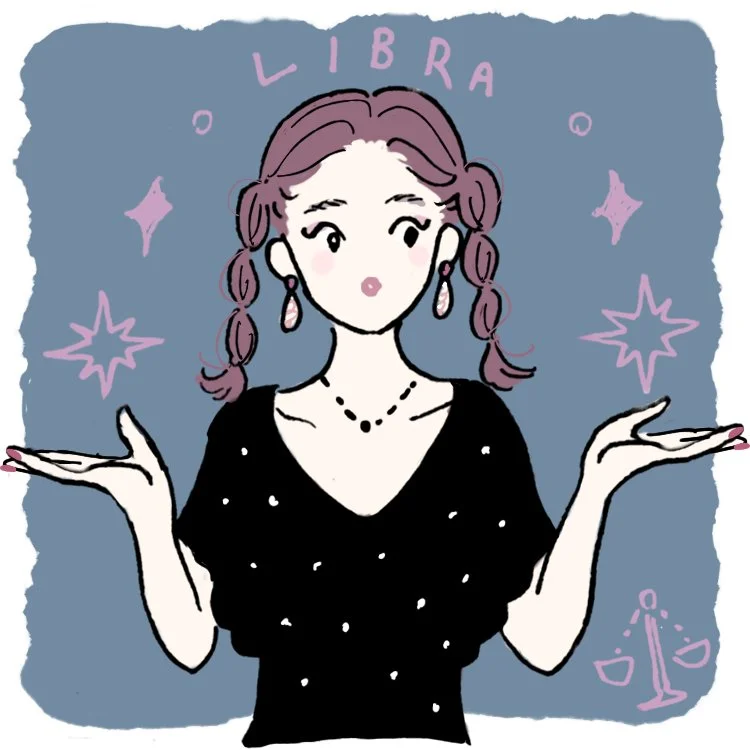
今期のてんびん座のキーワードは、「迷宮感覚」。
ルーマニア出身で20世紀を代表する宗教学者であり作家でもあったエリアーデが、戦後パリで活躍してからシカゴに移住するまでの1945〜58年の日記『エリアーデ日記(上) 旅と思索と人』は扱う内容も登場人物もじつに多岐にわたるのですが、中でも何度か現れる覚醒夢をめぐる記述や、自身の癌への疑惑によって一気に増してくる死の予感などが実に生々しく鬼気迫るものがあります。例えば、
「またもやあの奇妙な夢。荒涼とした悲しみの感情しか想い出せない。悲しみは全面的で透明だったから、眠りの深みのうちにあっても私の全存在が涙のうちに汲み尽くされるように思えた」
こうした美しい一節に出会ったかと思えば、次のような極めて冷静な考察も顔を覗かせます。
「<未開>人も、文明人と同様、デーモン的ディオニュソス的力や、異常な感動を誘う見世物的神像の方を好んでいる。人間はこれらの聖なる力がいずれも自分を助けることができないと確信した時にしか<神>を思い出さない。要するに古代的世界でも人は絶望を通してしか神に達しないのである。」
こうした傾向は今日ますます広く一般の人々において強まっているのではないでしょうか。著者は自身の魂の叫びとしてこう語ってもいます。
「私は繰り返される失敗、苦難、憂鬱、絶望が、ことばの具体的で直接的な意味での<地獄下り>を表していることを明晰な意志の努力によって理解し、それらを乗り越えうる者でありたい、と念じている。」
しかし果たしてそんなことが可能なのでしょうか。著者は先の記述に続けて、「人は自分が実際に地獄の迷宮中で迷っているのだと悟ればすぐ、ずっと以前に失ったと思い込んでいた精神の力が、新たに十倍になるのを感じるのだ」とも書いていますが、こればかりは実際に同じ境遇に立ってみなければ分からないでしょう。
その意味で、今期のてんびん座であれば、エリアーデのいう新鮮な復活ないし再誕を体験していくことができるかも知れません。いつも以上に、見た夢の内容に注意深く意識を向けてみてください。
参考:M・エリアーデ、石井忠厚訳『エリアーデ日記(上) 旅と思索と人』(未来社)
-

今期のさそり座のキーワードは、「波でなく、永久運動」。
現代においても、来世とか輪廻転生といった死生観をなんとなく信じている人は意外と多い。というより、統計数理研究所が5年ごとに実施している「日本人の国民性調査」などを見ると、1958年には「あの世」を信じる人が全世代平均で20%だったのに対し、2008年の調査結果では38%と2倍近くに増えています。
特に20歳代に関しては13%から49%と4倍近くに増えており、他の調査などを見ても、こうした傾向は多くの死者が出た2011年の東日本大震災以降ますます強まっているように見受けられます。
ところで、こうした死後の生について一生懸命考えていた人のひとりに、ドストエフスキーと並ぶ19世紀ロシアの大作家トルストイがいます。永年にわたる苦悩と煩悶の末に達した考察について記した『人生論』では、例えば次のように語っています。
「人間は、自分の生が一つの波ではなく、永久運動であることを、永久運動が一つの波の高まりとしてこの生となって発現したにすぎぬことを、理解したときにはじめて、自分の不死を信じるのである」
これは一昔前に有名になった、個々の生命あるいは種はそれぞれが独立していながら相互に依存/共生しながらひとつの広大で複雑な潮流として進化してきたというライアル・ワトソンの「生命潮流」にも似た考え方ですが、少なくともトルストイは「死とは迷信であり、人々の生命はこの世では終わらない」という強い信念を持っていたことは確かなようです。
ふつう人の死後に残るのはその人に対する思い出であると考えられていますが、トルストイいわく、愛をもって生命的に生きた人間についての思い出は、単なる観念ではなく、死後もその相手がわれわれに対して生きていた時と同じように作用してくる。いや、世界に対して作られた新しい関係によって、その働きはより一層強くなりさえするのだ、と。
今期のさそり座もまた、ふだん自身がどれだけ生命的に生きているか、つまりここで「永久運動」と呼ばれたものにどれだけ積極的に参加できているかが、改めて浮き彫りにされていくでしょう。
参考:トルストイ、原卓也訳『人生論』(新潮文庫)
-

今期のいて座のキーワードは、「複相的な地層の堪能」。
どこか遠く離れた異国の地に、見た目も性格も何もかもが違うのに、もう一人の自分と言えるような人物が今も息をして、彼彼女なりの生活を営んでいるのではないか―。
そんな思いに駆られた時は、直接行って確かめる代わりに、ロレンス・ダレルの『アレクサンドリア四重奏』のような作品を読むといいかも知れません。
物語は4つの作品に分かれており、『ジュスティーヌ』『バルタザール』『マウントオリーヴ』『クレア』という登場人物の名を冠し、ほとんど出来事の説明がないままに複相的に連続する連続作として展開していきます。
舞台となるのは、カイロに次ぐエジプト第二の都市で、かのアレクサンドロス大王が作ったとされるアレクサンドリア。
まず最初に案内してくれるのは、虚栄心の強い女神のようなジュスティーヌ。浅黒い肌に白いドレスが映えるアレクサンドリア社交界の申し子。また、そんな人妻ジュスティーヌとは真逆の存在とさえ言える、おだやかで孤独な芸術家のクレア。それから、「とても美しい低温のしわがれ声」と黄色いヤギのような目とひどく不格好な手の持ち主バルタザール。そして、学校の教師を務めながら、彼女たちと次々に恋に落ちる語り手のダーリー。
あるいは、彼らからすこし時代を遡って、エジプトへと派遣された将来を嘱望される若き外交官マウントオリーヴという人物も見過ごせない。彼らのうち一人が欠けても、四重奏としての物語は成立しないのです。
著者ダレルの考えでは、人の性格は生まれた土地によって形づくられますが、それ以上に人がその場所に性格を与えるのだとも言います。その意味で、この作品を読むことは、彼ら登場人物と町とが相互に折り重なってこそ作りあげられるアレクサンドリアの複雑な層を堪能するに等しく、そうでなければ、例えば誰が自分に近しい存在かなどは分かりっこないのです。
今期のいて座もまた、相互に複雑な影響を与えあう、人と町、町と町、そして人と人との複雑な連関についてよくよく思いを馳せていくことになっていくことでしょう。
参考:ロレンス・ダレル、高松雄一訳『アレキサンドリア四重奏』(河出書房新社)
-

今期のやぎ座のキーワードは、「いのちに触れる」。
「いのちにふれるというのは、乱れている相手を自分の内部に取り込むことだ」
そう語るのは、伝説的な生け花作家・中川幸夫。
彼がその名を轟かせた作品に『花坊主』(1973)があります。真っ赤なカーネーション900本の花をむしり、それをまるでうつ伏せになった女体の下半身のような形をした大きなガラス壺に一週間詰めておくと、花は窒息するのだそうです。
そして腐乱したその赤い花肉を詰め込んだ壺を、真っ白なぶ厚い和紙の上にどんと逆さに置く。鮮血のような花の液が、じわりじわりと滲み出してゆく。そんな狂おしい光景。
哲学者の鷲田清一が「ホスピタブル」なケアの現場をフィールドワークして綴った『<弱さ>の力』には、さらに次のような中川とのやり取りが記されています。
「お花を恨んだことってないですか?」
「ふふふ。恨むというよりは……言うことを聞いてくれませんしね」
「女のひとくらい、やっぱりむずかしいんでしょうか」
「そりゃ、もう、なんですなあ、なんとも言えないけれど」
中川を扱った章の表紙には、「血に染まる」「花と刺し違える八十二歳」とありますが、「癒す/癒される」という関係性も、彼にとっては「食う/食い破られる」といったものに近く、少なくともどちらかが一方的に関わって無傷でいられるようなものではないのでしょう。
その意味で今期のやぎ座もまた、もはや黙って素通りすることは許されない、徹底的に関わらざるを得ない何か誰かについて、改めて覚悟を深めていくことがテーマとなっていきそうです。
参考:鷲田清一『<弱さ>の力』(講談社学術文庫)
-

今期のみずがめ座のキーワードは、「祖先のこころが宿る場所」。
赤ちゃんが生まれた時、親や親戚、友人一同が見舞いに来て、まずいう言葉は昔も今も変わっていない。
「この子はお父さん似だ、鼻がそっくり」とか「目はおばあちゃん似だね」といった言葉である。
これは言う方も聞く方もあまりに日常的なことなので、少しも特別なことだと思わない訳ですが、実はそうではないのだと、長年にわたり民話の採録・再話に取り組んできた松谷みよ子は言います。
「こうした言葉ほど、ひとりの赤ちゃんの生命が連綿と祖先から受け継がれたものであることを語っている言葉はない。そして母の腕に抱かれ、ここはじいちゃんにんどころとあやされて育った子は、自分でも知らないうちに、生命の重みを知るのではなかろうか。」
戦後児童文学の開拓者でもあった彼女は、著書『民話の世界』(1974)の中で、子守歌や民話が語り継がれていくことの大切さについて、次のようにも言及しています。
「じいちゃんがあり、ばあちゃんがあり、とうちゃんがあり、かあちゃんがあり、姉ちゃんもいて、そして自分が存在するということ、木の股から生まれたのではないということ、良くも悪くも受け継がれた血をからだの中に持っているということを知るのではないだろうか。」
今ではすっかり歌って遊ぶ子供も少なくなってしまった「わらべ唄」が大切なのは、そこに「受け継がれていく生命の重みとして受けとめてきた、私たちの祖先のこころ」があるからに他ならないのだ、と。
一方で、ことばが“乱れ”ているという言論が飛び交い、米大統領選でトランプが選出された2016年には英国・オックスフォード英語辞典が「Word Of The Year(その年を象徴する言葉)」に「ポスト・トゥルース」を選んだことも記憶に新しい現代世界において、こうした「語り継がれてきた言葉の重み」やそこから言葉を発していくことはますます難しくなっているように思います。
そんな中、今期のみずがめ座にとって、自身の日常に埋没し、その価値や重みがすっかり見過ごされてしまうようになった「祖先のこころが宿る場所」としての言葉や語りを、改めて再発見していくことが一つのテーマとなっていくでしょう。
参考:松谷みよ子『民話の世界』(講談社学術文庫)
-
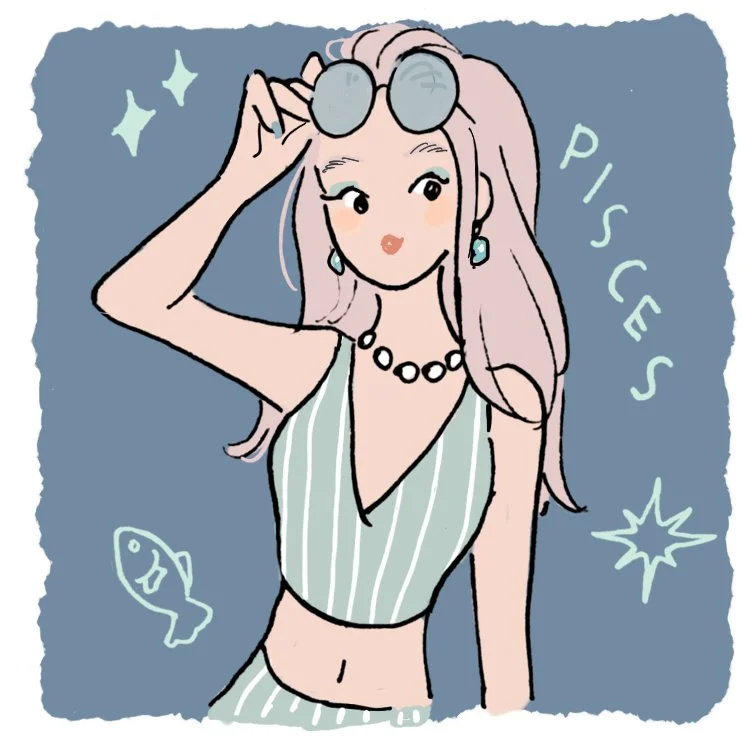
今期のうお座のキーワードは、「流動」。
宗教学者の中沢新一が長年研究してきた明治の生んだ稀代の博物学者・南方熊楠(みなかたくまぐす)についての講演をまとめた『熊楠の星の時間』を読んでいると、熊楠という破格のスケールの人物の持ち得た思想や活動を追いかけていくことで、そこに「東洋人の思想の原型」を見出そうという氏の野心的試みが平易な文体から浮かび上がってきます。
例えば、「南方マンダラ」と命名した熊楠流の学問の方法論について、著者は次のように記しています。
「事物には「潜在性の状態」と「現実化した状態」との二つの様態があって、現実化している事実もじつは潜在性の状態にある事実を介して、お互いにつながりあっています。そのため現実化した事実だけを集めて因果関係を示してみせたとしても、それは不完全な世界理解しかもたらさない、というのが熊楠の考えでした。」
これは何も粘菌や華厳経など、熊楠が学問をしていく上で関わったものに関係しているだけでなく、今日のエコロジー思想を先取りしていた神社合祀反対運動や霊魂についての考え、彼がその身をもって生きたセクソロジー、男色、ふたなり(半陰陽)なども含めての言及でしょう。
「事物や記号はいったん潜在空間にダイビングしていく見えない回路を介して、お互い関連しあっています。そして潜在空間ではあらゆるものが自由な結合をおこなう可能性を持って流動しています。」
そう、この「流動」をダイナミックに展開されていく姿こそが、熊楠が顕微鏡の粘菌を通して見出していったいきいきとしたビジョンであり、新自由主義的な思考に慣れきってしまった現代人が見失いつつあるこの世界の実相なのではないでしょうか。
今期のうお座もまた、これまでの自分の仕事や活動を支えてきた世界観を別の方向へとシフトさせていく上で、改めて自分なりの"オルタナティブ”な思想を模索していくといいでしょう。
参考:中沢新一『熊楠の星の時間』(講談社現代メチエ)
 【SUGARさんの12星座占い】<11/15~11/28>の12星座全体の運勢は?
【SUGARさんの12星座占い】<11/15~11/28>の12星座全体の運勢は? 今期のおひつじ座のキーワードは、「不条理に抗う」。 カミュの『ペスト』は、新型コロナウイルス感染症が世に広まってから、おそらく最も読み返されている文学作品の一つですが、じつは多くの人が感染症に脅かされた経験や事実から書かれたものではなく、第二次大戦中にナチスに支配された傀儡政権下のフランスで、閉ざされた生活環境のなか、結核の再発に怯えつつ過ごす中で構想された作品でした。
今期のおひつじ座のキーワードは、「不条理に抗う」。 カミュの『ペスト』は、新型コロナウイルス感染症が世に広まってから、おそらく最も読み返されている文学作品の一つですが、じつは多くの人が感染症に脅かされた経験や事実から書かれたものではなく、第二次大戦中にナチスに支配された傀儡政権下のフランスで、閉ざされた生活環境のなか、結核の再発に怯えつつ過ごす中で構想された作品でした。 今期のおうし座のキーワードは、「癖を愛でる」。 16~17世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンは、大法官として当時イギリスの政治事情にも深く関わっていた人物でもあり、そうした経験をふんだんに交えて書かれた『エッセー』の著者としても知られています。
今期のおうし座のキーワードは、「癖を愛でる」。 16~17世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンは、大法官として当時イギリスの政治事情にも深く関わっていた人物でもあり、そうした経験をふんだんに交えて書かれた『エッセー』の著者としても知られています。 今期のふたご座のキーワードは、「スナフキン」。 言われてみれば当然のことですが、人生は仕事がすべてではない。今すぐ仕事場の外へ出て、あたりをぐるりと見回したら、あくせく働いたりする生き方とは対極にある人物―『ムーミン』シリーズの影のヒーローであるスナフキン―のことを思い出してみてください。
今期のふたご座のキーワードは、「スナフキン」。 言われてみれば当然のことですが、人生は仕事がすべてではない。今すぐ仕事場の外へ出て、あたりをぐるりと見回したら、あくせく働いたりする生き方とは対極にある人物―『ムーミン』シリーズの影のヒーローであるスナフキン―のことを思い出してみてください。 今期のかに座のキーワードは、「後悔しないために」。 画家のポール・ゴーギャンと言えば、19世紀末のパリで新しい画壇の指導者的存在と見なされていたにも関わらず、ヨーロッパを逃れてオセアニアのタヒチ島に飛び出し、現地で牧歌的生活を送ったイメージが浮かびます。
今期のかに座のキーワードは、「後悔しないために」。 画家のポール・ゴーギャンと言えば、19世紀末のパリで新しい画壇の指導者的存在と見なされていたにも関わらず、ヨーロッパを逃れてオセアニアのタヒチ島に飛び出し、現地で牧歌的生活を送ったイメージが浮かびます。 今期のしし座のキーワードは、「生活を詩にすること」。 「労働者に必要なのは、パンでもバターでもなく、美であり、詩である」。
今期のしし座のキーワードは、「生活を詩にすること」。 「労働者に必要なのは、パンでもバターでもなく、美であり、詩である」。 今期のおとめ座のキーワードは、「Bライフ」。 都心に一戸建てを買う。その代わり、三十年ローンを組んで数千万の借金をして、家と会社に自身を縛りつける。そういう生き方がもう当たり前には成り立たなくなってきた昨今、郊外や田舎への移住だけでなく、「家は借金をしてでもいつかは買うもの」という常識自体が揺らぎ始めているように思います。
今期のおとめ座のキーワードは、「Bライフ」。 都心に一戸建てを買う。その代わり、三十年ローンを組んで数千万の借金をして、家と会社に自身を縛りつける。そういう生き方がもう当たり前には成り立たなくなってきた昨今、郊外や田舎への移住だけでなく、「家は借金をしてでもいつかは買うもの」という常識自体が揺らぎ始めているように思います。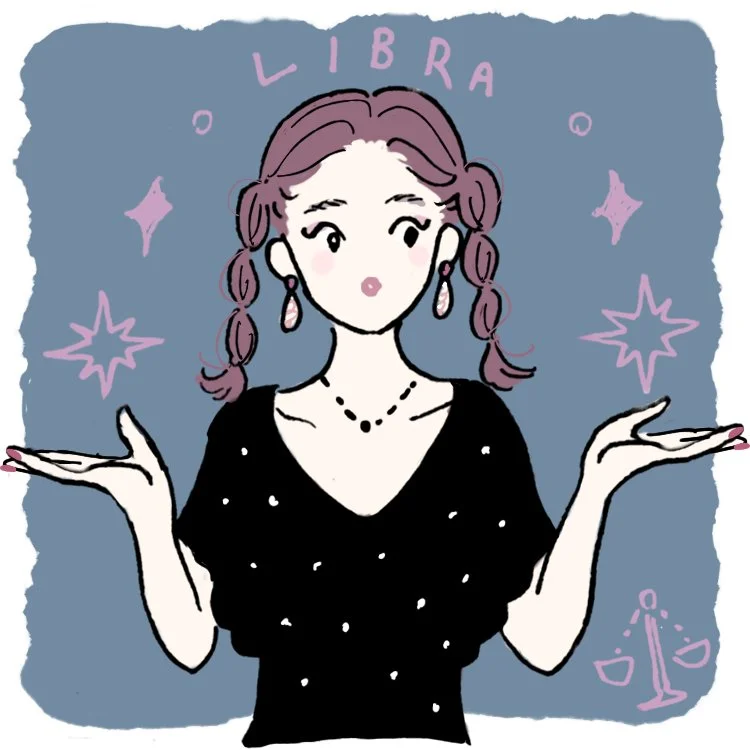 今期のてんびん座のキーワードは、「迷宮感覚」。 ルーマニア出身で20世紀を代表する宗教学者であり作家でもあったエリアーデが、戦後パリで活躍してからシカゴに移住するまでの1945〜58年の日記『エリアーデ日記(上) 旅と思索と人』は扱う内容も登場人物もじつに多岐にわたるのですが、中でも何度か現れる覚醒夢をめぐる記述や、自身の癌への疑惑によって一気に増してくる死の予感などが実に生々しく鬼気迫るものがあります。例えば、
今期のてんびん座のキーワードは、「迷宮感覚」。 ルーマニア出身で20世紀を代表する宗教学者であり作家でもあったエリアーデが、戦後パリで活躍してからシカゴに移住するまでの1945〜58年の日記『エリアーデ日記(上) 旅と思索と人』は扱う内容も登場人物もじつに多岐にわたるのですが、中でも何度か現れる覚醒夢をめぐる記述や、自身の癌への疑惑によって一気に増してくる死の予感などが実に生々しく鬼気迫るものがあります。例えば、 今期のさそり座のキーワードは、「波でなく、永久運動」。 現代においても、来世とか輪廻転生といった死生観をなんとなく信じている人は意外と多い。というより、統計数理研究所が5年ごとに実施している「日本人の国民性調査」などを見ると、1958年には「あの世」を信じる人が全世代平均で20%だったのに対し、2008年の調査結果では38%と2倍近くに増えています。
今期のさそり座のキーワードは、「波でなく、永久運動」。 現代においても、来世とか輪廻転生といった死生観をなんとなく信じている人は意外と多い。というより、統計数理研究所が5年ごとに実施している「日本人の国民性調査」などを見ると、1958年には「あの世」を信じる人が全世代平均で20%だったのに対し、2008年の調査結果では38%と2倍近くに増えています。 今期のいて座のキーワードは、「複相的な地層の堪能」。 どこか遠く離れた異国の地に、見た目も性格も何もかもが違うのに、もう一人の自分と言えるような人物が今も息をして、彼彼女なりの生活を営んでいるのではないか―。
今期のいて座のキーワードは、「複相的な地層の堪能」。 どこか遠く離れた異国の地に、見た目も性格も何もかもが違うのに、もう一人の自分と言えるような人物が今も息をして、彼彼女なりの生活を営んでいるのではないか―。 今期のやぎ座のキーワードは、「いのちに触れる」。 「いのちにふれるというのは、乱れている相手を自分の内部に取り込むことだ」
今期のやぎ座のキーワードは、「いのちに触れる」。 「いのちにふれるというのは、乱れている相手を自分の内部に取り込むことだ」 今期のみずがめ座のキーワードは、「祖先のこころが宿る場所」。 赤ちゃんが生まれた時、親や親戚、友人一同が見舞いに来て、まずいう言葉は昔も今も変わっていない。
今期のみずがめ座のキーワードは、「祖先のこころが宿る場所」。 赤ちゃんが生まれた時、親や親戚、友人一同が見舞いに来て、まずいう言葉は昔も今も変わっていない。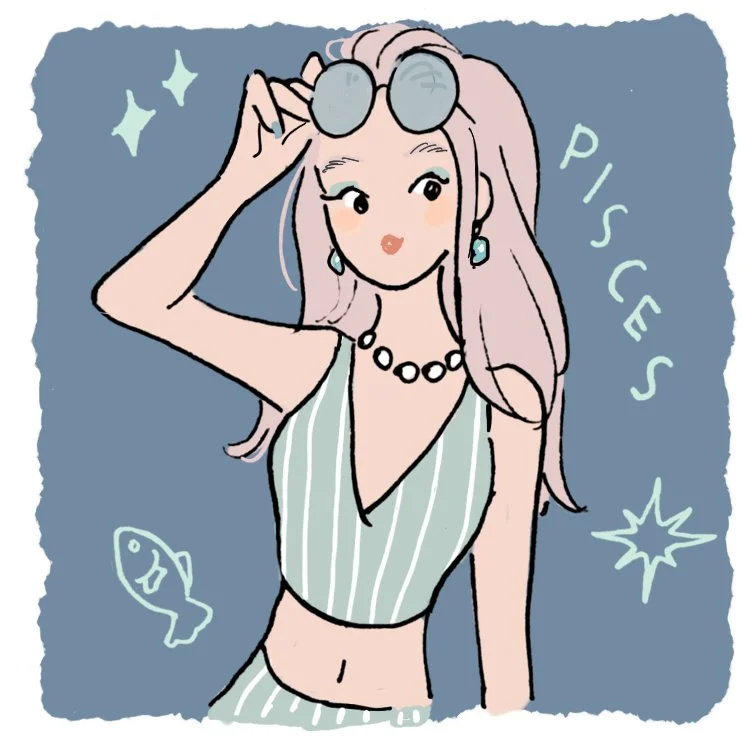 今期のうお座のキーワードは、「流動」。 宗教学者の中沢新一が長年研究してきた明治の生んだ稀代の博物学者・南方熊楠(みなかたくまぐす)についての講演をまとめた『熊楠の星の時間』を読んでいると、熊楠という破格のスケールの人物の持ち得た思想や活動を追いかけていくことで、そこに「東洋人の思想の原型」を見出そうという氏の野心的試みが平易な文体から浮かび上がってきます。
今期のうお座のキーワードは、「流動」。 宗教学者の中沢新一が長年研究してきた明治の生んだ稀代の博物学者・南方熊楠(みなかたくまぐす)についての講演をまとめた『熊楠の星の時間』を読んでいると、熊楠という破格のスケールの人物の持ち得た思想や活動を追いかけていくことで、そこに「東洋人の思想の原型」を見出そうという氏の野心的試みが平易な文体から浮かび上がってきます。











































































