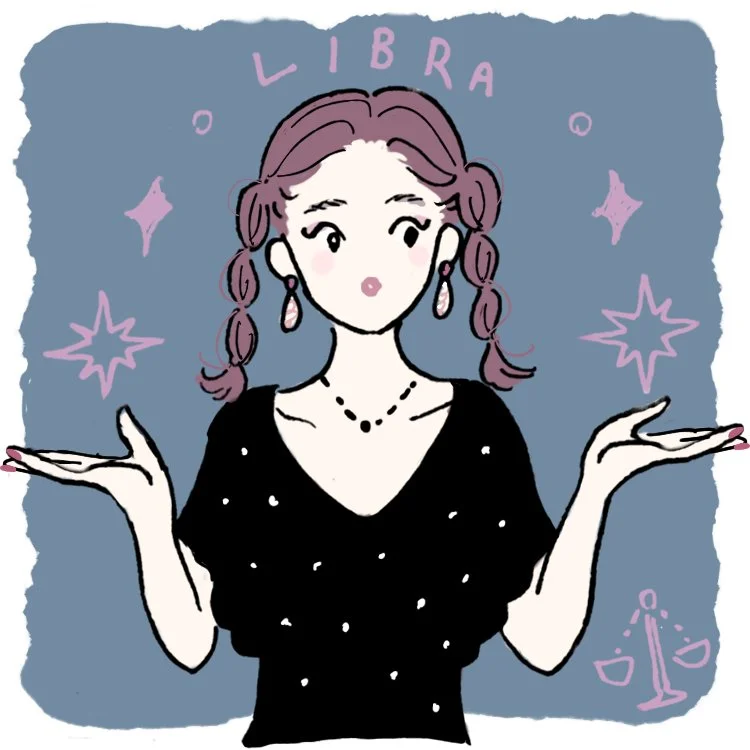【乙女座】哲学派占い師SUGARさんの12星座占い<2/20~3/5> 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモいー
12星座全体の運勢
「記憶の「虫だし」」
土の中にあたたかい気配が届き、それを感じた虫たちが穴の中から這い出してくる「啓蟄」直前である3月3日に、うお座12度(数えで13度)で新月を迎えていきます。
「非現実的で、過度な理想主義」や「既存世界の<外部>への遁走」を意味する木星と海王星の組み合わせのすぐそばで形成される今回の新月のテーマは、「負の記憶の解消」。
桃の花がほころびはじめ、青虫が蝶に変身して夢見るように見え始める3月はじめの新月は、新しいサイクルの本格的な始まりというよりは、これまでのサイクルのなかに取り残されたままのわだかまりや怨念をきちんと鎮めていくことにあります。
昔の人は、蛇やカエルやトカゲなど、小さな生物はみな「虫」と呼び、この時期になる雷の音におどろいて虫たちが這い出してくるものと考えて、春の雷を「虫だし」と名付けていましたが、逆に言えば、寒さに耐えて地中でちぢこまっている虫が残っている限りは、まだすべての生命が喜びとともに祝う春ではなかった訳です。
その意味で、今回のうお座新月は、きたる春分(新しい一年の始まり)に向けて、自分だけでなく周囲のみなが忘れかけている記憶や歴史の業を解消していく霊的な働きに、いかに自分を一致させていくことができるかどうかが問われていくことになるでしょう。
「非現実的で、過度な理想主義」や「既存世界の<外部>への遁走」を意味する木星と海王星の組み合わせのすぐそばで形成される今回の新月のテーマは、「負の記憶の解消」。
桃の花がほころびはじめ、青虫が蝶に変身して夢見るように見え始める3月はじめの新月は、新しいサイクルの本格的な始まりというよりは、これまでのサイクルのなかに取り残されたままのわだかまりや怨念をきちんと鎮めていくことにあります。
昔の人は、蛇やカエルやトカゲなど、小さな生物はみな「虫」と呼び、この時期になる雷の音におどろいて虫たちが這い出してくるものと考えて、春の雷を「虫だし」と名付けていましたが、逆に言えば、寒さに耐えて地中でちぢこまっている虫が残っている限りは、まだすべての生命が喜びとともに祝う春ではなかった訳です。
その意味で、今回のうお座新月は、きたる春分(新しい一年の始まり)に向けて、自分だけでなく周囲のみなが忘れかけている記憶や歴史の業を解消していく霊的な働きに、いかに自分を一致させていくことができるかどうかが問われていくことになるでしょう。
乙女座(おとめ座)
今期のおとめ座のキーワードは、「背後なる凡庸の力」。

YouTubeやTikTok、noteなど誰もが気軽に自身のコンテンツを配信できるようになって、コンテンツが過剰供給気味になってきている今の時代において、「独創性」といった言葉ほど陳腐化してしまっている概念はないように思いますが、そもそもよい作品は誰によって作られるのかということは、もっと問われてもいい問題であるように思います。
確かに誰もが超凡たる天才に憧れる気持ちを持つことは理解できますが、実際に天才を作り出していけばそれでよいのかと言えば、そうではないでしょう。
つまり、独創性というのはその起源を「作者」のなかに特定せずにはおかない訳ですが、例えば物語/ストーリーに必要なのは著名な作者ではなくその都度の「話者」であり、そこではむしろ「起源の不在」こそがヒットの原動力となっていく訳で、そうなるとよい作品をつくるのは一握りの天才というより、多数の人々による受容なのではないでしょうか。
この問題について民俗学者の柳田國男は『口承文芸史考』の中で、後者にあたる「口承の文芸」と前者にあたる「手承眼承の本格文芸」とを対比しつつ次のように論じています。
「私などの見たところでは、二種の文芸の最も動かない境目は、今いう読者層と作者との関係、すなわち作者を取り囲む観客なり聴衆なりの群が、その文芸の産出に関与するか否かにあるように思う。(…)ことに群衆が歌を思う場合などは、それが踊りの庭であり、酒盛りの筵(むしろ)であり、はたまた野山に草を刈る日であるを問わず、いまだ声を発せずして彼らの情緒は一致していた。何人よりも巧みにかつ佳い声でもって、これを言い現そうとした者が当日の作者であって、通例はこれを音頭といっていた。音頭を取る者は各自の器量次第、もしくは趣味のいかんによって、ありふれたる歌をうまく歌って褒められ、あるいは人の知らぬ文句を暗記して折を待ち、あるいは即興に自作を発表する者もあったろうが、いずれにしたところで、聴く者の言わんとしてあたわざる感覚を、代表するより他のことはできなかったのである。」
柳田はここで明らかに、無数の物語を語り伝えてきた無名の「常民(民間伝承を保持している人々)」を意識しており、国の文芸の進展は超凡なる天才の力によるよりも、それを証明してきた「背後なる凡庸の力」によるのだ、という考えがその根底にあったはずです。
今期のおとめ座もまた、そうした力を構成する一部として自分が何を受容しているか、そして受容していきたいのかということを、改めて振り返ってみるといいかも知れません。
参考:柳田國男『口承文芸史考』 (講談社学術文庫)
確かに誰もが超凡たる天才に憧れる気持ちを持つことは理解できますが、実際に天才を作り出していけばそれでよいのかと言えば、そうではないでしょう。
つまり、独創性というのはその起源を「作者」のなかに特定せずにはおかない訳ですが、例えば物語/ストーリーに必要なのは著名な作者ではなくその都度の「話者」であり、そこではむしろ「起源の不在」こそがヒットの原動力となっていく訳で、そうなるとよい作品をつくるのは一握りの天才というより、多数の人々による受容なのではないでしょうか。
この問題について民俗学者の柳田國男は『口承文芸史考』の中で、後者にあたる「口承の文芸」と前者にあたる「手承眼承の本格文芸」とを対比しつつ次のように論じています。
「私などの見たところでは、二種の文芸の最も動かない境目は、今いう読者層と作者との関係、すなわち作者を取り囲む観客なり聴衆なりの群が、その文芸の産出に関与するか否かにあるように思う。(…)ことに群衆が歌を思う場合などは、それが踊りの庭であり、酒盛りの筵(むしろ)であり、はたまた野山に草を刈る日であるを問わず、いまだ声を発せずして彼らの情緒は一致していた。何人よりも巧みにかつ佳い声でもって、これを言い現そうとした者が当日の作者であって、通例はこれを音頭といっていた。音頭を取る者は各自の器量次第、もしくは趣味のいかんによって、ありふれたる歌をうまく歌って褒められ、あるいは人の知らぬ文句を暗記して折を待ち、あるいは即興に自作を発表する者もあったろうが、いずれにしたところで、聴く者の言わんとしてあたわざる感覚を、代表するより他のことはできなかったのである。」
柳田はここで明らかに、無数の物語を語り伝えてきた無名の「常民(民間伝承を保持している人々)」を意識しており、国の文芸の進展は超凡なる天才の力によるよりも、それを証明してきた「背後なる凡庸の力」によるのだ、という考えがその根底にあったはずです。
今期のおとめ座もまた、そうした力を構成する一部として自分が何を受容しているか、そして受容していきたいのかということを、改めて振り返ってみるといいかも知れません。
参考:柳田國男『口承文芸史考』 (講談社学術文庫)
<プロフィール>
慶應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
慶應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
文/SUGAR イラスト/チヤキ