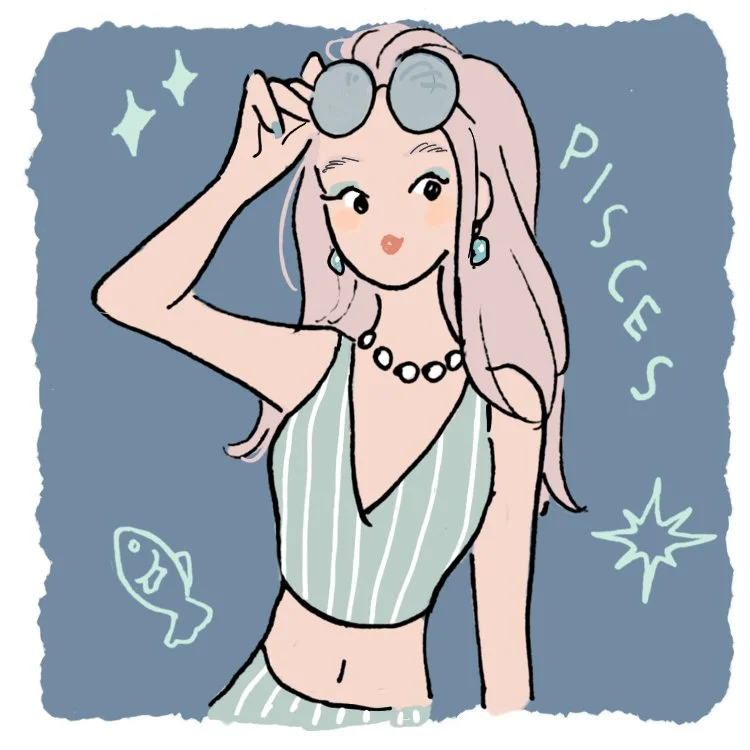【最新12星座占い】<6/13~6/26>哲学派占い師SUGARさんの12星座占いまとめ 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモい

【SUGARさんの12星座占い】<6/13~6/26>の12星座全体の運勢は?
「断ち切るための旅に出よう」
今年は6月21日に太陽の位置が最も高くなる夏至を迎え、夜も最も短くなったなかで、6月25日にはやぎ座3度(数えで4度)で満月を形成していきます。
今回の満月のテーマは、「運命的な旅の始まり」。すなわち、慣れ親しんだ居場所やこれまで繰り返してきた習慣から離れ、あるいは、習慣そのものが変わってしまうような機会に応じていくこと。
ちょうど6月の末日には各地の神社で「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われます。これは一年の折り返しに際して半年分の穢れを落とし、これから過ごす半年間の無病息災を祈願する行事なのですが、その際、多くの場合、「茅の輪くぐり」といって神社の境内に建てられた茅(かや)製の直径数メートルほどの大きな輪をくぐっていくのです。
そして、旅の始まりには、往々にしてこうした「禊ぎ」の儀式を伴うもの。例えば、ジブリ映画『もののけ姫』の冒頭でも、主人公アシタカはタタリ神から受けた呪いを絶つために、まず髪を落としてから、生まれ育った村を去り、はるか西に向けて旅立っていきました。
ひるがえって、では私たちはどんな汚れを落とし、その上で、どちらに旅立っていけばいいのでしょうか?
おそらくそれは、アシタカがタタリ神に鉄のつぶてを撃ち込んだ真相を知ろうとしていったように、いま自分が苦しんでいる状況の根本に何があって、何が起きており、その震源地の中心に少しでも近づいていこうとすることと密接に繋がっているはず。
今回の満月では、いま自分はどんなことを「もうたくさんだ」と感じているのか、そもそも何について知れば「こんなこと」は起きないですむのか。改めて考えてみるといいかも知れません。
今回の満月のテーマは、「運命的な旅の始まり」。すなわち、慣れ親しんだ居場所やこれまで繰り返してきた習慣から離れ、あるいは、習慣そのものが変わってしまうような機会に応じていくこと。
ちょうど6月の末日には各地の神社で「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われます。これは一年の折り返しに際して半年分の穢れを落とし、これから過ごす半年間の無病息災を祈願する行事なのですが、その際、多くの場合、「茅の輪くぐり」といって神社の境内に建てられた茅(かや)製の直径数メートルほどの大きな輪をくぐっていくのです。
そして、旅の始まりには、往々にしてこうした「禊ぎ」の儀式を伴うもの。例えば、ジブリ映画『もののけ姫』の冒頭でも、主人公アシタカはタタリ神から受けた呪いを絶つために、まず髪を落としてから、生まれ育った村を去り、はるか西に向けて旅立っていきました。
ひるがえって、では私たちはどんな汚れを落とし、その上で、どちらに旅立っていけばいいのでしょうか?
おそらくそれは、アシタカがタタリ神に鉄のつぶてを撃ち込んだ真相を知ろうとしていったように、いま自分が苦しんでいる状況の根本に何があって、何が起きており、その震源地の中心に少しでも近づいていこうとすることと密接に繋がっているはず。
今回の満月では、いま自分はどんなことを「もうたくさんだ」と感じているのか、そもそも何について知れば「こんなこと」は起きないですむのか。改めて考えてみるといいかも知れません。
《牡羊座(おひつじ座)》(3/21〜4/19)
今期のおひつじ座のキーワードは、「“あたりまえ”の相対化」。

しばしば、誰か何かにひどく傷つけられた当の本人ほど、自身が傷つけられたという現実を否定し、感傷的な幻想の中で生きたがるものですが、現実のあらゆる面で勝ち負けがつけられ、それがあらゆる場所で、かつ、いついかなるタイミングにおいても煽られるようになった現代社会では、ほとんどの人が何らかの意味で負け組であり、したがって、傷ついていない人などまずいないのではないでしょうか。
その意味では、いま私たちは万人が幻想を生きたがる時代に生きているのだと言えますが、イギリスの批評家マーク・フィッシャーは、こうしたグローバル資本主義にすっかり包み込まれた現代人が陥っている事態を「再帰的無能感」と名付けました。
その意味するところは、理不尽な状況に対して自分たちにはもはや何も為す術がないのだという、無関心ともシニシズムとも異なる感傷モードのことなのですが、フィッシャーは厄介なことにそれが「広く染みわたる雰囲気のように、文化の生産だけでなく、教育と労働の規制をも条件づけながら、思考と行動を制約する見えざる結界として」働いているのだと指摘した上で、そこから脱け出す方法について、次のように述べています。
「過去三十年にわたって、資本主義リアリズムは教育や保険制度を含む社会のすべてがビジネスとして経営されるのがごく自然なことだという「ビジネス・オントロジー」の確立に成功してきた。(中略)社会の開放を目指す政治はつねに「自然秩序(あたりまえ)」という体裁を破壊すべきで、必然で不可避と見せられていたことをただの偶然として明かしていくと同様に、不可能と思われたことを達成可能であると見せなければならない。現時点で現実的と呼ばれるものも、かつては「不可能」と呼ばれていたことをここで思い出してみよう。」
つまるところ、「この道しかない」ということが“あたりまえ”とされる現実があったとしたら、まずそこに疑問符をつけることこそが、再帰的無能感から脱け出すための出発点なのだとフィッシャーは言っているのです。
今期のおひつじ座もまた、自分がもっとも可能性を限定してしまっているのはどこなのか(例えば「この人とは離れられない」とか「この業界以外では生きていけない」とか)、というところから、今一度自分を無能感から救う道筋を探ってみるといいでしょう。
参考:マーク・フィッシャー、セバスチャン・ブロイ+河南瑠莉訳『資本主義リアリズム』(堀之内出版)
その意味では、いま私たちは万人が幻想を生きたがる時代に生きているのだと言えますが、イギリスの批評家マーク・フィッシャーは、こうしたグローバル資本主義にすっかり包み込まれた現代人が陥っている事態を「再帰的無能感」と名付けました。
その意味するところは、理不尽な状況に対して自分たちにはもはや何も為す術がないのだという、無関心ともシニシズムとも異なる感傷モードのことなのですが、フィッシャーは厄介なことにそれが「広く染みわたる雰囲気のように、文化の生産だけでなく、教育と労働の規制をも条件づけながら、思考と行動を制約する見えざる結界として」働いているのだと指摘した上で、そこから脱け出す方法について、次のように述べています。
「過去三十年にわたって、資本主義リアリズムは教育や保険制度を含む社会のすべてがビジネスとして経営されるのがごく自然なことだという「ビジネス・オントロジー」の確立に成功してきた。(中略)社会の開放を目指す政治はつねに「自然秩序(あたりまえ)」という体裁を破壊すべきで、必然で不可避と見せられていたことをただの偶然として明かしていくと同様に、不可能と思われたことを達成可能であると見せなければならない。現時点で現実的と呼ばれるものも、かつては「不可能」と呼ばれていたことをここで思い出してみよう。」
つまるところ、「この道しかない」ということが“あたりまえ”とされる現実があったとしたら、まずそこに疑問符をつけることこそが、再帰的無能感から脱け出すための出発点なのだとフィッシャーは言っているのです。
今期のおひつじ座もまた、自分がもっとも可能性を限定してしまっているのはどこなのか(例えば「この人とは離れられない」とか「この業界以外では生きていけない」とか)、というところから、今一度自分を無能感から救う道筋を探ってみるといいでしょう。
参考:マーク・フィッシャー、セバスチャン・ブロイ+河南瑠莉訳『資本主義リアリズム』(堀之内出版)
《牡牛座(おうし座)》(4/20〜5/20)
今期のおうし座のキーワードは、「見る者がアート/ゲームをつくる」

いまオリンピックの是非をめぐって、いよいよ世論がそのうねりを激しくしています。スポーツ界が開催の可否についてほぼ沈黙を決め込んでいる一方で、管総理の「コロナに勝った証としての開催」を筆頭に、政治家たちは何が何でも開催しかないのだと鼻息を荒くして前のめりになっている。こうした現状に、なにかきな臭いものを感じる人は今後ますます増えていくでしょう。
ここで一つだけはっきり言えるのは、パンデミック以前であればこうしたことは起きなかっただろうということ。その意味で、パンデミックがスポーツやオリンピックへの社会的関心の在り方を根本的に変えてしまったのだと言えますが、それはとりもなおさず「スポーツないしゲームとは何のためにあるのか」という問いが再提起されているということでもあるのではないかでしょうか。
そして、こうした問いを再考する上で思い出さなくてはならない人物に、マルセル・デュシャンがいます。彼は“美術史”において、アートを放棄したあとチェスに熱中し、フランスを代表するチェス・プレイヤーになったことで知られていますが、実際には少年期に絵画とチェスを同時に始め、その2つの活動はつねに継続され、結果的にチェスだけが生涯を通じて途切れることなくプレイされていたに過ぎなかったのだと言えます。
つまり、デュシャンという人は、アーティストであり、チェス・プレイヤーでもあったのか、それとも、チェス・プレイヤーであり、アーティストでもあったのか、いまいち判然としない人物だった訳です。
そもそも、デュシャンはアートとゲームとを明確に区別しておらず、アートというものを「アーティストと見物人のあいだのちょっとしたゲーム」なのだと考えていたようですし、70歳となった1957年には次のように語っていました。
「芸術家は一人では創造行為を遂行しない。鑑賞者は作品を外部世界に接触させて、その作品を作品たらしめている奥深いものを解読し解釈するのであり、そのことにより鑑賞者固有の仕方で創造過程に参与するのである。こうした参与の仕方は、後世がその決定的な審判を下し何人かの忘れられた芸術家を復権するときに、一層明らかになる。」
この「見る者がアート/ゲームをつくるのだ」というデュシャンの宣言を、今回の東京オリンピックの文脈に接続してみると、政治家たちがつくろうとしているアート/ゲームと、一般民衆がつくろうとしているそれとが、いつの間にかまったく別物になっているのだという印象がより一層際立って感じられてくるはず。
今期のおうし座もまた、改めて自分が見たいアート/ゲームとは何で、見たくないそれとは何なのかということを、明確にしてみるといいでしょう。
参考:マルセル・デュシャン、北山研二訳『マルセル・デュシャン全著作』(未知谷)
ここで一つだけはっきり言えるのは、パンデミック以前であればこうしたことは起きなかっただろうということ。その意味で、パンデミックがスポーツやオリンピックへの社会的関心の在り方を根本的に変えてしまったのだと言えますが、それはとりもなおさず「スポーツないしゲームとは何のためにあるのか」という問いが再提起されているということでもあるのではないかでしょうか。
そして、こうした問いを再考する上で思い出さなくてはならない人物に、マルセル・デュシャンがいます。彼は“美術史”において、アートを放棄したあとチェスに熱中し、フランスを代表するチェス・プレイヤーになったことで知られていますが、実際には少年期に絵画とチェスを同時に始め、その2つの活動はつねに継続され、結果的にチェスだけが生涯を通じて途切れることなくプレイされていたに過ぎなかったのだと言えます。
つまり、デュシャンという人は、アーティストであり、チェス・プレイヤーでもあったのか、それとも、チェス・プレイヤーであり、アーティストでもあったのか、いまいち判然としない人物だった訳です。
そもそも、デュシャンはアートとゲームとを明確に区別しておらず、アートというものを「アーティストと見物人のあいだのちょっとしたゲーム」なのだと考えていたようですし、70歳となった1957年には次のように語っていました。
「芸術家は一人では創造行為を遂行しない。鑑賞者は作品を外部世界に接触させて、その作品を作品たらしめている奥深いものを解読し解釈するのであり、そのことにより鑑賞者固有の仕方で創造過程に参与するのである。こうした参与の仕方は、後世がその決定的な審判を下し何人かの忘れられた芸術家を復権するときに、一層明らかになる。」
この「見る者がアート/ゲームをつくるのだ」というデュシャンの宣言を、今回の東京オリンピックの文脈に接続してみると、政治家たちがつくろうとしているアート/ゲームと、一般民衆がつくろうとしているそれとが、いつの間にかまったく別物になっているのだという印象がより一層際立って感じられてくるはず。
今期のおうし座もまた、改めて自分が見たいアート/ゲームとは何で、見たくないそれとは何なのかということを、明確にしてみるといいでしょう。
参考:マルセル・デュシャン、北山研二訳『マルセル・デュシャン全著作』(未知谷)
《双子座(ふたご座)》(5/21〜6/21)
今期のふたご座のキーワードは、「猿を愛して何が悪い」。

グリム童話であれ日本の昔話であれ、閉塞しきった状況を突き破るのは、得てして平時には“異常”として忌避される力や性質を備えた人物でしたが、現代のホラー作家・平山夢明の作品にも、「たびたび何らかの境界線を越える、あるいは限界を突き破る人物が出てくる」ことで知られています。
例えば、『ヤギより上、猿より下』という短編小説であれば、変態ジイサンに調教された末に売春宿に売られたポポロというオランウータンに惚れこんだお爺ちゃんがそれに当たります。
物語の舞台はそんなとある山のふもとにある売春宿『フッカーズ・ネスト』。ここには春をひさぐ50代の三人の姐さんたちがいるのですが、案の定、売り上げがジリ貧となったところに、新入りキャストとしてヤギの甘汁とオランウータンのポポロがやってきた。さすがに姐さんたちも動物に負けることはないだろうと思いきや、ポポロがまさかの大ブレイク! 姐さんたちが嫉妬や怒りから暴走して醜態をさらしていく中、ついにポポロのサービス料金が姐さんたちより一万円高くなるのですが、そこに登場してくるのが「純情漫画さん」という、どこかの社長さんだというお爺ちゃんです。
「ふえ」純情漫画さんはぱっちりした目の玉を一度だけ見開くと、直後に手を叩いて笑い出しました。「なあんだ。それじゃあ、正真正銘、あいつら猿より下になっちまったんじゃないか……あっははは」
「ですから、純情さんがそれじゃあ駄目ということでしたら、どうか憐れだと思って人間のあいつらを買ってやってください」
「はは。ああ、いいよいいよ。儂はね、猿を抱いてるんじゃないんだ。ポポロというひとつの魂と人生を共有させて貰ってるんだ。猿だって人間だって地球に暮らす同じ生命じゃないか。それに人間は元は猿だ。だから猿を愛して何が悪いとすら思ってる。だから、こうして料金が上がるのは逆に嬉しいくらいなんだよ。ポポロを単なる道具くらいにしか考えない奴らが減るだろうからね。いいよ、いいよ。払うよ払うよ。ごっくんごっくん」
あたいたちが話してる間にも、ポポロはしきりに手招きをしています。
「じゃあ、ごゆっくり。おほほほほ」
ここで「純情漫画さん」の口から出た「ひとつの魂と人生を共有させて貰ってる」という言葉の背後には、明らかに「文化」と「自然」という異質な原理のハイブリッドとしての「シャーマニズム」があり、宗教学者の中沢新一の言葉を借りれば、それは「人間の神化への可能性を開いている」のだと言えるのではないでしょうか。
今期のふたご座もまた、異常な人間的しがらみをほどくことができるだけの“自然”へと自身の軸足をずらしてみるといいかも知れません。
参考:平山夢明『ヤギより上、猿より下』(文春文庫)
例えば、『ヤギより上、猿より下』という短編小説であれば、変態ジイサンに調教された末に売春宿に売られたポポロというオランウータンに惚れこんだお爺ちゃんがそれに当たります。
物語の舞台はそんなとある山のふもとにある売春宿『フッカーズ・ネスト』。ここには春をひさぐ50代の三人の姐さんたちがいるのですが、案の定、売り上げがジリ貧となったところに、新入りキャストとしてヤギの甘汁とオランウータンのポポロがやってきた。さすがに姐さんたちも動物に負けることはないだろうと思いきや、ポポロがまさかの大ブレイク! 姐さんたちが嫉妬や怒りから暴走して醜態をさらしていく中、ついにポポロのサービス料金が姐さんたちより一万円高くなるのですが、そこに登場してくるのが「純情漫画さん」という、どこかの社長さんだというお爺ちゃんです。
「ふえ」純情漫画さんはぱっちりした目の玉を一度だけ見開くと、直後に手を叩いて笑い出しました。「なあんだ。それじゃあ、正真正銘、あいつら猿より下になっちまったんじゃないか……あっははは」
「ですから、純情さんがそれじゃあ駄目ということでしたら、どうか憐れだと思って人間のあいつらを買ってやってください」
「はは。ああ、いいよいいよ。儂はね、猿を抱いてるんじゃないんだ。ポポロというひとつの魂と人生を共有させて貰ってるんだ。猿だって人間だって地球に暮らす同じ生命じゃないか。それに人間は元は猿だ。だから猿を愛して何が悪いとすら思ってる。だから、こうして料金が上がるのは逆に嬉しいくらいなんだよ。ポポロを単なる道具くらいにしか考えない奴らが減るだろうからね。いいよ、いいよ。払うよ払うよ。ごっくんごっくん」
あたいたちが話してる間にも、ポポロはしきりに手招きをしています。
「じゃあ、ごゆっくり。おほほほほ」
ここで「純情漫画さん」の口から出た「ひとつの魂と人生を共有させて貰ってる」という言葉の背後には、明らかに「文化」と「自然」という異質な原理のハイブリッドとしての「シャーマニズム」があり、宗教学者の中沢新一の言葉を借りれば、それは「人間の神化への可能性を開いている」のだと言えるのではないでしょうか。
今期のふたご座もまた、異常な人間的しがらみをほどくことができるだけの“自然”へと自身の軸足をずらしてみるといいかも知れません。
参考:平山夢明『ヤギより上、猿より下』(文春文庫)
《蟹座(かに座)》(6/22〜7/22)
今期のかに座のキーワードは、「肉食の位置づけ」。

1990年代に主に西欧でにわかに浮上したものの、日本では2003年以降は確認されなくなった狂牛病ですが、これは牛の骨を原料とした粉末を飼料として牛に与えないという処置の結果でした。そしてこの点について、狂牛病の本質は「牛たちが共食い(カニバリズム)を人間に強いられたことに由来している」のだと指摘したのが、文化人類学のクロード・レヴィ=ストロースでした。
彼は「人間が抱える肉食という病理」という副題をついたエッセイで、例えば文字を持たない未開部族の一部は肉食を「カニバリズムのほんの僅かに弱められた一形態」と見なしているのだと言います。
「この人たちは狩人(または漁師)とその獲物の関係を、親族関係をモデルにして考えようとしている。すなわち、婚姻によって生まれる婚姻間の関係が、さらにもっと直接に、配偶者同士の関係としてである(配偶関係になぞらえることは、世界のすべての言語が、隠語表現におけるヨーロッパ諸語も含めて、性交を摂食行為になぞらえていることからも、容易になっているといえる)。このようにして、狩猟と漁撈は、一種の内輪の食人習俗(カニバリズム)とみなしうるのである。」
レヴィ=ストロースはここで、「カニバリズム」を人間同士だけでなく、他の動物間まで拡張していくなかで、家畜という名の食糧生産装置との関係がすでに限界を迎えつつあるのではないかと訴える。
「昔の人間は自分たちの食用にするために生きものを飼っては殺し、その肉を切り身にしてショーウィンドウに体裁よく陳列していたのだという考えが、十六、七世紀の旅行者にアメリカやオセアニアやアフリカの野生人たちの人肉の食事が感じさせたのと同じ嫌悪を催させる日が、いつか来るだろう。」
少なくとも、狂牛病の事例は、近代畜産が草食動物である牛に「過度の動物性」を付与し、彼らを肉食動物にするだけでなく「共食い動物(カニバル)」に強制的に変えてしまったことで、決定的な死の連鎖が引き起こされることを教訓として残しました。つまり、狂牛病は人間がつくった死に至る病だった訳で、なぜそうまでして人間は肉食にこだわり続けるのかという問いを孕んでいます。
ただ、とはいえ、おそらく人間の肉への嗜好そのものが消滅することはないでしょう。ただ、レヴィ=ストロースが予見したように、それが「稀で、高価で、危険にみちたもの」と化していくという未来予想図には、どこか不思議な説得力があるように思います。
今期のかに座もまた、「食べる/交わる/殺す」という複雑に連環するテーマについて、みずからの嗜好/志向性の来し方行く末について改めて考えてみるといいでしょう。
参考:クロード・レヴィ=ストロース、川田順造訳「狂牛病の教訓--人類が抱える肉食という病理」(『中央公論』2001年四月)
彼は「人間が抱える肉食という病理」という副題をついたエッセイで、例えば文字を持たない未開部族の一部は肉食を「カニバリズムのほんの僅かに弱められた一形態」と見なしているのだと言います。
「この人たちは狩人(または漁師)とその獲物の関係を、親族関係をモデルにして考えようとしている。すなわち、婚姻によって生まれる婚姻間の関係が、さらにもっと直接に、配偶者同士の関係としてである(配偶関係になぞらえることは、世界のすべての言語が、隠語表現におけるヨーロッパ諸語も含めて、性交を摂食行為になぞらえていることからも、容易になっているといえる)。このようにして、狩猟と漁撈は、一種の内輪の食人習俗(カニバリズム)とみなしうるのである。」
レヴィ=ストロースはここで、「カニバリズム」を人間同士だけでなく、他の動物間まで拡張していくなかで、家畜という名の食糧生産装置との関係がすでに限界を迎えつつあるのではないかと訴える。
「昔の人間は自分たちの食用にするために生きものを飼っては殺し、その肉を切り身にしてショーウィンドウに体裁よく陳列していたのだという考えが、十六、七世紀の旅行者にアメリカやオセアニアやアフリカの野生人たちの人肉の食事が感じさせたのと同じ嫌悪を催させる日が、いつか来るだろう。」
少なくとも、狂牛病の事例は、近代畜産が草食動物である牛に「過度の動物性」を付与し、彼らを肉食動物にするだけでなく「共食い動物(カニバル)」に強制的に変えてしまったことで、決定的な死の連鎖が引き起こされることを教訓として残しました。つまり、狂牛病は人間がつくった死に至る病だった訳で、なぜそうまでして人間は肉食にこだわり続けるのかという問いを孕んでいます。
ただ、とはいえ、おそらく人間の肉への嗜好そのものが消滅することはないでしょう。ただ、レヴィ=ストロースが予見したように、それが「稀で、高価で、危険にみちたもの」と化していくという未来予想図には、どこか不思議な説得力があるように思います。
今期のかに座もまた、「食べる/交わる/殺す」という複雑に連環するテーマについて、みずからの嗜好/志向性の来し方行く末について改めて考えてみるといいでしょう。
参考:クロード・レヴィ=ストロース、川田順造訳「狂牛病の教訓--人類が抱える肉食という病理」(『中央公論』2001年四月)
《獅子座(しし座)》(7/23〜8/22)
今期のしし座のキーワードは、「不自然極まる特殊な生きもの」。

イギリスの政治哲学者ジョン・グレイの『わらの犬 地球に君臨する人間』は、キリスト教と科学技術の発展を両輪に思いあがってきた人間の傲慢さをこれでもかと叩いているのですが、その矛先が人間のどこに向けられているのかという点を考慮すると、そこには不思議な景色が広がってきます。
「動物が人間とちがうのは自我の観念がないことである。だからといって、動物は少しも不幸ではない」
「自我とは、たまゆらの事象である。とはいいながら、これが人の生を支配する。人間はこのありもしないものを捨てきれない。正常な意識で現在に向き合っているかぎり、自我は揺るぎない。人間の根本的な誤りがここにある。そのせいで、人の一生は夢の間である。」
「動物は生きる目的を必要としない。ところが、人間は一種の動物でありながら、目的なしには生きられない。」
「労働をひたすらありがたがる現代人はどうかしている。そのように考える文化はほとんどない。有史以前はもとより、歴史をつうじて労働は一種の屈辱だった。」
ここでは、ほかの動物たちと並べると明らかに不自然さが目立つ人間という種特有の「人間くささ」が、他ならぬ人間が犯してきた数々の愚行やあやまちの発生源として批判されていることが分かります。
けれど、グレイの言い分を逆手に取れば、私たちはもう今さら自然な振る舞いになど大人しく戻れる訳がないのだということをいい加減受け入れるべきではないでしょうか。
私たち人間は、むしろ自我を捨てきれないがために時にすすんで不幸となり、ありもしない夢を抱き、生きる目的をやたらと追求し、屈辱だろうと何だろうと労働せずにはいられない。しかも、そういう生を送るにしても、いつまでたっても十分に習熟できない。そういう不格好で、不自然極まる生きものなのだ、と。
今期のしし座もまた、今さら生きものとしてのスマートさや自然な理想へ無理に自分を押しこめようとするのではなく、どこまでもゴツゴツと丸くなれない特殊な生きものとしての自分を受け入れて、ますます“人並み”から外れていく覚悟を固めていきたいところです。
参考:ジョン・グレイ、池央耿訳『わらの犬 地球に君臨する人間』(みすず書房)
「動物が人間とちがうのは自我の観念がないことである。だからといって、動物は少しも不幸ではない」
「自我とは、たまゆらの事象である。とはいいながら、これが人の生を支配する。人間はこのありもしないものを捨てきれない。正常な意識で現在に向き合っているかぎり、自我は揺るぎない。人間の根本的な誤りがここにある。そのせいで、人の一生は夢の間である。」
「動物は生きる目的を必要としない。ところが、人間は一種の動物でありながら、目的なしには生きられない。」
「労働をひたすらありがたがる現代人はどうかしている。そのように考える文化はほとんどない。有史以前はもとより、歴史をつうじて労働は一種の屈辱だった。」
ここでは、ほかの動物たちと並べると明らかに不自然さが目立つ人間という種特有の「人間くささ」が、他ならぬ人間が犯してきた数々の愚行やあやまちの発生源として批判されていることが分かります。
けれど、グレイの言い分を逆手に取れば、私たちはもう今さら自然な振る舞いになど大人しく戻れる訳がないのだということをいい加減受け入れるべきではないでしょうか。
私たち人間は、むしろ自我を捨てきれないがために時にすすんで不幸となり、ありもしない夢を抱き、生きる目的をやたらと追求し、屈辱だろうと何だろうと労働せずにはいられない。しかも、そういう生を送るにしても、いつまでたっても十分に習熟できない。そういう不格好で、不自然極まる生きものなのだ、と。
今期のしし座もまた、今さら生きものとしてのスマートさや自然な理想へ無理に自分を押しこめようとするのではなく、どこまでもゴツゴツと丸くなれない特殊な生きものとしての自分を受け入れて、ますます“人並み”から外れていく覚悟を固めていきたいところです。
参考:ジョン・グレイ、池央耿訳『わらの犬 地球に君臨する人間』(みすず書房)
《乙女座(おとめ座)》(8/23〜9/22)
今期のおとめ座のキーワードは、「オルフェウスの声」。

18世紀の思想家ジャン=ジャック・ルソーは、晩年に書いた『言語起源論』の中で、原初の人間たちは、私たちがいま日常的に使っている言語とも0と1からなるコンピューター言語とも異なり、詩と音楽によって互いに語り合っていたのだと書いていましたが、現代の詩人で著述家のエリザベス・シューエルはそうした言語を「オルフェウスの声」と呼びました(『オルフェウスの声』)。
彼女によれば、ギリシャ神話における吟遊詩人オルフェウスの物語は3つに分かれており、「まずその声をもって木石を動かし、野獣を大人しくさせ」、そこでは「おのずから音楽が言語と詩に結びついている」ことが端的に示される。次に、亡き妻を探して冥界へと下り、「その詩の力をもって冥府入りを許され、望みを聞き届けてもらう」が、「約定に背いて地獄の出口で思わず振り向いてしまい、妻を喪い」ます。そして第三に、「バッケーの狂女たちに八つ裂きにされたオルフェウスの頭部が、オウディウスによれば重々の谺を返しながらなお歌いつつ、川面を下って」いったのだと言います。
「嘆きの琴、心付かず嘆き、嘆きの
言葉の魂もなく囁きて、これに嘆きの汀(きし)の応うなり」
シューエルはこのオルフェウス神話こそ、ばらばらに分断された世界を統合する詩の力に重ねあわせることができるのだと考え、それを「陳述であり、問いであり、そして方法でもある」のだと述べました。
つまり、オルフェウス神話とは、詩的なるものとしての言語が死を招きもすれば死を克服しもする不思議な力を持っていることの隠喩であり、よき手本であり、その力をどこで使うべきかという絶えざる問いかけの源でもあるということ。
ひるがえって、あなたの周りに一見すると分離され、孤立しているように見えるものはあるでしょうか。引きこもりの中年であれ、家出中の少女であれ、目的を失った晴れ着であれ、先のオルフェウスの声を思い浮かべた上でもう一度見つめ直してみれば、現実のより深い層で彼らを他の何かと繋ぎ合わせている通底器の働きが感じ取れるようになり、世界がひとつの全体として呼吸している様子を、かすかにでもとらえることができるようになるはずです。
今期のおとめ座もまた、ばらばらになったパズルのピースを根気強く繋ぎ合わせていくかのように、みずからの言葉にオルフェウスを降ろしてみるといいでしょう。逆に、ただ分断を促すための言葉はもういらないのだ、と。
参考:エリザベス・シューエル、高山宏訳『『オルフェウスの声』』(白水社)
彼女によれば、ギリシャ神話における吟遊詩人オルフェウスの物語は3つに分かれており、「まずその声をもって木石を動かし、野獣を大人しくさせ」、そこでは「おのずから音楽が言語と詩に結びついている」ことが端的に示される。次に、亡き妻を探して冥界へと下り、「その詩の力をもって冥府入りを許され、望みを聞き届けてもらう」が、「約定に背いて地獄の出口で思わず振り向いてしまい、妻を喪い」ます。そして第三に、「バッケーの狂女たちに八つ裂きにされたオルフェウスの頭部が、オウディウスによれば重々の谺を返しながらなお歌いつつ、川面を下って」いったのだと言います。
「嘆きの琴、心付かず嘆き、嘆きの
言葉の魂もなく囁きて、これに嘆きの汀(きし)の応うなり」
シューエルはこのオルフェウス神話こそ、ばらばらに分断された世界を統合する詩の力に重ねあわせることができるのだと考え、それを「陳述であり、問いであり、そして方法でもある」のだと述べました。
つまり、オルフェウス神話とは、詩的なるものとしての言語が死を招きもすれば死を克服しもする不思議な力を持っていることの隠喩であり、よき手本であり、その力をどこで使うべきかという絶えざる問いかけの源でもあるということ。
ひるがえって、あなたの周りに一見すると分離され、孤立しているように見えるものはあるでしょうか。引きこもりの中年であれ、家出中の少女であれ、目的を失った晴れ着であれ、先のオルフェウスの声を思い浮かべた上でもう一度見つめ直してみれば、現実のより深い層で彼らを他の何かと繋ぎ合わせている通底器の働きが感じ取れるようになり、世界がひとつの全体として呼吸している様子を、かすかにでもとらえることができるようになるはずです。
今期のおとめ座もまた、ばらばらになったパズルのピースを根気強く繋ぎ合わせていくかのように、みずからの言葉にオルフェウスを降ろしてみるといいでしょう。逆に、ただ分断を促すための言葉はもういらないのだ、と。
参考:エリザベス・シューエル、高山宏訳『『オルフェウスの声』』(白水社)
《天秤座(てんびん座)》(9/23〜10/23)
今期のてんびん座のキーワードは、「野性味のある豊かさ」。
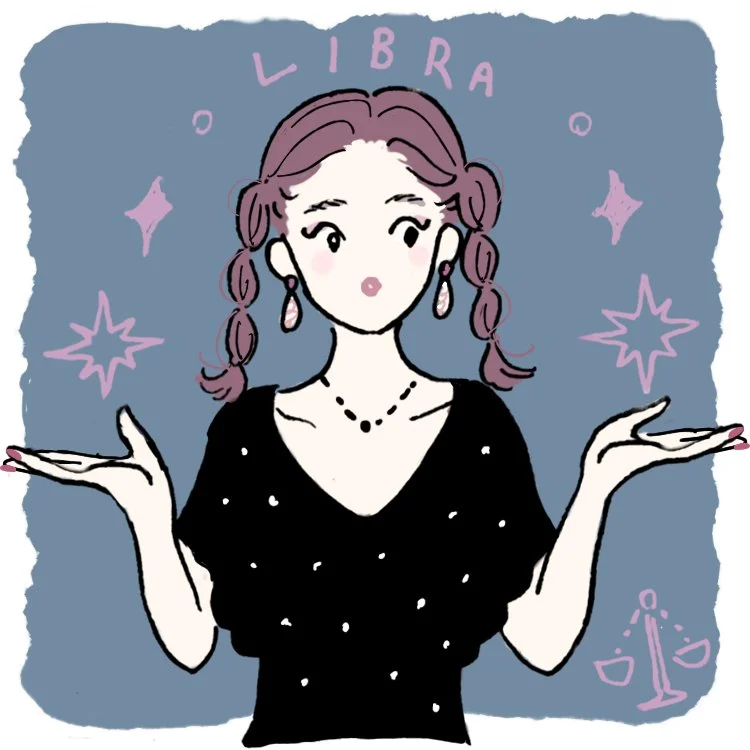
香港という都市は現在は中間人民共和国の統治下にありますが、150年以上もイギリスの植民地支配下にあった影響で、面積は狭くても高度に都市化かつ発展しており、高層アパートがおそらく世界最高密度で建てられている一方で、住民の経済格差も世界最大であり、正式な許可なく黙認されている「屋上建築物」が半世紀以上も存在しており、今後も少なくとも半世紀以上は存続すると言われています。
屋上家屋と言えば、マンガ『美味しんぼ』の主人公が雑居ビルの屋上に置かれた小屋に住んでいたのが有名ですが、香港の場合はそれが大規模な「街」レベルで存在し、そこに低所得層や移民が集まっている。
そんな香港の屋上家屋の生活を写真と図面と文章で紹介している『香港ルーフトップ』を見ていると、家屋の材料にはレンガやトタン、角材、ビニールシート、ベニヤ板、ロープなどさまざまな素材が使われていて、それらがあり合わせで調達されてきたことが分かります。
本書に日本語版解説を寄せている大山顕は、そうして近代建築の上に、きわめて原始的な建築が乗っている様子について、「まるで建築史の地層が逆転したような光景」だと表現しており、「近代以前の香港の街並みが、下から生えてきた近代のビルによって空中に持ち上げられ保存されているように見えないだろうか」とも述べています。
香港の屋上家屋には、こうした風景としての面白さに加え、何より日本社会からはとうに失われつつある「(家屋が)住み手によって改変されていく」高い自由度と、そこに入り込む偶然性によってつくり出され、さまざまな文脈を経て生み出される野性的な豊かさが存在しているように思います。
日本語では「屋上屋を架す」という言葉は無駄なことをする喩えとして使われますが、現代社会に失われてしまったのは、そうした無駄や猥雑さをあっけらかんと楽しむ余裕や余地なのかも知れません。
今週のてんびん座もまた、ショッピングやグルメ情報ばかりによって構成された観光ガイドには決して載らないような、独特のカオスな香りをみずからの生活に取り入れてみるといいでしょう。
参考:ルフィナ・ウー+ステファン・カナム、GLOVA訳『香港ルーフトップ』(PARCO出版)
屋上家屋と言えば、マンガ『美味しんぼ』の主人公が雑居ビルの屋上に置かれた小屋に住んでいたのが有名ですが、香港の場合はそれが大規模な「街」レベルで存在し、そこに低所得層や移民が集まっている。
そんな香港の屋上家屋の生活を写真と図面と文章で紹介している『香港ルーフトップ』を見ていると、家屋の材料にはレンガやトタン、角材、ビニールシート、ベニヤ板、ロープなどさまざまな素材が使われていて、それらがあり合わせで調達されてきたことが分かります。
本書に日本語版解説を寄せている大山顕は、そうして近代建築の上に、きわめて原始的な建築が乗っている様子について、「まるで建築史の地層が逆転したような光景」だと表現しており、「近代以前の香港の街並みが、下から生えてきた近代のビルによって空中に持ち上げられ保存されているように見えないだろうか」とも述べています。
香港の屋上家屋には、こうした風景としての面白さに加え、何より日本社会からはとうに失われつつある「(家屋が)住み手によって改変されていく」高い自由度と、そこに入り込む偶然性によってつくり出され、さまざまな文脈を経て生み出される野性的な豊かさが存在しているように思います。
日本語では「屋上屋を架す」という言葉は無駄なことをする喩えとして使われますが、現代社会に失われてしまったのは、そうした無駄や猥雑さをあっけらかんと楽しむ余裕や余地なのかも知れません。
今週のてんびん座もまた、ショッピングやグルメ情報ばかりによって構成された観光ガイドには決して載らないような、独特のカオスな香りをみずからの生活に取り入れてみるといいでしょう。
参考:ルフィナ・ウー+ステファン・カナム、GLOVA訳『香港ルーフトップ』(PARCO出版)
《蠍座(さそり座)》(10/24〜11/22)
今期のさそり座のキーワードは、「無明性と無明感情の区別」。

占い師として日々いろいろな人の悩み相談を聞いていると、誰か何かに助けてもらおうとするのではなく、みずから自分を救おうとすること、実際に負のスパイラルを脱け出すためには、その「質的転換」こそが大切なのではないかと思うことがあります。
精神科医の加藤清は、同じことを「無明性からの脱却」と呼び、『癒しの森』において精神科医の平井孝男との「宗教体験と心理療法」と題した討論の中で次のように語っています。
「頭を何回も壁に打ちつけていたある緊張病性の分裂病男子(※)ですが、この人はすべての医者から回復の見込みがないと言われてたんです。僕が受け持ったときもそうした行動があったんですけれど、その自罰的衝動行為の中に深い無明感情や罪業感を感じて、僕は患者に向かって思わず土下座してしまったんです。でも、それがきっかけで治療が展開し、五年後には退院、50歳で結婚して高校教師となりました。彼は、自分のことを阿修羅だ―人間ではない―と感じていましたが、そういって自分の無明感情を表現していたんでしょうね。」
※精神分裂病(分裂病)は2002年に統合失調症に病名変更されています
加藤はここで、人間存在そのものが背負わされている宿命としての「無明性」と、そこから派生してくる「無明感情」とを分けています。ここで言う「無明」とはみずからの苦しみを否認し、さらには苦しみの原因である執着ということについても目を逸らしている態度のことを言い、「無明感情」とは「自分はどうにもならない」「救われない」「生まれなければよかった」「普通の人間ではなくなった」といった具体性を伴った苦悩の感情のことです。
加藤によれば、総じて統合失調症患者は無明感情が強くて無明そのものを認識できないのに対して、健康人は無明感情が薄く、その反面、「無明に対する積極的態度を取りうる健康性はある」と分析しています。そして、この両方、すなわち深い無明感情と無名性の積極的認識の両方を徹底していったのがブッダであるとし、「無明そのものを直視し、それを突き抜けて明の世界に突き抜けていった人」としています。
占い師のもとを訪れる人というのも、こうした加藤の議論を踏まえると、ふとしたきっかけで無明感情に陥ってしまった人なのだと言えるかも知れません。ただし、実際にそこから救われるには無明感情の真っ只中にありつつも、人の手を借りながらみずからの「無明」への積極的態度を取り戻し、突き抜けていくのでなければなりません。
今期のさそり座もまた、そうして誰かとの縁によって明の世界に突き抜けていくこと、そして自分もまた誰か窮地にある人の質的転換を見届けていくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:加藤清監修『癒しの森 心理療法と宗教』(創元社)
精神科医の加藤清は、同じことを「無明性からの脱却」と呼び、『癒しの森』において精神科医の平井孝男との「宗教体験と心理療法」と題した討論の中で次のように語っています。
「頭を何回も壁に打ちつけていたある緊張病性の分裂病男子(※)ですが、この人はすべての医者から回復の見込みがないと言われてたんです。僕が受け持ったときもそうした行動があったんですけれど、その自罰的衝動行為の中に深い無明感情や罪業感を感じて、僕は患者に向かって思わず土下座してしまったんです。でも、それがきっかけで治療が展開し、五年後には退院、50歳で結婚して高校教師となりました。彼は、自分のことを阿修羅だ―人間ではない―と感じていましたが、そういって自分の無明感情を表現していたんでしょうね。」
※精神分裂病(分裂病)は2002年に統合失調症に病名変更されています
加藤はここで、人間存在そのものが背負わされている宿命としての「無明性」と、そこから派生してくる「無明感情」とを分けています。ここで言う「無明」とはみずからの苦しみを否認し、さらには苦しみの原因である執着ということについても目を逸らしている態度のことを言い、「無明感情」とは「自分はどうにもならない」「救われない」「生まれなければよかった」「普通の人間ではなくなった」といった具体性を伴った苦悩の感情のことです。
加藤によれば、総じて統合失調症患者は無明感情が強くて無明そのものを認識できないのに対して、健康人は無明感情が薄く、その反面、「無明に対する積極的態度を取りうる健康性はある」と分析しています。そして、この両方、すなわち深い無明感情と無名性の積極的認識の両方を徹底していったのがブッダであるとし、「無明そのものを直視し、それを突き抜けて明の世界に突き抜けていった人」としています。
占い師のもとを訪れる人というのも、こうした加藤の議論を踏まえると、ふとしたきっかけで無明感情に陥ってしまった人なのだと言えるかも知れません。ただし、実際にそこから救われるには無明感情の真っ只中にありつつも、人の手を借りながらみずからの「無明」への積極的態度を取り戻し、突き抜けていくのでなければなりません。
今期のさそり座もまた、そうして誰かとの縁によって明の世界に突き抜けていくこと、そして自分もまた誰か窮地にある人の質的転換を見届けていくことがテーマとなっていくでしょう。
参考:加藤清監修『癒しの森 心理療法と宗教』(創元社)
《射手座(いて座)》(11/23〜12/21)
今期のいて座のキーワードは、「そこにある愛とは何か」。

生物学者の福岡伸一は、2020年6月15日付けの毎日新聞の記事の中で、コロナウイルスは人類にとって戦うべき敵ではなく、遺伝情報を交換するある種の水平的な家族の一員なのだと述べていましたが、そこではワクチンを打つといった応急処置的な対処以上に、動物を含めた他者を攻撃するのでも支配するのとも異なる仕方で関わっていくにはどうしたらいいのか、という問いについて考えていく必要があるのではないでしょうか。
例えば、現代において実際に犬や馬をパートナーにして性的営みを行う「ズー」と呼ばれる動物性愛者たちを取材した濱野ちひろのノンフィクション『聖なるズー』には、取材を通してズーたちに抱いていた印象が変わっていったことについての著者の率直な思いが書かれています。
「ズーとは、自分とは異なる存在たちと対等であるために日々を費やす人びとだ。ズーたちは詩的な感覚をもっているのかもしれないと、私は思う。動物たちからの、言葉ではない呼びかけに応じながら、感覚を研ぎ澄ます。そして、自分との間だけに見つかるなにか特別なしるしを手掛かりに、彼らはパートナーとの関係を紡いでいく。」
「ズーたちは、セクシュアリティの自由を求めている。私もまたそうだ。だが、私と彼らの間には、その意味に違いがあるように思う。彼らは「誰を愛するかの自由」を求めている。私は「セックスを語る自由」を求めている。それは、ズーたちがカミングアウトすることに似ていると思う。結局は、なにものかわからない「社会規範」というものからいつの間にか押しつけられているセックスの「正しい」あり方は、一部の人びとを苦しめ続ける。セクシュアル・マイノリティと呼ばれる人たちだけではない。異性愛者であっても、その状況は同じだ。誰かが語らなければ、鋳型にはめられたセックスの輪郭は崩れていかない。」
「人間と動物が対等な関係を築くなんて、そもそもあり得ないと考える人は多いかもしれない。だがズーたちを知って、少なくとも私の意見は逆転した。人間と人間が対等であるほうが、よほど難しいと。」
みずからが性暴力被害の当事者でもある著者の言葉は時になまなましく、こちらの心をえぐるような鋭さがありますが、「誰かが語らなければ」という断固たる思いの部分には、いまのいて座の人たちにも通底するものがあるのではないでしょうか。
今期のいて座は、人間と人間、また人間と他の生きものとが対等にあることの難しさについて、改めて思いを巡らし、語らっていく時間を大切にしてみるといいかも知れません。
参考:濱野ちひろ『聖なるズー』(集英社)
例えば、現代において実際に犬や馬をパートナーにして性的営みを行う「ズー」と呼ばれる動物性愛者たちを取材した濱野ちひろのノンフィクション『聖なるズー』には、取材を通してズーたちに抱いていた印象が変わっていったことについての著者の率直な思いが書かれています。
「ズーとは、自分とは異なる存在たちと対等であるために日々を費やす人びとだ。ズーたちは詩的な感覚をもっているのかもしれないと、私は思う。動物たちからの、言葉ではない呼びかけに応じながら、感覚を研ぎ澄ます。そして、自分との間だけに見つかるなにか特別なしるしを手掛かりに、彼らはパートナーとの関係を紡いでいく。」
「ズーたちは、セクシュアリティの自由を求めている。私もまたそうだ。だが、私と彼らの間には、その意味に違いがあるように思う。彼らは「誰を愛するかの自由」を求めている。私は「セックスを語る自由」を求めている。それは、ズーたちがカミングアウトすることに似ていると思う。結局は、なにものかわからない「社会規範」というものからいつの間にか押しつけられているセックスの「正しい」あり方は、一部の人びとを苦しめ続ける。セクシュアル・マイノリティと呼ばれる人たちだけではない。異性愛者であっても、その状況は同じだ。誰かが語らなければ、鋳型にはめられたセックスの輪郭は崩れていかない。」
「人間と動物が対等な関係を築くなんて、そもそもあり得ないと考える人は多いかもしれない。だがズーたちを知って、少なくとも私の意見は逆転した。人間と人間が対等であるほうが、よほど難しいと。」
みずからが性暴力被害の当事者でもある著者の言葉は時になまなましく、こちらの心をえぐるような鋭さがありますが、「誰かが語らなければ」という断固たる思いの部分には、いまのいて座の人たちにも通底するものがあるのではないでしょうか。
今期のいて座は、人間と人間、また人間と他の生きものとが対等にあることの難しさについて、改めて思いを巡らし、語らっていく時間を大切にしてみるといいかも知れません。
参考:濱野ちひろ『聖なるズー』(集英社)
《山羊座(やぎ座)》(12/22〜1/19)
今期のやぎ座のキーワードは、「人間中心主義的な補遺」。

私たち人類はどこへ向かっていくのか。その行き着く先はテラフォーミングされた火星なのでしょうか。いや、そうあるべきなのでしょうか。
思い返してみると、16世紀にコペルニクスによって地動説が提唱されて以降、地球は宇宙の中心から追放され、人間は宇宙の片隅の、そのまた片隅に住む辺境者ないし“のけ者”としての位置づけを余儀なくされるようになりました。
ただし、コペルニクス革命は人間の位置が物理的な意味で宇宙の中心にあるという幻想は打破しましたが、その代わりに宇宙の中心は理念化され、その十分な認識という課題が人間の理性に与えられたことで、人間が宇宙に存在するということの意味や目的は維持され、そうした伝統は今日まで続いている訳ですが、20世紀の哲学者のハンス・ブルーメンベルクは、それを「人間中心主義的な補遺」と呼びました。
例えば、1975年に刊行された著書『コペルニクス的宇宙の生成』において、彼は地球と人間の位置づけについての長い長い考察を、次のように述べることから始めています。
「われわれが地球上で生を営みながら、しかも星々を見ることができるということ、生きるための条件が見るための条件を排除せず、またその逆でもないということ―これは信じがたい驚異である」
ブルーメンベルクによれば、こうした「驚異」の念は、人類が地球の大気圏から脱出して宇宙に乗り出し、地球がいかに特別な星であるかを人類みずからが認識しはじめたことによって、より増しているのだと言います。
すなわち、無限に近い宇宙の広大さに比した地球の卑小さという「コペルニクス説が残したトラウマ」は終わりを告げ、「人間が生きるオアシス、この例外的な奇跡、幻滅させる天の砂漠のただなかにある私たちのこの青い独特な惑星は、もはや「これも星」なのではなく、その名に値する唯一の星」なのだ、と。
今期のやぎ座もまた、自分や他者やさまざまな存在者が現に存在するという現実に対して、他ならぬみずからの視界から応答していくなかで、たとえ脆弱なものであれ意味と価値を見出していくという営みに改めてコミットしていきたいところです。
参考:ハンス・ブルーメンベルク、後藤嘉也他訳『コペルニクス的宇宙の生成Ⅰ~Ⅲ』(法政大学出版局)
思い返してみると、16世紀にコペルニクスによって地動説が提唱されて以降、地球は宇宙の中心から追放され、人間は宇宙の片隅の、そのまた片隅に住む辺境者ないし“のけ者”としての位置づけを余儀なくされるようになりました。
ただし、コペルニクス革命は人間の位置が物理的な意味で宇宙の中心にあるという幻想は打破しましたが、その代わりに宇宙の中心は理念化され、その十分な認識という課題が人間の理性に与えられたことで、人間が宇宙に存在するということの意味や目的は維持され、そうした伝統は今日まで続いている訳ですが、20世紀の哲学者のハンス・ブルーメンベルクは、それを「人間中心主義的な補遺」と呼びました。
例えば、1975年に刊行された著書『コペルニクス的宇宙の生成』において、彼は地球と人間の位置づけについての長い長い考察を、次のように述べることから始めています。
「われわれが地球上で生を営みながら、しかも星々を見ることができるということ、生きるための条件が見るための条件を排除せず、またその逆でもないということ―これは信じがたい驚異である」
ブルーメンベルクによれば、こうした「驚異」の念は、人類が地球の大気圏から脱出して宇宙に乗り出し、地球がいかに特別な星であるかを人類みずからが認識しはじめたことによって、より増しているのだと言います。
すなわち、無限に近い宇宙の広大さに比した地球の卑小さという「コペルニクス説が残したトラウマ」は終わりを告げ、「人間が生きるオアシス、この例外的な奇跡、幻滅させる天の砂漠のただなかにある私たちのこの青い独特な惑星は、もはや「これも星」なのではなく、その名に値する唯一の星」なのだ、と。
今期のやぎ座もまた、自分や他者やさまざまな存在者が現に存在するという現実に対して、他ならぬみずからの視界から応答していくなかで、たとえ脆弱なものであれ意味と価値を見出していくという営みに改めてコミットしていきたいところです。
参考:ハンス・ブルーメンベルク、後藤嘉也他訳『コペルニクス的宇宙の生成Ⅰ~Ⅲ』(法政大学出版局)
《水瓶座(みずがめ座)》(1/20〜2/18)
今期のみずがめ座のキーワードは、「狂っているのは社会か自分か」。

VALIS計画
画面外から声がする。「VALIS? いったい何のことでありますか、将軍」
太く低い声が言う「巨大にして能動的な生ける情報システムのことだ。きみはそんなことも……」
大ソヴィエト辞典1992年度第6版によれば(むろん架空の書物なのですが)、「VALISとはVast Active Living Intelligence System、アメリカの映画より。自発的な自動追跡をする負のエントロピーの渦動が形成され、自らの環境を漸進的に包含し、かつ情報の配置に編入する、現実場における摂動。疑似意識、意志、知性、成長、環動的首尾一貫性を特徴とする」そうですが、じつはそれが何であるのかは、フィリップ・K・ディックの長編小説『ヴァリス』に登場するどの人物もよく分かっていないのです。むろん、それは多くの読者にとってもそうでしょう。
はっきり分かっていることは、ディックという作家がこの小説の続編を書き終わった1982年に死んでしまったということ。53歳の早死にで、死因が不明だったことから、ディックがこの小説を書いていたときには既に狂っていたのではないかとも言われていますが、訳者があとがきでも書いているように、よく読めば「本書においてディックは訳の分からないことを一言も記していない」のだということが分かるのではないでしょうか。
「夢から目覚めて一時間後、わたしはまだ心の眼―第三の眼、アジナーの眼、何でもいい――で、ブルー・ジーンズをはいた妻がコンクリート舗装の車道でひきずっているホースを見ることができる。細部はほとんど見えず、夢にはプロットがまったくない。わたしは隣りの屋敷を所有したい。わたしがか。現実の生活でなら、わたしはただで手に入ろうとも屋敷など所有するつもりはない。屋敷を所有するのは金持ち連中だ。だいきらいだ。わたしは誰なのか。わたしは何人の人間なのか。わたしはどこにいるのか。南カルフォルニアのこの皮相的な狭いアパートはわたしの家ではないが、いま目を覚まして考えるに、わたしはここで、テレビ(やあディック・クラーク)、ステレオ(やあオリヴィア・ニュートン=ジョン)、書籍(やあ九百万のタイトル)とともに暮らしている。一連の夢の生活に比較して、この生活は孤独で、にせもの臭く、価値がない。知的で教養ある人間にはふさわしくない。薔薇はどこにあるのか。湖はどこにあるのか。緑色のホースをひっぱって水をまく、微笑をたやさないほっそりした魅力的な女性はどこにいるのか。わたしが現在そうである人物は、夢の人物に比較して、うちまかされ、敗北し、充ちたりた生活を楽しんでいる想像しているだけだ。夢の中で、わたしは本当に満ち足りた生活というものが何であるかを知るが、それはわたしにはおよそ縁遠いものだ。」
その後、インターネットの出現によって「巨大にして能動的な生ける情報システム」は上記のような体験を、夢ではなくPCやスマホの画面を通して、誰もが容易に体験することができるになりました。
今期のみずがめ座もまた、ディックほどではなくても、今はまだ妄想と区別が付かないような啓示を自由に書き連ねたり、あるいは、ほんの思いつきであれ誰かに向けて真剣に話してみるといいでしょう。
参考:フィリップ・K・ディック、大瀧啓裕訳『ヴァリス』(サンリオSF文庫)
画面外から声がする。「VALIS? いったい何のことでありますか、将軍」
太く低い声が言う「巨大にして能動的な生ける情報システムのことだ。きみはそんなことも……」
大ソヴィエト辞典1992年度第6版によれば(むろん架空の書物なのですが)、「VALISとはVast Active Living Intelligence System、アメリカの映画より。自発的な自動追跡をする負のエントロピーの渦動が形成され、自らの環境を漸進的に包含し、かつ情報の配置に編入する、現実場における摂動。疑似意識、意志、知性、成長、環動的首尾一貫性を特徴とする」そうですが、じつはそれが何であるのかは、フィリップ・K・ディックの長編小説『ヴァリス』に登場するどの人物もよく分かっていないのです。むろん、それは多くの読者にとってもそうでしょう。
はっきり分かっていることは、ディックという作家がこの小説の続編を書き終わった1982年に死んでしまったということ。53歳の早死にで、死因が不明だったことから、ディックがこの小説を書いていたときには既に狂っていたのではないかとも言われていますが、訳者があとがきでも書いているように、よく読めば「本書においてディックは訳の分からないことを一言も記していない」のだということが分かるのではないでしょうか。
「夢から目覚めて一時間後、わたしはまだ心の眼―第三の眼、アジナーの眼、何でもいい――で、ブルー・ジーンズをはいた妻がコンクリート舗装の車道でひきずっているホースを見ることができる。細部はほとんど見えず、夢にはプロットがまったくない。わたしは隣りの屋敷を所有したい。わたしがか。現実の生活でなら、わたしはただで手に入ろうとも屋敷など所有するつもりはない。屋敷を所有するのは金持ち連中だ。だいきらいだ。わたしは誰なのか。わたしは何人の人間なのか。わたしはどこにいるのか。南カルフォルニアのこの皮相的な狭いアパートはわたしの家ではないが、いま目を覚まして考えるに、わたしはここで、テレビ(やあディック・クラーク)、ステレオ(やあオリヴィア・ニュートン=ジョン)、書籍(やあ九百万のタイトル)とともに暮らしている。一連の夢の生活に比較して、この生活は孤独で、にせもの臭く、価値がない。知的で教養ある人間にはふさわしくない。薔薇はどこにあるのか。湖はどこにあるのか。緑色のホースをひっぱって水をまく、微笑をたやさないほっそりした魅力的な女性はどこにいるのか。わたしが現在そうである人物は、夢の人物に比較して、うちまかされ、敗北し、充ちたりた生活を楽しんでいる想像しているだけだ。夢の中で、わたしは本当に満ち足りた生活というものが何であるかを知るが、それはわたしにはおよそ縁遠いものだ。」
その後、インターネットの出現によって「巨大にして能動的な生ける情報システム」は上記のような体験を、夢ではなくPCやスマホの画面を通して、誰もが容易に体験することができるになりました。
今期のみずがめ座もまた、ディックほどではなくても、今はまだ妄想と区別が付かないような啓示を自由に書き連ねたり、あるいは、ほんの思いつきであれ誰かに向けて真剣に話してみるといいでしょう。
参考:フィリップ・K・ディック、大瀧啓裕訳『ヴァリス』(サンリオSF文庫)
《魚座(うお座)》(2/19〜3/20)
今期のうお座のキーワードは、「“平凡な当然さ”を打ち破ること」。
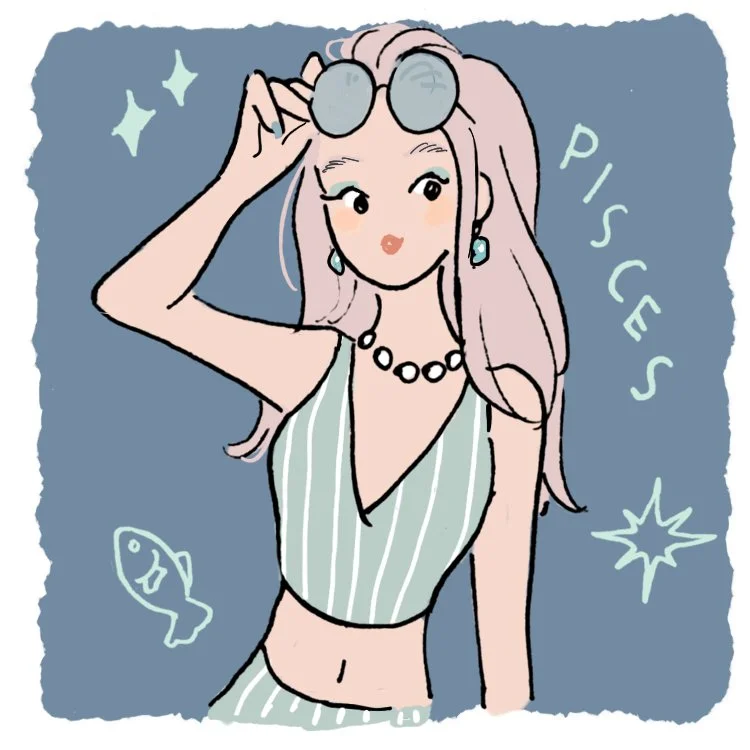
私たちは今後どこへ向かっていくべきかということを、どのような状態こそが理想的なのか、と置き換えてみましょう。例えば、思想家のシモーヌ・ヴェイユは、人間の魂のもっとも重要な欲求として「根をもつこと」を挙げつつも、同時にそれはもっとも定義の難しい欲求のひとつであると述べていました。
「人間は、過去のある種の富や未来へのある種の予感を生き生きといだいて存続する集団に、自然なかたちで参与することで、根をもつ。自然なかたちでの参与とは、場所、出生、職業、人間関係を介しておのずと実現される参与を意味する。」
さらに彼女はこう続けます。
「人間は複数の根を持つことを欲する。自分が自然なかたちでかかわる複数の環境を介して、道徳的・知的・霊的な生の全体性なるものを受けとりたいと欲するのである。」
こうした「根をもつ」ということには、風土や風俗だけでなく、職業や言語など多様な要因が複雑に絡み合っていますが、その一方で、ヴェイユは人間というのはしばしば「根こぎ」状態にも陥ってしまうのだとも考えていました。
それは経験・体験・実感に基づいていない、表面的な知識・感情の上に乗った人間生活、社会すべてを指しており、ヴェイユはそうした根無し草状態の人間は一見すると「魂の糧」の代替物のように見える「根を侵食する毒」を摂取しているのだと言います。
これはつまり、本質的に必要ではないのにも関わらず、一度手を出すと中毒的にハマっていってしまうような快楽を伴う行為のことで、現代社会には、SNS、YouTube、ファーストフードなど、日常のあらゆるシーンでそうした毒を見つけられるはずです。
ただし、ヴェイユによれば、そういうものを手にする代わりに、私たちが「道徳的・知的・霊的」に癒されるためには、ひとつの集団に参加するだけでは飽きたらず、複数の環境をはしごして、その影響を有機的に結びつけ、まとめあげていかねばならないのです。
今期のうお座もまた、そうして人生で陥りがちな「平凡な当然さ」を打ち破って、深く癒された状態を目指すこと、それを決意することがテーマとなっていくのではないでしょうか。
参考:シモーヌ・ヴェイユ、冨原眞弓訳『根をもつこと 上 』(岩波文庫)
「人間は、過去のある種の富や未来へのある種の予感を生き生きといだいて存続する集団に、自然なかたちで参与することで、根をもつ。自然なかたちでの参与とは、場所、出生、職業、人間関係を介しておのずと実現される参与を意味する。」
さらに彼女はこう続けます。
「人間は複数の根を持つことを欲する。自分が自然なかたちでかかわる複数の環境を介して、道徳的・知的・霊的な生の全体性なるものを受けとりたいと欲するのである。」
こうした「根をもつ」ということには、風土や風俗だけでなく、職業や言語など多様な要因が複雑に絡み合っていますが、その一方で、ヴェイユは人間というのはしばしば「根こぎ」状態にも陥ってしまうのだとも考えていました。
それは経験・体験・実感に基づいていない、表面的な知識・感情の上に乗った人間生活、社会すべてを指しており、ヴェイユはそうした根無し草状態の人間は一見すると「魂の糧」の代替物のように見える「根を侵食する毒」を摂取しているのだと言います。
これはつまり、本質的に必要ではないのにも関わらず、一度手を出すと中毒的にハマっていってしまうような快楽を伴う行為のことで、現代社会には、SNS、YouTube、ファーストフードなど、日常のあらゆるシーンでそうした毒を見つけられるはずです。
ただし、ヴェイユによれば、そういうものを手にする代わりに、私たちが「道徳的・知的・霊的」に癒されるためには、ひとつの集団に参加するだけでは飽きたらず、複数の環境をはしごして、その影響を有機的に結びつけ、まとめあげていかねばならないのです。
今期のうお座もまた、そうして人生で陥りがちな「平凡な当然さ」を打ち破って、深く癒された状態を目指すこと、それを決意することがテーマとなっていくのではないでしょうか。
参考:シモーヌ・ヴェイユ、冨原眞弓訳『根をもつこと 上 』(岩波文庫)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
--------占いの関連記事もチェック--------
文/SUGAR イラスト/チヤキ