【魚座】哲学派占い師SUGARさんの12星座占い<2/7~2/20> 月のパッセージ ー新月はクラい、満月はエモいー
12星座全体の運勢
「未来を肌で感じていく」
前回の記事では、2月12日のみずがめ座新月は「社会/時代の空気を読み、実感をもってそれに応えること」がテーマであり、それは立春から春分までに吹く最初の南風である「春一番」を察知して、肌身で感じていくことにも通じていくということについて書きました。
じつはこれは今年3度にわたって起きる土星と天王星のスクエア(90度)という、2021年の時勢の動きを象徴する配置の1回目が2月18日にあることを踏まえての話でした(2回目と3回目は6月と12月)。
土星(体制)と天王星(革新)がぶつかり合って、互いに変化を迫るこの緊張感あふれる配置が形成される時というのは、しばしば世の中の常識や秩序の書き換えが起こりやすく、これまでなんとなく受け入れてきた無目的な制限や命令の押しつけに対し、多くの人が「もう我慢ならない」と感じやすいタイミングと言えますが、同時にそれは、これまで考えもしなかったようなところから人生を変えるチャンスが転がってきたり、新たな希望の気配が差し込んでくるきっかけともなっていきます。
一方で、それは突然の出来事や予期しなかった展開を伴うため、現状を変えたくないという思いが強い人にとってはこの時期何かと振り回されたり、くたびれてしまうこともあるかも知れません。
しかしそれも、最初の「春満月」を迎えていく2月27日頃には、行き着くところまで行ってみればいいじゃないかという、ある種のカタルシス感が出てきて、朧月(おぼろづき)さながらに、ほのぼのとした雰囲気も漂ってくるように思います。
古来、春という新たな季節は東から風によって運ばれてくるものと考えられてきましたが、12日の新月から27日の満月までの期間は否が応でも感覚が研ぎ澄まされ、予想だにしなかった未来の訪れを少しでも実感に落としていけるかということが各自においてテーマになっていくでしょう。
じつはこれは今年3度にわたって起きる土星と天王星のスクエア(90度)という、2021年の時勢の動きを象徴する配置の1回目が2月18日にあることを踏まえての話でした(2回目と3回目は6月と12月)。
土星(体制)と天王星(革新)がぶつかり合って、互いに変化を迫るこの緊張感あふれる配置が形成される時というのは、しばしば世の中の常識や秩序の書き換えが起こりやすく、これまでなんとなく受け入れてきた無目的な制限や命令の押しつけに対し、多くの人が「もう我慢ならない」と感じやすいタイミングと言えますが、同時にそれは、これまで考えもしなかったようなところから人生を変えるチャンスが転がってきたり、新たな希望の気配が差し込んでくるきっかけともなっていきます。
一方で、それは突然の出来事や予期しなかった展開を伴うため、現状を変えたくないという思いが強い人にとってはこの時期何かと振り回されたり、くたびれてしまうこともあるかも知れません。
しかしそれも、最初の「春満月」を迎えていく2月27日頃には、行き着くところまで行ってみればいいじゃないかという、ある種のカタルシス感が出てきて、朧月(おぼろづき)さながらに、ほのぼのとした雰囲気も漂ってくるように思います。
古来、春という新たな季節は東から風によって運ばれてくるものと考えられてきましたが、12日の新月から27日の満月までの期間は否が応でも感覚が研ぎ澄まされ、予想だにしなかった未来の訪れを少しでも実感に落としていけるかということが各自においてテーマになっていくでしょう。
魚座(うお座)
今期のうお座のキーワードは、「浸透力」。
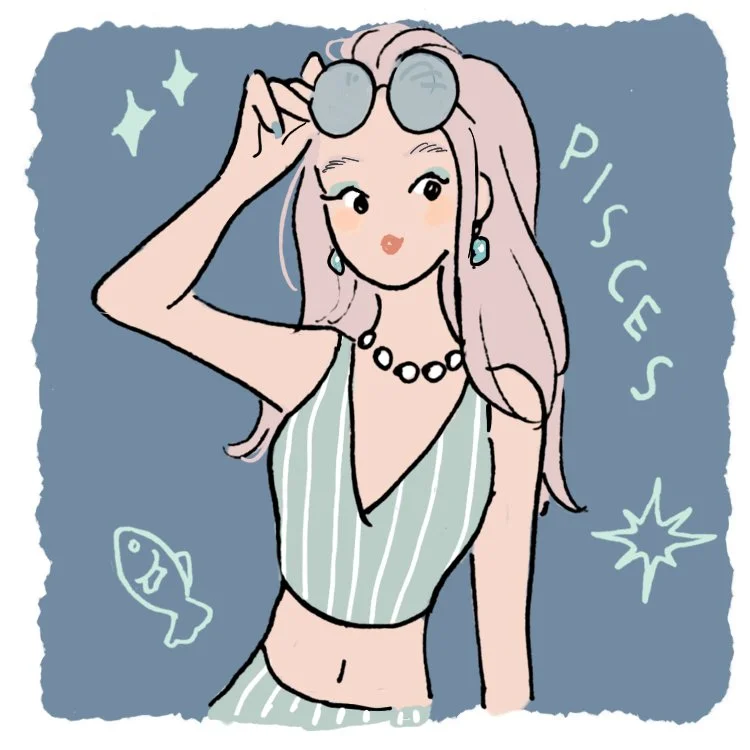
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」というあまりに有名な書き出しで知られる川端康成の『雪国』には、実際にはドラマチックな起伏や葛藤はほとんど出てきません。
親の財で暮らす主人公の島村と芸者の駒子との透けるような淡い交情が描かれているだけなのですが、それが死体のように冷たく澄んだ島村の心にどう映り、いかに浸透してきているのかということを、文体の間からまざまざと表現されているのをいったん感受してしまえば、途端に見事な作品に感じられてくるから不思議です。
この作品において「長いトンネル」の向こうの雪国とは、近代西欧文明がまだ浸透しきっていない世界として設定されているのですが、この小説の終わりの方で「天の河」が描写される頃になると、その浸透ぶりはいよいよ深まっていきます。少し長いですが、引用してみましょう。
「「天の河。きれいねえ。」
駒子はつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
ああ、天の河と、島村も振り向いたとたんに、天の河のなかへ体がふうと浮き上がってゆくようだった。天の河の明るさが島村を掬い上げそうに近かった。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このようにあざやかな天の河の大きさであったか。裸の天の河は夜の大地を素肌で撒こうとして、直ぐそこに降りて来ている。恐ろしい艶めかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の河へ写っていそうに感じた。天の河にいっぱいの星が一つ一つ見えるばかりでなく、ところどころ光雲の銀砂子も一粒一粒見えるほど澄み渡り、しかも天の河の底なしの深さが視線を吸い込んで行った。」
火事が発生した。駒子と島村が火事場へ走っていく途中、しかし二人は美しくて艶めかしい天の河を発見したのです。
川端文学において、男と女というのは性欲的な存在というより、互いに浸透し合っていこうとする自然物の関係であり、万物に神が宿るような原始宗教的な感覚がそこに透かし込まれていたのではないでしょうか。
その意味で、今期のうお座もまた自分がいま一体何に馴染みつつあるのか、そしてその対象のどこまで奥深く浸透していこうとしているのか、改めて問うてみるといいかも知れません。
参考:川端康成『雪国』(新潮文庫)
親の財で暮らす主人公の島村と芸者の駒子との透けるような淡い交情が描かれているだけなのですが、それが死体のように冷たく澄んだ島村の心にどう映り、いかに浸透してきているのかということを、文体の間からまざまざと表現されているのをいったん感受してしまえば、途端に見事な作品に感じられてくるから不思議です。
この作品において「長いトンネル」の向こうの雪国とは、近代西欧文明がまだ浸透しきっていない世界として設定されているのですが、この小説の終わりの方で「天の河」が描写される頃になると、その浸透ぶりはいよいよ深まっていきます。少し長いですが、引用してみましょう。
「「天の河。きれいねえ。」
駒子はつぶやくと、その空を見上げたまま、また走り出した。
ああ、天の河と、島村も振り向いたとたんに、天の河のなかへ体がふうと浮き上がってゆくようだった。天の河の明るさが島村を掬い上げそうに近かった。旅の芭蕉が荒海の上に見たのは、このようにあざやかな天の河の大きさであったか。裸の天の河は夜の大地を素肌で撒こうとして、直ぐそこに降りて来ている。恐ろしい艶めかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の河へ写っていそうに感じた。天の河にいっぱいの星が一つ一つ見えるばかりでなく、ところどころ光雲の銀砂子も一粒一粒見えるほど澄み渡り、しかも天の河の底なしの深さが視線を吸い込んで行った。」
火事が発生した。駒子と島村が火事場へ走っていく途中、しかし二人は美しくて艶めかしい天の河を発見したのです。
川端文学において、男と女というのは性欲的な存在というより、互いに浸透し合っていこうとする自然物の関係であり、万物に神が宿るような原始宗教的な感覚がそこに透かし込まれていたのではないでしょうか。
その意味で、今期のうお座もまた自分がいま一体何に馴染みつつあるのか、そしてその対象のどこまで奥深く浸透していこうとしているのか、改めて問うてみるといいかも知れません。
参考:川端康成『雪国』(新潮文庫)
<プロフィール>
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
應義塾大学哲学科卒。卒業後は某ベンチャーにて営業職を経て、現在西洋占星術師として活躍。英国占星術協会所属。古代哲学の研究を基礎とし、独自にカスタマイズした緻密かつ論理的なリーディングが持ち味。
文/SUGAR イラスト/チヤキ




















































































